いつからだろうか。
満開の桜を見ても、何も感じなくなったのは……。
こぢんまりとした昼の公園は、その名物である桜に反して閑散としていた。
爽やかな春の風に桜とブランコが虚しく揺れるばかりだ。
木陰のベンチに腰かけて見事なピンクを眺めるも、一向に食欲は湧かず、コンビニ弁当を持つ左手は重みに耐えかねて冷たいベンチに押し付けられていた。
nextpage
ー美しい。
この桜を簡潔に表すなら、その一言に尽きるだろう。鮮やかに色づいた薄紅色の花は、春の柔らかい陽射しに光を含ませ、それ一つで完成された自然の作品だった。
もしこれが8年前だったなら、圧倒的な美しさに感動し、少しでも良く映るようにとカメラ片手に奮闘したかもしれない。
だが今の私にとっては、「そこに桜がある」という、ただそれだけの事実に過ぎなかった。
桜に感動していられるだけの精神的な余裕は、もはや残っていなかった。それだけ心が摩耗していたのだ。
何を考えるのも面倒で、ただぼうっと桜を眺める。
しばらくして、寂しい公園に活気が戻ってきた。昼ごはんを済ませたと思しき子供達がまた遊びに帰って来たのだ。
何が楽しいのか、子供達の中では体格の良い男の子が笑い上戸になっている。
箸が転げても面白い年ごろというのはまさにあんな感じだろうか。
ふと、全くの無だった心に懐かしさがやってきた。確かに子供の頃は、楽しかった。
実家近くの土手沿い一面に広がった菜の花に心が踊り、ダンゴムシを転がすだけで満足していた。
そういえばあった。そんな頃も。
懐かしさに浸りながらも、眼前ではしゃぐ子供達も、やはりどこか別世界の存在のように思えた。
時計を確認すると、昼休みは殆ど残っていなかった。大きく息を吐き出すと、冷たい弁当を持って、また憂鬱な世界へと戻る。
陽が翳って光を失った桜は、それでも楽しげにそよいでいた。
nextpage
午後の業務を終わらせ、アパートの自室に戻ったのは、八時半を回ったところだった。
電気を付け、ただいまと呟く。
無論返答はない。
夕食を弁当で済ませ、簡単にシャワーを浴びると、一日の疲れがどっと出てきた。いや、日頃の疲れか。
不安を抱えながらも、微かな希望を抱いてここに来た時のことはもう全く思い出せないが、その日からの8年間で私は「現実」というものを十分に味わった。
「普通」の生活送るため、淡々と家と会社を往復する日々。これといった趣味の無かった私が、日常に心を削られ、心を失っていくのは時間の問題だった。
唯一打ち込んでいた仕事にも、やりがいなどといったものは皆無であった。
青かった私は会社のために身を粉にして働くことが素晴らしいと信じ、心身共に擦り減らしながら尽力した。
今は報われなくとも、いつかきっと、と。
そして結果として私が得られたものは、いかに自分が無能な人間であるかという確認だけだった。
気づけば涙も出なくなっていた。
同期や後輩が成功する中、いっそ自殺しようかと思ったこともあったが、そんな勇気はなかった。
どこまでも中途半端な人間だ。
私は感情を持たないようにと努力を重ね、喜楽を犠牲にして心を安定させた。何か楽しみを見つけるまで、この憂鬱を耐えようと。
そして、今に至る。
心が死んだまま、何の喜びも、感動もない。果たして私は、これで「生きて」いるといえるだろうか。
その答えはまだない。
笑えないバラエティ番組の為にテレビをつけるのも億劫で、疲れに身を任せてベッドに潜り込んだ。
まだ早すぎる気もするが、起きていたとしてすることはない。
唯一の安息の場所では、瞬く間に強烈な睡魔に襲われ、深い闇へと落ちて行く意識の中で、私は昼間の子供達を思い出していた。
nextpage
ーーーーーーーーーーーーーーー
ぼんやりしていた思考が急速に形作られ、私は既に起きていることを自覚した。
奇妙なことに、いつの間にかベッドの上に立っている。
眠気は無かった。
ふと違和感を覚えた私は、ベッドから降りて周囲を見渡す。そこは先ほど眠りについたアパートの自室そのものだった。
だがおかしなことに、枕元に目覚まし時計が無い。見れば、壁にも掛け時計はかかっていなかった。
いつものくせで咄嗟に左手を確認し、腕時計もないことを確かめて、そこでようやく違和感の正体に気が付いた。
腕が細い。いや、明らかに視点が低いのだ。
不思議な状況に好奇心が湧き、洗面所の鏡を見て、疑念は衝撃に変わった。
そこには見慣れた痩せ型の男の代わりに、小学生程度の子供が驚いた顔で立っていた。小さい頃の私そのものであった。
子供の頃に戻りたいという強い思いが通じたのか、私は子供の姿になっていたのだ。
そう、それはまだ夢の中だった。
恐ろしくリアルな、だが自分の理想の夢。
驚きが去ったあと、後に残ったのは強い喜びだった。
久しく忘れていた子供の頃の新鮮な興奮が戻ってくる。
夢から覚めないうちにと、私はアパートを飛び出した。やりたいことをやらなくては。せっかくの夢なのだから。
夢の中の街は現実のそれと全く同じだった。
ただ一つ、灯りが一つもないことを除いて。
街灯はおろか、アパートやビル、コンビニですら闇に包まれていた。
だが空では満月が煌々と輝いており、月明かりに照らされた市街は転ばない程度には明るい。
普段のやかましい街とは思えない静けさと、月明かりがマッチしていて幻想的な光景だった。
しばらく不思議な風景に見とれていると、遠く後ろの方で声が聞こえた。
何だろうか、ひどく懐かしい響きだ。
振り返ると、遠くの方から数人の子供が歩いて来ていた。
その姿を見るや、私は走り出していた。
子供の体は羽のように軽い。
月明かりの下、先ほどの4人の顔を確認した私は、思わず歓声を上げていた。
小学校の休み時間にいつも遊んでいた、最も仲の良かった面子だった。彼らも同じく、当時と何一つ変わっていない。
その顔を見ただけで、無邪気な喜びが体を駆け抜けた。体だけでなくどうやら心も少年時代に戻っているようだ。
夢の中の彼らは、真夜中であるにも関わらず、それが当然であるかのように振る舞っていた。当時と唯一違うのは昼か夜か、それだけだった。
「次は、なにして遊ぼうか!」
一人の言葉に、それぞれがうーんと唸る。
何をして遊ぶか。考えるだけで胸が高鳴った。
「かくれんぼでいいんじゃない?」
メンバー唯一の女子が提案する。
「やだー!つまんねー」
「じゃあ何がいいの?」
「おにごっこで!」
鬼ごっこか...定番だがもう数十年やっていないから、悪くない。
「じゃーオニ決めなきゃな!ジャンケンでいい?」
「おー」
では、とジャンケンを始めようとした矢先、声がかる。
「ジャンケンはいいよ、ボクがオニやるから」
自主的に鬼を選んだ少年は、しかし見覚えが無かった。声も聞いたことがない。
忘れていただけだろうか。
戸惑ったが、結局素直に鬼ごっこをすることにした。その時の一瞬の躊躇いが命取りになるとも知らずに。
「じゃあ30秒待つから!いーち、にー」
言うや否や、すぐにカウントを始める。わーっと歓声を上げながら、思い思いの方向へ散る中、私は違和感に気付いた。
鬼役が一人に、逃げたのが五人。
一瞬前まで五人しか居なかったのだが......。
あいつは、誰だ?
楽しげな雰囲気が一転、私は形容し難い恐怖に襲われたのだった。
nextpage
ーーーーーーーーーーーーーーー
夢の中だというに、硬質なアスファルトが容赦無く膝に負担をかける。
鬼ごっこから始まってから、もうかなりの時間が経った。とはいえ、どこにも時計が見当たらないため、正確な時間は分からない。
夜中の鬼ごっこは、圧倒的なスリルと緊張感をもたらしてくれたのだが、それが本当の恐怖に変わるのはあっという間だった。
自分の呼吸以外聞こえない、死んだように静かな世界。
その重々しい静寂を少女の悲鳴が破壊した。場所はそう遠く無かった。
一瞬、捕まっただけかとも思ったが、あの悲鳴は只事ではない。まるで断末魔のような悲鳴だった。
極限の恐怖に彩られた、聞くものを等しく怯えさせる悲鳴。
それは私も例外ではなかった。
暗闇の街で一人、全方位から襲い来る「鬼」から逃げる。それは体力的以上に、精神的に厳しいものがある。
先の悲鳴を聞いて、何かが危険だと直感が訴えていた。
いつの間にか、あまりにもあっけなく理想の夢は悪夢に成り代わっていた。
本来なら悲鳴のあった方に事情を調べに行くべきだろうが、そんなことは絶対に出来なかった。
全ての物陰の濃い闇から、気配を感じた。今にもあの六人目が飛び出してきそうな雰囲気に、気が気でない。
とにかく悲鳴のあった場所から遠ざるかるべく通りを走っていると、向かってくる人影を見つけた。一瞬凍りついたがその姿には見覚えがあった。
「おーい!オニかー?」
双方、距離を取りつつ、探りをいれる。
「いや違う!お前は?」
「オニじゃない!」
ひとまず互いに信用しあい、共に行動をとることにした。
二人になったことで、ぐっと安心感が増した。一人で暗闇に身を晒す恐怖は尋常ではない。
ちなみに彼も先の悲鳴を聞きつけたようだった。
「なあ、あのオニは誰なんだ?」
私の心からの疑問。
「わかんない。てっきりみんなの友達だと思って」
そうか、やはり。「奴」は最初から仲間では無かったのだ。疑問が去った代わりにこみ上げた、得体のしれない恐怖を飲み込み、何とか頭を回す。
「な、なあ。もう疲れたし一旦皆に言ってやめにしない?」
「そ、そうだね。僕ももう飽きた」
このまま鬼ごっこを続けるのは危険だ。何とかして終わりにしなくては。
何とか明るい方へ行こうと試みた私だったが、少年の意思に根負けして、結局悲鳴のあった方へと戻っていた。
「ケガでもしてたら大変じゃないか」
「まあ、そう......だけど...」
少し路地を抜けた先、悲鳴の聞こえた付近には団地がある。ひとまずそこを目指そうということになった。
薄闇の中にそびえる三棟の団地は、独特の近寄り難さを醸し出していた。
先の悲鳴とは裏腹に、耳が痛くなるほどの静寂が辺りを覆っている。
本当に終わらせたいのなら、大声で呼び回るべきなのだが、むしろ音を立てはならないような気がして、息を殺して二人で団地まで歩いて行った。人の気配はもちろん、虫一匹見つけられない。
冷や汗がだらだらと流れて、服が肌に張り付く。
見通しの面でも、団地の二階に居ようという結論に至り、近くにあったB棟の階段をこれまた慎重に登った。
向かって左側に約十件ほどの玄関が並んでおり、その長い廊下の両端に階段がついている。
ここならどちらから来ても逃げられる上に、近づくものがあれば前面は広場になっているためすぐに分かるだろうという寸法だった。
二階廊下に無事到達した私達は、ほっと胸を撫で下ろした。鬼ごっこが始まって以来の安心感だった。
「ちょっと待ってて」
私にそういうと相棒は廊下の逆はじに向かって歩き出した。
私はついて行く気になれず、じっとその後ろ姿を見ていた。
階段の付近は明かりが入らず、闇がわだかまっている。
少年が階段に近づいていくと、闇が動きを見せた。闇の中で、蠢くものがあった。誰かが隠れていたのか。
「おーい!もう鬼ごっこはおしまいだぞー!休憩しよー」
言いつつ、無造作に闇に近づく。
ーダメだ
思った時には遅かった。闇から切り離された人影が、月明かりに照らされた。
そこにいたのは、おおよそ子供には思えない、2メートルはありそうな人型の何かだった。はためで分かるほどの猫背で、ゆらゆらと歩いてくる。顔は俯いていてわからないが、体がその存在を拒んでいた。
驚きの余り固まった相棒に、とっさに叫ぶ。
「逃げろっ!」
ビクッと体を震わせると、少年は全力でこちらに走りだした。恐怖で顔が歪んでいた。
その表情を見て、凍りついていた心臓が暴れ出すのを感じた。彼が走ってきたのにつられ、私もすぐに走り出す。
ーところが
「ーああっ!」
ざーっと、何かが擦れるような音が聞こえ振り向くと、彼がつまづいて盛大に転んでいた。
気付けば「奴」も既に走り出している。
その時の私に、少年を助けるという選択肢は無かった。
恐慌状態に陥った私は、とにかくその場から離れたい一心で、必死に地面を蹴った。
「ーぉっおおああああああぁぁあああああ!!!!!!」
背後から聞こえた絶叫に、見てはいけないと思いつつも振り返る。そこにはモノトーンの世界では表現出来ない、鮮やか過ぎる鮮紅色が噴き出していた。
止まない絶叫と、強烈な赤に足がすくんだ私は、その場から目が離せなかった。
元凶は私を追って来ようとせず、痛みに絶叫し続ける少年に頭部を近づける。
ーやめろ......やめてくれ...
そして絶叫は不自然に途切れた。
ー喰われた
細部は見えなかったが、直感的にそう思った。
ゴッ、ブチブチ......。
生々しい音が響き、怪物が首を持ち上げる。
身体から離れた少年の首を咥え、軽く首を傾げた「それ」と目があった。
意外なことに、そこには見慣れた顔があった。
メンバー唯一の女の子。
化け物の胴体には恐ろしく不釣合いな少女の首が乗っていた。
異様としか言いようのない存在に、生理的嫌悪がこみ上げる。
怪物の下では、少年が最後まで逃がれようと限界まで伸ばした血塗れの左手が激しく痙攣していた。
もはや理性は飛んでいた。
本能的な生存欲が体を支配し、ペース配分など考えず全力で逃げた。団地が見えなくなっても、完全に走れなくなるまで走り続けた。
ガソリンスタンドに到達したところでぷつりと力がなくなり、地面に転がって空気を貪る。
酸素の足りない苦しさも、早鐘の如くうちつける心臓も、果ては転がったコンクリートの痛さも、その全てが圧倒的にリアルだった。
目を閉じると、瞼に焼き付いた惨劇が再生される。
恐怖がフラッシュバックし、胃が痙攣した。私は落ち着くまで何度も壁の隅に吐き続けた。
しばらくして落ち着いた後には、酷く頭が痛んだ。
辺りにはまた、こちらをあざ笑うかのような静寂が戻っていた。
幻想的に見えた街並みも、今や恐怖を掻き立てる廃墟の群れでしかなかった。
不用意に移動する気にもなれず、壁にもたれながら耳を澄ませる。
不意に「生きたい」と、強く思った。あんな奴に喰われるのだけは御免だ。
ここから生きて帰れるのなら、何を差し出しても惜しくはなかった。
たとえ残業3日間で連続で徹夜しても構わない。
とっさにそんな考えが浮かんだ自分に気付き、自嘲的な笑みがこぼれた。
ー私はなんて下らない問題で悩んでいたんだろう。生きていられることに比べたら、仕事の悩みんて鼻で笑い飛ばせるというのに。
死んだ心に、血が通っていくのが分かった。命の危機にさらされて、やっと私は気付けたのだ。
私は生きている。
それだけのことが、私にとっては世紀の発見だった。
この心を持って、絶対に生きて帰ろう。もう迷いはなかった。
そのためには僅かな音も聞き漏らすまいと、見通しの悪い視覚を捨てて、目を閉じる。
ーそれが間違いだった
ぞくりとした感覚を覚えた私は、薄目を開け、そして絶叫した。
ほんの10メートル先に、例の異形の怪物が佇んでいた。
先程とは異なり、少女の頭の代わりに少年の首が乗っていた。その顔は変わらず、声のない絶叫を続けている。
もう逃げられない。
そう悟った瞬間、理不尽な殺戮に対しての恐怖よりも怒りが勝った。
「何でなんだよっ!お前は誰だ!何がしたいんだっ!! ふざけんな」
全力で叫んでいる瞬間は、恐怖を忘れられる気がした。もちろん一時的なものに過ぎなかったが。
「そいつ」は足を引きずるようにズルズルと擦り寄ってきた。
だが私が動けば走って来るのは目に見えている。
あっけない人生の最後にして、目に熱いものが込み上げ、意地でも零すまいと真上を向いた。
それは相手に急所である喉を差し出すようなものだったが、どうせ死ぬなら変わりはしない。
図らずも見上げた漆黒の空は、涙の膜で歪んでいても分かるほど、大量の星が輝いていた。
思えば、まともに空を見たことなどなかったかもしれない。こんな綺麗なものが近くにあったとは。
無限の後悔の中で私は、涙が零れないよう静かに目を閉じた。
nextpage
ーーーーーーーーーーーーーーー
私に待っていたのは、喉を砕かれる痛みではなく、静かな声だった。
ーいつもの公園で待ってる
頭の中に、確かにそう声が聞こえた。
ゆっくり目を開けると、そこに怪物の姿は無かった。
突然の展開にしばし呆然と立ち尽くし、言葉の意味を考える。
いつもの...公園?
子供の頃に公園で遊んだ記憶はない。それなら校庭で事足りたからだ。
となると、会社の昼休みに毎日通っているあの公園だろうか。
他に思い当たる節は無く、ここに留まる意味も無かったので、ひとまず会社の近くの公園を目指すことにした。
急展開に全く着いていけない思考を放棄し、それが義務であるかのように淡々と歩を進める。
会社まではアパートから自転車で通っているが、歩いても行けない距離ではない。今のように、信号に引っかからないならなおのことだ。
そしてその公園は、会社から6分ほど歩いたところにある。通勤路とおなじくらい見慣れた道だった。
薄闇の中でも迷うことは無く、無事に公園に到着した。
左手に遊具があり、奥には大きな桜、その横にベンチがある。私の昼の特等席である。
月明かりに照らされた桜の下に、誰かの後ろ姿が見えた。大人にしては小柄で、異質ではあったが危険な雰囲気はない。
あと数歩のところまで近づくと、その人が振り返った。
白い着物の様なものを着た、黒い長髪の女性。こう書くと非常に不気味だが、小綺麗で可愛らしい印象だった。歳の頃は20代後半といったところか。だが童顔なせいで、ずっと幼く見える。
いずれにしろ、一度も会ったことがない(はずだ)が。
「何でここに?」
私はとりあえず、素朴な一番の疑問をぶつけた。
「貴方が聞いたんでしょう。誰だ、何がしたいんだって」
冷たい言い方だったが、敵意は感じられなかった。言ってみれば、子供が拗ねているようにも見える。
「入って来るなり私の年齢を決めつけておいて、子供が拗ねているみたいって本当に失礼な人ね」
無造作に発せられた言葉に、計り知れない衝撃受ける。
どうやらほぼ完璧に心が読めるらしい。
「まずは何がしたいんだって質問だけど、貴方がシャクだったから怖がらせてやったの」
「し、癪?」
全く見に覚えが無かった。
そもそもあったことも無いのだから......
そんな私の心を読んだのか、女はどことなく寂しげな表情を浮かべた。
「......知ってる? 春になるとね、大勢の人が桜を見にくる。綺麗だねって、笑顔になるんだ」
花見のことを言っているのだろうか。
私には話の意図が全く見えなかった。
彼女は寂しげな表情を隠すためか、顔を背けて桜を見上げる。
「でも......散ればおしまい。すぐに桜の事なんか忘れて、見向きもしなくなる。元から何も無かったみたいに......。まあ、それはしょうがないこと」
ーでもね
そう言ってくるりと振り返った姿は、思わず見とれてしまうほど魅力的だった。
「貴方は違った。毎日、お昼になると来てくれる。たとえ花がなくても、冬の寒い日でも。だから貴方を喜ばせようと咲いたのに......本当に何一つ思わないんだから。美しいとも、醜いとも思わない......その態度がシャクだった」
彼女は嬉しさと、悲しさと、怒りの織り混ざった繊細な表情を見せた。
待てよ、ということは....まさかこの子は......
「そうね、私はこの桜そのもの。誰だって聞かれても名前なんかないから......」
驚きで、言葉が出ない。
だが、桜の妖精と会話した......そんなバカな話、誰も信じてくれないだろう。
「バカだなんて、ほんと失礼。まあ、私もちょっとやりすぎちゃったかな。確かに子供っぽかったかも......」
今までの悪夢が全てこの子のイタズラだったと知っても、安心こそすれ不思議と怒りは湧いてこなかった。
緊張が全て溶けていき、安堵で心が満たされる。
ふうっと大きく息を吐いた。
「もうすぐ散っちゃうから、こうして来たんだけど......もういいや、用はないから。じゃあ」
素っ気ない言葉遣いとは裏腹に、嬉しそうな表情が見え隠れしていた。
もう少し話したい。強くそう思った。今の私なら、こんなメルヘンな話でも信じられる気がする。
だがその願いは叶わなかった。
それまで明瞭としていた思考は朧げに霞んでいき、夢が夢だと自覚できなくなっていく。
意識が闇に沈む直前、ちらりと見えたその横顔はやはりどこか寂しげに見えた。
nextpage
ーーーーーーーーーーーーーーー
窓に強く吹き付ける雨の音で眠りから覚める。
永遠のように思えた長い悪夢から解放されたというのに、私の心はもやもやしていた。
最後に見えた、あの横顔のせいだ。
だが夢の中で桜の妖精と会ったなどというのは、所詮ただの妄想だ。
もし私が他人なら、そう一蹴して正気を疑っているに違いない。
だが荒れる雨音を聞いて、じっとしていることなど到底出来なかった。
気が付けば、早朝の大雨の中を、部屋着のままカッパも着ずに自転車を飛ばすなどという大それた行動をとっていた。
もちろん会社を素通りし、一直線に公園に向かう。
ズボンもトレーナーもずぶ濡れだったが、全く気にならなかった。
入り口に自転車を乗り捨て、傘を持って全身ずぶ濡れのまま桜の元に走る。
状況はやはり最悪だった。
雨に打たれた花びらが無惨にもぎ取られ、ほとんど木には残っていない。
無類の桜好きでも目を背けたくなるような光景だったが、私は全く構わなかった。
ジャンプ傘を開き、一枚でも多くの花びらを守ろうと天にかざす。
雨が容赦無く体に打ち付け、体温を奪っていった。
だが私はその体勢のまま、ただ桜に見とれていた。
それは、今まで見たどんなものより儚く、美しく、健気だった。
「......綺麗だ」
無意識に口をついて出た言葉に自分でも驚く。
彼女には伝わっただろうか。
もし伝わっているならと、濡れた幹に手を添え、小さく呟く。
ーありがとう
透明な雫が一つ
雨に混じって、花びらと共に落ちていったのだった。




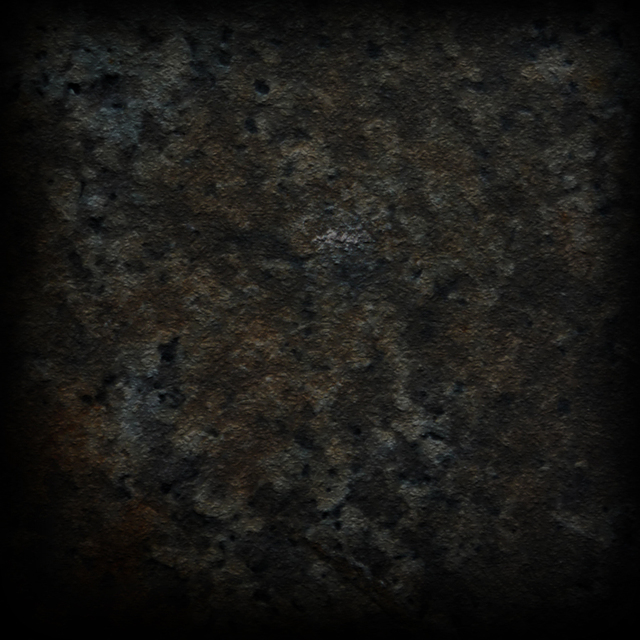
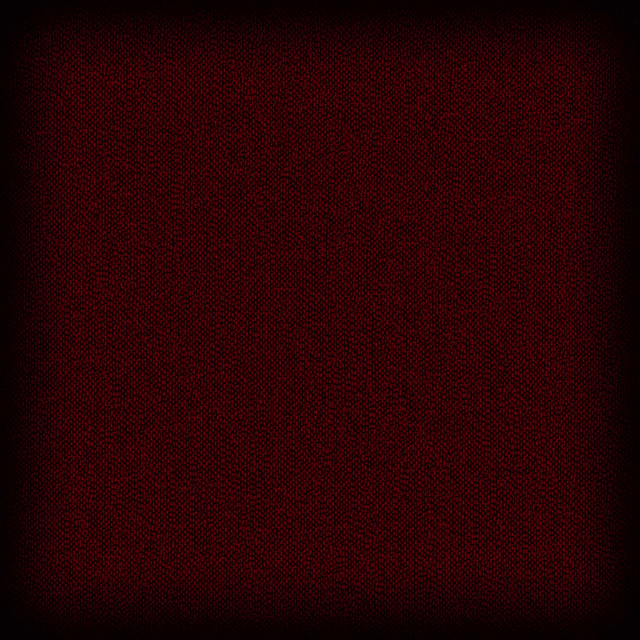
作者ダレソカレ
ご無沙汰しております、ダレソカレです
さて、春といえば桜の季節ですね。桜の樹の下には......という話もありますが、実は私の実家近くの神社にある桜の木で、昔自殺をした方がいたという話を聞きました。口外禁止になっているそうですが、知っている人は知っているとか。
恐怖というものは気づかないだけで、意外に身近にあるのかも知れませんね...
【追記】
多くの方からコメント、怖いを頂き、心より感謝申し上げます。不慣れな「いい話」に挑戦したので大変不安でしたが、少しでも楽しんで頂けたようで本当に良かったです。