wallpaper:48
ある日のこと、Tに誘われ一軒の店に訪れた。
そこは、見た目からは喫茶店のようなもので、店の中には何人かのお客さんがいた。
外見こそ木造築で2階建て、外で食事するようなスペースはなく、あるのは怪しげな看板が掲げられていることだった。
「T、ここの店は有名なん?」
「そうや、個々の裏メニューはめっちゃうまい! だから、君にも味わってほしいと思ったんや」
Tが誘った理由はここの裏メニューに関係していることだったらしい。
Tは昔から、あらゆる店に赴いては裏の裏メニューを探っていた。
それは、Tが幼いころに食した裏メニューがあまりにも絶品でお花畑、みんなが喜ぶ素顔、天高く飛び回っているなど、そんな風景や感触が味わえたとTが言っていた。
Tは、もう一度その味を知りたくて、いろんな店に行っては探しているのである。
nextpage
wallpaper:67
「失礼します、2名です!」
ピースサインで2名だとアピールした。出てきた店員はなんだかやる気がない女性だった。
見た目からしてだらしない服装、髪はボサボサ、目の下にはクマがある。少し不気味に感じた。
「よし! 成功だな」
Tはそのように呟いた。
僕はその意味をまだ理解できなかった。
窓側の席に着くなり、店員に注文した。
「コーラとコーヒーね」
店員は意味が分からなそうな顔をした。
もう一度同じものを頼んでみると、店員は「そんなメニューはありませんので、今持ってくるからそこにおれ!」と、明らかに上から目線で睨みつけながら言ってきた。
Tはニヤニヤしながら言った。
「普通のメニューじゃないと分かっていたんだよねえ、独特のメニュー…う~ん、味わいたいねえ」
僕は、なんだかいつものTに見えなかった。
「ほれ持ってきた。さっさと見て注文しろよゲスども」
明らかに悪口だ。
ぼくらに何か恨みでもあるのだろうか。まあ、注文すれば早いとこ立ち去れると思い、早々にメニューの中から注文する。
そのメニューになんだか、へんな感じがした。
以下メニューにあった名前(解読できた)もの
・モクゾウセイゾウ
新鮮な木のような味を締め出すは、人を狂わせる
・ヒトノコウウン
人から奪った幸運は、自身に幸せが訪れると思うか
・ゼッサンセカイ
この味を知ってしまえば、この味以外のものは絶対に味わえない
・エミノロ
当店のおススメジュース。一度は味わってください。
と、あったがどれも説明だけでは、なにが入っているのかわからない。
「はい、ゼッサンセカイをください」
Tが手を上げて注文をした。
「早いな」
「さあ、早く決めろ」
ぼくは、メニューを見ても説明だけではなんだか嫌な気がした。最後の方にあったエミノロを注文した。
店員は、さっさと奥の店に行き、調理場の中へ入っていった。
ぼくは、この店のあやしさにすこし嫌な気がした。そのことをTに報告しようとしたが、Tがせっかく誘った店だ。一度は味わったこともあるから、この店に連れてきたのだろう。
「なんで、ゼッサンセカイを頼まなかったの!」
不機嫌そうに、ぼくに尋ねた。
「いや、なんだか不気味に見えてね、今度来たときにTと同じものを頼むよ」
そう伝えると、Tはさらに不機嫌になりながらも、ゼッピンセカイの味を解説してくれた。
10分ほど時間が絶ったのだろうか、しかし、他の客お客さんはずっと席に座ったまま。
手を動かしている様子もない。食事している食器・汁・声がしない。
「T、この店って…」
ぼくが尋ねようとしたときに、店員が奥から注文した品物を持って、ぼくらの席に運んできた。
「はい、当店自慢んの味ゼッピンセカイと、雑魚のお客様の用のエミノロです。ゆっくりして行けよ」
ぼくに睨みながら、店員はそそくさに店の奥へ行ってしまった。
届いた料理は、なんだかすごい悪臭を放った。その悪臭の先はゼッピンセカイと呼ばれるものだった。地球のような形状をした丸い物体の上に細かく丁寧に1センチほどのサイズの人間の模型が置かれている。
Tがヨダレを垂らしながら、ナイフで地球を中心から切り裂くと、ドバーと赤い液体のようなものが豪快にTの頭部から腹にかけて飛び散る。異様な光景だった。
Tは、そんなのをお構いなく、それを口にする。
「うまい、最高だ」と、褒めながら口の中に入れていく。
だけど、臭いは最悪だ。たとえ、鼻を詰めても喉の奥へ入り込まれたら、胃の中にあるものすべてを戻してしまうほどの悪臭だ。とてもじゃないが、口の中に入れているTにこの世のものとは思えなくなってきた。
Tが夢中で食べる中、ぼくも小腹がすき、目の前にあったエミノロに手をつける。エミノロ自体には不思議と味がしない。アイスのように冷たく、ぼくの舌に触れては、泡のように消えていく魔訶の不思議な触感。
だが、味はない。
このようなものはいったい、どうやって作っているのか興味がわく一方で、Tが食べているようなものから見て、あまり見たくもない気がしてならない。
そうこうしているうちにTもぼくもたらい上げてしまった。
食べた気がしない。
でも、Tは満足だ。
服や顔にはべったりと赤い液体が付着していながらも。
「絶品だった、お花畑が見えた最高だった!」
と、褒めていたTに、少し近寄りにくかった。
早速お会計に向かおうと、店員を呼びつけるが、店員は出てこない。隣にいたTが言ってきた。
「あ、この店は全部食べれば、無料になるから」
と、教えてくれた。
しかし、そんなわけにはいかないと思い、店員を呼びつけるも、出てこない。
「……」
誰も出てこない。おかしいなと思い、店の奥へ入ろうとした矢先に、信じられないものを見た。
他の席に座っていた人が人ではなくマネキン。そして、目の前にあった備え付けられた料理には、どれも黒く濁り、中にはカビが生えているものもあった。
ハエが飛び回っている。
「うぐ」
戻しそうになった。そこにTが引き止める。
「戻したら、代金がとられるぞ! 君が頼んだのは俺よりも高価だ、戻したら戻したらで大変だぞ!」
と、ぼくの右肩に手を置きながらそう伝えてくれたTに感謝し、戻すのを必死にこらえた。
そうこうしているうちに、店員が出てくることもなく、その店から去った。
「不気味な店だった、もうあの場所には近寄りたくないな」
「いやいや、あそこほど絶品はないよ、今度こそもう一度行きたいなあ」
嬉しそうにニヤニヤと笑みを浮かべるT。ぼくは、しばらくの間はTと行動しづらくなったこともあり、しばらくの間、Tとは別行動をとった。
nextpage
wallpaper:68
個人的にあの店について調べた。
だけど、あの店についてはどこにも誰にも聞いても、知らないと返された。
Tに訊いてみても、「夢じゃない」と、返されてしまう。
Tは、あれ以降、絶品料理を食べてみたいということはなくなった。そのため、仲を解消し、一緒にいるようになった。
nextpage
wallpaper:717
ある日の夕暮れに、Tがあることを口に出した。
「この前、言っていた店のこと、本当は知っていたんだ」
「え?」
「あの店は、いや、あの屋敷には近寄らない方がいいと悟った」
「は? はい?」
「確かに、絶品だった。俺の舌を覆すほどに、でも、君が見せてくれた光景で目が覚めたよ、もうあの店に近寄りたくないって」
Tがとんでもないことを教えてくれた。
しかし、正直に教えてくれたのはぼくはうれしかった。
「なら、あの場所のこと、あの店のこと知っている?」
「ああ、知っているよ、僕なりにあの店のことを調べたんだ、あるのはマネキンの倉庫だけだ」
マネキンの倉庫? え? 喫茶店は?
「もう、思い出さない方がいい、いや忘れてしまったほうがいい、あれは見てはいけなかったのかもしれないかった」
Tが口をモゴモゴとしながら、必死に伝えた。
nextpage
wallpaper:115
それは、あの店はもしかしたら存在してないのではと、いったものだった。

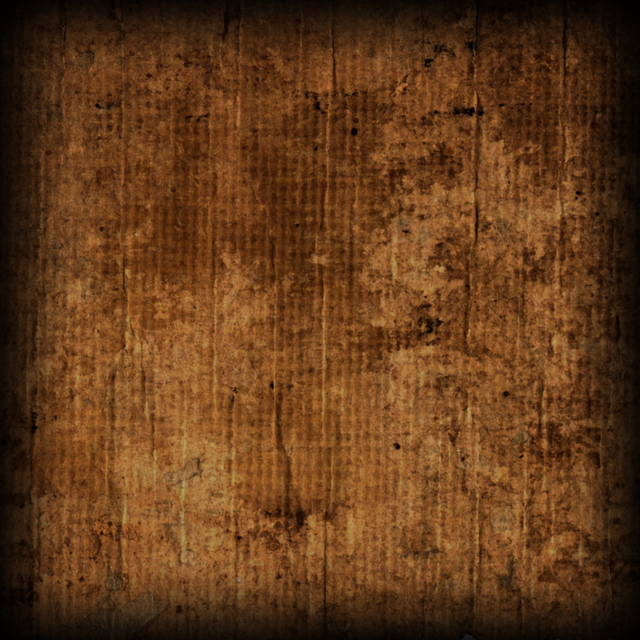


作者EXMXZ