むかし、人通りが全くない山あいに、小さな村がありました。
その村は、とても貧しい村で農作物もあまり取れず、飢饉の度に何人かの餓死者を出ていました。
そんな村であるためか、戦国の世にありながら戦禍を免れており、村人は世間を離れひっそりと暮らしていました。
この村には、一つの問題を抱えていました。
時々、山を越えて、「にやるほてうぷ」という化け物がやって来て悪さをするのです。
「にやるほてうぷ」は、嵐を呼んでは田畑をあらし、雷を落としては民家を焼く等、一晩、悪行の限りを尽くすと村を去っていきます。
村人たちはこの化け物を鎮めるため、「にやるほてうぷ」が暴れ始めると、山の向こうへ生贄を一人選んで捧げに行っていました。
ある日、村ではいつものように暴れ始めた「にやるほてうぷ」のために、誰を生贄に捧げるか集まりがありました。
そしてその集まりで、「まつ」という娘が生贄に選ばれました。
このまつというのは、生まれながらに顔の半分に火傷を負ったような痣(あざ)がある娘で
両親を小さいころに病で亡くすと、叔母の家に預けられ
まともに飯も食わせてもらえないくせに、そこでは奉公人のように扱われて暮らしているという、大変可哀想な娘でした。
叔母の家では、ちょうど同じくらいの歳の娘がおり、名前を「はな」と言いました。
はなは、まつが逆らえないのをいいことに、まつをいじめました。
家の掃除をしているまつの裾を踏みつけて転ばしたり、わざと部屋を汚して仕事を増やしたり、あれこれ用事を言い付けたり。
叔母は、それによってまつの仕事が遅れると、半ばはなのせいだと知りながらも、ここぞとばかりまつを叱り食事の量を減らしたりしました。
村人は、そんなまつを「痣女(あざおんな)」と罵り、叔母はそれを「家の恥だ」と事あるごとにまつに嫌味を言いました。
まつは、それらの不当な扱いを平身低頭でやり過ごすしかありませんでした。
そんなまつは、年ごろになっても当然嫁の貰い手などなく。
ますます、叔母の家では煙たがれていたので、まつを生贄にすることに関して、村中誰も反対する者はありませんでした。
村人が「にやるほてうぷ」が棲むという山に、まつを捧げに来たときでさえも、村長の儀礼的な
「では、あとはよろしくな」
という一言だけしかありませんでした。
叔母に至っては生贄を捧げたお礼を貰うと、もうまつには興味を無くしたみたいで、生贄を捧げる場にさえ姿を現しませんでした。
まつは自分を置いて帰る村人たちに
「叔母に今までお世話になりましたとお伝えください」
とだけ言い、帰る村人たちをいつまでも頭を下げて見送った。
村人が立ち去り、数刻が経過した後、ガサガサと何者かが近づいてくる物音をまつは聞いた。
まつは始め「にやるほてうぷ」が来たかと思ったがどうやら違うようだった。
それは人の集団だった。
彼らは、襤褸(ぼろ)をまとい、聞き取れないほどの小さい声でぼそぼそと一言二言、言葉を交わしながらまつを取り囲むように近づいて来た。
その中の一人が、杖を付きながらまつへゆっくり近づいて来た。
なにやら、すえた悪臭がまつの鼻を付いたころ、それはゆっくり口を開いた。
「ぬ……が……たび……か?」
まつは、よく聞き取れなかったせいか
「なんでしょうか?」
聞き返したところ
「ぬしがこのたびのにえか?」
先ほどより大きいはっきりした声で、それは言った。
まつはただ黙って頷いた。
「そうか……ならば付いて来い」
そういうと、それは踵を返し、元来た方向へ帰っていく。
残りの者たちは、まつの周りに一緒に捧げられた、農作物などを手分けして持ち運び始めた。
まつは彼らの後に付き従った。
不思議なことにまつは「付いて来い」といったその声に、今まで幼少の頃の両親以外からは感じことがない、優しい声音を感じ取っていた。
彼らは、山のさらに奥深い洞窟で生活しており、まつはその一因になった。
まつから見た、彼らの生活は異常だった。
何もしないのだ、一日を洞窟内で自ら決めた位置から出ないように、ただ寝っ転がって過ごすのだ。
必要がなければ一切声を発しない、簡単な世間話すらしない。
食事は一日一回、まつが生贄として捧げられた時に一緒に捧げられた農作物を調理を施して少しづつ食べた。
もっとも、大した調理器具はないので大したものはできないが。
まつは、そんな生活していく中で、彼らの正体が解りはじめていました。
『彼らは自分と同じなのだ、あの村、もしくは付近の同じ様な村で、生贄に捧げられた者たちなのだろう。』
よく見ると彼らは自分と同じように、見た目が醜悪だったり、片足を引きづっていたり、目が見えなかったり、耳が聞こえなかったり、何かしら生きにくい弱点を持つ者たちばかりだ。
そんな冷静に、この集団の生活を送っていたまつであったが、一つだけ気がかりなことがあった。
食料がもう2~3日もすると無くなりそうなのだ。
『そうなったらこの者達はどうするのだろう?』
まつはそこに、不安を感じざるを得なかった。
そして案の定、3日で食料は底を尽きた。
そこから、一週間ほどは水以外を口にすることはなかった。
まつが『これからどうするのだろう?』と思ったある夜のこと。
「呪(しゅ)の日だ」
隣にいた住人がまつを促し、洞窟のさらに奥に進んだ。
そこは少し広くなっており、中央に護摩焚きのようなものが用意されていた。
近くでは、おそらく最後の食料であろう鍋が煮えており、まつは一杯それを受け取ると、皆と一緒にそれを食した。
食事が終わると、護摩焚きが始まりそれを取り囲むように住人は座った。
そして誰ともなく。
「にぃまくれと もいにゃぺい せぎゃのたて せりねひとに しとぃけぎゅ
ていりのねと きくんこしょ らのぃひにび りゃちのとき ひゅのにぽじ」
何語かもよく聞き取れない、呪文のようなものを唱え始めた。
まつは、最初何のことかはわからなかったが、何度も聞いているうちにだんだんと覚えてしまい。
終いには、口ずさむようになっていた。
「にぃまくれと もいにゃぺい せぎゃのたて せりねひとに しとぃけぎゅ
ていりのねと きくんこしょ らのぃひにび りゃちのとき ひゅのにぽじ」
「にぃまくれと もいにゃぺい せぎゃのたて せりねひとに しとぃけぎゅ
ていりのねと きくんこしょ らのぃひにび りゃちのとき ひゅのにぽじ」
それは、洞窟内に響き渡り、声は入交り、どれが誰の声かもわからない。
まつは、一心不乱に呪文を唱え、場所も、時間も、自分さえも、分からないそんな状態になった。
『まるでここにいる全員の意識が溶け合って、一つの巨大な感情の渦のようになっているようだ』
自分を強く思わなくては、自分を保てない。
今まで自分の意を押し殺して、生きて来たまつであったが、この時ばかりは自分自身と向き合い、今まで心の奥底に閉まっていた感情を掘り出そう出そうとした。
「にぃまくれと もいにゃぺい せぎゃのたて せりねひとに しとぃけぎゅ
ていりのねと きくんこしょ らのぃひにび りゃちのとき ひゅのにぽじ」
「にぃまくれと もいにゃぺい せぎゃのたて せりねひとに しとぃけぎゅ
ていりのねと きくんこしょ らのぃひにび りゃちのとき ひゅのにぽじ」
「にぃまくれと もいにゃぺい せぎゃのたて せりねひとに しとぃけぎゅ
ていりのねと きくんこしょ らのぃひにび りゃちのとき ひゅのにぽじ」
そこに在ったのは、怨嗟、嫉妬、孤独感、自己憐憫、苛立ち、そして、憤怒であった。
『これが自分だ!これが自分だったのだ!』
そう強く思ったとき、それまでただ飲み込まれるだけだった巨大な感情の渦に、自己を保ったまま、まつは完全に同化した。
『なんことはないここにいるみんな同じ感情を持っているのだ。』
まつがそう思ったとき、頭の中に風景が浮かんできた。
それは、見覚えのある村であり、見覚えのある人々であった。
自分は巨大な何かになっており、足を強く踏み下ろせばそこに風や豪雨が猛威を現し、こぶしを振り落せばそこに落雷が落ちた。
まつは愉快な気分になり、自分が棲んでいた叔母の家にこぶしを振り下ろした、木っ端みじんに家が飛散しあっけにとられている、叔母やはなの姿が見えた。
まつは自分が「にやるほてうぷ」となっていることを自覚した。
それから連日、洞窟内では「呪(しゅ)の日」が繰り返された。
その度にまつは、村に対し暴虐の限りを尽くしたのであった。
そんな日々が続いたある日、付近の村々は再び生贄を捧げにやってきた。
そしてそこでまつは遂にこの集団のすべてを知ったのだった……
「呪(しゅ)」を行う直前に食した、あの鍋の材料はどうやって用意するのか?
我々が必要以上に口を聞かず、まるで情を持つことを避けるように過ごしているのは何故か?
「呪(しゅ)の日」があるたびにここの住人が一人づつ消えていくのは何故か?
それを教えてくれたのは、「呪(しゅ)の日」にまつを洞窟の奥に促してくれた人だった。
「私たちは、呪(しゅ)の度に仲間を一人づつ解体して食す、鬼畜生なのだ。
お互い、情を持ってしまったら、こんなことは出来なくなるため、必要以上に口を利かないのだ。
恨み、妬み、憤りはただの想いではない、それは体中に染み付くものなのだ。
私たちは、それら鬼性が染みついた肉を食すことにより、より一層強く鬼性をわが身に宿す。
そしてそれは代が進む度に、より一層濃く、深くなっていくのだ。
私は、お前が来る前までは一番最後に来た者だったが、私もこの事は、その当時最後に来た者から聞いた。
お前も今日来たあの者に、この話を必ず伝えなくてはならない。
自分の前後に来た者のみを知るということだけで、この集落は成り立っている。
自分の前の者が呪(しゅ)の日に捧げられたら、次は自分の番になる。
これがここでの唯一の掟だ。
これにより、自分の最期を知るものがただ一人となるため、常に死の恐怖に悩まされるものは最小限の一人で済む。
直前の者の死の恐怖は、尋常ではないがそれすらもこの呪(しゅ)を強める事になる。
この掟も随分前から出来ていたようだが、その連鎖が途切れないということは私も含めて、この掟に皆、賛同しているということなのだ。
皆それ程まで村が憎いのだ。
村は『にやるほてうぷ』を鎮めるつもりで、生贄を捧げるがそれこそがこの呪いをより強力なものへと成長させるのだ。
いいか、この鎖を決してと断ち切ってはならぬ」
その者の表情には、狂気の笑みが浮かんでいた。
そしてその笑みは、まつにも……。

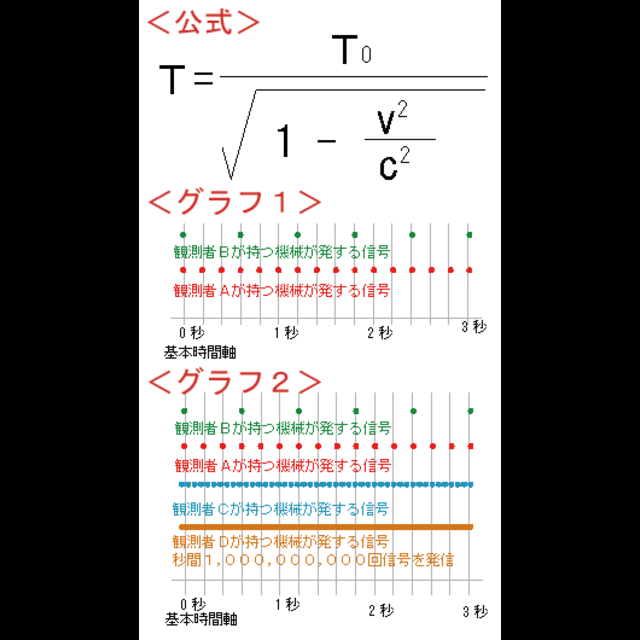
作者園長
昔話風の怖い話に挑戦しました。