ある深夜のことだった。
当時、私は尿意を感じて、自室を出た末にトイレに行った。
用を足した後、トイレから出てリビングを通り過ぎようとした時、ふとカーテンを仕切っていた窓が赤く光っていた。
救急車が来ていたのだ。
どうやら、向かいの家で何かあったらしく、救急車の光が点滅しながらそこに留まり続けている。
何か事故でもあったのだろうかと私がその灯りを見ていると、不意に耳元で、
「あと一人、入れますよ。」
と、ハッキリそう聞こえた。
反射的に振り向くも、誰もいない。
空耳かとも思ったが、それにしてはハッキリと男の声でそう聞こえ、私は怖くなった。
私がもう一度恐る恐る救急車の方を見れば、救急車は患者を乗せたであろうドアを閉めて、走り去って行った。
突然一人になった感覚に、私は階段を駆け上がり、自室に戻って布団を頭まで被った。
その日はあまり眠れなかった。
あの声は明らかに背後から聞こえた。
なのに、まるで救急車にもう一人乗れますよと言うような言い方に、私は何か不吉なものを感じていた。
そんな不吉な暗示は見事に当たり、翌日、母から向かいの家に住む高齢の女性が無くなったとの事だった。
あの声は、「もう一人、向こうに乗せて逝けますよ」ってことだったんじゃないか?
そう思うと、私は背筋が冷たくなった。
あまり考えないようにしながら学校へ行き、私はその当時友人だった、霊感体質のウロコくんにその事を話してみることにした。
ウロコくんは、幼少期、海で人魚と呼ばれる異形の存在に襲われ、常人には見えないものが見えるようになり、海水を浴びると体から魚の鱗が生えてくる体になったのだとか。
その鱗は霊感がある人間にしか見えず、真水を浴びると剥がれ落ちていく。
そんな不思議かつ、性格は中々無愛想なウロコくんと、私は友人という関係を築いていた為、彼なら何か知ってるかもと思った結果だった。
けれど、彼からは、
「何だそれ。」
とそう言われてしまった。
「いや、ウロコくんなら何か知ってるかなって思ったから……」
「知らん。聞いたこともない。」
「ええ……」
ウロコくんに経験がないのであれば、ますます嫌な予感がして堪らなくなる。
「大丈夫かな……」
「まあ、声が聞こえたなら、そっちには行かない方が無難だろうな。」
「それは分かってるよ。引き寄せられたらって思うと不安なんだよ。」
「怒るなよ。」
「怒ってない。」
怒ってるだろ。とそう言われ、私はウロコくんをじとっと睨む。
「見えるのが嫌なら、俺と関わるのを控えたらどうなんだよ。」
「見える人間と一緒に居ると、その人間も見えるようになるって言ったろ。」とウロコくんから返答が返ってくる。
「それは嫌だ。ウロコくんと話してないと暇だし。」
「そんなんだから巻き込まれるんじゃねえのか。」
またウロコくんを睨んだ。
「なんだよ。」と不満そうな声が返ってきた。
「もういい。」
ちょうどチャイムが鳴ったので、私は教室に帰る。
何でウロコくんと話したいのが分からないのか、突き放すような言動を取る彼に、私はウロコくんの声を無視して、教室に戻る。
私が怒っているのが目に見えて分かったのか、昼食の時に一緒に食べようと誘いに来たのはウロコくんだった。
屋上に続く階段で、コソコソ二人で食べるのも、もう私とウロコくんの日課になっていた。
屋上に続く階段は、普段鍵がかかっていて行けないようになっている。
だから、普段は誰も来ない所で、二人で昼ご飯を食べている。
仲直りという名の、ウロコくんの弁当の一部のカツアゲで、全てを許し、その日の放課後。
家に帰って来てすぐ、私は宿題が入ったファイルを持って帰って来るのを忘れたことに気付いた。
時間は既に生徒が学校から帰って、辺りが薄暗くなってくる頃。
一人で行くのは、昨日のこともあり、何となく怖かった。
ので、前に連絡先を交換していたウロコくんに電話をかけた。
ウロコくんに着いてきて欲しいと頼むと、「めんどい」と一喝されたが、その後すぐ、電話口から「そんなことばっか言ってたら振られるぞ。」とおじいさんの呆れた声が聞こえた。
結局、おじいさんのファインプレーのおかげか、渋々彼は私と学校に着いてきてくれることになった。
私がすぐに自転車で学校に行くと、唇をとがらせた彼は既に校門前に居て、「ごめんて…」と謝ると、「良いから行くぞ。」と手を引っ張られた。
怒る彼に「ジュース奢るから」と言うと、「いらない」と突き放されてしまった。
しゅん…としながら教室へ続く階段を上り、教室まで向かう。
だが、教室に着いた時、不意に私のクラスに誰かがいるのが見えた。
出入口前に立っていたので、ウロコくんと
「ねえ」
と声をかけると、「うわぁああ!!」と声をかけた人物が叫んだ。
そんなに驚くか?と、「え、ごめん」と謝ると、尻もちを着いた相手は、「な、なんだ……」とすぐに立ち上がった。
相手はなんと、前に出会ったことがあるイケメンくんだった。
調理実習の際、地雷系の女の子に変な卵焼きを盛られた傷は癒えたのか、何をしているのだろう。
「アンタ、何してんの?」
「お、お前の方こそ何してんだよ、」
「宿題取りに来ただけだ、早く取ってこい。」
「怒らないでよ、分かったから。」
「怒ってねえよ。」
ウロコくんに背中を押され、私は自分の机にあった宿題の入ったファイルを取り出し、小脇に抱える。
「取ってきたよ、帰ろ。」
イケメンくんが何をしてるのかは知らないが、まあこれ以上関わる必要も無いと、私はウロコくんの隣に並ぶ。
「は?帰るの?」
「いや、当たり前でしょ。元々は宿題取りに来ただけだし。」
ポカンとした様子のイケメンくんにそう言えば、
「お前らも肝試しに来たんじゃないのかよ?」
とそう言われた。
ウロコくんと顔を見合せて、
「肝試し?」
と私が呟くと、どうやらイケメンくん、幽霊部員として、ウロコくんが前に言っていた『心霊研究調査部』に無理矢理入れられていたらしい。
そのせいで部員二人の学校探検という名の肝試しに巻き込まれ、今に至るのだとか。
「なんか、イケメンくんって思ってた以上にビビりだよね。」
「イケメンくんって誰だよ!、俺は月島っていう名前があるんだ!!」
「じゃあな、月島。」
ウロコくんのドストレートな別れの言葉に、私は苦笑を落とす。
めんどくさくて堪らないと言ったウロコくんの顔に、私も帰りたいと、月島くんを放って帰ろうとした。
だが、不意に月島くんの立っている方角から、人が歩いて来た。
心霊研究調査部の二人が月島くんと合流したらしい。
「ちょっと月島くん、ちゃんと教室探索したの?」
懐中電灯と訳の分からない不気味な本片手に、いかにもなあの時の地雷系の女の子がそう言った。
おかっぱの黒髪に、前髪によく分からない柄のピンを指している。
なんか、トイレの花子さんに居そうな感じのする女の子で、紺色のワンピースを着ていた。
可愛い子ぶってるが、卵焼き事件の後、停学寸前まであと一歩の所だったのが校内中で噂になっている。
「う、うるさいな!ちゃんとしたよ!」
月島くんのヤケクソな叫びに、もう一人部員の男の子が前に出て来た。
「コイツ、ビビりだから教室の探索を一人なんて無理だよ、咲さん。さっきだって声かけられただけで、ビビって叫んでたろ、お前。」
ニヤニヤと笑みを浮かべる、咲さんとよく似た人種っぽい男の子だった。
黒くて長い前髪と、謎に黒いネイルがある爪、夏なのに長袖の薄手を身にまとい、上から半袖のシャツとズボンを着ていた。
「よ、余計なこと言うなよ、雨京(うきょう)!元はと言えばお前が……っておい!帰るなよ!!」
「何でよ、別にいいじゃん。」
ウロコくんと歩き出した辺りで、月島くんがこちらに駆けてくる。
余程あの二人といるのが嫌なのか、月島くんも私とウロコくんに便乗して帰ろうとしているようだった。
「なんでそんな、私とウロコくんに固執するのさ。」
「だ、だって、お前ら幽霊とか見えても大丈夫そうじゃん。」
「そんなくだらんことで、俺らを巻き込むな。」
「くだらんってなんだよ!」
「え、君達、もしかして幽霊見えるの?」
不意にウロコくんと月島くんの間に、雨京と呼ばれたさっきの男の子が入ってくる。
「見えたらなんだよ。」
ウロコくんが無愛想にそう返した。
「見えるなら、僕達の部活に入らない?部員がいないから困ってるんだよね。」
「断る。」
「私もいいや。」
即答でそう返した私とウロコくんに、雨京くんは「ええ〜」と不満そうな声を上げた。
「入ってくれたら面白そうなのに。」
「もう、階段降りんのめんどくせえから、エレベーターで帰んぞ。」
ウロコくんがそう言って、階段を通り過ぎて、エレベーターのボタンを押す。
生徒がエレベーターを使うのは禁止されているのだが、もう誰もいないしいいだろうと、私もそれに了承した。
ベラベラうるさい三人組を無視してエレベーターを待っていると、ピンポーンとすぐにエレベーターは降りてきた。
ドアが開き、皆でエレベーターに入ろうとしたその時だった。
“もう一人、入れますよ”
男の声で、私の背後からハッキリとそんな声が聞こえた。
ウロコくんには聞こえなかったのか、そのままエレベーターに入ろうとするウロコくんの腕を、反射的に私は掴んだ。
「なんだよ。早く乗って……」
「乗らなくていい。」
私は食い気味にそう言った。
ハッキリとそう言ったので、ウロコくんと私の異変に気付いたのか、三人もエレベーターに乗る直前で止まっている。
「……声が聞こえたのか?」
事情を知っているウロコくんにそう言われ、私は頷いた。
「声って何?、どんな感じ?誰が言ったの?」
雨京くんが私とウロコくんの話を聞いて、興味津々にこちらに近付いて来た、その瞬間。
ガチン!!とも、バチン!!とも付かないような猛烈に嫌な音が響き、誰も載っていないエレベーターが急降下した。
一瞬、周りの音がなくなり、エレベーターが地面に叩き付けられる轟音と、微かな揺れが私達を襲った。
徐々に徐々に、周りの音が戻り出した頃には、最終下校時刻の鐘が学校中に響いていた。
全員、無言で階段を降りた。
何も知らずアレに乗っていたら、間違いなく確実に、死んでいた。
そんな一瞬の出来事に、全員何も話すことはなく、一階に降りると、職員室から出て来た教師や用務員で、エレベーター前はごった返していた。
後から聞いた話じゃ、どうやらエレベーターのワイヤー部分に不備が見付かったらしく、それのせいで今回事件が起きたとの事だった。
皮肉にも、あの声のおかげで今回助かったのだ。
あの『もう一人、入れますよ』は、何か別のものがエレベーターに乗っていて、もう一人乗れば、向こうに行けますよ、みたいな声なんじゃないかと私は思った。
何はともあれ、誰も命を落とすことがなくて良かった。
だが、次の日から、雨京くんには、部活に入らないかとしつこく勧誘されるようになってしまったのは、どうにも痛手だったが。
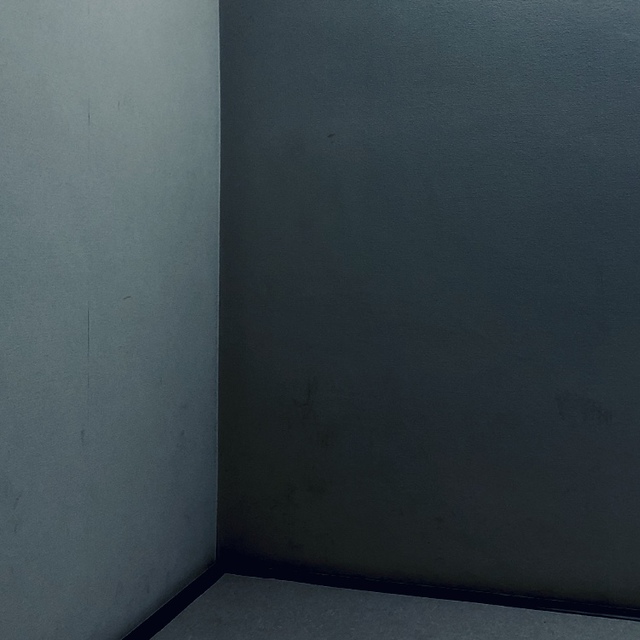





作者銀色の人
視える人が増えました、その名も雨京くん。
モチーフは、藤原くんシリーズの藤原くんです。
爪を黒く塗っているのは厨二病じゃなくて、あらゆる心霊現象に首を突っ込みすぎて、爪が汚れるため、それを隠すためです。