music:4
僕の住む町から、県境を跨いで、車で四時間ほど走った先にある小さな街。
数年前、その街で、身元の分からない一人の男の子が保護された。
wallpaper:4
調べてみると、男の子は街の人間ではなく、遠く何百キロも離れた他県で行方不明になっていた子供だった。その子の証言によると、数日間、見知らぬ女の家に監禁されていたのだという。
実は同様の事件、――他県で行方不明となった子供がこの街で見つかるという事件――、は過去にも四回程起こっており。警察は連続児童誘拐事件とみて、捜査をしていた。
被害にあったのは全員、小学校低学年程の男児。けれどもこの事件が特異だったのは、発見された男児たちに特に目立った外傷も無く、何かしらの危害を加えられたわけでもない、ということだった。親元に、身代金が要求された様子もなかった。
誘拐された男の子たちが入れられた部屋は、外が見えないように、窓の部分が塗り固められていたという。といっても電灯はついており、食事は三食きちんと与えられ、部屋にはTVの他、本やマンガ、ゲーム等もあった。
誘拐犯の女は、顔を隠すこともせず、連れてきた男児を本名では無く、『●●』 と同じ名前で呼んだ。そうして子供たちに、自分と会話することを求めた。
そうして数日が経つと、女は眠っている子供を車に乗せ、街の外れで解放した。
警察は、被害にあった子供たちの証言から、街に住む一人の女性を容疑者に上げた。彼女は街外れの古民家で一人暮らしをしていて、彼女自身の子供も、誘拐事件が起こるよりも以前に、事故か事件に巻き込まれたのか、行方不明の届けが出されていた。
失踪した息子への想いが犯行に走らせた、と警察は考えた。
そうして、警察は彼女の家を訪れたのだが、その時、すでに家に彼女の姿は無かった。
古民家の中からは、子供たちの監禁に使ったと思しき部屋が見つかり、その部屋の中からは、『息子の元へ行きます』 という内容の遺書らしき紙と共に、誘拐した子供たちへの謝罪の手紙が見つかった。
『●●』 とは、彼女の息子の愛称。誘拐された子供たちは、『怖かったけど、女の人は優しかった』 と口をそろえて証言した。
自身も行方不明となった女性は、彼女の息子と共に、未だに発見されていない。
その特異性から、この誘拐事件は一部のメディアでも取り上げられることになった。そうして、有名になった代価か、事件の舞台で今や廃屋となった古民家には、夜な夜な親子の話声が聞こえるだとか、行方不明になったはずの子供の霊が出る、といった、真偽の定かではない噂話がまとわりつくことになる。
――――――
誰かが玄関のドアを叩いている。
sound:14
wallpaper:198
閉められたカーテンの隙間を縫って、強い陽の光が室内に差し込んでいた。壁にかけてある時計を見ると、短針はアラビア数字の11を僅かに通り過ぎている。ベッドの中で目を覚ました僕は、両腕をつき上げて伸びをする。
来客か、それとも宅配便か何かだろうか。コンコン、コンコンと人を急かすようなノックだ。
「……はーい!」
と向こうに聞こえるよう大声で返事をして、僕は未だ名残惜しいベッドの海から抜けだした。玄関まで行く途中で洗面台の鏡を覗きこみ、酷い寝癖が無いのを確認してから、ロックを外しドアを開けた。
玄関前は無人。
あれ、と思い左右を確認するも、各部屋のドアが並ぶアパート二階の通路には、人の気配は無い。おかしいな、と首をかしげる。寝ぼけてあるはずのない音でも聞いたのだろうか。いずれにしても誰も居ないのだから、しょうがないか。
扉を閉めて、あふあふと欠伸などしつつ、二度寝をするため玄関に背を向けた。
コンコン。
sound:14
背後で扉を叩く音がして、僕は振り向く。確かに、誰かがノックをしている。「はいはい」 と返事をしつつ、再度、扉を開けた。
けれどそこには誰もいない。
閑散とした通路を見回し、子供のイタズラかな、と思う。でも、僕の部屋はアパート二階のほぼ中心にあり、ドアをノックして急いで逃げたとしても、端の階段につくまでに背中くらいは見えそうなものなのに。
下から石でも投げたのだろうかと地面を見やるも、そんな痕跡も無かった。
しばらく、一体どうやったのだろうと思案してみて、止めた。分からないものは分からない。そんなことより眠たくてしょうがない。もどって寝よう。僕は扉を閉めた。
……コンコン。
sound:14
また、ノックの音だ。
どうやら、向こうはこちらの動きをどこかで監視しているらしい。こういう手合いは、相手の反応自体を楽しんでいるのだ。もうドアは開けてあげません。僕は居間へと戻って夢の続きを見ることにした。
もぞもぞと、布団にもぐり込む。
コンコン……、コンコン……、コンコンコン。
sound:14
しつこい。あのドアの向こうに居るのが誰であれ、相当しつこい。僕がドアを開けるまで、そうしている気だろうか。やれやれと思いながら、再度布団から這いだして、足音を立てないよう気配を殺して玄関まで向かった。
ドアの目の前まで来る。ノックの音は続いている。その時、ようやくというか、ふと一つの疑問がわく。これがピンポンダッシュなら、どうしてインターホンではなくて、ノックなのだろうか。
本当は、ここでいきなりドアを開けて、逆に驚かしてやろうと思ったのだけれど、その前にと、僕はドアに顔を近づけ、そっと覗き穴から外の様子を覗いてみた。
wallpaper:1
魚眼レンズを通して見る、一点を中心にぐわりと湾曲した玄関先の光景。
そこに見えるのは、赤ペンキが塗られた手すりと、コンクリートの通路だけだった。誰の姿もない。ドアを叩いて、音を出すようなものは何も無い。
コンコン。
sound:14
ノックの音。外の様子を覗いている最中だった。その意味を理解した途端、首筋、うなじの辺りが粟立つのを感じた。
姿が見えないモノのノック。
残っていた眠気が綺麗に吹き飛ぶ。どうやら、金属のドア一枚隔てた向こう側に、得体の知れないナニカが居るらしい。
その時、アパートの階段を上って来る足音が聞こえて、身構える。足音はこちらへと向かってくる。覗き穴の前を、買い物袋を下げた人が通り過ぎた。
同じアパートに住む隣人だった。
wallpaper:175
反射的に、僕はドアを開いて外に出ていた。そうして、部屋に入ろうとしていた隣人を呼びとめる。
「あの、すみません」
隣人とは、あまり親しくは無く、会えば挨拶する程度だ。確か僕より一つ二つ年上で、学部は違うけれど同じ大学に通っているくらいにしか知らない。どうやら昼ご飯を買って来たらしい彼は、突然呼びとめられ、一体何事かと僕を見やった。
「はあ、え、何?」
「今さっき。僕の部屋のドアを誰か叩いてませんでした?」
「いや、見てないな。俺は叩いてないよ?」
「ここまで上がって来る時、誰かとすれ違いました?」
「いや」
「ノックの音とか聞きました?」
「……いや」
僕は確信する。やはり、この通路には最初から誰も居なかったのだ。
「そうですか……。分かりました。ありがとうございます」
隣人はどうにも釈然としない表情をしていたけれど、それ以上関わり合いになることもないと思ったのか、「じゃ」 と言って自分の部屋に入って行った。
僕も部屋に戻る。扉を閉めると、途端にノックの音が再開した。とりあえず構うことはせず、台所で砂糖入りのホットミルクを作って、居間に戻り、ベッドの縁に腰かけてゆっくり飲んだ。
飲みながら、現状を確認する。もはや、子供のイタズラである可能性は低いだろう。だとすれば、所謂ラップ音と呼ばれる現象と同じ類だろうか。今のところ被害は音だけ。それ以上害が無いなら、放っておいてもいいのかもしれない。
けれども、と思う。どうして、『今日』 で、『僕の部屋のドアを叩く』 のだろうか。大学生活のためこのアパートに越して来て大分日が経つけれど、こんな現象は今日が初めてだし、この部屋が曰くつきだなんて話は聞いてない。
部屋が原因で無いとしたら、原因は僕自身にある、ってことになる。部屋のドアをしつこく何度も叩かれる原因を、どこかでつくったのだ。
一つだけ、微かな心当たりがあった。
wallpaper:154
ホットミルクを飲みほした後、僕は携帯を取り出して、友人のKに電話をかけた。
コール音が耳元で何度も繰り返される。結局、Kは電話に出なかった。たぶん寝ているんだろう。Kは自他共に認めるオカルティストなので、色々と相談したかったのだけれど。
次に、僕はもう一人、友人のSに電話をかけた。
数回のコールの後、『……何だよ』 とSの声が聞こえた。
「あ、Sー? 僕だけど」
『ンなこた分かってる。要件を言え』
Sの声は少々不機嫌だ。どうやら、彼も寝起きらしかった。
「じゃあ、簡潔に。あんさ。昨日肝試しに行った場所までさ、もう一度、連れてって欲しいんだけど」
今からまだ数時間前の今日のことだ。真夜中、僕とKとSの三人は、ここから大分遠い街の、女性と子供の霊が出ると噂の古民家へと、肝試し兼オカルトツアーに繰り出していた。それ自体はいつものことなのだけれど、街までが非常に遠かったため、帰りが朝方になり、そのせいで今日は三人とも起きるのがおそい。
古民家では、何も見なかったし、何も起こらなかったのだけれど。もしかしたら。いわゆる、『お持ち帰り』 をしてしまったのかもしれない。
『昨日の? ……理由は?』
訝しげなSの声。僕は、つい先ほど体験したことをかいつまんで説明する。これがオカルティストのKならノって来るのだけれど、Sは超常現象と聞くと鼻で笑うタイプの人間なので、何時、『……くだらねぇ』と言われ、電話を切られるかとドキドキしながらの説明だった。昨日だって、Sだけは肝試しでは無く、夜の長距離ドライブという感覚だったに違いない。
「……あ、もちろん、ヒマだったらで良いんだけど。駄目っていうなら、電車とバスで行くし」
幸い、途中で切られもせず、全部話すことができた僕は、最後に、そう付け加えた。
『電車とバスで行け』
電話が切れた。
だよねー、と思う。存外に遠いというのは昨日の経験から自明だし、断られるのは、予想していた。
それに何しろ、どうしてもう一度そこへ行くのか、自分でもよく分かっていないのだ。本当なら、何かに憑かれたようなのでお払いしてください、とお寺に行くか、もしくは幻聴が聞こえますと病院に駆け込むのが正解なのだろう。
コンコン、といくらかの間を開けながら、未だにノックの音は続いている。
sound:14
けれども、どうしても気になってしまう。何故か、気味が悪いだの、鬱陶しい、煩わしいなどとは思わなかった。むしろ、原因を突き止めたいといった好奇心、もしくは使命感が、僕の中にあった。
立派なオカルティストであるK程ではないが、僕自身も、そういう類の話には関心の強い方だ。自分が住むアパートで起こったのなら、なおさら、探究心は膨れ上がる。
それに、主な被害がノックの音だけ、というのが気になっていた。そのせいで危機感も薄いのだろうけれど。
ノックの音が聞こえるも、おもてに人はいない。その手の怪談は聞いたことがある。夜中にノックの音がして、けれども、扉を開けても誰もいない。聞き間違いかと思い、戻ろうと振り返ると、背後に居た。というヤツだ。その際のノックの意味とは、扉を開けさせることなのだろう。
そう言えば、前に読んだ小説だけれど、陰陽道に関する話で、家とはそれ自体が家主を守る結界のようなもので、あやかしは中から招かれない限り、入ることは難しい、と書いてあったことをふと思い出す。
自らドアを開けることは、相手を受け入れるのと同意。なので、その作中のあやかしはあの手この手で中のものに扉を開けさせようとする。
けれども、この場合は事情が違う。僕は一度ドアを開けた。なのに、ノックの音だけが続いている。
嫌がらせでなければ、それはまるで、僕にこの部屋から出てきて欲しいと言っているようだった。呼ばれている、と言えばいいのだろうか。延々と扉を叩く目的が、自らが中に入るためでは無く、僕を外に連れ出すためだとしたら。
あの音の主は、一体僕に何をさせたいのだろう。
wallpaper:175
考えた結果が、あの昨日訪れた古民家だった。ここ数日の内に原因があるとすれば、あの場所しか思い当たるふしはない。
ベッドから立ち上がり、しかし自分って本当に行き当たりばったりで無計画な人間だなあ、などと内心思いながら、出掛けるための身支度をする。
シャワーを浴びて出て来ると、携帯が一軒のメールを受信していた。
Sからだった。
【件名】さっきの件について。
【本文】昨日の分と合わせてガソリン代を出すなら、考えなくもない。
全くSらしいというか。僕は少し笑って、『おいくら?』 と返信した。
走行中の車の窓から外の景色を見やる。前方から後方へ。車に近いものほど早く、遠いものほどゆっくりと。
wallpaper:123
約半日前にも通った道なのだけれど。状況は違う。あの時は陽が昇る前だったので辺りは暗く、車酔いのため後部座席で死体のように寝転がっていたKも、今はいない。
運転席の方から、欠伸が聞こえて、僕は窓の外から視線をそちらに移す。
ハンドルを握るSは、先程から非常に眠たそうだ。居眠り運転で事故されても困るので、何か話しかけることにする。
「あんさあ、Kが昨日話してくれたこと。覚えてる?」
「……誘拐事件の話か? ああ、大体はな」
数年前。僕らが高校生の時に起こった、連続児童誘拐事件。僕は覚えていなかったけれど、そこそこ世間を賑わしたらしい。
真夜中。その事件現場である古民家の庭先で、Kは、僕とSを前に、誘拐事件発生に至る経緯から、警察の捜査状況、どこで仕入れたんだというような情報まで熱く語ってくれた。
「冗談半分に聞いてくれればいいけど。もしかしてさ。昨日、あんな話をKがしたから、僕の家にやって来たんじゃないか、って思うんよね」
「何が」
「さっきも言った、ノックの主」
Sが欠伸をする。眠たいのか、馬鹿にされているのか。
「いや、でも、そんなことのためにわざわざ悪いね。二度も。遠いのにさ」
「ああ、全くだな」
Sは、心底面倒くさそうに言った。だったら、あんなメール寄こさなきゃいいのに、と思う。ちなみに、ガソリン代として要求されたのは、4480円だった。十円単位で要求してくるとは、ちゃんと残量をはかって計算したのだろう。キッチリしてるというか、何というか。
「そういや聞きそびれてたな。お前、あの空き家に行ってどうするつもりなんだ?」
「んー、まだ決めてないな」
「……何だそりゃ」 と前を向いたままSが呟く。実際に決めてないのだから仕方が無い。
「もしかしたら、家の中に入ることになるかもね」
前夜の段階では、事件のあった古民家を外から眺めるだけだった。現在、誰が管理しているのかは分からないが、窓にカーテンが掛かっていて中は見えなかったけれど。おそらく、家具はそのままにしているのだろう。ここの住人はあくまで、行方不明扱いで、いつか戻って来るかも知れないのだ。
「住居不法侵入だな」
「分かってるよ。でもさ、それってさ。向こうの方からウチに来いって、『呼ばれて』 それで入ったとしても、罪になるんかな」
「……お前がどういう場合を想定してるかは無視してだ。今回の場合では、なる」
「あーそっかぁ」
「大体どうやって入るつもりだ。玄関にはカギが掛かってるだろ」
確かに。当然の話だけれど、昨日確認した限りでは、玄関のドアは鍵なしでは開かないようになっていた。侵入できそうな窓もない。一ヶ所だけ、内側から窓が塗り固められている部屋もあった。
「ノックすれば開けてくれるんじゃない?」
僕は、冗談のつもりで言ったのだけれど、Sは、今度は確実に僕のことを馬鹿にしているのだ、と分かるような欠伸をして、こう言った。
「……中に人が居りゃあな」
それから数時間と数十分車で走って、僕はSの二人を乗せた車は、目的の古民家がある街まで辿りついた。時刻は、四時半を過ぎたところだった。
昨日と同じ場所、少し離れた場所にある住宅街の一角に車を停める。
「着いたぞ。ここからは歩いて行けよ」
とSが言う。そうして彼はシートベルトを外すと、後ろにシートを倒して目を閉じた。どうやら、これ以上付き合う気はなく、僕が戻って来るまでに、ひと眠りするつもりなのだろう。
しばらくして、Sが目を開けた。
「……何だよ。早くいけよ。場所は分かってんだろ?」
怪訝そうに言うSを、「ちょっと待って、静かに」 と制す。
何か、聞こえた気がした。
……コンコン。
sound:14
ノックの音。
早く車から出ろと言っているのだろうか。
「この音、聞こえる?」
僕が尋ねると、Sは、「……いや」 と首を横に振った。
「あーそっか……、これ、今日以降もずっと続くようだったら、やっぱ病院かなぁ」
「おい……」 と何か言おうとしたSを置いて、車を出る。少し歩くと、後ろでドアの閉まる音がして、振り返ると、Sがのろのろと大儀そうに車を降りていた。
住宅街からしばらく歩いた、山へと続く細い坂道の脇に、家はあった。ここに来るのは二度目だ。振り返ると、眼下に僕らが車を停めた住宅街が一望できる。近くに他の家の姿は無く、まるで仲間外れにでもされたかように、ぽつりと、その古民家は建っていた。
wallpaper:178
瓦屋根の平屋で、建物自体は相当古くからここにあるのだろう。昨日は夜中だったのでよく分からなかったのだけれど、所々に年季を感じる。ただ、窓の向こうに見えるカーテンの模様などは現代風で、つい数年前まで人が住んでいたという名残もあった。
外から家自体の大きさは、親子二人だけで暮らすには、少々もてあましそうだった。
雑草の生えた花壇のある小さな庭を通り、玄関の前で立ち止まる。擦りガラスがはめ込まれた木製の二枚戸だ。
「で、どうすんだ?」
とSが言う。
僕は、戸に手をかけ、力を込める。当然のことだけれど、鍵が掛かっていて開かない。昨日の夜も確認したことだ。ノックの主が僕をここまで呼んだのなら……。という淡い期待もあったのだけれど、現実はそう甘くは無いようだ。
しばらく、無言のまま玄関を見つめていた。
始まりは、僕の部屋の玄関から聞こえたノックの音だ。僕は、その音に誘われて、四時間もかけて、再度ここまでやって来た。運転したのはSだけど。
玄関に呼び鈴等は付いていなかった。二度、軽くノックする。扉が揺れて、ガシャガシャとガラスが身悶える音がした。
コンコン。
sound:14
中から、返事があった。渇いた響き。僕がアパートの自分の部屋で聞いた音とまるで同じだった。
たとえこの音が幻聴だとしても、僕はこの音に呼ばれている、それは確信できた。
後ろに居たSの方を振り返る。
「どうにかしてさ、この中に入れないかな」
僕が尋ねると、Sは、非常に面倒くさそうな表情をした。そうして投げやりな口調で、
「……どうにかしたいんなら、入る方法なんていくらでもあるが」
と言った。
「どうにかしたいね」
僕は答える。Sは肩をすくめた。
「一応念を押しとくが、どういう形で入るにしろ。れっきとした犯罪だぞ」
「今さら?」 と僕は少し笑って返す。Sは少し上を向いて、ふー、と小さく息を吐く。
「……やれあの街に連れてけだのやれ扉を開けろだの。全くやれやれだな」
嘆きながら、Sはドアの前にしゃがみ、戸の下部分、ガラスがはめ込まれている細い骨組の部分を掴んだ。ん、と一声、力を込める。どうやら、襖を外す時のように、二枚の戸を同時に持ち上げようとしているらしい。
鍵が掛かっているなら、扉ごと外してしまえという作戦だ。そんな安易な力技で大丈夫なのだろうか、と僕が思った瞬間だった。
派手な音がして、二枚戸が玄関の奥へと倒れる。
扉が外れた。
唖然としている僕を尻目に、Sは外した二枚戸を引きずって玄関の端によせると、
「二枚戸で、立てつけの悪い家なら、こういう侵入方法もある。まあ、窓を割るのが一番手っ取り早いが、不法侵入に器物破損が加わるのもアレだしな」
と何気もなく言った。何でそんなこと知ってんだと正直思ったけれど、聞かないことにした。
戸の無くなった玄関から、家の中を覗く。すぐそこは、四畳半ほどの板の間だった。一本の紐を渦巻状に敷き詰めたような丸いカーペットが無造作に敷かれている。正面と左右にそれぞれ戸があり、各部屋へと繋がっているのだろう。
「とっとと行って来い。人が来ないか見ててやるからよ」
Sの声に背中を押される形で、僕はその一歩を踏み出した。
「おじゃましまーす……」
wallpaper:22
玄関で靴を脱ぎ、僕は一人、中に入る。玄関の方からしか陽の光が届いていないせいか、意外と薄暗い。埃が舞っているらしく、鼻孔が少しムズムズした。
しばらく、じっと耳を済ます。けれども、何も聞こえてこなかった。あのノックの音もない。何故だろう。自分で探せといいたいのだろうか。
ふと、家の西側の部屋が、誘拐事件の際に子供たちの監禁に使われた部屋だということを思い出す。昨日鍵の有無と共に確認した事柄だ。内側から窓を塗り固めた部屋。そこへ行こうと僕は左手の戸を開いた。まっすぐな廊下が伸びてあって、三つほど扉がある。
手前のドアから順に開けて、確かめていく。物置。次いで客間だろうか、空の部屋。そうして残ったのは、一番奥の部屋。ドアノブに手をかけ、ゆっくりと開ける。
一瞬、ドアの隙間から、暗闇が飛び出してきたような錯覚を覚えた。暗い。辛うじて、開いたドアから差しこむ光が、室内を僅かに照らしている。
誘拐された子供たちは、ここで監禁生活のほとんどをすごしたのだ。
部屋の中、ドア近くの壁に、明かりのスイッチらしきものがあったので、押してみる。
途端に、温かみのある柔らかな光が室内に満ち、見えなかった部屋の様子が照らし出された。どうやら、電気は未だ送られているようだ。そうして、僕はハッとする。電気をつけてしまって良かったんだろうか。まあしかし、やってしまったものは仕方が無い。
部屋の入り口から見て、左手には大きなベッドと、天井に届くかという程の高さで、マンガ本や図鑑などがびっしり収まっている本棚。右奥にはいくつかのゲーム機器が並ぶ納棚があり、その上に、当時としては最新型だっただろう薄型テレビが置かれている。
壁の方を見やると、クレヨンだろうか、全身真っ黒な人間を書いた落書きがあった。子供が書いたものじゃないかと推測する。
その落書きの上、窓があると思われる部分が、周りの壁と同じ色の薄い板で覆われていた。窓がないという一点を除けば、ここで過ごすのに不便など何も無い、快適な子供部屋と言えた。
天井には、電球に白い傘を被せただけの簡素な照明がぶら下がっている。
「白熱灯だな」
いきなり、背後から声。
比喩でなく、心臓が弾け飛び散るかと思った。振り向くと、いつの間にかSが背後に立っていて、僕の肩越しに室内を覗きこんでいた。
「あー、びっくりした……足音くらいたててよ」
「勝手に入った見も知らぬ人の家でか? 馬鹿言うなよお前」
まるで正しいことのように聞こえるけれど、それはどうなのだろう。
「……見張ってるんじゃなかったん?」
「飽きたんだよ。……それにKの話をよくよく思い出してみりゃ、気になることがいくつかあったしな」
入口付近に立っていた僕の肩をちょいと押し、脇にどけると、Sは室内の丁度真ん中でぐるりと周囲を見回した。
「お前は、どう思う?」
突然のSの質問に、僕は、「え、何が?」 としか返せなかった。
「何がも何も、この部屋だ。気にならないか?」
言いながらSは徐に、ベッドの下から何か箱を引き出してくる。「失礼」 と言ってSが箱のフタを開けると、中には様々な種類の玩具が詰め込まれてあった。
「あれもこれも、小さな子供の身分にしちゃ、少し、贅沢過ぎるんじゃないか? まあ、一人っ子なんて大体こんなものかも知れんが。やっぱり、ちと過保護の気があるな」
Sが何を言いたいのか分からない。まさか、自分の子供時代と比較して拗ねているのだろうか。
「誘拐してきた子供のために買いそろえたんじゃない?」
僕が言うと、Sは首を振った。
「全部じゃないかも知れんが、名前が書いてある。●●ってな。ここの子供の愛称だったか」
玩具箱を覗きこむと、確かに、一つ一つの玩具に、『●●のもの』 と書かれたシールが貼られている。
「ここで数人、Kが言うには四、五人だったか、の子供たちが何日間か監禁されたんだったな」
玩具箱のフタを閉め、元通りにベッドの下に戻しながら、Sが言った。確かに、その通りなんだろう、と僕は頷く。
「おかしいだろ」
「どこが?」
立ち上がったSは、部屋の中をぐるぐると色々見物しながら、僕の方は見ずに言った。
「ここが監禁に使った部屋だとしたら、一人監禁して逃がした時点で普通バレる。普通ならな」
それはどうだなのろうか。Sの言葉に、僕は首をひねる。
「……そうかな?」
「子供は証言したんだ、『窓の無い部屋だった』 ってな。詳しく聞けば、警察も内側から窓を隠したってことが分かったはずだ。そうして、家を外からみりゃ、この部屋が窓を塗り固めてるってことは一目で分かる。つまり、傍から見ても犯行現場である可能性が大なんだよ、ここは」
窓のない部屋が存在する家。同じ街で解放される行方不明だった子供。誘拐犯の女。
被害にあった子供の証言とこれだけの要素があれば、容疑者を特定して、逮捕に至るのは簡単だ。とSは言う。
なのに何故か、事件は二度目ならまだしも三度目、四度目まで起こった。
「たぶん警察は犯人が、子供たちが窓の外を見て、景色を覚えるといけないから、窓を潰したんだと。その視点で捜査をしたんだろう。だから捜査が遅れた。それともう一つ、近所の住人からこの家の情報が警察に行かなかったのも、同じ理由だな」
僕自身も、この部屋の窓を潰した理由は、子供に場所を特定させないためだろうと思っていた、大体、他に一体何の理由があるというのか。
「光線過敏症」
shake
wallpaper:87
耳慣れない言葉が、Sの口から出て来る。
「平たく言やあ、紫外線を受けると、人の何倍もの速度、深度で日焼けする体質のことだ。まあ、それを誘発する病気によって症状はいくつかあるがな。ともかく、この部屋に、『本来』 住んでいた子供は、それだったんだろう」
「え……、や、ちょ、ちょっと待ってよ。何でそんなことが分かるのさ」
するとSは天井を指差し、「白熱灯はな、光量が少ないわりに電気代が高いんだよ」 と良く分からないことを言った。
「まあ、まだ他にも色々と根拠はあるが。別の部屋にいくつか本があってな。光線過敏症、またはポルフィリン症についての本だった。が、一番は、写真があったからな。黒い頭巾を被った子供の写真がな。……ともかくだ。この部屋の窓が潰されたのは、誘拐事件が起こるずっと前で、なおかつ、周りの人間もそれを知っていたんだろうな」
「その、光線過敏症ってことは、太陽の照っている時は、外に出られないの?」
「そうだな。陽の光には当たらない方がいいからな。だから、部屋の中で不自由なく遊べるよう、色々買い与えたんだろ」
僕はあらためて、この日光の差さない部屋を見やった。内側から潰された窓、まだ小さな子供に過保護な程与えられた本や玩具。もしかすれば、Sのいう通りなのかもしれない。
「……それが、Sの気になったことなん?」
「気になったことの、一つ、だ。でもそれは、向こうで見た光線過敏症に関する本と、この部屋の白熱灯で大体確信できた。問題はもう一つ、その先の話だな」
うろうろと見物しながら歩きまわっていたSが立ち止まり、僕の方を見やる。
「光線過敏症である子供がだ。日光を避ける生活をしている子供が、行方不明なんかになるか? たとえ、行方不明になったとしてもだ。未だに発見に至ってないのは、何故だ」
言葉に詰まる。
「それは……、ただ単に行方不明になって、ただ単にまだ見つかってない……じゃ、駄目なん?」
「こういった症状を持つ子供の行動範囲がそれほど広いとは思えない。となれば誘拐、ということになるが、お前が誘拐犯だとして、黒い頭巾を被って顔も見えない子供を誘拐しようと思うか?」
「それは、分からないけど」
「身代金の要求があったわけでもなさそうだしな。ただ単に行方不明なんだよ。ここの女が起こした事件と同じでな」
「じゃあ、Sは、どう思ってんの」
「俺は、」
Sは、そこでいったん、言葉を切った。
「……俺は、その失踪した息子が、いや、誘拐犯の女自体も、まだ、この家にいるんじゃないかと思っている」
誘拐犯の女とその息子が、まだこの家の中に居る。
wallpaper:156
すぐには理解できなかった。噛み砕いて、その言葉の意味をゆっくりと脳に染み込ませる。ようやく理解し、最初に出てきた感想は、そんな馬鹿な、だった。
「そんなこと……」
「無いと言い切れるか? お前、Kが言ってた、犯人の女が失踪する前にのこした遺書らしき手紙の内容覚えてるか? 確かな情報じゃないかも知れんが、『息子の元へ行きます』 って言葉は、『息子の居場所』 を知っている者の台詞だ」
「……何年も行方不明で、死んだものと思ったんじゃない?」
「個人的な視点になるが、俺はそうは思わない。息子のために、白熱灯ならまだしも、部屋の窓を潰すような母親だぜ?」
「でも、だったら……、行方不明は、狂言だったってこと?」
「さあな。それは分からないな」
「狂言なら、まさか、二人共生きてる……?」
「いや。少なくとも息子は死んでるだろうな。だから、彼女は誘拐事件を起こすんだよ。動機については、警察の見立てで間違ってないと思う」
いなくなってしまった息子への想いから、同じ年頃の男の子を誘拐しては、数日間だけ一緒に暮らす。息子と同じ部屋に閉じ込めて、息子と同じように会話をしようと話しかける。
「つまり、だ。俺は、母親は何らかの理由で死んでしまった息子の死体をどこかに隠し、周りには行方不明になったと伝えた、と考えてる。認めたくなかったのか、他の理屈が働いたのかは知らないがな」
そして、一人に耐えきれなくなった母親は誘拐事件を起こす。息子の部屋で子供と接することで、自分の子供は生きていると思い込みたかったのだろうか。けれども、その行為を数回終えたところで、悟ったのだろう。所詮、彼らは、自らの息子じゃないのだから。
「でもさ、何で、その二人の死体が『この家にある』 って分かるんよ?」
「別に分かってるわけじゃない。ただの希望的確率論だ。自分の一人息子なんだから、少しでも傍に置いときたいと思うのが人情だろ」
そうして、Sは壁を二度、コンコンとノックする。
「……そして、だから、お前は今日ここに来たんだよ」
「は……?」
紙風船から空気が抜けたような間抜けな音が、僕の喉から滑り落ちる。
「……僕が、何?」
「言っとくが、今俺が言ったのは、未だ真相でも何でもない。全て想像と憶測の産物だ。ただ、お前も、俺と同じように考えたに違いないんだ。否定するか? お前は無意識下の元ロジックを組み立てたんだよ。そうして、それを探したい、見たいという欲求がノックの音になって意識下に現れたんだ」
「なっ、な、おい、何でSにそんなことが分かるのさ」
「お前に聞こえるノックの音は、俺には聞こえない。だとすれば、そいつはお前の中で鳴っている音だ。お前自身が脳みそをノックしてたんだよ」
「そんなこと言ったって、僕は、この家の子が、日光に触れちゃいけない体質だったなんて初めて聞いたよ?」
「数年前に、この事件が世間で話題になった時、そのくらいの情報は流れただろうな」
「し、知らないし、見てないし、覚えてないし」
「覚えてなくたって、ちらりと見やっただけの情報も、脳みそはちゃんと保存しているもんだ」
そんな馬鹿な、と言おうとしたけれど、それより早くSが口を開く。
「じゃあ聞くが。お前、この家に入ってから、ノックの音は聞いたか?」
その言葉に、僕は絶句する。確かにそうだ。この家の中に入ってから、それまで僕を誘導していたノックの音は、ぱたりと止んだ。まるで、その役目を終えたかのように。
「その音の役割は、お前を、親子二人の死体がある『らしい』 この家に連れて来ることだ。ここまでは無意識下で組み立てられても、肝心な死体がどこにあるかなんて、分からないからな。誘導しようがないのさ」
僕は目を瞑り、後ろの壁にもたれかかる。身体から、どっ、と力が抜けてしまったようだ。
Sが小さく笑って、僕の肩をたたく。
「もう、ノックが聞こえることは無いだろ。ま、喜べよ。Kにいい土産話が出来たじゃないか」
全く慰めになってない。僕は、力なく笑った。
それは結局、僕は自身の思い込みに従い、大きな大きな無駄足を踏んだということだ。
「帰るか」
というSの言葉に、僕は黙って頷いた。トボトボと、Sの後ろをついて家を出ることにする。当初、ノックの主に呼ばれているだなんて思っていた僕が馬鹿みたいだ。
それでも。と頑張って思い直す。今日の体験が、非常に不思議で、なおかつドキドキワクワクして面白かったことは間違い無い。ノックの音に誘われて、僕は、こんなところまで来てしまい、そこで起こった事件の裏の一面を少しでも垣間見たかもしれないのだ。
まあ、良い体験をしたと思おう。
玄関のある部屋まで戻る、Sはもう靴を履いて外へ出ていた。これから、あの外した玄関の戸を元に戻さなくてはいけない。立つ鳥跡を濁さずってわけだ。
その時、ズボンのポケットの中で、携帯が振動した。電話だ。誰だろうと思い取り出してみると、それはKからだった。
少し早めに、恥ずかしい土産話を披露することになるのだろうか。一人で苦笑いしながら、僕は、外に居るSに、「Kから電話」 と伝えて、玄関の段差に座り、通話ボタンを押した。
『よおー。俺だ。昼に電話くれてたけどよ。何か用かー?』
どことなく陽気なKの声。
「え? K、まさか今起きたん?」
『わりーかよ』
確か、時刻はもう五時に近いはずだ。
「遅いよ。何時だと思ってんだよ、もう夕方になるよ?」
『うっせーなー。何だよ。ソッチの要件は何だったんだよ』
う、と言葉に詰まってしまう。Sの方を見ると、そっぽを向いて欠伸をしていた。
「……ノック」
『はぁ?』
「ノックだよノック。そのノックのせいで精神的にもノックアウトしちゃってさ。もうまいっちゃってさ」
やけくそになって、僕は床を拳で軽くコンコンコンコンと叩きながら、あはは、と笑う。上出来な自虐ギャグだ。自分でも可笑しかった。可笑しくて、笑う、床を叩いて、笑って。
そうして、僕は、笑うのを止めた。
電話の向こうで、Kが何か言っている。でも、何を言っているのか、まるで聞こえない。
床を叩く。
コンコン。
sound:14
もう一度、違う場所を。
コンコン。
sound:14
立ち上がって、携帯を切った。
外と室内を繋ぐ四畳半程の部屋には、カーペットが敷かれている。最初に入って来た時も見た、渦まき模様の丸いカーペット。僕はその端を持ち、少しめくってみた。
カーペットの下は板の間で、そこには、半畳程の大きさの正方形の扉があった。
心臓が、音を立てて鳴っている。頭の中を様々な思考が飛び交っているのに、何も考えることが出来ない。
それは、取っ手の金具を引き出して上に持ち上げるタイプの扉だった。この先に何があるのか、何の扉かもわからない。
手を伸ばして、扉を叩く。
コンコン。
sound:14
それは、僕が今日、今まで聞いてきたノックの音と、全く同じ音だった。
どうしてだろう。どうして僕は、『この音』 を聞くことが出来たのだろう。先程Sが言ったことが正しければ、僕は、僕が聞いたことが無い『この音』 を、創り出せたはずがないのだ。
……コンコン。
sound:14
僕は叩いていない。
それは、今まで聞いた中で一番弱々しかったにも関わらず、一番はっきりと聞こえたノックの音だった。決して、脳内で創り出した音なんかじゃない。僕の鼓膜は、確かにその微弱な振動を捉えていた。
扉についている金具を引き出し、僕は、扉を持ち上げる。かなり重かったけれど、ゴリゴリと音を立てて、扉の下からゆっくりと、まるで井戸のような黒いうろが姿を見せた。
据えた匂いと、ひやりとした空気が、穴から立ち上る。背筋がぞくりとして、全身に鳥肌が立った。
扉を落としそうだったので、裏側にあったつっかえ棒で、固定する。
「……何やってんだ?」
wallpaper:1
いつの間にか、Sが玄関からまた家の中に入って来ていた。僕は返事もしないで、扉の奥の穴を見つめていた。
「そいつは……、たぶん、芋つぼだろうな」
「芋つぼ……?」
「その名の通りだよ。芋を保存しとくために地下に掘る天然の土蔵だ。古い民家なんかにはたまにある。……というか、お前これどうやって見つけたんだ?」
Sの話を聞くでもなく耳にしながら、僕は穴の奥から目が離せないでいた。
「……Sさ、車の中に、懐中電灯ある?」
少しの沈黙の後、Sは、
「あるぞ」
と言った。
「それさ、取って来てくれない?」
Sは、何も言わず、黙って車へと向かった。しばらくして戻って来たSの手には、二本の懐中電灯が握られていた。玄関先からその内の一本を、僕に投げてよこす。
「ありがと」
ちゃんと光がつくかどうか確かめて、僕は再び穴に向き合った。
そっと、光の筋を、穴の奥に這わす。
思ったより穴は深いようだった。三メートルほどだろうか。木の梯子がかかっていて、下まで降りたところで、横穴がまだ奥に続いているらしい。横穴の様子は、ここからでは伺えない。
何故か、迷うことは無かった。僕は、穴の中に入ろうと、扉の縁に手をかけた。
「おい」
Sの声。僕は顔を上げる。
「数年間放置されてたんだ。梯子が腐ってることもある、気をつけろよ」
「……OK」
梯子に足をかける。最初の一歩を一番慎重に。腐っている様子は無い。二歩、三歩と、僕は芋つぼの底に降りてゆく。頭まで完全に穴の中に入ったところで足元が見えなくなり、あとは完全に感覚で、僕は梯子を下った。
しばらくすると、足の裏が、地面の感触を掴む。芋つぼの中は、かなり寒かった。湿気なども無さそうで、なるほど、と思う。食料を保存しておくには適した場所だろう。
スイッチを入れっぱなしにしていたライトを、ポケットの中から出す。そうして僕は、ライトの光を、そっと横穴に向けた。
あの時の光景を、僕は一生忘れない。
wallpaper:124
暗闇の中、足元からすぐ先に、一枚の茶色く変色した布団が敷かれている。
その上で、一組の親子が、互いに寄り添う様にして静かに眠っていた。
掛け布団の中から、二つの頭だけが出ている。きっと、あの見えない部分では、母親がわが子を抱きしめているのだろう。
僕はライトの光を向けたまま、茫然と立ち尽くしていた。
それ以上、一歩も前に進むことが出来なかった。足やライトを持つ手が震えているのが分かった。恐怖では無い。ただ、身体が震えていた。
息をするのも辛くなって、僕は二人に背を向けた。その時、初めて自分が泣いているのだと知った。嗚咽もなく、ぼろぼろと涙だけがこぼれた。
涙は熱く、頬に熱を感じる。
怖くは無い。悲しくもない。感動しているわけでもない。よく分からない。ただ、強いて言うなら『痛いから』 だった。自分の中の芯の部分が、ネズミのような何かに、集団で齧られているような。そんな気分だった。
頭上から、ライトの光が降って来る。Sだった。自分が照らされていることを知り、僕は俯いて涙をぬぐった。身体の震えは、いつの間にか消えていた。
梯子をつたって、上へと上る。震えは止まったけれど、思うように身体が動かず、えらく時間をくった上に、最後はSに引っ張り上げてもらった。
Sは何も言わなかった。僕が落ち着くまで待つつもりなのだろう。ふと玄関の方を見やると、家の中を隠すように、戸が玄関に立てかけられていた。
「ごめん……。もう大丈夫」
そうして、僕は、Sについ先ほど見てきた光景を話した。
「そうか」
Sの感想は、ただそれだけだった。
僕はずっと考えていた。それは、僕がどうして、あの二人を見つけることが出来たかについてだった。偶然だったのか。または必然だったのか。僕が無意識下でまたやらかしたのか。それともあの二人に、もしくはどちらかに、呼ばれたからだろうか。
答えは出なかった。
僕は、ポケットから携帯を取り出す。
「止めとけよ」
その次の行動を見透かしたように、Sが言った。
「……何を?」
「警察に通報するつもりだろう」
「……そうだけど。どうして?」
「俺が警察なら、お前を真っ先に疑う」
その口調には何の力も込められていおらず、ただ、いつも通りのSの言葉だった。
「あの二人をここに閉じ込めて殺した犯人としてな。ノックの音が聞こえたんでそれで来ました、なんて言ってみろ。それこそ、精神異常者として扱われるのがオチだ。まあ、色モノが大好きな世間様には気に入られるだろうが」
「それじゃあ、公衆電話から……」
「そんな電話、こちらから名乗れない以上、イタズラと思われて終いだろう。警察はイタズラ電話多いからな」
「じゃあ、どうすんのさ……、だからって、このままにしとくわけにはいかないしさ」
すると、Sは、ゆっくり息を吸って、こう言った。
「何がいけないんだ?」
それは、予想もしなかった言葉だった。
「何がって……」
「俺は別に良いと思うけどな。このままでも。親子水入らずで過ごせるんだ。別に悪いことじゃないだろ」
僕はあの二人の姿を思い出す。二人で寄り添い、一つの布団に入って眠っていたあの姿を。ここで、親子の居場所を外に教えることは、あの二人の間を裂くことになるのではないか。
何故いけないのか。そうだ、何故いけないのだろうか。
僕は答える。
「……やっぱり、駄目だ。知らせよう」
病弱な息子を守りたい、危険から遠ざけたいとした母親。でも、息子の方からすればどうだったのだろう。生きている頃も、窓の無い部屋でずっと母親に守られ、死んでからも、こうして母の手に抱かれている。
「あのさ……、性懲りもなくって思うかもしれないけんど……。僕が聞いたノックの音って、あの男の子が僕を呼んだんじゃないか、って思うんよ」
芋つぼの扉を叩いた、弱々しくもはっきりとしたあの音。あれは、『外に出たい』 意志の表れではないだろうか。
「あの子が、生前、病気で思うように外に出られなかったとしたら。死んで身体から離れた今だから、自由にしてあげたいじゃない。……でも、あれだけ母親に大事に抱え込まれてたらさ、それも出来ないんじゃないかなぁって……だから、何と言うか、お母さんの方も、子離れしないといけないのかなぁ、てね?」
最後の方は、何か言ってて自分で恥ずかしくなったのだけれど、Sは黙って聞いてくれた。そうして、ふー、と欠伸ともため息ともつかない息を吐くと、
「親の心子知らず、されど子の心親知らず、ってか」
と小さく呟いた。
「分かった。好きにすりゃあいいさ。ただ、直接警察に言うのは止めとけよ。見知らぬ親子のために、色々犠牲にすることは無いからな」
じゃあ、一体どうすればいいんだろう。そんなことを思っていると、いきなり、Sが立ちあがり、未だ開いていた扉から、穴の中に片足を入れた。
「え? わ、何、どうすんの?」
慌てる僕を横目に、身体の半分ほど穴に下りたSは、ひとこと。
「まあ、任せておけばいい」
と言って、さっさと降りて行ってしまった。
穴の下を覗きこむも、Sが何をしているのか分からない。というよりも、Sはあの空間に居て平気なのだろうか。
しばらくして、Sが梯子を上がって戻って来た。やはりというか、当然だけれど、その表情には動揺が見えた。でも、僕ほど取り乱した様子もない。
「流石保存用の土蔵だな。イモだけじゃなくて、人間も保存できるのか……」
それから、Sは携帯の写メを使って色々家の中を取り始めた。あっちの部屋に行ったと思ったらこっちの部屋に行き、芋つぼの様子を真上から撮影して、最後に外に出て、家全体の様子を映して、ようやく何かが終わったらしい。
「さて、もう良いだろ。おい、外した戸を元に戻すから手伝え」
二人で、二枚戸を元に戻す。外すことが出来たんだから、戻すのも簡単だろうと思っていたのだけれど、それは間違いで、思ったよりも時間がかかってしまった。
ようやく、戸が元に戻った時には、もう時刻は午後五時半を過ぎていた。カラスの鳴き声と共に、辺りが段々と暗くなり始めている。
Sが家に向かって、一礼した。僕も倣う。そうして、僕らは、未だ一組の親子が住む古民家を後にした。
「帰りに、ちょっとネカフェに寄ってくぞ」
車に戻りながら、Sが言った。
「Sさ……大丈夫なん? 眠いんじゃない?」
「大丈夫だ。さっきのを思い出しさえすれば、眠気は飛ぶからな」
そういうSの表情からは、冗談かそうでないかの判別がつかない。
ふと、そう言えば、Kの電話を切ってから、携帯の電源をOFFにしていたことを思い出す。電源を入れると、着信履歴にKの名前がズラリと残っていた。電話するのも面倒くさいので、メールを一通入れておく。
『約四時間か五時間後にそっち行くよ。尚疲れたので、帰るまで電話もメールも受け付けません』
そして、再び電源を切った。
車に戻る頃には、陽は西の山に全部沈んでいた。夕焼けの残りが、オレンジ色の光を僅かに空に留めていた。
「それで、ネカフェに行って何すんの」
帰りの車の中、僕はSに尋ねる。
「別に……大したことじゃない。ただ掲示板上に、写真を織り交ぜて、体験談風のウソ話を投稿するだけだ。もちろん過去に起こった誘拐事件の概要、不法侵入の場面や、死体を発見した場面は真実を添えてな。後は勝手に親切な有志達が警察に通報してくれる」
「……写メ撮ったの?」
「肝心なとこは撮ってねえよ。そんな気も起こらなかったしな」
「……大丈夫かね。その文章と写真、直接メールで警察に送った方が早いんじゃない? 何か余計な話題にもなりそうだし」
「別に評判を貶めようってわけじゃないんだ。それに、メールで通報ってのは、ネット上の犯罪行為に限られてくるからな。心配しなくても、ちゃんと警察まで届くよう、別の手も打っとくさ」
「何なん、別の手って」
「そのうち分かる」
そのまま、僕とSは、帰り道の途中にあったネットカフェに立ち寄り、そこで軽い食事もとって、また自分たちの街へと車を走らせた。その際にSは何度かKとメールのやり取りをしていて、帰りに彼の家に寄っていくことになった。
やっぱりと言うか、Sも相当疲れているらしく、運転中、何度も眠たそうに目をしぱしぱさせていた。
Kが住む大学付近の学生寮についたのは、午後十一時頃だった。
Kはどうやら僕らが来るのを待ちかねていた様で、僕らが部屋の扉の前まで来ると、ノックをする暇もなく、戸が開いて中に引き込まれた。
wallpaper:198
「うおおっ、お前ら見ろお前ら! 昨日行った児童誘拐事件の現場がすごいことになってんぞっ!」
Kのテンションがすごいことになっている。
そうしてKは、開いたノートパソコンの画面を僕らに押し付けて来た。そこには、数時間前にSがネカフェで作成したウソ半分本当半分の体験談が、もちろん僕とSの名前は伏せて載っていた。
「いや、俺もSに言われて初めてこのスレッド知ったんだけどよ。いやあ、やべえなあこいつら。何かさ、扉壊してまで入ってさ。中で地下の隠し通路見つけてさ、さらに死体発見してやんの。しかもそのまま逃げ帰ってるしよ。あんまりなもんでさ、俺警察に通報しちゃったよ! マジで」
ああ、なるほどな、と思う。別の手とは、コレのことだったのか。
興奮冷めやらぬKとは間逆に、Sは心底眠たげな目を、ぐい、と擦ると、「……おい、K、悪い、布団借りるわ。数時間寝る」 と言って、部屋の隅にあった折りたたみベッドを広げると、ばたん、と倒れるように眠ってしまった。
「何だよあいつ。ことの重大さが分かってねえぞ。……いや、ってか俺さ、明日暇だからよ。も一度あそこに行ってみようかと思うんだが。なあなあ一緒に行こうぜー!」
正直僕も眠たいのだけれど、がくがく肩を揺さぶられては、仕方が無い。
「……すくなくとも、Sは行かないと思うよ」
「何でよ? いやまあいいや。そんなこともあろうかと、ちゃんと電車代とバス代いくらかかるか調べてあるから。片道四時間二十分。往復で五千円もかからないとよ、……ああ、アレだ、そう、片道2240円だとよ。往復で4480円」
ん、何か聞き覚えのある数字だな、と思うけども、疲れて頭が上手く働かないので、思い出すことが出来ない。
「あれ……、そういや、お前ら、今日どこに行ってたんだよ?」
その言葉に、僕は思わず笑ってしまった。
そうだった、そもそも土産話をしにここへ来たのだった。疲労でぼんやりとした頭を二度、コンコンとノックして、僕は、この元気な友人に一から語ってあげることにした。
「いやぁ、今日の昼頃なんだけど、ノックの音がね……」
走行中の車の窓から外の景色を見やる。前方から後方へ。車に近いものほど早く、遠いものほどゆっくりと。
約半日前にも通った道なのだけれど。状況は違う。あの時は陽が昇る前だったので辺りは暗く、車酔いのため後部座席で死体のように寝転がっていたKも、今はいない。
運転席の方から、欠伸が聞こえて、僕は窓の外から視線をそちらに移す。
ハンドルを握るSは、先程から非常に眠たそうだ。居眠り運転で事故されても困るので、何か話しかけることにする。
「あんさあ、Kが昨日話してくれたこと。覚えてる?」
「……誘拐事件の話か? ああ、大体はな」
数年前。僕らが高校生の時に起こった、連続児童誘拐事件。僕は覚えていなかったけれど、そこそこ世間を賑わしたらしい。
真夜中。その事件現場である古民家の庭先で、Kは、僕とSを前に、誘拐事件発生に至る経緯から、警察の捜査状況、どこで仕入れたんだというような情報まで熱く語ってくれた。
「冗談半分に聞いてくれればいいけど。もしかしてさ。昨日、あんな話をKがしたから、僕の家にやって来たんじゃないか、って思うんよね」
「何が」
「さっきも言った、ノックの主」
Sが欠伸をする。眠たいのか、馬鹿にされているのか。
「いや、でも、そんなことのためにわざわざ悪いね。二度も。遠いのにさ」
「ああ、全くだな」
Sは、心底面倒くさそうに言った。だったら、あんなメール寄こさなきゃいいのに、と思う。ちなみに、ガソリン代として要求されたのは、4480円だった。十円単位で要求してくるとは、ちゃんと残量をはかって計算したのだろう。キッチリしてるというか、何というか。
「そういや聞きそびれてたな。お前、あの空き家に行ってどうするつもりなんだ?」
「んー、まだ決めてないな」
「……何だそりゃ」 と前を向いたままSが呟く。実際に決めてないのだから仕方が無い。
「もしかしたら、家の中に入ることになるかもね」
前夜の段階では、事件のあった古民家を外から眺めるだけだった。現在、誰が管理しているのかは分からないが、窓にカーテンが掛かっていて中は見えなかったけれど。おそらく、家具はそのままにしているのだろう。ここの住人はあくまで、行方不明扱いで、いつか戻って来るかも知れないのだ。
「住居不法侵入だな」
「分かってるよ。でもさ、それってさ。向こうの方からウチに来いって、『呼ばれて』 それで入ったとしても、罪になるんかな」
「……お前がどういう場合を想定してるかは無視してだ。今回の場合では、なる」
「あーそっかぁ」
「大体どうやって入るつもりだ。玄関にはカギが掛かってるだろ」
確かに。当然の話だけれど、昨日確認した限りでは、玄関のドアは鍵なしでは開かないようになっていた。侵入できそうな窓もない。一ヶ所だけ、内側から窓が塗り固められている部屋もあった。
「ノックすれば開けてくれるんじゃない?」
僕は、冗談のつもりで言ったのだけれど、Sは、今度は確実に僕のことを馬鹿にしているのだ、と分かるような欠伸をして、こう言った。
「……中に人が居りゃあな」
それから数時間と数十分車で走って、僕はSの二人を乗せた車は、目的の古民家がある街まで辿りついた。時刻は、四時半を過ぎたところだった。
昨日と同じ場所、少し離れた場所にある住宅街の一角に車を停める。
「着いたぞ。ここからは歩いて行けよ」
とSが言う。そうして彼はシートベルトを外すと、後ろにシートを倒して目を閉じた。どうやら、これ以上付き合う気はなく、僕が戻って来るまでに、ひと眠りするつもりなのだろう。
しばらくして、Sが目を開けた。
「……何だよ。早くいけよ。場所は分かってんだろ?」
怪訝そうに言うSを、「ちょっと待って、静かに」 と制す。
何か、聞こえた気がした。
……コンコン。
ノックの音。
早く車から出ろと言っているのだろうか。
「この音、聞こえる?」
僕が尋ねると、Sは、「……いや」 と首を横に振った。
「あーそっか……、これ、今日以降もずっと続くようだったら、やっぱ病院かなぁ」
「おい……」 と何か言おうとしたSを置いて、車を出る。少し歩くと、後ろでドアの閉まる音がして、振り返ると、Sがのろのろと大儀そうに車を降りていた。
住宅街からしばらく歩いた、山へと続く細い坂道の脇に、家はあった。ここに来るのは二度目だ。振り返ると、眼下に僕らが車を停めた住宅街が一望できる。近くに他の家の姿は無く、まるで仲間外れにでもされたかように、ぽつりと、その古民家は建っていた。
瓦屋根の平屋で、建物自体は相当古くからここにあるのだろう。昨日は夜中だったのでよく分からなかったのだけれど、所々に年季を感じる。ただ、窓の向こうに見えるカーテンの模様などは現代風で、つい数年前まで人が住んでいたという名残もあった。
外から家自体の大きさは、親子二人だけで暮らすには、少々もてあましそうだった。
雑草の生えた花壇のある小さな庭を通り、玄関の前で立ち止まる。擦りガラスがはめ込まれた木製の二枚戸だ。
「で、どうすんだ?」
とSが言う。
僕は、戸に手をかけ、力を込める。当然のことだけれど、鍵が掛かっていて開かない。昨日の夜も確認したことだ。ノックの主が僕をここまで呼んだのなら……。という淡い期待もあったのだけれど、現実はそう甘くは無いようだ。
しばらく、無言のまま玄関を見つめていた。
始まりは、僕の部屋の玄関から聞こえたノックの音だ。僕は、その音に誘われて、四時間もかけて、再度ここまでやって来た。運転したのはSだけど。
玄関に呼び鈴等は付いていなかった。二度、軽くノックする。扉が揺れて、ガシャガシャとガラスが身悶える音がした。
コンコン。
中から、返事があった。渇いた響き。僕がアパートの自分の部屋で聞いた音とまるで同じだった。
たとえこの音が幻聴だとしても、僕はこの音に呼ばれている、それは確信できた。
後ろに居たSの方を振り返る。
「どうにかしてさ、この中に入れないかな」
僕が尋ねると、Sは、非常に面倒くさそうな表情をした。そうして投げやりな口調で、
「……どうにかしたいんなら、入る方法なんていくらでもあるが」
と言った。
「どうにかしたいね」
僕は答える。Sは肩をすくめた。
「一応念を押しとくが、どういう形で入るにしろ。れっきとした犯罪だぞ」
「今さら?」 と僕は少し笑って返す。Sは少し上を向いて、ふー、と小さく息を吐く。
「……やれあの街に連れてけだのやれ扉を開けろだの。全くやれやれだな」
嘆きながら、Sはドアの前にしゃがみ、戸の下部分、ガラスがはめ込まれている細い骨組の部分を掴んだ。ん、と一声、力を込める。どうやら、襖を外す時のように、二枚の戸を同時に持ち上げようとしているらしい。
鍵が掛かっているなら、扉ごと外してしまえという作戦だ。そんな安易な力技で大丈夫なのだろうか、と僕が思った瞬間だった。
派手な音がして、二枚戸が玄関の奥へと倒れる。
扉が外れた。
唖然としている僕を尻目に、Sは外した二枚戸を引きずって玄関の端によせると、
「二枚戸で、立てつけの悪い家なら、こういう侵入方法もある。まあ、窓を割るのが一番手っ取り早いが、不法侵入に器物破損が加わるのもアレだしな」
と何気もなく言った。何でそんなこと知ってんだと正直思ったけれど、聞かないことにした。
戸の無くなった玄関から、家の中を覗く。すぐそこは、四畳半ほどの板の間だった。一本の紐を渦巻状に敷き詰めたような丸いカーペットが無造作に敷かれている。正面と左右にそれぞれ戸があり、各部屋へと繋がっているのだろう。
「とっとと行って来い。人が来ないか見ててやるからよ」
Sの声に背中を押される形で、僕はその一歩を踏み出した。
「おじゃましまーす……」
玄関で靴を脱ぎ、僕は一人、中に入る。玄関の方からしか陽の光が届いていないせいか、意外と薄暗い。埃が舞っているらしく、鼻孔が少しムズムズした。
しばらく、じっと耳を済ます。けれども、何も聞こえてこなかった。あのノックの音もない。何故だろう。自分で探せといいたいのだろうか。
ふと、家の西側の部屋が、誘拐事件の際に子供たちの監禁に使われた部屋だということを思い出す。昨日鍵の有無と共に確認した事柄だ。内側から窓を塗り固めた部屋。そこへ行こうと僕は左手の戸を開いた。まっすぐな廊下が伸びてあって、三つほど扉がある。
手前のドアから順に開けて、確かめていく。物置。次いで客間だろうか、空の部屋。そうして残ったのは、一番奥の部屋。ドアノブに手をかけ、ゆっくりと開ける。
一瞬、ドアの隙間から、暗闇が飛び出してきたような錯覚を覚えた。暗い。辛うじて、開いたドアから差しこむ光が、室内を僅かに照らしている。
誘拐された子供たちは、ここで監禁生活のほとんどをすごしたのだ。
部屋の中、ドア近くの壁に、明かりのスイッチらしきものがあったので、押してみる。
途端に、温かみのある柔らかな光が室内に満ち、見えなかった部屋の様子が照らし出された。どうやら、電気は未だ送られているようだ。そうして、僕はハッとする。電気をつけてしまって良かったんだろうか。まあしかし、やってしまったものは仕方が無い。
部屋の入り口から見て、左手には大きなベッドと、天井に届くかという程の高さで、マンガ本や図鑑などがびっしり収まっている本棚。右奥にはいくつかのゲーム機器が並ぶ納棚があり、その上に、当時としては最新型だっただろう薄型テレビが置かれている。
壁の方を見やると、クレヨンだろうか、全身真っ黒な人間を書いた落書きがあった。子供が書いたものじゃないかと推測する。
その落書きの上、窓があると思われる部分が、周りの壁と同じ色の薄い板で覆われていた。窓がないという一点を除けば、ここで過ごすのに不便など何も無い、快適な子供部屋と言えた。
天井には、電球に白い傘を被せただけの簡素な照明がぶら下がっている。
「白熱灯だな」
いきなり、背後から声。
比喩でなく、心臓が弾け飛び散るかと思った。振り向くと、いつの間にかSが背後に立っていて、僕の肩越しに室内を覗きこんでいた。
「あー、びっくりした……足音くらいたててよ」
「勝手に入った見も知らぬ人の家でか? 馬鹿言うなよお前」
まるで正しいことのように聞こえるけれど、それはどうなのだろう。
「……見張ってるんじゃなかったん?」
「飽きたんだよ。……それにKの話をよくよく思い出してみりゃ、気になることがいくつかあったしな」
入口付近に立っていた僕の肩をちょいと押し、脇にどけると、Sは室内の丁度真ん中でぐるりと周囲を見回した。
「お前は、どう思う?」
突然のSの質問に、僕は、「え、何が?」 としか返せなかった。
「何がも何も、この部屋だ。気にならないか?」
言いながらSは徐に、ベッドの下から何か箱を引き出してくる。「失礼」 と言ってSが箱のフタを開けると、中には様々な種類の玩具が詰め込まれてあった。
「あれもこれも、小さな子供の身分にしちゃ、少し、贅沢過ぎるんじゃないか? まあ、一人っ子なんて大体こんなものかも知れんが。やっぱり、ちと過保護の気があるな」
Sが何を言いたいのか分からない。まさか、自分の子供時代と比較して拗ねているのだろうか。
「誘拐してきた子供のために買いそろえたんじゃない?」
僕が言うと、Sは首を振った。
「全部じゃないかも知れんが、名前が書いてある。●●ってな。ここの子供の愛称だったか」
玩具箱を覗きこむと、確かに、一つ一つの玩具に、『●●のもの』 と書かれたシールが貼られている。
「ここで数人、Kが言うには四、五人だったか、の子供たちが何日間か監禁されたんだったな」
玩具箱のフタを閉め、元通りにベッドの下に戻しながら、Sが言った。確かに、その通りなんだろう、と僕は頷く。
「おかしいだろ」
「どこが?」
立ち上がったSは、部屋の中をぐるぐると色々見物しながら、僕の方は見ずに言った。
「ここが監禁に使った部屋だとしたら、一人監禁して逃がした時点で普通バレる。普通ならな」
それはどうだなのろうか。Sの言葉に、僕は首をひねる。
「……そうかな?」
「子供は証言したんだ、『窓の無い部屋だった』 ってな。詳しく聞けば、警察も内側から窓を隠したってことが分かったはずだ。そうして、家を外からみりゃ、この部屋が窓を塗り固めてるってことは一目で分かる。つまり、傍から見ても犯行現場である可能性が大なんだよ、ここは」
窓のない部屋が存在する家。同じ街で解放される行方不明だった子供。誘拐犯の女。
被害にあった子供の証言とこれだけの要素があれば、容疑者を特定して、逮捕に至るのは簡単だ。とSは言う。
なのに何故か、事件は二度目ならまだしも三度目、四度目まで起こった。
「たぶん警察は犯人が、子供たちが窓の外を見て、景色を覚えるといけないから、窓を潰したんだと。その視点で捜査をしたんだろう。だから捜査が遅れた。それともう一つ、近所の住人からこの家の情報が警察に行かなかったのも、同じ理由だな」
僕自身も、この部屋の窓を潰した理由は、子供に場所を特定させないためだろうと思っていた、大体、他に一体何の理由があるというのか。
「光線過敏症」
耳慣れない言葉が、Sの口から出て来る。
「平たく言やあ、紫外線を受けると、人の何倍もの速度、深度で日焼けする体質のことだ。まあ、それを誘発する病気によって症状はいくつかあるがな。ともかく、この部屋に、『本来』 住んでいた子供は、それだったんだろう」
「え……、や、ちょ、ちょっと待ってよ。何でそんなことが分かるのさ」
するとSは天井を指差し、「白熱灯はな、光量が少ないわりに電気代が高いんだよ」 と良く分からないことを言った。
「まあ、まだ他にも色々と根拠はあるが。別の部屋にいくつか本があってな。光線過敏症、またはポルフィリン症についての本だった。が、一番は、写真があったからな。黒い頭巾を被った子供の写真がな。……ともかくだ。この部屋の窓が潰されたのは、誘拐事件が起こるずっと前で、なおかつ、周りの人間もそれを知っていたんだろうな」
「その、光線過敏症ってことは、太陽の照っている時は、外に出られないの?」
「そうだな。陽の光には当たらない方がいいからな。だから、部屋の中で不自由なく遊べるよう、色々買い与えたんだろ」
僕はあらためて、この日光の差さない部屋を見やった。内側から潰された窓、まだ小さな子供に過保護な程与えられた本や玩具。もしかすれば、Sのいう通りなのかもしれない。
「……それが、Sの気になったことなん?」
「気になったことの、一つ、だ。でもそれは、向こうで見た光線過敏症に関する本と、この部屋の白熱灯で大体確信できた。問題はもう一つ、その先の話だな」
うろうろと見物しながら歩きまわっていたSが立ち止まり、僕の方を見やる。
「光線過敏症である子供がだ。日光を避ける生活をしている子供が、行方不明なんかになるか? たとえ、行方不明になったとしてもだ。未だに発見に至ってないのは、何故だ」
言葉に詰まる。
「それは……、ただ単に行方不明になって、ただ単にまだ見つかってない……じゃ、駄目なん?」
「こういった症状を持つ子供の行動範囲がそれほど広いとは思えない。となれば誘拐、ということになるが、お前が誘拐犯だとして、黒い頭巾を被って顔も見えない子供を誘拐しようと思うか?」
「それは、分からないけど」
「身代金の要求があったわけでもなさそうだしな。ただ単に行方不明なんだよ。ここの女が起こした事件と同じでな」
「じゃあ、Sは、どう思ってんの」
「俺は、」
Sは、そこでいったん、言葉を切った。
「……俺は、その失踪した息子が、いや、誘拐犯の女自体も、まだ、この家にいるんじゃないかと思っている」
誘拐犯の女とその息子が、まだこの家の中に居る。
すぐには理解できなかった。噛み砕いて、その言葉の意味をゆっくりと脳に染み込ませる。ようやく理解し、最初に出てきた感想は、そんな馬鹿な、だった。
「そんなこと……」
「無いと言い切れるか? お前、Kが言ってた、犯人の女が失踪する前にのこした遺書らしき手紙の内容覚えてるか? 確かな情報じゃないかも知れんが、『息子の元へ行きます』 って言葉は、『息子の居場所』 を知っている者の台詞だ」
「……何年も行方不明で、死んだものと思ったんじゃない?」
「個人的な視点になるが、俺はそうは思わない。息子のために、白熱灯ならまだしも、部屋の窓を潰すような母親だぜ?」
「でも、だったら……、行方不明は、狂言だったってこと?」
「さあな。それは分からないな」
「狂言なら、まさか、二人共生きてる……?」
「いや。少なくとも息子は死んでるだろうな。だから、彼女は誘拐事件を起こすんだよ。動機については、警察の見立てで間違ってないと思う」
いなくなってしまった息子への想いから、同じ年頃の男の子を誘拐しては、数日間だけ一緒に暮らす。息子と同じ部屋に閉じ込めて、息子と同じように会話をしようと話しかける。
「つまり、だ。俺は、母親は何らかの理由で死んでしまった息子の死体をどこかに隠し、周りには行方不明になったと伝えた、と考えてる。認めたくなかったのか、他の理屈が働いたのかは知らないがな」
そして、一人に耐えきれなくなった母親は誘拐事件を起こす。息子の部屋で子供と接することで、自分の子供は生きていると思い込みたかったのだろうか。けれども、その行為を数回終えたところで、悟ったのだろう。所詮、彼らは、自らの息子じゃないのだから。
「でもさ、何で、その二人の死体が『この家にある』 って分かるんよ?」
「別に分かってるわけじゃない。ただの希望的確率論だ。自分の一人息子なんだから、少しでも傍に置いときたいと思うのが人情だろ」
そうして、Sは壁を二度、コンコンとノックする。
「……そして、だから、お前は今日ここに来たんだよ」
「は……?」
紙風船から空気が抜けたような間抜けな音が、僕の喉から滑り落ちる。
「……僕が、何?」
「言っとくが、今俺が言ったのは、未だ真相でも何でもない。全て想像と憶測の産物だ。ただ、お前も、俺と同じように考えたに違いないんだ。否定するか? お前は無意識下の元ロジックを組み立てたんだよ。そうして、それを探したい、見たいという欲求がノックの音になって意識下に現れたんだ」
「なっ、な、おい、何でSにそんなことが分かるのさ」
「お前に聞こえるノックの音は、俺には聞こえない。だとすれば、そいつはお前の中で鳴っている音だ。お前自身が脳みそをノックしてたんだよ」
「そんなこと言ったって、僕は、この家の子が、日光に触れちゃいけない体質だったなんて初めて聞いたよ?」
「数年前に、この事件が世間で話題になった時、そのくらいの情報は流れただろうな」
「し、知らないし、見てないし、覚えてないし」
「覚えてなくたって、ちらりと見やっただけの情報も、脳みそはちゃんと保存しているもんだ」
そんな馬鹿な、と言おうとしたけれど、それより早くSが口を開く。
「じゃあ聞くが。お前、この家に入ってから、ノックの音は聞いたか?」
その言葉に、僕は絶句する。確かにそうだ。この家の中に入ってから、それまで僕を誘導していたノックの音は、ぱたりと止んだ。まるで、その役目を終えたかのように。
「その音の役割は、お前を、親子二人の死体がある『らしい』 この家に連れて来ることだ。ここまでは無意識下で組み立てられても、肝心な死体がどこにあるかなんて、分からないからな。誘導しようがないのさ」
僕は目を瞑り、後ろの壁にもたれかかる。身体から、どっ、と力が抜けてしまったようだ。
Sが小さく笑って、僕の肩をたたく。
「もう、ノックが聞こえることは無いだろ。ま、喜べよ。Kにいい土産話が出来たじゃないか」
全く慰めになってない。僕は、力なく笑った。
それは結局、僕は自身の思い込みに従い、大きな大きな無駄足を踏んだということだ。
「帰るか」
というSの言葉に、僕は黙って頷いた。トボトボと、Sの後ろをついて家を出ることにする。当初、ノックの主に呼ばれているだなんて思っていた僕が馬鹿みたいだ。
それでも。と頑張って思い直す。今日の体験が、非常に不思議で、なおかつドキドキワクワクして面白かったことは間違い無い。ノックの音に誘われて、僕は、こんなところまで来てしまい、そこで起こった事件の裏の一面を少しでも垣間見たかもしれないのだ。
まあ、良い体験をしたと思おう。
玄関のある部屋まで戻る、Sはもう靴を履いて外へ出ていた。これから、あの外した玄関の戸を元に戻さなくてはいけない。立つ鳥跡を濁さずってわけだ。
その時、ズボンのポケットの中で、携帯が振動した。電話だ。誰だろうと思い取り出してみると、それはKからだった。
少し早めに、恥ずかしい土産話を披露することになるのだろうか。一人で苦笑いしながら、僕は、外に居るSに、「Kから電話」 と伝えて、玄関の段差に座り、通話ボタンを押した。
『よおー。俺だ。昼に電話くれてたけどよ。何か用かー?』
どことなく陽気なKの声。
「え? K、まさか今起きたん?」
『わりーかよ』
確か、時刻はもう五時に近いはずだ。
「遅いよ。何時だと思ってんだよ、もう夕方になるよ?」
『うっせーなー。何だよ。ソッチの要件は何だったんだよ』
う、と言葉に詰まってしまう。Sの方を見ると、そっぽを向いて欠伸をしていた。
「……ノック」
『はぁ?』
「ノックだよノック。そのノックのせいで精神的にもノックアウトしちゃってさ。もうまいっちゃってさ」
やけくそになって、僕は床を拳で軽くコンコンコンコンと叩きながら、あはは、と笑う。上出来な自虐ギャグだ。自分でも可笑しかった。可笑しくて、笑う、床を叩いて、笑って。
そうして、僕は、笑うのを止めた。
電話の向こうで、Kが何か言っている。でも、何を言っているのか、まるで聞こえない。
床を叩く。
コンコン。
もう一度、違う場所を。
コンコン。
立ち上がって、携帯を切った。
外と室内を繋ぐ四畳半程の部屋には、カーペットが敷かれている。最初に入って来た時も見た、渦まき模様の丸いカーペット。僕はその端を持ち、少しめくってみた。
カーペットの下は板の間で、そこには、半畳程の大きさの正方形の扉があった。
心臓が、音を立てて鳴っている。頭の中を様々な思考が飛び交っているのに、何も考えることが出来ない。
それは、取っ手の金具を引き出して上に持ち上げるタイプの扉だった。この先に何があるのか、何の扉かもわからない。
手を伸ばして、扉を叩く。
コンコン。
それは、僕が今日、今まで聞いてきたノックの音と、全く同じ音だった。
どうしてだろう。どうして僕は、『この音』 を聞くことが出来たのだろう。先程Sが言ったことが正しければ、僕は、僕が聞いたことが無い『この音』 を、創り出せたはずがないのだ。
……コンコン。
僕は叩いていない。
それは、今まで聞いた中で一番弱々しかったにも関わらず、一番はっきりと聞こえたノックの音だった。決して、脳内で創り出した音なんかじゃない。僕の鼓膜は、確かにその微弱な振動を捉えていた。
扉についている金具を引き出し、僕は、扉を持ち上げる。かなり重かったけれど、ゴリゴリと音を立てて、扉の下からゆっくりと、まるで井戸のような黒いうろが姿を見せた。
据えた匂いと、ひやりとした空気が、穴から立ち上る。背筋がぞくりとして、全身に鳥肌が立った。
扉を落としそうだったので、裏側にあったつっかえ棒で、固定する。
「……何やってんだ?」
いつの間にか、Sが玄関からまた家の中に入って来ていた。僕は返事もしないで、扉の奥の穴を見つめていた。
「そいつは……、たぶん、芋つぼだろうな」
「芋つぼ……?」
「その名の通りだよ。芋を保存しとくために地下に掘る天然の土蔵だ。古い民家なんかにはたまにある。……というか、お前これどうやって見つけたんだ?」
Sの話を聞くでもなく耳にしながら、僕は穴の奥から目が離せないでいた。
「……Sさ、車の中に、懐中電灯ある?」
少しの沈黙の後、Sは、
「あるぞ」
と言った。
「それさ、取って来てくれない?」
Sは、何も言わず、黙って車へと向かった。しばらくして戻って来たSの手には、二本の懐中電灯が握られていた。玄関先からその内の一本を、僕に投げてよこす。
「ありがと」
ちゃんと光がつくかどうか確かめて、僕は再び穴に向き合った。
そっと、光の筋を、穴の奥に這わす。
思ったより穴は深いようだった。三メートルほどだろうか。木の梯子がかかっていて、下まで降りたところで、横穴がまだ奥に続いているらしい。横穴の様子は、ここからでは伺えない。
何故か、迷うことは無かった。僕は、穴の中に入ろうと、扉の縁に手をかけた。
「おい」
Sの声。僕は顔を上げる。
「数年間放置されてたんだ。梯子が腐ってることもある、気をつけろよ」
「……OK」
梯子に足をかける。最初の一歩を一番慎重に。腐っている様子は無い。二歩、三歩と、僕は芋つぼの底に降りてゆく。頭まで完全に穴の中に入ったところで足元が見えなくなり、あとは完全に感覚で、僕は梯子を下った。
しばらくすると、足の裏が、地面の感触を掴む。芋つぼの中は、かなり寒かった。湿気なども無さそうで、なるほど、と思う。食料を保存しておくには適した場所だろう。
スイッチを入れっぱなしにしていたライトを、ポケットの中から出す。そうして僕は、ライトの光を、そっと横穴に向けた。
あの時の光景を、僕は一生忘れない。
暗闇の中、足元からすぐ先に、一枚の茶色く変色した布団が敷かれている。
その上で、一組の親子が、互いに寄り添う様にして静かに眠っていた。
掛け布団の中から、二つの頭だけが出ている。きっと、あの見えない部分では、母親がわが子を抱きしめているのだろう。
僕はライトの光を向けたまま、茫然と立ち尽くしていた。
それ以上、一歩も前に進むことが出来なかった。足やライトを持つ手が震えているのが分かった。恐怖では無い。ただ、身体が震えていた。
息をするのも辛くなって、僕は二人に背を向けた。その時、初めて自分が泣いているのだと知った。嗚咽もなく、ぼろぼろと涙だけがこぼれた。
涙は熱く、頬に熱を感じる。
怖くは無い。悲しくもない。感動しているわけでもない。よく分からない。ただ、強いて言うなら『痛いから』 だった。自分の中の芯の部分が、ネズミのような何かに、集団で齧られているような。そんな気分だった。
頭上から、ライトの光が降って来る。Sだった。自分が照らされていることを知り、僕は俯いて涙をぬぐった。身体の震えは、いつの間にか消えていた。
梯子をつたって、上へと上る。震えは止まったけれど、思うように身体が動かず、えらく時間をくった上に、最後はSに引っ張り上げてもらった。
Sは何も言わなかった。僕が落ち着くまで待つつもりなのだろう。ふと玄関の方を見やると、家の中を隠すように、戸が玄関に立てかけられていた。
「ごめん……。もう大丈夫」
そうして、僕は、Sについ先ほど見てきた光景を話した。
「そうか」
Sの感想は、ただそれだけだった。
僕はずっと考えていた。それは、僕がどうして、あの二人を見つけることが出来たかについてだった。偶然だったのか。または必然だったのか。僕が無意識下でまたやらかしたのか。それともあの二人に、もしくはどちらかに、呼ばれたからだろうか。
答えは出なかった。
僕は、ポケットから携帯を取り出す。
「止めとけよ」
その次の行動を見透かしたように、Sが言った。
「……何を?」
「警察に通報するつもりだろう」
「……そうだけど。どうして?」
「俺が警察なら、お前を真っ先に疑う」
その口調には何の力も込められていおらず、ただ、いつも通りのSの言葉だった。
「あの二人をここに閉じ込めて殺した犯人としてな。ノックの音が聞こえたんでそれで来ました、なんて言ってみろ。それこそ、精神異常者として扱われるのがオチだ。まあ、色モノが大好きな世間様には気に入られるだろうが」
「それじゃあ、公衆電話から……」
「そんな電話、こちらから名乗れない以上、イタズラと思われて終いだろう。警察はイタズラ電話多いからな」
「じゃあ、どうすんのさ……、だからって、このままにしとくわけにはいかないしさ」
すると、Sは、ゆっくり息を吸って、こう言った。
「何がいけないんだ?」
それは、予想もしなかった言葉だった。
「何がって……」
「俺は別に良いと思うけどな。このままでも。親子水入らずで過ごせるんだ。別に悪いことじゃないだろ」
僕はあの二人の姿を思い出す。二人で寄り添い、一つの布団に入って眠っていたあの姿を。ここで、親子の居場所を外に教えることは、あの二人の間を裂くことになるのではないか。
何故いけないのか。そうだ、何故いけないのだろうか。
僕は答える。
「……やっぱり、駄目だ。知らせよう」
病弱な息子を守りたい、危険から遠ざけたいとした母親。でも、息子の方からすればどうだったのだろう。生きている頃も、窓の無い部屋でずっと母親に守られ、死んでからも、こうして母の手に抱かれている。
「あのさ……、性懲りもなくって思うかもしれないけんど……。僕が聞いたノックの音って、あの男の子が僕を呼んだんじゃないか、って思うんよ」
芋つぼの扉を叩いた、弱々しくもはっきりとしたあの音。あれは、『外に出たい』 意志の表れではないだろうか。
「あの子が、生前、病気で思うように外に出られなかったとしたら。死んで身体から離れた今だから、自由にしてあげたいじゃない。……でも、あれだけ母親に大事に抱え込まれてたらさ、それも出来ないんじゃないかなぁって……だから、何と言うか、お母さんの方も、子離れしないといけないのかなぁ、てね?」
最後の方は、何か言ってて自分で恥ずかしくなったのだけれど、Sは黙って聞いてくれた。そうして、ふー、と欠伸ともため息ともつかない息を吐くと、
「親の心子知らず、されど子の心親知らず、ってか」
と小さく呟いた。
「分かった。好きにすりゃあいいさ。ただ、直接警察に言うのは止めとけよ。見知らぬ親子のために、色々犠牲にすることは無いからな」
じゃあ、一体どうすればいいんだろう。そんなことを思っていると、いきなり、Sが立ちあがり、未だ開いていた扉から、穴の中に片足を入れた。
「え? わ、何、どうすんの?」
慌てる僕を横目に、身体の半分ほど穴に下りたSは、ひとこと。
「まあ、任せておけばいい」
と言って、さっさと降りて行ってしまった。
穴の下を覗きこむも、Sが何をしているのか分からない。というよりも、Sはあの空間に居て平気なのだろうか。
しばらくして、Sが梯子を上がって戻って来た。やはりというか、当然だけれど、その表情には動揺が見えた。でも、僕ほど取り乱した様子もない。
「流石保存用の土蔵だな。イモだけじゃなくて、人間も保存できるのか……」
それから、Sは携帯の写メを使って色々家の中を取り始めた。あっちの部屋に行ったと思ったらこっちの部屋に行き、芋つぼの様子を真上から撮影して、最後に外に出て、家全体の様子を映して、ようやく何かが終わったらしい。
「さて、もう良いだろ。おい、外した戸を元に戻すから手伝え」
二人で、二枚戸を元に戻す。外すことが出来たんだから、戻すのも簡単だろうと思っていたのだけれど、それは間違いで、思ったよりも時間がかかってしまった。
ようやく、戸が元に戻った時には、もう時刻は午後五時半を過ぎていた。カラスの鳴き声と共に、辺りが段々と暗くなり始めている。
Sが家に向かって、一礼した。僕も倣う。そうして、僕らは、未だ一組の親子が住む古民家を後にした。
「帰りに、ちょっとネカフェに寄ってくぞ」
車に戻りながら、Sが言った。
「Sさ……大丈夫なん? 眠いんじゃない?」
「大丈夫だ。さっきのを思い出しさえすれば、眠気は飛ぶからな」
そういうSの表情からは、冗談かそうでないかの判別がつかない。
ふと、そう言えば、Kの電話を切ってから、携帯の電源をOFFにしていたことを思い出す。電源を入れると、着信履歴にKの名前がズラリと残っていた。電話するのも面倒くさいので、メールを一通入れておく。
『約四時間か五時間後にそっち行くよ。尚疲れたので、帰るまで電話もメールも受け付けません』
そして、再び電源を切った。
車に戻る頃には、陽は西の山に全部沈んでいた。夕焼けの残りが、オレンジ色の光を僅かに空に留めていた。
「それで、ネカフェに行って何すんの」
帰りの車の中、僕はSに尋ねる。
「別に……大したことじゃない。ただ掲示板上に、写真を織り交ぜて、体験談風のウソ話を投稿するだけだ。もちろん過去に起こった誘拐事件の概要、不法侵入の場面や、死体を発見した場面は真実を添えてな。後は勝手に親切な有志達が警察に通報してくれる」
「……写メ撮ったの?」
「肝心なとこは撮ってねえよ。そんな気も起こらなかったしな」
「……大丈夫かね。その文章と写真、直接メールで警察に送った方が早いんじゃない? 何か余計な話題にもなりそうだし」
「別に評判を貶めようってわけじゃないんだ。それに、メールで通報ってのは、ネット上の犯罪行為に限られてくるからな。心配しなくても、ちゃんと警察まで届くよう、別の手も打っとくさ」
「何なん、別の手って」
「そのうち分かる」
そのまま、僕とSは、帰り道の途中にあったネットカフェに立ち寄り、そこで軽い食事もとって、また自分たちの街へと車を走らせた。その際にSは何度かKとメールのやり取りをしていて、帰りに彼の家に寄っていくことになった。
やっぱりと言うか、Sも相当疲れているらしく、運転中、何度も眠たそうに目をしぱしぱさせていた。
Kが住む大学付近の学生寮についたのは、午後十一時頃だった。
Kはどうやら僕らが来るのを待ちかねていた様で、僕らが部屋の扉の前まで来ると、ノックをする暇もなく、戸が開いて中に引き込まれた。
「うおおっ、お前ら見ろお前ら! 昨日行った児童誘拐事件の現場がすごいことになってんぞっ!」
Kのテンションがすごいことになっている。
そうしてKは、開いたノートパソコンの画面を僕らに押し付けて来た。そこには、数時間前にSがネカフェで作成したウソ半分本当半分の体験談が、もちろん僕とSの名前は伏せて載っていた。
「いや、俺もSに言われて初めてこのスレッド知ったんだけどよ。いやあ、やべえなあこいつら。何かさ、扉壊してまで入ってさ。中で地下の隠し通路見つけてさ、さらに死体発見してやんの。しかもそのまま逃げ帰ってるしよ。あんまりなもんでさ、俺警察に通報しちゃったよ! マジで」
ああ、なるほどな、と思う。別の手とは、コレのことだったのか。
興奮冷めやらぬKとは間逆に、Sは心底眠たげな目を、ぐい、と擦ると、「……おい、K、悪い、布団借りるわ。数時間寝る」 と言って、部屋の隅にあった折りたたみベッドを広げると、ばたん、と倒れるように眠ってしまった。
「何だよあいつ。ことの重大さが分かってねえぞ。……いや、ってか俺さ、明日暇だからよ。も一度あそこに行ってみようかと思うんだが。なあなあ一緒に行こうぜー!」
正直僕も眠たいのだけれど、がくがく肩を揺さぶられては、仕方が無い。
「……すくなくとも、Sは行かないと思うよ」
「何でよ? いやまあいいや。そんなこともあろうかと、ちゃんと電車代とバス代いくらかかるか調べてあるから。片道四時間二十分。往復で五千円もかからないとよ、……ああ、アレだ、そう、片道2240円だとよ。往復で4480円」
ん、何か聞き覚えのある数字だな、と思うけども、疲れて頭が上手く働かないので、思い出すことが出来ない。
「あれ……、そういや、お前ら、今日どこに行ってたんだよ?」
その言葉に、僕は思わず笑ってしまった。
そうだった、そもそも土産話をしにここへ来たのだった。疲労でぼんやりとした頭を二度、コンコンとノックして、僕は、この元気な友人に一から語ってあげることにした。
「いやぁ、今日の昼頃なんだけど、ノックの音がね……」
怖い話投稿:ホラーテラー なつのさん
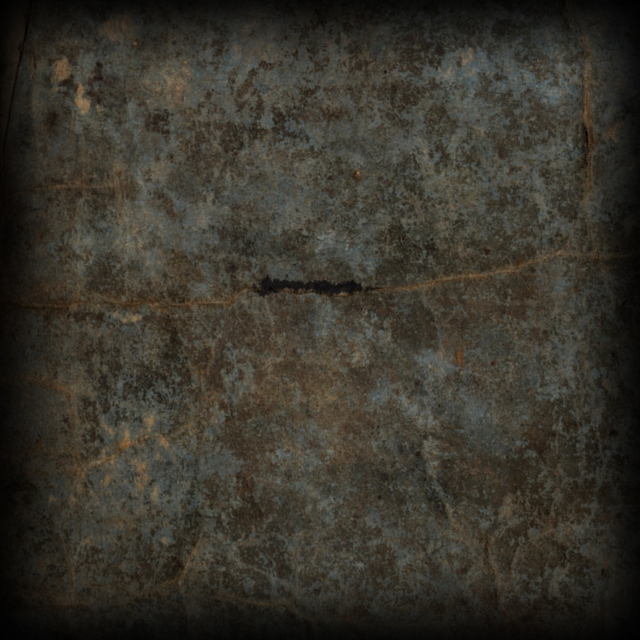





作者怖話