先生が家庭教師を引き受けてくれてから約二週間が立った。
早いもので先生がこの家を訪ねて来るのも四回目となる。
その間俺は先生に、この家に初めて来た時の事について質問の嵐を試みた、勿論前回の襖で起こった事についてだ。 が、そのほとんどが、
「勉強に集中しろ」
だの、
「この問題が解けたらな」
などと言って、あきらかに一般の高校生では解けないような問題を出してくるなどの妨害にあい、程なくして質問するのを諦めた。
かわりに先生は、あれが一体何なのか? などといった事について色々と聞かせてくれた。
あれとは、前回俺の部屋で見た女の生首の事だ。
単純に俺はあれの事を、
「幽霊ですか?」
と先生に尋ねた、すると先生は、
「さあ、何なんだろうな」
と曖昧な返事を返してきた。
先生が言うには、幽霊とはそもそも生きている人間が後付けで考えたものでしかない、との事。
「怨霊だの地縛霊だのと、勝手にカテゴライズされたのでは、奴らもうかばれないな」
と先生。
幽霊〔仮〕、といったところなのだろうか?
何んだか面倒くさい話だったが、どうやら先生は幽霊、という名詞は使わず、あれ、や、奴ら、などと言った呼び方をしているようだ。
ではその奴ら、とは一体何なのかと聴くと、先生は俺にこう答えてくれた。
「奴らはバラバラになったパズルのピースみたいなもんさ」
俺が首を傾げると、先生は軽い笑みを浮かべながらこう続けた。
「失ったピースを集めて、元の自分を完成させようとしている、だけど残りのピースを見つけられないんだ、奴らにはな……だから代わりに見つけてくれとせがむんだよ」
先生はそう言って黙ると、口の端をにっと歪め、俺の目の前で人差し指と親指をだし、何かをすり潰すような真似をして見せた。
その表情に薄ら寒い悪寒を感じながら、俺は以前、この部屋で起こった怪奇現象を思い返していた。
つまり先生は、以前俺の部屋の梁の部分に付着していた、縄の繊維の事を言っているのだろうか? あれこそが失われたパズルのピ-スだったと?
その後も色々と話を聴かせてもらったが、まあほとんどが意味不明な先生なりの解釈が続き、俺は素直に、世の中俺より電波な人っているんだなと、しみじみと思った。
まあその事は置いといてだ、俺にはどうしても気になる事が一つあった。
それはなぜ俺があんなものを見てしまったのかだ。
あんなものとは所謂、幽霊といった類のもの。 それについて自分なりに考えられる事は二つ、
一、俺の霊力が増した。
二、先生程の霊感の持ち主が近くにいたから、それに俺が感化された。
それに関して先生に疑問をぶつけてみたところ、
「漫画の読み過ぎだ馬鹿」
と、俺の頭をはたいて言った。
「霊感や霊力なんてものに固執するな。見えるものは見えるんだ、それでいいじゃないか」
先生はそう言って俺の疑問を一蹴。
「だって見える人って、霊感があるんでしょ?」
俺はしつこく聞き返した。 それに対して先生は、
「誰が決めたんだそれ? 見えるイコール霊力なんて安易過ぎるだろ、だいたい霊格なんて考え方自体、人間のエゴだと思わないか?」
この後、先生の話は段々とベクトルを変えていき、結局肝心な事ははぐらかされたまま、先生の授業は二回~三回と過ぎていった。
その間も俺はネットなんかで色々と心霊に関する事について調べたが、やはりどの話も霊感、霊力云々の話へと辿り着く為、若干の行き詰まり感を覚え、次第にあまりこの手の事は考えないようになっていた。
実際、先生と初めて会った日以来、あの部屋で怖い体験はしていない。
まあ襖の建て付けが抜群によくなったのは事実なのだが……
しかし、そんな事さえも、緩やかに忘れ去っていくんじゃないかと思えるようになったある日、俺は急遽電話で先生から、
「今日は社会見学に行くぞ」
と、半ば強引に誘われた。
家庭教師の社会見学なんて聴いた事はなかったが、正直この頃はあの奇妙な体験の事よりも、先生と会える日が新作のゲームの発売日よりも楽しみになっていた。
内心ワクワクしながら、俺は学校が終わると同時にダッシュで帰宅した。
時刻は午後四時。
あらかたの用意を済ませ一人部屋で待っていると、遠くからけたたましい排ガス音が近づいてきた。
俺はハッとして部屋の窓から外を確認すると、急いで玄関へと向かう。
履き崩した靴を乱暴に履き、踵を鳴らして扉を開けると、家の前にブルーのスポーツカーが一台鈍いエンジン音を轟かせながら止まっていた。
まあアニゲーオタクの俺が車種なんか知る由もないのだが、それがスポーツカーだという事くらいはすぐに分かる仕様だ。
運転席側に目をやると、そこにはだいぶ見慣れた人影があった。
ドアが開き、ゆっくりと人影が顔をだす。
先生だ。
全体的に白と紺色で統一された服装、首元のブルーのリボンが可愛いらしい。
先生は紺色のスカートをヒラヒラさせながら車を降りると、
「すまん、またせたか?」
と、聴いてきたので俺は、とんでもないとばかりに首を振って見せた。
先生は見た目だけならどこかの清楚な美人令嬢なのだが、いかせん目の前の車が不釣り合い過ぎる。
たまたま側を通った、自転車に乗った四十代くらいの男性に奇異の目で見られていた。
無論、俺にも不釣り合いなのは百も承知。
「何してる? 早く乗れ」
先生はそんな事を気にする様子もなく、一人さっさと車に乗り込んでしまった。
それを見て俺も慌てて車に乗り込む。
「し、失礼します」
先生と会うのはこれが四回目だが、外でこうして会うのは初めてだ。
会話にも随分と慣れたつもりだったが、いつもと勝手が違うせいか俺は僅かばかり緊張していた。
心なしか先生もいつもと違ってみえる。
「おっ、今気が付いたけど、お前髪切ったんだな」
「えっ? あ、ええ、まあ……」
と、はにかみながら答えて照れる俺。
うんうん、我ながら気持ち悪いぞ。
「ふふ、似合ってるじゃないか、今度会った時まだ髪伸ばしてたら丸坊主にしてやろうかと思ってたんだが、何だ手間が省けた」
「ソ、ソウデスカ……」
俺は照れるかわりに額に冷や汗を感じながらそう答える。
やはりいつもの先生だった。
先生がギアを上げアクセルを踏み込む。
アスファルトを削るような音と共に車が走り出す。
車体の振動と共に、先生の耳元でダイヤのピアスがヒラリと揺れた。
俺が助手席の窓に写る先生の横顔を見ていると、先生はそれに気付き、気恥ずかしそうに、
「気持ち悪いな、私の顔に何かついてるのか?」
そう言って横目で此方をチラリ。
俺は慌てて視線を逸らし、話を変える為、
「せ、先生車好きなんですか?」
と質問した。
「車が? いや別に、何でだ?」
「いや……だってこんなスポーツカーに乗ってるし、好きなのかなと……」
俺のぎこちない質問に先生は軽いため息をつきながら答えた。
「歩きだと大学でよく声を掛けられるんだ、『送っていきましょうか?』 とか言ってな、それが心底ウザい。 で、知り合いから安く買い取った車がこれだ。 安くてよく走るなら何でもいいさ」
なるほど、確かに先生ならありえる。
ちなみに先生が通っている大学は、地元でもかなり金持ちの学生が多いと有名だ。
ああいけすかない……
「じゃあ電車やバスは?」
それに対し先生は、
「痴漢にあうから絶対に乗らん」
と吐き捨てるように言い切った。
むしろこの人相手なら痴漢をした奴の方がヤバい目にあいそうだと思ったことは、俺の胸の内に秘めておく。
その後も、俺と先生は他愛もない会話を交えつつ、目的地へと向かった。
途中何度かその目的地がどこなのか聞きだそうとしたが、その度に先生はわざとスピードを出してきて、俺は何度か舌を噛む事となり結局聞くことはできなかった。
観念して通り過ぎる対向車のライトに目を細めていると、隣の席から、
「もうすぐ着くぞ、」
と声を掛けられた。
決して乗り心地の良いとは言えない車に揺られること、約三十分といったところか、肌寒いこの季節、空は既に茜色から青黒い空へと、夜が浸食しつつあった。
先生は適当に駐車場を見つけると、巧みな運転捌きで狭い駐車場に一発で駐車し、そそくさと車から降りた。
俺も慌てて降りると、ふと辺りを見渡す。 そこはどこか見慣れた景色のように感じた。
以前、来たことあったっけ?
高架線の下、怪しげな占い小屋に傾いた飲み屋の屋台。 その周りを囲むようにして建ち並ぶ薄暗く小汚い雑居ビル。
遠くから車の騒音と喧騒が入り混じった、なんとも耳障りな音が微かに耳に入ってくる。
遠くの空にふと目をやると、どこかで見た事あるような高層ビルの影が、暗い夜空にそびえ立っていた。
もしや……
「ここって○○駅の裏通り……ですか?」
先生の背中に声を投げ掛けるが、先生は振り向きもせず、
「いいからさっさと来い」
と言って、薄暗い街灯の下、スタスタと奥の道へと進んでいく。
俺は置いていかれまいと、すぐにその後を追った。
○○駅、大型デパートや多種多様な店などがあり、深夜でも賑やかなこの町の一面を見せる場所だが、駅裏の通りに行くと、薄暗い通り道に、居酒屋、古びたパチンコ店、更に奥に進むと、派手な電飾の看板がチラホラと見えてくる、どこかアンダーグラウンドな場所だ。
いつの頃だったか、電車に乗っていた時、窓から眺める外の景色に、これと同じ看板を遠目にだが見た事がある。
あの派手な看板の店はそう、その……あれだ、いわゆる休憩所というやつだ。
二次元の世界でなら何度か行った事はあるが、まさかこの俺が現実の世界でこんなとこを歩く日が来るとは……
「おい、気持ち悪い顔してないで早く来い、こっちだ」
そう言って、先生は親指を立て奥の道を指し示す。
妄想くらい自由にさせてくれと胸の内で愚痴りながら、俺は先生の後を追った。
まあ何であれ、先生みたいな人とこうして外を歩けるだけでも、昔の俺からしてみれば想像もつかない事だった、そう思うと思わず自然と顔がにやけてしまうのも仕方がない事。
「さっきから何なんだお前、気持ち悪い顔しやがって……ほら、着いたぞ」
俺はにやけた顔のまま、先生が立ち止まり視線を向けた先に目をやった。
先生の切れ長の目が見つめる先には、雑居ビル?
いや待て、入り口の看板にはどこかで見たような英語表記が……H O T E L。
えっ……?
一瞬頭が真っ白になりかけたが、俺は必死に自我を保ちつつ、すぐさま先生に向き直り声を荒げた。
「ええっ!? せ、先生こ、ここ、ほ、ホテル──」
と最後まで言い終わる前に、ガツンという鈍い音と共にに俺は前のめりに突っ伏した。
まあ早い話が先生の鉄拳制裁だ。
「この馬鹿! よく見ろ、たっく……」
……よく見ろ?
俺は後頭部を押さえつつ、顔をしかめながらもう一度建物を見た。
何度見てもホテルだ……ただし、
「廃墟……廃ホテル、ですか?」
先生は俺の返答に黙って頷くと、再び廃ホテルをじっと見つめる。
高架線の上を、耳をつんざくような音と共に電車が走った。
電車の明かりが断続的に先生の横顔を照らしていく。
明かりは先生の瞳の中に吸い込まれるようにして、まるで蝋燭の火のようにゆらゆらと揺らめいている。
その時の先生の横顔はとても綺麗で、なぜかそれと同じくらい怖い……と、俺はどこかで感じていた。
しばらく廃ホテルを眺めていた先生は、持っていたハンドバックから徐に懐中電灯を二つ取り出し、その一つを俺に手渡してから、ツカツカとまるで勝手知ったる他人の家のように、中へと入っていった。
この人には躊躇いというものがないのだろうか?
俺は脳裏に浮かび上がる、不法侵入という言葉にびくびくしながら、辺りを見渡し先生の後に続いた。
外観はそこまで荒れてないように見えたのだが、中はかなりの荒れ放題だった。
まあ得てしてこういう場所は変な輩の溜まり場になるのがセオリーだし仕方がない。
壁一面にスプレーのようなもので書かれた罵詈雑言の落書き、床のタイルには何かが焼かれた後や、雨漏りによって腐食した後が数多く見られる。
先生はそれらには何も興味を抱かないといった表情で、中央フロント付近にある階段へと向かった。 置いて行かれまいと俺も後に続く。
階段を踏みしめる度に、床に張ってあるラバータイルがめりめりと嫌な音を立てる。
不意になる嫌な音というものは、どうしてこう人の恐怖を掻き立てるのか。
もしここに先生がいなかったら、俺はとっくの昔に叫び声を上げながら階段を駆け降りていただろう。
というか今更だがなんで社会見学がここなんだ、これじゃ悪質な肝試しじゃないか。
俺は胸の内で悪態をつきながらも、黙ったまま先生の後ろを歩いた。
まあそれでも先生と一緒と考えれば少しは気も晴れる。
そんな事を考えながら進んでいると、不意に先生がポツリと呟くように俺に言った。
「この間、お前の家で何人死んだんだと、聴いたな?」
辞めてくれ、何でこんな最悪のタイミングでそれを言うんだこの人は。
何人死んだんだ、とは以前、俺の家に先生が初めてやってきた時の事、先生が帰り際に言い放った無責任な発言の一つだ。
俺はあの後しばらくは家中の電気をつけて夜を過ごすようになった。
まあ出張中の母親に今月の電気代について説教された為、今はつけたままなんて事はしてないが、それでもたまに思い出しては夜一人でびくびくしている。
もしあの家を引っ越す予定があるのなら、俺も詳しく過去の事を調べてみたいもんだが、残念ながら高校を卒業するまでの約二年間は、俺はあの家に嫌でも住み続けなければいけないのだ。
それに昔の人はとても素晴らしい言葉を残してくれているじゃないか、
触らぬ神に祟りなし、と。
「ええ、覚えてます……あの後ちょっと家の事について調べてみたけど何も分かりませんでした、それが?」
勿論調べてなどいない、調べるつもりもないが、
「いや、あの家はいいんだ、いずれ調べれば分かる事だしな。 一筋縄ではいかないだろうし」
と先生。
おいおい調べる気なのか……
俺が気をもんでいると先生は、それより……と付け加えて話を続けた。
「問題はここさ、このホテルでも人が亡くなっている、過去に三人、な」
先生はそう言うと、足下にあった窓ガラスの破片の上に足を置いた。 その足にゆっくりと力を込める。
静寂に包まれたロビーにパキン、という乾いたような跳ねる音が響き渡る、と同時に、先生はゆっくりと口を開きぽつりぽつり、と語り始めた。
「丁度今から一年前、ここホテル○○ワールは、とある女性がオーナー件支配人をやっていた。 しかし女性がこのホテルで病気で亡くなると、その女性の親族達の手によって、このホテルは閉鎖され、買い手がつくまでの間放置される事となった。 だがそんなある日、事件は起こった」
「事件……?」
俺が聞き返すと、先生はそれに軽く頷くようにして再び口を開く
「市内に住む、とある女子高生が、ある日この廃ホテルに侵入した」
俺が固唾を飲んで先生の話に耳を傾けていると不意に、足元に何か柔らかいものが触れた。
何だ? と思って下を見ると、黒い毛で覆われた小さなものが物凄いスピードで駆け抜けていくのが見えた。
あまりの突然の事に、俺は声を出すのも忘れてその場から大きく飛び退く。
「なんだ?」
先生がそう聴いてきたので、俺は狼狽しながら、
「な、ななな何かいます!」
と答えた。
すると先生が俺の背後を指をさして言った、
「何かって、あれの事か?」
すぐさま先生が指をさす方に振り向くと、階段の踊場を通り過ぎる猫らしき後ろ姿がチラリと見えた。
「ね、猫……?」
「みたいだな」
呆れたような顔で腕を組み俺を見る先生、
「オーナーの女性が大の動物好きだったみたいでな、亡くなった後もその数を増やしてここに住み着いているらしい、野良猫や野犬の住処になってて、近所でも問題になってるみたいだ」
なるほど、と俺は黙って頷く。
先生の俺を見る視線が痛い。
俺はペコペコと先生に何度も頭を下げ、途中だった話の続きを伺った。
「それで、その女子高生はなんでこんなとこに侵入したんですか? 肝試しですか?」
「言ったろ、ここでも亡くなった人がいるって、ついてこい」
先生はニヤリとしながらそう言うと、さっきの猫が駆け上がって行った踊場に向かって、階段を上り始めた。
どうやらこれ以上は教えてくれないみたいだ。 後はついてのお楽しみと言いたいのだろうか?
先生は一体俺に何を見せる気だ?
もしかしてその女子高生がここで亡くなって、幽霊になったからそれを見にきたとか?
「おい、何してる」
考え込み立ち止まる俺に、先生がついて来いと手で合図を送ってきた。
「あ、すみません」
慌てて階段を駆け上がる。
踊場に出ると、目の前に壁があり、左右に長い廊下が伸びている。
奥の方は真っ暗だ。
ふと腕時計を見るともう午後6時を回っていた。
もう夜の闇はそこまで来ている。
先生は迷わず右に曲がると、慣れた足取りでそのまま奥へと進む。
「ここにはよく来るんですか?」
何となく気になったので聴いてみた。
まあこんな所に一人で来るなんていうのもおかしいが、この先生なら十分ありえる。
「ここのはまだ解けてないんだ」
先生はそれだけ答えると、また黙ったまま懐中電灯で廊下を照らしながら奥へと進む。
やはり来ていたのか。
というか解けてないっていうのはどういう事だ?
一人頭の中で連想していると、不意に先生が言ったある言葉が、俺の頭の中を過ぎる。
『奴らはバラバラになったパズルのピースみたいなもんだ』
以前、先生が俺に聴かせてくれた言葉だ。
俺はハッとして目の前を歩いている先生の背中に質問を投げかけた。
「ここに、解けないパズルが……あるんですか?」
先生が急に立ち止まる。
俺もその場で急停止。
「へ~、分かってきたじゃないか」
先生は振り向きもせずにそう言うと、再び奥へと歩き出す。
俺にはその声がどことなく嬉々をはらんでいるように聴こえた。
正直、頭のおかしな会話だと俺は思う。
確かに俺と先生は、説明のつかない奇妙な体験をした。
だが、信じれば信じるほど裏切られるもの、それがオカルトで、俺はそれを高校の頃に身を持って体験している。 だから遊び感覚くらいが丁度いい……丁度良いはずだった、先生に出会うまでは。
誰かと何かを共有するなんて事はなかった。 ずっと一人、それが当たり前だと思っていた。
でも、先生と出会って初めて俺は、誰かと同じ目的で行動する事、同じ世界を共有する事が楽しいと感じる自分に、この時気づき始めていたのだ。
だからなのかもしれない、社会見学だと言われ、こんな廃墟に連れて来られても、どこかワクワクした気持ちでいられるのは……
などと一人想いを馳せていると、
「また気持ち悪い顔してるな、たっく、ほら着いたぞ」
振り返りこちらを見る先生から辛口な言葉が飛んできた。
俺は頭を掻きながら先生の方を見た、廊下の突き当たりにある部屋の前に立っている。
どうやら目的の場所に着いたようだ。
急いで駆け寄ると、先生がゆっくりと両手でドアノブを回した。
分厚い鋼鉄製の扉だった。 ズシリ、と扉が重々しい音を立てながら開く。
扉はまるで暗闇の中、巨大な怪物が大口を開けて、俺と先生を飲み込もうとしているようにも見えた。
想像して思わず息をのむ。
「入るぞ」
先生はそう言うと俺の返事を待たずに、部屋の中へ吸い込まれるように入っていった。
慌てて俺もその後に続く。
中は想像以上に暗い。
入り口から外の光が僅かに差し込んだが、部屋の奥まで照らすにはいたらなかった。
開け放っていた扉が、その重みでゆっくりと勝手に閉まり、再び部屋の中全てを闇が覆い始める。
俺は部屋の中を、手に持っていた懐中電灯で照らそうとスイッチを押した。 すると先生は俺の持っていた懐中電灯をすかさず取りあげると、すぐさまスイッチを切ってしまった。
「何するんですか? 暗くて何も見えないですよ」
俺がそう口にすると先生は、
「こいつらは明かりが苦手なんだ、それに部屋の中は私が頭の中に叩き込んでる、来い」
そう言ってぶっきらぼうに俺の手を握り、部屋の奥へとズンズンと進んでいく。
こいつら? すぐに聞き返そうとしたが、俺は手を握られたせいで恥ずかしさの余り口を噤んでしまった。
「ここに座れ、ほら」
先生はそう言いながら、握っていた俺の手に、ひんやりとした鉄の板のようなものを掴ませた。
空いた手でその物体を確認する。 どうやらパイプ椅子のようだ。
俺がそのパイプ椅子を広げ座ろうとすると、直ぐ隣で先生が何やらゴソゴソとしだした。
何か液体のようなものを器に注いでいるようだ。
とりあえず椅子に腰掛けると、俺は先生にさっきの事を聴く事にした。
ついでに今何をしているのかも、
「さっきのこいつらって、一体何の事です──うわっ!」
最後まで言いかけた瞬間だった。
またもや突然、俺の足元を何やら生暖かいものが、しかも今度は通り過ぎるのではなく、俺の足元にすり寄ってくる。
これはもしや……
「ね、猫?」
暗闇にうっすらと目が慣れてきた俺の視界に、子猫ほどの大きさの影が、暗闇の中蠢くのが見て取れた。
暗すぎてはっきりと捉えられないものの、先生のこいつらというニュアンスといい、さっきの液体を注ぐ音といい、俺はようやく自分が置かれた状況を理解する事ができた。
「肝試しじゃなかったんですか……?」
「誰が肝試しなんて言った?」
ごく当たり前のように身も蓋もない事を言う先生。
社会見学でもないでしょとツッコミたかったが、なんだか呆れてしまったので言うのはやめた。
陶器の乾いたような音、先生が何か皿のようなものを床に置いた、同時に部屋の四隅から別の気配がし、俺は咄嗟に辺りを見渡す。
子猫は一匹ではなかったようだ。
三匹、いや四匹か。
皿の中はミルクだろうか?ほんのりとした乳製品の微かな匂いが、俺の鼻先をくすぐった。
「それ、ミルクですか?」
俺がそう聴くと先生は、
「まあな、母乳はでないし、こいつで代用するしかない」
そう言って左手に持っていたものを俺に近づけてきた。
市販で売られている牛乳パックの影がうっすらと見える。
というか母乳って……。
俺は妄想を掻き消すように頭を振ると、それをごまかすように先生に話し掛けた。
「え、餌をやりに来たかっただけならそう言えば良かったのに……せ、先生って猫そんなに好きなんですか?」
「別に、まあ可愛いとは思うけどな……ん? 餌?」
ふと会話が途切れた。小首をかしげる俺、なんだか先生と話がかみ合わない感じ。
どうしたんだろうと思い俺は、
「子猫に餌をやりに来たんじゃないんですか?」
と、確認するように聞いてみた。
すると先生は何が可笑しいのか、
「ははは……そうか、そうだったな、まだ話の途中だった」
そう言って愉快そうに笑いながら言ってきた。
何だ? 餌やりでもないのか?
先生の態度に俺が戸惑っていると、そんな俺の様子を察したかのように、先生は独り言のようにポツリ、と話し始める。
「女子高生がこの廃ホテルに侵入したのには訳があったんだ」
女子高生、確かこの部屋に来る途中に先生が話してくれたやつだ。
さっきは途中までだったが、どうやらやっと続きが聞けるらしい。
まあ話の出だしからして、おそらくその女子高生がここで自殺したというような内容だろうか。
「その女子高生は普段学校にも行かず、その当時付き合っていた男の家で暮らしていたらしい。 まあ素行の悪い家出娘だな。 そんなある日、その付き合っていた男と女子高生の間に子供ができてしまった」
そこまで聴いて俺は、率直によく聞く話だと思った。
子供ができたのを潮時に、男は女を捨て、女はそれを悲観して死を選ぶ。
俺の父親もそんなろくでもない男の一人だ。
ただうちの母親は俺を産んでちゃんとと育ててくれた。
「赤ちゃんができた事を男に相談するも、最悪な事に男はそれを期に女の子を家から追い出そうとした」
やはりその展開か、俺は胸の内で軽いため息をつきながら先生の話に耳を傾ける。
「女の子はそれを拒み何とか男との生活を続けるが、子供をおろす金もなく、ましてや男が出すはずもない。 かといって家出した手前、家族にも頼れない。 そんな八方塞がりの中、やがて時間だけが過ぎて行った」
「だから……その女子高生はここで自殺を図ったんですか?」
何だか聞くのも酷な話になってきたので、俺は先生の話を最後まで聞かずに後の展開であろう結末を聞いた。
すると先生は、
「いいや、その女の子は今もピンピンしてるよ」
「えっ?」
予想だにしなかった展開だ、まさか男の気が変わって子供を産む事になりハッピーエンド、なんていうリア充爆発しろみたいな展開にでもなったというのか?
いや待て、先生はここで人が亡くなっていると言っていた。
死んだのが女子高生ではないとすると……何だか嫌な予感がする。
「その女の子は産んでしまったのさ、もちろん病院なんかじゃない、その男の家でな」
話が一気に殺伐としてきた……確かに何かの拍子で子供が産まれたという話は、テレビなんかでたまに見聞きした事がある。
それよりも、肝心なのはその産まれた赤ちゃんだ。
「その赤ちゃんは……どうなったんですか?」
恐る恐る先生にそう聞くと、先生は俺に、
「さっから言ってるだろ、その女子高生は訳があってこの廃ホテルに侵入したんだって」
と、何か言い含めるような言い方をしてきた。
そのせいか、見えるはずのない先生の顔が、暗闇の中で歪んだ笑みを浮かべているように見え、俺は背筋が僅かに粟立つのを感じた。
静まり返る部屋に、ペチャペチャ、という耳障りな音が響く。
暗がりの中、子猫達が必死にミルクを舐め回しているのだろうか。
それはさながら赤ん坊が母親の乳を貪る様子とも伺える。
赤ん坊……
その瞬間、なぜか妙に胸の内がざわめくような感覚に襲われた。
周りの音が遠くなり、自分の胸の鼓動や脈拍が逆に近くで鳴り響いているのがよく分かる感じ、
先生はここに解けないパズルがあってきた。
それはつまり世間一般的に例えると、幽霊といったものがここにいると示唆する。
でもここで亡くなったのは女子高生ではない、おそらく先生の話からして亡くなったのは赤ちゃんだ。
何だ、なぜこんなにも気持ちがざわつく。
何か大事な事が解り掛けているのに、それが頭の中ではぼやけている、そんな歯痒い思いがしてならない。
俺がそんなジレンマをしていると、先生が話の続きを語り出した。
「女の子は産まれた赤ん坊をこの廃ホテルに捨てたと、後に警察に証言している、」
警察?
「つ、捕まったんですかその女子高生は?」
「ああ、まあ正確には自首したんだよ、後になって怖くなったそうだ、赤ん坊が捨てられてから丸四日が経過していて、もちろん赤ん坊は既に死亡していた」
四日も放置しておいて怖くなったなんて……自分の保身しか考えていないとか、どれだけ身勝手な奴なんだ。
先生の話を聴いて俺は胸を強く締め付けられるような窮屈感を感じた。
絶え間ない喉の渇きと、落ち着かない感情からして、自分がその母親に怒りを感じている事に気付く。
先生はそんな怒りすら感じさせない淡々とした喋り方でなおも話を続けた。
「一応テレビでも取り上げられたらしいが、なにぶん未成年が絡んでる事件で報道規制がしかれていてな、記事やネットなんかで普通に調べられた限りではここまでだ」
先生はそこまで話すと口を閉じた。
暗闇の中に、再び静寂が訪れる。
静かだ、駅から少し離れているとはいえ騒音や喧騒といった音すら聞こえない。
それに妙に暗い、普通いくら夜でも外には街灯や月明かりだってある。 なのにあるのは、、ドアの隙間から差し込む僅かな光だけ。
カーテンをした窓でさえ、隙間から外の明かりが微かに差し込んでもおかしくないはずだ。
なのにこの部屋は……
そこまで考えて、俺の思考は一度そこで停止した。
そして一瞬の間を置いて再び稼働し始める。
そうだ窓だ。
「この部屋、窓ありませんよね?」
俺がそう聞くと先生は、さも当たり前のように、
「ないよ、ここは制御室だからな。 扉はあそこだけ。 窓もないし他に出入り口はない、完全に密閉された場所さ」
密閉された場所?
この部屋に入った時、いたのは先生と俺だけだ。
子猫達は……一体どこから来たんだ?
その瞬間、 俺はさきほどの妙な感覚の正体が頭の中で見え隠れしている事に気が付いた。
なぜこの違和感に気がつかなかったのだろう。
俺はまだ、一度もこの子猫達の鳴き声を聴いていない。
ペチャペチャと、耳障りな音が響いている。
先生は黙ったままその様子を伺っているようだ。
俺は口を開き先生に質問しようとしたが、声がだせなかった。
歯と歯がぶつかり合い、カチカチと小刻みな音を立てた。
そこで初めて自分が震えている事に気づく。
先生は何に、餌をやっているんだ……?
馬鹿げている、自分でもそう思う。
あれは子猫だ、さっきだって猫らしき動物が足元にまとわりつくのを俺は見た。
暗がりだが扉の僅かな隙間から漏れる月明かりで、その輪郭は捉えられた。
だったら何も疑問に思う事はない。
今先生の足元にいるのは子猫だ、間違いない。
と、今までの俺ならそう断言できていた。
だが今の俺は以前と違っている。
幽霊を見たいという自分から、あれはただの見間違いだと言い切る自分へ、そして先生と出会ってからの俺は…
…俺は、魅せられている。
知りたいという自分と知りたくないという自分、そこに生じる何か危うい存在から、暗闇の中、手招きされているような、
「どうした何に怯えている?」
俺を呼ぶ暗闇からの声、それが先生の声と分かりながらも、今の俺にはまるで別人のように思えた。 危うく、禍々しい、惹かれる存在。
「一つ、聞いてもいいですか?」
「何だ?」
俺の声に暗闇が応える。
「その、足下にいるのって、子猫……ですよね?」
暗闇は何も答えない。
だが今の俺には分かる。
暗闇が、先生が今、この上ない笑みを浮かべているんだと。
「何とか言ってくださいよ……」
沈黙に堪えきれず俺から口を開いた。
「懐中電灯まだ持ってるだろ、確かめてみろ、自分の目でな」
今度はハッキリと耳で聞き取れた、言葉の端に残る先生が零した微かな笑みが、
「ふ、ふざけないでくださいよ、あれは子猫でしょ? さっきだって子猫らしきものを僕はこの目で、」
「事件から半年後、女の子の彼氏である男が指名手配された」
「えっ?」
俺の言葉を遮るように、先生がまた事件について話し始めた。
というか続きがあったのか?
思わず俺は口を噤む。
「私の大学のOBで記者をやっている人がいてな、ここから先はその人から聞いた話なんだが、事件が発覚して数日後、警察の取り調べにより、女の子が男を庇っていた事が分かったんだ。 女の子は寸前で思い留まり、産まれた赤ちゃんを一度は育てようとしたらしい、が、男が赤ちゃんを奪い取り、この廃ホテルに再度捨てたそうだ。 女の子はその後、『気が動転して自分が捨てた』、と嘘の供述をしたが、罪の意識からか、その赤ちゃんへの贖罪のつもりなのかは分からないが、最後まで嘘を突き通す事ができなかったらしい」
「救われない……話ですね」
ありきたりな感想だが、俺は素直にそう思った。
その女子高生にも、一応は母親としての自覚が僅かにはあったのだ。
まあだからといってやはり許される事ではないが。
「救われない話は、ここからさ」
先生はそう言うとまた言葉の橋に笑みを零す。
なんだか嫌な予感がする。
「なぜ男はここに赤ちゃんを捨てたと思う? おかしいと思わないか? こんなとこに捨てたりしたら、それこそ直ぐバレるだろ、死体となっても、それ自体が証拠になるんだからな」
確かに先生の言うとおりだ。
いくらここが廃ホテルとはいえ、一応は管理会社だって見回りに来る可能性だってあるし、それこそ所有者、またはそれ以外の第三者の侵入により発見される可能性がある。
その男だって、ここが安易過ぎる場所だと分かっていたはずだ。
ではなぜ分かっていてここに赤ちゃんを捨てたのか……
俺が思考を巡らせていると、先生がそれを見計らったように口を開く。
「オーナーの女性が亡くなって以来、ここは野良猫や野犬の住処になっていると、言ったよな?」
「ああはい、さっきここに来る前に言ってまし……えっ、そ、それって……」
「出産前の飢えた動物達の群れと、赤ん坊をこの部屋に閉じ込めたらどうなると思う?」
先生の問に俺は考える間もなく吐き気を感じ何も答えられなかった。
「さっきも言ったように事件は未成年が絡んでいたせいで報道規制がかかっいた、しかし一部では、赤ん坊の遺体はかなりの損傷痕があった為、猟奇的な事件じゃないかと問いだたされる面もあったそうだ」
淡々とそんな話を語る先生も先生だが、同じ人間として、その男がなぜそんな事をしたのか、理解のしようがないし、したいとも思わない。
「ここまで聞いたら分かるだろ? さあ答えろ、私の足下にいるのはなんだ?」
子猫──とはもう言えなくなっていた。
赤ん坊……いや、もうそれすらでもないんじゃないのか?
何にせよ、俺にそれを見る勇気はない。
「もう出ましょう先生、さっきから気持ちが悪くて、」
事実だった。
正直吐いて楽になりたいくらいだ。
「そうか……しかたないな、ほら手を貸せ」
先生はそう言うと僕の手を掴み、暗闇の中を慣れた足取りで出口に向かった。
勿論俺は下を見ずに先生の後をついて行く。
ノブを手に取り、扉を押し開けると同時に月明かりが暗い部屋の中に差し込む。
俺と先生は互いに押し黙ったまま部屋を出ようとした、その時だ、
泣き声が、聴こえた。もちろん猫ではない。
赤ちゃんの泣き声。
「今のって……?」
俺がそう聞くと先生は、
「振り向いて自分で確かめてみればいい」
と冷たく言い放った。
するとまた、小さくすすり泣くような赤ちゃんの声が、後ろの制御室から聞こえてくる。
見てはいけない、そう思っていたはずなのに、俺の体は自分の意思とは反対にゆっくりとボイラー室の方へと反転した。
扉の向こうに広がる深淵の闇、その闇の中に浮かぶ、子猫の体をした、しわくちゃで歪な無数の顔。
おぎゃぁ……おぎゃぁ
心臓に楔を打ち込まれたように俺の体は固まった。
喉が痙攣し叫び声すら上げられない、だがそれよりも、俺は……泣いていた。
泣く? なぜ?
恐怖から? いや違う。
恐怖からの涙ではない、泣いているという感覚ではないからだ。
目元の熱さも感じない、まるで涙が勝手に俺の目から溢れているような感じ。
すると今度は俺の口から嗚咽のような声が漏れ始めた。
勿論俺の意思ではない、口を閉じようにも体全体が全身麻痺を起こしたかのようにいう事をきかない。
指先からつま先までの感覚も失い、俺の体はまるで糸の切れた操り人形のようにガクンと地面に崩れ落ちる。
が、地面に倒れ込む瞬間、すぐ側にいた先生が俺を何とか抱きかかえてくれた。
「おいどうした!? しっかりしろ!」
先生の呼び掛けにも応えられず、俺は恐怖のあまり叫び声を上げた、が、出たのは叫び声ではなく、嗚咽のような泣き声、すすり泣くような……赤ちゃんの泣き声。
体の自由がきかず、身の内から湧き出る恐怖だけが俺の体を支配する。
すると、俺を抱きかかえていた先生が俺を見下ろす格好で驚愕したような表情を見せた。
先生はそのまま俺をゆっくり抱き寄せると耳元で、
「そうか、そうだったのか……お腹がすいていたんじゃなかったんだな」
と囁く。
そして右手で俺の背中を支え、左手を頭の上に置くと、今までの先生からは想像もつかない優しく穏やかな声で、
「こうか……よしよし……」
と、小鳥がさえずるような声で呟いた。
涙が、泣き声が、止まっていく。
同時に急激な睡魔が俺を襲った。
こんな状況下なのに、俺は抗う事もなくその睡魔に身をゆだねてしまった。
ふんわりとした温もりと、心地よいさえずるような先生の声。 まるで、まるで母親に抱かれているような……俺の意識はそこで途絶えた。
目が覚めると、そこは見覚えのある車内だった。
助手席から運転席を見ると、先生がこちらを向いたまま目を瞑っている。
微かに寝息が聴こえる。
寝ているようだ。
「先生が運んできてくれたのか……」
腕時計に目をやると、時計の針が両方とも真上を指し示していた。
辺りは真っ暗で、街灯と月明かりだけが俺と先生を照らしていた。
先生を起こそうと思ったその時、俺は自分の右手に違和感を感じ目をやった。
先生が、俺の手を握ってくれていた。
右手に優しい温もりを感じながら、起こすのはもう少し後で、そう思った……
※後日談
赤ちゃんを廃ホテルに捨てた男は現在も逃亡中。
ただ、男のものと思われる車が、その廃ホテルの付近で発見され、車内の中には、財布や携帯といった所持品も発見されたらしい。
が男は今現在も行方が分からないまま。
作中に、先生は、
亡くなったのは三人と述べていました。
一人はこのホテルで病死したオーナー、もう一人は名もなき赤ん坊、そして三人目は……
これはあくまでもヲタ君の話を聞いた私の勝手な見解ですが……いや、その答えは、先生だけが知っている、という事なのかもしれません。


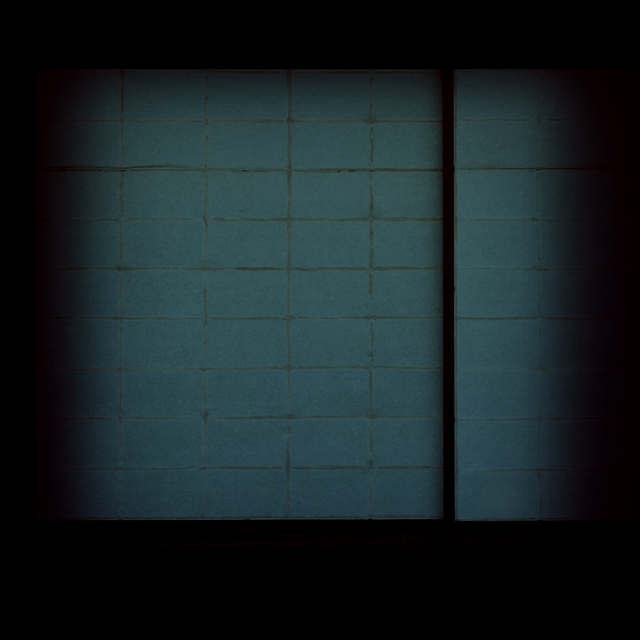

作者退会会員
できれば第一話を読んでからお読みくださいませ。
ヲタ君の家庭教師第一話→http://kowabana.jp/stories/25725