叢雲が漂う朧月夜に、巨大な菊の形をした花火が打ち上がった。
手を伸ばせば届きそうな程の近さ。
眩い光が一瞬で空一杯に広がり、キラキラとした火の粉が、合わせ鏡の様に水面に降り注いだ。
──桜の花は、直ぐに散るからこそ美しいのです……。
散りゆく花火を目の前にし、ふと思い出した言葉。
彼女が僕に言った言葉だ。
彼女と言っても、僕が付き合っている子と言う訳では無い。
忘れもしない、あれは……風が吹くと、桜の花弁が雪の様に舞う、そんな風の強い春の日の事だった。
「あれか?」
此方に振り返りもせず、男性はぶっきらぼうに言いながら目の前にある巨大な八重桜を睨み付けた。
三日前この場所で、僕の通う高校の同級生二人が怪異に見舞われた。
何処からともなく聞こえる声に呼ばれ、この八重桜に近づいた所、突然足を掴まれた。
転倒した二人が起き上がり桜を見上げると、花弁から滴る血が地面に吸い込まれてゆくのを目撃したという。
「あの狗甘(いぬかい)さん?」
僕が名前を呼ぶと、ようやく男性は此方に振り向いた。
「冬弥(とうや)でいいよ」
「いや、でも先輩だし……じゃ、じゃあ冬弥さんで」
そう、狗甘 冬弥さん、彼は僕の高校の先輩だ。
僕の通う高校で彼の名前を知らない奴はいない、それぐらい有名な人だったりする。
それは単に彼の親が有名な占い師で、お金持ちだからという理由だけでは無い。
政界にも顧客がいるという彼の親の力をついだのか、彼、冬弥さんもまた、不思議な力の持ち主なのだ。
数々の霊的な事件はもちろんの事、実際に刑事事件になった女子高生の失踪事件を解決したという噂まである。
オマケに端正な顔立ちで、学校の女子にも人気があり、まるで漫画から抜け出したような人だなと、出会った時に僕はそう思った。
「んーまあいいや、じゃあそれで。で、その二人が被害にあった場所はここでいいんだな?」
冬弥さんは僕らの前にそびえ立つ八重桜を指さして見せた。
「は、はい」
被害にあった同級生二人にお願いされ、三年生の教室に、この冬弥さんに相談に行ったのが、昨日の放課後の事だった。
快諾してくれた冬弥さんを連れて、今日の学校帰り件(くだん)の八重桜まで僕らは来たという訳だ。
冬弥さんは僕の返事に黙って頷くと、スタスタと八重桜の根元まで歩み寄った。
かなりの巨木で、樹齢何年など詳しくは知らないが、他の桜と見比べても何かこの桜だけ特別なものを感じてしまう。
「あ、二人が足を掴まれたのはその辺です」
僕は冬弥さんに駆け寄り、彼の足元付近に屈んで地面を叩いて見せた。
「ふーん」
「で、血が滴ってきたのが……えっ?」
その時だった。
──ポタポタ
と、上から何かが降り落ち、水滴音を立てた。
屈んだ姿勢で僕は上空を見上げた。
「ん?何だ?」
僕の異変に気が付き、冬弥さんも釣られて上を見上げる。
その途端、
──ポタポタ
八重桜の枝先、花弁から滴る、赤い……血……。
見上げる冬弥さんの顔にそれが振りかかった。
「う、うわあぁぁあっ!?」
突如叫び声をあげる冬弥さんだったが、次の瞬間、
──ズルッという音と共に、冬弥さんはその場で体制を崩し、前のめりに突っ伏す様にして盛大に倒れ込んでしまった。
「うわあぁっ!!」
余りの事に僕まで叫び声を上げた。
すると倒れた冬弥さんは素早く起き上がり、脱ぎ落とした靴を拾いもせず、その場から脱兎の如く駆け出した。
「えっ?ええっ?ま、待ってください冬弥さん!」
叫ぶように言って走り去る冬弥さんの背中を追いかけた。
暫く走った後、冬弥さんは大きな日本家屋の門のインターホンを鳴らした。
「俺だ!柚月葉(ゆずは)!開けてくれ!!」
扉の前で冬弥さんが大声で言った瞬間、雅な楼門の扉が、重苦しい音を立てながら開いた。
冬弥さんは直ぐに門を潜り抜け中へと入って行く。
僕は何が何だか分からないまま、後を追うようにして門の中へと入った。
「何だ……ここ……」
僕の視界の先に、突如平安時代が広がった。
滝を模した水が起伏した山を伝って流れ、庭石で囲まれた、雅な鯉達が泳ぐ池へと注ぎ込まれてゆく。
色取り取りの花や木々が立ち並ぶ、これぞといった純和風庭園だ。
そしてその横に設置された石畳の先に、大きく立派な日本家屋が佇んでいた。
見ると、玄関の扉が開かれており、その横に、着物姿の少女が僕の方を見て軽くお辞儀をしていた。
少女は顔を上げると、開けられた扉に手を添えるようにし、どうぞというように合図してきた。
余りの光景に緊張しまくっていたが、やがて腹を括った僕は、少女の元へと歩み寄った。
近づいて分かった事がある。
扉の前で僕を迎えてくれた少女は、かなり美人だったという事。
高級そうな着物に負けないくらいの、大和撫子と言ってもいい。
まだあどけない顔からして僕と同い年か年下だろう。
艶やかな唇はにこやかに微笑んでいて。
憂いを帯びた瞳は見るからに清らかだ。
目元からすうっと通った鼻筋は凛々しく、濡れそぼった様にしっとりとした黒髪が、そよ風にさやさやと揺れ動いている。
「あ、あの……その」
「宗介様……で、ございましょう?兄様(あにさま)から話は伺っておりますわ、ささ、どうぞ中へ……」
少女が喋る度に甘い匂いが辺りに漂う。
極度の緊張に、僕は名前を呼ばれた事も忘れ、少女に従うまま、家の中へと足を踏み入れた。
広い屋敷内に案内され、僕は居間の様な場所に通された。
外の純和風庭園とは打って変わって、ここはどこか生活感を感じる。
僕が近くのソファーに恐る恐る腰掛けると、少女は短く頷いて部屋を出た。
すると部屋の外から、
「いいよ別に後で」
冬弥さんの声だ。
「なりません兄様、この様な汚し物は直ぐに処理なさいませんと。」
どうやら先程の少女と何やら話している様子だ。
兄様?
あの二人は兄妹だったのか?
「おっ、待たせちまったみたいだな、すまんすまん。あ、宗介って呼んでいいか?いいよな!よし、宗介何か飲むか?」
矢継ぎ早に冬弥さんはそう言って、冷蔵庫から炭酸と書かれたラベルのジュースを、僕に投げてよこした。
「あ、ありがとうございます」
シャツ一枚になった冬弥さんは、顔を洗ったのだろう、首に巻かれたタオルで頭と顔を拭きながら、さっぱりした顔で大きく息を吐いた。
「いやあ参った参った、完全に不意をつかれちまったな!ははははっ」
そう言って冬弥さんは膝を叩きながら笑って見せた。
不意というか、あれは完全にビビって逃げ出した様にしか見えなかったのだが……。
「はは、そ、そうですね」
「でもまあ、奴の対処方法はこれで分かった、次はああはいかないからな。なっ宗介!」
「え?ええ、まあ……」
「なんだ暗いやつだな、もっと自信持てよ。じゃないとまたいいようにやられちまうぞ」
やられたのは冬弥さんです。
そう言いたかったがやめておいた。
代わりに、
「と、冬弥さんは、どうしてそう前向きなんですか?」
「ん?何が?」
「いや、だってさっきあんな事があったのに、もう次の事考えてるみたいだし、普通ならおじけついちゃったりとかしません?」
僕が尋ねると、冬弥さんはんーと首を傾げた後、僕の方を向いて口を開いた。
「だって、お前ら困ってんだろ?」
「えっ?」
「いや、困ってるから俺に助けを求めたんだろ?だったら、助けてやんなきゃだろ、男としてな」
冬弥さんはあっけらかんと僕にそう言って見せた。
「す、凄いな……僕とは大違いだ」
そう、僕とは全く真逆だ。
根暗で友達も少ない。
僕が冬弥さんの立場なら、今回の事件の依頼なんて絶対に引き受けたりなどしないだろう。
「あら、こんな所にゴミが……失礼、間違えましたわ。兄様でしたか……」
「ゆ、柚月葉」
冬弥さんは戸惑いを隠せないでいた。
というか何だ今の会話?
ご、ゴミ?冬弥さんの事?
「あ、あのな柚月葉、これでもお前の兄貴なんだからな、それをお前ゴミって」
「それはそうと兄様、例の怪異の件はどうなりまして?」
冬弥さんの言葉を遮るようにして、妹の柚月葉ちゃんは言った。
何だか思っていた性格とかなりかけ離れているみたいだこの子……。
僕は認識を改め、二人の会話に耳を向けた。
「ああうん……まあ大体分かったよ。あれは樹木子(じゅぼっこ)の類だな、うん、間違いない!なっ宗介!」
「じゅ、樹木子?なんですかそれ?」
突然話を振られ慌てて返事を返す。
「お前俺の助手のくせにそんな事も知らないのか?樹木子ってのは、戦場なんかで死んだ死者の血を吸って、妖怪化しちまった木の事だ。人の血を吸って生き長らえる吸血鬼みてえな野郎だな、うん」
そこまで言って、冬弥さんは自分で納得し大きく頷く。
ていうか助手って何だ助手って……。
「して、解決なされたのですか?」
「えっあ……いやその、今日は偵察というか……なっ!宗介!」
「じーっ……」
柚月葉ちゃんの射抜く様な視線が痛い……。
僕は助けを乞う冬弥さんから目を逸らし、
「えっ、ええと……様子を見に行ったら上から血が滴り落ちて来て、それで驚いた冬弥さんがその場で倒れてしまい、そのまま逃げ帰ったというかなんというか……」
僕はそこまで言って、最後の方は口ごもってしまった。
「う、裏切りやがったな宗介!だ、だけどあれはこけたんじゃないからな!靴を掴まれたんだ!ほ、本当だそ?あのまま反撃しようとしてたのにまさかあんな姑息な手にやられるとは思ってなかったんだ!」
冬弥さんが一気に捲し立てるように言った。するとそれを見ていた柚月葉ちゃんが、人差し指をそっと冬弥さんの唇に当てて見せた。
「クスッ……相も変わらず、無能でノロマですこと。兄様ったら。」
酷い追い打ちを見た気がする……泣きっ面に蜂というやつだ。
僕なら立ち直れないな、そう思った時だった。
「い、いつものやってくれたら……がが、頑張ってやらん事も……ない……」
なぜか突然、冬弥さんが照れ始めた。
全くもって意味の分からない展開だ。
すると柚月葉ちゃんはそんな冬弥さんを見て小さく笑みを零して見せた。
「いつもので頑張れる?フフ、本当にキモい変態さんですわね。」
そう言うと、冬弥さんの顎を親指と人差し指で挟むようにして、柚月葉ちゃんは続けて言った。
「このシスコン……きちんと解決しなさいな。」
「は、はい!」
微かに頬を赤らめ、冬弥さんは突然声を張り上げて返事を返したかと思うと、踵を返し玄関の方へと猛スピードで走り去って行った。
何なんだこの二人……えっ?何?そう言う関係?いや待て、どんな関係だ……。
思わずその場で頭を抱え込む。
「さてと。私は外出致しますが、宗介様は?」
「へっ?あ、え、ええと僕も用があるから、こ、これで失礼します!」
「左様ですか。では、門までお送り致しますわ。」
結局、僕は何だかよく分からない状況の中、狗甘邸を後にした。
暮れていく夕日を受け、桜の花弁が淡い金色に縁取られていた。
風が吹き花弁が空に舞うと、キラキラと輝いている様に見える。
僕は今、あの件の八重桜の前に一人立っていた。
いや、正確には一人じゃない。
「本当に来るんだよな?」
「お前いざって時に使いもんになんねえからな」
僕を合わせ三人だ。
今喋っていた二人は、僕が冬弥さんに話した、ここで被害にあった同級生の二人。
いや、正確に言うと被害になんかあってはいない。
「うん……来るはずだよ。こっちに向かったの確認したから……」
「ならいいけど。次はいよいよクライマックスだからな。めっちゃビビらせた所動画に撮って晒してやろうぜ!」
「それまじ賛成!」
二人は面白可笑しそうに話し合っている。
「ねえ……やっぱり止めない?こういう……事……」
僕はそんな二人に、掻き消えるようなか細い声で言った。
「はあ?お前今なんつった?」
二人のうち一人が、そう言いながら僕の前まで近付いてくる。
「いや、こ、こういう人を騙すのはもう止め、」
言いかけた瞬間、腹部に激痛が走った。
前蹴りだ。
近付いてきた一人に、突如お腹を勢いよく蹴り飛ばされたのだ。
僕は自分の腹を抱えるようにして地面に倒れ込んだ。
「痛っ!!」
「白けるような事言ってんじゃねえよ!だいたいあいつが悪いんだぞ?人の女かっさらいやがって、復讐しねえとこっちの気が収まらねえだろ!」
「そうそう、俺たち友達だろ?協力してくれるよな宗……ええと名前なんだっけ?まあいいや適当で、はははっ!」
痛みに顔をしかめる僕に、二人は笑いながらそう言った。
そう……冬弥さんに依頼した内容は全て出鱈目(でたらめ)だった。
端からそんな事件起こってもいなかったのだ。
僕を蹴りあげた同級生の彼女が、冬弥さんの事を好きになってしまい、同級生に別れ話を切り出してしまった。
つまりは逆恨みによって生まれた作り話だったのである。
全ては冬弥さんを罠にはめるための事だったのだ。
そして僕はこの気弱な性格のせいで、二人の言いなりになってこの悪事に加担してしまった。
けれど、そんな僕に冬弥さんは真っ向から相談にのってくれた。
疑いもせず、僕の事ちゃんと名前で呼んでくれた。
だけど断りきれなかったとは言え、僕にも責任がある。
ならせめて……。
「お、おねがいだから、もも、もう……」
「カッチーん、はいはいなんかムカついてきたよ~!」
そう言って同級生は、僕の頭を掴み無理やり立たせた。
髪を引っ張られ痛みに耐えていた、その時。
「成程……やはりそういう事でしたのね……」
聞き覚えのある声に、思わずハッとして声の方を向く。
そこには、さっき狗甘邸であった柚月葉ちゃんの姿があった。
「はあっ?なんだお前?」
「うわめっちゃ可愛いじゃん、何?誰あんた?」
二人の声に何も反応せず、柚月葉ちゃんは話を続けた。
「兄様の御召し物についた血は、どう嗅いでもペンキ独特の化合物の香りが致しましたので……それに……」
柚月葉ちゃんは言ってから八重桜の元に歩み寄ると、冬弥さんが脱ぎ捨てた靴を見つけ、それを手に取った。
「成程、靴に針で刺した様な跡がございますね。釣り針……でしょうか?という事は、おそらく釣り糸ですわね。まず兄様の靴に釣り針を刺し、予め仕掛けておいたペンキ袋を釣り糸で引っ張った。そしてペンキを兄様の頭上へと垂らす……それに驚いた兄様を、今度は靴に仕込んだ釣り針と糸を用いて転倒させた。といったところでしょうか?」
唖然とした。
二人も開いた口が塞がらないといった様子で、掴まれた手の力が緩んだのを確認した僕は、その隙にその場から脱出した。
「な、なんなんだお前……?」
辺りに異様な緊張感が漂う。
だか、そんな中でも柚月葉ちゃんはクスリと微笑んで見せた。
「早くお逃げなさい……貴方がたは些か騒ぎが過ぎました……こんな余計なものを起こしてしまって……」
「えっ?」
柚月葉ちゃんの言葉に、僕が返事を返したその瞬間、
桜の花弁が……散った。
いや、散る?では無い。
雨だ……桜の雨。
膨大な桜の花弁が、まるで雨の様に僕らに降り注いだのだ。
「な、なんだこれ……!?」
「おお、おい!どうなってんだ!?」
二人が取り乱し喚き出す。
僕もこの異常な事態に膝が震え身動きできないでいた。
花弁は振り続ける。
しかも、淡い桃色の花弁では無い……血の様に真っ赤な花弁だ……。
見ると足元が花弁で埋め尽くされそうになっていた。
「やばいっておい!!」
「うわぁぁっ!!」
二人は叫び声をあげながら転がるようにし、その場から走り去って行ってしまった。
残された僕は、花弁から抜け出そうと震える体を何とか柚月葉ちゃんの方へ向けた。
「宗介様、少々お待ち下さいな……」
柚月葉ちゃんはやんわりと僕に言うと、八重桜の元へ再び歩み寄っていく。
「あっ……」
手を伸ばし僕も歩み寄ろうとするが、足がいうことをきかない。
「成程。拠り木でいらしたのですね……ですが私達は死者ではなく、生者にございます。寂しいでしょうけど、もう引き寄せるのはお止めなさい。ついでですので、こちらの方々も解き放って頂きます……」
拠り木?生者?解放?
一体何を?
柚月葉ちゃんはそう言ってその場でしゃがみこむと、ゆっくりと手の平を八重桜の根元に押し当てた。
降っても降っても次々と花を咲かせ、それが桜雨となって僕らに降り注ぐ。
やがて柚月葉ちゃんの姿が、花弁で埋もれそうになった時だった。
突然眩い光が、柚月葉ちゃんの周りから放たれた。
その眩しさに思わず僕は顔を背ける。
「何だ……これ!?」
光を両手で遮るようにして前を向いた瞬間だった。
雨が……桜の雨が、止んだ。
上を見上げると……無い、桜の花が。
一片も。
まるで真冬の枯れ木の様に、花弁も蕾も見当たらない。
そして八重桜だったはずの巨木の根元には……柚月葉ちゃんの姿があった。
いや、柚月葉ちゃんだけでは無い……八重桜を囲むようにして、人の形をした薄い靄がかったものが、微かに蠢いていた。
「な、なんだ……あれ……」
呆気に取られそれを見ていると、柚月葉ちゃんは立ち上がり、手を合わせるようにして口を開いた。
「貴方がたの拠るべき場所は、ここではございませんわ。道をお作りしましょうね……其方へ」
──パン
柚月葉ちゃんはそう口にし、両手を力強く合わせた。
すると靄がかった得体の知れない者達は、夕暮れの空へと立ち昇るようにして、すうっと掻き消えていってしまった。
一連の流れを呆然として眺めていた僕に、柚月葉ちゃんは、
「こちらの八重桜は戦時中の、あの大空襲をも生き長らえたのです……しかし、その周りには沢山の死者で溢れかえってしまいましたわ。八重桜は、そんな救われない死者の寄り所となったのでございましょう。」
悲哀に満ちた目で、柚月葉ちゃんは八重桜を見上げそう言った。
つまり、今の白い靄がかった人のようなものは……ここで亡くなって、長い間この八重桜に寄りかかっていた人達の……。
そこまで思い、僕はハッとした顔で柚月葉ちゃんを見た。
「ご、ごめんなさい!ぼ、僕冬弥さんに……!」
後悔してもしきれないそんな思いで、僕の胸はいっぱいになっていた。
「私と宗介様との秘密……と、いう事としておきましょう……」
「えっ?」
「宗介様は、あの輩にもきちんと物言えたではございませんか……」
「えっ?あ、いやでも……」
靴に釣り針を仕掛けたのは僕だ。
僕が加担した事は事実なのだ。
「どうしても償いたいと仰るのなら。そうですわね……兄様の、助手……」
「へっ?」
思わず変な返事をしてしまった。
じょ、助手?
「兄様は何事も形からお入りになる御方でして……以前より『助手が欲しい』と、愚痴をこぼされておりましたわ……宗介様さえよろしければ、お勤めになって頂けませんこと……?」
助手……。
「ぷっ……ははっ……う、うん、僕なんかで良ければ、よ、喜んで!」
顔を上げ、僕は満面の笑みで柚月葉ちゃんに返事を返した。
「あれ?そういば冬弥さんは?」
「ああ、兄様でしたら私が電話で家へと呼び戻しましたわ。宗介様に迫られ押し倒されそうなので、助けて。と……」
「え?……ええっ!?」
「その後に貴方がタクシーに乗り込むのを見届け、私もタクシーで後を追った。という訳ですわ……」
な、なんて妹なんだこの子は……いや、それどころか、この子は……。
「も、もしかして、冬弥さんの噂、数々の事件を解決したって……あれってまさか柚月葉ちゃんが全部!?」
そこまで僕が言うと、柚月葉ちゃんはくすりと妖艶な笑みを浮かべたかとおもうと、もはや枯れ木となった八重桜を見上げた。
「ノロマで変態で、どうしようもなく世話の焼ける。愛しい兄様ですから……ね」
愛しの……?兄妹として?それとも……。
思わず勘ぐっている僕をよそに、柚月葉ちゃんは話を続けた。
「それにしても見事な散り様でしたわ……何事も、散り際こそが美しいと、思いませんこと?宗介様……」
「散り際?」
「ええ……桜の花は、直ぐに散るからこそ美しいのです……人の命もまた同じ……散り際こそが儚く、そして美しいのですわ」
そう言って、柚月葉ちゃんは振り返り、僕に微笑みかけた。
どこからともなく降る桜の花弁が、柚月葉ちゃんへと舞い落ちる。
瞬間、その一枚を、柚月葉ちゃんは口からついと出した真っ赤な舌ですくい上げたかと思うと、それを口に含み、妖しげな笑みを浮かべて見せた。
妖艶な仕草に圧倒され、僕は何も言えずに固唾を呑んだ。
この子は一体……。
幾つもの交差する思いに僕は、体の奥底から凍りつくような感覚に、陥っていった。
「たっまや~」
花火大会の群衆から、威勢のいい声が上がった。
同時に、大きな火の玉が夜空へと打ち上げられる。
あれから月日が立ち、僕は大学生になった。
冬弥さんの助手として色々な体験をさせてもらったあの頃が懐かしい。
大学の都合で住む場所も代わり、あの二人とももう一年近く会っていない。
今頃どうしているのかな……。
時々そう思い出しては、一人孤独な夜に思い耽ってしまう。
今日だって、家に一人でいるのが何となく耐えられなくなり、近くで花火大会がある事を知ってここまで出向いたのだ。
歓声を横目に、僕は人集りから抜け出て、川沿いを一人とぼとぼと歩いた。
時折射し込む花火の閃光に、僕の孤独な影が明滅する。
本当に沢山の不思議な体験をした。
沢山の思い出が、そこにはあった。
沢山の……。
「お~い宗介」
「えっ……?」
聞い事のある声だった、いや、忘れようにも忘れられない声だ。
当たり前の様に、数分前に会ったばかりの様な、そんな着飾らない声……。
「冬弥……さん?」
顔を上げた先に、一年前と何も変わらない、冬弥さんの顔がそこにあった。
「おっす。花火大会なんか行くなよ、探すの大変だっただろうが」
出会って数秒で悪態をつかれてしまった。
でもそんな冬弥さんの顔は満開の笑顔だ。
「宗介様……」
傍らからの声、振り向くとそこには柚月葉ちゃんの姿が。
相変わらず美しい着物姿。
こっちも昔となんら変わりない。
いや、どちらかと言うと幼さが少し削られ、大人の色気が……。
などと見とれていると、
「おい!」
──ガツン
と、頭を冬弥さんにどつかれた。
シスコンは相変わらずのようだ。
「痛いな~いきなり殴らないでくださいよ~」
苦痛に歪む振りをし、僕は目に浮べる涙を誤魔化した。
「ほら、行くぞ助手」
「えっ?ええっ!?い、今なんて?」
「あん?お前は俺の助手だろ?今でっかい事件に巻き込まれてんだ、ボザっとしてないで手伝いやがれ」
冬弥さんはぶっきらぼうに言って手でついて来いとジェスチャーしてきた。
本当に、この人は相変わらずだ……。
冬弥さんは振り返り、再び花火会場へと歩き出す。
「ま、待ってくださいよ!」
「宗介様……」
柚月葉ちゃんに呼び止められ振り向く。
「人の命もまた、散り際こそが美しいと……私、そう申しましたわね……?」
覚えている。
僕が初めて柚月葉ちゃんと出会い、その力に圧倒され、彼女を恐ろしくさえ感じたあの日……。
「宗介様と巡り合い、一つ、思い直す事がございましたの……」
「思い直す?」
「ええ……人の散り際……されど、そこから足掻く人の姿もまた甘美なものだと……フフ……」
ぞくりとするような笑み……。
美しくも、そこには何か得体の知れないものを隠し持っている。
彼女は愉しんでいるのかもしれない。
人の生死を超えた先にあるものを……そしてそこで足掻こうとする僕と冬弥さんは、まさに彼女の……。
「おーい!何してんだお前ら!置いてくぞぉ!!」
冬弥さんがこちらに振り返り僕らを呼んでいる。
ハッとして
「は、はい!」
と返事を返し、僕は急いで冬弥さんの元へ駆け寄った。
「か~ぎや~!」
観衆からまたもや威勢のいい声が響いた。
同時に打ち上がる花火。
幻の様に鮮やかな花火が夜空一面に咲いた。
瞬間、僕は振り返った。
柚月葉ちゃんはまだ僕らをじっと見つめている。
花火が赤や緑と色彩を変える度、人々の瞳に宿る色は変化した。
が、柚月葉ちゃんの瞳に妖しく灯る、嬉々とした色だけは、何ものにも染まらぬまま、こちらをじっと、いつまでも見据えていた。

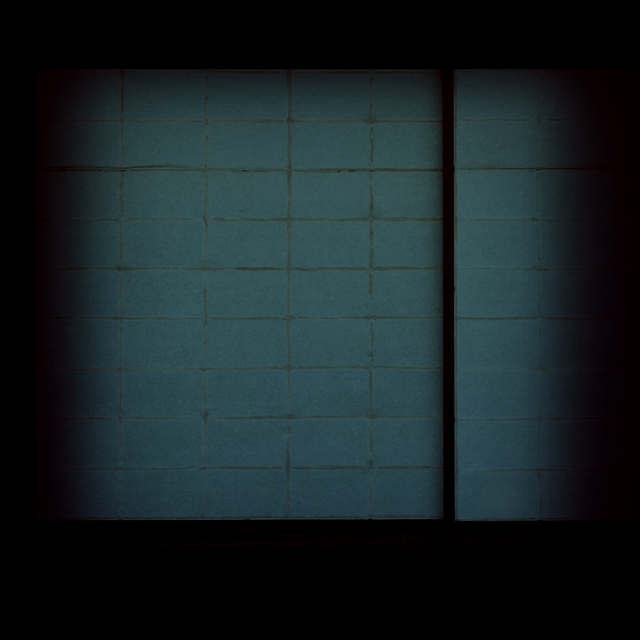



作者コオリノ
Twitterアカウント(狗甘マグマ@magma_maniac )様のイラストお題コラボでございます。
素敵なイラストレーターの方ございますので、是非Twitterで一度拝見してみてくださいませ。
夏真っ盛り、共に怪談界隈を盛り上げて参りましょう。