これは、私が当時少しの間努めて居た病院で体験した話です。
当時私は一般の病院で働いていたのですが、新しく新設されていた介護老健施設に異動する事になりました。
短期リハビリ型の入所者をメインにしていた所ですが、中には重度の患者さんも居て、リハビリというよりも、病院の空きベッド確保の為の処置と言った方が正しいでしょう。
そして私はその中でも、四階にある認知症病棟を担当する事になりました。
認知症というのは皆さんご存知かと思われますが、記憶などの情報をつなぎ合わせて適切に判断することができなくなっている状態を指します。
例えば、昨日の食事は何を食べたかをふと思い出せないことはあっても、何かを食べたことは覚えています。
落ち着いて記憶をたどると何を食べたか思い出せるでしょう。
しかし認知症が進行すると、食べたものだけでなく、食べたこと自体を忘れてしまったり、メニューを教えられても思い出せなくなります。
このように一般的な、もの忘れ、と違い認知症では日常生活にも支障が及びます。
私が受け持った部署は、まさにそういった患者さんが入所する所でした。
その中で個別に患者さんを受け持つ事が義務付けられており、私はOさんという七十四才の女性の方を、受け持つ事になりました。
Oさんは普段は大人しい性格の方なのですが、精神的に不安になると、酷い被害妄想に陥る事があったんです。
私もそのせいで、何度かOさんに暴力的被害を受けた事がありました。
そんなある日の事です。
夜勤で朝を迎えた私は、日勤の方と引き継ぎを行っていました。
すると同僚の看護婦から、
「Oさんがいない!」
と慌てた様子で告げられました。
その場に居た数人ですぐに捜索にあたりました。
認知症病棟は、入り口がオートロック式の電子解錠となっていて、扉のパスコードを入力するか、もしくはナースステーションの解錠ボタンで開けるしかありません。
ですが入所者のご家族などが帰りの際、認知症患者と知らず一緒に扉を出てしまう事があるんです。
特にOさんは、患者さんの中でもまだ七十代と若く姿勢もいいので、見た目からか入所者と見られない事が多々あったのです。
二十分程探し周った頃です。
「居たよOさん!」
同僚の看護婦の声に、私は急いで駆けつけました。
するとOさんは一階の隅の方にある、鉄製の扉の前で、
「呼んでる!呼んでるのよ~!」
と大きな声を張り上げ叫んでいました。
私が、
「何が?誰が呼んでるの?Oさん?」
彼女の肩を抱き寄せそう聞くとOさんは、
「ここよここ!呼んでるのよ私を!」
そう言って扉のドアノブを激しく掴みガチャガチャと鳴らしてみせたのです。
そこは、ポンプ室でした。
その後、Oさんは無事保護され、元いた部屋へと戻されました。
私はその時あった出来事を、カルテに記入していました。
するとOさんを一緒に探してくれた先輩のKさんが、何やら暗い面持ちで考え事をしているのに気が付いたんです。
いや、Kさんだけでなく、その場にいた他の先輩方もまた、暗い表情でした。
気にはなったですが、夜勤明け、しかも大騒動の後で、私の体と心は衰弱しきっていましたので、その時は何も聞かず仕事を優先しました。
それから数日たったある日、次の日が休みだった私は、深夜病院から呼び出しを受けました。
人手が足りないからと。
訳も聞かされないまま、私は病院に駆けつけました。
すると、そこには当直でもないのに婦長さんがいたんです。
そこで、私は事の内容を打ち明けられました。
Oさんが急死したと。
ショックでした。あれだけ元気だったはずのOさんがなぜ?
頭の中はそれで一杯でした。
Oさんの遺体はどこかと聞くと、婦長はこう答えました。
「遺体安置室よ……」
「遺体安置室!?」
私は驚いて婦長に聞き返しました。
私がなぜ驚いたのか、それはこの老健施設にそんな部屋があるなんて、一度も聞かされた事がなかったからです。
「そ、そんなのいつできたんですか?」
そう聞くと、
「実はねコオリノさん、あなたには話した事がないけれど、実は一年前、この施設が建てられて直ぐに、一人の入所者が亡くなったの……」
初耳でした。
普通は様態が悪くなれば、提携先の病院に緊急移送されます。
ですがOさんの様に急死を遂げた場合は、移送前に警察や医者、家族立会いなどが義務付けられています。
しかし急死といっても稀な例で、普段ならそんな事例は少ないのです。
「そ、それで?」
婦長の言葉がどこか含みを持っていた事に気が付いた私は、再び聞き直しました。
「以前亡くなった方、Sさんって言うんだけど、その方が亡くなった時、まだ遺体安置室なんてうちにはなかったのよ」
「えっ?じゃ、じゃあその時は、ご遺体はどうしたんですか?」
「その時はね、Sさん四人部屋だったの。他に部屋は空いてなくて、それでご家族に相談したのよ、地下にあるポンプ室、そこにまだ、何も置かれてない部屋があるって」
「ポンプ……室?」
私はなんだか嫌な予感がしました。頭の中に、あの時夜勤明けで見た、先輩達の暗い顔が浮かびます。
「元々そこは倉庫にする予定だったの。でもできたばかりの部屋は、綺麗で何もない場所だった……それに空調も効いていたから問題ないと思ったの」
「そ、それでそのSさんのご遺体を、ポンプ室の地下に……?」
「ええ、勿論、医者の診断と警察署への対応、それとご家族の同意を得てね……」
全て聞き終え、私は驚きの余り言葉を失いました。
ですが同時に、何か足元から這い上がるような、得体のしれないぞわぞわとした感覚に襲われたのです。
気づけば、私の肌は恐怖で粟立っていました。
震える口をゆっくりと開き尋ねました。
「O……Oさんが今安置されてる遺体安置室ってまさか……?」
「ええ……そのSさんが安置された、元倉庫だった場所よ」
陰鬱な顔で、婦長は私にそう言いました。
その言葉を聞いて、私の脳裏にあの声が蘇ります。
──呼んでる!呼んでるのよ!ここよここ!私を呼んでるのよ!!
以上が、私が病院を辞めたきっかけとなる体験談です。
今でも、あの老健施設には、ポンプ室の地下に遺体安置室があるそうです。
私が辞めた後も、元同僚からはこんな話を聞きます。
「たまに出るのよね、Oさんみたいな人。呼んでるって言ってさ、ポンプ室の前で叫んでるの。で、主任は、それ見たら数日の間、夜勤帯の連中は覚悟しとけって、若い子達には言い聞かせてるみたいよ」
以上です。

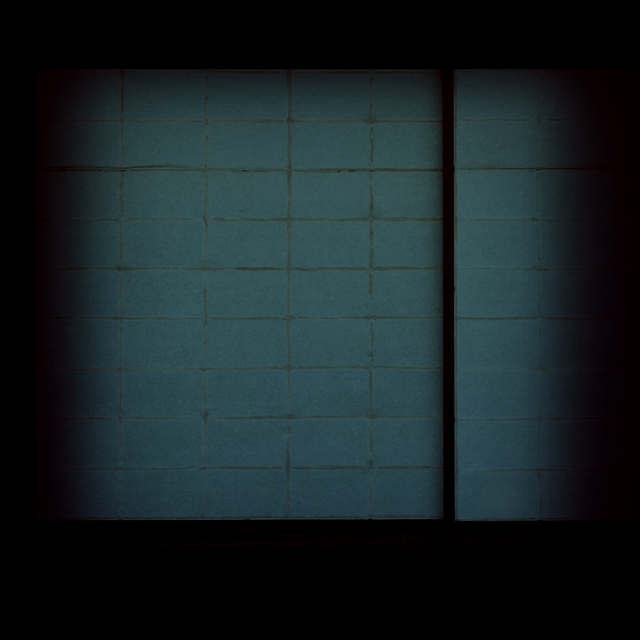



作者コオリノ
私コオリノが、以前勤めていた病院で体験したお話です。