もう一週間。
肝試し。
祟りを受けたんだ。
友達を含め、あの日肝試しに行くといった彼らは、学校に現れないまま、夏休みに突入していた。肝試しに行くと言ったのは、夏休みに入る一週間前のこと。七月初め、というと、早いように聞こえるかもしれないが、一応進学校を歌うこの学校ではほかの場所に比べてかなり早くに休みが始まる。そうして、自由な時間という名の講習を大量に入れることで、より受験に特化した勉強をさせるのだ。
彼らと連絡が取れなくなって、一週間。
夏期講習の真っ最中、高校ではその噂でもちきりになり、私は憂鬱な日々を過ごしている。家で留守番をしていて一緒に行かなかった、と答えた私に、クラスメイトは同情的だったし、行かなくてよかったねと声をかけてくれた。白いのは、だいぶうまくなった体育座りで、私の足元にいる。
あれから、白いのは、私が自分を大事だと言ったのがとても嬉しかったらしい。
ますます私にべったりになり、そして私は相変わらずの日常を送っている。
「田中、来てるか?」
「はい」
担任に呼ばれて、顔を上げる。
「ちょっと書類のことで話があるから来てくれるか」
「あ、分かりました」
書類、って何の話だろう。とは思ったが、なんだか含みのある話だと感づいて、頷く。じゃあね、とクラスメイトに別れを告げて、担任の後をついていった。
案内されたのは、校長室。周囲に人気がないことを確認して、担任が言う。
「……田中、行方不明になった5人と、最後にやり取りしていたってことだったな」
「見つかったんですか?」
「……正確に言うと、行方不明ですら、無い。事情があって、登校できないんだそうだ」
何かあったんだ。
やっぱり、あそこで、何かあったんだ。
それを確信して、私の顔が青ざめる。白いのは、守るように私に抱き着いている。
「原田の、お父さんが来ている。事情を、詳しく知っている人だ」
「由美子のお父さん」
「お前に会いたいというのは、本当らしいんだが……なんだかあまりに妙な気がしてな」
そっと囁くように、担任の境先生が私に言う。
頷いて、先生の後について部屋に入った。校長先生、お父さんと同じくらいの年のひとと、お坊さんだろうか。私が入ってきたほうを見て、お坊さんは浅く目を見開いている。白いのが、見えているらしい。白いのもそれを分かっているのか、お坊さんのほうをじっと見つめている。
ややあって、お坊さんはゆっくりと頭を下げた。
「突然、申し訳ございません。わたくし、上法寺に居ります者で、恵栄と申します」
丁寧な名乗りをしたお坊さん、恵栄さんの横。由美子の父親は、深々と頭を下げた。
「いつも、由美子から話を聞いています。由美子の父で、治正と言います」
「えっと、田中恵美、です」
お坊さんは涼やかな面立ちのまだ若そうな人で、白いのとのご対面衝撃も耐えきったらしい。
しかし、本当に、奇妙なことだった。由美子のお父さんと警察の人なら、まだわかる。なのに、お坊さんが一緒。しかもその状況を、校長先生も先生も、なぜか納得している。
ふと荒木教授の”そういうものになってしまった”という一言が、胸中をよぎった。
「田中の担任の境です。田中に用事とは、どういうことでしょうか」
間に入って、境先生が話を始めてくれた。由美子の父親は、迷うような様子で視線を落としてから、決意したように前を向き直る。
「うちの娘を含めて、現在登校できていない子供たちについて、お話をしにきました」
その言葉に、校長先生も、境先生も表情を硬くする。行方不明、というわけではないのだ、と親たちから連絡ははいっていたそうだけど、実際のところは詳しく知らなかったのだ。
「もしそれがほかの生徒にも影響することなら、学校として対策を講じる必要があります。教えていただけませんか」
「……状況としては、娘やその子らは、怪我をして動けない状態なんです」
由美子の父親曰く、由美子たち5人は、やはりあの、神社に行ったのだという。
あの神社は地元の人ですら、ほとんど寄り付かない。元々の地層のせいか、ひどく地盤が緩いのだそうだ。取り残されているのは、地盤が緩く重機が入れないため解体もできず、自然と倒壊するのを待っているらしい。ただ、もともとはそれ相応に手入れのあった神社のためなかなかそうもならず、こうして70年近く残ってしまったのだという。
これまでも、由美子たちのように肝試しをしにいく人はいたそうだ。
「しかし、特別、何も起こりません。いえ、起こるほうが、稀にございます。地盤が緩いとはいっても、重機に耐えられないのであって、人なら大丈夫と言ってよい場所です。そのため、事前にご神体等々は別の場所にお移ししまして、きちんと祀ってございます」
恵栄さんはそう言いきった。私が、白いのに抱き着かれていることも、分かっていての言葉らしい。困惑した面持ちの境先生や、校長先生。それとは対照的に、由美子の父親の顔は、強張るばかりだった。
私は、思わず尋ねた。
「5人とも、命に別状はないのです、か?」
「……今のところは」
今のところ。
この先は、不明。
「現状を端的に申し上げましょう。神社に行かれました5人は、何かに狙われております。寺の本堂にいる限りは身の安全は確保できておりますが、寺にたどり着くまでに、皆さま怪我をなされていますし、また恐ろしい思いをしたようです。その何かは分かりません、住職にも手掛かりは掴めていません、ただ皆さまここなら何も聞こえないと安心されて、本堂から出られなくなっていらっしゃいます」
そして、ようやく、人心地ついた由美子は、スマートフォンを開いた。ぎりぎり残された電池、目に飛び込んだメッセージ。それは、私からの、メッセージ。
「危険な場所らしいから近づくな、というそのメッセージを送りました貴女が、何か知っているのではないか。皆さま、そう思われておりまして」
「……そうだったん、ですね」
合点がいった。
用事があるからと行くのを断った私から、危険な場所だから近づくなというメッセージを貰ったら、疑いはかかる可能性は高い。もともと危険な場所だと知っていて、嘘をついたんじゃないかとか、そういうことを考えられているのかもしれない。だから、なのだろう。
由美子の父親は、顔をこわばらせて、私を見ている。
どうして娘を止めてくれなかった、とでも、言いたいのかもしれない。
「……しかし、私としては、合点がいきました。誰かに行くのを止められた、そうですね?」
恵栄さんに言われ、私は頷いた。
「あそこがどのような場所か、ご存知の方がいらっしゃったのですか」
「……懇意にさせていただいている、大学教授がいらっしゃって。その方に、危ないところだから、と」
「お名前をうかがってもよろしいですか」
少し迷ってから、私は荒木教授の名を出した。すると恵栄さんは、ああ、と納得がいった面持ちになる。
「知っております。民俗学の研究で、こちらにもいらっしゃいました。大変お詳しい方ですし、何かご存じだったのですね」
こくりと、私は頷く。
「なんの記録も残っていない場所だから危ないって、そういわれました。由来も、何が祀られていたかも、どんな場所だったかも、誰が持ち主の土地か、記録も残されていないって」
だから送ったんです。私は、続ける。
あのラインのメッセージを送ったのは、教授にそうやって止められたからだ、そう続けた。けれどそう続けてから、一つ引っかかる。それは目の前に一瞬、靄が現れたような引っ掛かりで、すぐさま消えていった。それ以上に私には、由美子に、そして同級生に疑われている状況というのが、恐ろしかった。
私に義務はない、私に理由はない、白いのに責任はない。だけど。きっと、この状況はそれを、許しはしない。
警察に頼ることができないらしい、という疑問点を、呑み込んでしまった校長先生と担任。私こそが手掛かりと信じるお坊さんと、友人の父親。何かが、ひどく、傾いでいる。
「貴女を縁に、あそこに何が居たかを、探りたい。協力していただけないでしょうか」
それを理解して、私は一つ、頷いた。
====
登校しない五人の生徒。そのことは、親たちの中にも広まっている。それもあって、私の口から寺へ行くことと、少し時間がかかるかもしれないことを告げられた両親は、もちろんのこと動揺したし、反対もした。
最後にやり取りをしていたものとして、私を頼りにそこに何があったかを、探る。
そんな突拍子もない、としか言えない話を聞いて不安がる、当たり前の反応をする両親。そこへ、俺が付いていきます、と付き添いを名乗り出たのは、荒瀬さんだった。
このために、あの傷んだ深紅の髪を黒く染めてくれた荒瀬さん。たとえそれがどんなに突拍子のない話でも、そんなことを馬鹿正直に学校まで来て話す大人が、どれだけいるだろうか。それだけ切羽詰まった状態に置かれている人が、しかもそれは私の友人。話を聞かされただけでも不安だろうに、ここで自分は行かないという選択肢をすることが、どんなに怖いことなのか。
「このまま疑われたままなのは、嫌なの」
校長室であったことを正直に伝えると、両親の顔がこわばった。
確かに、そんなことを校長室で話すような人じゃない、とお父さんが腕を組む。昔から知っているだけあって、母さんは荒瀬さんをそれなりに信頼している。ややあって、こくん、と頷いた。
「荒瀬君がついていくなら、安心は安心だわ。私たちが付いていくより、いいかもしれない」
お父さんが、びっくりした顔をして、母さんを見る。
「ついていかないつもりかい?」
「……蟲のことに巻き込まれたとき、私たちにはなすすべがなかった。でも、少なくとも、恵美や荒瀬君なら、危険を避けることはできる。私たちがへたなことをしてしまって被害を広げないように、私たちは私たちが見える範囲のことをすべきだわ。見えない世界、分からない世界におびえる訳じゃなく、私たちの領分でできることをしましょう」
少なくとも、そういう不思議に関して、恵美はもう一人前のようなものじゃない。母さんがそう言うのを、白いのがにこりと笑って聞いていた。
「そうだね。……私たちは、恵美を大人たちの言葉や手から守ることはできても、異常から守れるわけじゃない」
悔しそうにつぶやいたお父さんに、首を横に振る。これは、私の、わがままだ。これは、私の、エゴに近い、何かだ。
白いのという安全に頼った、私のわがままだ。
母さんはそれを察するように、微笑んだ。
「巻き込まれたことを避けることはできない。でも恵美は、蟲さえも受け止める強さがある。私は信じるわ」
「父さんも信じるよ。けれどね、逃げることも、避けることも、悪くはない。恵美に、救う義務も、関与する必要も、無いんだ」
「うん」
でも。
行かなくちゃいけない。見なくちゃいけない。
LINEの向こう側で、私が見なかったことを知らなくちゃいけない。避けることができた私は、たとえそこに飛び込む必要性がなかったとしても、でも。
「由美子に疑われたままなのは、嫌なの」
友達からの感情を、分からない何かより恐れたのは、悪いことじゃないはずだから。
====
上法寺、というその寺は、父さんの運転で2時間かかる県境の大きなお寺だった。山深いところに、まるで守られるように、ひっそりと建っているような印象を受けた。敷地面積はものすごく広いのに、全てが、なんというか、静かだった。山門が見えるまで、そこにあると気が付かなかったくらいだ。
私と荒瀬さんが後部座席に、白いのはなぜか、お父さんの隣である助手席に座っている。私から離れるなんて、滅多にあることじゃない。まるで、この車そのものを守るかのように、すとんと助手席に座っている。それだけでいつもと違うから、どきどきと胸がざわめいてならなかった。
「修行寺?」
「ええ。きちんとした、霊的なものへの目を養ったり、祈りを捧げることでそれに対する恐れを薄めるための寺だと。禅寺とも、また違うのでしょうね」
去っていく父さんの車に向けて、何かぱんぱんと手をたたく荒瀬さん。何してるんですか、と聞くと、縁を一時的に切った、と返された。
「怖れを薄めると、言ったでしょう。白いのが何時もと違う時点で、だいぶ、普段の場所よりは気を配ったほうがいいようです」
「……被害を受けてる人がいるってことですか?」
「何かしらに呪われたり、気に入られたり。そういった人が、己を強く持つことで、なんとかそこから意識をそらす。そうして得られる安寧も、あるということでしょうね」
荒瀬さんが歩き出す。私もそれに、ついていく。白いのは、不思議なほどに、しゃんとした歩き方をしていた。着流しも、なんだか綺麗に着こなしている。その複眼を黒々と輝かせて、私の手を握っている。
「……白いの、張り切ってるね」
「……ああ、そうですね」
そうだ、張り切っているのだ。どうしたんだろう、と思って見つめていると、不思議そうに首をかしげてくる。
「綺麗に歩けるようになったねぇ」
私が思わずそう言うと、んふふ、と言いたそうに、その口元がにっこりと笑った。とたん、いつもの白いのに戻って、ぐだぐだ私にもたれてすり寄ってくる。なんとなくその頭をなでると、余計嬉しそうになった。荒瀬さんは苦笑交じりだが、
「こうも見慣れると、なんだかかわいく思えてきますねぇ」
と前向きな発言をしてくれた。褒められたの、と首をかしげる白いのに、イイ子イイ子と頭を撫でてあげた。
寺の方から、恵栄さんがやってくる。
「お待ちしておりました。……そちらが」
「荒木教授に執事しております、荒瀬と言います。恵美さんとは懇意にさせていただいておりまして、ご両親の意向もあって今回は保護者としてまいりました」
「そうでしたか」
同じく見える人、と察したらしい。白いのがぐだぐだ私に絡んでいるのに、苦笑を漏らした恵栄さんは、どうぞ、と、ひときわ見事な建物の方を示した。
「皆さま、あちらにいらっしゃいます」
「立派な建物ですね……本堂、っていうやつですか?」
「あの中なら、平気、なのです」
どこか困ったように、恵栄さんが言う。
道すがらに話すのはよくないからと、恵栄さんが別の部屋へ案内してくれた。地元の銘菓だとかいう饅頭と、お茶が出される。私はそれが当たり前のように、半分に割って、包み紙に自分の分を、皿の上に白いのの分を乗せてあげる。白いのはそれを、食べる、という行為はしないが、私から何かを貰うこと自体が嬉しいことらしく、にこにこと目を細めてそれを眺めている。
恵栄さんにも白いのは見えているからか、興味深そうに呟かれた。
「驚きました……。このような状態のものにお目にかかるのは、初めてです」
その表現は気になったけれど、今は追及すべきじゃないだろう。私が何も言わなかったのを見て、恵栄さんは言葉を選ぶようにゆっくりと、話し始めた。
「……この寺は、お聞き及んでいると思いますが、修行の場です。世俗から離れるため、解脱を目指すためのみならず、心の安寧を得るために修行を積むものが集うております。世の中には、人の手では解決できぬ、何か別の法に基づく何かしらが、人と言う存在を蝕んでいくこともございます。
私は、生まれつきそういうものを目にし、同時に生家の成り立ちにより強い加護を頂けたこともあって、そうした方々の修行の手助けをしてまいりました。この土地そのものが、大変に強い土地の守護者が守っているために、御仏のご加護と合わせますと時として安らかな眠りの土地となります。別の法に蝕まれた方々が少しでも、心安らかに過ごせるようにすること。それが、私を含め、この寺に暮らす僧侶の役目であり……目的なのです。
恵美さんのように、何かに憑かれた、気に入られた、慕われたお方も、この寺には訪れます。しかしあなたのように、お互いに信頼関係に近いものを構築し、尚且つ程よい距離を探りながら、ともにあることができる方は、少なくとも私は初めてお会いいたしました。もっと年上の者なら、経験もあるかもしれません。
……ご友人の方々が寺に助けを求めていらっしゃったのは、恵美さんが友人にメッセージを送られた時間の、おおよそ5時間後です。親御さんたちが、皆さんを車に乗せられて、寺へとやってこられました。皆さま、何かにひどく怯えておられまして、しかし私どもとしてはそれも、そこまで気にすべきことがらではございませんでした。大体の方が、そうなのです。
認識できぬ者、警察や友人には対処できぬもの、もう何にも頼ることもできず、疲れ果ててこちらにまいりますから」
そこで一度言葉を切って、恵栄さんがお茶を一口呑み込んだ。
「彼らを一度、どのようなことがあったかお聞きするために、こういう部屋へとお招きしようとしたのです。ですが、そこで上役の者たちが止めました。すぐさま本堂へ、そう言われ、我々は断る道理もなかったので、本堂でお話をお聞きすることとなったのです。そうすると、皆さま途端に、ほっとした様子で、口々に”聞こえなくなった”と申されました」
聞こえなくなった。
皆には、何かが、聞こえていた。恵栄さんたちが分からなくて、うわやく、とかいう人たちは分かったもの。
差が出た、ということは、うわやくという人たちにはつながりがあって、恵栄さんたちにはつながりがなかったこと。
「ああ、上役、と言うのはですね。この寺を取り仕切る、上位の僧侶です。僧侶にも、修行や、その教えやあり方によって、位が生ずるのです。
経験値が違うからでしょうか、私どもには、分からなかった声。それを聞きつけて、本堂にお招きされたその上役たる甘英様の手腕に、彼らは助けられたのです。そこで彼らに、何があったのか、を聞きました。
あの日、貴女に連絡を取ったときには、彼らはすでに南光神社におられました。貴女が来ないことを確認してすぐ、神社の敷地内へ向かい、あたりを散策して最後に……神社へお参りをされたそうです。そこまでは、何も起きませんでした。しかし彼らが神社から出たときに、何かが起こったようです。具体的な話をできる方は、どなたもおられませんでした。皆さま、それを語りたくない、とおっしゃられていて、誰も聞き出せなかった」
怪訝そうに、荒瀬さんが尋ねる。
「誰も? では、何もわからないままなのですか」
「今のところは。しかし甘英様の見立てたところによると、どうやらその神社にいたものが、そのまま彼らに接触を図ってきたようですね」
私の脳裏に、荒木先生の話が蘇る。
廃神社、という存在はない。しかし、その土地に何かがある、と聞かれたとき、白いのはなんといったのか。そうだ、確か……。
「あの、いいですか?」
「どうぞ」
「私が、肝試しにいくのを止めたのは、白いのでした。そこには、神社の中ではなくて、土地に居ついているものがいて、それが私を行かせたくない理由だったんです」
そうだよね。と、視線で同意を求めると、こくん、と頷いた。それを見て、恵栄さんは思考に何か変化が起きたのか、顎に沿うように手を当てる。
「その土地、そのものですか?」
「白いのは……”とちゅうのもの”、と表現していました」
「……とちゅう」
難しい顔をした恵栄さんが、立ち上がる。と、外の方が騒がしい。どうやら本堂の方角らしくて、友人たちに何かあったんじゃないかと、私は思わずそわそわとしてしまう。
「こちらの部屋は、お二人の宿としてお使いいただいて大丈夫です。ただ、ご存知かとは思いますが」
「むやみに声には答えませんし、開けませんよ」
心得た様子の荒瀬さんに、私も頷く。恵栄さんはくれぐれも気を付けるよう言いおいて、部屋を出ていった。扉が閉まり、少しして。
ふと荒瀬さんが、焦ったように舌を打つ。
「どうしたんですか?」
「うまいこと、使われたかもしれませんね」
「えっ?」
その瞬間、勝手に、庭に面している障子が開いた。何もいない、私を庇うように荒瀬さんが抱き寄せてくる。心臓が、きーん、と小さくなる。
そういったものに遭遇して、初めてのことだった。
白いのが、私から離れた。勝手に開いた障子戸のほうへ、すたすたと歩いていく。何もいない方へ、何かが居ることを、分かっているように。
「なに、ほしいの?」
答えはない。しかしややあって、白いのは私を見た。いや、正確には、私の腕にある安物の腕時計を見た。
「えみ、それ、ちょうだい」
腕時計を恐る恐る外して、私は白いのへ差し出す。荒瀬さんが、食い入るように、その様子を見つめていた。
「これ、ほしい?」
私に見えないそれを、荒瀬さんは見ているらしい。しかめっ面で、外をにらんでいる。
「あげるけど、えみの、だから、だいじ、して」
はい。白いのが手渡したらしい、腕時計。それが、べしゃんっ、と音を立てて粉々にはじけ飛ぶ。あっ、と小さく私が声を上げたとたん。
白いのが、甲高い声を上げた。
「やくそく!!」
その瞬間だった。外に広がっていた黒い雨雲の中から、一筋の光が、
sound:9
地面を貫きそうな勢いで飛び込んでくる。雷だ、と思うより早く激しい衝撃音に私は、思わず蹲ってしまった。うわぁ、と誰かの悲鳴が聞こえて、そして。
音が消え去ったとき、光がなくなったとき、白いのが私を包むように抱きしめた。
「えみ、もう、へいきだよ」
優しい声に顔をあげる。いつもの真っ黒な、トンボの様な複眼。そのいつもの白いのを見て、私は。
私はひどく、安心、した。


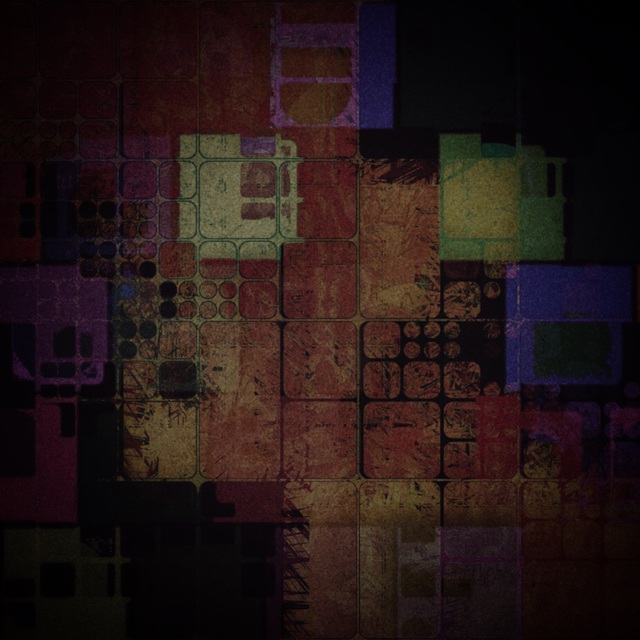
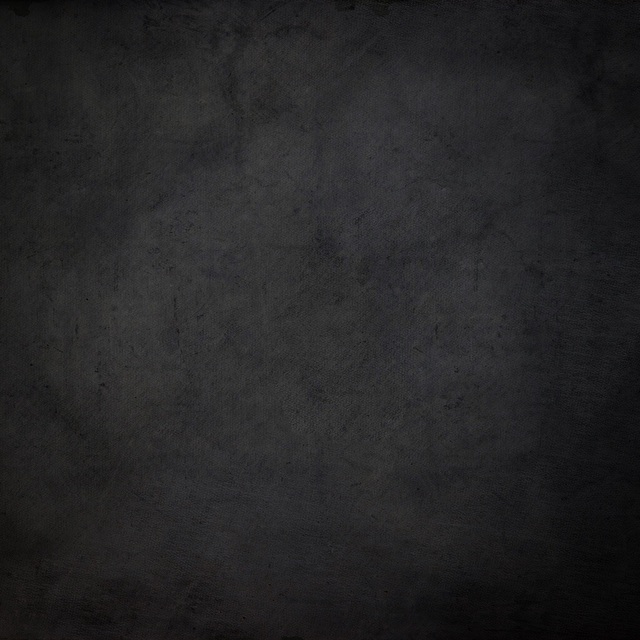
作者六角
お読みいただきありがとうございます。
たいっへんお久しぶりにこちらを更新。
ああ、どんどん長くなる……。