鎌倉にある、昔の佇まいを残すどこか懐かしい古い町並み。そこに俺の家はある。
腰をやらかした祖父さんが長期療養する事になり、その祖父さんが一人経営していた古本屋を、大学中退組みの俺が手伝う事になったのが半年前。
一応初めての客商売だったが、元々売り上げなんか気にしていない祖父さんだったから、やる方も気楽だった。
おかげで俺はこの、のんびりとした町で、ゆったりと商売をしている。
そんなある日の事だった。
ふと見上げた店先から見える山間に、妙な光の束を見つけた。時刻は午後六時。
町は淡い黄昏に包まれ、空には冴え冴えとした星が、澄んだ夜空に現れ始めていた。
こんな時間にあの山で……何か祭りでもあっただろうか?
ふと気になりながらも、
「まあいいか、」
そう呟くと、俺は夕飯の用意に取り掛かった。
七輪を軒先に用意し、冷蔵庫から秋刀魚を用意する。
店の前は静かなもので、地元住民しか殆ど通らない。
顔見知りも多く、外で魚を焼いたぐらいでああだこうだとならないのが、ここの良い所だ。
実に住みやすい町だとつくづく思う。
「おっ秋刀魚かい?良いねえ」
真向かいの織物屋の二階から、御主人のYさんが声を掛けてきた。
窓から顔を出すKさんに軽く会釈を返すと、笑いながら手を振り部屋へと戻って行った。
さてと、そろそろかな……そう思い秋刀魚をひっくり返した時だ。
「やあ」
夜風に紛れるようにして一人の若い男が、俺の前に姿を現した。そして網の上の秋刀魚を見ながら
「秋刀魚か、いいねえ、ちょと待っててくれたまえ」
そう言って男はさも当たり前のようにして、店の中へと足を運ぶ。
男の名はS。
俺がこの家を継いですぐに祖父さんが、
「二階の部屋、空いてるだろ?一人住まわせてやってくれ」
そう言って紹介してきた男が、俺と同い年で地元の大学に通う学生Sだった。
端整な顔をしており、初めて会った時は女かと勘違いしそうになった程だ。
黙っていればモテそうだが、あいにくと偏屈物で、本人曰く大学内では少し浮いた存在として煙たがられているらしい。
その原因の一つは、彼が大のオカルト好きだということ。
何度かSの部屋に入ったことはあるが、部屋の中はほとんどオカルト関係の本で埋め尽くされている。
一度電子書籍にしてみては?と持ちかけたが
「そうだねえ……でも、この紙媒体も、僕は捨てがたいのさ……」
と気の無い声で返事を返された。
とまあとにかく偏屈物だ。
「おまたせ。さて、これがないと始まらないだろう?」
店から出てきた着物姿のSが、手に純米吟醸とラベルを巻かれた酒を俺に見せて来た。
確かに。おかずに相性のいい純米酒は外せない。
その言葉に黙って頷き返すと、Sは店の前にある長椅子に腰掛け、二人分のグラスになみなみと酒を注いだ。
──チリンチリン……。
凛、とした風鈴の音色が響く。
気持ち良い夕暮れの風が、ふと、俺の前髪をサラサラと揺らした。
少し肌寒く感じる夏の夜。季節はもうすぐ、夏から秋に変わろうとしている。
俺とSは互いのグラスを合わせ乾杯をし、互いに無言のまま、酒を口に運んだ。
美味い。そう思い余韻に浸っていた時だった。
「A、君は逢魔が時という言葉を知ってるかい?」
唐突に言うS。
「何だ、一口でもう酔ったのか?」
Sはたまに、こうやって突然オカルトめいた事を口にする事があった。
それもこんな機嫌の良い時に限ってだ。
「はは、まあ聞きたまえよ。暮れ六つといってね、昔で言う酉の刻、現在の時刻だと、十七時~十八時の事を指すんだが、昔から魑魅魍魎、魔物が出る時刻だと言われてきたんだ」
魑魅魍魎……魔物?
最近やったスマホのゲームにそんなのが出てきた気がする。
決して現実めいた話ではない。
けれど、俺はSのこういった話は嫌いじゃなかった。
むしろSがきっかけで、こういった関係の話が好きになったと言っても、過言ではないからだ。
「魔物が闊歩する時間か、そういえばさっきから人っ子一人通らないな。これも逢魔が時ってやつのせいか?」
冗談めかしながらそう言うと、Sはくすっと小さく笑って見せた。
「かもね。特にこの町は、そういった事に近しい場所にあるから、何かと化かされる事もあるかもしれない」
Sが再びグラスを口に運ぶ。
ふと、先ほど見た山間の光の束に目をやった。
さっきとは少し形を変えている。
「なあS、あの提灯の灯り祭りだと思うんだけど、何か分かるか?」
俺が聞くと、Sは顔を上げ山間に視線を移した。
「ああ、あれは麓にある稲荷神社の祭りだよ」
「稲荷神社の祭り?」
「知らないのかい?そうか……なら少し長くなるが、こんな逸話があるんだ」
そう言って、Sはぽつりぽつりと語り出す。
「その昔、あの山の主でもあった一匹の化け狐が、一人の男に恋をした。けれど人と狐が添い遂げるなんて事はできない。思い余った狐は人間の女に化け、その男と添い遂げようとしたんだ。けれどふとしたきっかけで、男はそれが狐だと分かってしまった。男はその場から急いで逃げ出したが、悲しいことに、男は途中にあった崖から足を滑らせ、そのまま命を落としてしまったんだ。狐は鳴きに鳴いた。流れ出す涙は行く晩も止む事はなく、やがてその涙は山の川に流れ込み、麓にある村を襲った。村人達は困り果て、徳の高い僧にお願いして、狐と悲劇に見舞われた男の為にお堂を作り、弔いの祭りを開くようになったという……」
そこまで話して、Sはグラスの中の酒を一気に飲み干した。
「そんな祭りがあったのか。知らなかった……今度、行ってみようかな」
そう言って俺も酒を一気に飲み干す。
その時だった。
「どこに行きたいって?」
「えっ?」
突然、後ろから声を掛けられた。
思わず振り向くと、
「なんだい、一人でそんなとこに座って、月見酒かい?」
キョトン、とした顔で俺にそう言った人物は、
Sだった。着物ではなく、余所行きの普段着姿だ。
「ん?七輪?何か焼いてたの?」
Sが視線を落として言う。
ハッとして七輪を見るが、そこに秋刀魚はなかった。
「えっ?あれ?」
思わず声が上擦る。
「どうした、変な声まで出して、おかしな奴だな。ん?あれは……?」
Sが山間に目をやった。
つられて俺も視線を向けた。
「狐火……?いや、まさか……な」
「狐火?あ、あれは祭りじゃないのか?稲荷神社の?」
せかすように聞く俺に、Sは微笑した。
「稲荷神社?祭り?君は一体何を言ってるんだい?」
そう言って笑い出すSに、俺は唖然として何も言えなくなってしまった。
ふと、通りの向こうで何やらちらちらと動く影が見えた。
Sも気がついたらしく、同時に影の方を向いた。
「狐か……?珍しいな、山から下りてきたのかな?」
Sはそう言って首を捻った。
そう、影の正体は狐だった。
しかもよく見ると何か口にくわえている。
まさかあれは……?
「お、俺の、秋刀魚……?」
ようやく出た声に反応したのか、キツネはこちらにお辞儀でもするように頭を下げ、その場から駆け出しあっという間にいなくなってしまった。
「ふふ、なんだい、狐に化かされたような顔して、おや、これは?」
Sはそう言うと、長椅子に置いてあった見知らぬ竹筒を手に取った。
布のようなもので蓋がされており、Sはそれを取って鼻を鳴らして匂いを嗅ぐ。
「酒だな……それもかなり良質で良い酒のようだ」
「酒?」
「ああ、もしかしてさっきの狐と、この酒と秋刀魚を交換でもしたのかい?」
けらけらと愉快そうにSは言う。
「いや、その、何から話したらいいか……」
後ろ手に頭を掻きながら俺は首を捻ってこたえた。
「ははは、まあいいさ。夜は長い、これで一杯やりながら何があったか、ゆっくり聞かせてもらおうじゃないか」
そう言ってSは何やら上機嫌な様子だ。
対して俺は、狐につままれたような顔で、鎌倉山に浮かぶ狐火に、目を細めた……。

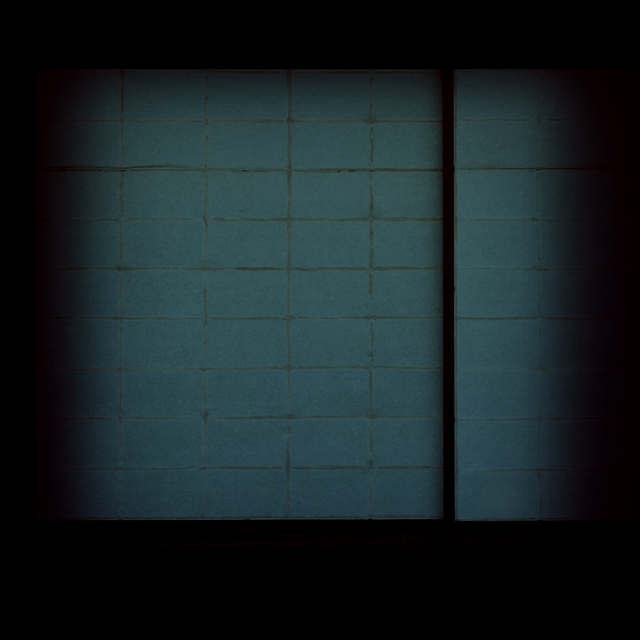



作者コオリノ
秋の夜長、もう少しだけ私の話にお付き合いくださいませ。
読んで雰囲気を感じてもらえれば、これ幸いです。
次回→「少女怪帰」http://kowabana.jp/stories/29796/edit