music:1
足元にぺったり折り曲がって、収納されているような白い何か。でも不思議と、私はそれに驚くだけだった。怖い、とは思わない。
異質。
異常。
奇怪。そう思うだけで、何故か恐怖だけが欠落している。
「恵美?」
急に足元を見つめて黙りこくった私に、母さんが話しかけてくる。
「い、色々あって、驚いちゃった」
努めて明るく笑ってみせると、母さんがほっとしたように笑顔を見せる。足元の白い何かは、首をやや傾げている。
「そうね、色々あったわね。……荒瀬君のところに着いたら、話すから。今は、眠りなさい」
「うん」
私が頷くと、足元の何かも頷く。まるで、母さんの言葉に同意するかのように、何度も。
私が目を閉じると、母さんがほっと安心したような息を漏らした。白い何かはそこに居るのに、脚に触れる感覚は空気にも等しい。何なのか分からないものに、人間は本能的な恐怖を抱くと言う。
けれど私には、何か、への恐怖は、少しもない。それがおかしい、それが不自然、それが奇妙。
これは、本当に、なんなのだろうか。
nextpage
その時、声が聞こえた。
「えみ」
慈しむように、守るように、柔らかく優しい声。この何かは、私をなんだと思っているのだろうか。その柔らかな声が引き金になって、意識が急に蕩けていく。
眠い。
そう思って数秒くらいで、車が止まる感覚に目を開く。本当に眠ってしまったらしく、あたりはうす暗い。その上、どれほど走ってきたのだろうか。山間の、のどかな、山林に面した場所に来ていた。
「恵美、よく寝れた?」
母さんが笑う。その問いかけに頷きながら起き上がり、やはり変わらずにいる白い何かと目が合う。白い何かは嬉しそうに笑い、車を降りる母さんの後に続くように、折りたたまれた姿のまま、べろんと転がった。軟体生物みたい、とか考えながら、私も車から降りる。
ふと視線を上げると、なかなかに立派な平屋が建っている。
wallpaper:536
表札には、『荒木』の文字。あれ、と思う。
「ねえ、荒瀬さんじゃないの?」
「彼はうちの客人だからねぇ」
私の疑問に答えたのは、先に降りていた父さんの横に立つ、温厚そうな丸眼鏡が似あう男性だった。なんだか、国語教師っぽい雰囲気で、白いシャツに緩めのスラックスをあわせている。
「はじめまして。荒木正治と言います。もう夜も更けましたし、さあ、中へ」
wallpaper:906
居心地の良い居間に通されて、荒木さん手ずから淹れた緑茶にほっと一息つく。昼間から色んな事があり過ぎて、喉の渇きすら忘れていた。
この男性、荒木さんは、元々とある国立大学の教授を務めていたという。定年退職してからはこの平屋を終の棲家として、荒木さんと同じ分野を学ぶ学生らが学びを兼ねて遊びにくることが出来る、市民活動のようなことを続けているのだそうだ。
荒瀬邦彦さんは、荒木さんのかつての教え子で、今は荒木さんの身の回りの世話をしながら、この平屋に蓄積された荒木さんの研究を整理している人らしい。今は私たちを迎えるべく、食材の買い出しに出ているのだそうだ。
御茶請けにどうぞ、と荒木さんが出してきた梅干し。それを一人でもぐもぐと食べながら、荒木さんは言う。
「荒瀬君から、話は聞いています。皆さん、八塚家の『白菊の儀』に参加されたそうで」
「儀式に呼ばれたのは全員です。でも、参加させられたのは、娘の恵美だけで……」
荒木さんは、どうやら、白菊の儀について知っているらしい。母さんが、驚いている。身を乗り出す様にして、尋ねた。
「荒木さんは、白菊の儀についてご存じなのですか?」
「荒瀬君から話は聞いている、それは貴方達が今日来ることだけではありません。何故、荒瀬君を貴方達が訪ねてくるのか。その理由も、聞かされているのです」
私は思わず、ちらりと、横の白い何かを見た。
どうやら正座を真似ようとして、失敗しているらしい。何度も挑戦して、バランスが取れずに後ろにひっくり返っている。動きだけはコミカルだが、真っ白な青年がべちんべちん後頭部を打ちつけつつ、痛がる様子もなく、ただ正座が出来ないことに悲しそうな顔をしている。
正直、どう反応していいのか、色々と困る。
そんな私の葛藤も知らず、荒木さんが話を進めた。
「白菊の儀は、八塚の姫を決める行事だと、聞いています。そうですか?」
「……ええ、そのとおりです」
母さんが頷く。荒木さんも、興味深そうに頷いた。
「八塚の姫が何なのか、までは私は知りません。ですが、八塚の姫になることが決まった少女がどんな末路をたどったのか。それは、知っています」
ようやく、正座の姿勢が取れたようだ。隣の白いのが、満足そうな笑みを浮かべる。そっちが気になってしかたないが、この話はきちんと聞かないと絶対にまずい。
荒木さんが語るところによる、八塚の姫。
姫、と言うだけあって、それは古くから例外なく女性であったそうだ。八塚の姫になるには、女性であること、20歳以下であること。この二つが、絶対条件になる。
姫と成った女性に、外見上の変化は無い。
精神に異常をきたした人もいたそうだけど、全体を見れば選ばれたからといって特別何か起きるわけでもない。
「ただしそれは、20歳の誕生日を迎えるまでのこと」
声のトーンが低くなる。荒木さんは研究者じみた透明な目で、五枚ほどの紙を見せた。そこには女性の名前、年齢、誕生日、そして死亡日時が記されている。ざっと数えても、50人はいるだろうか。
それらを見ていくうち、私はあることに気がついた。
誕生日と、死亡日時が、同じなのだ。
つまり、このリストに名を連ねている女性たち。彼女達は、皆、誕生日に死んでいる。
そのことに気がついた私が、荒木さんを見つめる。彼は頷いて、呟くように答えてくれた。
「みたとおりです。……20歳の誕生日を迎えたその日の夜。八塚の姫は、例外なく、亡くなっています」
ぞく、と背筋が粟立った。
「これは近代になって、戸籍というものがほぼ正確に記録されるようになってからの数字です。姫が居ない時期もありますが、彼女達はほぼ確実に、八塚家に関わりがある、八塚の名字を持つ女性たち。そして一人の例外もなく、20歳の誕生日を迎え、死んでいます」
母さんが、ため息を漏らす様に目を閉じた。唇が微かに動き、やっぱり、という文字を描く。
「田中、紗枝さん。八塚の姫とは、そういうものなのですね?」
荒木さんの質問に、母さんが頷いた。
「ええ。……八塚家の中では、八塚の姫は幸運の証にして、一族の繁栄の象徴なのだとされています。ですから、20歳で死ぬその日まで、彼女達は一族の姫君として、それは大切に守られるのです」
「なるほど。……ですが、何故、20歳で亡くなられるのでしょうか? 私には、それが疑問だった。そして、その疑問を私より強く持ったのが、荒瀬君だった」
荒瀬邦彦。
旧姓、八塚邦彦。
荒瀬さんは、先代当主、おじいちゃんの弟の孫にあたる。八塚家の分家でも、当主の血筋に最も近いのだそうだ。
そんな荒瀬さんには、妹がいた。生きていれば、今年で21歳になる、妹が。
「荒瀬君の妹さんは、八塚の姫と成った。そして、20歳の誕生日に、八塚家の屋敷で亡くなられた。……荒瀬君には、それが許せなかった」
「許せない?」
「ええ。……彼とその家族が、妹さんの死を知ったのは、すでに葬儀が済んだ後だったそうです」
私と父さんが、目を見開く。母さんは何かを理解したかのように、目を伏せた。
そうだ。母さんは、八塚家の本家の娘。
荒木さん以上に、内情を良く知る人。
そして、私にも、父さんにも、その沈黙を保ち続けてきた人。
「荒瀬君、そして私が貴女方をここに置くことを決めたのは、そういう理由でもあるのです。田中紗枝さん。本家の娘たる貴女が持つ情報は、荒瀬君にとって何よりの、妹さんが何故死んだのかという疑問の、その解決に結びつく……」
にっこりと、荒木さんが笑った。私の横で、また、白いのが正座に失敗する。
sound:16
話を遮るように玄関の方から聞こえた現代的な音に、一同揃って振り返った。とん、とん、と足音の後。荒木さんの下で学んでいたと言うから勝手に想像していた、荒瀬邦彦さんという存在のイメージをブチ壊す、痛んだ深紅の髪をかきあげて、男性がぬうっと部屋に入ってきた。
両手にぶら下げたエコバックが、実に似あわない。
「ああ、来てたんですか」
そして、三度目の裏切り。声だけ聞いたら好青年だ、この人。
「おかえり、荒瀬君」
「色々買ってきたので、最悪籠城しましょう。……はじめまして、荒瀬邦彦です」
斬新な、奇怪な、エキセントリックな、うーん。
コスプレでもしているのかな、この人。
ともかく。私の目の前に現われたのは、深紅に染めたド派手な長髪に、渋い茶鼠色の着物。夏らしく透けた黒い羽織とエコバック姿の青年だった。
とりあえず、出会ったことすらないタイプの人だとは、嫌でも分かる。そんな荒瀬さんは、母さんを、父さんを、そして最後に私を見て、二度ほど目を瞬かせた。
「……えっ」
驚いたような声を上げた彼の視線は、私の横に向いている。私の横で、正座を諦めて膝を抱えて座る、白い何かに向いている。
ちょっと困っている、いや完全に困っている。そんな様子の荒瀬さんからは、予想していたことが完全に裏切られた状態、という雰囲気が伝わってきた。
困惑しきった表情のまま、彼は努めて明るく告げる。
「とりあえず、夕飯用意してきますね」
逃げたな。
実に失礼な感想を抱く私の横、白い何かはぺたぺたと、左右に揺れている。
「驚かせましたね。外見はああですが、気のいい子ですよ」
荒木さんが朗らかに言うと、両親は戸惑いながらも頷いた。おそらく、先ほどの彼の反応が、気になっているのだろう。
私としても、非常に気になる。この白い何かがなんなのか分かれば、それに越したことは無い。
「彼のご飯は美味しいですよ」
そんな、どうでもよい様な良くない様な情報を付け加え、荒木さんは笑う。
この人が一番凄いのかもしれない。そんなことを、ふと考えた。
つづく
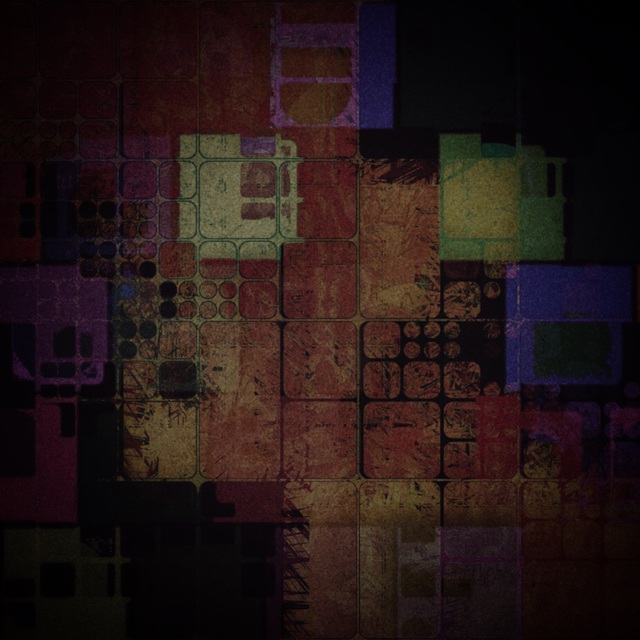

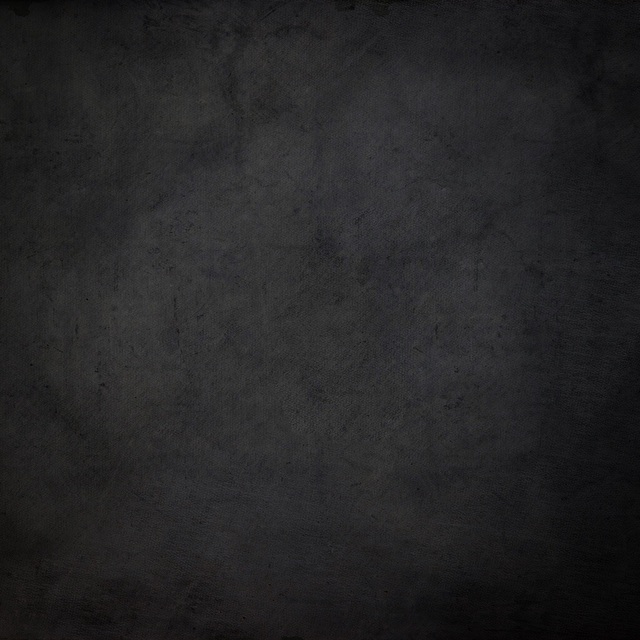
作者六角
どうも。
もうちょっと続きます。