music:4
wallpaper:1101
幼子はまだ死に近く、神様に近い所にいると言う。そんな古い記憶の話。
母方の祖父は私が2才の頃に亡くなった。
心臓疾患だったように思う。
祖父はお舟の船長さんで、超が付くほどの御人好しだったらしく、私が小さい頃はよく「ああ、その健康枕はお爺さんが騙されてさ……」とか「全く、あの爺さんはーーー」と愚痴しか聞いたことがなく、次第に祖父の話は禁句の様な扱いだったのを覚えている。
けれど、どんなに悪く聞かされても、どんなに家族思いでなかったエピソードを聞いても、私は祖父が好きだった。
私と祖父は多分そんなに触れあったことはなかった様な気がするが、祖父と道路の縁石で遊んだ事やお歌を歌った事、おトイレを手伝ってくれた事、頭を撫でられた記憶は強烈に残っている。
そんな祖父は前述の通り、私が2才の時に亡くなった。
病院で臨終を伝えられ、葬儀の用意をし、遺体が自宅へ運ばれてきた時の記憶もちゃんとある。
死んだと言うことが何なのかも大体は理解していた。
私は祖父の死に対し、これは悲しい事ではなくて「あの安心する所に帰るんだから、良い事だ」と思っていた。
なので葬式の間は気が向けば踊りさえした。
祖父の遺体には全く興味がなかった。
母に見るように言われても、亡骸と言う言葉があるように、遺体にはなんの本質も見い出せずに、ただ眺めるだけだった。
弔問客には死を悼む事さえ分からぬ幼子と涙を誘ったのかもしれない。
今にして思えば、2才の女の子がどれだけ達観していたのかと思うし、とても変だ。
けれど当時は『あの暖かくて満たされていて何の心配もない安心する』世界があると何となく知っていた様な気がする。優しい暗闇のイメージで。
なんであんな考えをしていたのか、歳をとる毎に不思議に思いながらも、徐々に死とはとても悲しい物だと言う考え方に変わり、小学生になる頃には周りと変わらなくなった。
ただ、不意にあの頃を思い出すと、死後の世界は優しいんじゃないかな、と思える。
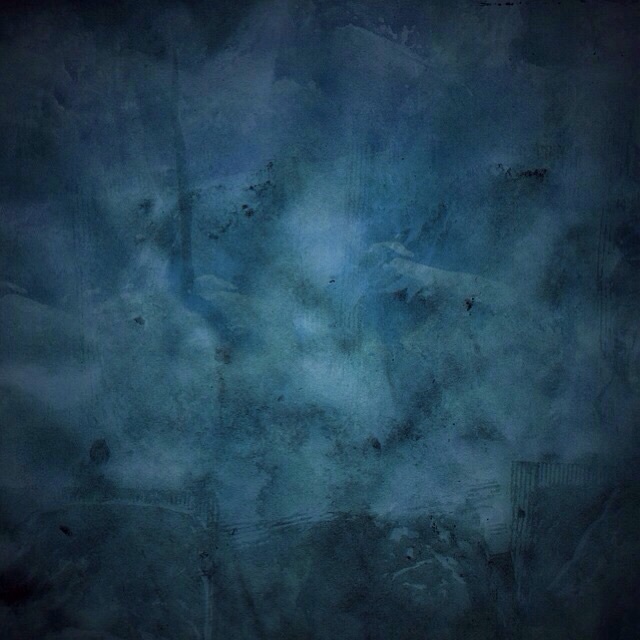

作者お藤
この話は怖くありません。
実体験の殆どは、人に話しても怖くなくなります。
この話も、勘違いと言われたらそれまでですが、一時の暇潰しになれば幸いです。