窓辺で白いカーテンが揺れている。
今日は生憎の天気だが、風は湿っておらずそこそこ気持ちがいい。
揺れるカーテンの隙間から見えるキャベツ畑を見ながら、多岐絵はパリフレーバーティーを啜っている。
多岐絵はこの時間が大好きだ。
日本で青々と育ったキャベツを見ながら、芳醇な香りのするパリフレーバーティーを啜る、このミスマッチ感がたまらなく好きだった。
「…チッ。 熱いわね」
そう言って手に持っていたカップを睨みつけ、いつもよりキャベツ畑に夢中になりすぎてお湯を沸騰させすぎた事を後悔した。
なぜ、いつもより夢中になってしまったのか。
それは、自分に死期が迫っているからだ。
はじめは死期なんてものは悟っていなかった。
家族のいない多岐絵は、自分の大好きなキャベツ畑で生涯を終えたいと思い、九州に広い土地を購入してキャベツ畑の真ん中に家を設けた。
だが、皮肉にも多岐絵は、そのキャベツ畑で死期を悟ることになった。
「最期に飲むお紅茶がこんな出来なんて…」
多岐絵はそう呟きながらカップからまたキャベツ畑に目を移した。
間もなく、多岐絵は死ぬ。
自分でもそれはよく理解していた。
どうして自分で理解できたのか、それはキャベツ畑に最近までなかったあるものを見たからだった。
それは、初めはなんなのか多岐絵にも全くわからなかった。キャベツ畑の遠くの方で、人間の動きを早送りにしたような奇妙な動きをしながらゆっくり近づいてくる人型のような存在があった。
はっきりは見えなかったその存在が日に日に近づいてくるにつれ、 "あぁ…そうなのか" と悟った。
さらに多岐絵との距離が近くなったその存在は、既に窓の横に立ってウネウネと動いていた。
だが多岐絵は恐怖は全く感じなかった。
いつもは日に日に近づいてくるが、今日はどうやら急ぎ足のようだ。恐らく今日、多岐絵の一生は終わるだろう。
詳細に見えるようになったその存在を見て、多岐絵は微笑み、その存在にカップを掲げ最期にこう言った。
「乾杯」
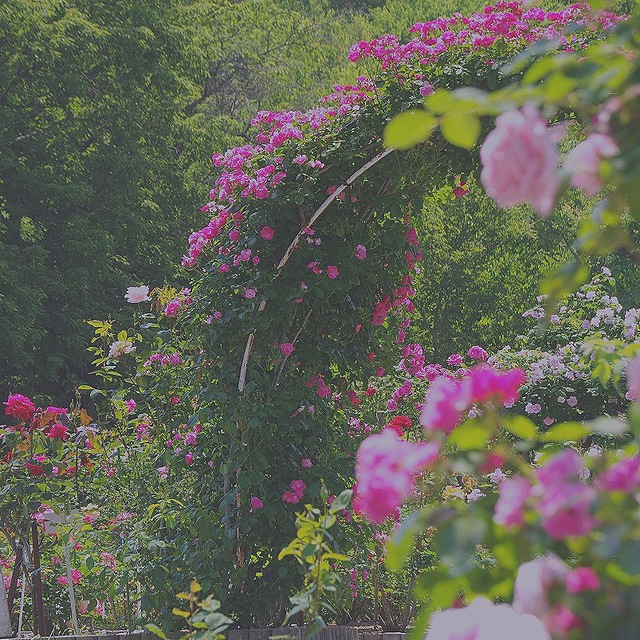
作者あざらし