私は梅雨が嫌いだ……。
鬱陶しく付き纏う雨雲も、街を包むようにして降りしきる霧雨も、肌にまとわりつく不快で湿ったこの空気も……。
梅雨は……嫌いだ。
これは、そんな私が高校二年の梅雨に体験した話。
天気予報の微妙な数値にタカをくくっていた私は、その日見事に傘を忘れ、なくなくびしょ濡れ確定で家路へとついた。
部屋干ししてあったタオルを掴むと、腰まで伸びた黒髪を一気に拭き流す。
「はぁ」
湿った空気が部屋の中を漂う。
私はそれを解放させるかのように庭へと通じる窓を開けた。
縁側に腰を下ろし外に目をやる。
植えたばかりの花壇に、紫の色を鮮明に濃くした紫陽花が開いていた。
そして、その上に一匹の小さな雨蛙が、雨宿りでもしているかのように座っていた。
「よ、よう」
「えっ……?」
突然聴こえた声に慌てて周囲を見渡す。
誰も居ない。
今家にいるのは私一人だし、家の前を通る人影も、隣家の人影もない。
あるのは私と、一匹の雨蛙……。
「ゴホン……よ、よう」
言葉に合わせ口をパクパクと開く雨蛙……。
「う、嘘……!?」
声は……蛙から聴こえた。
動悸が一気に激しくなるのを感じながらも、私は一瞬首を傾げた。
何処か気になる点があったのだ。
声だ、聞き覚えのある懐かしい声。
「いや……ま、まあ驚くのは無理ないよな……蛙が喋るとかまず有り得ないし、いきなりそれを信じろとかも言えないしな。実は俺、」
「お兄ちゃんでしょ?」
「えっ?ええっ!?そ、そうだけど、えっ?あ、いやなんで分かったの?ていうか反応薄くない?」
「いや、だってそんな回りくどい喋り方するのお兄ちゃんくらいしかいないし、あと声で分かるし」
「うわっ今時のJK反応薄っ、な、何かこうもっと驚くとかあるだろ、蛙だぞ蛙?」
「いや、見れば分かるし、蛙強調されても困るし」
「うっわ、今時のJKテンション低っ、怖いわぁ……」
蛙が兄の声で喚いている。
何故私はこんなに落ち着いているのだろう。
有り得ない状況、想像だにしない出来事なのに、何故かそれを受け入れている私。
だがそれは、私とこの兄との関係に原因があるのかもしれない。
兄は二年前、交通事故で亡くなった。
学校ではいじめられっ子で、不登校で引きこもりだった兄。
ある日ようやく学校へと向かうも、こんな梅雨の雨の日に、交通事故にあって亡くなってしまった。
「あっ!何?もしかしてもう直ぐ自分の二周忌だから出てきたとか、そういうベタな話なわけ?」
「べ、ベタ言うな!ああ最近のJK本当に冷めてて怖いわぁ、お兄ちゃん本当に悲しいわぁ……」
「蛙のくせに兄貴ぶるなし……」
「うっせ……」
「あっ」
私が一声発すると同時に、蛙は拗ねたようにピョンとその場から飛び跳ね、何処かへと行ってしまった。
「何だったの今の……」
しばらくその場で待ってみたが、兄の声で喋る蛙はもうその場に姿を表さなかった。
シャワーを浴び部屋に戻った後、この事を誰かに話そうか迷ったがやめておいた。
頭のおかしな奴だと笑われるのがオチだからだ。
それでもやはり兄の事が気になった。
なぜ突然現れたのか……なぜ蛙なのか……。
次の日も、私は家に帰り着くと直ぐに庭の様子を伺いに行った。
あれはただの幻だったんじゃないか、まだ疑う余地はあると……が、私の予想を覆すように、昨日の蛙はあの紫陽花の上にさも当たり前の様に鎮座していた。
「よ、よう」
私を見るなり唐突に喋り出す蛙、もとい兄。
「よっ……」
軽く返事を返す。
何かもう一々驚くのも癪に障る。
長い沈黙が続いたが、お互いにどちらからともなくくだらない話を始め、終始他愛もない話だけをした。
何で?どうして?といった質問は、なぜかできなかった。
次の日も、そのまた次の日も、私とカエ……兄は、どうでもいい思い出話に花を咲かせた。
そんなある日の事、
「なあ覚えてるか?」
私が縁側で首を傾げると、兄はこちらを二三度見て再び口を開いた。
「俺がその……死んだ日……」
「覚えてるよ……忘れるわけ……ないじゃん」
全ての灯りが消えた、そんな真っ暗な日だったと記憶している。
父も、母も、そして私も、家族全員が無気力に、そして無感情になるまで泣き疲れていたあの日の出来事。
「ごめんな……俺ドジでさ……道端に蛙見つけてさ、お前引かれるぞって思って、捕まえて逃がしてやろうとしたら、後ろから車来ちゃって……」
「はあ?それで車に跳ねられたの?バカじゃないの!?」
本当にバカだ。
一瞬たがあの日流した涙を返して欲しいとさえ思った。
「ば、バカなのは知ってるよ。そりゃお前は頭良いしさ、顔も良いし、友達も多いし……お前と比べて俺なんかその……バカで引きこもりだしさ……」
「何自分で言って自分で落ち込んでんのよ」
頭をもたげるようにする蛙の仕草がどことなく可愛い。
思わず指でつっつきたくなる。
「う、うっせえな……と、ともかくだ、お前が俺なんかより良くできた妹で、何の心配もいらないっては分かってるんだけどさ、い、一応兄としては気になるんだよ、そ、その妹の事が……」
「な、何がよ、何の心配よ」
やめて……。
「何のって……」
言わないでお兄ちゃん……。
兄が何を言おうとしているのか、それはある程度予想が着いていた。
いや、そもそもそれが嫌で、今日まで他愛もない話ではぐらかしてきたのかもしれない。
「お前のせいじゃないって……事だよ……」
その瞬間、兄のその一言で、私は遠い過去に封じ込めた記憶が、頭の隅々まで駆け巡るのを感じた。
堪えきれず目に熱いものが込み上げてくる。
視界が滲み俯くと、両の膝にポツポツと大きな雫が落ちた。
「何がよ!私のせいじゃない!あれば私のせいなの!私のせいでお兄ちゃんは……」
続く言葉が出ない。
出そうとしても喉が焼ききれるように熱く感じて上手く話せない。
あの日、私は兄に言った。
ーそんなんだからいじめられるんだよ!ママもパパも私だって、皆困って皆悩んでるんだからね!いい加減にしてよお兄ちゃん!!
あれは……そう、こんな憂鬱な梅雨の日だった。
機嫌が悪く、私は朝登校前にそう言って兄に八つ当たりしてしまったのだ。
兄はその後昼頃になってから、突然母に学校へ行くと言って、以来帰らぬ人となってしまった。
「私の……私のせいなんだよ……お兄……ちゃん」
救いようのないバカで浅はかな私の言葉が、兄を傷つけ、そして死に追いやったのだ。
「えっ?」
ピトリ、と膝に何か柔らかい感触がした。
両手で覆う指の隙間から、僅かに膝に視線を移すと、そこには蛙、もとい兄の姿があった。
顔を上げ、私の顔を覗き込むようにしてこちらを見ている。
「いいかよく聞け、本当にお前のせいじゃないんだ」
兄の慰めの言葉が、耳障りな雨音と共に響く。
聞きたくなかった。
「聞きたく……」
「聞け!頼むから聞いてくれ!」
口をパクパクと開く兄。
水かきのついた両手を必死にバタバタとさせている。
「あの日、確かにお前に言われて俺は落ち込んだよ……でも母さんから聞かされたんだ……」
「ママから……?」
「うん……お前が来年、うちの高校受けるって……同じ高校なら、傍で俺の事守ってやれるからって、母さんにお前がそう言ったんだって聞かされてさ」
それは、兄の事で悩み落ち込んでいた母に、私が掛けた言葉だ。
「俺さ、それ母さんに聞かされてさ、いてもたってもいられなくって……お前に少しでも恥かかせないように少しづつでも学校に行こうって思えてさ……」
「お兄……ちゃん」
「だからなんて言うか、お前のせいじゃないんだよ、あれは俺の意思だ、俺の意思で学校へ行ったんだ、ま、まあ最後の登校になっちゃったけどな……はは」
「はは、じゃないよバカ兄貴……」
「ああ……うん、そうだな面目ない」
蛙の小さな手が、大きな自分の頭をすりすりと掻いている。
「さてと、ぼちぼち行くかな」
「えっ?い、行くって、お兄ちゃん?」
「雨、止んじゃうからな……」
膝に乗っていた兄はそう言い残すと、くるりと方向転換し、そのまま紫陽花のある花壇へと飛び跳ねた。
「お兄ちゃん!!」
慌てて紫陽花に駆け寄り花壇を見回すが、蛙の姿はもう何処にもない。
「お兄……ちゃん……」
降りしきる雨。
着衣に染みた雨水が全身に伝わり、僅かな重みを感じる。
梅雨は嫌いだ……こんな悲しい雨も……。
頬を伝う雫が、雨水となって流れ落ちていく。全て洗い流してくれれば楽なのに、そう思いながら、締め付けられそうな心臓を両手でギュッと押し込めた。
その夜、テレビで気象予報士が、全国的に梅雨明けだと、明快なトークで報じた。
あの日以来、兄は……蛙は姿を現さなかった。
そして、あれから一年。
高校三年生になった私は、ある日、微妙な天気予報の数値を当てにし見事に裏切られ、ずぶ濡れのまま家路へと着いた。
部屋干ししていたタオルを掴むと、前にもこんな事があったなあと思いながら、肩まである黒髪を拭き流す。
庭へと通じる窓を開け、縁側に腰を下ろした。
街を包む静寂な雨。
人の声も、車の音さえも、今はただ、降りしきる雨音が全てを塗り潰しているようだった。
私は梅雨が嫌いだ。 憂鬱な気持ちになるから。
ふと紫陽花に目をやると、一匹の雨蛙が目に止まった。
蛙がのそりと此方に振り向く。
「よく降るねぇ」
聞き覚えのある声。
「そう……だね」
私は驚きもせず何故かそう返事を返し、思わず苦笑いを零した。
梅雨は……きら……ううん、もう、大丈夫。

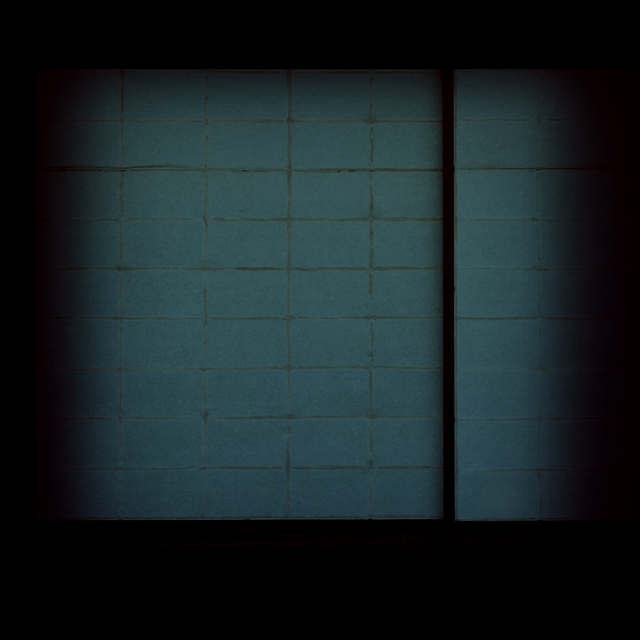



作者コオリノ