世界には多種多様な憑依現象がある。
その内日本では大まかに分けて三種類。
動物や人間の霊魂。精霊や神といったものが突発的に憑依するものと、特定の家筋が故意的にそれらを使役し憑依させるものや、その家筋に生まれたがために、知らぬ間に憑き物筋として生きる事を余儀なくされた物、この三つに分類される。
特に三つ目に関しては、この日本の格差社会と根強い関係性を持っている。
憑き物筋とは言わば中世ヨーロッパで流行った魔女裁判のようなものだ。
対象に対し、何かしらの理由を付け排除する。
特に女性はその立場からか標的にされやすい。
また、古くから存在する同和問題や村八分といったものも、これに該当するだろう。
さて、憑き物筋といえば、特に有名なのが犬神信仰と言われるものだ。
その多くは西日本を中心に近世に出現した。
大分県、島根県、四国北東から高知一帯なので根強く見られる傾向がある。
今回、研究の一環として行っているこのフィールドワークでは、憑き物筋と一般的社会との密接的な関係性を改めて認識し調査するものであり……。
「教授!真昼教授!!」
突然名前を呼ばれ、俺はハッとしてノートPCの画面から目を離した。
「あれ、椿……」
そう呼んだ先には、眉間に皺を寄せ俺を非難するかのような目で見つめる女の子が一人。
吉永 椿。
大学の生徒で、つまり教授である俺の教え子だ。
民俗学部のフィールドワークで、俺は付き人として椿と共にここ、大分県に来ていた。
来ていたはずなのだが……。
「椿……じゃないですよ教授!」
さっきよりも輪をかけて怒鳴りつけてくる椿。
怒っている理由は一つ。
実は、俺たちは今、遭難中真っ只中だったりする。
「何こんな時に呑気にパソコン何か弄ってるんですか!」
「何を言ってるんだ、こんな時だからこそ落ち着いてレポートをだな」
「変人ぷりをアピールするのは研究だけにして下さい!」
「変人ってお前なあ、その言い方は酷くないか?」
「変人に変人って言って何が悪いんですか!民俗学の研究と称して自分のオカルト好きを満喫するために、可愛い生徒を大学の単位で釣ってこんな所まで連れ回し、あまつさえ道に迷ったあ!?」
「いや、それはまあそうなんだが……ていうか今さり気なく自分の事可愛いとか言ったか?」
「だって可愛いでしょ?これでも大学じゃ結構人気あるんですからね」
ドヤと言わんばかりに腕組みし鼻を鳴らす椿。
なんだかんだ言いつつも、まだ余裕がありそうだ。
「はいはい……」
「あっ何その態度!そんなんだから四十にもなるのに独身なんですよ、ふん!」
「ほっといてくれ……それより少し近くを散策してみよう。携帯の電波が届く場所に出られればみっけもんだ」
「そう……ですね。下手に動くのもアレですけど、流石に私もこんな山奥で一晩明かすのは嫌ですし。ていうか本当にこんな山奥にいるんですか?その、神谷 静子って人」
「正確には神谷 静子の痕跡だ。本人はとうに亡くなってるはずだからな。調べ回ってやっと掴んだ情報だから間違いはないと思うんだが……」
今回のフィールドワークの目的は、憑き物筋、犬神の研究なのだが、この犬神に関して、俺はある人物をここ、大分県で探していた。
神谷 静子。
その昔、大分県速見郡山香町で、ある事件が起きた。
とある巫女が、犬神の霊薬だと称して、犬の生首に群がる蛆を乾燥させ、それを煎じたものを町の人間に売り付けたという。
巫女は逮捕されたが、憲兵の厳しい取り締まりにあい、その短い人生の幕を牢屋で閉じてしまった哀れな女性。
その女性の名前が、神谷 静子だ。
一見してこの女性はただの詐欺師だと言われているが、この神谷 静子の事を調べるうちに、俺はある興味深い情報を掴んだ。
そしてある一つの可能性を導き出したのだ。
神谷 静子は本物の霊能者であり、本物の狗神筋だったのではないか……と。
それを確かめる為にも、まずはこの森から脱出しなければならないが。
「さてと、」
「あ、あぁぁっ……!?」
バックパックを担ぎ直し立ち上がった時だった。
先に立ったはずの椿が突然震えるような驚きの声を上げた。
何事かと立ち尽くす椿の元へ向かう。
「なんだ変な声出して、蛇でも居た……」
そこまで言いかけて、俺は言葉を失ってしまった。
「グルルルルッ……」
身の毛もよだつような呻き声。
葉や小枝をベキベキト押し退け、木々の間から、1メートルはゆうに超える黒い巨体が姿を現した。
熊だ。
「嘘だ……ろ……」
九州には熊は居ない。
2001年には、この地方で絶滅宣言が出されたはずだ。
然し、今俺と椿の目の前にいるのは間違いなく熊だ。
しかも明らかに威嚇体勢を取っているのが分かる。
「き、教……授……!」
「しっ……!静かにしろ……!刺激するな……」
俺は震える足を何とか前に出し、椿を庇うような形で構えた。
こんな事をしても何にも解決しない事は分かりきっているが、せめて教え子である椿を逃がす事くらいは出来るかもしれない。
俺は椿に顔を寄せ、小声で話しかけた。
「椿……合図したら逃げろ……」
「そんな……教授は……!?」
「俺も逃げる、けどもしダメな時はお前が誰か見つけて助けを呼んでくれ……」
「で、でもそんな……」
「グルルルッ……!」
──ドスンッ
熊が前のめりになり、四足歩行へと切り替えた。
俺はそれを見るなり無我夢中で叫んだ。
「逃げろっ!!」
──ドンッ
椿を押し退けるように突き飛ばし、熊の注意を引く。
「きゃあぁぁぁっ!!」
泣き叫ぶようにして走り去る椿。
振り返ると熊は勢い良く俺へと迫り、今にも飛び交ってきそうな状況だった。
足が動かない。それどころか腰が砕けるようにして全身の力が抜け、俺はその場にへたりこんでしまった。
巨体が俺に暗い影を落とす。
俺目掛けて振り下ろされる熊の鋭利な尖抓が、スローモーションのように見えた。
衝動的に目を瞑る。
振り下ろされた爪は俺の肉を裂き!骨すら砕く……はずだった。
おかしい。
体感的にはもうやられてもおかしくない。
然し痛みも何も無く、状況は変わらぬまま。
まるで時が止まったかのような感覚。
必死に瞑った眼をうっすらと開け、視界が開けたその時だった。
信じられない光景が、俺の目の前で繰り広げられていた。
「そ、そんなっ……!?」
熊の前に立ちはだかる人影。
しかもよく見ると少女の姿。
絹糸のような真っ白な髪をたなびかせる少女が、熊の腕を掴み、その動きを制している。
少女の腕は血管が浮き出るほどの筋肉が盛り上がっており、とてもじゃないが現実とは思えない姿。
だが実際に今目の前で、そんな非現実的な事が正に起こっている。
思考が追いつかない。
頭の中はパニック寸前で、それ以上俺は言葉を発せなかった。
「グアッ!」
硬直した状況に痺れを切らしたのか、熊は掴まれた腕を振りほどき距離をとった。
その瞬間だった。
「ワオォォォォンッ!!」
顔を上げると同時に、少女が叫ぶ。
天を衝くような咆哮。
木々がざわめき、強風が森全体を震わすように吹いた。
瞬時に、熊が怯えるように辺りを見回す。
そして急に背を向け、元から来た方向へと実を翻しその場を立ち去って行った。
助かったのだろうか……。
そう思いながら少女を見ると、それに気が付いたのか、少女もまた振り返り俺を見下ろした。
綺麗に整った、何処と無くあどけなさの残る顔。
一目見て引き締まった身体をしているが、不思議な事に先程熊を止めた時のような筋肉隆々の姿ではなかった。
見間違いか……?
いよ、そもそも熊とやり合うこと自体が人間離れしている。
それにさっきの、狼を思わせるような鳴き声は……。
「教授!教授!!」
声の方に振り向くと、顔をクシャクシャにさせながら此方に走りよる椿の姿が見えた。
「良かった……無事……か、」
椿の無事な姿を確認した瞬間だった。
極度の緊張、生死の境、そここら解放された衝動からか、糸が切れたかのように俺の体は倒れ天を仰いだ。
視界が薄れる中、泣きじゃくる椿の顔と、真昼の陽光に照らされた、少女の凍てつくような冷たい眼差しが、微かに見えた……。
瞼の上に、微かな明かりを感じた。
重い瞼を開くと、木造の天井に、古い電灯が目に映った。
外ではない、家の中……?
「教授!教授!?」
耳元で聞き慣れた声がする。
顔を横にすると、枕元で俺の顔を心配そうに覗き込む椿の姿があった。
そしてその隣には見知らぬお婆さんの姿もあった。
「ほらなあ、気を失ってただけだから心配いらんよ、もう大丈夫」
お婆さんは椿の肩に軽く手を置いて言った。
「は、はい」
椿もそれに落ち着いたのか、目橋の先を指で何度か拭う。
俺は上半身だけ起こすと、お婆さんに向かって深々と頭を下げた。
「すみません、どうも助けて貰ったみたいで、失礼ですが貴女は?私は東京の大学で、」
「ああ、ええよええよ、あんたの事はこのお嬢ちゃんから聞いとるから、わしは杉原 元子、この民宿の女将をしとるもんだ」
「杉原……元子さん、助けて頂きありがとうございます。何とお礼を言えば……」
「助けたのはわしじゃない、わしはハクが連れてきたあんたらをこの宿で休ませただけよ」
「ハク?」
「教授を助けてくれた女の子ですよ」
元子さんの隣に居た椿が、なぜか得意そうな顔で言った。
「何でドヤ顔なんだお前……まあいい……あの子はハクって名前なのか……」
白く雪のような肌、氷のような冷たい眼差し……人とは思えない美しさすら感じた。
ハク……。
「名前は珀明(ハクメイ)……わしらはハクと呼んどるけどな」
「珀……明。あの、そのハクって子は?」
「あの子は普段、森の中に住んどる、滅多な事じゃこの辺りの集落にも姿を現さんが、アンタをおぶって家に来た時は本当に驚いたよ」
「そう……ですか、何から何まで助けて貰ったんですね……その子にお礼がしたいのですが、どうにか会えませんか?」
「あ、ハクちゃんなら後でまたここに来るそうですよ!」
「何だって?本当かい、あのハクが……?」
「はい!ハクちゃんに私からお礼がしたいって言ったら後で顔を出すって」
「はあ、たまげたもんだね。あの子は誰とも関わろうとしないし、ましてや森から出る事も滅多にないってのに」
元子さんが驚く顔を見せ椿の顔をまじまじと見つめた。
椿の人懐っこさには常日頃から目を見張るものがある。
どんな相手の懐にも飛び込んで、いつの間にか仲良くなっている。
大学でも顔が広く、常に輪の中心にいるが、そのくせ人当たりもよく人気者だ。
実は今回このフィールドワークに連れて来たのも、聞きこみ調査等の事も考えての抜擢だった。
「まあいいさ、ハクが来るまでには時間があるんだろ?その間に晩飯の用意でもしとくから、風呂でも浸かってゆっくりするとええ、どうせこの辺りじゃ泊まる場所なんて、このボロ民宿ぐらいしかありゃせんからの。なあに、人間屋根と飯、畳一畳ありゃあ十分よ、でも料金はちゃんと頂くけどね、あははは」
軽快な笑い声で立ち上がり、元子さんが部屋から出て行く。
その様子に呆気に取られ、俺と椿はしばし放心したまま互いの顔を見合せた。
元子さんが言う程、民宿はそれ程ボロ屋ではなかった。
確かに古い木造であちこち傷んで来てはいるが、埃も垢もない、こじんまりとはしているがよく手が行き届いている雰囲気のある良い宿だ。
風呂も露天風呂とはいかないが、天然掛け流しの湯は旅の疲れを癒し、何より地元の山菜と魚をメインにした夕食は、その辺の旅館にも負けない程絶品だった。
椿なんかお代わり三杯目で元子さんに呆れられ、俺が太るぞとつっ込むと、勿論素足で躊躇なく蹴られた。
凶暴な教え子である。
あらかたの事を済ませ、俺と椿はまた後で訪れると言った命の恩人、ハクを部屋で待っていた。
「そう言えば椿、お前あのハクって子と何を話したんだ?」
「ああ、教授情けない顔して気絶してましたもんね」
「情けないは余計だ、ふん」
テーブルの湯呑みを手に取りわざと音を立ててすする。
「まあでも、私を庇ってくれた時はその……カッコよかったかなあって……」
「ん?」
「ああいや!なな、なんでもないです!あははは……そうそうハクちゃんの事ですよね?」
「あ、ああ」
「あの時私が教授って呼んだでしょ?」
「ああ……気を失う瞬間、確かに呼んでたな」
「そしたらそのハクちゃんが、そいつの名前教授って言うのか?って聞いてきたんですよ」
「俺の名前がか?」
「そうなんです。最初こんな時に冗談なのかなって思ったんですけど、どうも本気で聞いてきてたみたいなので、教授っていうのは学校の先生みたいなものだよって説明してあげたんですよ。そしたら先生って言葉に凄く反応して、字は読めるのか!?字は教えたりするのか!?って興奮気味に聞いてきたんです」
「興奮気味に?」
「ええ、それはもう大興奮でしたよ。で、ハクちゃんがそのまま教授を担ぎ出して安全な場所まで送ってやるって言うんで、私がなにかお礼をしたいって伝えたら……ううん……」
「どうした?」
そこまで言って椿は神妙な顔で唸り出した。
「それがですよ、ハクちゃん私に何て言ったと思います?」
椿が俺の鼻先まで顔を近付け鼻息荒く聞いてきた。
「お前が興奮してどうする……何て言ってきたんだ?」
「そいつが起きたら字を教えてくれ!」
そう言って椿は俺に向かって人差し指を突き付けてきた。
「お、俺が!?ハクって子に字を?」
驚きの声をあげると、椿はそれに大きく頷く。
その時だった。
──ドタドタドタドタッ
階下から階段を駆け上がる足音が迫ってきたかと思うと、
──ガラッ!
木造の扉が勢い良く開かれた、そして、
「先生!字を教えてくれ!!」
「えっ……ええっ!?」
そこには、昼間俺達を熊から助けてくれたあの少女、珀明の姿があった。
──ゴーンッ
古めかしい時計の針が、丁度真上を指しながら重い鐘の音を響かせた。
時刻は午前零時。
窓の外には、真っ暗な夜闇に大きな月が顔を出している。
「すぅぅ……おかわりぃ……」
なぜか俺の布団の上で寝言を呟く椿。
その横には、先程からテーブルに置かれたノートに、必死にかじりつくようにして鉛筆を走らせる少女が一人。
珀明だ。
何でこうなっているのか、自分でも未だに現状が把握出来ていない。
いや、分かってはいるがなぜこうなったと疑問だらけなのだ。
俺達は昼間、彼女に命を救われた。
そのお礼に、なぜか彼女は俺に字を教えろと言ってきた。
勿論彼女は命の恩人だ。
断るわけなどない。
ないのだが……なぜ俺は彼女に平仮名を懇切丁寧に教えているのか。
確かにあどけなさはあるものの、少なくとも彼女の歳は十七、十八といったところ。
そんな歳の子が字を教えて欲しいというのは明らかにおかしい。
この国には義務教育というものがあるのだ。
文字なんて今時小学校に上がる前に習うものだろう。
「なあ先生、これであってるか?」
ハクはノートを手に取ると、それを俺の前に拡げ見せてきた。
「あ、ああ、あってるよ」
蛇がのたうつ様な文字で書かれてはいるが、最初に教えた頃よりは上手くなっている。
たった三時間でここまで覚えられれば、文字の習得に時間は掛からなそうだ。
と言ってもあくまで平仮名だけだが……。
「そ、そうか」
嬉しそうに言うハクだが、何か様子が変だ。
もしかして……褒めてもらいたいのか?
「あっ……おほんっ……うん、良くできてる、凄いな珀明ちゃんは」
「うん!あっハクでいいぞ先生!」
ハクは強く返事を返すと、満足そうに顔をほころばせた。
こうして見ると本当に普通の女の子だ。
だが、俺が昼間見たハクは明らかに人ならざるものだった。
常識的に考えても成立しない異常さが、俺の脳裏に焼き付いて離れない。
彼女は一体……。
「なあ先生」
「えっ?ああ、なんだ?」
「明日も来ていいか?」
「明日?あ、ああ、午前中は調査があるけど、午後になったらここに戻るから、それからなら大丈夫だが、」
「そうか!良かった……また明日も教えてくれ」
「あ、ああ、分かった。帰るのか?」
「うん」
「途中まで送って行こう」
「いいよ、森の中暗いし、夜は危険だ」
ハクなら大丈夫なのかと聞きたかったがやめておいた。
「森にははいらないよ、夜風にちょっと当たりたいし、本当に途中までだ」
そうやって苦笑いをこぼすと、ハクは、
「分かった」
と言って頷いた。
「あれえ、帰るのハクちゃん?」
椿だ。寝惚けた声で目を擦りながらハクを見ている。
「ああ、また明日来るぞ」
「そっかあ、私まだハクちゃんと遊んでないのにい……あっそうだ」
「?」
椿が隅に置いていたポシェットの中を漁りだした。
「あったあった、ハクちゃん後ろ向いて」
そう言ってポシェットから何やら赤い紐のような物を取り出す。
「ん?こうか?」
ハクが言われた通り後ろを向くと、椿は慣れた手つきでハクの長い髪をまとめあげ、赤い紐で結び始めた。
「はい、どうだ!」
言いながら椿は俺に向かって大袈裟に手を広げてきた。
「おおっ」
どうやら赤い紐はリボンだったようだ。
ハクの絹糸の様に綺麗な白髪に、赤いリボンはよく映えている。
「これ……いいな!」
ハクは気に入ったのか、頭を振ってリボンをヒラヒラさせ嬉しそうに笑っている。
「良かった気に入ってもら……えて……」
そこまで言うと、椿は電池が切れた玩具のように、またもや布団の上に崩れ落ちた。
「つ、椿?」
心配そうにハクが椿の顔を覗き込む。
「大丈夫だよ、疲れて寝てるだけだ」
そう言ってハクにクスリと笑って見せた。
俺は椿に掛け布団を被せ部屋の明かりを落とすと、ハクと共に宿を出た。
街灯や民家のあかりもなく、あるのは月明かりだけ。
車や人の声すらない静寂な田舎道を、俺とハクは並んで歩いた。
「なあハク」
「何だ先生?」
「昼間俺達を助けてくれた時……あれは一体……?」
「あれって?」
「いや、ほら、熊から守ってくれただろ?」
「ああ、そうだな」
「そうだなって、いや普通は人間が相手にできるもんじゃないだろ?ましてやハクみたいな女の子が」
「そうなのか?まあ俺は強いしな」
「いや、そうじゃなくてだな……」
ダメだ、話が噛み合わない。
ハクにとっては自分の強さが基準なのだろう。
「ほらアレだ、熊と戦っていた時遠吠えみたいなのあげてただろ?あれだって」
「この山も熊のやつほとんどいなくなっちゃったしな、できれば傷付けたくなかったんだ、だから威嚇して追い返した」
「い、威嚇って……」
ハクは当たり前のように言ってのける。
困った。
これじゃ何を聞いても埒が明かない気がする。
質問を変えた方がいいかもしれない。
「そう言えばハクは何で森に住んでるんだ?家族は?家はあるのか?」
「家はあるぞ、でも家族はいない」
「いない?いないって一緒に暮らしてないのか?学校とか」
「学校!?」
突然ハクの目が爛々と輝いた様に見えた。
学校という単語に反応したのだろうか。
「あ、ああ、学校通ってないのか?」
「この山の麓に小さな学校があるんだ。そこで小さい子供たちが先生に勉強を教わってた」
「麓に……?」
麓に学校なんてあっだろうか……?
「うん、俺、毎日通ってたんだ、先生の言ってること難しかったけど、そこで色々学んだんだ……字は教えて貰えなかったけど」
通っている?でも字は教えて貰えないって、一体どんな教育してるんだその学校。
「そ、それで両親は?」
釈然としないまま、俺は質問を変えた。
「お父さんは死んだ。お母さんは一度会ったたきりだ……」
「会った事が?今は?離れて暮らしてるのか?」
「うん……」
ハクの表情に僅かに影が落ちた。
離れて暮らしているのなら寂しいだろう。
不躾な質問だったようだ。
「ああ、す、すまん変な事ばかり聞いて!あ、明日も一緒に勉強しような!」
「ぷっ……あはははは」
吹きこぼすようにお腹を抱え笑い出すハク。
「えっ?な、何?」
「先生は変な奴だな、何でそこで謝るんだ?」
「いや、何でってそりゃ、変な質問しちゃったしな……」
「変な質問?ううん……まあいいや、ここまででいいぞ先生」
気が付くと、周りに民家はなく、目の前には鬱蒼とした森が広がっていた。
「あ、ああ、一人で大丈夫か?」
「うん、慣れてるからな。先生も気を付けて帰れ」
「お、おう……」
年下の女の子にタメ口で話をされるのは如何なものかとも思ったが、なぜだかそれがハクだと嫌に感じなかった。
むしろ純粋なハクの気持ちが表れているようで、俺には心地よくすら感じられた。
ハクは俺に向かって二三度手を振ると、森の方へと駆け出し、暗闇に吸い込まれるようにして消えていった。
「本当に大丈夫か……?」
こんな時間にこの暗さで、あんな年頃の女の子が一人で……そう考えるだけでも寒気がするものだが、やはり俺にはあの昼間見たハクの姿が目に焼き付いて離れない。
あれは……本当に人間なのか……。
そんな馬鹿げた妄想ですら、現実味を帯びてくる。
そう思うと、今はこの真っ暗闇の森よりも、ハクの得体の知れない何かに、俺は少しだけ恐怖を感じていた。
顔を上げると、眩い光に軽い眩暈を覚えた。
雲一つない、夜空に浮かぶ満点の星々。
そして澄み切った夜空に冴え冴えとした心月が、妖しく煌々と輝いていた。
翌朝、俺と椿は予定通りフィールドワークを開始した。
正直ハクの事が気になったが、一応仕事でもあるため来た以上はやらねばならない。
一旦街まで戻ると、レンタカーを借りて犬神に関しての痕跡調査を進めた。
憑き物筋が実際に居たとされる村落や、犬神進行と関わりを持つ神社等を周り、俺達は一旦、大分にある大学で、民俗学の研究をしている知り合いと情報交換をする事となった。
「久しぶりだな真昼、元気してたか?」
「ぼちぼちな、幸村こそ元気そうで何よりだ。足の調子は?」
そう言って俺は幸村の左足に目をやった。
「ああ、まあ日常生活を送る分には不自由してないよ」
そう言って幸村はごつい手を俺に向けて差し出してきた。
俺はその手を握り数年ぶりの握手を交わす。
幸村 浩一。
大学時代の旧友で、同じ民俗学を研究する仲間だ。
「まあとりあえず座れよ、珈琲でも飲むか?」
「おっ悪いな」
幸村にそう促され俺達は研究室のソファーに腰掛けた。
「ほれ」
席を立った幸村が、戻ってくるなり俺と椿に缶コーヒーを手渡してきた。
「って珈琲入れに行ったんじゃないのかよ……」
「文句言うなよ、それに俺が入れるより確実にこっちの方が美味い。それで、そちらさんは?」
「も、申し遅れました、私、吉永 椿って言います!よろしくお願いします!」
「へえ、お前には勿体ないな真昼……」
「あほか……俺の教え子だ」
幸村がニヤついた顔でこちらを見てくる。
分かってて聞いてきたなこいつ……。
「そ、そそそうですよ!私と教授はそんなんじゃありません!だ、大体何で私がこんな中年男とその……け、結婚なんてしなきゃならないんですか!?」
そう言ってなぜか顔を真っ赤にして幸村に抗議する椿。
「落ち着け椿、誰も結婚してるなんて言ってないだろ、幸村の冗談だよ」
「へっ?」
「ははははっ、面白い嬢ちゃんだな、良い助手を持ったじゃないか」
「まあな、そこは否定しない」
「ちょっと、私何かバカにされてませんか?」
「褒めてんだよ」
そう言って肩をすくめてみせると、椿は俺を睨みつけてきた。
「むうぅぅ」
「ははっ、本当に仲が良いなお前ら」
幸村は膝を叩いて笑っている。
「あのな……まあいい、ところでこの前電話で話した件なんだが」
「ん?ああ、あの爺さんの話か?」
「爺さん?」
椿が俺に聞き直す。
「ああ。お前にも話しただろ。神谷 静子。その彼女の情報をくれた人物がいてな……」
遡る事三ヶ月前、俺はとあるフォーラムで憑き物筋の論文を発表した。
その際に、会場に来ていたある老人と出会ったのだ。
老人の名は、影井 清隆。
何でも若い頃に、俺と同じ様に憑き物筋の研究をしていた事があるらしく、興味が湧いて声を掛けたと本人は言っていた。
時代が時代で研究そのものは続けられなかったが、歳をとり財を成し、余った時間をもう一度この研究に使いたいと影井氏は語っていた。
まあこう言ってはなんだが、所謂金持ちの道楽って奴だろう。
会場では互いに名刺交換だけを済ませ、軽く話した後に別れたのだが、その夜、俺の元に影井氏から一通のダイレクトメールが届いた。
それが、件の人物、神谷 静子の情報だったのだ。
神谷 静子は四国で代々犬神落としを生業とする家計に産まれた。
犬神落としとは、四国で有名な賢見神社が、病気平癒、家内安全を祈る御祈祷の事を指す。
一方犬神憑きとは、動物霊を使役し、対象者に取り憑く事により災いをもたらすと言った、言わば呪いという行為だ。
当時は第二次世界大戦終戦間近で、日本全体を暗い影が覆っていた。
人々は欺瞞に充ちた世界で、明日を生きることに必死な時代だったのだ。
呪いとは、そんな暗い影から生まれる、言わば病の様なもので、人々の心を蝕んでいた。
そんな中、神谷 静子は幼少の頃から犬神落としの才を発揮し、類まれなる巫女として、名を馳せていたという。
齢十五という若さで神殿の勤番を勤めていたとか。
勤番とは、神社の管理や参詣者を世話する係の事らしいが、当時では病気治療にも一役買っていたそうだ。
そんな彼女だが、何故か二十歳を過ぎた頃に、四国を出てここ大分に流れ着いている。
理由は不明だが、元々優れた力を持っていたとされる静子は、ここ大分の地でも、霊験あらたかな犬神落としとして重宝された。
静子の名は瞬く間に近隣へと広まり、やがて遠方からわざわざ静子の元を訪れる者もいたという。
次第に人々は、静子そのものを神格化し崇め始めた。
が、そんなある日、事件は起きた。
神谷 静子が、霊感商法の詐欺事件の首謀者として逮捕されたのだ。
腐った犬の首に沸いた蛆を、すり潰し乾燥させ、それを犬神の霊薬と称して町で売り捌いたという。
神谷 静子は町の憲兵に逮捕され、厳しい取り締まりの上に、獄中でその短い生涯を閉じたという。
当時の憲兵での取り調べでは、そうやって命を失くしたものは少なくないと聞く。
「それなんだがな真昼」
幸村が少し神妙な顔で此方を見た。
「何だ?」
「こっちでも色々調べてみたんだが、どうも事件を起こしたのは神谷 静子では無いらしいんだ」
「静子じゃない?だったら捕まったのは?」
「いや、捕まったのは神谷 静子で間違いはない。だが事件を起こしたのは、当時神谷 静子の信者とされていた男達だったらしい」
「ちょっと待って、じゃあ神谷 静子は濡れ衣を着せられて捕まったって事か?」
「ああ、どうもそうらしいな。おお方神谷 静子の名を使って一儲けしようと企てたんだろ。彼女が獄中で死んだのも、事件の事を否認し続けたのが原因だとされているしな」
なんてこった……その力を必要とされながらも、最後はその必要としていた村人達に裏切られ、悲運な最後を辿ったのか。
そう思うと、人として単純な怒りが湧いてくる。
本当にやるせない事件だ。
「それともう二つ程、気になる話がある……」
「もう二つ?」
不意に発した幸村の言葉に、俺は顔を上げた。
「神谷 静子が獄中で死んだ後、彼女の呪いを恐れた信者が、遺体を丁重に埋葬しようと引取りに行ったそうなんだが」
「そこで何かあったのか?」
幸村は缶の珈琲を手に取り一気に飲み干すと、その缶を片手でグシャリと握り潰して言った。
「遺体を預かっていた問所が突然発火し、その場にいた憲兵と遺体もろとも焼失してしまったそうだ。しかも亡くなった憲兵は、その時神谷 静子を拷問した連中だったらしい」
愕然とした。
それじゃあ正に村人達が言っていた
「神谷 静子の呪い……か」
「かもな……」
幸村が返事をしながら缶をゴミ箱へと放り投げた。
──ガコン
と音を立て、缶は箱の中へと落ちる。
「もう一つは……?」
段々と聞く度に陰惨な話になってきた。
隣にいる椿も、さっきから肩を落とし俯いたままだ。
「これが一番の謎なんだが……神谷 静子には子供がいたらしいぞ」
「子供!?」
思わず前のめりになり、持っていた缶珈琲が床に落ちそうになった。
慌てて掴みテーブルに置くと、俺は改めて幸村に尋ねた。
「子供って、本当に静子の子か?性別は?名前は?父親は誰なんだ?」
「おいおいそこまでは俺も分からんよ、お前俺を探偵か何かと勘違いしてないか?」
幸村がお手上げのポーズで首を横に振る。
「あ、いや悪い、つい興奮して……でもまさか子供が……生きてれば八十幾つってとこか……」
「生きてればな。静子も死んで身寄りと言えば、実家がある四国だけだろうが、その実家も当主が戦争に駆り出され、とうの昔に没落したと聞く、恐らく生きてはいまいよ」
そこまで聞いて、俺は押し黙ってしまった。
神谷 静子……その生涯は、陰惨な幕引きと共に多くの謎をまだ残している気がした。
「あ、あのう……?」
隣にいた椿が、俺たちの間に入りにくそうにしながら幸村に口を開いた。
「ん?ああ、なんだい椿ちゃん?」
女慣れしたコミュ力。俺も幸村ほどのコミュ力があれば、もう少し選考してくれる生徒も増えるとと思うんだが……
素直にそう思いながら、俺は椿を振り返った。
「あの、ハクちゃんって女の子の事、聞いた事ありませんか?」
「ああっ!」
「な、何ですか教授、突然大きな声出して!」
そうだった。
完全にそれを忘れていた。
本来なら神谷 静子と同じくらい重大な事だったのに。
「な、なんだなんだお前ら」
戸惑う幸村に向き直り、俺は再度椿と同じ質問と、昨日山で出くわした少女、珀明の事について話した。
「く、くくく熊ぁっ!?」
「あ、ああ、胸の模様からして多分月の輪熊だと思う……」
「ううん……まあこの地方でも絶滅宣言が出た後も、小例の目撃情報があったと聞いた事があるしな、ないとは言いきれんが……それより熊と渡り合ったっていう女の子の話は本当か?歳は幾つぐらいだ?」
「ああ、十七、十八といったところかな。漫画みたいな話だが、実際に俺も椿も、その珀明って子に助けられたんだ」
「珀明……ね」
「何か知ってるのか?」
幸村は顎に手を当てしばらく思案した後、ゆっくりと口を開いた。
「以前、大規模な捜索隊が、その山で組まれた事がある」
「捜索隊?」
「ああ、麓の学校で授業を受けていた小学生達が、毎日山から現れる一人の女の子がいると、学校側に証言したそうだ」
「麓の学校……」
昨夜、ハクもそれと同じ様な事を口にしていた。
「以前から山で女の子を見たとの目撃情報がいくつかあってな、中には山で遭難した所をその少女に助けて貰ったという話もある。つまりお前らみたいな例が今までもあったらしいんだ。それで警察も捜索隊を組んでな、当時登山部だった俺も、地元のボランティアとしてその捜索隊に参加したんだよ」
「そうだったのか……」
やはり俺達が想像していたよりも、ハクの事は結構大きな問題になっていたみたいだ。
まあ普通に考えれば、あの歳の女の子が一人森の中に住んでるとなれば大事にもなるだろう。
「お前、肝心なとこ忘れてないか?」
「えっ?」
突然、幸村が怪訝そうな顔を向けて言ってきた。
「俺が登山部だった頃はいつの話だよ……」
そう言って幸村は自分の左膝を叩いて見せた。
「あっ……!?」
その一言で、俺の全身から一気に血の気が引いていく。
幸村の左足を凝視し、混乱する頭を抱えた。
「えっ?ちょ、ちょっと教授?ど、どういう事ですか幸村さん?」
異変を察したのか、椿が慌てて聞いてきた。
俺は、その質問に答えられなかった。
完全に聞き落としていた。
ハクと話していた時もそうだった。
何か話が噛み合わない、違和感を感じていたのだ。
愕然とする俺の代わりに、幸村が重苦しい口を開いて言った。
「昔、登山中にこの足をやっちまってな、それ以来、山登りはもうやっていない。因みに俺が登山をやっていたのは、もうかれこれ十数年も前の話だ」
「そ、それって……!」
椿の顔が見る間に青ざめていく。
「ああ……捜索隊が組まれたのは、今から十二十年も前の話なんだよ」
幸村との話を終えた俺達は、そのまま元子さんの宿に戻る事にした。
途中、俺は影井氏からメールが届いていないか確認した。
影井氏は今回のフィールドワークのスポンサーでもあり大事な情報提供者でもある。
それに神谷 静子との繋がりも何かないかと疑っていた俺は、昨夜の内にハクの事を影井氏に報告しておいたのだ。
メール受信ボックスの0件と書かれた表示を見て、俺は小さくため息をついた。
車内を重苦しい空気が支配していた。
気分を紛らわすためにラジオをつけてみたが、その内容はほとんど頭に入ってこない。
それだけ幸村から聞いた話が衝撃すぎたのだ。
幸村もまた、ハクの事でかなり衝撃を受けていたようだ。
幸村の話だと、当時の目撃情報によるハクの見た目は小学生高学年、少なくとも十は超えていたという。
しかも捜索隊が組まれたのは一度ではなく何度かあったらしく、結局見つけられず警察も役人も、子供達の証言だからと誤報扱いのまま、捜索は半年程で打ち切られたらしい。
別人、そう位置づけた方が現実的かもしれない。
子供達が見たハクは別の少女で……。
考えれば考える程頭の中は混乱するばかり、結局宿に着くまで、俺と椿は一言も交わさなかった。
フロントガラス越しに、くたびれた民宿の看板が見えてきた。
専用駐車場と、手書きで書かれた板が無造作に立てられている。
駐車場というより小さな空き地だ。
ギアを入れ替え車をバックさせる。
が、その時、
──キュキュッ!
タイヤが擦り切れるような音を立てながら、一台の車が駐車場から飛び出してきた。
慌ててブレーキを踏み車を止める。
「危ないな……」
走り去る車を横目で追いながら、俺は再び車をバックさせ駐車場に車を停めた。
「ただいまです元子さん」
宿に戻り扉を開くと、入口に元子さんの姿があった。
「ああ、あんたら、丁度いいとこに来たね、今……ん?なんだいこれ……」
元子さんはそう言って俺の足元に目をやりかがみ込んだ。
何か落ちている。
紫の小さな巾着袋のような物。
元子さんそれを手に取ると。
「中に何か入って……」
そう言って袋の中身を手の中に広げた。
その瞬間、
「ひいぃぃっ!」
突然、元子さんが驚くような声をあげた。
「大丈夫元子さん!?」
慌てて椿が元子さんの側に駆け寄った。
俺は元子さんの手からこぼれ落ちたそれを拾うと、角度を変えながらまじまじと見つめた。
粗砂にも似た白くザラザラした粉瘤物、石炭灰のような固形……。
これと似たようなものを、俺は大学の研究部で見た事がある。
「動物の骨……か?」
「骨?何でそんなものが……?」
椿が怪訝そうな顔で俺に聞いてきた。
すると椿に支えられていた元子さんが、
「さっきの……」
と、ぼぞりと口にした。
「さっきの?」
気になって聞き返すと、
「さっきあんたらが帰ってくる前に、二人組の男がここを訪ねて来たんだよ、しかもこの辺りで真っ白な髪の毛をした女の子を見た事がないかって……明らかにこの辺じゃ見かけない連中だったね」
「それって……ハクちゃんの事?」
椿の声に俺は頷く。
「だろうな。おそらく、さっき駐車場から出ていった車の奴らだろう……」
そいつらがコレを落としていったのだろうか?
手のひらの骨のような物を見つめながらしばし考える。
「元子さんはその男達に何て?」
「ふん、感じの悪そうな奴等だったからね、そんな子知るわけないだろ、客じゃないんだったらとっとと帰んな!って言ってやったさ」
元子さんはそう言ってニヤリと笑って見せた。
「あははは……」
椿が苦笑いで返す。
「俺、ちょっと今からハクの事探してきます」
「教授?だったら私も」
「いや、椿はここに残っててくれ、ハクと行き違いになる可能性もあるしな」
「あ、そっか……はい分かりました!」
「うん、じゃあ頼んだそ」
「あ、ちょっとあんた!」
扉を開け宿から出ようとしたとこで元子さんに呼び止められた。
「ハクの事、よろしく頼むよ……」
少し不安そうな顔をしながら元子さんが頭を下げてきた。
「はい、任せておいてください」
そう言い残し、俺は駐車場に停めてあった車へと一人乗り込んだ。
宿を出て、田んぼのあぜ道をしばらく走っていると、昨日ハクを途中まで送った森の入口までやってきた。
車から降り、急いで森の中へと入る。
日中とはいえ、鬱蒼と茂った森の中は予想よりも暗く感じた。
不意に昨日の熊のことを思い出し一人で来た事を後悔しそうになったが、今はそれどころじゃない。
ハクを探す男たちの事がどうしても気になる。
親類?とは考えにくい。
それなら元子さんが知っていてもおかしくないはずだ。
だとしたら一体……。
──ガサガサ
不意に前方から茂みをかき分ける音が聞こえた。
反射的に身を屈め、木々の間から様子を伺う。
人影がこちらに近付いてくる。
よく見ると二人組、どちらとも男だ。
「クソっ!こんな事ならあの婆さん締め上げてでも居場所を聞き出すんだったぜ」
「バカか、影井さんに目だった事は控えろって言われてるだろ」
影井……!?
その言葉に、思わず口から声が漏れそうになった。
今男達は影井と確かに口にした。
それが俺の知るあの影井氏なら、この男達と影井氏は知り合いという事になる。
どういう事だ?なぜ影井氏と繋がりがある男達が……まさか……。
そこまで考えて俺はハッとした。
メールだ。
昨夜俺が報告した内容にはハクの事だけが記されていた。
他の事は何も知らせていない。
影井氏は最初から神谷 静子ではなく、ハクの事を探していた?
なぜ?なぜハクを探す必要がある?
「一旦戻るか?」
「そうだな、やっぱりもう少し情報を集めよう。影井さんにも一度連絡を取ってみる 」
そう言い残し遠ざかっていく男達の足音。
木陰から顔を少し出してから、男達が居なくなるのを確認する。
もう大丈夫か?
「ふぅ……」
安堵のため息をついたその時、
「んぐっ!?」
背後から物凄い力で口元を押さえられながら体を引っこ抜くようにして持ち上げられた。
激しく尻餅を着くようにして地面に叩きつけられた。
「先生……?」
口元を抑える手から力が抜けるのが分かった。
「いってえぇぇ……は、ハク?」
打ち付けた場所を擦りながら顔を上げると、キョトンとした目で俺を見下ろすハクと目が合った。
「何で先生がここに?」
「えっ?あ、いや、ハクの事が心配で、その様子を見にだな」
「俺の事が?心配って、もしかしてさっきの奴らの事か?」
「あ、ああ、知ってる奴らか?」
俺が聞くと、ハクは首を横に振って見せた。
「だろうな、明らかに様子が変だし、元子さんの言ってた奴らで間違いないか……」
「おばばが?」
「おばばって元子さんの事か?」
「うん。おばばは良い奴だぞ。この服もおばばがくれたんだ」
「そうか、元子さん面倒見良さそうだもんな。似合ってるよそれ」
「へへへ」
そうやってハクは照れ笑いを浮かべる。
こうして見ると年相応の純粋無垢な女の子だ。
そんな子がなぜ……考える度に疑問が頭をよぎる。
「なあ、ハクはこの辺に住んでるのか?」
「ああ、すぐ近くだ。家に来るか?先生ならいいぞ!」
そう言うとハクは俺の腕を掴み無理やり立たせると、急かすようにして腕を引っ張ってきた。
「お、おい引っ張るなって」
「いいからついて来い!」
そのまま俺は森の中をハクに引っ張り回された。
苔の生えた倒木の橋を渡り、崖沿いの獣道をしばらく進んでいくと、崖下に古い木造の建物が見えた。
あれは……。
風化し腐食した壁、赤錆だらけの鉄門。
朽ちかけた入口には……。
「学校?」
俺がそう口にすると、ハクは振り返り俺が見ていた建物に視線やった。
「あっ、ここが学校だ!昨日先生にも話したろ?」
「あ、ああ……言ってたな……でもここってもう……」
そう、見るからにこの朽ちた建物、いや学校は、とうの昔に廃校となったのだろう。
草木が割れた校舎の窓にまで伸び、ツタは絡み放題、おそらくろくに管理もされていないようだ。
「前はここに皆いたんだ。俺は外で見てるだけだったけど、先生達からたくさん教えてもらった。でももう今はいない……」
そう言ってハクはもの哀しげな顔で俯く。
「ハク……お前、自分が今何歳とか分からないのか?」
「何歳?」
「歳だよ。ハクにも誕生日ぐらいあるだろう?」
「誕生日……歳?ううん、分かんないや。だって俺ずっとここにいるから、もう数えるのもやめちゃったし、数字覚えるの苦手なんだ」
顔を上げはにかむ様に笑うハク。
そんなハクの顔を見ながら、俺は愕然とした思いだった。
この子は間違いなく、幸村の言っていた、二十年前この辺りで目撃された少女で間違いない。
なのにこの見た目は……。
医学的に見てもそう言う症例がない訳でもない。
ファブリー病。
先天的な遺伝子疾患による病気で、その確率はおよそ五十五万人に一人と言われる程の難病である。
実際に海外でも、見た目は十二歳位の少年が、実年齢二十五歳という症例もある。
ただし、ファブリー病は人体にもかなり負担を強いるため、もしハクがそんな病気なら、こんな森の中で一人暮らせるわけが無い。
だとすれば、やはりハクの体には何か特別な……。
そう考えればあの時、ハクが熊から俺達を守ってくれた時の事も説明がつく。
「それよりもほら先生、もう着くぞ」
そう言ってハクは再び俺の腕を引っ張った。
廃校のある場所から斜面を登っていると、
「あれだ」
ハクが指を指して言った。
視線をやると、そこには小さな山小屋の様なものがあった。
ひび割れた壺や酒瓶、柄の折れたフライパンや鍋などが小屋を取り囲むようにして積まれている。
「ここがハクの家か……?」
「うん。母さんが用意してくれたんだ」
「母さん?」
ハクの言葉に思わず目を見開く。
「どうした先生?」
「は、ハクのお母さんってどんな人だったんだ?」
「どんな……?ううん……綺麗な人だったぞ、それに優しかった」
「一度しか会った事がないって言ってたよな?」
「うん。ここに連れて来てくれた時な、すごく悲しそうな顔してた……」
「そっか……その時、お母さん何か言ってたか?」
「いつか迎えに来るから、父さんと一緒に待っててって、だからずっと待ってるんだ。父さんは先に逝っちゃったけど、俺がいないと、母さん戻って来た時に困るだろ?」
「お父さんと……」
ハクは父親と二人でここに暮らしていたのか……。
その後は一人でここに……。
「ずっとって、どれぐらい?」
「さあ、分かんないや。言ったろ?俺数えるの苦手なんだよ」
そう言ってハクは後頭部をかいた。
「寂しくはないのか……?ずっと一人なんだろ?」
「学校の子達が居なくなった時は寂しかったな……多分俺だけ文字が書けなかったから置いてかれたんだと思う……だから俺、文字を覚えたかったんだ。覚えたらまた皆と勉強できるし、先生も戻ってくるかもって」
「だから文字を……?」
「うん!でも先生って周りにいなかったし、ずっと教えて貰えなかったから我慢してたんだ」
「元子さんじゃダメなのか?」
「おばばは先生じゃないだろ?」
「あ……いや、分かった」
ハクにとっては、勉強は先生という存在が全て教えるものだという認識なのだろう。
「その、色々聞いてごめんなハク、嫌じゃないか?」
「いいよ、先生優しいから」
「俺が?」
「うん!俺の事心配して来てくれたんだろ?」
「ま、まあな……でも今までだってハクの事心配して森の中を探しに来た奴らもいただろ?」
「居たな。でもあいつら嘘つきだ。何もしないからって言ってたのに大勢で俺を捕まえようとしてきたんだ、だから逃げた。ここは俺の庭みたいなもんだからな、誰も捕まえられない、逃げるのなんか簡単だ」
「なるほどな……皆と一緒にいるのは嫌か?」
「皆と?」
「ああ、俺や椿が住んでる所だ。そこでは皆が仲良く暮らしてる。勉強だってできるぞ」
「椿も?椿も優しいから好きだ。先生や椿も達と一緒に暮らせたら楽しいだろうな……おばばも?」
「も、元子さんもか?」
「うん!でも……やっぱり俺はここに残らなきゃ」
「お母さんとの約束か……?」
「うん……」
「そうか……お母さんの名前って覚えてるか?」
「うん覚えてるよ。静子って言うんだ」
「へえ、静……静子?」
思わず聞き返す。
ゴクリと俺の喉が大きく鳴った。
「うん」
「神谷……静子?」
「あぁ、うん、何かそんな名前だった気がする」
俺の問にハクはあっけらかんとした態度で答えた。
「う、嘘……だろ?」
唖然とする俺。
そんな俺をハクが心配そうな顔で覗き込む。
その瞬間だった。
突如ハクの背後から二人の人影が現れ、ハクの背中に何かを貼り付けた。
「きゃっ!!」
「は、ハクッ!?」
ハクが苦しそうに仰け反り叫び声を上げた。
そのまま体勢を崩しその場に崩れ落ちる。
直ぐに駆け寄ろうとハクに手を伸ばす、が、
「おっと、教授」
銀色に鈍く光る切っ先が、俺の鼻先を掠めた。
ナイフだ。
「大人しくしていてくださいよ」
「しかし凄いなこの札、影井さんの言う通りだ。それにこの狐の匂い玉。流石の犬の鼻もこいつのせいで効かなかったみたいだな。俺た達が近づいても全く気付きもしなかったぜ」
札?匂い玉?
どうやらあの札がハクに何かしたらしい。
ハクと男達を交互に見る。
「変な気は起こさないでくださいよ、何かしたらこの女がどうなるかは分かりますよね?」
そう言って男は倒れたハクに向けてナイフを構え直した。
「やめろ!」
俺がそう叫んだ瞬間
──ドンッ!
「ガッ!?」
首元に凄まじい衝撃と激痛が走った。
膝が崩れ落ち、前のめりに倒れ込む。
意識が昏倒すしてゆく。
「行くぞ、山頂で影井さんと待ち合わせだ」
「あいよ……」
男は吐き捨てるように言うと、ごとりと、大きな石を床に捨て立ち去って行った。
瞼の上に、僅かな光を感じた。
「うっ……痛っ……!」
混濁した意識を引き戻そうと目を開けた瞬間、首元の激痛で一気に目が覚めた。
どうも背後から殴られ気絶してしまっていたらしい。
まずい、今何時だ?
左腕の時計を見た。
時刻は午後八時。
「くそっ!」
スマホを取り出そうとポケットをまさぐるが、ない。
ご丁寧にスマホを持っていかれたようだ。
痛みを堪え立ち上がり周りを見渡した。
月明かりがあるとはいえ、行きと違い森の中は真っ暗だ。
方向感覚さえ失いそうだった。
キョロキョロと当たりを見回すと、木々の間から不自然な光が垣間見えた。
光は二つ。不規則に揺れてはいるが、こちらに近付いてくる。
一瞬あの男達が戻ってきたのかと警戒したが、
「教授!」
聞きなれた声、椿だ。
「椿!ここだ!!」
光に近付き大きく手を振ると、二つの光が俺を捉え照らしてきた。
眩しさに目をしかめるが、光の先に目をやると椿の姿、そして元子さんの姿がそこにあった。
「大丈夫ですか教授!?」
「あ、ああ、それよりなんで二人共ここに?」
「決まってるじゃないですか!心配して探しに来たんですよ、一人じゃ迷うからって、元子さんも着いて来てくれたんです」
「そ、そっか、すまん助かった、元子さんも、わざわざすみません」
俺は椿と元子さんを交互に見てから二人に深々と頭を下げた。
「そんな事よりもハクは、ハクはどうしたんだい?」
元子さんが心配そうな顔で椿の後ろから身を乗り出してきた。
「それが……」
俺は歯痒さを堪え、さっきここで起こった出来事を全て二人に話した。
「そんな、ハクちゃんが……」
「すまん椿、元子さん、俺が着いていながらこの様で……」
「あんたのせいじゃないよ。相手も二人いてハクを人質に取られたんだ、一人じゃどうしようもないさ」
「奴らの居場所は分かっています。今から追い掛けるつもりです」
「しかしだね、アンタ一人じゃ……」
元子さんが心配そうに俺を見た。
すると突然椿が
「私も行きます!」
と、声を張り上げ手をおでこに当て、なぜか敬礼して見せてきた。
「あのなあ……いや、危ないからお前は、」
「いいえ、私も行くんです!」
「遊びに行くんじゃないんだぞ?」
「そんな事私にだって分かりますよ!ハクちゃんはもう私の友達でもあるんですから!」
ダメだ、こうなると椿は俺の言う事なんて聞こうとしない。
「分かった、分かったから落ち着け。その代わり危なくなったら直ぐに逃げるんだぞ?いいな?」
「はい!」
本当に大丈夫なのだろうか……不安になってきた。
「元子さん、森の外まで案内してもらっていいですか?」
「あ、ああ分かった、ついといで!」
元子さんは大きく頷くと、先頭に立ち先を進み始めた。
俺と椿は互いに顔を見合せ頷くと、元子さんの後に続き、森の外を目指した。
森の中を足早に駆け、俺達は森の外へと出た。
元子さんはが慣れた足取りで俺たちを先導してくれたので、おかげでだいぶ早く外へと出られた。
俺は二人を車に乗せ元子さんを宿に送り届けると、再び車を走らせ目的地である山頂を目ざした。
「教授、何か考えがあるんですか?」
助手席に座っていた椿が不安そうな顔で聞いてきた。
「一応な……」
「一応?」
「ああ、さっきも言ったが、ハクは御札みたいなもので気を失ったみたいなんだ。奴らはハクの持ってる特殊な力を良く知っているみたいだったしな、予め対抗策を考えてたんだろ。じゃなけりゃ、熊とも戦っちまうハクが簡単にやられるわけが無い。だったら、隙を見てあの札さえ剥がすことができれば、上手く助け出せるかもしれん」
「御札ですか?なんでそんなものでハクちゃんが……」
「さあな。幽霊云々ならともかく、生きている人間があんな紙切れ一枚でどうにかなるとは思えないけどな。それとも……ハクは人間じゃないのかも……」
「やめてください!ハクちゃんはハクちゃんですよ。あんなに素直で可愛い女の子が、そんな化け物みたいな言い方……」
「すまん、そんなつもりで言ったわけじゃないんだ……ただ今回の一件は全てそこにある気がするんだ。ハクが持っている力こそが、今回の騒動に深く関わっている筈だ」
「それは何となく薄々とは……助けられますかね、ハクちゃんの事……やっぱり最初から警察を呼んだ方が?」
「俺もそうしたいが、ハクに何かあっても困る。それに流石に奴らも俺を殺しまではしないよ。こんな所で俺が死んだらそれこそ大事だ。警察も馬鹿じゃないし直ぐに足がつく。問題なのはハクだ」
「ハクちゃん?」
「ああ、ハクはおそらくこの国じゃ実在しない人間扱いだ。多分戸籍もないだろう。もしこの件の発覚を恐れた奴らが、証拠隠滅のためにハクを消そうとする可能性はある。ハクさえいなくなれば今回の一件、警察は立件すらできないだろうからな。それにハクの事を考えれば警察沙汰はかなり厄介な事になる、その為にも最後の手段にしておきたい。だから椿、向こうに着いたらお前は何処かに隠れていてくれ」
「隠れるって、私だけですか?」
「ああ。無理そうだったら元子さんに連絡して、お前の判断で警察を呼べ、そして逃げろ」
「い、嫌ですよ!私だって覚悟を決めたんですから!」
「椿!頼む……」
思わず声を荒らげてしまった。
椿は一瞬驚いた顔をしていたが、理解してくれたのか、今度は少し落ち込んだ様子で小さく頷いてくれた。
「すまん……」
そう言ってから俺は椿の頭に手を置き二三度撫でた。
「こんな時に優しくするとか……卑怯ですよ……」
「えっ?」
「な、何でもありません!こんな事……他の生徒にもよくするんですか……?」
「はあ?バカ、こんな事お前以外にするわけないだろ」
「ほ、本当ですか?」
「当たり前だ。他の子にしてみろ、セクハラで大学一発退場だぞ。だいたいお前はこんなの気にしないだろ」
突然、椿に頬っぺをギュッとつねられた。
「痛っ!」
──キュキュッ
ハンドルを握る手が思わず緩み、車体が中央線からはみ出しそうになる。
スピードを落としすかさずハンドルを制御した。
「お前な!着く前に死んだらどうする!」
椿は頬っぺを膨らませなぜか俺を睨んでいる。
「何だよ、急にしおらしくなったと思えば今度は怒り出して」
「何でもありませ……教授!?」
椿が何かを見つけフロントガラス越しに前方を指さして見せた。
山頂間近の駐車場に微かな明かりが見える。
おそらく奴らだろう。
「ああ……」
何とか間に合ったようだ。
ライトを消し、車を停める。
「俺は裏から周る、椿は反対から周って様子を伺っていてくれ。あんまり近づかないようにな」
そう言うと、椿は真剣な眼差しで俺を見ながら頷いて見せた。
それが決行の合図となり、俺達は車を降りて身を屈めながら移動を開始した。
椿は道路脇の林の中から、俺は反対の斜面から近付いた。
慎重に、ゆっくりと確実に距離を詰めていく。
やがて二十メートル程の距離に達した所で、一旦様子を伺う。
車は二台。一台は昼間宿で見た黒のCROWN。
もう一台は黒の見慣れぬベンツだった。
ベンツの方は運転席に一人、CROWNの方にはさっきの二人組の男が載っていたが、二人とも車を降りて一人はベンツの方へ、もう一人はCROWNのトランクへと向かった。
俺はCROWNのトランクが見える位置へと移動し、男の背後に回り込んだ。
物陰から僅かに顔を出し覗き込むと、トランクの中に横たわる人影が僅かに見えた。ハクだ、間違いない。
「おい、ちょっといいか?」
「なんだ?」
突然ベンツの側に居た男が、トランクの前にいる男を呼んだ。
呼ばれた男は面倒くさそうにしながらトランクを開けたままベンツの方へと向かう。
「よし!」
小さくガッツポーズを取り、俺は忍び足でCROWNへと近付いた。
車の側面へと回り込み、ゆっくりとトランクの前に近寄る。
しゃがみ込んだまま上半身だけを浮かせ中を見ると、そこには両手足を縄で縛られたハクの姿があった。
思わず声を掛けそうになり口元を自分の手で押え噤んだ。
よく見るとハクは眠っているようにも見える。いや、気絶しているのか?
背後にはあの札が貼られているのが確認できた。
俺はハクを揺さぶりながら縄を解こうと手を伸ばした。
「何をしてるんだそんな所で」
「しまっ!?」
背後からの男の声に逃げようとしたが既に遅かった。
片腕を背中に捻られもう片方の腕で頭を車に強く押し付けられた。
「ぐっ!!」
声も出せない身動きも取れない。
「やっぱりいましたか。先程から狗が騒がしくてね、ネズミが居ると直ぐに教えてくれましたよ」
聞き覚えのある老人の声がベンツの方から聞こえた。
靴音を鳴らしながらゆっくりと此方に近付いてくる。
「おい」
ベンツの方にいた男がそう言うと、俺を取り押さえていた男が腕だけを背後に捻ったまま体を立たせてきた。
眩しい車の明かりの中から現れた、男の姿、
「影井……清隆……!」
そう、三ヶ月前に、フォーラムで俺に接近してきた男だ。
あの時も今日みたいな黒い着物を着ていた
「おや、もう一人……まだ隠れているようですな、教授?」
「何を……?」
どうやら椿の事がバレている。
「隠しても無駄ですよ。こう見えてわしも狗神筋の端くれなんでね、身に巣食う狗が教えてくれるんですよ」
「狗神筋!?」
「そう……ふふふ、さて隠れているのは分かっていますよ、真昼教授の事を大事に思うのなら今すぐ出てきた方がいい、妙な真似をせずにね……」
「椿逃げろ!!」
「黙れ!」
──ガツッ
「ぐはっ!!」
目の前にいた男から強烈な右フックを叩き込まれた。
視界がチカチカし、頬に激痛が走る。
膝が崩れそうになったが、背後にいる男によって倒れる事は許されなかった。
「待って!いい、今そっちに行くから!!」
「椿……」
林の暗がりから人影がぎこち無い動きで現れた。
椿だ。
「おやおや可愛いお嬢さんじゃないですか、いけませんよこんなお嬢さんを危険な目に合わせては……ではお嬢さん、スマホを下にゆっくりと置いて貰えますかな?」
「椿やめろ!いいから逃げっ」
──ドスッ
鈍い音が俺の腹から響いた。
「ぐはっ……!」
男の拳が俺の腹にめり込み、体がくの字に折れ曲がる。
「置くから!お願いだからもう殴らないで!!」
悲痛な椿の叫び声が耳に響いた。
激痛に顔をしかめながら何とか踏ん張ろうとするが、足がふらついて今にも倒れてしまいそうだ。
「良い子だ、そのままこっちに来なさい。何、手荒な真似はせんよ。二人ともわしらがいなくなるまでの間大人しくしてもらうだけでいい、後は解放してやろう」
「ほ、本当に……?」
「そう怖がらなくていいよお嬢さん、わしは約束は守る男だ」
「何……が約束だ……」
「貴様っ!」
男が腕を振り上げる、が、影井がそれを首を横に振って制した。
「真昼教授、心外ですよ、わしは何一つ嘘はついていない。貴方には神谷 静子の足取りを探して欲しいとお願いしただけだ。今までの連中にもね」
「今……までも?」
「そう、今までもわしはずっと神谷 静子の足取りを追った。全国各地にね」
「全国各地……?どういう事だ?」
「神谷 静子……いや、わしの娘、影井 静子は、この大分で亡くなる前に、一度ここを出ているんだよ」
「娘!?そんな馬鹿な!!だってお前は……!!」
神谷 静子が、影井 清隆の娘?
じゃあこいつはハクの祖父?
いや、そもそも影井 清隆がなぜ今も生きている?
……そうか、ハクの祖父という事は、この男にもハクと同じ力が……?
そこまで考えるが、頭が混乱し思考が追いつかない。
「ハクの事を知っているのなら分かるだろう。わしにも狗神の邪法が宿っているのだよ」
「邪法だと……?」
「静子の家は偉大な狗神筋だった。そしてそれに漏れず静子もまた類まれなる狗神筋としての才を受け継いでいた。しかし、戦争で一家は没落し主を失った静子の家は貧困に窮していた。そこで手を差し伸べたのがわしだったのさ」
「お前が?」
「ああ、静子をわしの養子にする代わりに、神谷の家を助けるとね……」
「取引したってわけか……?」
影井が不気味な笑みを浮かべながら頷く。
「条件は一つ、影井の家に伝わる代々の邪法を完成させる事……ふふふ、真昼教授、君も見たのだろう?人の域を超えた力を!神成せる業を!!」
目を見開き俺に語り掛ける影井の目は、大きく見開かれまさに狂人の目だった。
「ハクの……あの力か?」
「そうだよ!君から報告があった時は本当に胸が踊った!静子はあの邪法を完成させたのだと直ぐに分かったよ!」
「完成……?」
「ああっ……静子はわしと約束した、邪法を完成させると……なのに静子は、いや奴は!わしを騙し国を出た」
「邪法は……完成しなかった?」
「そうだ……わしに掛けられた邪法はただの延命にしか過ぎなかった……若返りもしない、いつか朽ち果てる身だ。だからわしは方々を尽くし探し回った、静子を連れ戻すために……そして数年が立ち、ある日静子が大分で子供を産んだ事を知った。急いで此方に向かったが、静子は産んだ子供を連れてどこかへと姿を消していた。おそらくわしからの追っ手を交わす為だろう……そこで、わしは静子の信者共を使う事にしたのだよ。いや、正しくは静子の夫をね」
「静子の夫は信者だったのか……ちょっと待て……使うって……もしかしてお前が!?」
「察しがいいな真昼教授。そう、静子の夫に、静子が戻ってくる為、親子三人で暮らす為には大金がいる、だから協力しろと吹き込んだんだよ」
「影井っ……!」
「はははははっ!あの男はまんまと騙されてくれたよ!!余程静子が子供と消えたのがショックだったのだろうな。奴が憲兵共に捕まると、静子は予想通り直ぐに姿を現した、後は憲兵共に金を払い、静子を拷問させ子供の居場所を吐かせるだけだった……」
影井はそこまで言って僅かに俯いた。
その表情には悔しさにも似た感情が宿っているように見える。
神谷 静子は憲兵に屈しなかった。
最後まで娘を、夫を守ろうとしたのだ。
そして最後はその身を焼き付くし……。
「後は君が知っている通りだよ真昼教授。おかげで私はハクを探すために膨大な時間と金を注ぎ込む事になったがね。まさか、灯台下暗しというべきか、この大分の地に隠れ住んでいたとは……静子め、本当に恐れ入ったよ」
「ハクの力は……邪法によるものなのか……?」
「恐らくな。静子が自分の体を使い完成させ、その力を受け継いだのがハクだ。なあに、ハクの体を使い、未完成の邪法を完成させるぐらいの時間の猶予はある。後は君たちさえ邪魔しなければ、誰も傷つかず至って平和的に物事は解決する。分かるだろ、真昼教授?」
そう言って影井は下卑た笑みを椿に送った。
椿がそれを見てビクリと肩をふるわせる。
「誰も傷つかない?ふざけるな……!ハクはずっと傷付いてきたんだぞ!」
「真昼教授……」
やれやれと言った感じで影井が肩を竦め首を横に振った。
「ハクは人間ではない。何をそこまで怒る必要があるのかね?ハクはそう、モルモットのようなものだ。人類の進化のためには、常にハクの様な実験対象が必要だろう?それは真昼教授、君のような学問を志す者なら十分に理解できる事だと思うがね?」
「倫理から外れ人の心を捨てた奴が学問を語るな!ハクは……ハクはずっと母親との再開をあの森で待ってたんだ!先に逝ってしまった父親の死を乗り越え、一人で……ずっと……!お前にその気持ちが分かるのか!?」
「無駄だよ真昼教授。わしは十歳を迎えた頃にはもう、この身の内に狗を飼わされた。奇行が目立ち、心の制御もできない。それが永遠とも思われる時間の中で続いて行く。蔑まれ罵られ忌み嫌われね。しかし狗を制御し、静の研究によって生まれ変わったわしの世界は一変した。誰もがわしに忠誠を誓い。思いのままとなったよ。くくく……一度手に入れたこの力……みすみす手放すと思うかね?」
そこまで言ってから、影井は邪悪な笑みを俺達に向けてきた。
「このっ!」
──ドンッ!
俺は一瞬の隙をつき、背後にいる男に頭から体当たりをかました。
もつれるようにして男と一緒に倒れ込む。
「今だ逃げろ椿!」
「えっ!?」
俺の叫び声に椿が衝動的にその場を駆け出した。
だが、
「おっと!」
もう一人の男が逃げようとした椿の髪の毛を乱暴に掴んだ。
「あうっ!!」
「や、やめろっ!!」
悲痛に顔を歪ませる椿を見ながら叫ぶ。
「抵抗してんじゃねえよ!」
倒れていた男が立ち上がり俺の顔目掛けて拳を振りかざした。
──ブンッ
風切り音がし思わず歯を食いしばり顔を背けたが、なぜかその後の衝撃が襲ってこない。
「えっ……?」
おそるおそる顔を上げると、何故かその場にいた全員が驚愕の顔のまま固まっていた。
「何が、」
そこまで言いかけて、俺は一瞬言葉を失ってしまった。
叢雲から指す僅かな月光に照らされた、雪のように真っ白な髪。
風になびく度、光を反射し銀色にキラキラと光って見える。
ハクだ。
その右手には、今しがた俺に振り下ろされたであろう男の拳が握られていた。
「な、何で……!?」
男が上擦るような声で言った。
「お前が俺を引き剥がした時だよ」
ニヤリと笑ってみせ、俺はトランクの前で捕まった時、ハクの背中から剥がした札を取り出し、影井と部下の男達にヒラヒラとさせながら見せてやった。
「きっ貴様ぁぁ!!」
影井が怒声をあげた瞬間だった。
──ブンッ!!
ハクが男の拳を握ったまま車の横っ面に投げ飛ばした。
百八十はある男の巨体が軽々と放られ
──ドゴンッ
と、鈍器で力いっぱい殴ったかの様な音が響いた。
ベッコリと凹んだ車のボディに寄りかかるようにして男は完全に伸びきっている。
「ばば、化け物!?」
椿の髪を掴んでいた男が、慌ててCROWNへと乗り込んだ。
車のエンジン音が鳴り、急発進しようとした車の動きが……止まった。
──キュキュキュキュッ!!
激しいタイヤの回転音と、鼻を突く白煙が舞い上がった。
ハクが隆々と盛り上がった両手でCROWNの後部を掴んでいる。
ハクは両足に力を込め、思いっきり踏ん張るり、両手で車を持ち上げたかと思うと、そのまま車を横倒しに引っ繰り返した。
──ドドーンッ!
雷でも落ちたかのような轟音と、大量の砂埃が辺り一面に舞う。
それを見ていた影井は腰が抜けたのか、ズルズルとベンツに寄りかかるようにして座り込んでしまった。
小刻みに肩を震わせ、歯をガチガチと鳴らし怯えている。
「ひっ……!ひいぃぃぃ!?」
舞い上がる白煙の中から、明らかに異様な出で立ちのハクが姿を現す。
昼間見た華奢な女の子はそこにいなかった。
身体中の筋肉が異様に隆起し、瞳は全てを射すくめるような獣の目をしていた。
火を灯した様な緋色の目が、影井を見下ろしている。
「くくっ来るなぁぁ!!」
影井が目の前を振り払うように両手を振るが何の意味もなさない。
「フウゥゥッ!」
熱を帯びた吐息がハクの口から漏れる。
僅かに開いた口端には突き出た鋭い犬歯が見えた。
「は、ハク…?」
おそるおそる声を掛けるが、ハクの反応はない。
「ハクちゃん!?」
見かねた椿も声を掛けるがやはりハクの反応はない。じっと影井を睨んでいる。
「た、頼む……頼むから命だけは……!」
影井はこの期に及んで必死に命乞いを始めた。
「お前は皆をいっぱい傷つけた……母さんも、父さんも、椿も、先生も……!だから絶対に許さない……!」
さっきの影井の話を聞いていたのだろ。
ジリジリとハクが影井との距離を詰める。
「ひっ!ひいぃぃぃっ!!」
「ハクっ!」
まずいと感じた俺は急いでハクの目の前に両手を広げ立ちはだかった。
「どけ!グルルルッ……邪魔……するな!!」
ハクの様子が明らかにおかしかった。
徐々に自我を失いかけているような、そんな感じがした。
ともかく、今は引き下がる訳にいかない。
もしこのままにしておけば、ハクは間違いなく影井を殺してしまう。
ハクの手をこんな奴の血で汚す訳にはいかない。
もしそうなってしまったら、ハクは今度こそ人には戻れなくなってしまう。
「ハク……やめるんだ」
言い聞かせるようにハクに言った。しかしハクは嫌々をする様に首を激し振る。
「ためだ……だめだだめだ!!どけ……!どかないと……ガルルルルッ!!」
ハクに両肩を掴まれた。逃れようともがいてもビクともしない。
「ハク!もうやめるんだ!」
もう一度ハクに向かって叫んだ。
次の瞬間、
「ぐっ!?」
全身を麻痺させるような衝撃、皮膚を食いちぎられそうな痛みが全身を襲った。
「教授!?」
椿が急いで駆け寄ってきた。が、俺は何とか片手を上げてそれを制した。
「待て、つば……き!」
「で、でもこのままじゃ……!」
血の気が引いていく。
首から肩にかけて、着ていた服がじんわりと赤い鮮血に染め上がっていくのが分かる。
「ハク……もういいんだ。もう大丈夫だから……なっ?」
鋭い犬歯を俺の首筋に突き立て噛みついたままのハク。
その形相はもはや人とは思えない。
けれど、俺は知っている。
本当は普通の女の子なんだと。
生まれた場所がみんなと違うだけで、彼女は普通の女の子だと言う事を……。
本当は優しくて、寂しがり屋で、頑張り屋な子なんだと言う事を……。
「ハク……もう……いいんだ……」
かろうじて動く右手を上げ、ハクの頭を撫でる。
ハクの髪を結んでいた赤いリボンに指が絡む。
ヒラヒラと揺れるリボンの紐がハクの鼻先を僅かに掠めた。
その瞬間、
「せん……せい?」
首元からそう聞こえた。
「あ、ああ……先生だぞハク……だからもう大丈夫だ……だいじょう……ぶ……」
意識が遠のいて行く。
「先生!!」
「教授!?」
ハクと椿の泣き叫ぶような声が同時に響く中、俺の身体は深海の奥底に沈む様に、真っ暗な闇の底へと、落ちていった……。
ほのかに香る柑橘系と甘い匂いが、俺の鼻腔を微かに擽った。
瞼を開けようとしたが針で縫っていたかのように重い。
ようやく目を開くと、今度はカーテンの隙間から射し込む強烈な陽の光に顔をしかめた。
顔を横に向けると、目の前に人影が見えた。
ベッドに突っ伏すようにして眠ってしまっている。
椿だ。
すやすやと寝息を立てている。
どうやらここは病院らしい。
「ふふ……」
寝ている椿の頭を撫でると、さっきの甘い香りが風に乗って漂ってきた。
匂いの正体はこれか。
椿がよくつけている香水だ。
昔は凄く甘い香水を付けていて俺が苦手な匂いだと言ったら、翌日からこの柑橘系の香水に変えてくれていた。
「いつもありがとうな、椿……」
そう言って俺が体を起こした時だった。
「全くだ、嬢ちゃんにはちゃんと感謝しとけよ」
「ゆ、幸村?痛っ……!」
痛みに顔をしかめながら声に振り向くと、ソファーに腰掛ける幸村の姿があった。
「おいおい大丈夫か?無理するなよ」
「あ、ああ、お前も来てくれてたんだな」
「ああ、お前が世話になってる民宿の婆さんも来てるぞ」
そう言うと幸村は入口まで歩き廊下にいた元子さんに声を掛けた。
「俺は医者に話をしてくる」
「あ、ああ、すまん」
俺がそう言うと、幸村はクスリと笑い、元子さんと入れ替わるようにして部屋を出ていった。
「はあ、目を覚ましたんだね、良かった良かった……ハクを守ってくれて、本当にありがとうよ」
「いえ……守ったというか、守られたというか……」
「いいんだいいんだ……あの子はね、子供のいないわしにとっちゃ本当に孫のような存在でな……だからな教授さん、本当にありがとな……」
「此方こそですよ……元子さんには本当にお世話になりました」
深々と頭を下げてくる元子さんに、俺は返すように頭を下げた。
「なあ教授さん……?」
「はい、なんでしょうか?」
突然、元子さんがあらたまって口を開いた。
「実は教授さんに頼みがあるんだ」
「頼み……ですか?」
「ああ……ハクの事だ」
「ハクの?」
聞き返す俺に、元子さんが大きく頷く。
「ハクを……一緒に連れて行ってもらえんかね?」
「ハクを……?」
「ああ、あんたにならハクを任せられる、いや、あんたしか任せられん」
そう言ってまたもや元子さんは深々とお辞儀をしてきた。
「も、元子さん頭を上げてください」
薄々は考えていた。
ハクにとって最良の道。
待ち人が来ないと分かったあの森で、ハクが暮らしていく意味。
ずっと一人で生きてきたハクを、これこら先誰が見守ってやれるのかを。
元子さんならそれができるがもう歳だ。
失礼な言い方だが、そんなに長くはハクと一緒に居てやれないかもしれない。
それに、ハクにはまだ色々と学ぶチャンスがある。
色々な事を学ぶチャンスが。
そして人生の大半を一人で過ごしてきたハクにとって、寂しくないんだという安心した生活を送らせてやりたいとも、俺は思っていた。
「おっ、なんだ、覚悟を決めたって面して」
声に振り向くと、扉の前で俺を見ながらニヤニヤしている幸村の姿があった。
「覚悟か……そう……だな」
「じゃ、じゃあ……!」
元子さんが顔を上げ、涙で顔をくしゃくしゃにしながら聞いてきた。
俺はそれにゆっくり頷いてから再び幸村に向き直る。
「悪い幸村、大至急行きたい所があるんだ、頼めるか?」
「やれやれ、人使いが荒いやつだな。退院の手続きしてくる、用意しとけ」
「すまん……恩に着る」
そう言って幸村に頭を下げると、俺は窓の外へと視線を移した。
真昼の太陽が雲一つない空から顔を出している。
暖かい日差しと、心地好い風。
俺はこんな陽の当たる場所に、人目も気にせずハクを連れ出してやりたいと思った。
世界にはたくさん楽しい事と、感動できることがあるんだと教えてやりたかった。
行こう……ハクの所へ。
元子さんからハクの居場所を聞き、俺達は幸村の運転であの森へと向かった。
途中、俺が二日間も寝ていた事と、影井達があの後行方をくらました事を聞いた。
椿はあの後警察に連絡しようか迷ったようだが、ハクのあの姿を目にし、結局警察沙汰にするのはやめたらしい。
どうやら椿も何らかの覚悟をしたようだった。
病院を出て山道へと入る。
窓を微かに開けると、水の貼った田んぼからしっとりとした青草の匂いが漂ってきた。
夏が近づくに連れて濃い匂いを放ち、季節の到来を知らせてくれる。
喉かな田園風景をしばらく眺めながら車で移動していると目的の場所が見えてきた。
「この辺でいいのか?」
幸村は車を停め俺に確認する様に言ってきた。
森の入口。ここへ来たのはこれが三度目だ。
「ありがとう幸村」
「気にすんな、俺は車に残るよ。会ってみたいが警戒されても嫌だしな。後は……まっ、頑張れ」
そう言って俺にウインクしてきた。
「気持ち悪いからやめろ」
「ははっ 」
そう憎まれ口を叩きながら、俺は車を降りた。
元子さんが先頭を歩き、森の中へと入っていく。
相変わらず歳を感じさせない軽快な足取りでハクの家まで案内してくれた。
俺は椿に体を支えてもらいながら何とか着いていくのがやっとだった。何とも情けない姿。
しばらく歩くと、先頭を歩いていた元子さんから、
「着いたよ……」
と声を掛けられた。
俺と椿は元子さんに頷くと、目の前に見える山小屋の玄関へと向かった。
「ハク!居るなら顔を見せてくれ!」
入口で声を上げると、中から微かに物音がした。
どうやら居るのは間違いなさそうだ。
「ハク!」
「もう……大丈夫なのか?」
か細い声が扉越しに返ってきた。
「あ、ああ、こんなのもう何ともないぞ!ほら、痛っ……!」
そう言って自分の肩を叩いて言ったものの、
「ほらもう強がるから!」
横にいた椿が慌てて俺の肩を摩ってくれた。
「何しに……来た?」
「何しにって、そりゃハクに会いに、」
「ごめん先生、俺もう先生とは会えない……」
「な、何で?どうしてそんな事言うんだ?」
「だって、俺先生に怪我させた……危ない目に合わせた。全部……俺のせいだ……」
ハクの声は、最後の方はもう上擦っていてよく聞き取れなかった。
だが、ハクが俺の怪我に負い目を感じでいる事くらいは分かる。
「いいんだハク、あれは俺が望んてやった事なんだからお前は気にしなくていい。だから顔を見せてくれないか?」
「そうだよハクちゃん。私達もう友達なんだから、顔ぐらい見せてよ、ね?」
椿も扉越しに声を掛ける。
「もう……帰っちゃうのか?」
「ああ……」
そう返事を返すと、しばらく無言が続いた後に、俺はこうつけ加えた。
「お前も一緒にな、ハク……」
「い、今何て……?」
聞き返してきたハクの声に、先程までの暗い影はない。むしろ少し元気を取り戻したかのようにも聞こえる。
「聞こえなかったか?なら顔を見せてくれ」
──ガチャ
扉がそっと開き、目元を真っ赤にしたハクが姿を現した。
おそらく俺たちがここを訪れる前から一人で泣いていたのだろう。
「ようやく顔を見せてくれたな……ハク」
「うん……」
「俺達と一緒に来ないか……?その、もちろんハクがそうしたいって気持ちがあるならの話だが……なっ、椿?」
「何で急に私に振るんですか!もっと自信もって言ってくださいよ、大人でしょ?」
「ハク!」
後ろからハクの名を呼ぶ声。
「おばば……!」
振り向くと、目に涙をうかべた元子さんの姿があった。
「ハク……お行き。お前を縛るもんはもうここには無いんだ。これからはこの人達がおる。もう寂しい思いも、辛い思いも、一人でせんでええ」
「おばばは……?おばばは一人じゃないか……」
「わしは老い先短いババアだ。それに近所に知り合いもおる。最近は寄り合い所でゲートボールも始めたしの、これが中々面白いんだ、ははははっ」
元子さんはそう言って、所々抜けた歯でにっこりと、満面の笑顔を見せてくれた。
「うん……うん……ひっく」
「ハク……俺達と一緒に行こう。いっぱい勉強して、色んなものを一緒に見よう。今まで知らなかった事、見た事ないものが沢山……沢山待ってるから」
「お、俺……怒ったらあんなんだし……」
「知ってる……」
「ご飯も沢山食べるし……」
「お、おう、まあ育ち盛りだから仕方ない」
「また……また昨日みたいな事があるかも……しれ……ひっく……」
ハクのその姿は、まるで駄々をこね、泣きじゃくる幼子の様だった。
いや、実際そうなのだ。
これが、これこそがハクの本当の姿なのだと、俺は今あらためて思った。
誰にも甘えられず、ずっと我慢してきた、ハクの本当の姿。
だから……。
「大丈夫……何度でも噛みつかれてやる。お前が帰って来るなら何度でも、だから……一緒に帰ろう」
そう言って俺はハクに手を伸ばした。
瞬間、ハクは俺の手を掴むのではなく、俺の胸に飛び込んできた。
「ひっく……うぅぅっ……」
泣きじゃくり俺にしがみついてくる。
「ふふ、教授とハクちゃん、何か本当に親子みたい」
「そうだな……うん、それでええよ、ハク……」
椿と元子さんに言われ、親子という言葉に多少の違和感を感じたが、それも悪い気はしなかった。
ハクの頭を撫でながら、俺は空を見上げた。
あれだけ鬱蒼と暗く感じていた森が、今はやけに心地好く、暖かな陽の光に溢れた場所だと感じていた。
微かに聴こえてくる蝉の声。
照り付ける陽の暑さと、それを撫でるように冷やしていく健やかな風。
夏が、近付いているのだと……そう思った。
地元に戻った俺は、相変わらずな日常を送っていた。
ハクは俺のマンションで一緒に暮らしていて、此方の生活にもだいぶ慣れてきたようだった。
ただ、まだ一人で外出させるのは色んな意味で危険なので、もっぱら留守番の日々だが。
──ブーブーブーブーッ
ボケットのスマホのバイブが鳴った。
液晶画面には元子さん、と表示されている。
「はい、真昼です」
『おお、久しぶりだね教授さん、元気にしてたかい?』
「ええ、元気ですよ、ハクも、お陰様で元気にしています」
『そうかいそうかい、そりゃ何よりだ』
「あの……民宿、お辞めになられたんですね」
『おや、もう耳にしたのかい?そうなんだよ、最近腰を悪くしちまってね、年甲斐もなくゲートボール何かに手を出したからかねえ、はははははっ』
「行方も分からないと、幸村から聞いています……」
『そうかい……そうそう、実は渡したい物があってね。もう教授の家に送っておいたから明日にでも届くと思う、』
「このまま、ハクには名乗らないつもりですか……?」
俺は元子さんの話を遮るようして言った。
『何の……話だい?』
「貴方は元子さんなんかじゃない……貴方は……貴方は神谷 静子、ハクの……母親ですね?」
『……』
元子さん、いや、神谷 静子は何も応えなかった。
「覚えていますか?貴方が民宿の入口で拾った巾着袋の事?」
『あれが……何だって言うんだい……?』
「あの時貴方の行動が不自然だったんです。確かに、あれが何かの骨だと分かれば、誰だって驚きはします。けれどあの時俺は、あれが骨だと確信するには時間が掛かった、しっかりと確認し記憶を辿って得た回答なんです。なのに元子さん、貴方はあれを袋から取り出した瞬間から驚き怯えていた。だから俺はあれが気になって、あの骨を幸村に頼み分析に掛けてもらいました」
『それで……?』
ドキリとした……。
そう聞き返してきた元子さんの声が、明らかに違って聞こえたからだ。
年老いた老婆の声ではなく、若く艶のある妖艶な声。
「あ、あの骨は狐の骨でした。二人組の男達が言っていたんです。ハクを捕らえた時、札と匂い袋の話をしていました。あのハクが侵入者に対し気付けず、あっさりと捕らえられてしまった。あの匂い袋には、狗神の感覚を麻痺させる様な効果があったのでは?狐は昔から狗神の天敵と言われています。おそらくあの札と匂い袋は、狗神に対抗するために作られた呪具の様なもの……そう考えると全てが納得できたんです。つまり、あの時貴方が驚いたのは骨に、ではなく、あれが狐の骨だといち早く気付いたからだと……」
そこまで言い切った後、長い沈黙が流れた。
校庭から運動部の掛け声が響き、忙しない蝉の鳴き声が更に騒がしく聴こえた。
『流石だね教授さん……』
明らかに別人の声。
いや、これが本来の声、神谷 静子の声なのだろう。
「認めるんですね」
『ああ……だけど、残念だけどハクには名乗らない』
「何故ですか?ハクはずっと母親である貴方を……!?」
『私が母親である以上。あの子は命を狙われる。だから、今までもそれを隠して生きてきた』
「憲兵に捕まった時ですか……?」
『ああ……影井が私の子供を探している事に気が付いたよ。だから私は一芝居うったのさ。自分が死んだように見せかけてね。影井の馬鹿はまんまと騙されてくれたよ。でも奴のしつこさは重々承知していたからね。奴が諦めるまでは、私はハクと一緒に暮らす事はできなかった。だから夫に頼み、あの子の面倒を見てもらいながら、あの山の中で隠れて生きて貰う事にした。でも夫は私やハクと違って普通の人間だ。慣れない山暮らしで直ぐに病にかかり、私らを置いてあの世に逝っちまったよ。本当に、最後まで良い人だった……世話焼きの所なんか、教授さん、アンタにそっくりさ』
なんと答えていいのか分からず、俺は思わず黙りこくってしまった。
『ハクが父親と一緒に暮らしている間、私も色々な術を完成させた。見た目を誤魔化したりもお手のもんさ。色々なやばい奴らとの繋がりもできて、戸籍や証明書何かも手に入れた。さっき言ってた教授さんへの贈り物もそうさ、ハクの新しい証明書類だよ。全部偽造だけどその辺のパチもんと違って作りはぴか一だ。ちょっとやそっとじゃバレないから安心して使いなさいな』
「貴方がその気になれば、ハクと一緒に暮らせたんじゃないんですか?身分を偽ってでも、一緒に暮らしてあげれば、」
『甘いね教授さん……』
「甘い?」
『ああ、甘々だよ。狗神の血が影井だけだと思ってるのかい?』
「そ、それは……」
『狗神筋はまだまだ根深くこの日本を蝕んでるのさ。もちろん全てが全て悪いものでは無い。狗神落としの血を脈々と受け継ぐ者もいる。けれど、少なくともこの狗神の邪法を手に入れたがっているのは、影井だけじゃないのは確かだよ』
「つまり、これからもハクは……」
『そうさせない為に、教授さん、あんたにハクを預けたんだよ……』
「そうさせない為?」
『ふふ、決まってるだろ。私は十分力をつけてきた。そして今はハクも安全な場所にいる。だとしたら、私が取る次の行動くらい、教授さんはお見通しだろ……?ふふ、あははははっ!』
「まさか……!?」
『いつか奴らを根絶やしにした時は……その時は……それまで、あの子を頼んだよ……教授さん……』
「まだ話は終わっていない!静子さん!静子さん!?」
──ツーッツーッツーッ
通話はそこで切れてしまった。
手から滑り落ちるように、スマホが床に転がった。
いつの間にか日は沈み、あれだけ煩かったセミの鳴き声も、今は遥遠くに感じる。
ひぐらしの鳴き声が、不気味な前触れでも告げるように、ひっそりと鳴り響いていた。
帰り支度をし大学を出た俺は、マンションの近くで見慣れた顔と出くわした。
「椿……?どうしたこんなとこで」
「あっ、教授!」
「あ、ああ、お前家こっちじゃないだろ?」
「そ、そんな事知ってますよ!は、ハクちゃんの様子どうかなあって思って……あれ?教授、何か元気ないですね、何かありました?」
「へっ?ああいや、大丈夫、何でもないよ。ハクの様子だっけ?元気にしてるよ。最近料理が上手くなってな、晩飯はハクが作ってくれてるんだ」
「ふ、ふうん……晩御飯ですか、そ、そりゃあいい奥さんになりそうですね……」
「奥さんって、ハクがか?想像つかんな、はははっ」
「教授はその……奥さん、見つけないんですか……?」
「えっ?お、俺か?何だ急に……ううん、俺みたいな変人じゃあな、ははっ」
「自分で言わないでください!教授はその、自分で思っているよりも、へ、変人じゃありませんから」
「そうか?ふふ、ありがとう椿。そうだ、お前も飯食っていけよ?晩飯まだだろ?」
「えっ?わ、私はそんな、邪魔しちゃ悪いし……その、」
「椿っ!」
突然、マンションの入口から此方に駆け寄る足音と声が響いた。
目をやると、白いワンピース姿のハクが此方に向かって走ってくる。
「は、ハクちゃん?わわっ!?」
ハクは椿の元に駆け寄ると飛び付くようにして抱きついた。
「聞いたぞ椿!一緒にご飯食べよっ!」
「えっ?えっ?」
戸惑う椿だが、
「一緒に食べようよお!」
「わ、分かったから、分かったから落ち着いてハクちゃん!」
「へへへっやったな先生!」
「おう、でかしたハク!」
とまあこんな感じでハクに押し切られた。
まあ俺もこんな感じで日々ハクに押し切られている気がする。
「じゃあ行きますか」
そう言って俺はハクと手を繋ぎ並んでマンションへと歩き出す。
ハクを挟むようにして、三人横に並びながら。
ハクは俺と椿の腕を掴み、途中両足を浮かせたりしてはしゃいでいた。
「おいおいハク、はしゃぎすぎだ」
「へへへへっ、だって楽しいもん、何かお父さんとお母さんができたみたいだ、なっ、椿!」
「えっ……?ええぇぇっ!?」
「ちょっ椿声デカすぎ、近所迷惑だそ?」
「あっ、先生!大変だ椿の顔が真っ赤っかだ!」
「ここ、これは違います!大丈夫です!」
「どうした椿?本当に大丈夫か?」
「大丈夫です!」
「あ、また赤くなった!椿面白いな!あははははっ」
「ハクちゃん!!」
その日、俺達は三人で食卓を囲んだ。大勢で食べるのは楽しいからと、ハクがまた来てと椿におねだりしていた。
俺は二人のそんな光景を目の当たりにし、こういうのも悪くないと、ふとそう思った。
翌朝、ポストを開けると、昨日静子さんが言っていた書類が届いていたのを確認した。
ついでに朝刊を手に取とり、俺は大学へと向かった。
駅のホームに着き徐に新聞を広げると、そこにはこんなニュース記事が書かれていた。
──徳島に住む、影井 清隆氏が、今朝、自宅で遺体となって発見されました。また近くには影井氏の秘書と思われる男性二人の遺体も見つかっており、警察は事件事故、両方の線で捜査しているとの事です。
影井が……死んだ。
思わず席から立ち上がった時だった。
ホームに電車が近付き、滞留していた人混みが一気に流れ出した。
みな乗り遅れまいと電車の自動ドアに向かう。
力ない足取りで俺も自動ドアに向かった、その時だった。
「またね、教授さん……」
耳元でそう囁かれた。
釣られて振り向くと、長く美しい髪と、透き通るような白い肌をした女性が、此方に一別し、人混みの中に姿を消した。
駅のスピーカーからサイレンとアナウンスが鳴り響く。
人混みは消え、駅長のアナウンスが流れ終わった。
呆然と立ち尽くす中、ふと、昨日の静子さんの声が、俺の頭の中で静かに再生された。
『根絶やしにするまで……』
額に浮かぶ汗を手で拭った。
夏だと言うのに汗はひんやりとしていて、それが冷や汗だと分かったのは、しばらく呆然とした後だった。
いつか……また。
─了─

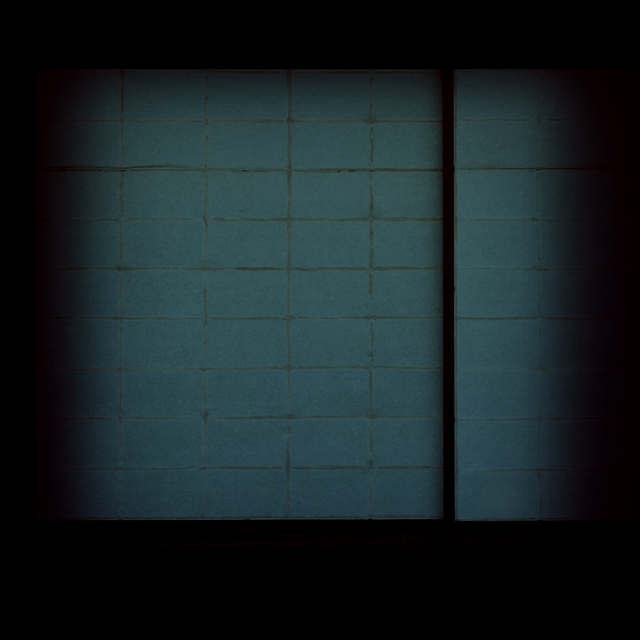



作者コオリノ
その日、俺は狗神をその身に宿した一人の少女と出会った。
素敵なイラスト作家様
↓↓↓狗甘 マグマ 様
Twitter→@magma_maniac