これは私の知り合い通称ヲタ君が、学生時代に体験した話を一部、私の脚色を用いて書いたお話です。
長文で申し訳ありませんが、良ければお付き合いください。
ちなみにヲタ君というのは、高校一年生自称エロゲ大好きで、同級生達からキモヲタ呼ばわりされていた頃のあだ名らしいです。
以後、ヲタ君の語り。
俺は今、母方の亡き祖父が残してくれた、古い日本家屋の二階建て一軒家に、一人で住んでいる。
所々住みやすく改築はされているものの、この大きな屋敷に一人で住むのは余りにも不便だが、悠々自適な一人暮らしをおくれる事に関しては大満足だった。
が、ある日、俺の家に家庭教師が来る事になった。
母子家庭で、しかも息子を一人置いて遠方に単身赴任中、ろくに俺の面倒が見れていない事を危惧しての、母親の行動らしい。
せっかく夏休みの間はエロゲ三昧という至福の時を送る予定だったのに、と悔しさを滲ませる一方、母親から仕入れた情報に気になる点が一つあった。
家庭教師は知人に紹介してもらったらしく、美人の女子大生との事。
これが悪質な釣りだとしても、一応確認だけはしておきたい。
そう思い、もとい開き直った俺は、朝から夕方までエロゲーをやりながら、二階にある部屋で一人、やがて来るであろう家庭教師を待っていた
──ピンポーン、と、突如玄関の呼び鈴が鳴った。
誰だ? と思ったと同時に、母親との会話が脳裏に蘇る。
『女子大生……』
いざとなるとやはり焦る。
期待はしていたものの、コミュ症の俺には難易度が高いミッションだと、今更ながらに気づかされる。
早まる鼓動を抑えながら、俺はPCの電源を落としたのち、全てのエロゲーを机の下に隠す。
部屋を出ようと襖に手を掛け、立て付けの悪さに苦戦しながら戸口を引いたその時だった、
フッと、何かが俺の眼前を横切った。 横切った先を瞬時に目で追う。
shake
「えっ……?」
それは、余りにも突然の事だった。
部屋の入り口、何もない空間からスーッと透き通るような白い足が、僅かに宙に浮いた格好で、くねくねと姿を現したのだ。
一瞬唖然とする俺、だがすぐに我に返り
「うわっ!」
と、短く驚きの声を上げた。
足はのた打ちながらその場で身動きすると、スーッと消えてしまった。
俺は息が詰まりそうになり、飲み込んだ息を吐きだすようにしながら 、
「はっ、はぁっ……」
小さく声を漏らす、だがすぐに苦笑いを浮かべ、
「またか……」
と力無く呟く。
そう、またなのだ。
実はこういった事が俺には昔から多々あった。
ふと振り向いた物陰に、一瞬だけ人の顔が見えた。
何となく見ていた風呂場の壁に、手形の様なものが見えた、などなど。
まあ簡単に言えば俺の思い込み、妄想の類い、もっと平たく言えば壮大な勘違い、果ては幻覚というやつだ。
小学生の頃、俺は同級生に対し、得意げに、
『俺、幽霊みたぜ』
何て言ったりしていた。
子供特有の目立ちたい、驚かせたい、などという、そういったありがちな思いだったんだろうけど、我ながら痛い子だったんだなあと、今更ながらにしみじみに思う。
見える、言わばこれは自分を特別に見せたいがための偽装に過ぎない、 と俺は思っている。
自分は特別なんだと、周りとは違うんだと言い聞かせ、周囲から切り離された自分を正当化する手段。
そう、高校に入って周りの同級生をみる度に、今までの自分が間違っていたんだと痛いほど思い知った。
だいたい、オタクで根暗なうえに電波とか、これ以上救いようがないじゃないか。
それならオタクで根暗の方がまだましだ。
俺は人生の最低ラインを保ちつつ、趣味を楽しみながら引きこもる事を選んだ人間だ。
幽霊だのなんだのとそんな非現実的な事に、一々囚われて生きていくなんてたまったもんじゃない。
そんな事を頭の中で悶々と考えていると、
──ピンポーン、と再び呼び鈴が鳴った。
俺は振り払うように頭を二三度振り、階段を足早に掛け降りた。
忍び足で玄関の扉に近づくと 、そっとのぞき穴から外の様子を伺う。
玄関の扉の前で、呼び鈴に指を掛けたまま立ち尽くす女性の姿が見て取れる。
腰まである長い黒髪に、切れ長で物憂げな大きな瞳、なるほど、と、俺は一度だけ頷くと、今回ばかりは母親に感謝した。
逸る気持ちを押さえ込むように、扉の前で手もみしつつ、
「落ち着け、落ち着け……」
と、自分に言い聞かせた。
何せクラスの女子とさえまともに会話した事がない俺が、女子大生と話をするなんて事は、天地がひっくり返っても有り得ない事だったからだ。
すると突然、ガチャリ、と金属がゆっくりと噛み合うような音が鳴り、同時に目の前の扉が開かれた。
思わずドアから後ずさる。
するとドアの合間から、
「あ? 開いてる」
と、女性が顔を覗かせ一言呟いた。
俺は余りの突然の事に頭の中が真っ白になって、目の前の女性をガン見したまま唖然。
そんな俺を余所に女性は、
「あ、すみません勝手にドア開けちゃって、失礼しました。 私、政子おば様の紹介で来ました、○○千都(ちづる)と言います」
と、丁寧な挨拶。
女性、以後先生は自己紹介を終えると、こちらに向かって頭を下げてきた。
先生の長い黒髪が波打つようにサラサラと揺れる。
対する俺は口をポカンと開けてマヌケな顔のまま。
「あの、……どうかされましたか?」
と、先生。
俺は何とか自分を落ち着かせ、取りあえず先生に家に上がってもらうと、ろれつの上手く回らない口調でなんとか自分の部屋へと案内した 。
「凄い……家ですね……」
階段を登る途中、不意に後ろから声を掛けられた。
「じ、じいちゃんの弟さんが昔住んでたそうです。 そ、その弟さんが亡くなって僕達がここに引っ越してきたんですけど、まさかこんなに広い日本家屋に住む事になるなんて、僕自身思ってもいませんでした。所々改築はされてますけど……」
俺が何とかそう答えると、
「あ、そうではなくて……いえ、何でもありません」
と、先生は何か言うのを躊躇うような素振りを見せ、結局口を閉じ押し黙ると、それ以上は何も聞いてこなかった。
先生のその反応が気になったが、次は何を話せばいい? どんな話題を振ればいい?
などというくだらない思考で頭の中がいっぱいだった俺は、それ以上はなにも聞き返さなかった。
やがて階段を登りきり自分の部屋の前までやってきた。
先生は階段を登りきった所でしきりにキョロキョロと辺りを見渡している。
そんなにこの家が珍しいのだろうか ?
一部改装はされているものの、明治の頃に建てられた歴史ある家らしいのだが、俺からしてみればただの古い家、だだっ広く埃臭い古屋敷だ。
胸のうちで悪態をつきつつ、部屋の入り口である襖に手を掛ける 。
この襖がなかなか融通のきかないやつで、普通に引いても開かないという曲者。
おそらくこの屋敷で、ダントツの立て付けの悪さだ。
「こ、この襖立て付け悪くって、」
俺は苦笑いを浮かべながら、軋む襖を開けた。
ガタガタと耳障りな音が鳴る。
「あの、実はお話がありまして……」
不意に後ろから先生が声を掛けてきた。
俺はハッとしながらも急いで部屋に入ると、近くにあったしわくちゃの座布団を先生の前に差し出し、正対するようにして自分も座った。
「あ、はい、何でしょうか?」
今後の授業の説明かなと思い聞き返す。
すると先生は、そんな俺に腰を下ろしながら徐に口を開いた。
「実は……大変申し訳ないのですが、 今回のお話はなかった事にして頂きたいんです」
一瞬、えっ何で? と言いかけたが 、俺はすぐにその意味を理解し、思わず喉元まで出掛かっていた言葉を呑み込んだ。
つまり先生は今日、俺の家庭教師として来たのではなく、家庭教師を断りに来たというわけなのだ。
俺は自分でもよく分からない、消失感にも似た感情にかられた。
まあありきたりに言えば、ただ哀しかったのかもしれない。
俺の人生からしてみれば、父親に見放され、クラスメートからも見放され、人に嫌われてばかりの人生だ。
今回だって、俺を見て引き受けたくないと思ったのかもしれない。
悔しさよりも、とめどなく惨めな思いが胃の辺りをギュッと締め付けてきた。
腹の内からこみ上げてくる何かが、口の中で苦々しい味へと変わっていく。
俺はうなだれるように俯き、今の心境を悟られまいと、なんとか必死に笑顔を作り再び顔を上げた。
だが、その時だった。
俺の視界に、映りこんではいけないもの、いや、正確には映ってはいけない異質なものが飛び込んできたのだ。
足先から手先までが一気に氷付き、胸を突き破りそうなほど心臓が、ドクンドクンと暴れだす。
焦点が合わない、いや、合わせたくない。
だが、意に反するように、俺の両目はその異質な物体に吸い寄せられていく、そしてそれが何なのか、脳が理解するのにそう時間はかからなかった。
先生の肩越し、正確に言うと部屋の入り口、中途半端に開いた襖と柱の間、暗闇の中、襖の隙間からこちらを覗く、能面のような、
宙に浮かぶ女の生首……。
氷の塊を首筋に押し付けられたかの様に、俺はその場で身体を仰け反らせ、
「うわぁっ!?」
と、短い悲鳴を上げてしまった。
すると先生は
「えっ?」
と言って小首を傾げながら俺に不振そうな視線を送ってきた。
やばい、と思いとっさに、
「あ……いや、さ、寒くないですか? ふ、襖閉め忘れてたから風が入ってきてるのかな……」
などと誤魔化し、俺はその場から立ち上がって部屋の入り口へと向かった。
俺は喉をゴクリと鳴らしながら、目の前のわずかに開いた襖に視線を向けた。
今まで見てきたこの類のやつは、全て気のせいだと思ってきた。
さっきだって、先生が来る前に部屋の前で見たやつは、一瞬で視界から掻き消えた。
ずっとそうだったはずだ。
得体のしれない火の玉、水面に写る不気味な笑みを浮かべる老婆のような顔、それらは忽然と姿を消し、俺を嘲笑ってきた。
見間違え、勘違い、自分には霊感がある、などといった電波な考え、そんな風に見えたらと思う、俺の妄想癖の名残、だったはず……。
だが、今目の前にある女の顔、生首は……消えない。 女の顔はその表情を一片たりとも崩す事なく、襖の隙間に浮いていた。
まるでそこにいるのが、さも当たり前のように。
年は二十代ぐらい……どこか幼さの残る女の顔にそっと近づき 、目を背ける準備をしながら、見上げるようにしてそっと覗き込む。 首の断面がえる。
グロテスクな血肉の塊かと思いきや 、黒い……どこまでも黒い。
首の断面には真っ黒な闇が広がっていた。
心臓がバクバクと激しい音を刻んでいた。
余りの鼓動の激しさに呼吸が乱れ、ひゅうひゅう、と、口から息が漏れた。
俺は頭がおかしくなったのか……?
微かに震える手で襖の取っ手を掴む 。
そのせいでカタカタと襖が小さく鳴った。
俺は激しく鳴り続ける心臓を左手で無理やり押さえつけながら俯く。
落ち着け、いつものあれだ、悪い病気だ、
自分の今の状況に当てはまりそうな事を何でもいいから心の内で呟く。
幻だ……きっとそうだ、強く、もっと強く念じろ。
そうやって自分に言い聞かせ無理やり現実へと引き戻すと、俺は頭上を見ないようにして襖を閉めようとした。
待て……
俺はふと襖の建て付けの悪さを思いだした。
もしかして……。
今までの建て付けの悪さはこれのせいか!?
頭の中で嫌な映像が浮かぶ。
襖を閉めようとする俺、女の生首に襖が引っ掛かり閉まらない。
シュールにも見えるが、今の現状を考えると洒落にならない。
wallpaper:1
俺はさっと身を引くと、襖から手を離し、その場で踵を返して元の場所へと戻った。
そして自分に言い聞かせる。
見るな、見なければ消える。
家庭教師なんていう妙なシチュエー ションのせいで頭がテンパってるだけだ。
俺が必死に頭の中で何かしら言い訳を考えていると、それまで黙ってこちらを注視していた先生が、重苦しい空気を振り払うように、突然口を開いた。
「なぜ……なぜ襖を閉めないんだ?」
瞬間、俺は両肩をビクりと震わせ先生の顔を見た。
その声は、とても先程までの物静かで丁寧な口調とは違い、威圧感漂う物言いだった。
目つきも精鋭さがまし、見つめ返すと射竦(いすく)められてしまいそうだ。
というか……先生は今、俺に何て言った……?
襖をなぜ閉めない?
なぜそんな事を聴くんだ? いや、襖を閉めに行ったのに閉めなければ確かにおかしい、
そう思いながら恐る恐る襖をチラリ と見やる。
女の顔はもうそこにはなかった。
俺はホッと胸をなで下ろす。
良かった、やっぱり気のせいだったんだ。
肩の力が抜け全身の硬直が弱まっていくのを感じる。
俺は軽く息を整えると、先生に向き直って、
「あ、いえ、建て付け悪いってさっき言いましたよね? し、閉めるのけっこう面倒だし後でいいかなって、」
と、俺がそこまで言いかけた時だ、 先生は俺の話を遮るように切り出してきた。
「女がそこにぶら下がっていたから閉まらない、の間違いじゃないのか?」
射すような視線、吸い込まれそうな程の先生の黒い瞳が、俺を捉えて離さない。
妖艶なその瞳に見つめられ、 全身の毛が逆立つような感覚に襲われる。
「それ借りるぞ」
先生はそう言うと急に立ち上がり、 窓辺の机にある椅子に手を掛け 、襖の方へと持っていった。
そこで俺はある妙な変化に気が付いた。 先生の雰囲気が、さっ きとはまるで別人のようだ。
おしとやかな、何て言うイメージは既に俺の頭からは掻き消えていて、 変わりに、粗暴で、自信に満ち溢れているような人、という印象へと塗り替えられていた。
「あの、ど、どうしたんですか急に ?」
椅子を襖に寄せ、先生は俺の問いには答えず、椅子の上に登り立ち上がろうとしてこちらを向き口を開いた。
「覗くなよ? 今日穿いてないんだ 」
一瞬、俺の頭は真っ白になりかけた。
「えっ……ええっ!?」
と一人喚き立てる。
何を言ってるんだこの人は!?
「嘘だよ、興奮するな変態」
先生は蔑むような冷たい眼差しで俺に言うと、再び襖の方に向き直り、天井の梁(はり)の部分に手を伸ばした。
先生が手を伸ばした梁の部分に俺も目をやる。
「あった……」
先生は梁の部分を弄(まさぐ)る手をピタリと止めてそう呟いた。
そして親指と人差し指で何かを摘み ながら、椅子からゆっくりと降りだす 。
「こいつが何か分かるか?」
先生はそう言うと、指で摘んでいたものを俺の前に差し出してきた。
俺は顔を近づけてそれを注視する。
それは、薄汚れ埃が混じった、細い小さな繊維のようなものだった。
細かく刻まれた小さな糸の束にも見えるが、それよりも更に細い。
「何かの……繊維、ですか?」
俺が自信なさげにそう答えると、先生は俺に、
「そう、まあ縄だな、けっこう古い 」
と言ってから、指先で摘んだまま、 その繊維の塊をこすった。
すると繊維の塊は、まるで砂のようにパラパラと分解され、先生の手の平へとこぼれ落ちていく。
確かにかなり古いものだったらしい。
先生は黙ったままそれを部屋の隅においてあるゴミ箱に捨てた。
そして襖を見ながら言った。
「この縄で吊ったのか……」
吊った?
梁の柱の一部に目をやる。
繊維の塊があった部分が、何かの圧力がが掛かったかのように一部凹んでいる。
「他に何か見たりしたか?」
先生が突然聴いてきた。
何かとはつまり、さっきのようなやつの事か? それなら昼間……
俺はそこまで思い出して。
「あっ、」
と小さく声を漏らした。
思い出し掛けた俺の脳裏に、嫌な映像が浮かんだからだ。
階段を下る途中に見た、あの透き通るような細い足。
まるで何かにぶら下がったように足をぶらんとさせすぐに消えた。
あれはつまり、首を吊った時の女の足だったのか ……
「ふふ、」
背筋が逆立ち、すっかり萎縮してしまった俺を見ながら、先生が微かに笑う。
冷笑というか、何というか乾いた笑みだった。
だが、さすがの俺も今日会ったばかりの人間に笑われ馬鹿にされるのは納得がいかない、思わず聞き返した。
その笑みの正体について。
「な、何がおかしいんですか?」
すると先生は一瞬間を置いてから、 耳元を覆い隠していた長い黒髪を緩やかに掻き上げた。
改めてみると、やはり綺麗な人だと思い知らされる。
だが今はそれすらも腹だたしく思えた。
だからといって何でも許されるなんて思ったら大間違いだ。
「すまん、お前の事を笑ったんじゃないんだ」
「えっ?」
思いがけない言葉に、俺は思わず小さく驚きの声を漏らした。
というか、少しはにかむように謝る先生は何というか……可愛い。
「嬉しかったんだ、こんなとこでこんな拾いものができるなんて思ってもみなかったから」
「ひ、拾いもの?」
意味が分からず、俺はすぐに先生に聞き返す、だが先生はその問には答えてくれず、代わりに、
「家庭教師の件、やっぱり引き受けるよ」
と、今日会った中で一番優しい笑みで返してくれた。
どういう心境の変わり方をしたのかは分からないが、俺は先生が家庭教師を引き受けてくれると言ってくれた事が、素直に嬉しかった。
正直得体の知れない人という気持ちは拭えないが、それ以上に湧き上がる好奇心が、今の俺の心を支配していた。
言葉に言い表す事が出来ない不思議な感覚が、目の前にいるこの先生から感じ取れるような気がした。
「ただし、条件が二つある」
「条件……ですか?」
突然の先生の言葉に、俺は困惑しながら聞き返した。
「ああ、一つはさっき起こった事を誰にも話すな」
そう言って先生は襖の方を指差した 。
さっきの事とは、先生が襖の女に気付いていたということだろうか? そしてその後にとった行動の事?
俺が考え込むと、先生はそれに構わず口を開く。
「二つめ、そこの……ええと何だ、机の下の不埒なヤツは禁止だ、そんなの買う金があったら参考書の一つでも買え」
そう言って頭を軽く叩かれた。
俺は途端に頬が熱くなり顔を伏せた。
そして心に誓った、隠し場所を変えようと……
「ふう……今日は断るつもりできたから何も持ってきてないんだ、だから勉強を見るのは次からになるがいいか?」
先生は徐に立ち上がりながら言った 。
もちろん俺は、
「はい!」
と、即答し、もう帰るであろう先生を見送る為立ち上がろうとした。
すると先生は手のひらをこちらに向けながらそれを制止した。
「いや、見送りはいい、まだ……アレが少し残っているから」
そう言いながら、先生は襖の梁の部分に目をやった。
俺も釣られて思わずその部分に目をやる。
先ほどの異様な光景が脳裏に蘇る、洒落にならない。
背筋に寒気を感じ身を強張らせていると、先生は俺に背を向けたまま、呟くようにこう言った。
その言葉を、俺は生涯忘れることはないだろう。
「なあ……この家、一体何人死んだんだ?」
そう言って、先生は俺に突き刺すような冷たい視線を向けてきた。
俺はまるで、冷たい刃物を首に突きつけられたかのような感覚に襲われ、思わず後ずさりしてしまった。
だが次の瞬間、
「オォォォォッ!」
突然、どこからともなく地の底から響くような呻き声が、家の中を一斉に駆け巡った。
逆立つ鳥肌に身をよじりながら、俺は顔を強張らせながらその場で硬直してしまった。
押し潰されそうな圧迫感に不意に襲われる、音もなく得体の知れない何かが、背後から迫ってくるような感覚。
「な、何なんですか今の!?か、風の音ですよね?」
締め切った窓を確認しながら、俺は辺りをキョロキョロと見渡す。
「ごくり……」
静寂に包まれた部屋の中、俺の喉元から息を呑む音が大きく鳴った。
無意識に握った拳に、じんわりと嫌な汗が滲む。
「今のは警告……だそうだ。じゃあ、またな……」
唖然とする俺をよそに、先生はそう言って、悲しげな表情のままその場で踵を返し、部屋から出ると、襖をそっと閉めた。
階段を降りる先生の足音が、ゆっくりとフェードアウトしていく。
俺はふと、先生がこの部屋から出ていくのを思い返してハッとした。
襖はまるで、新築の家の襖のように、 静かに、そして滑らかに閉まった。
ただし、僅かばかり、縄紐くらいの隙間を残して……
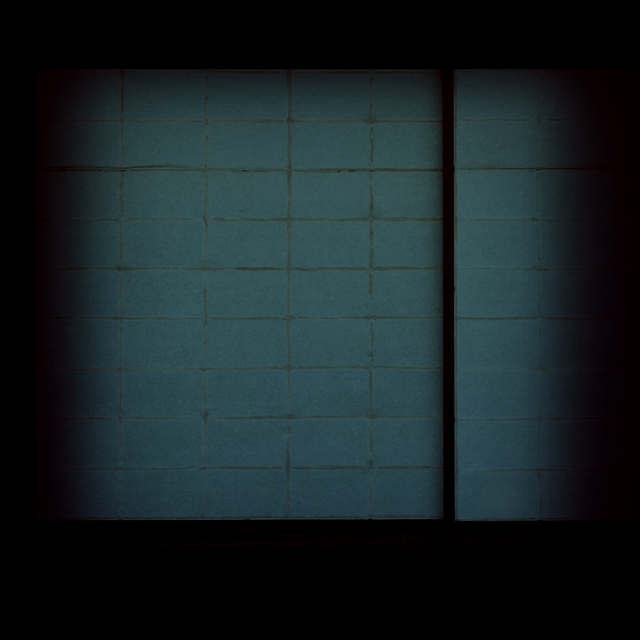



作者コオリノ
もう4~5年前に書いた話です。
今でさえ幼稚な文章が更に…続編を書くにあたって投稿しました。お目汚しでなければいいのですが…
第二話へ続きます。→http://kowabana.jp/stories/25758
一話完結型となっております。
以前のアカウントを削除し、新アカウントで新しく執筆しなおし中でございます。
以前書いたものにコメント、怖いをくれた方には本当に大変申し訳なく思いますが。
これからも変わらず応援して頂けると幸いです。
反響があれば、今後も執筆を続けていきたいと思っております。