月並みだが時が経つのは早いもので、彼が死んでからもう10年と言う歳月が過ぎようとしている。
この10年は私にとって幸せだったのだろうか?
それとも不幸せだったのだろうか?
最近はこの木を見ると、そんな事を考えずにはいられない。
私の目の前にある、手を回す事が出来るかどうかというこの木は、私にとって希望そのものである。
その木は私の自宅兼、研究施設の敷地内にある。
私はしゃがみ込み、木の幹にある一際大きく、異様な瘤に手を当てる。
手には幹の感触、そしてその木の脈動が伝わってきていた。
どうやら予定通り、今夜あたり収穫となりそうだ。
私はそれを確信すると立ち上がり、自宅に戻るべく歩みを進めた。
今夜に備え、昼は寝ておかなくてはならない。
自宅に戻ると、逸る気持ちを抑える為にお茶入れた。
私は毎年この日が来るのを心待ちにしていた。
お茶をゆっくり飲み終えると、私は床に着いた。
==============================================================================================================
幼い頃に大病を患い、学校に通う事がなかった私の原初の記憶は、研究室にて両親の姿を楽しく眺めてるところから始まる。
私の育った環境は、両親が共に農学の研究者で、自宅が研究施設兼ねているという、ちょっと特殊なものであった。
しかし、幼なかった私にとってはそれが世界の全てであり、それに対して特に疑問を持ったことはない。
やがて自我が芽生えてくるに従い、私は両親のやっていることに興味を持ち始めた。
まぁ、目に入るものすべてが両親の仕事に関係する物なので、当たり前と言えば当たり前と言えた。
「これはなに?」「あれはなに?」と聞く私に対して、両親は特に面倒くさがることなく、私が理解できるよう解りやすく説明してくれていた。
両親は十分な愛情を私に与えてくれたし、私もそれを十分に感じることが出来た。
多分に閉鎖的ではあったのかもしれないが、私を取り巻く環境は子供が育つ上で、ほぼ理想的な環境だったのかもしれない。
両親の英才教育の賜物か、それとも私の好奇心が強いせいか、他の子が小学校卒業する頃には、私は既に高校生並みの知識を持っており、また中学校を卒業する頃には大学生ぐらいの知識を持っていた。
もっともそれは、生物や数学、化学と言った知識に限定された話だが。
やがて、高校生に上がる歳になった私は、進路について選択を迫られた。
そろそろ高校に進学し社会との接点を持つべきか、それともこのまま両親の手伝いをして、専門的な分野にもっと特化していくべきか。
既にこの頃の私は、両親の助手を務められるほどになっていた。
悩んだ挙句、私は高校に進学することを決めた。
理由としては、既に病はその兆候すら見せていなかったし、さすがにこの歳になれば自分の状況の異常さに気付き始めていたからだ。
しかし、この選択は高校に通うようになって、すぐに後悔する事となった。
理系の科目については始めから問題にもしていなかったし、他の科目についても優秀とまではいかないまでも、それなりにこなすことは出来た。
問題は人間関係にあった。
周りの人間が幼く見えて仕方なかった。
大して面白く思えないようなことばかり話題にしたり、どうでもよい事で人を貶したり嘲笑したり。
自ら進んで人間関係を持とうと思える人間が、少なくとも同年代には居なかった。
だが、それと同時にそういったことを理由にして、他人を避けている自分にも気づかされた。
今思うと、それまでの人生で両親としか接点のなかった私は、他人と関係を持つことを恐れ、無意識に他人を避けていたのだ。
結局3年間、私は一人も友達が出来なかった。
それでも私は、大学に進学する事を決めた。
大学に行くと、少し状況が変わっていることに気付いた。
僅かではあるが、私は自然に人と接することが出来るようになっており、友達と呼べる人も数人出来た。
恐らくは、農学部に進んだせいで、同じような事に興味を持つ人が周りに増えたことと、皆少し大人になって大学内で過ごす上で、政治的な理由から友達を作る事が必要になったからだと思われる。
しかし、それでも初めての友達と言える存在であり、私は純粋に嬉しかった。
少し恥ずかしいが青春と言うものを感じていた。
そして、大学に通い始めてから2年が経った頃、私についに彼氏というものが出来た。
馴れ初めについては特に変わったことはない。
友達から聞いた体験談と似たり寄ったりであり、ごく平凡な推移を経て、私たちはそうなるべくして付き合うようになった。
強いて言うなら、私は彼に対して自分との対称性を見出したのだ。
彼は、幼い頃に両親を亡くしており天涯孤独の身であった。
彼は中学卒業と同時に預けられていた擁護施設を離れ、自分で生計を立てるべく仕事を始めた。
やがて夜間の高校を卒業し、私の通う大学にやって来た。
彼は同期で私の大学の夜間部に入学してきたが、二つほど年上だった。
それは浪人をしたからというよりは、境遇によるハンデによるもので、彼にしてみれば当初の計画通りであった。
彼と私とは、取り巻く環境が何もかも違っていた一方、趣味や興味の対象が妙に一致しても居た。
そんな彼が私は大好きだった。
正にそれは、私の人生の中での絶頂期であった。
しかし、絶頂期と言うのは読んで字のごとく頂であり、頂は狭いからこそ頂なのだ。
私の幸せはそう長く続かなかった。
まず、両親が亡くなった。
両親は私が大学に通うようになってからというもの、少し私から距離を置いていたようだった。
こういうと両親の愛情が薄れたと思うかもしれないが、そうではなかった。
私が大学に通うようになり、友達もできたことで二人は安心し、次の段階へ移ったのだ。
つまり、私に対して自立を望んでいたのだ、決してそれは愛情が薄れたという事ではない。
ある日、両親は2週間ほどの予定で、海外旅行へ出かけた。
考えてみたら、私はそんなに長く両親と離れいて居た事はなかった。
しかし、それに対して特に不安を感じたりはしなかった。
二人はその旅路において、飛行機事故で亡くなったのだ。
遺体は発見することが出来ず、私は二度と両親の姿を見ることが出来なくなった。
私は両親を失ったことにより、自失した。
それから一月ほど、私は再び社会との接点を持たない生活をし続けた。
幾度か彼からの電話もあったが、それに出ることもしなかった。
しかし時は、人の悲しみを癒すものらしい。
私は段々と自分を取り戻していった。
そのきっかけは、彼の事を思い出したことから始まった。
彼も両親を亡くしていたが、それでも前を向いて立派に生きている。
そう思ったら何時までも沈んでいる自分が恥ずかしくなり、そして無性に彼に会いたくなったのだ。
私は彼の携帯に電話をかけた。
しかし、彼は出ない。
家の電話番号にも電話かけた。
やはり出ない。
私は居てもたっても居られなくなり、彼の家に向かった。
そこで見たものは、ベッドの中で静かに眠る彼であった。
その傍らには瓶があり、どうやら睡眠薬であるらしかった。
彼は自殺していた。
私の心の中を、形容のしがたい感情が駆け巡った。
それは両親を失った時とは別種の感情であり、酷く耐えがたいものであった。
彼は私の中で、もはや一番大事な人だった。
私は両親の願い通り、自立していたのだ。
誰かの庇護を離れ、他の誰かを大切に思う。
誰かのために生きようとすること、それが自立なのだ。
形容しがたかった感情が後悔という形になり、私の中で渦巻いた。
なぜ彼は死んだのか?
なぜあの時に自分の事だけばかり考えて、彼の電話に出なかったのか。
なぜ力になってあげられなかったのか。
そして、なぜあの時に力になって貰おうと思わなかったのか……。
==============================================================================================================
目が覚めると、夜の10時を少し回っていた。
昔の夢を見ていたせいであろうか、眠りが深かったようだ。
私は急いで自宅を出ると、研究施設内の例の木へ向かった。
昼間確認した幹の瘤は、木の薄皮がはがれ始め一部“実”が見えていた。
“実”は昼間より、その脈動を顕わにしている。
りーりーりーりーりーりー。
秋の虫達が、けたたましいぐらいに鳴いている。
私は収穫作業を始めた。
ゆっくりと、丁寧に、細心の注意を払って、木の薄皮を剥がし始める。
徐々にだが“実”が姿を現し始める。
それは人の形をしていた。
今年は去年より出来が良いらしい。
りーりーりーりーりーりー。
やがて全ての瘤の薄皮を剥がすと、私は“実”を幹から取り出した。
それは人の形をしているが、明らかに人とは違うもの。
皮膚が一部しか覆われておらず、それ以外の場所は筋組織が直接外気に晒されている。
所々、欠損や奇形も見受けられる。
あるべきところに指が無い。
あるべきでない所に耳がある。
それは簡単すぎる間違い探しである。
りーりーりーりーりーりー。
しかし、それは紛れもなく生きている。
私はそれを研究室に慎重に運び込んだ。
「仁瘤朴(ジンリュウボク)」
その木の名前だ。
もっともそれが正しいものかどうかは分らない。
この木が研究施設の一角に植えられていたことを、両親の遺品整理の時に初めて知った。
恐らく名付け親は、父親と思われる。
もちろん一般に公表もしていないだろう。
この木は、ウツボカズラやモウセンゴケの捕虫葉に代表される、食虫植物に似た一種と思われる。
他の生物を捕食するのだ。
しかしこの木が他の食虫植物と違うのは、取り込んだ生物を成長のための栄養源とするわけではないという事だ。
それは共生体という概念が一番近い。
この木は取り込んだ生物の各器官を、成長のための道具として利用するのだ。
それは消化器官であったり、筋組織であったり、脳細胞であったりだ。
そして、成長が止まる秋の訪れとともに、免疫機能によりおそらくは遺伝子というレベルで、自身の細胞以外を排泄する。
排泄方法は、木の幹に瘤を作り、そこに免疫機能が異物と判断した細胞を集約させ、時が来たら切り離すのだ。
私はこのことを人間側からの都合で収穫と呼び、収穫物を実と呼んでいる。
収穫量は、その年の個体の成長量に依存する。
その個体が発芽間もない場合は、その成長度は最も大きくなるが、個体自体が小さいためその排泄量は決して多くない。
しかし、その個体が大きくなるにつれ、成長度は少しづつ低下するものの、その成長量は増加する。
最大でおおよそ成人男性一人分ぐらいだ。
そう、成人男性一人分。
両親については、遺体すら手に入れることが出来なかったため、諦めざるを得なかった。
しかし、彼はその姿を全て残していたため可能性が残った。
私はあの日、彼の部屋から人知れずその遺体を自宅に持ち帰り、あの木の根元に埋めた。
その時の木は、今の半分ぐらいしか太さが無かった。
1年目の収穫は、ひどいものであった。
それは決して人と言える、ものではなかった。
しかし、その細胞一つ一つは確実に生きていた。
その事に私は希望を見出した。
結局その生体反応も数分したら消え失せてしまったが、私はそれを再び木の根元に植えた。
そして翌年を待った。
2年目は昨年より、木の太さも増し、実も人の形に近づいていた。
しかし、やはりそれもまだ人と呼ぶにはほど遠い存在だった。
その年も私は、生体反応が消えるまで待ったのち、再び木の根元に植えた。
そうして繰り返す事10年、ようやく人の形と言えるようなところまで漕ぎ着けた。
今では夜空が明るくなりはじめるぐらいの時刻まで、延命出来るようになって来ている。
いつもこの収穫作業をしながら思うことがある。
果たして、これは本当に彼なのだろうか?
やがて来るであろうその日、私はそれを彼として再び愛することが出来るのだろうか?
そして、彼はそんな私を愛してくれるだろうか?
それに対しての結論も毎回同じである。
それは可能であるはずだ、他でもない私の存在がその証拠である。
愛とは、理由や結果を求めるものではない。
ただ純粋に相手を思う心さえあればいい。
かつて、両親が私にそうしたように。
研究室の机の上に寝かせた彼に視線を移す。
私はこれから一晩中彼を診つづける。
どんなに頑張ったところで、彼は次の日の昼まで持つことはないだろう。
だが、それでいい。
私は結果を求めない、それが彼を愛するという事だからだ。
私達はまるで、季節外れの織女星と彦星だ。
柄にもなくそんなロマンチックな事を考える。
私はその日が来るまで、この年に一度の逢瀬を楽しみに生きて行くことだろう。
収穫の秋を待ちわびながら……。

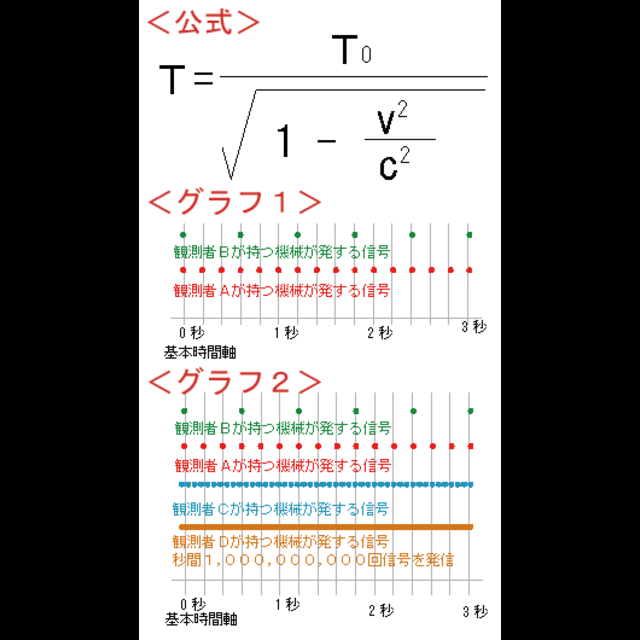
作者園長