「いのちの電話」
めったに繋がらないと聞いていた。
話を聴いてくれるのなら、全国どこにつながっても構わないと思った。
パソコンの画面に表示されている都道府県の電話番号全て
かたっぱしからかけてみたが、
そのほとんどが受付時間外か お話中だった。
二巡三巡と掛けなおす。
気が付いたら、午前1時を過ぎていた。
諦めかけた頃、受話器の向こうから、女性の柔らかい声がした。
「はい、○○いのちの電話です。どうぞお話しください。」
やっと繋がった。
「今から死にたいと思う。
その前に恨み言を聞いてほしい。」
すがりつくように話し始めた。
この10年間、身内の葬儀ばかりしている。
近所では、「呪われた家」と噂され、会う人たちは皆よそよそしく誰も近づこうとしない。
疲れた。
もう、生きていく気力も体力も財力もない。
私が死んでも悲しんでくれる身内もいない。
「いのちの電話」の女性は、否定も肯定もせず、ただ黙って頷いていた。
風邪をひいて熱を出しても、
咳をしてもひとり
笑っている時も
泣いている時も
ひとり
どんなに美味しい食事を作っても
食べるのは、私ひとり
眠る時も
いつもひとり
ひとり、ひとり、ひとり・・・この部屋でたったひとり。
「ひとりなんです私。
私が死んでも、悲しんでくれる人なんて いないんです。」
伝えたいことの千分の一も話せない。口をついて出る言葉は、せん無き事ばかりだ。
受話器の向こうで、すすり泣く声が聞こえてきた。
共感してくれているのだろうか。
この私に、同情してくれたのだろうか。
ささくれ、爛(ただ)れた心の痛みが少し和んだ。
「あなたは、一人ではないと思います。あなたのような人が、孤独なはずはない。孤独であってはいけないのです。」
幼子を諭すような優しい口調は、どこか懐かしく切ない響きを帯びていた。
「・・・・ごめんなさい。こんなこと申し上げていいのかどうか解らないのですが、怒らないで聞いていただけますか。」
その人は、躊躇(ためら)いがちに こう語った。
「このお電話を頂いた時から、あなたの声に混じって、赤ちゃんの笑い声と 赤ちゃんをあやす穏やかな男性の声が聞こえて来るのです。他にも、ご年配の方数人の声が聞こえます。
あなたは、本当にお一人でお暮しなのでしょうか。」




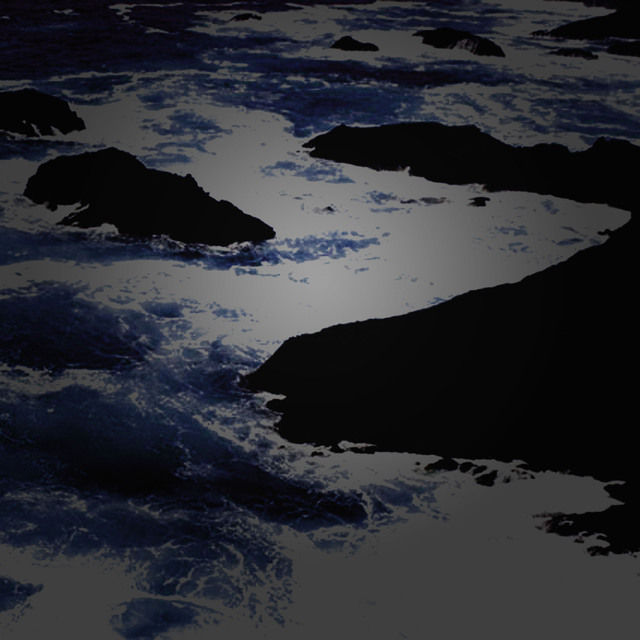

作者あんみつ姫
久しぶりの投稿となります。
今回は、短編です。
ほぼ実話ですが、怖くはありません。
あえて感動作にもいたしませんでした。
読んでいただけて、とても嬉しいです。
お世話になった「いのちの電話」
この貴い奉仕に心より感謝をささげたいと思います。