ある日、一人の若い生物工学者が一人の哲学者を訪れこう尋ねた。
「ヒトの定義とは一体なんでしょうか?」
哲学者はひとつ大きく深呼吸をするとゆっくりしゃべり始めた。
「そうですね。それは我々、哲学者にとって永遠のテーマの一つだと思います。
私の私見を述べる前にまずは、貴方が考えるヒトの定義を聞かせてもらえますか?」
生物工学者は眉一つ動かさずに、その問いに答える。
「そうですか、では僕のというより生物学から見たヒトの定義を言います。
はるか昔にヒトゲノム(人間の全遺伝情報)の解読宣言されましたが、その時に判った事があります。
それは、どの人も99.9%は同じ遺伝子配列を持っているということです。
つまり、ヒトとヒトとの個性というものは遺伝子的に見れば0.1%の物でしかないのです。」
「ほぉ……」
「つまり僕と貴方と言わず、全人類含めて99.9%の遺伝子配列を共有していることになります。
それはつまりその99.9%がヒトの定義であるという根拠に十分なりえると思いますが如何でしょうか」
哲学者は、小刻みに首を縦に振りつつ、興味深げに生物工学者の意見を聞き入っているようだった。
「なるほど、実に生物工学者らしい意見だと思いますが2~3お聞きしたいことがあります。
ご意見はヒトの定義を遺伝子配列を基にして定義を行うという事だと理解したのですが
既に死亡している人についてはどう考えますか、死亡した直後の遺体にはまだ遺伝情報は残っていると思いますがどうでしょう。
また、遺伝子に何らかの先天的な欠損や損傷がある人についてはどう判断しますか?
例えばそれによって四肢の欠損や、感覚器官に障害のある人達についてです。
またその判断結果についてあなたはどう思われますか?」
生物工学者はその時、一瞬暗い表情を見せた……。
「死亡した人については論外です。それはもうヒトというより、生物ですらありません。
遺伝子に欠損や損傷がある人達については、生物学的には定義に当てはまらないためヒトとは言えません。
しかし、心情的にいえば彼らはヒトであり人権だって存在します、それ相応の権利もあれば義務もあると考えます」
「はい、私もそうあるべきだと思っています。
人権という非常に社会的な言葉が出てきたのでついでに聞きますが、社会的見地からみた……つまり法律的な見地で考えた場合ヒトとはなんだと思いますか?」
「すみません、法律にはあまり詳しくないので僕の思い込みの部分もあると思いますが、ヒトから生まれた人はやはりヒトであるということに尽きると思います。
また、会社や団体などにも法人という形のヒトということになります」
「そうですね。ではその会社や団体などがヒトであるということについて心情的にどう思いますか?」
「法律的それらを便宜上ヒトとして扱うだけで、心情的にはヒトであるとは受け入れにくいです」
哲学者は僅かに笑みを浮かべた。
「ええ、そうですね。私も同意見です。
今、生物学から見たヒトと法律上のヒトの定義について考えましたが、どちらの定義も心情的に受け入れられない部分があったと思います。
つまりこれはそれぞれが便宜上のヒトの定義であるため、多角的な方面から見た場合に著しく受け入れがたい部分ができてしまうということです。
しかし、われわれ哲学者はこの著しく受け入れがたい部分こそが重要だと考えており、それこそがヒトの定義だと考えています」
「しかし、それは哲学的なヒトの定義であり、やはり多角的に見た場合に受け入れがたい部分ができてしまうのではないですか?」
「ええ、当然あるでしょう。しかし、他の学問や分野と違うのはそれを含めて再定義をしても哲学ではは構わないということです。
ヒトの定義というのは常にその時代ごとに変遷し続けるものであり、だからこそ我々哲学者にとって永遠のテーマとなりうるのです」
生物工学者は判ったような、判らないような顔をした。
「ははは、よく学生でそのような顔をした人を見ますよ」
「で、結局のところヒトの定義とは一体なんでしょうか?ということに戻るのですが……」
「ああ、失礼しました。今までのはこれから私が言うことはそういう立場での私見になりますという、前提であり言い訳みたいなものです」
「はぁ」
「まぁ、今しがたその時代ごとに変遷し続けるものと言いましたが。
それはあくまで枝葉であり、大筋のところでは大昔にはほぼ固定されているのです。
『ヒトは考える葦である』、『我思う、ゆえに我あり』等という言葉は聞いたことありますか?」
「ええ、言葉だけは」
「つまりはそういうことです。ヒトと他の動物とで決定的にに違う所は、ヒトは考えることが出来るということです」
「知性の有無がヒトの条件であるということでしょうか?」
「そうです」
「では、脳科学の全てを注ぎ込んで作られたAIはヒトという事になるのでしょうか?
高機能AIが人が追い付けないほどの知性を持って既に久しくなりますが……」
「ははは、すいません。これは言わずもがなの前提と思い割愛してしまいましたが、生きている物……つまり生物であることは当然の大前提になります
つまり高機能AIにどれほど知性があろうとヒトではありません。それは高度に複雑化されたただの入出力デバイスでしかありません」
それを聞いた生物学者の表情は、先ほど一瞬見せた暗い顔になっていた。
「生きている物……生物と非生物の違いはなんでしょうか?」
「これもまた難しい質問ですね、大雑把に言えばそこに魂があるかないかだと思います」
「魂?ずいぶんまた、非科学的な言葉ですね」
「ええ、哲学は科学ではありませんからね。でも便利な言葉ですよ魂。そしてあなたも無意識に魂という存在を認めていると思いますよ」
「僕は科学的に検証されたものしか信じません」
「本当にそうですか?
不謹慎な例えですが、貴方の近しいご親族が亡くなられたとします、きっと貴方はお通夜や告別式を行い墓も用意することでしょう。
しかし、その行動は世間体を考えてだけの行動ですか?もう故人はこの世に完全にいないというなら、魂の存在を否定するというなら
あなたはそれらの行動動機を100%説明できますか?」
「……」
「もし誰も見ていないのなら、故人の遺体がそこらの野良犬の餌になっても構わない。
貴方はそういう人間ではないと私は考えますが如何でしょうか。
だとするならば、理性的には魂の存在を否定しようが、心情的は魂の存在を肯定したほうが実利的ではないでしょうか」
「そ、その場合、魂の有無はどのように判別できるのでしょうか?
例えば人には魂があり、AIには魂がないといった根拠は一体どこにあるのでしょうか?」
生物工学者は、ついに顔を歪め追い詰められたような表情をしていた。
「私は私自身に魂があることを知っています。
もし、魂という言葉がどうしても受け入れられないのなら意識という言葉に置き換えても構いません。
それはただの記号ですので私にとってはなんでもいいのです。
そして貴方には貴方の意識があると仮定して私は貴方と話をしています。
しかし実際のところ、貴方に本当に意識があるかないかを私は知ることはできません。
それは貴方にしか知りえないことです、例え貴方の体を詳細に解剖したところで判らないでしょう。
哲学的ゾンビという言葉は聞いたことありますかね」
「……」
「私にはAIには魂がないといった根拠を示すことはできません。
およそ哲学者としては失格なのですが、私は直観に従いAIには魂がないと判断しました
哲学はまだまだ不完全であり、発展途上です。
現時点では何に意識があり、何に意識がないかは個人に委ねるしかありません
それはご自分でご判断くださいとしか言えません」
「……」
生物工学者は肩を落とし腰を丸めていた。
その表情は、先ほどの追いつめられたからそれから深い絶望のそれへと変化し、あたりに重い雰囲気をもたらしていた。
「あなたは今回何故このようなことを聞きに尋ねられたのですか?」
哲学者はその雰囲気に耐えられなかったのか、しぼりだすようにたずねた。
「少し…僕の研究の話をしてもよろしいでしょうか?」
「もちろん、差支えなければ」
生物工学者はポツリポツリとしゃべり始めた。
「万能細胞を使った再生医療の飛躍的な発展は、20世紀の終わり頃から21世紀の初頭にかけて数多く発見・確立した万能細胞の作製方法に端を発しています。
そうして作成された万能細胞を体中の各組織へと分化させる技術が即座に開発され、21世紀の中頃にはそうして作成された体組織を使った新しい再生医療が現場へ普及していました。
しかし、その医療方式も21世紀末頃には急激に廃れることになります。
きっかけとなったのはナノマシン細胞です。
これは複数のナノマシンから人間の細胞を構成する技術で、作成された細胞はオリジナルの細胞と見分けがつかず細胞分裂なども回りの細胞と同期をとって行う、まさに夢の人工細胞でした。
ナノマシン細胞にはには個体の遺伝情報を持たせることで、その個体のあらゆる臓器などを作ることが可能でした。
ナノマシン細胞で作られた臓器は再び病気になることがなくオリジナルの臓器の数倍もの処理能力を持つ点で万能細胞から作られた臓器よりも優れており、ほどなく万能細胞による再生医療にとって代わりました。
人類はそのうち、どこも悪くないのに体中の臓器や四肢をナノマシン細胞で作られたもので置き換えることが主流になったのはご存じの通りです。
僕の研究はこのナノマシン細胞を万能化させることでした。
今のナノマシン細胞は、作る臓器や四肢によって種類が異なり、他の部分の細胞では他の部分の細胞になりえませんでした。
僕が作り出したかったのはどの部分の細胞にもなれる、ナノマシン細胞の万能細胞ともいうべきものでした。」
生物工学者はここまで話す頃にはさっきとは打って変わって、少し興奮しているような様子だった。
どうやら自分の研究の話をするのは好きらしい。
「そして僕は、そのナノマシン万能細胞を設計し……製造しました。」
「製造しただって!?
そんな話聞いたことありません。ナノマシン細胞の開発は研究機関で稟議がなされ承諾しなければできないはずです!」
「ええ、通常はそうです。しかし僕は誰にも言ってませんから。研究施設の予約は何でもない一般的なナノマシン開発の理由で申請しましたし、実際その通りの利用をした上で余暇の持間で作成しました」
この告白に哲学者はすくなからず驚かせたようで、で生物工学者の顔を見つめていた。
「僕は造ったナノマシン万能細胞を自分の体に注入しました。
注入されたナノマシン万能細胞は体のどこかの組織に吸着すると自己増殖を始めます。
従来のナノマシン細胞で作られた臓器は、オリジナルの臓器を超えた性能を見せるのですが、僕の万能細胞は吸着した組織がすべてナノマシン万能細胞にならないとその効果は発揮しません、それまではオリジナルの組織の細胞と全く同等の働きをします。
数か月たったころ体に変化が表れ始めました。僕は従来のナノマシン細胞で体組織の入れ替えを行わなかったせいで、その変化は顕著でした。もちろんそうであるからこそ僕は僕自身を被験者に選んだのです。
初めは右腕でした、僕は気づくと信じられないほどの力を右腕で使えることに気づきました。
しかもそれは暴走することなく僕の意識の制御下に置かれ、卵を割るなどの繊細な作業からジャッキのような力を発揮することまで細かく段階的に行えるようです。
そしてその変化はそのうち、左腕、右足、左足の順に広がっていきました。
内臓の変化も起こっていたはずですが、それらについてはほとんど自覚することが出来ませんでした、しかし心臓や肺などの変化は顕著でした。
四肢が強化されても心肺機能が常人のそれである以上は、長時間での超ヒト的な行動がとれなかったのですが、間もなくそれが可能になった時、僕はついにスーパーマンなったような気がしました。
そしてついには最後の臓器のみを残すことになったのです」
「最後の臓器?」
哲学者は額の汗をぬぐった。
自分がずいぶん汗をかいてることに気づいたようだ。
「ええ、もうそこしか残っていません。脳です」
「……」
「当然、従来のやり方ではオリジナルの脳をナノマシン細胞で作った脳と入れ替えるなんてことはできません。
仮に行ったとしても、それは何ら殺人という行為と変わることがありません。
しかし僕のナノマシン万能細胞ならどうでしょう?
脳に吸着したナノマシン万能細胞は回りの脳細胞と同期をとりつつ細胞分裂を繰り返し、やがて脳全体を……」
ここにきて饒舌だった生物工学者は口ごもった。
「脳全体をナノマシン細胞化していきます。
そして先日、僕は自分の中で起きた変化にびっくりしました。
僕は瞬間視が出来るようになっていたのです。
瞬間視とは一瞬見た風景をを詳細に記憶したりする能力で、特別なトレーニングで身に付けたり、脳に何らかの疾患がある人が出来たりりするものです。
その他にもフラッシュ暗算が出来るようになったり
絶対音感が身に付いたり
見ただけで物の大きさをmm単位で言い当てることが出来るようになったり
時間の流れをゆっくり感じるよう意識的に調整したり
僕は脳全体がナノマシン細胞が入れ替わり、脳が強化されたのだと実感しました」
「そ、そんな話……信じられません」
生物工学者は短くくすっと笑うと
ポケットから20面ダイスをいくつか取り出した。
「高めに放り投げてください」
哲学者は、一つダイスをとると上空に放り投げた。
ダイスが放物線を描き、その頂点が天井ぎりぎりに近づいたころ。
「13」
生物工学者がポツリとつぶやいた。
ダイスが床に落ちて、コロコロと転がると「13」と書かれた面がちょうど上部にきて止まった。
「どういうことです?脳が強化されて未来でも見れるようになったとでも言いたいのですか?」
「いいえ。もっと簡単なことです。ダイスが放物線の頂点に来た時の向き、水平方向の角度と速度、床の硬さや衝突時の反発係数から、どの面が表になるかを計算したのです。
この程度の予測なら大気の存在を無視したニュートン力学で十分です」
哲学者はテーブルに転がっている、残り5つダイスを手に取ると一斉に放り投げた。
「3,5,8,11,17」
生物工学者は淡々と宣言し、ダイスは初めからそう決められていたかのようにその面を上にして止まった。
「……判った。仮に貴方の言うことを信じたとしてだ。
貴方はなぜヒトの定義なんて知りたいのですか?」
「万能ナノマシンはその組織がすべて入れ替わると、その臓器を超えた性能を見せると教えしましたよね
これはつまりナノマシンのモードが変わるということなのですよ。
つまり、それまではオリジナルの細胞のように振舞っていたのが細胞一つ一つがフルスペックで稼働し始めることで起こる現象なので。
その瞬間、ほんの数百万分の1秒間でプロセスが停止し、再生成される事になります。
これがつまり、僕の脳でも起こった訳です」
生物工学者はここで一旦、話を区切ると大きく深呼吸した。
「この場合僕という存在はどうなるんですかね?
一回死んで生き返った?それとも死という状態を一瞬でも潜り抜けた以上、僕の意識は完全に消滅したんでしょうか?
そうすると今の僕は、高機能AIのようにすごく複雑な、しかし機械的な入出力デバイスという事なのでしょうか?
先ほどのあなたの話一つだけ納得できないことがあります。
僕に意識があるかないかを、僕にしか判断できないとおっしゃいました、しかし、僕に意識がないのなら僕に意識がないと意識することも出来ないことになります。
いずれにしろ、特定の知性に意識があるかないかは個人に委ねられてるということなので、改めて質問させてください
そして貴方の私見をお聞かせください」
哲学者はごくりと唾をのんだ。
「僕はヒトですか?」

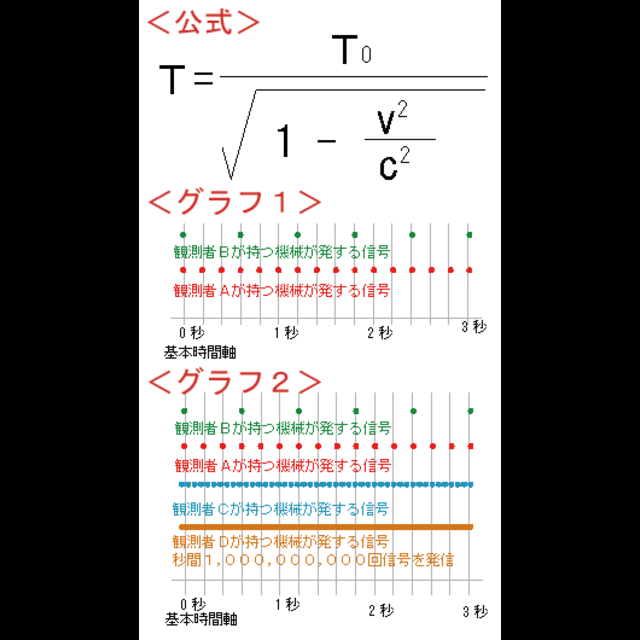
作者園長
SFホラー的な?内容です。
薄っぺらい知識で知ったかぶりして書きました。
内容の細かい指摘は聞かれても答えられない場合がございます。ご容赦ください。