ねぇ、肝試し、一緒に行かない?
私はこのラインのメッセージに、なんと答えるべきだったんだろう。友人の一人、真奈美が送ってきたこのメッセージをふと思い出して、私はそう考える。
そんなラインを貰ったのは、6月の終わりの週、土曜の昼過ぎだった。
特に部活もなかった私は、一人で食べたお昼ご飯の後片付けをして、慎重にお皿を布巾で拭いている白いのを見守っていた最中だった。白いの、というのは、私に憑いている謎多き存在だ。謎、そのものでもある。
私、田中恵美の母の実家。八塚家に代々憑いていた、蟲、とされる存在だ。
真っ白な体。真っ白な肌。真っ白な襦袢。真っ赤な舌。現代芸術家の作った、彫刻のような青年の姿。
ただしその目は、トンボのような黒い複眼。
その存在は、憑いたものを平穏無事に暮らすことを約束し、周囲に繁栄をもたらすという。
その白いのは、私にひどく懐いており、私のやることは小さな子供みたいになんでも真似したがる。お皿拭きは白いのにとってブームらしく、丁寧に磨いてくれるので私も助かる。
「ありがとうね」
私が声をかけると、白いのは嬉しそうににっこりと、歯を見せて笑った。
慎重にお皿をかごに入れ、次のお皿をそっとシンクに置き、丁寧に拭き始める。その横で私は、友人から来たラインのメッセージに、目を通していた。
ちょっと前に父親の次の仕事が決まって、我が家はようやく落ち着きを取り戻した。両親は私に心配をかけたから、というのと、情報が共有しやすいから、という理由でスマートフォンに買い替えてくれたのだ。あの二つ折りの携帯も好きだったけど、友達とラインが出来るのは正直にありがたい。高校生の社会というのも、なかなかに面倒なのだ。
その友達らとのグループメッセージには、今日肝試しに行く話が楽しそうにやり取りされていた。来るメンバーは、このグループにいる3人の女友達と、同学年の男子2名。そこに私も、一緒にいこうよ、と誘われていた。
友人たちが興奮した様子でやり取りするのを見るにあたり、どうもイケメンと話題のバレー部員である、春日井君が来るらしい。たしかに、ジャニーズ系の甘い顔立ちをした彼のことは、私もちょくちょく耳にする。サブカル系な私とは、縁のないヒエラルキーの頂点に君臨する輩である。
ただ、もう1人は部活が同じだったり、クラスが一緒だったりで、会話をしたことがある、三島君だったので、少し安心した。
「でもなんで肝試し? てか、学校から行ける位置にそんな場所、あったっけ……」
確かに、もうじき夏という季節。
でも土曜日の午後、という時間設定が、少し気になった。部活の関係、とか言えば親は許してくれそうだけど、肝試しの時点で私は正直乗り気ではなかったのだ。
理由は至極単純で、白いのとかかわるようになってから、そういった霊的存在がばっちりいることを知ってしまった。そのうえ、とんでもない存在はともかく、ある程度は私も霊的存在を感知できるのである。白いのを信頼しているが、何か触りがあったら怖い。
ごめん今見た。どこにいくの? 、と私がメッセージを打ち込むと、すぐに返事が来た。
「南光神社? 神社?」
神社に対して、肝試しというイメージがいまいちくっつかなかった私は、首をかしげる。ややあって、墓地にでもいくのかな、と思い当たった。が、しっくりこない。
おやつがてらに専門分野についてお話をしてくださる、隣の御屋敷に暮らしている、この家の家主。荒木教授の講釈によると、神社における葬式は、よくイメージする寺の葬式とは目的が違うという。
寺で行われる葬式は、亡くなった人をあの世へ送るための葬儀。
神社で行われる葬式は、亡くなった人を家の守護神としてその家に奉り、見守ってもらうようにする儀式。
儀式と、葬儀。この時点で、目的はかなり異なっている。
だからこそ余計に、肝試しと神社が、なんとなく結びつきにくかった。
山深いところにあるのだろうか。
「どこにあるんだろ」
聞き覚えのない神社の名前に首を傾げた私は、ふと、白いのがこちらを見ていることに気が付いた。お皿を拭き終えた、訳ではない。
心当たりを覚えて、尋ねた。
「……南光神社、知ってる?」
「いく、の?」
「友達がね、誘ってるの。肝試し、ええと、その神社に行ってみようって」
白いのはゆらゆらと体を揺らす。お皿はきちんとかごにしまってからだったので、割れる心配をする必要はない。なんだか何か言おうとするけど、ひどく言うのを躊躇っているらしい。泣き出す手前の小さな子供のような表情を浮かべるので、ぎゅ、と手を握ってやった。
「どうしたの?」
「だめ」
「……行くのが、だめってこと?」
こくん、と頷いた白いのが、おろおろとしている。
「怒らないよ。理由があるんだね」
そう返すと、ほっとしたのだろう。何度も、首を縦に振ってきた。
白いのがこういうことを言い出すのは、正直かなり、怖い。自分の心当たりがない場所に行くだけで恐ろしいのに、白いのが行くなと言うのだから、相当なんじゃないかと思う。
「……どうしてダメか、教えてくれる?」
私がここで、ラインで、用事があって行けないのと返すのは簡単だ。でも、もしも、もしも本当にとんでもないことが起きたら、私は口を閉ざしていられる自信がない。
白いのは身振り手振りを交えながら、とつとつと、言葉を並べてなんとか、ダメだと思う理由を教えてくれた。
「そこの、ぬし。もう、いない。だから、だめ」
「ぬし? ……もしかして、神様?」
「そう。もういない、だから、からっぽ。からっぽ、は、からしか、はいってない」
廃神社。
そんな単語が、脳裏をよぎった。これは荒瀬さんが教えてくれたことなのだが、むやみやたらに、道端にある仏像やお社に手を合わせてはいけないという。
中に入っているのが、神社の神様や、仏様とは限らないからだ。手を合わせる、ということそのものが、その対象に気持ちを傾けるということ。気持ちを傾けられることで、力を得る存在は多い。
私は、迷った。友人たちは、行く気満々だ。これを止めるのは、とても難しい、とも思った。そして私は、行きたくない。
少し考えてから、都合が悪くて今回は行くことができない、というメッセージを送った。私が引っ越したり、家に一人で留守番をすることが多いと友人たちも知っているから、そんなに変に思われなかったらしい。むしろ、急にごめんね、と返信が来た。
そこまで見て、白いのに伝える。
「……分かった、いかないよ」
そう言うと、白いのは嬉しそうに笑顔を見せる。
「うん。えみ、いかない。いかないの、いい」
「でもね、私の友達は、行く気みたいなの。大丈夫かな」
「……えみ、ともだち、だいじ?」
大切なことを聞くように、からだをこちらへ向けて聞いてきた白いのに、頷く。そりゃ、もちろんそうだ。
「そうよ。お父さん、お母さん、おじいちゃんやおばあちゃんとは違うけど……そうね。荒瀬さんとか、荒木教授みたいに大事」
「……そっか」
白いのは、こくん、と頷いた。
「それと同じくらいにね、白いのが言うことも、大事なの」
「だいじ」
びっくりしたように、白いのがゆらゆらと体を揺らす。
「だいじ、わたし、だい、じ」
「そうだよ。私は、白いのが行かないで、って言うから、行かないでおこうと決めたの。同じように大事な友人たちも、できることなら行かせたくない」
そう話しかけると、白いのは余計、ゆらゆらと体を揺らし始めた。どうしよう、どうしよう、とブツブツ呟いているようで、困らせてしまったと思って私は急に、申し訳なくなる。
「……なんとか、言ってみるね」
「もう、いってる」
「え?」
その時だった。
私の脳内に、ざざっ、と何かが流れ込んでくる感覚があった。友人らと、男子2人。由美子が、スマートフォンをいじっている。テレビの中継みたいに、声が遅れて聞こえてくる。
『やっぱり、恵美ちゃん来れないって』
『急にだもんねー、恵美ちゃんの家からも近いから、行けるかと思ったんだけどさぁ』
神社。いや、あれは、神社なのだろうか。
『そっか。じゃあ行こうぜ』
『明るいしあんまり雰囲気ないけどね』
笑いながら、彼らが石造りの鳥居をくぐった。左右に並ぶ、古い木々。ぞわぞわ、ぞくぞくと、する。待って、待ってほしい。今日、とは言われたけど、まさか、そんな。
もうみんなそこに、行っている?
「えみ」
白いのの声に、ハッとして、あたりを見回した。頭の中に流れ込むような映像と音は消え失せていて、白いのの複眼に私の顔がたくさん映っているのが見える。
「……みんな、もう、神社に」
「だいじ、だいじ、まもる、えみ、だいじなの、わたしは、えみのむし、だから」
にこり。
白いのが笑うと同時、なんだか私は急に、恐ろしくなった。何かとても、とても恐ろしいことを、白いのにやらせようとしていた気がしてきた。
だって。だって、白いのは、ただ、ただ、私を想っているだけだ。それだけなのだ。かつての、今もなお変わらないのかもしれないけれど、20歳で生贄を取殺すのとはわけが違う、何かもっと別の存在になりつつあって。でも、ともかく。
「待って。やっぱり、行く」
「……えみ」
「みんなを、放っておけない。あそこ、とても、悪いものがいるんじゃないの?」
少し考えるようにして、白いのは首を横に振った。
「ちがう、から。からっぽの、がらん、どう」
「何もいないってこと?」
「から、なんでも、はいる。おおきいとこ、なおさら、はいる」
分からない。でも、皆が危険な目に合うかもしれないこと、それだけが私の中を占めている。
と、玄関のチャイムが鳴った。びっくりしたけれど、慌てて玄関に向かう。
「……あ、荒木先生」
「やあ。知り合いが訪ねてきてね、くず餅を置いて行ったんだが、どうにも僕は苦手で……よかったらどうだい?」
すっかり顔なじみとなった荒木先生が、包みを片手に立っていた。にこやかで、穏やかな様子に、気持ちが落ち着くのを感じていた。
詳しく本を読んだことはないが、民俗学の教授として、その学会では権威の一人という荒木先生。国語科教師のような温厚さを持つが、語りだすと止まらないところもある。彼の専門は、仕来り。古来から、日本各地で受け継がれ、また世界各国にも存在する、慣例や習慣に関する研究をしているのだという。
「せっかくですから、上がっていってください」
「おや、一人かい?」
「白いのは一緒ですよ。あ、あとちょっと、聞きたいことがあって……」
荒木先生も、白いののことは知っている。白いのも、自分がいるようにふるまう荒木先生のことは、好感というか……悪い感情を持っている様子はなかった。
はいこれ白いの君の分ね、と分けられたくず餅を、不思議そうに眺めている。
「聞きたいことって?」
「荒木先生、南光神社ってご存知ですか?」
先生は一口お茶をすすって、うーん、と唸った。
「知っているよ。この辺りでは、一番といっていいほど古くて、そして小さい神社なんだよ」
「小さい?」
「規模というか……まあ有名度も小さくてね、ずいぶん前に後継者も絶たれたのか、近隣から世話をする神主が来ることもなくなって、もともと人気のないところだったからね。町内会どころか氏子の掃除の手が入ることも、自然と減ってしまったところだよ」
荒木先生が、続けて尋ねる。
「しかし、どうしてその名前を?」
「ああ、えーと。私は留守番があるからって断っちゃったんですけど、友人たちがそこで今日、肝試しをするって言うんです。どんな場所かなぁって」
荒木先生が、静かにまた、お茶をすする。
「……これは荒瀬君の受け売りなんだがね、何を祭っているか自分で分からない場所、人が来ているとは思えない場所にある地蔵、神社、寺。そういった類のものに、手を合わせてはいけないって話。知っているかい?」
「はい。あ、そういえば……神社は、神様とかを祀りますけど、廃神社とかの御神体ってどうなるんですか? どこかほかの場所に、引っ越しするんですか?」
色々あるよ。
そう言いおいて、荒木先生は言う。
「例えばだけど、廃神社って存在はないんだよ。まあとりあえず、廃神社だと共通認識にしやすいから、廃神社って呼ぼうか」
えっ、と私は声を上げた。廃神社って存在が、ない?
「日本の神様はね、大本があって、そこから各地の神社に分身みたいに存在なされている。それ以前にね、土地という土地は、基本的に誰かの所有地なんだよ。近代に限った話じゃない、その昔から、あれはどこそこの誰の土地だってのは、たいてい決まっていたものさ。だからね、廃神社。廃墟と化した神社はあっても、神様が消滅するとか、所有者がいないということは、ふつうはありえないんだよ」
なるほど。
つまり、オカルトのなお話における、廃神社という存在にも持ち主は存在する。そして、神社は神社であり、その神様が狂うということは基本ないことだろう。神様だって、引っ越しが必要になったら、勝手にすぽんともとに戻ったっていいわけだ。
「神社だってね別の場所に引っ越しの必要ができて、中身をきちんとした手順で引っ越しすることもある。その後、神社を取り壊したりする余裕がなくて、そのままになってしまっている場合もあるんだ。基本的にはね、ご神体なるものを移動させることは、お墓の中の御遺骨を移すのと似たように、各々手順と作法が決まっていたり、震災で被害にあったりで、必要になることはあるんだよ。だけどね……廃神社と呼ばれるもの中には、人の手が入らなくなったことで記録そのものが途絶え、今中がどうなっているかとか、ご神体はどうしたとか、そもそも何が祀られていたとか、そういった”情報”が零になってしまうこともあるんだ」
いかなるまつりごとを取り計らっていたのか、まったく今では、分からない。ただただ、もぬけの殻なのか、何かあるのか、それすら分からない寂れた社、神主さんの暮らしていたという舎宅、そして鳥居。それだけが、今もなおそこにある。
南光神社はこれに当たる、のだそうだ。
もしかしたら地元のお年寄りなら知っているのかもしれない、と、荒木先生は言う。しかし、荒木先生が持つ土着の資料の中で、南光神社に関する詳しい記載というものは、ほとんど出てこないらしい。かろうじて、今から70年前、終戦間際までは、お祭りもあったらしい。さらに不明確なのが、役所記録を当たってみても、南光神社のはっきりとした持ち主が分からないという点だ。
一応、現在はこの街の土地ということになっているが、本当はもともとの持ち主が居たらしい。ただ、その記録が、どこをどう当たってもまったく見つからなかった。
聞いただけで、なんだか嫌な感じのする場所だ。
「何があるかわからない、しかし神社だ。この時点で、人はいくつかの作法を思い当たるだろう」
神社に行って何をする?
荒木先生に聞かれて、私は率直に答えた。
「お参り、でしょうか。手を打って、頭を下げて、お祈りをして……」
「君や荒瀬君に関わってきた以上、この世に不可解な存在があることを、僕は確信している。……それでね、南光神社の余計に不思議なことなんだが、そんな70年近く前から記録のないような場所。どうして今もなお、残していると思う?」
まさか。
と、思った。
まさか、残すしか、方法がなかった、とか。
「僕はね、どうにもできなかったんじゃないか、と思っている。ほら、事故の多発する工事現場とか、あるだろう。ああいった類のことがあって、それに霊的なことが関わっていなくても、誰もが避ける土地になってしまった。そして、70年というときの中で、”関わってはいけない場所”という認識に変貌したんだ」
「……あの、私、みんなが、心配で」
「白いのに、止められたんじゃないかい?」
尋ねられて、素直にうなずく。白いのは荒木先生を、じっと見つめていた。
「荒瀬君に聞いたよ。君を、何かしらから守るのが、白いのにとって今分かっている存在意義であり役目なのだと。その白いのが行かせたくないのなら、確かに、友達らも危険なのかもしれないな」
「どうし、よう」
「一つ言っておこう。君に、その義務はない。君に、その責任はない。白いのにも、ね」
こくり、と頷いた。私には、力などない。白いのには、凄まじい力があるけれど、それは白いのが思うとおりに使うべきだ。
私の願い通りにしたら、白いのがどうなるか、分からない。
「でも、みんなに、何かあったら」
「ないかもしれない。荒瀬君も、南光神社を不気味だとは言うし、進んで近づかないが、特に危険扱いしている様子もなかった」
そうなのか。
ちょっと肩の力を抜いた私に、白いのが言う。
「えみ、いかない、よ、ね?」
「……うん、行かないよ」
笑って見せると、よかったよかった、と小さく繰り返しながら私の手を握ってきた。どうも、私のことを、本当に心配していたようだ。
「……そういえば、からっぽ、って言ってたけど。神様は、もういないの?」
白いのにそう尋ねると、うん、と首を縦に振る。
「からっぽ」
荒木先生が、ふうん、と頷いた。
「神様はもういないのかい?」
「そうみたいです。白いのが言うには、空っぽで、何もいないって」
「でも、行っちゃだめなんだね」
何かが、引っかかる。しばし黙っていると、荒木先生が呟いた。
「もしかして、神社は関係ないのかもしれないな」
「え?」
「南光神社の、ある、土地。そこはどうなんだい? 白いの君」
とち? 、とつたない口調で白いのが呟く。意味がよく分かっていないらしいので、
「神社が建つその場所だよ。その場所も、からっぽなの?」
と、私が尋ねた。白いのが、ぴたっと動きを止めた。私の手をぎゅっと掴んで、どこにも行かせないとばかりに、腰にも腕をまとわりつかせる。そして膝上に顔を乗せ、私を見上げて口を開いた。
「とちゅう」
「……とちゅう?」
「とちゅう。あそこ、いるの」
途中? それって、なんだろう。
「途中って、それって、白いのの……仲間?」
白いのが、首を横に振った。
「にてる、でも、わたしは、えみのむし。あれ、とちゅう、とちゅうのもの、むしじゃない、わたしとはちがう」
え、と小さく声が出る。荒木先生が、身を乗り出す。その手には、鉛筆とノート。白いのは、お皿が拭ける通り、本人というか、本蟲がやろうと思えばこの世のものにも触れることができる。どうも文字で書いてほしいようだが、まだ難しいと思う。
「ん、と。……むし、は、むし。あれは、にてる。むし、まね。まね、むし」
「なんか似てるだけで、真似しているだけってこと? 白いのは、作られたとかじゃなくて、白いのそのものってこと?」
「そう。わたし、は、むし。ずっと、むし。ひと、ひとのまま。むし、むしのまま」
蟲は、蟲。白いのは、白いの。ひとは、ずっと、人のまま。
じゃあその、似ているって、何?
「ちがうもの、ちがうまま」
なんだかわからない感覚に、ぞくり、とする。不安になったので、友人のラインへメッセージを打ち込んだ。
そこがとても危ない場所らしいということ、もし何かあったらまっすぐ引き返してくること、家に帰ったら塩をまいてお風呂に入ること。気休めかもしれないけど、そう思いながら伝えた。
友人のところへ行く度胸は、無かった。
関わらない、そういう選択を、私は私のためにした。
卑怯者なのかもしれない。大事な存在と言っておいて、こんな選択をした私を、許せなくなる気もしたけれど、だけど。
私は、専門家じゃない。白いのは、私の力じゃない。あるように、あるだけだ。
わたしも、白いのも。
あるようにしか、なれない。
私は友達以上に、白いののあり方を、ゆがめたくなかったんだ。
「……君は何一つ、悪くないよ」
「……はい」
荒木先生が、静かに微笑む。私に力はない、私に権利はない。運命とは、捻じ曲げるものじゃない。今が、ただ今として、続くだけだ。
けれどその決意を、揺るがすのは、空白だと知った。
私のメッセージに、既読の文字は、何時になってもつかなかったのだ。
つづく


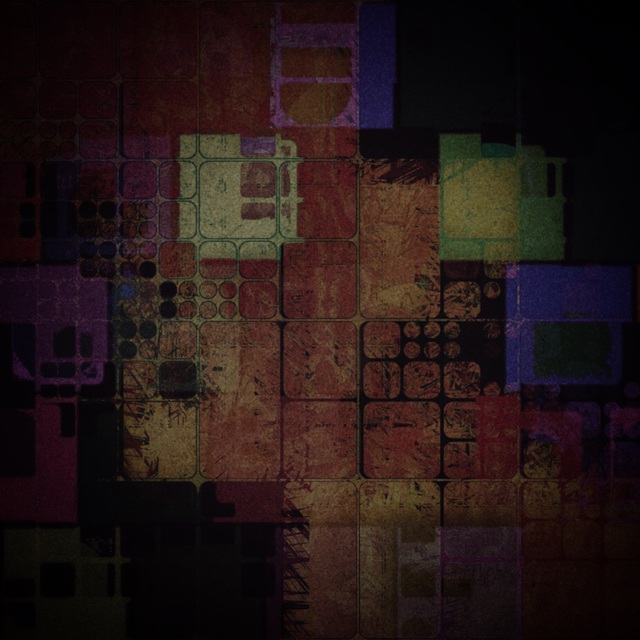
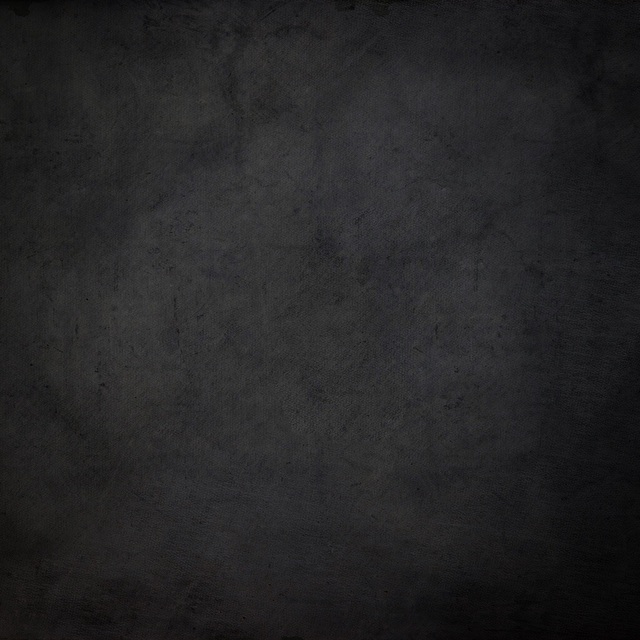
作者六角
さてはて、ゆるりとまいりましょうか。
今回は少々、蟲の、なかみについてのお話し。