ある男性から聞いたお話です。
nextpage
もう20年以上前になりますが、この方には同じ大学に通っていたNさんというご友人がいたそうなんですね。
同じゼミに入ったことがきっかけで仲良くなり、よく一緒に遊んでいたらしいんですが、彼は1つだけこのNさんに対して不満を持っていたんです。
それは、Nさんがよく道端で唾を吐くこと。
どこだろうとお構いなしに、そのへんにペッと唾を吐き捨てるんですね。
酷い時だと日に何回も。
時々奥歯に何か挟まっているのか、口をモゴモゴ動かしていたりもするので少し気になっていたんですよね。
特に指摘するようなことはしていなかったそうなんですが、ある時彼が講義を終えて帰ろうとした際に横で何やらクチャクチャと咀嚼音のようなものが聞こえてきたんですね。
視線を向けるとやはり一緒に講義を受けていたNさんでした。
Nさんはガムでも噛んでいるかのように口を動かしています。
またやってるなぁと思っていたらNさん、今まで座っていた席の下に、頭を入れたんです。
ペッ
Nさんが何をしているのか彼には見えませんでしたが、その音を聞いて2、3歩Nさんから離れました。
この時、彼は流石に頭にきてNさんを咎めたそうです。
「おい、お前ふざけるなよ」
「ん?あぁ、わるい。かかった?」
顔を上げたNさんは冗談めかして笑っています。
「そういう問題じゃないだろ、何考えてるんだよ。あり得ないだろ」
「……」
彼が本気で言っていることに気づいたNさんは、きまりが悪そうに俯いたそうです。
「うーん……一回さ、下見てくれねーかな?」
「……は?」
彼はNさんの言っている意味がわかりませんでした。
当然Nさんが指す先にはたった今Nさんが口から出した唾液が床に張り付いているはずだったからです。
「んなもん何で見ないといけないんだよ汚ねーな」
「いいから早く」
Nさんは食い気味に自分が吐いたものを見るよう促しました。
「何だよ、何を見ろっていうんだよ……」
Nさんの真剣な様子に彼も折れ、渋々座席の下を覗き込みました。
消ゴムのカスと埃にまみれた床、そこにテラテラと光る液体。
「おい、何見せんだよ汚い」
「よく見てみろって」
頭をあげようとした瞬間、Nさんの手が彼を押さえつけました。
「お、おい!」
無理やり視線が汚ならしい唾液に向けられる。
白く濁ったそれは、細かい泡を弾けさせながら床にじんわりと広がっていく。
しかしその弾ける泡の中、何やら動くものが見えたそうなんです。
暗くてよく見えませんがよく目を凝らすと、粘り気のある液体の中で蠢く者の姿をとらえることができました。
それは赤くて小さい生き物でした。
1ミリにも満たない何かがNさんの唾の中を動き回っている。
はじめはクモに見えたそうですがそうじゃない。
手足はそんなに多くない。というより、二足歩行している。
しかも1匹じゃあない。
2匹……いや3匹いる。
真っ赤な小さい生き物が、二足歩行で唾液の中をモゾモゾと動いている。
その姿は虫、というより極小サイズの人間でした。
赤の全身タイツを着たような人間が3人。彼は目の前の光景が信じられませんでした。
彼が何も言えないでいると、今まで彼の肩を押さえていたNさんの手は離れ、そこで彼はようやく頭を上げました。
「な?いるだろ?」
「何だよあれ」
彼の見たものは完全に彼の理解を超えているものでした。
Nさんは困ったような顔で頭をかき、言葉をつまらせました。
「何だよ、あり得ないだろあれ。人か?何であんなもんが……」
「うーん……」
Nさん自身、何と答えていいかわからないようでした。
「……ずっとさ、ああなんだよ。気づくと口ん中にあいつらがいて、舌やら歯の上を走り回る」
Nさんは口を大きく開き、舌を出して彼に見せました。
その時咄嗟に彼は目を背け、Nさんの方を見ないようにしたそうです。
まずい、これはきっと関わってはいけないことなんだ。そう直感しました。
「噛んで潰すとさぁ、やっぱり鉄の臭いがして気になるんだよ」
Nさんは彼の反応もお構いなしに続けます。
「放っておくとどんどん増えるし、気持ち悪いからなるべく吐き出すようにしてるんだよな」
「そ、そうか……た、た、大変だったんだな……」
彼はなるべくこの話を早く終わらせようと無理に声を出しました。
「ほんとだよ。昔からずっとだし、おかしいよな」
「あっえっとその、すまん。キツい言い方して」
「こいつら本当にふざけてやがる。寝てるときでも動き回って増えるし」
Nさんの様子はこの辺りから少しおかしくなり始めました。
普段は明るいNさんが、今はボソボソと恨み言を吐き出すかのように話し始めたんです。
「時々歯茎にこびりつく奴もいて、吐き出そうとすると爪を歯茎に食い込ませて抵抗してくる。あー鬱陶しい」
ペッ
Nさんはまた講義室の床に唾を吐きつけました。
「あーまただよ。また1匹残ってやがった」
そう言ってNさんは吐き出した唾を靴の裏で執拗に踏みつけました。
地団太を踏むように何度も靴底を叩きつけ、磨り潰すように床を擦りました。
「どうして俺なんだよ……」
「……」
「あー……これ、ほんと誰かに移せねーかな……」
そう言ったっきり、Nさんは黙り込んでしまいました。
一刻も早くその場を立ち去りたかった彼は、この後バイトがあると嘘を吐き、そそくさとNさんを置いて下宿先に戻ったそうです。
nextpage
それからは、なるべくNさんに近づかないようにしていたそうです。
遊びに誘われても何かと理由をつけて断り、大学を卒業してからは一切連絡をとらないようにしました。
罪悪感はありましたが、それ以上にあの正体不明の生き物が恐ろしかったと言います。
しかし彼も社会人になり仕事に追われる日々が続くと、流石にそんな記憶も薄れ、Nさんのこともほとんど忘れていたそうです。
彼が就職した会社はいわゆるブラック企業というやつで、毎日遅くまで会社に残るのが日常になっていました。
良くも悪くも会社に慣れ始めた頃、いつものように駆け込んだ際、ふと足の裏の違和感に気づいたそうなんですよね。
靴の裏に何かが当たっている。
気にはなったんですが終電とはいえ周りにはたくさんの疲れた顔をしたサラリーマンたち。
流石に足を上げて靴の裏を確認するのは躊躇いました。
仕方なく自分が降りる駅まで我慢したそうです。
それで駅に着くと、ホームに置かれたベンチに腰掛けて右の靴を脱いでみたんですね。
そして裏を確認してみる。
「あっ何だよ……」
まあ案の定というか、ガムがついていたんですね。
彼は少し苛立ち、地面に擦り付けてガムを取ろうと靴を履き直そうとしました。
しかし、そこで彼はあるものに気づいたんです。
土にまみれて黒くなったガムの中に、何かが混じっている。
暗くてよく見えなかったのでベンチの隣にあった自販機の光で照らしてみると、それが何なのかわかりました。
千切れた赤い腕と頭。
虫ほどの大きさしかありませんが作りは紛れもなく人間のものでした。
この小さなバラバラ死体を見て彼は学生時代のトラウマを思い出しました。
Nが近くにいたんだ……
会社の近くか、あるいは電車の中に……
彼は自分の行動範囲内に化け物たちが吐き捨てられていたという事実に寒気を覚えました。
もしかしたら普段知らず知らずのうちにもっとたくさん踏み潰していたのかもしれない。
そう考えるようになってから彼は足元を見ながらでないと外を出歩けないとおっしゃっていました。

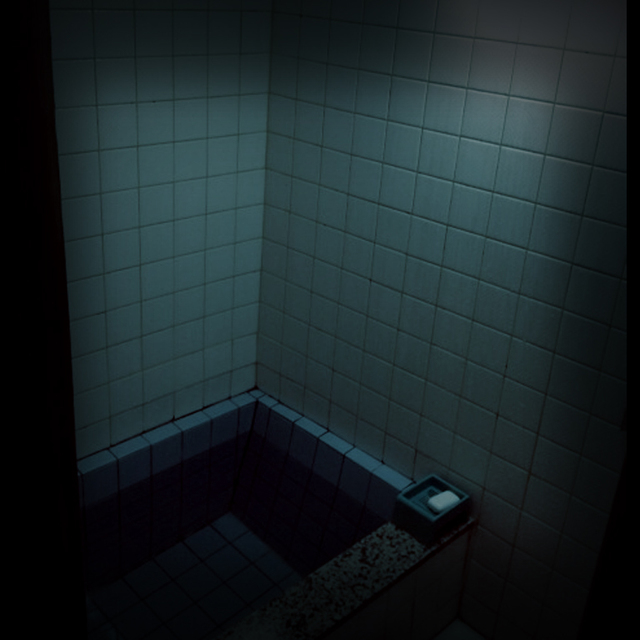


作者千月
普段何気なく歩いている道でも、足元にはくれぐれもご注意を