wallpaper:1
これは、私が大学2年の時の話だ。長いあいだ忘れていたが、ふと思い出したので投稿しようと思う。
長文、駄文で申し訳ないがどうか書かせて欲しい。俗に言う、「本当にあった怖い話」である。
nextpage
私は大学2年の夏、サークルの仲間と夏合宿に行くことになった。行き先は富士山で、山頂からご来光を眺めようという目的だった。
登山の経験が何度かあった私は、富士登山もそんなには苦労しないだろうとタカをくくっていた。
結果的にそれは当たっていたとも外れていたとも言える。
私は景色を楽しむ余裕があったのだが、メンバーの1年女子が高山病にかかってしまったのだ。
彼女一人での下山は当然不可能だということで、3合目あたりであえなく下山することになってしまい、私は初富士山に興奮していたこともあってかなり落胆していた。
7合目にある救護所まで彼女を送った私たち7人はさすがに疲れてしまっていて、もう来光の見られない富士山に再突撃するほどの気力は残っていなかった。
ほどなくして彼女の体調は回復するのだが、救護所についた時、私はよからぬことを考えていた。
それは「樹海」に行くこと。
今考えてみれば正気の沙汰とは思えないが、当時の私には冷静さというものが全くもって欠けていたのだ。
しかし、皆に言えば反対されるのは火を見るより明らかだ。私は無用なリスクを回避すべく、静かに行動を起こした。
「N先輩……」
「ん?どうした」
N先輩は荷物を下ろすと、近くのベンチに腰を下ろした。
nextpage
先輩は当時大学3年生、私の一つ上であった。中学で剣道を始めた私は、道場で一緒だったN先輩と特別仲が良かったのだが、先輩は高校三年生で剣を手放してしまい、先輩とのつながりはそれきりだった。
それゆえ、大学構内でN先輩を見かけた時は思わず飛び上がるほど驚き、また嬉しかった。
身長こそわずかに勝っていたものの、幼少から剣道を続けていたN先輩は、中学で全国大会に出場するほどの実力者であり、県大会すら届かなかった私などとは比べるのも恐れ多い。
それはさておき、私たちの仲が良かったのは、共通の趣味があったからだといえる。
その趣味とは言うまでもなく、オカルトだ。
剣道の合同合宿でも自主的に肝試しを行うほどオカルトマニアであった私たちは、心霊スポットを回ってみたり、怪しげな儀式に臨んでみたりもした。
しかし霊感がない(と、決め付けていた)せいか、結局霊を見ることは叶わなかった。
さて、話の本筋に戻ろう。
先輩の隣に腰掛けた私は、声を落として話を持ちかけた。
「実は―」
―樹海に行ってみたいんですよ。
さすがの先輩もこれには驚いたようだった。
「は、本気か?」
「はい。流石に一人では危ないと思うので……」
いつになく真剣な面持ちで、数秒思案するポーズを見せたあと、先輩は小さく頷いた。
そして先ほどとは打って変わって、いたずらっぽい笑みを浮かべる。
「よし、行ってみるか」
「やたっ!」
思わずガッツポーズをする私に、苦笑する先輩。
このとき、先輩が止めていればあんな思いはせずに済んだのだが……。
すっかり意気消沈しているほかのメンバーに、私は登山の再開を提案した。が、結果は惨敗。誰ひとりとして同意するものはいなかった。
ただひとりN先輩を除いて。
全ては私の計画通りだ。
そうして、私とN先輩は登山再開を口実にメンバーから離脱したのだった。
nextpage
wallpaper:224
まっすぐ青○ヶ原を目指した私たちは、初めての樹海に興奮していた。登山に慣れている私はともかく、先輩も自慢の体力で全く疲れを感じさせなかった。
林道を通って目的地に到着した私は、正直なところ少しがっかりしていた。樹海というイメージにそぐわず、道も作られ、案内板も立っていたからだ。
先輩も同じ気持ちだったのだろう。私たちは無言で林道をそれて深い森に入っていった。
来た道からまっすぐ、木々のあいだをぬって奥に進む。すぐに元の道は見えなくなり、周りは私の望んだ「樹の海」の様相を呈し始めた。
私はここに来てようやく満足感を覚えた。
そこが地獄の入口だとも知らずに。
樹海は、読んで字のごとく360度が木に覆われていた。もう日は昇ったはずなのに、空気はじめっとしてかなり薄暗い。
先の見えない森を進む2人を完全な静寂が包んだ。すべてが陰った世界の中、地面を踏む音だけが響き、落枝を踏む音が時々アクセントを加える。
森はえもいわれぬ不気味な雰囲気で満ちていた。
もう私は夢中だった。
真夏とは思えないような冷気が、進むにつれてその鋭さを増していくかのようだった。
森の奥が私をさそっていた。
おくへ、もっとおくへすすまなくては。
すすみたい。なんで。たのしいから。
ほら、はやくいかなきゃ。いかなきゃ。
いかなきゃいかなきゃいかなきゃ。
いつのまにか、前を歩いていた先輩はとなりになり、後ろになった。
でももうそんなことは気にならなかった。なにか強い衝動が私を前に進めた。
自然と速度が上がる。足元を確かめるような歩きから、早歩きへ。そして地面を蹴って―。
「おいっ!」
shake
世界が回った。背中に受けた強い衝撃に、肺の空気が全て吐き出される。
気がつけば私は地面に転がっていた。
先輩が私を投げたのだと理解するのに時間はかからなかった。ズキズキと体が痛み、私は体を起こして犯人を睨みつけた。
「―ってぇ。何すんだよ!」
思わず乱暴な口調になるが、先輩の様子に口をつぐんだ。
先輩は、泣き出す寸前のようなひどい顔で固まっていた。
急に私を強く抱きしめると、良かった、良かったと何度も繰り返した。
「もう助からないかと思ったよ。だって入ってすぐに引き返そうとしたのに、お前返事もしないし。流石にやばいかもって思って怒鳴ったら、お前笑いながら走り出したんだから」
「え……」
全く、覚えがなかった。樹海に入ったところまでは鮮明な記憶があるのに、ここまで歩いた記憶が曖昧だった。先輩の様子からして嘘をついているとは到底考えられない。
ゾクリ、と私の背中を冷たいものが撫でた。
「やっぱりな。絶対とりつかれてたよ、お前」
「ま、まさか……。ははっ」
薄ら笑いを浮かべてみても、気分は最悪だ。
「まあでも、投げた衝撃で正気に戻ったみたいだな。なによりだ」
ほっと息をつく先輩だったが、状況は芳しくない。
知らぬ間にかなり奥の方まで進んでしまったらしい。
「先輩……。俺たち―」
「―迷った、な」
私の言葉を先輩が継ぐ。
迷った、その言葉が頭の中をぐるぐる回わる。急に胸が苦しくなり、手先が冷えるのを感じた。
あたりをキョロキョロと見回すものの、もちろん目印はない。
私はもはや、パニック寸前だった。
もしあのとき私が一人でそこにいたなら、生きては出られなかっただろうと確信している。
だがあのとき私には、N先輩がいた。
「まあ、座れや」
先輩はさして慌てた様子もなく、あくまでもマイペースだった。
それが私にとっての唯一の救いで、大きな希望だった。
先輩はまるで家に居るかのように、湿った地面にどかっと座ると、私にも座るように手で示した。
「さて、どうだ? だいぶ落ち着いたか?」
「はい、おかげさまで」
うん、と一つ先輩が頷く。
するとまたもや、先輩はにやりと笑った。
「な、俺前から気になってたんだけど、樹海だとコンパスが狂うって聞いたことないか?」
この状況で良くもそんなことを。私は思わず笑ってしまった。
「試してみます?」
そう言ってバックの小ポケットから方位磁針を取り出すと、先輩は新しいおもちゃを得た子供のように目を輝かせた。
「おお!持ってたのか!忘れてきちゃったって後悔してたんだよ」
「やってみますね」
私は立ち上がって、右手にのせた小さな箱を胸の高さに合わせた。
先輩も立ち上がり、不安定な針の行く先を見守った。
果たして――。
針は少しの間ゆらゆらと迷っていたが、やがてピタリと定まった。コンパスは北(と思われる一方)を指していた。
「なんだぁ、迷信かよ」
「使えるんですね」
コンパスが使えることよりも先輩が落ち着いていることのほうが心の支えになり、私は少しだけ冷静さを取り戻すことができた。
「さて……どうしましょうか」
「うーん、そうだな」
一応、といった様子で携帯を取り出した先輩は、画面を見るなり顔をしかめる。
「やっぱな、ほら。圏外だ」
ずい、と突き出されたそれにははっきりと圏外の文字があった。
ダメ元で私も確認してみたが、やはり圏外。携帯で助けを呼ぶのは無理なようだ。
「ま、こんなもんだろ」
淡々とそう言うと、先輩は回れ右の要領で正確に真後ろを向いた。
「まっすぐ入ってきたから、コンパスで確認しながらまっすぐ戻れば出られるさ」
得意げに親指を立てるN先輩の姿に、自分もなぜかそんな気がしてくる。
かくして単純な理論に従い、私たちは樹海脱出を試みた。
そして――。
――出られなかった。
行けども行けども、出てくるのは樹、樹、そして樹だった。
延々と同じ場所をさまよっているような感覚に襲われ、心の中に徐々に不安が忍び込んで来た。
不気味な薄暗い森は不安を呼び起こし、不安は焦りをうむ。一向に出口の見えない恐怖に、疲れもあいまって正常な精神状態を保っていられなくなりそうだった。
コンパスに従ってまっすぐ歩き続けた私たちの疲労は、やがてピークに達した。
二人で少し開けたところに座り込むと、休憩を取ることにした。
幸いにして、水と食料は十分にあったため、それを分けあって空腹を凌ぐ。一度落ち着いてしまうと、登山の疲労もどっと出てきてもう立つ気にはなれなかった。
もともとバッグの容量に余裕があった私は、小型のブランケットを詰めていたのを思いだし、二人で肩を寄せ合って樹海の異様な寒さを防いだ。
そして、私たちの本当の地獄が始まった。
夜が来たのだ。
夜の樹海は世界で最も恐ろしいと、私は嫌というほど思い知った。
一人でいたならまず間違いなく、その恐怖から逃れるために自殺を選んだだろう。そのぐらい怖かった。
見渡す限りの黒が視界を埋め尽くしている。先輩が隣にいるとわかってはいても、周りが見えない暗闇というのは原始的な恐怖を呼び起こした。
手元にある明かりは私の持つヘッドライトと、先輩のバッグに入っていた懐中電灯2本だけだった。替えの電池は単3が2本。夜を明かせるかどうかは完全に運だった。
もちろん、眠ってしまえば明かりなどは必要ないが、それだけは死んでも嫌だった。常になにかに見られているような気がしてならないのだ。
眠りについた瞬間に、なにかこの世のものでない物体に喰われてしまうのではないか、なんの根拠もないそんな疑念が頭を支配していた。
その時既に私の精神状態は正常ではなかったと思う。
私とN先輩は、少しでも気分を紛らわせようと、ハイになるほどテンションを上げ、騒ぎ、そして話し続けた。
その内容は多岐に及んだ。
サークルのこと。
友人の色恋沙汰。
家族旅行に行った時の話。
売店のおばちゃんにイタズラを仕掛けた話。そして、剣道の話。
「――実はな、親にも言えなかったんだけど、俺、剣道好きじゃないのよ」
「えー? 先輩めっちゃ強いじゃないっすか!」
「まあ、小さい頃からやらされてたからな。でもお前も剣道やってたからわかると思うけど、あれ痛いじゃん。夏場は臭いし」
「あははー。それを言ったらおしまいですよ」
「まあね。それにさ、稽古も毎回同じでつまんなかった」
「確かに、それはありますね」
「強くなっても結局優勝できるほどではないしさ」
「十分すぎるほど強いですよ、先輩は。俺なんか県大も出られませんでしたし」
「それは修行が足らんよ、君」
という調子で先輩の暴露話や、自分の話、友人や家族の話など、とにかく話して話して話しつづけた。
話題が途切れれば下らないギャグをはさみ、面白くもないネタで腹を抱えて笑い転げる。
バカ話で笑っているときは、一瞬恐怖を忘れられるような気がした。
しかしそれもいつまでもは続かなかった。
どれほどの時間が経ったかは定かではないが、ヘッドライトの明かりが弱々しくなり、ふっと消えた。
すかさず先輩が懐中電灯をつけて、暗闇を払う。そこまでは良かった。
問題は、それを上に持ち上げた時に起こった。
LEDの無機質なライトが照らす先、その狭い可視範囲内に何か動く物体を捉えたのだ。
ドキッと心臓が跳ね、ライトが少しだけブレた。先輩も驚いたのだろう。
無言になった二人はライトの先に全神経を集中させた。
耳鳴りがしそうなほどの静けさの中、ドッ、ドッ、ドッと自分の心臓の鼓動がやけに大きく響く。
ライトが先ほどの場所をまた照らした。
「ひっ!」
思わず情けない声を上げてしまった。
そこにあったのは、枝から吊るされた先端に輪っかのついたロープ。
もしかすると、いや、もしかしなくてもアレだった。
「うっわ……」
空のロープが風に揺れている。
静止していない分、ゆらゆらとした動きが情景に生々しさを加えていた。
先輩は光をゆっくり下ろし、ロープ下の地面を照らした。肝心のロープの中身がいなかったからだろう。
しかし、地面にも何もなかった。
「きっと吊ろうとしてやめたんだな」
ぼそっと、N先輩がつぶやく。
私も全くの同感だった。
なんとなく嫌な感じを覚えた私は、先ほどのようなバカ話を始めようと口を開きかけた。
「シッ……。静かに……」
ところが先輩に制され、耳を澄ますしかなくなる。初めは何も聞こえなかった。
そう、初めは。
風で木々が蠢く音に混じって、かすかに足音のようなものが聞こえた。
それはお約束のように、だんだんと近づいてくる。地面を踏む音が大きくなるのにつれて、体が凍ってしまったかのように冷たくなり、すぐに身体は動かなくなった。
「……め、…な。…めん……。…め、んな」
独り言のようにぼそりぼそりとした低い声が聞こえてくる。
私と先輩は、痛いほど肩を寄せ合った。金縛りにあったままで。
左の方からから足音と奇妙な声らしきものが聞こえてきた。私はそいつが、接近してきているのを肌で感じた。
そのとき、金縛りによって腕が固定され、先輩に握られた懐中電灯は異様なほどピタリと空間を照らしていた。
―サ、サ、ササ、サ、パキ、サ
ふらり、ふらりと不規則な足音でそれが近づいてくる。
パニック寸前だった私は目を瞑ることもできずに、しかと明かりの先を見つめていた。
nextpage
wallpaper:531
そして明かりの左端、木を数本隔てた向こうに“それ”が映った。
“それ”はひょろりとした体に、ボロボロのスーツのようなものを纏っていた。
「……んな。ごめ…な。ごめんな」
スーツ姿の男は、こちらに気づく様子もなく、明かりを横切ろうとする。
私は男の言っていることを理解した。
―ごめんな。
男は確かにそう言っていた。なぜかその時の私にはわかったのだ。
もうすぐで明かりを渡り切ろうかという時、男はぴたりと動きを止めた。
―バレたっ!
私はそう確信した。と、次の瞬間。
バババッ、と今までの動きからは想像できないほどの俊敏さで、私たちに近づいてきた。
殺される……。
なんとか目を瞑ることだけは成功し、ギュッと閉じると同時に股間に温かいものを感じた。
だが失禁の恥ずかしさなど微塵も感じなかった。あるのはただただ純粋な恐怖だ。
「……え!お!。…え、お!」
不意に大きな声が聞こえた。
つい薄目を開けて確認してしまう。自分たちから数歩先の木立の隙間に、男が立っていた。
しかし、それ以上寄って来ようとはしない。まるで何かを伝えようとしているかのように、必死に意味不明な声を上げていた。
「…えおっ!い…え、お!」
なんだ……?何が言いたい……。
さっぱり意味が分からない。
一瞬恐怖心すら忘れ、男の言葉を理解しようと努力したが、結局聞き取れなかった。
私が更に耳をすませたとき、既に木立の間には何も残っていなかった。
金縛りから解放され、深く息をつく。
そのあまりに唐突な消え方に、私の幻だったのではないかという気さえしてきた。
しかし、股間の湿り気は私に逃れられない現実を告げていた。
とりあえずの危機からは逃れられたはずだというのに、手放しでは喜べない何かが引っかかっていた。
「おい……。今の、見たか?」
心なしか声が震えていたため、先輩も私と同じ気分だったのだろうと推測できた。
「…はい」
「なんて言ってたんだろうな……」
「……わかりません」
先輩もやはり同じところが引っかかっているようだった。
「気を抜くなよ、まだ近くにいるかもしれない」
「分かりました」
先輩は四方をライトで照らし、安全を確認する。と、男がいた木立の根元に何か光るものを見つけた。
「N先輩……、あれ…」
「ん?……いたのか!?」
「いや、そうじゃなくて、あの地面に何かありませんか」
「ん……、見てみよう」
付き合いたてのカップルのようにガッチリと腕を組むと、ゆっくり木立に向かって進んだ。
よりにもよってロープのすぐ隣であったため、まず近づきたくはないところだった。二本の木のあいだ、それらの根元付近に輝きの正体があった。
「これは――」
nextpage
wallpaper:226
汚れたテープレコーダーだった。
土の付着したそれは、えもいわれず嫌な雰囲気を存分に放っていた。しかしここまで来て放置するわけにもいかず、一応持っていくことにした。
先程の位置まで下がり、同じように腰を下ろす。
圧倒的な精神的疲労で、二人とも口を開く余裕すらなかった。
そして危険な好奇心に負け、よせばいいのにテープレコーダーを再生した。
今考えれば、自分たちの意思でというよりは、半ば勝手に再生ボタンがおされたという感じだった。
カセットテープ独特のジー、という音に続けて先程の男の、こもった声が流れ始めた。
内容は薄々想像がついたが、やはり遺書のようなものだった。
夜の樹海でさっき会った幽霊の遺書を聞く、これは発狂しそうなほどの恐怖だった。
内容は十分にも及んだ。
会社での日々、借金に追われ自殺に至った経緯、それから愛する家族へのメッセージだった。
聴き終わって数分、私たちは放心状態であった。
あまりに辛く、悲しい物語だった。
先輩の心はいざ知らず、私のなかでは男に対する恐怖心というより、同情の念がこみ上げた。
先輩も何か思うところがあるのか、口を開こうとはしなかった。
そして二人ともが、そのままの微妙な沈黙が続くと思っていた。
だが――
テープレコーダーを止めて数分後、再びジーという音が流れ始めた。
何か、とてつもなく嫌な予感が私を貫いた。金縛りはないものの、体中からどっと冷や汗が吹き出る。
このままではまずい、早く止めなくては。
私の第六感のようなものが最大音量でアラームを鳴らしていた。
先輩はすぐにカセットテープを手に取ると、無言で停止ボタンを押し込んだ。
ガチャっとボタンが押され、そして……声が流れ始めた。
「なんでだよっ!」
先輩は叩き壊すような勢いでやたらにボタンを連打した。
だが、一向に止まる気配はなかった。
「ああクソッ!」
止めるのは不可能だとわかった先輩は、テープレコーダを遠くに投げる。
それは一直線にロープの吊られていた木に飛んでいき、大きな音を立てて正面からぶち当たった。
しかし、再生は止まらなかった。
それには、先程の男と思われる声と共に、明らかに別人だと思われる謎の声が録音されていた。
wallpaper:43
―ジー
……もうこの世に未練はない……これでやっと………ウフ、ミツケタ……
………うわっ!何だお前!やめろ、やめてくれっ!……ヘヘヘヘ……
来るなっ!やめろ!……ニガサイヨ………嫌だ!死にたくない!まだ(聞き取れない喚声)!……
アハハハh………いやだ!死にたくない、やめ―…ぁぁぁああああ!…………クフ
大声で喚き続けた男の声は絶叫に変わり、唐突にぶつりと途切れた。
あまりの恐怖に、手足の震えが止まらなかった。縋った先輩の腕も、尋常じゃないほどに震えていた。
私は地面に転がるテープレコーダーに全神経を集中させた。
一瞬の沈黙。
そして
wallpaper:535
―クフ、ミツケタァ
しわがれた声が真後ろから聞こえた。
「うわあああああああああああああああああ!!」
「っおおおおおおおおおおおおおおおお!」
shake
同時に絶叫した私と先輩は、ほぼ同時に前に転がった。
完全に腰が抜けてしまっていて逃げることなど全くもって不可能だった。
一瞬前まで私達が背中を付けていた木の横に、2mはありそうな人の形をした何かが立っていた。
髪は地面につきそなほど長く、洋服とも呼べないようなボロ切れが体に張り付いている。むっとした臭気が立ち込め、そいつは口らしき亀裂を大きくあけた。
腕をぶらぶらと振りながらゆっくりと近づいてくる。
私は息をするのも忘れ、ただその姿を見ていることしかできなかった。
こいつに喰われるんだ。
なんとなくそんな気がした。もう恐怖のパラメータは振り切れ、不思議なことにパニックにはならなかった。
そいつはぶら下げた腕を私に伸ばして更に近づいてきた。
wallpaper:158
と、思った次の瞬間。
「うおおおおぁぁぁぁああああ!」
凄まじい大声が私のすぐ隣からから聞こえ、私に触れかかった手は後ろに吹っ飛んでいた。
見ると、いつの間にそうなったのか、N先輩が巨大な枝を振り抜いていた。
先輩は剣道でいう中段の構えを取ると、すっと私とそいつの間に割り込んだ。
吹き飛んだそいつはすぐさま立ち上がると、腕をめちゃくちゃな方向に振り回しながら突っ込んできた。
しかし。
「イヤァァアアア、メェェェエエエエーン!!!」
大上段から振り下ろされた先輩渾身の面が炸裂し、そいつはボロボロになって地面に転がった。
その隙に私を引っ張って立ち上がらせる。そいつはすぐには起き上がれないようだった。
一刻も早く逃げなくてはならなかったが、いかんせんどちらに行けば良いのかさっぱりわからなかった私たちは、とっさに動くことができなかった。
と、その時。私はロープが左に揺れているのを見留めた。
道を探していた先輩の腕をとり、私は何かに導かれるようにして一心不乱に左に走り続けた。
―ニガサナイ
後ろから声が聞こえたが、振り返ることなどできようもない。
私たちは本能のままに暗い森の中を走り続けた。
何度も転びそうになり、幾度となく木に衝突しそうになったが、なんとか進むことができた。
走って、走って、走り続けた。
どれくらい進んだかわからなくなった頃、ようやく前方に明かりが見え始めた。
―ニガサナイニガサナイニガサナイ
やつとの距離が縮まっているのが分かったが、とにかく走るしかない。木に当たることはおろか、よろけることすら許されない。
そして――
wallpaper:83
私たちは樹海を抜けた。
それはまさに、奇跡のような瞬間だった。
人間の手によって整備された林道に出た私たちを朝日が照らす。
これほどまでに太陽の光を偉大に思ったことはなかった。
日に当たった瞬間に、間近に迫っていた気配は嘘のようにさっぱりと消えたのだった。
私たちは地面に転がり、夢中で空気を貪った。
助かったんだという実感が後から後からどんどん湧いてきて、溢れ出した分は熱い涙となってこぼれ落ちた。
男二人で泣きながら抱き合い、歓声を上げた。涙はなかなか止まらなかった。
wallpaper:67
こうして私たちは、あの地獄から抜け出すことができた。
今なら分かる。
あのサラリーマンの霊は私たちに「逃げろ」と言っていたのだと。そして樹海から逃れられたのも彼の助けがあったからだと私は心から思っている。
共に奇跡の生還を果たしたN先輩は今、私の目の前でコーヒーをすすっている。
恐怖体験の回想を終え、やっとひと段落したところだ。
先輩はグイっとカップを傾けると、静かに受け皿に戻し、私の目を見てにやりと笑った。
「でもまあ、あの時初めて剣道やってて良かったって思ったよ」
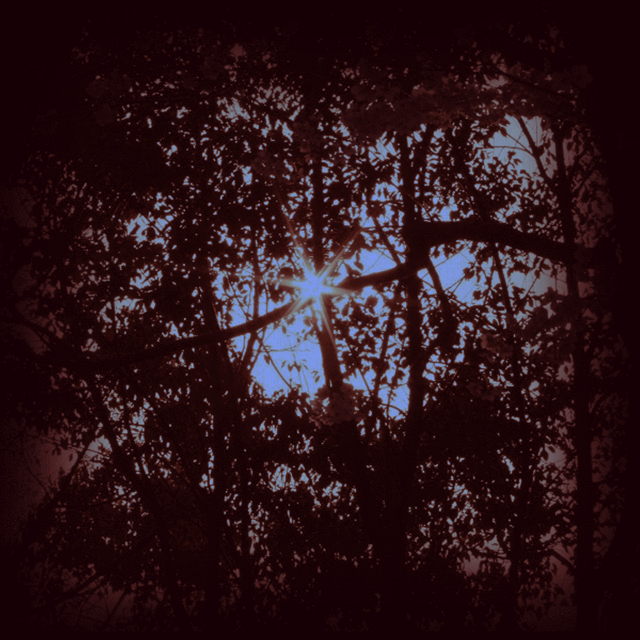



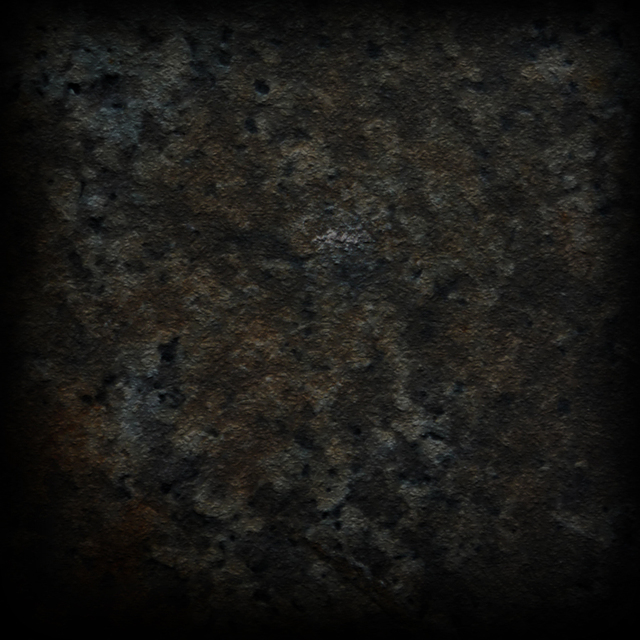
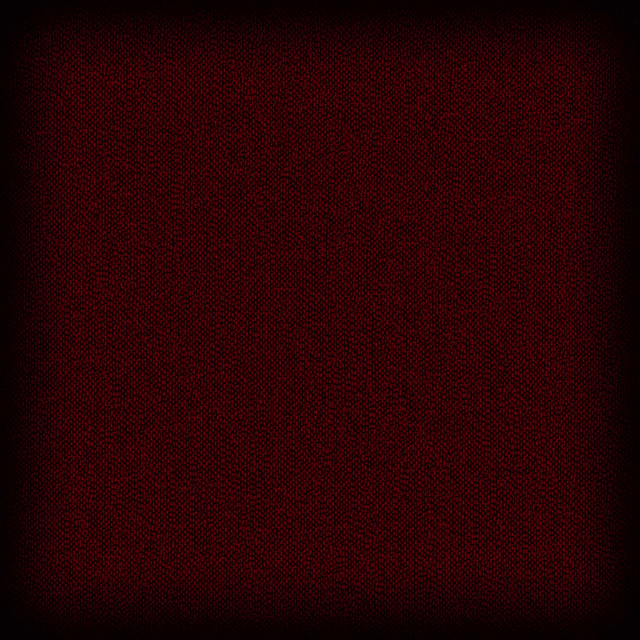
作者ダレソカレ
お久しぶりです、ダレソカレです
今回は実話系の話になっております。どうぞ暇な時にでも読んで頂けたら幸いです。
改めましてコメント、怖い、タグ等大歓迎です
追記
おかげさまで2013年11月の月間アワードを受賞させて頂きました。過去、様々な怖い話を拝読し、一怖話ユーザーとして、アワード受賞は私にとって夢でありました。
これはひとえに、読者の皆様の温かい評価のおかげです。また多くコメントを頂き、非常に励まされました。
長くなってしまいましたが、長文にも関わらず読んで下さった皆様に深く感謝を申し上げたいです。
【2014/12/7 改稿】