母親が居なくなってどれくらい経ったのだろう?
父は世界的な人形作家だ。
父の作るそれは他の誰もが作るものより、美しく、優雅で、官能的だ。
父は気が向いた時にしか人形を作らない。
しかしその人形はそれで十分に余裕のある暮らしをしていける程の値段で取り引きされる。
お蔭で私たちは世間とは隔絶した生活を送っていける。
私達には年頃の親子に在りそうな父と娘の反目なんて関係なかったし、口喧嘩一つした事なかった。
出来る事ならこの生活を維持し続けたいと私は思っている。
父が死ぬまで、私は父を見守りたい。
そしてできる事なら……。
私は父親に、父親に対する以上の感情を抱いてしまっている。
私もそうだが、父が狂ったのはいつの頃からだろう?
自問しなくても分り切っている、母が死んだ時からだ。
父は母との思い出の世界に、自分の逃げ場を見出した。
しかし、その世界は完璧ではなかったのだ。
崩れゆくその世界とともに、父の正気も壊れて行った。
私はそれを哀れに、悲しく、疎ましくも、愛おしく感じた。
父が完全に狂ってしまってどれくらいたったのだろうか?
母は居なかったが、私は父と人形たちに囲まれた生活が好きだった。
父は頑固者だったがそれはあくまで世間に対してであり、私に対して父はとても優しかった。
私は常々『もっと世間に対しても私と同じように接したらいいのに』と思っていたのだが、その反面、なんとなく父を独占しているようで私は嬉しかった。
珍しいことなのかもしれないが、年頃の娘にありがちな父親との反目も私には皆無だった。
今思い出しても、あの頃の私は幸せだったと思う。
しかし、その幸せはそう長くは続かなかった。
ある日、父は私の前に一人の女を連れてきた。
父は何も言わなかったが、私はすべてを理解した。
口には出さなかったが内心では言葉には言い表せないほどの嫌な気持ちでいっぱいになった……。
そして何よりも、私の心を掻き乱したのはその女の容姿だ。
女は生き写しかと思われるほど、母に似ていたのだ。
いや、正直に言えば似てるどころではない。
母は同性として見てもかなり美しかった。
しかし、私の記憶にある母より若いというのもあるかもしれないが、それをさらに上回るほどの美しさをその女は持っていた。
その女は私を見ると
「あら、可愛い。」
と感嘆の声を上げ、屈託のない笑顔で抱きしめようとした。
その瞬間私は、何かおぞましいものが背中を掻け上がるような感覚がした。
「その子に触るな!!」
父が叫ぶ。
もしこのとき父が女を止めてくれなかったら、私はどうかなっていたかもしれない。
やがて、始まった父、私、そして新しい母との生活は私にとって苦痛以外のなにものでもなかった。
父は、新しい母に溺愛し、徐々に私との間に距離を置くようになっていった。
父との会話が減っていく中で、私の中で芽生えていくある感情、それは紛れもなく嫉妬であり、新しい母に対する怨嗟そのものであった。
何故父は私のこの気持ちに気付いてくれないのだろう?
新しい母は、始めは私に好意的に接していたが、いつまで経っても懐かない私に嫌気がさしたのか、次第に仲良くする努力を放棄するようになっていった。
いや…ひょっとするとあの女は同性として、私の父に対する気持ちに気付いていたのかもしれない……。
やがて、あの女は汚らわしいものでも見るような目で私を見るようになった
一方、私の方でもあの女に対する憎悪は膨れ上がる一方だった。
父はあの女と私の仲が最悪なことは知っていたようだったが、何もしてくれなかった。
◇
「私の父を返してよ!!」
私はついに我慢しきれずにあの女に口走った。
それは丁度あの女がいつも通り、アトリエの掃除をしていた時だ。
私はこれもいつも通り、部屋の隅であの女を睨むようにその様子を見ていた……いや実際、睨んでいたのかもしれない。
女は一瞬びっくりしたような顔をしたが、やがて、その顔は恐怖にひきつっていった。
「やっぱり……普通じゃない……」
女はやっとのことでその言葉を口にし、意を決したようにに言葉をつづけた
「いい?貴女がどんなに、あの人のことを想っても、あなたはあの人と結ばれることはないわ。それは、あなたが娘だからとかではないのよ、なぜなら、あの人は私を選んだからよ。女として私を選んだからよ。悪いことは言わない、お願いだから諦めて頂戴……。」私の心は屈辱と悔しさでいっぱいになった……。
「私のお父さんを返してよ!!還してよ!!反してよ!!かえせ!!カエセ!!カエセ!!カエセ!!カエセ!!カエセ!!」
もはや自分でも自分を制御できなくなった。
しかし、それはあの女も同じだったようだ。
「いい加減にしてよ!!」
それを期に女も堰を切ったように叫び始めた。
「貴方が亡くなったあの人の娘がモデルになってるのか何だか知らないけど……所詮、『人形』じゃない!!」
なにを言っているんだろうこの女は?
私が父の娘をモデルにしている『人形』?
それは違う、確かに私は『人形』だ。
しかし、決して何かをモデルにしたのではない。
私は父の娘そのものだ。
「どうしたんだ?」
その時、騒がしくなったアトリエが気になったのか、父がやって来た。
「何でもないわ、いつもの事よ。」
私は父に語りかけた。
父はその場で泣き崩れる女に、優しく包み込むように背中を抱いた。
そして私の方を指差すと
「近づいてよく見てごらん。あの子だけは他の人形と違って特別なんだ。」
と女に優しく囁いた。
女は泣きじゃくりながら頭を振る。
父は抱きかかえたまま女を立たせると、私の方に近寄ってきた。
「ほら、よく見て御覧。」
父は同じ言葉を優しく呟くいた。
女はその泣き崩れた顔を上げ私の方を恐る恐る見上げる。
「『完璧な美しさ』とはどういうものだと思う?」
「え?」
女はきょとんとした顔をする。
「『完璧な美しさ』とはどういうものだと思う?」
父は同じ質問を繰り返す。
「そんな事、分らないわ。」
父はおそらく女が何と答えようと次の台詞を用意していたのだろう。
「単純な事だよ。完璧な美しさとは時代、宗教、性別、年齢、国籍、ホモセクシャル、レズビアン、バイセクシャルその他人間に付随するすべての条件に無関係で、全人類が例外なく美しいと感じるものが放つ美しさだ。」
「……。」
「では、『完璧な美しさ』の条件とはなんだと思う?」
「え……?」
父は優しく抱えていたのとは逆の手で、女の髪を強引に引っ張った。
「『完璧な美しさ』の条件とはなんだと思う?」
「痛い、痛い、痛い!ごめんなさい、ごめんなさい!!!分りません、私は何もわかりません!!」
それを聞くと父は、女の髪を離した。
「人が何を美しいと感じるかは人それぞれだ。しかし、仮に誰もがそのように感じる『絶対的な美しさ』が存在するとして、それだけでは『完璧な美しさ』とは言えない!それが『完璧な美しさ』となるには、未来永劫に存在し続けなくてはならないのだ!!それは決して朽ちてはならんのだ!!そうでなくては、過去の人々はともかく、少なくとも未来の人々には美しいと感じさせることができないからだ!!『完璧な美しさ』が永遠であることは必須条件なのだ!!」
女に父の話は届いているのだろうか、女は先程からずっと項垂れてる。
「よく見ろと言っただろう!!」
その様子に気付いた父は、再び女の髪を引っ張った。
「痛い、痛い、痛い!すいません、すいません!!!見ます!!ちゃんと見ます!!」
顔を上げた女の顔はもはや、絶望に暮れているように見えた。
「この子の母親が死んだ時、私はそれを作ろうと思った。この子の母親が絶対的な美しさを持っていたかどうかは分らない。しかし、それは未来の人たちが勝手に評価すればいい事だ。私はただこの子の母親の美しさを永遠なものにしたかった。」
「……!!」
女は黙って私を力のない目で見ながら父の話を聞いていたのだが、ようやくそのことに気付いたのか驚愕した表情をした。
「しかし、当時の私にはそこまでの技術力が無かった。防腐処理が上手く行ってなかったのだ。皮膚はその鮮やかさを失い土気色に変色し、眼球、鼻、耳など分泌物がある器官は腐敗が早かった。ずぶずぶになった頭皮からは髪の毛抜け落ち、この子の母親の美しさはどんどん失われていった。それと同時にきっと私の正気も失われいったのだろう。」
「ちょ、ちょっと待ってください……ひょっとして……この人形……」
父はもはや悦に入っており、女の言うことなど耳に入っていない。
「その時の経験は私の中で生きた。死んでから用意したのでは遅いのだ、完璧な美しさを作るには生きている頃から処理はしなくてはならない。私はこの子の美しさが最も成熟する時を待った。」
その瞬間、女はその場で嘔吐した。
胃の内容物を全てその場にぶちまけ、さらに激しく嗚咽し続ける。
父のズボンが少し吐瀉(としゃ)物にまみれたが、全く気にせず父は続けた。
「勘違いしないでほしいのは、私はこの子に一切の強制していない。この子は自ら願ってこうなったのだ。むしろ私は反対したが、崩れゆく母親の姿は私だけではなくこの子も正気を失わせた様だ。この子は今まで全ての私の作品の中で、最も『完璧な美しさ』に近い。」
父は女を支えていた腕の力を抜いた、女はゆっくり自ら生み出した吐瀉物の水たまりへ、その身を横たえた。
「が、しかし、君ならもっとそれに近づけるかもしれない」
それからほどなくして、女と私は本当の親子になった。

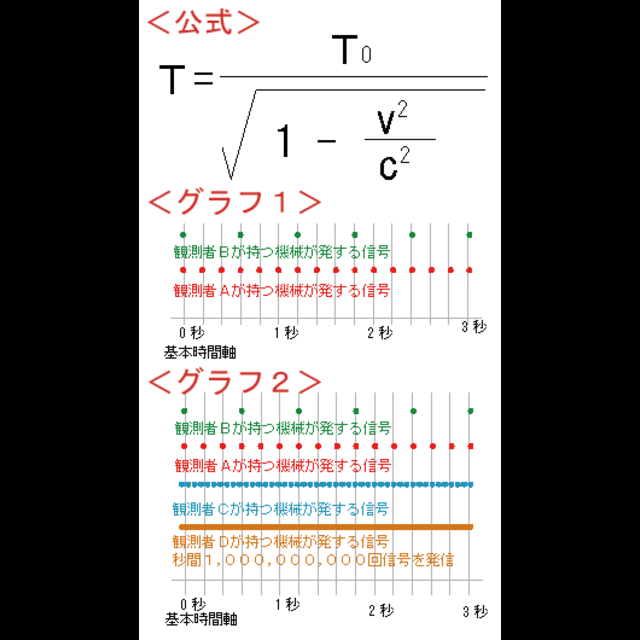
作者園長
んー、なんか詰めが甘いような……我ながら少し練りこみが足らないか……。
語り部の娘の意識がどこにあり、父親や新しい母親がそれをどこまで感知していたかはご想像にお任せします。
次頑張ります。