目の前に静かに横たわる義母を目の前にして、私は自失していた。
義母が目覚めることはもうない。
「君には本当に感謝しているし、おふくろもきっと同じ気持ちだよ」
夫は私の肩をそっと抱いた。
「確かに悲しいことだけど乗り越えていかなくちゃいけない」
そういうと夫はそっと立ち上がり、その場を離れた。私と義母の二人だけにしてくれたつもりなのだろうか。
確かに悲しいこと……ですって?
あの人に私の悲しみがどれだけ伝わっているというのだろう。
きっと私の気持ちを勝手にこうだと想像し、それっぽい励ましの言葉を言って悦に浸ってるに過ぎないのだ。
「おかぁさん……」
娘の恵理子が怯えたような顔をしながら私に声をかけてきた。
私は恵理子を引き寄せると、ひざの上に座らせた。
「……」
再び、もう二度と動かぬ義母へ視線を送る。
義母は私にとって生きる目的であった、ここ数年の生活は義母のためにあったといっても過言ではない。
というのも数年前から、義母は痴呆が進み記憶の欠落おきたり、論理的思考が困難になったりするようになり目が放せない状態になったのだ。
「おかぁさん……泣いているの?」
「うん……、ごめんね」
「何で泣いてるの?」
「悲しいからよ」
「何で悲しいの?」
「もう会えなくなるから」
「ふーん」
恵理子は分かったかどうか判別のつかぬ顔しながらこちらをつぶらな瞳で見上げてくる。
私は抱きかかえながら、恵理子の頭をなでた。
「ねぇ、なんでおばぁちゃんさっきから動かないの?」
「おばぁちゃんは亡くなってしまったからよ」
「亡くなってしまうと動かなくなるの?」
「そうよ、亡くなってしまうと、二度と動かなくなるのよ」
「何で人は亡なってしまうの?」
「おばぁちゃんの場合は寿命よ」
「寿命じゃない場合もあるの?」
「……ええ……あるわ」
ふと気づくと恵理子が怯えたような顔をしてこちらを見上げていた。
私はできる限り自然な笑みを見せた。
私は今どんな顔をしていたのだろうか。
「おばあちゃんが動かないってことはおばあちゃんにもう合えないってこと?」
「ええ、そうよ」
「もうおばあちゃんに会えなくなるから、お母さんは悲しいの?」
「ちょっと違う……おばあちゃんのお世話ができないのは残念だけど。あえなくなるのは悲しくないわ」
「お母さん、あんなにおばあちゃんお世話したのに悲しくないの?」
「ええ」
「おばあちゃん、熱いお風呂が好きだったから60度近いお湯に入れてあげたり、昼間はベッドから落ちないように身動きひとつできないほど紐で縛りつけたり、下のお世話もちゃんと二日に1回、臭くならないようにオシメ交換のときはお風呂で冷水を浴びせたり。歯も弱ってたから柔らかい腐りかけの野菜とかに出してあげたりとかしてたのに?」
「ええ」
「あれ?でもさっき、会えなくなるから悲しいっていわなかった?」
「ええ、そうよ」
「誰と会えなくなるの?」
「あなたよ」
「え?私?」
恵理子は不思議そういうと驚いたような表情でこちらを見上げた。
「ええ、たぶん。あなとはもう会えななる」
「……そっか……もうだめなんだね……」
私は恵理子が愛おしくなり、思わずぎゅっと抱きしめた。恵理子も私にしがみついてくる。
「私にどうしてあなたが見えるのかは分からない……私の脳がおかしくなってそれを見せているのか……ひょっとして魂なんてものが本当にあるのか……」
「……」
恵理子は私にさらにぎゅっとしがみつく。
「でもなんとなく分かるの。きっともう私はあなたを見ることができなくなる」
「……」
「ごめんね。ごめんね」
私にはもうそれしか言えなかった。
「ね、お母さん最後にひとつ聞いていい?」
「なに?」
「何で私は生まれなかったの?」
「あなたを身ごもったとき、おばあちゃんに階段から突き落とされたからよ」

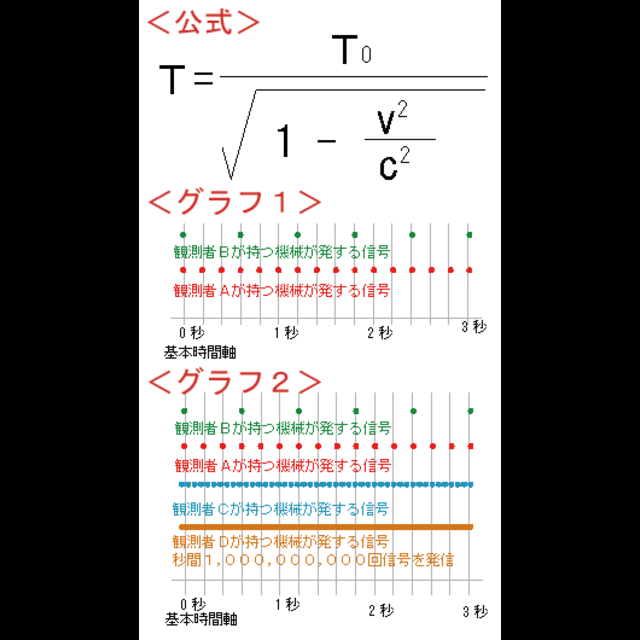
作者園長