wallpaper:213
その後。
そして。
夏休みの終わりとともに、不思議なほど自然に、日常は私の傍らに戻ってきた。
田中恵美。
何の変哲もない、私の名前。どこにでもいる、高校生。
そういうものに、おそらく私はいま、擬態している真っ最中なのだろう。
取り留めない空想をやめ、私はシャーペンを走らせる。数学は、嫌いじゃない。きれいに答えが決まっていて、それを導き出せた時の快感は好きだ。ただ、得意ではない。それだけだ。
問題に集中する私の横で、首を緩やかに揺らしながら、真っ白い何かがうごめいている。
トンボのような複眼、白い髪に白い肌。真っ赤な舌が、時折見える。見た目だけなら、きれいといえば、綺麗なのかもしれない。
傍らにうごめく、かろうじて人の形をした何かは、白無垢のような羽織をまとっている、それだけだ。でもそこに厭らしさはなくて、真っ黒な複眼を気にしなければ、芸術家の作品のような、そんな神秘性がひっそりと眠っているようだった。
これは、一応、蟲らしい。
ただそれも、ただの推測に過ぎない。
確かのは、かろうじて人の姿をしており、私のことが大好きで、私の言うことを盲目的に信じてしまう存在という、三つのこと。
何と呼べばいいかもわからないので、とりあえず私は、白いのと呼んでいる。
霊感少女を気取るつもりは、微塵もない。ただ、私が思うに、こういう謎めいた存在に出会ってしまうのは、いわば通り魔の類に近いと思う。実際私は、そうだった。だれが、夏休みに祖父母の家に遊びに行って、謎の儀式に参加して、意味の分からない存在について来れられて、挙句なつかれるだろうか。
これは、もはや、事故だ。
内心ぶつくさ文句を言いながら、数学の問題を解いていく。数学のいいところは、解き方さえ分かっていれば、いらない思考をしていても勝手に問題を解けることだ。一応、平均点くらいはとれそうな予感がした。
今日は、夏休み終わってすぐの、テストの日。この数学が終われば、今日の授業は終了する。
「はい、そこまで」
問題が解ききれたあたりで、先生の声がする。同時に、チャイムが響き渡る。
sound:15
ああこれで、ようやくテストも終わる。誰となく、ふぅ、とため息をはく。テスト用紙が回収されて、解散が告げられてすぐ、白いのは私の足元にぺとぺとと座り込んだ。早く帰ろう、とねだるように、制服の裾を引っ張る。
「恵美っちー、今日部活いくー?」
背後から、声をかけられる。ぷにぷにっとした丸い頬に、モンブランみたいなショートカットがよく似合っている。派手目の化粧も相まって、まさに現代の女子高生。同じクラスで同じ部活……写真部に所属している、香織だ。
「ごめーん。今日、母さんパート出てて、早めに家帰ってきてって頼まれてるのー」
「そっか。じゃあしょうがないねー。また明日」
ひらひらっと手を振る香織に、手を振り返して教室を後にする。白いのは、最近ようやく覚えたまともな人間の歩き方で、得意そうについてきた。
「できた」
保育園児のような口調で言うから、周囲の人に怪しまれない程度に、うんうんとうなずく。まったく、本当に、なんなんだろう。
何度繰り返したかわからない疑問を心の中で考えてから、ふと私は思い出した。
カバンの中から、書類を一枚取り出す。
「そうだ、先生のとこ行かなきゃ」
例の件の後から、私の住所は変わってしまった。そのことを学校に伝えると、書類を提出するようにと郵送されてきたもの。担任がクラスにいるうちに渡せばよかった、と思いながら、国語科室を目指す。
ほかの高校ではどうなのか知らないが、うちの学校に職員室は存在しない。それぞれの教科の部屋があり、それぞれの教科を担当する教員がそこにいる。だから担任の先生を探すには、それぞれの教科の部屋に行く必要があった。
「しつれいしまーす」
ドアをノックして同時に開けると、担任の境先生が振り返る。
「田中か。ん、住所変更届だな?」
「そうです。お願いします」
書類を手渡すと、境先生は書類に不備がないかするっと確認する。特別、いうべき点もなかったんだろう。
「じゃあ、これは事務局に出しとくから。ところで今日のテストどうだった?」
そんな、ありふれた会話。それをする間、立ってるのに疲れたらしい白いのは、ぺっとり私の足元で、腰からきれいに折りたたまれた状態で、隙間に挟まって休んでいたのだった。
separator
wallpaper:693
元の自宅から、だいぶ離れた今の家。駅まで自電車で10分、そこから高校に近い駅まで電車で15分。割と、遠めだと思う。
それでも通える範囲で済んでいるのは、よかったとしか言いようがない。
「ただいま」
まだ誰もいない家の玄関で、そういいながらカギを開ける。
靴を脱ぐ私の横、靴を脱ぐ真似をしようとして自分が靴を履いてないことを悟ったらしい。白いのが、不満そうに素足をぺたぺたと鳴らす。それを横目に台所に向かって、炊飯器のスイッチを入れた。
母さんも、父さんも、この謎の存在のことは見えていない。けれど娘に、得体のしれない何かがくっついていることだけは確かで、それについていろいろ話している様子もあった。
だけど当の私が焦りもせず、それどころかその得体のしれない何かに、歩き方や読み書きを教えているらしいと分かってからは、話さなくなった。何というか、接し方を考えあぐねている様子だった。母さんは自分の知る限りの≪蟲≫とはあまりに違う様子に、戸惑いっぱなしなんだろう。
wallpaper:944
今も、八塚の蟲がどこからきて、どうして八塚にずっといたのかは、わからない。
母さんという協力者を得て、荒瀬さんもずいぶん調べているようだけど、やはり詳しくはわからないままだ。
「手を洗わなきゃね」
「あらう」
「もちろん私も洗うから」
洗面所で、おぼつかない手つきで手を洗う白いのを見守る。
白いのの知能指数的なものは、相当に低い。いや、本当に蟲だったのだとしたら、言葉が喋れる時点で相当高い。低いんだか、高いんだか、わからない。
そう。人の姿をしている割には低いけれど、こういう存在としては賢い方なのかもしれない。
荒瀬さんのように白いのの姿が見えているらしい人に、まれに出会う。彼らに出会ったとき、少しでもびっくりさせないために、できるだけ普通の幽霊ですって感じになってもらわないと困る。
「何なのかわからないものに、よくそんなに教えられるね」、と荒瀬さんには言われたけれど、わからないから分かる範囲の存在になってほしいんだと思う。
「じゃあ、私これから晩御飯の用意するから」
「うん」
小さな子供のように、白いのはリビングの隅に座り込んだ。ちょっと影になっているカーテンの横が、お気に入りらしい。
食事をとる様子は、ない。チョコレートをあげてみたけれど、そもそも食べるという概念がないらしい。それどころか、私がくれたからと、いつまでも手に握って離さないから困ってしまった。
「えみ」
不安そうに名前を呼ばれるたび、振り替える。振り替えれば、嬉しそうに笑う。
思えばこの、謎の多い複眼にも慣れてしまった。
蟲だというなら相応しいけれど、人というには奇妙すぎる。
相も変わらず、白いのがなんなのかは、わからない。でも分からないなりに、なんとか私は付き合うことができている、と思う。
その思考を、玄関を開ける音に合わせて止める。
「ただいま」
「あ、お祖父ちゃん、お祖母ちゃん、おかえり」
「畑にいってきたのよ。ほら、お野菜。バス停の近くに畑つくって善かったわぁ」
急に家を引っ越したことにも、八塚の家が関わってるなら、と文句を言わない父方の祖父母。二人のその気遣いが、嬉しかった。
いくつかの夏野菜を囲んで、三人で話す。と、白いのが窓の外を見つめていることに気がついた。視線をたどり、おや、と思う。
music:6
此方を、なにか、伺っている。
「えみ、だめ」
白いのが、そう言った。
最近、ああいうものを、よく見るようになった。白いのが駄目だと言うから、近づかないし、見てないことにしている。
庭でこちらを見ていたなにかは窓まで近づいてくると、どん、と鈍い音をたてた。祖父母が驚いて、そちらを見る。
風でも吹いたかな、と不思議そうに言う二人に、なにかはまた、どん、と音をたてた。けれどもう、二人には聞こえない。
今のはたまたま、二人に隙があったから気づいた音だ。そういう異質なものを、感じ取れる隙を、もっていたからだ。でもそういう隙は、滅多に出来上がらない。私は隙だらけではなく、感じてしまっているのでまた別だと思う。
「じゃま」
ぽつ、と呟いた白いのが、窓の外をその複眼で見つめる。それだけで、音は消えた。
music:4
白いのが、何をしているのか、私には分からない。分かりたくはない。邪魔、なんて言って、なにをしたのかは、知りたくない。
「大丈夫だよ」
着替えのためリビングを出た祖父母に、聞こえないような声で言う。白いのは、分かりやすく喜んだ。
「えみの、むしだから」
そうだね。
私はそう小さく笑い、台所へと戻ったのだった。
おわり


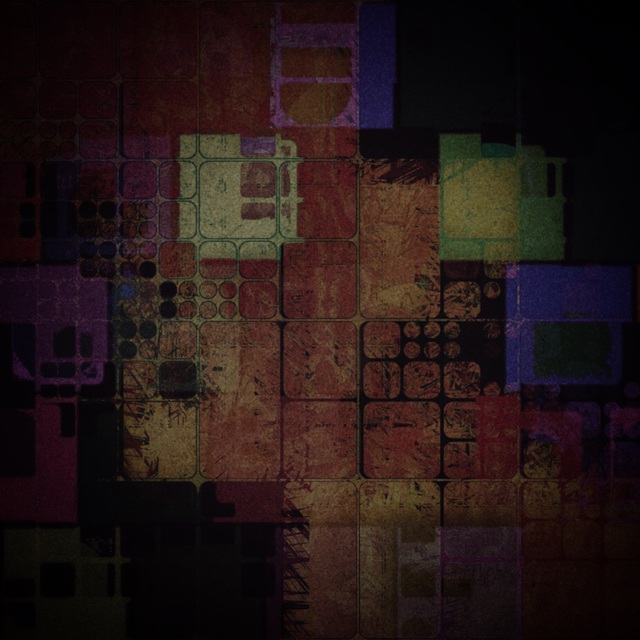
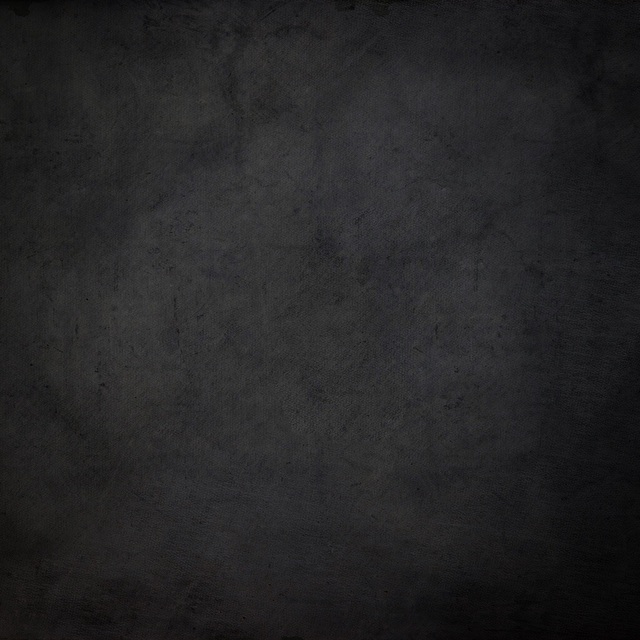
作者六角
続きました。
感想いつも、ありがとうございます。
折り合いながら付き合ってく、怪異とは、そうして付き合い、互いの一線を越えずにいたいものです。