これは、謎の“蟲”に出会った私が、〝蟲”を白いのと呼び慣れてからの話だ。
wallpaper:53
荒瀬さんは、私の知る限り、白いのを含めてあらゆるものが確実に見えている人だ。妙なものにつきまわされてる私のことを、変わり者と言いながら、自分の妹の死の謎を追い求めている人だ。
ただその外見は、軋んだ赤い髪のどう見ても堅気じゃなさそうな、弾けすぎた大学生のような姿。しかも普段着が着物。
おかしい。
そんなことを思いながら、私はカーテンの向こうに見える、知らない世界を見つめた。
歪に上品な店内。
独特なコール。
着飾った男性。
金を積む女性。
それに引き換え、このスタッフルームは、わりかし居心地がいい。目の前に出されたお菓子をつまみながら、私は、田中恵美は素直にそう思った。
「嬢ちゃん、キモ据わってんな」
笑いながら言うのは、タバコを吸いたそうに人差し指と中指を擦り合わせるひと。金のメッシュがはいった黒髪、不自然なブルーの目。野性的な笑みを浮かべ、私の前に並ぶスナック菓子をつまんだ。口寂しいんだろう。
「吸っていいですよ」
そう言うと、気まずそうに返してくる。
「アラヤさんの連れにタバコの臭いなんてつけられねーよ」
なるほど、そういう気遣いだったか。
そう納得した私は、更衣室、という文字の張り付いた部屋から出てきた人に、目を見張る。なるほど、これは。
「どう見てもホストですね、荒瀬さん」
「どう見なくてもホストですし、ここではアラヤでお願いします」
ため息混じりに返されて、私はふむふむとうなずき返す。
赤く傷んだ髪は、簡素にまとめられている。すらりとした長身に似合う、ダークブルーのスーツ。先のとがった革靴は、ピカリと光っている。薄い化粧でもしてるのか、いつもより目元が鋭い。
「荒瀬さんってナンバー?」
「この店のナンバー3を頂いております」
荒瀬邦彦。彼は、民族学の権威の一人、荒木教授の教え子で、今は教授の身の回りすべてを世話しながら、妹さんの死んだ理由を求め、八塚家に絡む《蟲》の存在を調べている。私にとっては、隣の家の奇特な、そして秘密を共有するお兄さんだ。
そのお兄さんがどんな仕事をしてるかは知らなかったが、妙な縁から知ることとなった。
「なんでホストなんですか?」
「大学時代からやってましてね。以外と金がかかるんですよ、古いものって」
ふうん、と私はうなずく。
民俗学に関わる資料は、基本古かったり、貴重だったりする。所謂、骨董、アンティークだったりもする。となると、お金は必要になる。
潤沢な資金がなければ、好き勝手な研究は難しいだろう。
妙なものが見える、着物姿の人。そうくれば、最近流行りの古書店店主かと思い込んでいた。でも、言われてみたら、納得した。
「今日は予約客だけですから、三時間ほどでしょうか。店長にも話してありますから、まあ、ゆっくりしていってください」
「お言葉に甘えます」
ぺこりと頭を下げた私に頷いて、彼は店へと出ていった。残されたのは、私と、もう一人。
私がここに来ざるを得ない理由を作った、ジュンヤという男性だけだ。
「はー、しかし、嬢ちゃんがアラヤさんの知り合いで助かったわ」
「いえいえ」
私が首を横に振ると、ジュンヤさんは意外なほど真剣な表情で、しっかりと頭を下げてくる。
「本当に、ありがとうな」
そんなふうにお礼を言われるのははじめてで、私は少し照れてしまう。しかし、私が何かしたわけではない。
正確に言うと、今そこで、ジュンヤさんの真横で覚えたばかりの体育座りを披露している、白いのがしたのだ。
トンボみたいな黒い複眼、赤い舌。それ以外は、すべて真っ白な、奇妙なそれ。
いまのところ、荒瀬さんと私にしか見えていない、それ。
複雑怪奇。
原因不明。
正体、未定。
それを、私は、白いのと呼んでいる。
「本当に、感謝してんだよ。それは皆もだ」
「お礼は荒瀬さんしてください。私は、特別、なにもしてないですから」
ホストクラブに、私のような高校生がいるのにも、ちゃんと訳がある。いや、訳と言うと、少し足りないのかもしれない。
事の始まりは、荒瀬さんからの電話だった。
separator
wallpaper:244
学校と、部活が終わった午後六時半。電車を待つ私の横で、別のクラスの子達が話している。どうやら、流行りの怪談らしい。
内容を簡単にまとめると、どこぞの店に女の幽霊が出る、という話だった。男への未練でこの世に留まり、店の入り口で自分から男を奪った女を探しているという。
「そのひと、どうして死んだの?」
「そこが怖いんだけどさ、自殺じゃないんだって。病死でもなくて、噂だと、殺されたらしいよ」
「うわ、最悪」
その、最悪、という言葉を最後に、話は終わる。とりとめもない、日常会話が続くなかで、白いのがびちりと私にまとわりついた。
背後から、大切そうに、抱き締められる。
「くるよ」
囁かれ、勘弁してほしいと思う。その、来るものは、大体嫌なものだ。
最近こうやって、白いのが私を何かから守ることが増えた。気づけるようになってしまった私を、来るものから守るために。どうして守るのかは、分からない。でもたまに、眼を覆ったりもしない存在とは、すれ違うことがある。大抵はやたらとはっきりくっきりとした存在で、私の方を興味深そうに見守る空を漂う老人や、突然消える猫とかは見せてくれる。
ただこういう、嫌なものは、絶対に見せようとしない。
「あれは何?」
小さく問いかける。目の前を通りすぎるのは、黒い塊だ。それに合わせて、電車がやってくる。
「ひと」
白いのは、そう答える。
「ひとは、ひとから、きえる。むしは、むし。ひとは、ちがう」
「へえ」
よくわからない。もとから、明確な答えは期待してないけど、どうやら白いのは白いのなりに、答えを持っているみたいだった。だからこそ、私を守ろうとするんだろう。
重みも暖かさも、冷たさもない腕に抱かれ、黒い塊を見送る。電車が止まり、目の前でドアが開いた。と、その時。
「荒瀬さんだ」
震える携帯に、私は車内に乗り込みながら連結部分へ歩きだす。ぱきり、と音を立てて、二つ折りの携帯を開く。
「もしもし?」
「ああ、よかった。今どちらに?」
「学校が終わったので、家に帰る電車に乗ってますけど……」
何の用事だろう。荒瀬さんがこうして電話してくることなんて、数えるほどでしかない。たとえば、両親とどこかに行くから帰りが遅くなるとか、私が両親へと言伝を頼んだりとか。そういう事務的な連絡が殆どで、しかもああよかったなんて言われるとは、余程のことだろう。
「17時34分の電車ですか?」
「え、そうです」
「やっぱり」
ぷつ、と電話が切れる。なんだろう、と思って視線をずらすと、二両目の方からこちらに向かう荒瀬さんが見えた。相も変わらず傷んだ赤い髪に、今日は珍しくありふれたTシャツとジーンズ、それに皮靴を身につけている。珍しい。寝巻すら浴衣のこの人が、洋服を着るところなんて初めて見た。
「後ろ姿が見えたんです。声をかけるのもどうかと思いまして」
「そうだったんですね」
女子高生に後ろから声をかけるなんて、昨今では中々出来なくなってしまったらしい。一歩間違えたら、通報されかねないからだろうか。しかしそんな荒瀬さんも苦笑を隠しきれていない。そりゃあ、そうだろう。大の大人ほども大きさがある白いのが、私にべったりひっついておんぶ状態なのだから。
「相変わらずだね」
「はい」
ちょっと肩をすくめる私に、白いのは荒瀬さんの方へくるりと視線を向けた。
「ひと」
ぽちり、呟いて、また私に肩を寄せた。
荒瀬さんに自分が見えていることを、白いのはなんとなしに理解している。視線を合わせているのだろう、荒瀬さんの表情が微かにこわばった。
「本当に過保護だね」
「えみの、むしだから」
「ああ、そうだね」
苦笑を零した荒瀬さんに、私も苦笑いを返す。なだめるように白いの抱きつく腕をたたいてやると、余計に腕を絡ませてくる。
「今日はずいぶん、甘えているね」
「……気をつけた方が良いってことですよ」
「なるほど」
頷いた荒瀬さんの目線が、すいと動く。眼差しの先を見ようとすると、白いのの手が私の顔面を覆った。暗闇に閉ざされた視界、温度があるようで無い、白いのの存在が私を包んでいく。
「荒瀬さん」
「うん」
「この電車に乗った理由は?」
困ったように、荒瀬さんが微笑んだような気がした。
その瞬間、どんっ、と重い音が近くで聞こえる。ただ周囲の雑音は変化がないから、きっとこれは私や荒瀬さんだから聞こえる音だ。
「実はね、俺が仕事しているところで、困り事があるって言われて」
悲鳴だ。悲鳴が聞こえる。女の人が、長く高く叫んで、泣いている。人としての姿を捨てて、獣のように、犬のように這いつくばって泣いている。白いのは、私をそれから護るように、ぎゅうと強く抱きついてくる。
彼女はただ、そばにいてほしかった。叶わない願いだとも知らず、ただ純粋に、願ってしまった。
願うしか能がなかったのだ。
かなえる力も、叶える知恵も、彼女にはなかったから。
「少しだけ、付き合ってもらえるかい?」
「……わかりました」
白いのがいれば、事足りる内容なんだろう。
白いのは私に害を及ぼそうとする存在を、徹底的に排除する。私に、わずかでも、その何か達が向かってこようとした瞬間に、それすべてをどうにかしてしまうらしい。でも私は、未だにそれがどういう状況なのかは、わからない。
「白いのが、必要なんですよね」
「うん、端的に言うと、そういうこと」
そうして私は荒瀬さんにくっついて、このホストクラブにやってきたのだ。
wallpaper:932
営業が始まっていない真正面の出入り口を、私が通ってすぐ。白いのがかくかく、と首を左右にゆする。
「じゃま」
その一言をこぼして、何かをたたくような仕草をした。どごんっ、と大きな音。思わずびくついた私を、こっち、と荒瀬さんが手を引いてくれる。
ややあって、奥から名札に店長の文字が刻まれた人が、はあと大きなため息をついてやってきた。
「電話、ようやく、鳴りやんだか」
「もう大丈夫ですよ」
「そうか、助かった」
店長さんだろうか。きょとん、とした顔で見上げる私に、別の意味でため息をついたらしい店長さんは、荒瀬さんにごつんと勢いよくこぶしを落とした。
「制服姿の女子高校生を普通に正面から入れてんじゃねぇ!!」
「誰にも見られていませんから」
「そこじゃねぇ! この子がくだんの子だってんなら、余計に迷惑かけるような真似をすんなって話だボケ。わかってねーな本当」
そんな感じでどやされてる荒瀬さんに、思わず笑ってしまう。本当に済まねえな帰るときはこれ着てけ、と誤魔化しの利くズボンをくれた店長さんにお礼を言って、店の奥に案内された。
「悪かったな。妙なもんが店の前に居座っちまってよ、荒瀬の野郎も手が出ねぇっていうもんでつてを頼るったら、お嬢ちゃんに声がかかったってわけか」
「いえ。……女のひと、だと思うんですけど」
店長さんが頷く。
荒瀬さんの勤め先、ホストクラブの入口に、奇妙な現象が起きるようになった。その入り口を通った人のスマートフォン、それもある特定の機種にだけ、謎の着信が残るようになったらしい。出てみると、女の人の声がする。
聞き覚えのない男性の名前を呼んで、自分死んじゃったよと繰り返す。それが何度も起きていて、そして始末の悪いことに、そういう現象に強い荒瀬さんもどうにもできなかったらしい。
「みえないんですよ」
「みえない」
「ええ、元凶だろう存在が、ね」
それで、白いのを連れてきた。
「でも私にも害が及ぶかなんて、そんなこと」
「いえ、及びますよ」
みえないのは、理由だけなんですよね。
荒瀬さんがそう言って、私は首を傾げた。白いのは、電車を降りてから私に巻き付いたままだったので、きっといろいろ見せたくないものがあったのだとは思っていたけど、もしかして。
「あの、その女のひとそのものは、見えたんですね?」
「そうなんですよね」
そこの出入り口。ぶらーんって、ぶら下がってましたので。
肩をすくめた荒瀬さんに、私はああなるほど、と納得する。白いのは、叩き落としたのだ。その、女のひとそのものを。でも彼女がどうしてここにきて、なぜここに居座って、どうしてそんなスマホに影響を与える存在になってしまったのか。その理由は、分からないというわけだ。
「白いのがぶっ叩いた瞬間に、文字通り消えてしまいましたので、大丈夫でしょうよ」
そうでしたかそうですか。しみじみ頷いた私と、お手上げ、という表情の店長。ともかく何とかなりましたから、と荒瀬さんが店長を言いくるめて、奥に帰してしまう。
と、その時だった。
「じゃま」
また呟いた白いのが、何かを叩いた。荒瀬さんが、動きを止める。私は、思わず尋ねた。
「……何かいました?」
「……いえ、何も」
とりあえずスタッフルームに行きましょうか、と荒瀬さんがいう。通路を奥に進む間、じゃま、じゃま、と歌うように言う白いのに、私の顔は引きつりっぱなしだった。荒瀬さんも、顔がこわばっている。
わたしたちに見えなくて、白いのには見えているらしい、なにか。
そうしてスタッフルームで、私は荒瀬さんの後輩とかいうブルーメッシュのジュンヤさんに出会い、ホストという荒瀬さんの職業を知ったのだ。スタッフルームの中では、白いのはじゃまとは言わないので、ちょっと安心していた。
「じゃま」
安心していた、のに。
「じゃま」
また繰り返しだした。今は、スタッフルームに、私一人だ。
「どうしたの?」
そっと手を握り、問いかける。そこで私は、はたと気が付いた。
白いのは、じゃまというし、何かを叩く仕草を見せるけど、私の目を隠してはいない。不安そうな顔をした私に、白いのはハッとしたように、きゅうと腕を絡めてくる。
「だいじょうぶ」
そうして優しく声をかけて、私をぎゅうと、抱きしめた。
「だいじょうぶ、だよ」
一体何が、あなたには邪魔に思えたんだろう。
一体何から、あなたは私を守ろうとしているんだろう。
「じゃーまー」
どこか楽しそうに言っている白いのに、私は仕方なく、その頭をぽんぽんと撫でた。酷く嬉しそうに笑顔を浮かべて、ぎゅうぎゅうと抱き着く白い腕に目を落とし、私は残り時間のつぶし方を考えるのだった。


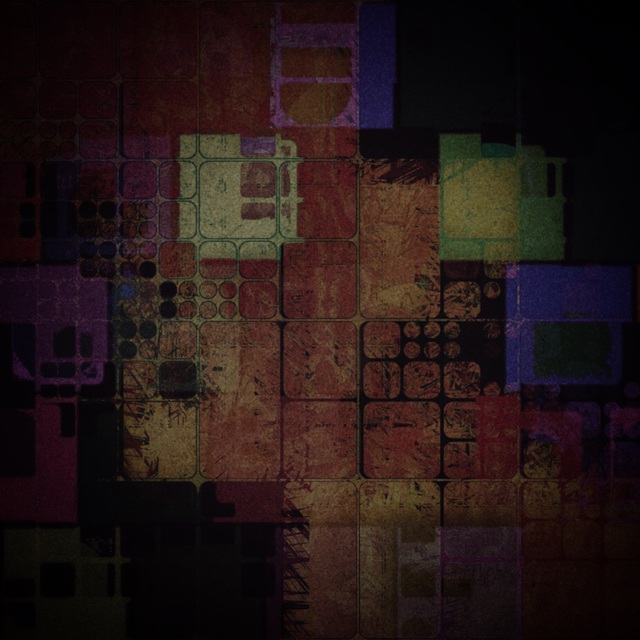
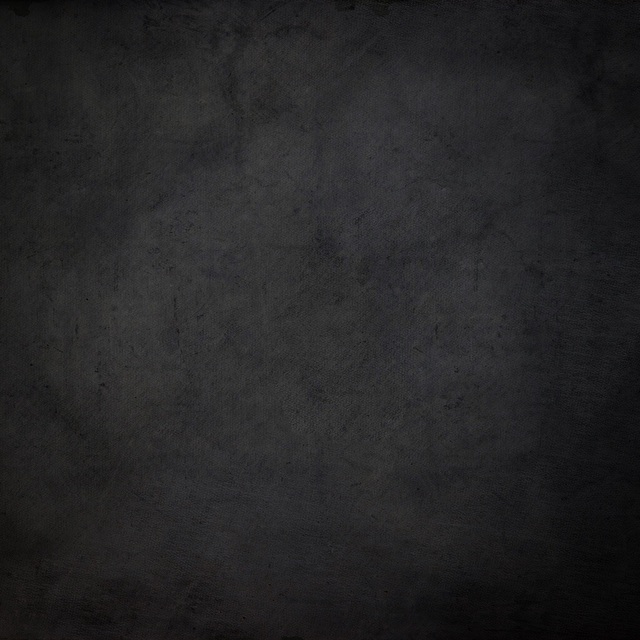
作者六角
どうも、お久しぶりです。
なんとなしにぺろっと書きました。