二、十二月
nextpage
小石のように小さかった弟も少しばかり大きくなり、底の景色も夏が過ぎるとすっかり変わってしまった。
僕は川から上がって、すっかり冷えた巌の上で、半分よりも小さくなったお月様を眺めていた。
どんなに青い葉っぱも茶色く枯らしてしまいそうな、そんな冷たい風が背中をなぞる。
今日の雲は広くまばらだ。
隣で体を丸める弟は、ふるふるとした口から泡を膨らませている。
nextpage
『やっぱり僕の泡のが多きや』
自慢げに話す弟は、自分の方が僕よりも大きな泡を吐けるのだと、口の前で膨らむ泡を僕に見せびらかす。
目がニヤッとしていて、顎を突き出すように口が上がっている。
どうも弟は近頃自慢したがりな年頃になったみたいだった。
ドヤァとした顔が少しうっとおしい。
僕は深呼吸をするように大きく息を吸うと、ゆっくりと泡を膨らます。
nextpage
『いや、僕の方が大きいさ』
半分よりも小さくなった月が目の前の泡にとらわれる。
その月が丸い泡の表面をふふふっと揺れて、月も寒がっているように見えた。
弟はその泡を見て少しムッとすると、
nextpage
『兄さん、わざと大きく吐いているんだい、僕だってわざとならもっと大きく吐けるよ。』
と言って、自分も大きく息を吸うとふぅーっと息を吐いた。
泡はゆっくりと膨らんでいったが、半月より後の月がその中に収まり切るかどうかの所で、ぽんっと音を鳴らして割れてしまった。
nextpage
『おや、たったそれきりじゃないか、やっぱり僕の方が大きいだろう』
先ほどのドヤァとした顔をお返しする。
『大きか無いやい、おんなじだい。』
弟はムムムッと赤い顔をもっと赤くすると、
両のはさみをばたつかせるように抗議する。
『近くだから自分のが大きく見えるんだよ。それなら一緒に吐いてみよう。いいかい、そら。』
『もういいやいっ。』
弟は少し拗ねてしまって、ぷいとそっぽを向いてしまった。
そのそっぽを向いた頭の先を見ると、弟の泡に入れなかった月が居場所をなくして、揺らぐ川面へと落ちてしまっている。
波が青白い火を、燃したり消したりしているようにふるえて、
あたりはしんとしたまま、只いかにも遠くからというように、その波の音が響いて消えた。
ぐぅぅ、と寂しそうにお腹の虫が鳴った。
nextpage
『だめだい、そんなに伸びあがっては。』
岩の間から、お父さんのカニが出て来た。
『もう寝ろ寝ろ。明日はイサドへ旅立つんだから。』
『お父さん、僕たちの泡どっち大きいの』
『それは兄さんの方だろう』
『そうじゃないよ、僕の方大きいんだよ』
弟のカニは泣きそうになって訴える。
『お前も、もっと大きくなれば、兄さんよりでっかい泡が吐けるさ。』
お父さんが右のはさみを弟の上に置く。
『じゃあ、イサドに行けば大きくなれるかな。』
『ああ。』
『兄さんより大きくなれるかな。』
『ああ、なれるさ。』
『イサドには食べるものがあるかな。』
『ああ、きっと。だから、今日はもう寝ろ寝ろ。』
『うん。』
弟はそう言うと寝床の方へと消えていった。
『お前も、もう寝ろ』
『...うん……』
nextpage
空を見上げる。
寒空の一番高いところから、ゆっくり傾く遠くの月は、今にも灰色の雲に飲み込まれてしまうところだった。
足元の川は今では常に土煙が広がっていた。
こんな遅い夜更けにも、毒ガスがまかれるように、辻を作って細かい土埃が流れている。
お父さんはこの川の上流の方でよく無い事が起きているんだと言っていた。
そこで何かが起きているから、こんな毒のような土煙が流れて、エサも無くなってしまったんだと、そう言っていた。
nextpage
ほんの数日前に、近所の大人のカニ達が上流の様子を見に行った。
その時上流へ行ったカニ達で、無事生きて帰って来たのは五匹の内のたった一匹だけだった。
しかも、その一匹でさえ体の片方をしびれたように引きずっていた。
聞けば、一匹は土埃に混じった泥がエラに詰まって死んでしまい、二匹がドロドロした白い粘土のようなものに飲み込まれてしまったという。
白い粘土に飲まれなかった者も必死になって逃げてきたが、そのうち一匹はイタチに捕まり食べられてしまった。
生き残ったカニも危なかったのだという。
よくわからない白い粘土に怯え、でもイタチがいるから川からは出られず、土煙でまともに先が見えない川の中を、必死になって逃げてきたそうだ。
でも、その生き残ったカニでさえ、二日と経たず、死んでしまった。
上流の方の土煙には、毒が混ざっていたようで、徐々に体が動かなくなって死んでしまったのだ。
その上流の川の水が、薄まっているとはいえ、ここにも流れている。
この場所はまだ川底が見えるが、上流ではちょっとの先も見えないそうだ。
上の方はこの世の地獄だ、この場所もいずれその毒が溜まってしまう。
nextpage
イサドに行けば、川下の方へと行けば、この土埃も川底に落ち着いているだろう。
食べるものだって、きっと……
月が厚い雲に覆われ、僅かな光もついに途切れた。
僕は寝床に潜ると、明日去る故郷の石を抱いて静かに眠りについた。
お腹に抱いた石ころは、一つだけ外れたボルトのように無機質で、
そのやけに冷たい手触りに、この場所が冷え切ってしまったことを僕は思い知らされた。
nextpage
○○○
nextpage
イサドへの道のりは七日も掛かるのだそうだ。
僕と、弟と、お父さんの三匹で、縦一列になって歩いていく。
外にイタチやアライグマがいるかもしれないので、ずっと澱んだ水の中に隠れながら歩く。
先頭にお父さん、その後ろを弟がきょろきょろしながら歩いていて、僕は最後尾でその二人の影を追いかけた。
もやもやと煙たい川の中は先を行く二匹の影を曖昧に隠して、執拗に不安をあおる。
好奇心旺盛な弟がわき道へ消えてしまったら、という危なっかしさも僕の心にゆとりを与え無い。
しかし、下の方へと下っていく程にたしかに水の色は透明になっていった。
お魚も僅かながら泳いでいるのが見える。
視界がクリアになっていくごとに、故郷から遠ざかる実感がする。
それは、寂しさと悲しさを背負わせつつも、卑しく安心感を見せびらかした。
nextpage
『お父さん見て見て、周りが綺麗だよ。』
弟がはさみを振り回して声を上げる。
太陽が丁度一番高いところに登っていて、日の光が少しずつ川の中に照明をもたらす。
薄く、チリが舞ったように浮いている砂の粒が、天井から射す光に乱反射して川全体が薄い雲のように白ばむ。
弟はそれを、乳を零したようだと笑っている。だけど、僕にはその白さが毒々しく思えた。
お父さんは弟にそうだな、と一言いうと、何も言わずにまた歩き出した。
細く、つたない足を動かして歩き続けると、二日目の夕方頃には川の水は完全に透明になった。
雲を抜けた後の川底は、夢から覚めたようにはっきりと現実を映していた。
nextpage
三日目、道中、お魚がひっくり返って死んでいた。
その時にはもう日が沈んでいた事もあり、その顔がなんだかゾンビのようで恐ろしかったけれど、久しぶりの食料だから、みんなで食べた。
ゾンビになったお魚はやけに骨が小さくて、肉も少なかった、僕らはそれをゆっくりと時間をかけて咀嚼する。
半ば腐りかけている魚は、お腹を壊すといけないから内臓を食べてはいけないと、お父さんが注意をする。
ぐちゃぐちゃとしたお魚の肉は、硫黄の様な嫌なにおいがした。
吐き気を我慢するように顔を上げ、重力にさせるがままに今食べたものを飲み込む。
上を向いたまま天井の方を見やると、視線の先で細く頼りない三日月がゆらゆらゆらと、波に押されてひしゃげていた。
あんまり大きくないお魚は、三匹で食べるのには小さかった。
特に食べ盛りの弟には明らかに足りてなさそうな様子だ。
お魚の内臓にまで手を出そうとして、ぴしゃりとはさみを叩かれていた。
nextpage
ふいっと、弱々しい月の明かりに一瞬影が入った。
僕は背中をなぞられたような寒気を感じた。
『クラムボンだ……』
上流から流れてきたそれは、薄暗い夜に出会ったためか、ひどく恐ろしいものに見え、死に対する恐怖が掻き立てられる。
それは、ここでお魚の死体を食べているからかすぐ身近に感じられて、僕は猛烈な吐き気をもよおす。
上の方を見ていられず、横を見るとお父さんは悲しい目を向けていた。
あのクラムボンが故郷から流れたモノでないことを祈っているように見える。
nextpage
その隙に、お父さんのすぐ後ろでは、弟が食い意地を張って食べてはいけないお魚の内臓に口を付けた。
僕は、それを止めようと口を開きかけるが、言葉が出るより先に無理にせき止められていた吐き気が気管を塞いだ。
反射的に口を塞いでしまった僕は、弟が潰れたナメクジのようなはらわたを飲み込むことを、止められなかった。
nextpage
次の日、沼の中から起き上がるように目が覚めると、川の水が無くなっていた。
どういうわけか、一晩でほとんどの水が引いてしまっていたのだ。
お父さんもどうしてこんな事になってしまっているのか、皆目見当もつかない様子だった。
それでも、真っ直ぐこの川を下らなければならない、イサドに行けば、きっと大丈夫なんだからと、小さな希望に縋りついて僕らは歩いた。
nextpage
僕らは歩いた、下へ下へと急ぎ足で。
だけど、すぐに立ち止まってしまった。弟がお腹を抱えて蹲ってしまったのだ。
あのお魚の内臓は、やっぱり食べてはいけなかった。
暫く葉っぱの影で休んでも弟は回復しなかった。ずっと苦しそうに、お腹をまるめて呻いている。
仕方がないので、僕とお父さんが交代で弟を背負って歩いていくことになった。
ずっと御免なさいと言いながら泣いている弟は惨めで、その身体は枯れ枝のように軽かった。
出来るだけ早くイサドに行けるように、僕とお父さんは速足で歩く、
それでも弟を背負いながらだから、三匹で歩いているときと同じくらいのペースにしかならなかった。
そんな苦しい状態で一日歩き、二日歩いた。
道中食べるものも無くて、ずっとお腹が空いていた。早く弟に何かを食べさせないと、そう思ってもどうする事も出来なかった。
nextpage
弟を背負って三日目で、ついに弟は何も言わなくなった。
僕はそれが何を意味するのか、分かりたくなくて、ピクリとも動かない弟を背中に乗せたまま、その身体を下ろす事も出来ずにずっと黙って歩いていた。
お父さんがもう止せと僕に言っても、背負い続けた。
僕の背中で、弟がお腹が空いていると言っているような気がした。川の底に沈んだどんぐりがそろそろ食べ頃じゃないかと言っている気がする。
ああそうだねと、僕はその声に頷いて背中へ目を向ける。
そこに見えるのは生意気な弟の顔であるはずだった。
でも、僕の視界に入ったのは、色の失った乾いた双眼と、中身のない赤い殻だった。
その薄い殻の隙間をヒューヒューと入り込む風の音が、弟の死を証明していた。
僕はその音が世界に聞こえないように精一杯の声で泣く事しか出来なかった。
この日の夜は、月が丁度全部欠けていて、いつも以上に暗く冷たい夜だった。
nextpage
○○○
nextpage
イサドに着いたのは、次の日の午後だった。
空にはどんよりと厚い雲が広がっていて、湿った空気が朝からずっと纏わりついていた。
結局、僕らはあのお魚のゾンビ以降、何も食べていなかった。
何も、苔一つ食べるものが無かったのだ。
だから、それが見えたときには例えようの無い安堵の気持ちが湧き上がった。
少し岩が出っ張ったその奥に、たくさんの赤い点々が見えたのだ。その赤色は、間違いなくカニの殻の色だった。
僕は一目散にその赤色の場所へと駆け寄った。
あれだけのカニがいるんだ。きっと食べるものだって沢山あって、僕とお父さんにも分けてくれるはずだ。そう信じて疑わなかった。
近くに来てみると、カニの甲羅特有の生き物の香りがしてきて、その匂いがこの場所に活気が残っているものだと期待させた。
nextpage
けれど、その場に動くものは、何もなかった。
水も、虫も、植物も、そこには何もなかった。
イサドにいる沢山のカニ達のその全員が、只の殻だった。それは、ここにある全てが餓死していることを表している。
深い絶望感が僕を襲い、あの死の音がクレッシェンドで耳をつんざいた。
nextpage
ヒューヒュー、ヒューヒュー、ヒューヒュー、ヒューヒュー、ヒューヒュー、ヒューヒュー、ヒューヒュー、ヒューヒュー、ヒューヒュー、ヒューヒュー、ヒューヒュー、ヒューヒュー、ヒューヒュー、ヒューヒュー、ヒューヒュー、ヒューヒュー、ヒューヒュー、ヒューヒュー、ヒューヒュー、ヒューヒュー、ヒューヒュー、ヒューヒュー、ヒューヒュー、ヒューヒュー、
nextpage
赤茶けた、枯葉のような殻の間で僕は立ち尽くした。
視界の端で、お父さんが近くに食べ物が無いか探し回っている。きっとお父さんは非常食の置き場所を知っているのだろう。
けど、そんなことは無駄だと僕は思った。そして、
nextpage
ばりっ、
僕の視界の中でお父さんが砕けた。
岩の後ろから飛び出してきたアライグマが、父さんを捕らえて噛み砕いたのだ。
酷く乾いた音だった。まるで中身が空っぽのように、軽い音だった。
僕を残して消えていく命があまりに儚く、小さなものだと、教え込む様な理不尽な音だ。
僕はまたも動けなかった。目の前でお父さんが死んでしまうのに、声を掛けることさえ出来なかった。
アライグマは、その場でぱりぱりとお父さんを食べると、口元も拭かずにこちらを向いた。
その顔がこの世の物では無いようにぐにゃりと歪み、ナイフの様に鋭く尖った犬歯が光る。
nextpage
…あぁ、ああぁ……
殺される。そう思った時には走り出していた。
アライグマの腕が届かない岩の影へと潜り込んで、その奥の方へとさらに逃げていく。
必死に逃げた、僕は死にたく無かった、死ぬのが怖かった。
お腹が空いて十分に動けない体を精一杯動かして、とにかく走った。
日は知らないうちに朱色に染まり、背の高い木々の影が槍のように伸びている。
ごつごつした石が散らばった地面が僕の足を挟もうとする。
この世の全てが、僕を殺そうとしていた。
nextpage
『うぁっ』
足場の無い切り立った崖を、僕は滑り落ちた。
真っ逆さまに生きたまま地獄に落とされたような感覚がする。体の節の辺りがカラカタと揺れた。
ガン、と途中で体が木にぶつかって、枝ががさがさと音を立てる。
nextpage
ポチャン。
薄赤く染まった水の中に僕は落ちた。
ぶくぶくと細かい泡を立てながら体が沈む。
どうやら、ちょっとした窪みに水が溜まって、僕は一命を取り留めたみたいだ。
甲羅を下に向けた状態で僕は底に着いた。
nextpage
トブン。
黒くて円い大きなものが、僕が落ちた場所から沈んで、直ぐに上へとのぼって行く。きらきらと黄色の皮が光った。
さっきぶつかった木が実を落としたのだろう。
夕日の影になって暗いが、その形に見覚えがあった。
nextpage
ヤマナシだ。
よく熟している。あと三日もすれば、きっとこの水辺の下に降りて来るんだろうな……
まともな食べ物を見たのは、いつぶりなのか分からない。
ヤマナシは炎立つ天井でじっくり煮込まれたような香りを立たせ、ただぷかぷかと揺れていた。
僕はそっと左手を伸ばす、先ほどぶつけた右半身は潰れて動かない。この池の深さはあまり無いはずなのに、精一杯に伸ばせない腕が空を切る。
なんだか本当に力が抜けていった。
斜めに入る日の光が心地良い。
あんなに苦しかった空腹感も何も感じなくなって、僕はゆっくりゆっくり瞳を閉じた。
風も無いのにヒュウヒュウという音が聞こえた気がした。
nextpage
やがて日は落ち、中身の無くなった赤い殻は、水の流れに遊ばれて、いつか浮き上がる様に昇って行く。
nextpage
クラムボンはかぷかぷわらった。



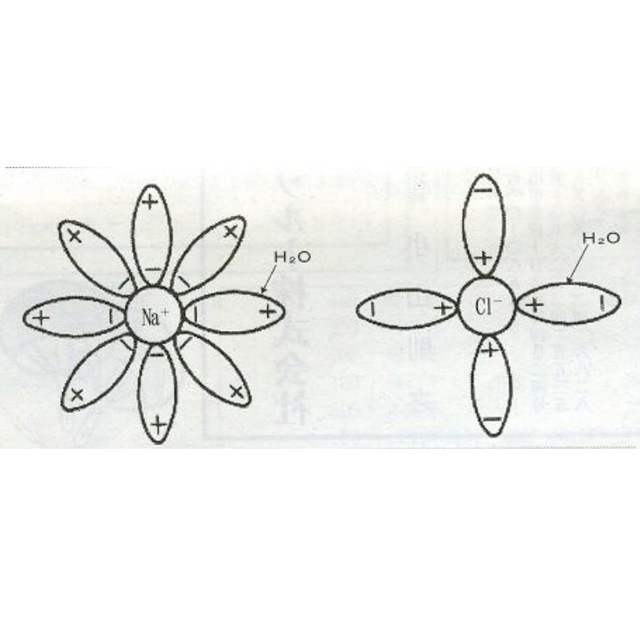
作者ふたば
前半は此方になります。出来れば先にお読み下さい。
→ http://kowabana.jp/stories/27474
私の桃源はこれでお終いです。
最後まで読んで下さった方々有難うございました。
誤字脱字、おかしな日本語が御座いましたら遠慮無くお申し付け下さい。