新社会人になってすぐの時借りた部屋は、安さもあって、玄関と廊下の区別がない。
なんというかトイレ風呂、そしてキッチンを左右に置いた真ん中のスペースが、一応廊下にあたるらしかった。
その先に部屋が一つ、そして隣にもう一つ。そんな間取りで、俺はそこに4年ばかり暮らしており、去年から大学生になった弟が転がり込んできた。
物も食い扶持も増えたが、親からの家賃支援が来るようになったので、そこは感謝している。
朝から出かけた弟は、最初に決めた約束通り、朝食を作って置いていった。味噌汁はなんとか作れるようになったらしく、具が山のようになった味噌汁をすすっていると、玄関のインターホンが鳴った。
sound:16
通話ボタンを押して声をかけると、郵便局です、と初老の男性が笑みを浮かべて立っていた。そう言えば、書類が会社から届くことになっていた。サインが必要なタイプの奴だったのだろう、と思いながら、一応人前に出ても大丈夫なことを確認して、ドアを開けた。
先ほど述べた通り、我が家の廊下は真っすぐで、すぐに部屋が見える。その上、キッチンも玄関に接しているようなものなので、そこを目隠しするために、暖簾をつけていた。暖簾から首と上半身を出すようにして、やり取りをする。
サインをフルネームでお願いします、ご苦労様です。
受け取ったものにサインをして、ボールペンと共に返そうとすると、男性の反応がない。
「どうしましたか?」
彼の視線は、俺の真上を見ている。
なんだかわからない直感が働いて、スリッパをはいたまま、男性を押すように家の外へ出る。玄関先の鍵を一緒に持って、いつもの出勤と変わらない手際で鍵を閉めた直後。
どすん。どっ、からん、からん、からんからんからん……。
何かが落ちて、のれんも落ちて、のれんを通してあったポールが落下した音。そして、ぎゃーーーっ、と言う、どこか高い声が響いた。
俺がぽかん、としていると、ブルブルと震えていた男性が恐る恐る、俺に尋ねてきた。
「お子さんは、いらっしゃいますか」
「は? いいえ、いません」
「そう、ですよね。あ、自分、ここが配達ルートで、こちらにも荷物を届けたことがあって、その時もお兄さんだけだったので」
「ああ、いつもお世話になっております」
ぺこりと頭を下げると、男性はどこか気まずそうに続ける。
「……こういう仕事してるとね、見かけるんです。玄関先で、のれんとか、カーテンを目隠しに使ってらっしゃったり、ドアの隙間からやり取りされる方。そういった方の、背後にね、ありえる位置や、ありえない位置から、みえるものが、あるんです」
「……子供がいたんですね?」
「……ええ。あなたの、真上。のれんの上から、顔だけ見せてました」
ちょっと考えて、ああなるほど、と思った。
おそらくそれは、俺に肩車してもらってる状態だったのだ。それでのれんの上から顔だけ出していたが、俺が部屋から出てするーっと居なくなったものだから、のれんに引っかかって落下したのだろう。
それで、のれんも、落ちたのだ。
首でも引っかかっていたのだろう。
「まいったな……お祓いでもした方がいいのか」
「あ、あの。私は、これで」
「ええ、ああ。はい、気を付けてくださいね、少し落ち着いた方がよさそうですよ」
青ざめた顔で、逃げるように立ち去る男性を見送って、俺は部屋の玄関をにらむ。さて、開けるべきか、開けざるべきか。
と、入れ替わるように、軽い足音が聞こえてきた。
軽快なレゲエのリズムが、小さく響いている。
「兄貴、なにやってんの?」
「おかえり」
帰ってきたのは、朝から出ていった弟だった。日課のジョギングを終えて、コンビニに寄って、ちょうど帰り着いたらしい。
いや本当に、ちょうどなことだ。
「俺もちょっと出てたんだけどな」
「ああ」
「鍵、持ってくの忘れちまって」
弟が、あー、と苦笑いする。
そう我が家は、オートロックなのだ。古い築年数をハンデとするこのアパートは、大家さんの地道なリフォームにより、そこそこ人気を保っている。オートロックなのも、防犯設備が良いとして、評価が高いらしい。
「じゃあ俺開けるから」
「すまん」
「いいって」
そうして、弟が、鍵を開けた。
ドアが開いて、その瞬間に何か影の様なものが駆けだしていく。弟が不思議そうな顔で、俺を振り返った。
「兄貴、今、ばかやろうって言った?」
「なんで言わなきゃなんだよ、鍵開けてくれてんのに」
「空耳かな……あ、のれん落ちてる」
ポール買い替えなきゃかな、そんなことを言う弟に続いて家の中に入る。鍵を後ろ手に閉めて、ちょっとかわいそうなことをしたなぁと、少しだけ思うのだった。


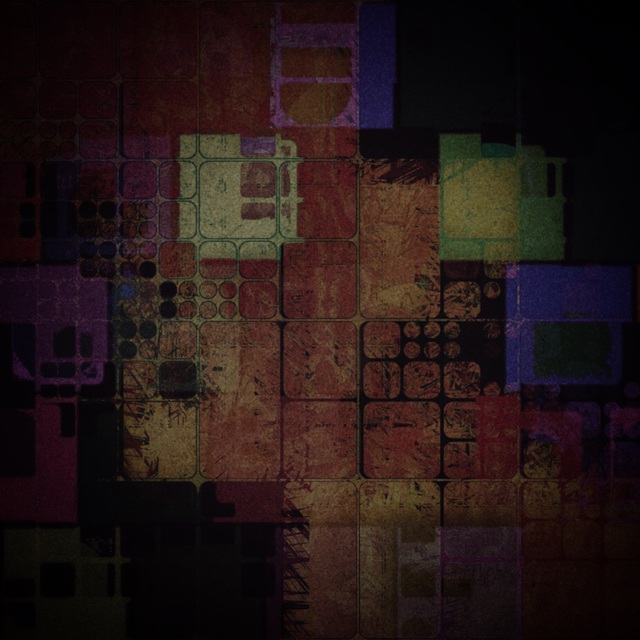
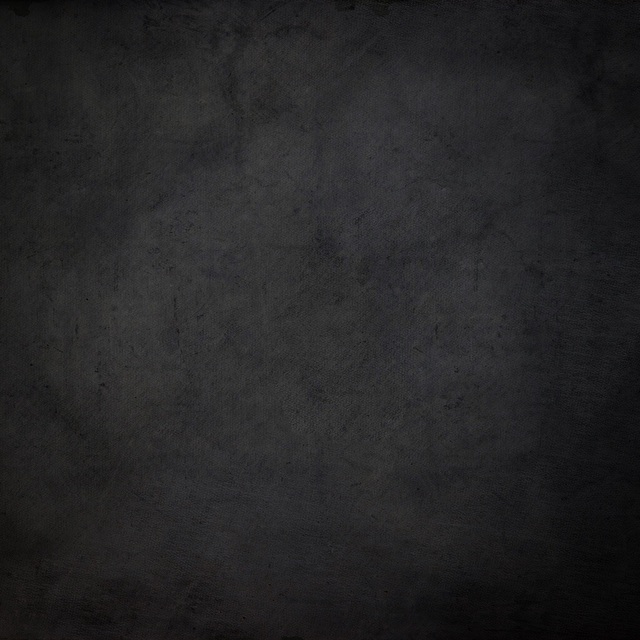
作者六角