複雑怪奇。奇妙奇天烈。おおよそ遠く、おおよそ近づけず、理解とは対極に座るもの。
私、田中恵美が、その不可思議な存在との縁を持ってから、1年余り。
それはふと、気が付いたことだった。
歯磨きをして、パジャマにも着替えて、明日の用意を確認してメールとラインのチェックを済ませたら、私は電気を消してベッドにもぐりこむ。ふー、とため息を吐きながら目を閉じて、なんだかわからないけど、突如気になった。
「……白いの?」
「どうしたの、えみ」
暗闇にまだ慣れない目にも、ぼんやりと映る真っ白な影。いつもの着流し姿のままに、それはふわふわと歩いてきて、ぺとんと私のベッドの横に座った。
「そういえば、アナタ、寝てるの? ううん、寝れるの?」
「わかんない」
「えーと、じゃあ、私が寝てる間はどうしているの?」
おやすみって、言った後の時間。それを白いのがどう過ごしているのか、ふと気になった。いままではなぜか気にならず、放置していた。
「えみが、ねたら、ひま」
「暇でしょうね」
「ひと、は、ねる。むし、は……」
どうしてたっけ。
真剣な顔で悩み始めた白いのに、今まで本当に何をしていたのか怖くて聞けなくなる。とりあえず、寝るという概念がないことは分かった。
「でも真っ暗ななかだと、遊びもできないしなぁ」
「うん」
「……あっ」
そうだ、部屋が真っ暗だからこそだ。
「かくれんぼなら出来るかな。真っ暗だし」
「おに、いないよ?」
「……本当だ」
それじゃあどうしようもない。しばらく考えたけれど、いい案が思いつかなかった。
「じゃあ白いの、一緒に寝よう」
何かわからないことをされるよりは、そっちの方がましだ。白いのはぴくんと顔をあげて、私とベッドを交互に繰り返し見た後で、
「せまく、なっちゃう」
至極まっとうなことを、心配してくれた。
「うーん……あ、それじゃあ」
思いついて部屋の押入れから、布団を引きずり出す。この部屋には来客用の布団がしまってあるので、とりあえずそれを床に敷いた。
「ここで寝ればいいよ。まねっこで、横になっているだけでもいいし」
「わかった」
布団に入る仕草は私を見て分かっていたのか、真似をしてするりと入った白いのは、ちょっとごろごろと左右に転がり、私の方を向いて横になった。
「ふかふか」
「おお……感触の表現、新しい。じゃなくて、良かったね」
「うん」
おやすみ、と私が言うと、おやすみ、と声が返る。そこで私は目を閉じて、翌日までぐっすりだった。白いのも布団の中が気に入ったらしく、夜はここにする、と楽し気に言うので、布団の敷き方と畳み方が当面の目標となったのだった。


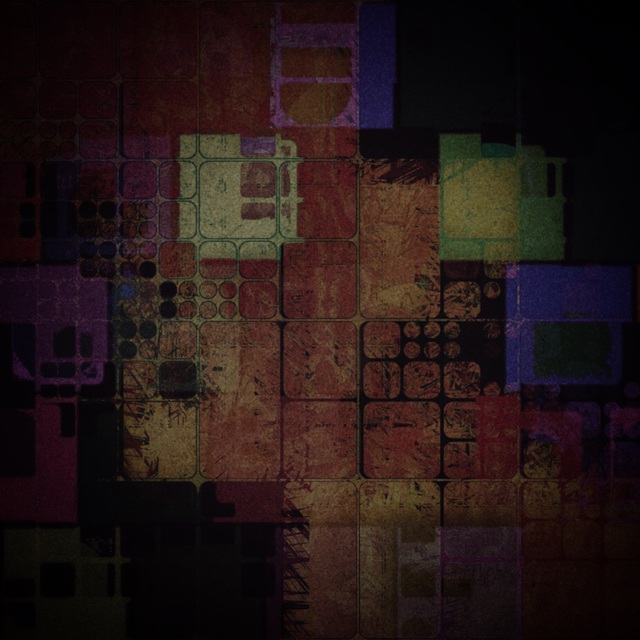
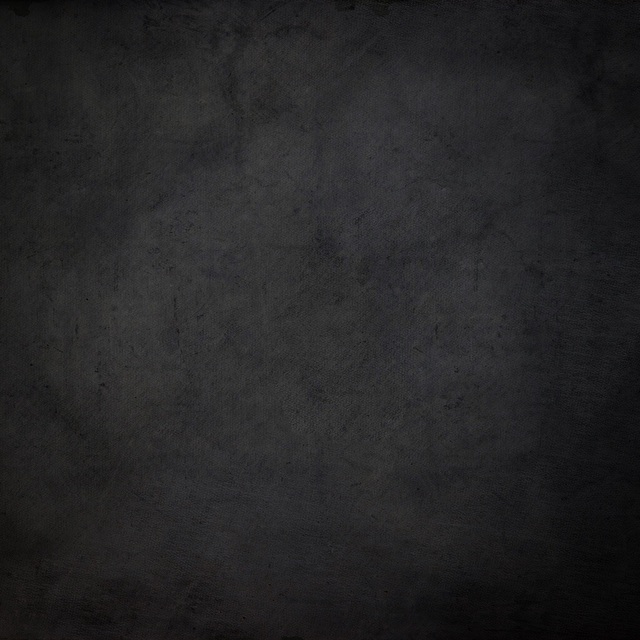
作者六角
はたしてそれは、眠るのか、眠っていたのか、それとも目を閉じただけか、それまで何をしていたのか。
謎なのでございます。