雨が、絶え間なく鎌倉の町を、包むようにして降っていた。そんなある日、俺と同居人のSは、一階の庭先にある縁側で、ボーっと雨を眺めていた。
二十一にもなろうという男二人が、縁側で茶をすすりながら、しとしとと降る雨音に耳を澄ませ、糸の様に細い雨粒を見て、目を細めている。
他人から見れば、昼間っから若い男が何をやっているんだと、悪態をつかれるのかもしれないが。生憎と今日は、Sは大学が休みで、俺は古書店が定休日。別にサボっているわけではないのだ。
ただ、たまにはこんな日があってもいいと思う。
何か目的があるのもいいが、何も考えずただこうやって、思考を緩ませ、怠惰に身を任せるのも悪くない。
「そういえばあれがあったな」
Sはそう言って立ち上がると、廊下を歩き台所へと向かった。
俺はSを見送りながら、再び庭先に視線を戻す。
──ピョン
ふと、縁側の下で何かが跳ねた。
視線を落とすと、またもや、
──ピョン
再び跳ねた何かは、今度は俺が腰掛ける縁側に上ってきた。
珍しい、雨蛙だ。
ころんとした喉元をコロコロさせながら
「ゲコ」
と、小さく一鳴き。
「雨蛙か、可愛いね」
いつの間に戻ったのか、Sが平皿を手にしてこっちを見ている。
「それは?」
俺が聞くと、Sは平皿を縁側に置いてそのまま自分も腰掛けた。
「この前Mさんがくれたやつだよ。茶請けにぴったりだなって思ってね」
Mさんは近隣に住む、農家を営んでいるおばさんだ。そういえばこの前、家で取れた野菜を漬けてみたのと言って、大根やキュウリの漬物を頂いたのを、俺は思い出した。
「ああなるほど、確かにこれは合いそうだ」
薄く変色した沢庵を一枚手に取ると、俺はそれをポリポリとかじりながら茶を啜った。
「うん、さすがMさん、良い味付けだね」
Sの声に、俺も賛同するように頷く。
「ゲコッ」
雨蛙が喉を鳴らした。
「君もそう思うかい?」
Sが雨蛙を覗き込みながら言う。
「いや、食べた事ないだろ」
思わず俺が言った時だった。
Sが縁側の下に視線を落として、何やら凝視している。
気になり俺も目をやると、そこには、
「蛇だ!」
思わず俺は声を上げた。
が、Sは動じもせず、
「見れば分かるさ。大丈夫、毒はないやつだよ」
Sはそう言うが、さすがに体長一メートル近くはありそうな蛇が、縁側の木柱を伝い上ってくる様子を、平然としながら見守る事はできない。
俺は直ぐに蛇との距離を取った。
「おいおい、そんなにビビらなくても、雨蛙君を見てごらんよ?」
「え?」
言われて雨蛙を見る、すると
「ぴ、ぴくりともしないね」
「だろ?蛇に睨まれた蛙、と言いたいとこだが、どうも蛇も蛙も、お互い眼中にないって感じだ」
そう言ってSはケラケラと笑って見せた。
確かに。Sの言うとおり、蛇は蛙には目もくれず、縁側に上ってきて、そのままとぐろ巻いたかと思うと、じっと庭先を見つめている。
対して蛙は、蛇に気付いていないかのように、相変わらず喉を鳴らして、
「ゲコッ」
と、まるでSに返事でも返しているかのようだった。
「こんな事ってあるんだな」
不思議に思いながら、俺は縁側に座りなおす。
「蛇も蛙も、雨宿りがしたかったんだろうさ」
Sはそう言って湯飲みを口に運ぶ。湯気がふわりと舞い上がり、雨粒の中に紛れ、消えていく。
俺とS、そして2匹?は、再び静まり返る縁側で、しとしとと降る雨空を眺める。
なんともおかしな光景だろうな、そう思った時だった。
背筋が急にひんやりとしだした。
肌がじわじわと粟立つような感じだ。
隣にいるSに目をやる。明らかに顔色がおかしい、何かに勘付いた様な顔をしている。
何だ?
注意深く辺りを見渡そうとした時だった。
Sの隣側に、何か違和感を感じた。
もう一度よく見る。
「あっ……」
思わず小さな声が漏れ出た。
分かった、違和感の正体が。雨だ、Sの隣だけ雨が降っていない。いや、正確には、部分的に雨が降っていない。
しかもその雨が降っていない箇所は、良く見ると、まるでそこにもう一人、人が座っているかのように形どっている。
透明人間、とでも言えばいいのだろうか?よく分からない何か、その何かが、Sの隣に息を潜め、いつの間にか座っているのだ。
直ぐにSの名を呼ぼうとした。が、Sはそんな俺の行動を察知するかのように、人差し指を口元に当て、ジェスチャーを返してきた。
それを見て、俺は浮かした腰を元に戻し、縁側に腰掛けなおす。
それでも目は離せない。
Sの肩越しにその何かに目をやる。
それは微かに動いていた。
体を小さく前後させ、ゆらゆらと体を動かしているようにも見える。
それを見て、俺はハッとした。
ふと、昔この家で見た光景が頭を過ぎる。
小学生だった俺、まだ現役だった頃の祖父さん、そして隣に住んでいた、祖父さんの友人でもあったKさん。
祖父さんとKさんは、よく今の俺とSのように、二人して縁側に腰掛けて、外を眺めていた。
小さい頃の俺は、そんな静けさが苦手で、直ぐに外に遊びに出かけてしまうのだが。
そう、あの時のkさんが、まさに今の様に、体を前後させ、ゆらゆらと小さく体を揺らせながら、縁側に腰掛けていたのだ。
「K……さん?」
思わず俺が声を掛けた時だった。
「止んだよ……」
Sがぽつりと言った。
言われるまま俺は空に視線を移した。
あれだけ降っていた雨粒が、今はどこにも見当たらない。
それどころか、鎌倉の町を覆っていた曇天の空には、雲の切れ間から光が差し込もうとしていた。
「あ、Kさん?」
直ぐに視線をSに戻した。が、Sの隣にはもう、誰もいなかった。
雨が降っていないから見えないではなく、確かにそこには、何の気配も感じられない。
「おや、彼らもいないようだね」
Sの言葉に、俺は思い出し辺りを見回した。
蛙と蛇もいない、いつの間に……。
「さてと、雨も上がったし、洗濯でもしようかな」
Sはそう言って大きく背伸びをする。俺はそんなSを見ながら、
「な、なあ、さっきのあれ、何だったと思う?」
と聞いてみた。
するとSはにこやかに笑って見せてこう言った。
「蛙も蛇も雨宿りするんだ……幽霊だって、雨宿りしたっていいだろ」
言われてから、俺の頭の中に、生前のkさんの柔和な笑みが浮かんだ。
「そう……だな」
Sに続き、俺も立ち上がると、その場から離れようとした。その時、ふと視界に映るものがあった。
庭を挟んだ向かい側の道路、そこを、紫陽花柄の傘が横切る。
傘を差した人物は、雨が止んだ事に気がついたのか、上空を見上げ、差していた傘を閉じた。
傘から出てきたのは、地元の女子高の制服を着た少女の姿。
その姿に、俺は見覚えがあった。
あれはそう、近くにある山の麓で行われた、幻のお祭り。真夜さんが招待してくれたあのお祭りに、真夜さんと同じ、リンドウの着物を着て、隣にいたあの少女。
「人間……だったのか?」
唖然とする俺の声に気がついたのか、少女はゆっくりと、こちらに振り返った。

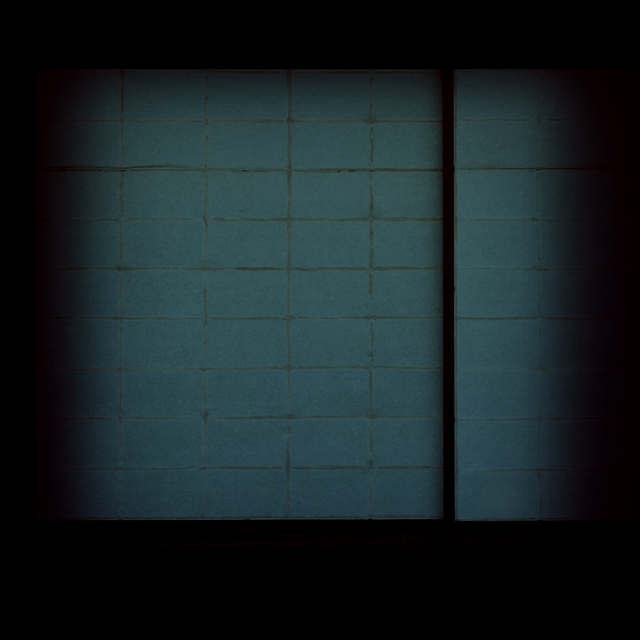



作者コオリノ
次回予告の表題を変更しております。
あー沢庵食べたい。
前回→同居人「本ノ蟲」http://kowabana.jp/stories/29820
第一話→同居人「狐現灯篭」http://kowabana.jp/stories/29793