wallpaper:1797
寒い日で、今にも雪が降りそうだった。
今日は家族を連れてきた。
「あったあった」
「あなた、どこ行くの」
「すぐ終わるから」
俺は目を閉じた。
nextpage
separator
「何でも恥ずかしがってるよな、おまえ」
「ん」
俺の顔をしっかり見てから、みーちゃんは顔を反らす。俺が視線を戻すと、またじっと見てくる。
「ん」
本当に人を好きになると、一つの行為を延々とできるようになる。無意味とかそういう次元の話じゃなくなることを、俺はみーちゃんと出会って理解した。
一緒にゲームをしたり、キスしたり、見つめ合ったりするだけで馬鹿みたいに時間を消費できた。
「神経に作用する何かが生まれるんだな」
「また難しいこと言ってる」
「おまえはまたアホな顔してる」
「なんやと!」
くだらないことの方が楽しい。
元々俺は無駄なことや非効率なことが大嫌いで、人生の中で最もそう感じるものは恋愛だ。
第一印象が良いのか、近づいてくる女は何人もいた。けどみんな実際に付き合うと飽きたように逃げていく。それも気を遣って、変な理由をでっち上げて。
ともかく、どんな人間の前でも俺は恋愛観を語れなかった。
「余計なこと考えやんでいいやん」
「え?」
はっと我に返ると、みーちゃんの寝顔が目の前にあった。
「なんか言ったか?」
問いかけに、みーちゃんはすうっと息をするだけだった。俺と違って布団をむちゃくちゃにせず、大人しく寝ていた。頭を撫でてやった。
みーちゃんを撫でる感触は昔飼っていたハムスターを思わせた。俺に女の髪を撫でる習慣が無いからだろうか、とても脆い存在に感じた。
ペットを一方的に可愛がることは好きだった。だけど、育てきれずに死なせることが多かった。そんなんだから恋愛も実らなかったんだろう。
どうやら俺の手のひらは、みーちゃんの小さな頭を気に入っていた。
「けーくん」
「起きたか」
「けーくんがおる」
みーちゃんは俺といる間はとにかく幸せそうだった。
「時が止まってしまえばいいけど、俺もおまえも動けなくなるんだよな」
「どっちがいい?」
「考えとく」
nextpage
みーちゃんが仕事の都合で遠距離恋愛になってから、あっけなく俺たちの関係は悪化した。
単純なことだ。まず会う回数が減る。そうすると連絡が滞るだけでソワソワする。
つまり連絡を待つだけでストレスになる。
どこかに遊びに行くとなれば、誰と行くのかを気にし始める。
何時に帰るのか、何しに行くのか。
そうして自分が卑しくなり<もうだめだ>と落ち込んでいると、いつもみーちゃんが察して声をかけてくれた。
「わたし、けーくんのこと好きよ」
このときの彼女は、いつになく真剣になる。
「プロポーズしてくれたら、すぐけーくんのとこ行くから」
「ありがとう」
そのうち俺にも耐性が付いたのか、みーちゃんを信じる強さのような、形容し難い感情を持てるようになった。
感情より行動を先にするっていう、どっかの偉そうな人の教えも参考にした。
nextpage
そろそろ結婚を考えようとしていたとき、みーちゃんは音信不通になった。
「しばらく会えなくなるかも」事の発端がこれだ。
「どういうこと?」
「これからのこと、考え直そうと思って」
嫌な言葉だった。俺は物事を1か0かで決める癖があったので、<振られるのか>と考えてしまった。それでも言葉にせず、やりとりを続ける。
「距離を置くってことか?」
「うん。ごめんね」
「理由は?」
「今は何も言えない」
なんだかんだかっこつけてきたけど、俺の理性はあっけなく崩れた。
ただ、みーちゃんに怒りをぶつけることだけはしなかった。できれば死ぬまで一度もしたくなかった。
「わかった。待ってる」
かろうじてそれだけ伝えて、俺は携帯を投げた。
それから半年経っても音沙汰は無く、いい加減に振られたと悟った。
それにしても、遠距離で自然消滅とはひどいもんだ。こっちがどうしていいか分からない。ストーカーのように電話をかけまくるわけにもいかず、亀みたいに何十年も待つわけにもいかない。
また失恋だ。
そしてすぐに切り替えようとした。俺には仕事がある。仕事が。今度こそ恋愛はしない。
nextpage
連絡が途絶えて1年が経った。
気持ちのいい朝だ。俺は空をぼんやり見てから、あっちがいいか、こっちがいいかと迷っていた。後ろで<ギギ>と音がした。風でドアか壁かが軋むのはいつものことなので、放っておいた。
それが、ドスンという響きに変わったものだから、慌てて部屋に戻った。
「けーくん!」
こもった声が届いた。
「みーちゃん?」
玄関のドアを開けるとみーちゃんがいた。
「お墓参り行こう。そんなに遠くないから」
「はあ?」
久々に会って第一声がなぜ<お墓参り>なのか。
12月。朝の6時で外は暗い。みーちゃんの服は完全防寒着で、初めて会ったときから使っているストールを巻いていた。
「何しに来たんだよ。というか誰の墓?」
「私の家族」
「え?」
変な空気を感じ取った俺は、みーちゃんを部屋に入れた。
「家族が亡くなったの?」
「うん。事故の後、昏睡状態になって。弟も乗ってた」
「それは、その」
俺はどう声をかけていいか分からず、項垂れた。
自分の浅はかさを痛感した。
「ごめん。俺ただ振られたとしか」
「そんなわけないやん。ずっと会いたかったんやで」
「そっか」
全く変わっていない、丸っこい顔を見ると、それまでのことがどうでも良くなった。みーちゃんを抱きしめ、その温もりを奪った。
「けーくん寂しかったんやなあ」
「あたりまえだろ」
「わたしの実家こっちやから、けーくんと一緒に行けるって思ってん。サプライズやな!」
正直、墓参りなんかせずにみーちゃんとくっついていたかった。それでも俺はこの子に手を引かれたら、絶対に断れなかったんだ。
nextpage
家を出て、閑散とした商店街を歩いた。不思議と風は冷たくないが、息は白くなり、声は小さくなる。
耳を澄ませば、まるで二人以外誰もいない世界のようだった。
ボロボロの屋根はいつになっても修繕されなくて、台風のときには屋根の一部が落ちてきたことがある。今でこそ笑えるけど、やっぱり通るたびにおっかない。
「こんなに静かだったかな」
みーちゃんが繋いだ手を何度も握りしめてくる。
「けーくん、彼女できた?」
「できてないな」
「なんで?けーくん優しいからすぐできそう」
「優しいだけじゃできないんだ。ああいうものは」
みーちゃんが言ってほしいのはそこじゃないと気づく。
「いや、みーちゃんを待ってたからな」
「ほんまに?ほんまに?」
急に嬉しそうに腕を揺らした。
「おまえなら別れるにしても連絡の一つはすると思ってた」
「周りがずっとバタバタしてたわあ。ドタドタかなあ」
「どっちでもいいけど、ドタバタだろ」
本来ならここからバスに乗りたいところだけど、みーちゃんが歩きたいと言うので歩き続けた。
「思ったほど遠くないけど、おまえは時間あるのか?」
「余裕」
「墓参り終わったらどうするんだ」
「けーくんが決めて」
「はあ?」
そもそも、家族が死んだのに、なんで悲しい素振りを見せないのか。そんなに早く立ち直れるものか?
「一緒に暮らすか?」
「いいなあ。それめっちゃいいと思う」
「一人は寂しいだろ」
「うん」
ようやく真顔になってくれた。ここまでずっと笑顔だったのが、ほんの少しだけ怖かった。
「あれ」
俺は駅の方に違和感を感じた。
何かは分からないけど、肝心なことが。
「けーくん何か飲む?」
薄暗い自販機の前でみーちゃんが立ち止まった。
「ああ」
「おーいおちゃか、いえもんか、ゆずれもんか」
「おーいおちゃ」
ペットボトルが大げさな音を出して落ちてきた。
「ありがとう」
「こういうのって手を温めるのに使うのか、飲んで温まるのに使うのか、迷うやんなあ」
「そうかな、いつもすぐ飲んでる」
「じゃあ今日は温める方に使って」
「いいけど。あのさ。みーちゃん」
「なに?」
「電車もバスも、さっきからぜんぜん走ってないんだよ。それだけじゃない、人がいないんだ」
みーちゃんは目を丸くした。
「やっぱりこれ、夢なのか」
「ううん、けーくんが見ようとしてないだけ。そういうのは存在でけへんねん」
「何を言い出すんだ」
「わたしの腕にぎってみて」
「うわ」
俺はその不気味な感触に、すぐに手を離した。
みーちゃんの腕が低反発マットのように凹み、時間をかけて元に戻った。
「けーくんがわたしを疑い始めてる」
「なんだよ今の」
「あんなー、わたし実は死んでんねん」
「は?」
息が止まった。
「うそうそ!ごめん!まだ生きてる!」
みーちゃんが軽快に笑う。
「そんな嫌な嘘つくなよ」
俺は不機嫌になったが、彼女の笑顔には太刀打ちできない。
nextpage
separator
「もうすぐやでけーくん」
「案外きついな」
歩きっぱなしでさすがに足が重い。
山に近づくと、そこかしこにホタルが現れた。ゆらゆらと飛んで、俺たちの後をついてくるようだ。俺は寝ぼけているのか、その光が橙や黄や緑といった色とりどりに見えていた。それは街灯よりも自然的で弱々しく、俺の心を鎮めてくれた。
この坂を登れば墓地に着く。俺はふと、無性にみーちゃんに触れたくなって、頭を撫でた。
「なあに?」
「こうしてると落ち着く」
「わたしも」
「やっぱり別の日にしないか?」
「だめだよ。ここまで来たのに」
「そっか」
何か、今までの会話でいろいろと見過ごした気がしていた。怖いわけじゃない。懐かしさに似たものが込み上げるのだ。でも俺はこの墓地に来たことは一度も無い。
不可解な気持ちを残したまま、俺たちは坂を登ってゆく。入り口が見えてきたところで、みーちゃんは駆け足になった。
「なんでそんな元気なんだよ」
俺は離れないように後を追った。
nextpage
開けた場所に出ると、ようやく墓石たちが出迎えてくれた。
やっぱり俺はこの景色を知らない。
少ししてみーちゃんは立ち止まり、指差した。
「あった!わたしのお墓」
ドンと胸の真ん中を突かれたように俺の体が固まった。
「わたしのって」
4人の名前があった。見てはいけないものを見る気持ちが吐き気と共に込み上げた。冷たい感触が指先に伝わる。
掘られている名前を辿ると、確かに彼女の名前があった。
「やっぱり夢か」
「ちがう。ほんまのほんま。分かったやろ?」
みーちゃんの表情は穏やかだった。俺はその腕をつかみ、帰ろうとした。
でも、何も掴めていなかった。
「もう触られへんね」
「ふざけるな」
俺は現状を理解できずに叫んだ。何度掴んでも、立体映像のようにすり抜ける。
みーちゃんの体はスカスカになっていた。そしてさっき見たホタルのように、色とりどりにグラデーションしていた。
「いやだ。来るんじゃなかった」
「けーくんが証拠見せろって言うから見せたんやで」
「もういい。証拠は。いいから帰ろう」
「あかんねん。けーくん、信じてもうたやろ?というか最初っから認めてなかっただけ」
俺は<うう>とうずくまり、何とかみーちゃんを現実に留める方法を探した。それは渦巻きのように頭の中を掻き回すだけだった。
じんわりと涙がこぼれた。
「わたし、けーくんのこと好きよ」
おぼろげな手が俺の頭に触れる。
「けーくんが優しいこと、一番分かってる。誰よりも分かる自信がある。だから、前に進んでほしいねん。そのためにここに呼んでん。だってけーくん」
みーちゃんは微笑んだような、哀しんだような顔でうつむいた。
「今日死のうとしてたやん」
そうだ、俺が彼女を呼んでしまったんだ。
どうでも良かった。あれから俺は光を失っていき、何を見ても、何に触れても、砂を体に刷り込まれるような苦痛だけを感じていた。やがてその感覚すら失くし、なんだかみーちゃんが空にいるような気がしてたまらなくなった。
「おまえが呼んでくれたと思ったのに、なんだよ」
涙がいよいよ止まらず、顔を二度三度こすった。みーちゃんを見れなかった。
「俺はおまえがいないと」
「わたしはいつでもおるよ。勝手におらんことにせんといて」
その手が俺の握りこぶしをほどいた。
「けーくん赤ちゃんみたい」
「おまえだろそれは」
みーちゃんは昔のように笑った。
「あーあ、わたしけーくんと結婚したかったなあ」
「音信不通は結局何だったんだ」
「けーくんとの結婚、反対されててん。あんたは体が弱いから金持ちじゃないとあかんって。1ヶ月くらいケンカしてた。そんなことしてたからバチが当たったんやな」
「結婚か」
いつかは当たり前のように結婚するものだと思っていた。
こいつはどんな想いで死んでいったのだろう。痛かったに違いない。悔しかったに違いない。
もうそんな想いをさせちゃいけない。
「よし」
俺は目一杯の息を吐いて、けじめを付けることにした。空を見て、墓石を見て、みーちゃんを見て、自分を見つめた。
「なんか俺ばっかり泣いて恥ずかしいな」
「知ってた?幽霊は泣かんねん。でもな、けーくんにも泣いてほしくないから」
みーちゃんは空を見上げ、口元を結んで、何か呟いた。
「わたしの魔法で、けーくんの涙を止めたろ」
あたりがひんやりした。
「おまえが降らせたの?」
か細い雪だった。子どもが見ても嬉しくならないほどの。
「どや!」
「すごいのかすごくないのか分からない」
「すごいって!魔法やん!」
「なんていう呪文?」
「えっと、ユキフルデイ!」
「適当すぎるだろ」
二人で笑ってしまった。
あとはいつもようにくだらない話をした。皮肉にもこのとき、どんなに中身のある話を考えても無駄に感じた。何十回も話したことを、仕草を、繰り返すだけで心が澄んでいった。
墓石に背中を預けて、決して積もりはしない雪を眺めると、この先には何も生まれないんだと分かった。
nextpage
「あ、今から振り向かんといて」
俺がたまたま背を向けたとき、みーちゃんは言った。
「なんで?」
「わたしが帰れなくなる」
語尾が震えていた。緊張したときや別れ際にそうなるのを俺は知っている。
「おまえも寂しいんだな」
「けーくんの背中見たらいろいろ思い出した。あと、そのお茶は置いてって」
未だ不自然に温かいペットボトルを手に俺は何か言おうとしたが、黙ってその場に置いた。
「けーくん」
「何?」
「一人で抱え込まんといてね。苦しくなったらここ来て、全部話すんやで。わたしけーくんの性格知ってんねんから」
「俺も知ってるよ」
「私よりも。弱い部分があること、知ってんねん」
「わかったよ、わかったから泣かないでくれ」
「幽霊は泣かんもん」
「そうか。じゃあ行くからな」
灰色の空から落ちてくる真っ白な粒に、頭を撫でられながら歩を進めた。
「けーくん!今日は来てくれてありがと」
これがみーちゃんを見た最後の時だった。
nextpage
separator
「あら、降ってきたわね」
目を開けると、妻が隣に立っていた。
「誰のお墓?」
「ん、昔の知り合い」
「若いうちに亡くなったの?」
「まあな」
「そう」
妻はすっと前に出て、手を合わせた。その慎ましさに、どこか似たものを感じた。
「ねえパパ、なんで冬に墓参りするの?ともだちはみんな夏に行くって言ってたよ?」
俺は答えを考えるフリをする。
「パパは雪が好きなんだよ」
「雪って、ほとんど降ってないし」
「これくらいがいいんだ。寒すぎずに見れる。これくらいが」
あいつが運んできた幸せを俺が生かす。
思い切りのない雪を見ると、そんなふうに感じるんだ。
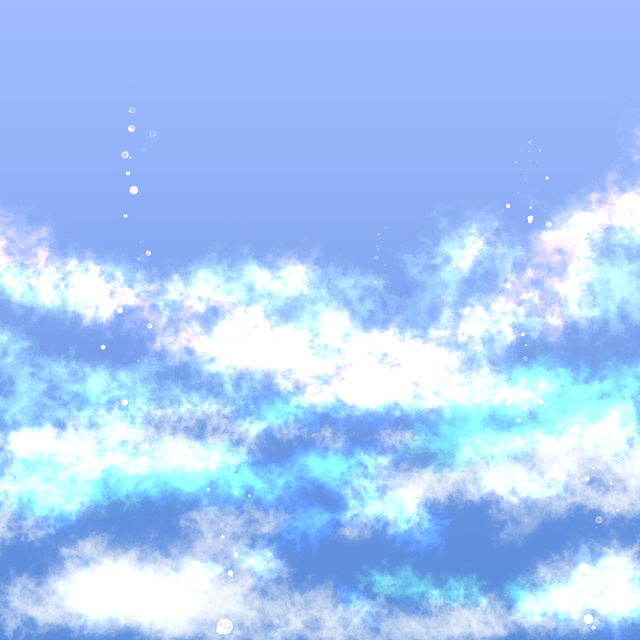

作者ホロクナ
一転してほんのり温かい方の話を書いてみました。
こんなの怖い話じゃない!と言われるかもしれませんが。