「まただ…」
朝、目覚めると枕があらぬ所へと移動している。
最近、このようなことが毎朝続いている。
昨日なんて勉強机の下に移動していた。
「そんなに寝相悪いのかな…」
私は寝る時、畳の上に布団を敷いて寝ている。
そのため、寝相が悪い私の枕が夜な夜などこかに移動していてもさほど可笑しくはない。
しかし、ものには限度がある。
自分が寝ている反対側、つまり足下にまで枕が移動するなんて、本当に有り得るだろうか?
一体、自分は毎晩どんなふうに眠っているのだろか。
生憎、私の両親は共働きで、殆ど自宅にいることはない。
そのため、私は物心ついた時からずっと祖母に育てられていた。
流石に祖母に二階まで様子を見に来てもらうわけにもいかない。
私は着替えると一階へ降りて行く。
祖母が作ってくれた朝食の匂いが朝の透き通った空気と混ざり合い、とても心地良い気分にさせてくれる。
「おはよう。早く、ごはん食べちゃいなさい」
食卓にはすでに私の分の朝食が並べられている。
私はできたての朝食を口に運びながら、今朝の出来事を話した。
「ああ、それはきっと『座敷童子様』の仕業だよ」
「えぇ!?ざしきわらし!?」
私はつい大声を出してしまった。
「ああ、そうだよ。おばあちゃんの田舎では、昔から枕の移動は『座敷童子様』の仕業だって言われているのよ」
祖母は味噌汁をよそいながら口にする。
「嘘だぁ〜、今どき、座敷童子なんているわけないよ」
「あら、信じてないの?」
「だって…」
「でも、本当よ。だって、おばあちゃんが昔小さい頃、疎開先のお家によく現れたもの。紅や藍色のとても綺麗な着物を着た可愛いらしい童子様だったわ」
祖母は懐かしそうに目を細めながら言った。
「おばあちゃん、見たことあるの!?」
「もちろんよ。一緒に遊んだことだってあるのよ」
信じられない…。
まさか、祖母が座敷童子と遊んだことがあるだなんて…。
「それじゃあ、そろそろあなたにも、この家の秘密を教えてあげましょうね」
祖母はそう言うと、おもむろにキッチンの戸棚から駄菓子の入った籠を取り出した。
「さぁ、ついておいで」
わけもわからず私は祖母の後について行く。
そして階段を上がり、二階にある自室へ向かうと祖母は天井を見上げた。
「時々、天井から足音が聞こえたりするでしょ?あれはみんな座敷童子様の足音なんだよ」
私は当惑した。
確かにネズミの足音にしては少し大き過ぎると思っていた。
しかし、まさかそれが座敷童子の足音だなんて一体誰が思うだろうか。
そもそも、どうしてうちに座敷童子様がいるのだろうか?
私は訊ねると、祖母はしばらく考え込んでから、少し長くなるけど…と前置きして話し始めた。
「さっきも言ったけど、おばあちゃんが昔疎開していたお家にはたくさんの座敷童子様が棲んでいたの。だからお家は凄く栄えてたし、あの時代でも食べるに困らなかったの。でも敗戦後、先代の主人が亡くなって、そのお孫さんがお家を継いだんだけど、このお孫さんがとても性格が悪い人でねぇ…。古いお家も全部壊して工場を作るだなんて言い出して、しまいには私たち全員を追い出したのよ。みんな途方に暮れてたわよ。でもね、おばあちゃんは運良く、そのお家で家政婦をしてた奥様に拾われて、その日のうちに家を出ることになったの」
祖母は当時の記憶を呼び覚ますかのように、ゆっくりと語っている。
「そしたらその晩、部屋に知らない童子様が入って来て『オラたちも一緒に連れてってくれ』って言ったの。それで家政婦さんに訊いたら『それはきっと、座敷童子様だから、まとめて全員連れて行く』って。それでおばあちゃんたちは夜のうちに座敷童子様たちを連れて家政婦さんのお家に行くことになったのよ」
祖母はしみじみ口にすると「ね?」と、天井に向かって訊ねる。
すると、あろう事か天井裏からケラケラと子どもたちの笑い声が聞こえてきた。
私はぎょっとして、祖母に抱きつくと祖母は「大丈夫よ」と言って、私の頭を撫でた。
「座敷童子様たちは決して悪いものではないから。まぁ、たまに悪戯はするけど、それは座敷童子様たちに気に入られたなによりの証拠よ。それに────」
私はなんとも言えぬ気持ちで天井を見上げると、心なしか天井の染みが子どもたちの微笑む顔に見えてきた。
「このお家はその家政婦さんの住んでたお家なのよ」
「えぇ!?そうなの!?」
「おばあちゃんはね、その家政婦さんの一番上の子ども、つまり長男と結婚したのよ。それがあなたのお祖父ちゃん」
「じ、じゃあ、今うちにいるこの座敷童子様たちは、みんなそのおばあちゃんが連れてきた座敷童子様たちだってこと?」
「そうよ。ただあの時より確実に人数は増えてるけど───と、言うのもね、おばあちゃんもおじいちゃんも、他に行き場所の無い座敷童子様たちをたくさん保護したの。だって、お家が無かったら可哀想でしょう?」
祖母はそう言うと、駄菓子の入った籠を手に「よっこいせ」と、押入れの二段目へと上がった。
私はわけがわからないまま、そんな祖母のことを眺めていると「ほら、見てごらん」と、祖母は私を手招きする。
「ここに羽目板があるでしょ?これが天井裏に続いていて、座敷童子様の棲む世界とも繋がっているのよ」
祖母はそう言うと、ゆっくりと御札の貼られた羽目板を外した。
すると、闇よりも深い闇の中からけらけらと笑い声と共に何本もの白い腕がニュっと着物の袖口と共に伸びてきた。
「ほらほら、喧嘩しない。まだたくさんありますから」
祖母は馴れた手つきで差し出された腕に駄菓子を配ると、頭上から嬉しそうな少女たちの笑い声が幾重にも重なって聞こえてくるのでした。
「ね、本当にいたでしょ?」
────以来、私が座敷童子様たちのおやつ係です。



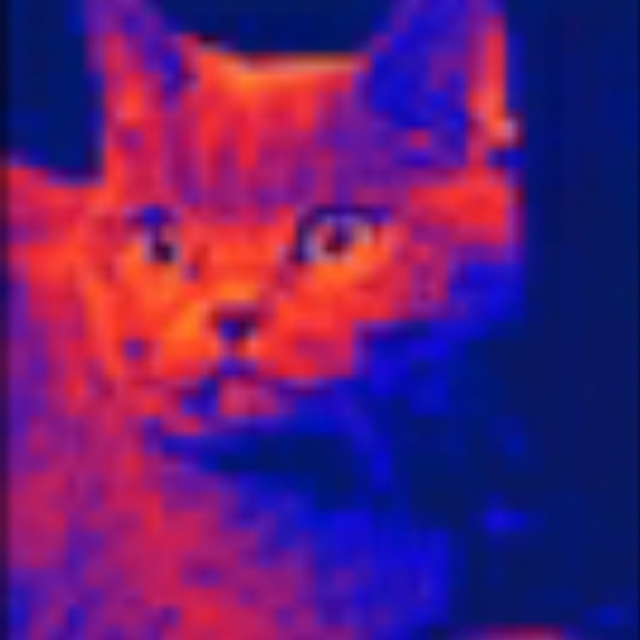


作者トワイライトタウン