wallpaper:119
小学生から中学生の頃、塾へ行くのがいつも楽しみでしかたありませんでした。学校よりもずっと好きでした。
別に私は勉強好きだったわけじゃありませんし、そもそもは親に無理やり行かされたクチです。
今改めて思い返しても奇跡なんじゃないかと思うほど、講師陣の奔放な授業スタイルにまったく退屈しなかったんです。
基本的には一対一の個別指導なんですが、どの講師の授業も半分は無駄話のようなものでした。
当時は「こんなので高い金払って大丈夫か」と子供ながらに心配したものです。
おそらく集中力の散漫な子供相手にみっちり授業するよりは、遊びを入れつつメリハリをつけることを重視していたんだと思います。
現に私の学力はぐんと上がりましたし、授業後は早くまた塾に来たいといつも思わせてくれました。
特に楽しかったのは夏期講習。全ての科目の講師が、毎回授業のはじめに怖い話をするんです。
どれも今思えばありがちな怪談でしたが、当時は新鮮で私たち生徒はみんな素直に怖がっていました。本当に楽しかったんです。
…
数年経ち、大学院に進んだ私は講師となって再びその塾に舞い戻りました。
私は講師をするにあたって、自分がそうだったように生徒たちには塾を楽しんでもらいたいと考えていました。
だからいかに遊びの部分を充実させるかということに神経を注いでいましたし、勿論、夏になったら怖い話を聞かせていました。
…怖い話のパターンとして、一通りの物語を話し終えた後に「この話を聞いた人間には呪いがかかる」と付け加えて脅かすものがありますよね?
定番は、呪いを解くためには同じ話を何人以上にしなければならない、というやつ。
一昔前のチェーンメール、さらに昔は不幸の手紙がこの要領で流行りましたよね。
この手の話は怪談というよりは怪談風の子供だましが多く、他にも様々なパターンがあったんじゃないでしょうか。
例えば「夢を見る」パターン。
聞くとその晩必ずある夢を見るので、夢の中で特定の行動を間違えずに遂行しなければ二度と目を覚ますことができない、みたいなもの。
私が子供のときに流行ったのはこの夢パターンの一種でした。
…ABCDの四人がある館へ肝試しに行くと殺人現場を目撃してしまい慌てて逃げ帰る。
その晩彼らの夢の中に館で殺された人物が現れ、ある言葉を伝えようとしてくる。ところがその人物の声が不明瞭で聞き取れない。
それを解読出来なかったABCは変死してしまい、Dだけがメッセージを理解し生き残る…ざっくりとこういう話。
そしてこの話を知ってしまった人間も彼らと同じ夢を見てしまうため、Dのように解読しなければ死んでしまう。
本編はあくまで前フリみたいなもので、雰囲気さえ出せればディティールは話し手任せ。だから仕掛けは同じでもストーリーは様々でしょう。
子供だった頃の私が講師に聞いた話では、解読メッセージは五文字の日本語でした。
「先生教えて!」「ヒント頂戴!」…講師は一文字、二文字ともったいぶりながら明かしていき、さんざん怯えさせたところで、
「ぜ・ん・ぶ・う・そ」
「なーんだ」「くだらねー」…悪態をつきながらもみんなほっと安堵した顔で授業が始まる。
昔から私はこのネタがお気に入りでよく友達をからかっていましたし、教え子たちにもこのネタを披露しています。
ただ、皆一様に怖がっていた私の頃と違って今の子供たちの反応はバラバラです。
ある子が期待通り怯えてくれたかと思えば、またある子には「それよくあるパターンじゃん」の一言で挫かれますし、別の子はネタはわかっていないけど全然怖がらなかったり。
やはり時代は変わったんだなと思わずにいられません。だから私も新鮮なネタを仕入れるのに苦労しました。
…
この日は中学二年生の子を相手に一コマ授業があるだけで、それを終えると特に塾に居残る用事も無く、私は帰宅の準備をしていました。
事務所を出ると教室の前に男の子が立っていたので「さようなら」と言って過ぎ去ろうとしましたが、腕をつかまれました。
「僕の先生まだ来てないみたいなんだけど、いつまで待てばいいですか?」
担当の講師が遅刻した場合は手の空いた者が受け持たなければいけません。ちょうどその子は英語の授業だったようで、私にも教えられます。
「じゃあ今日は先生が担当するから教室入ろうか」
私は事務所へ戻って塾長に事情を説明し、男の子を席へ連れて行きました。
机に教材を出させると、ノートの表紙には「シロタ」と名前がありました。
「シロタ君、今日は始まるのが遅れたから二十分ぐらい延長するけど、お母さんに電話しとかなくていい?」
シロタ君は「大丈夫」と言った後、「僕知ってるよ。先生は怖い話してくれるんでしょ?」と身を乗り出してきました。
なるほど。私の担当の教え子たちから聞いたんでしょう。「聞きたい?」と言うとシロタ君はうんうんと目を輝かせます。
私は少し考えて、あの「夢」パターンをやってみようと決めました。
「ある四人の若い男たちが、みんなで有名な心霊スポットに肝試しに行こうってことになってね、そこは廃墟になった大きな洋館なんだけど…」
まだ出鼻でしたが、シロタ君に「ねえ」と話を遮られました。「それって夢で死んだ人が出てくるやつ?」
…すでに誰かから聞いたことがあるようです。私は苦笑して、「そうそう。くそー、知ってたか」とうな垂れました。
私は頭の中のストックから他のネタを探しましたが、シロタ君はなかなか手強そうです。ここは新ネタを…と思ったときでした。
「先生、僕が怖い話教えてあげるよ」
シロタ君はそう言って、淡々と話し始めました。
…
ある大学院生の話なんだけどね、昼は研究室で論文書いて、夜は塾講師の仕事してるんだ。
肝心の論文はさっぱり進んでないっていうのに、余計なことにばっかり時間を割いてるんだって。
自分が塾で教える子供たちを楽しませるために、手品覚えたり、クイズ考えたり、怖い話仕入れたり…
…
私は朦朧としており、気がつくと隣にシロタ君の姿がありません。
慌てて辺りを見回すと、彼は私のすぐ後ろに立っていました。
わけがわからず唖然としたまま、私はシロタ君がくるりと反転してドアの方へと歩き出すのを見ていました。
「ちょっと待って」と言ったつもりですが、声になっているのかわかりません。
ドアを開けて出て行くシロタ君を目では追うものの、私はその場に座ったまま動けません。
バタンとドアが閉じられた瞬間、私のいる世界がゆっくりと光を失いはじめます。
ドアの窓だけが煌々として、それ以外すべてが真っ黒に染められていくのを、ぼんやりとした意識の中で感じて。
sound:14
コツコツ、と窓を叩く音。
四角い光の向こう側で、シロタ君が私に合図を送っているようです。
彼は私の目を真っ直ぐに見つめたまま微笑んで、短く何かを呟きました。
私の耳には届きません。届きませんが、私には解りました。
この時、すべてが解ったのです。
…ぜんぶうそ
wallpaper:153
nextpage
●
彼女は私の話に最後まで黙って聞き入っていました。
「ちょっと出来すぎじゃない?作り話じゃないよね?」
事故からずっと私の恢復を信じて待っていてくれた婚約者です。
「全部嘘って、どういう意味で言ってんの?この話が全部嘘ってことでしょ?」
「いや、この話は嘘でも作り話でもないよ。…でも、俺の脳の中で起こったことだから、そういう意味では作り話なのかな」
…
私は意識が戻ってからもなかなか退院できませんでした。
一ヶ月も寝たきりだったために、筋肉が衰えてまともに歩けなかったので。
加えて記憶にも問題がありました。
そもそも外傷はたいしたことがなかったんですが、脳が強い衝撃を受けてしまったようです。
事故前の記憶と事故後の記憶…つまりは昏睡状態のまま脳内で経験した虚構の記憶ですが、しばらくそれらを混同していました。
今でも虚構の記憶は残っていますが、身体とともに頭もゆっくり恢復し、現実としっかり判別できるようになりました。
私が敢えて「虚構の記憶」と言うのは、単に「夢」と言い捨てられないほどリアルに経験した記憶だったからです。
実際の私は塾講師などしておらず、地元を離れて仲間たちと東京で起業していました。
一応は私が代表ということで冗談半分にCEOなんて言ってますが、まだ社員十名の小さな会社です。
それでも事業は波に乗っていて、それで私自身も調子に乗ったんでしょう。
気の緩みから交通事故に巻き込まれ、生死を彷徨うほどの重体になってしまいました。
私が不在の間は仲間たちが必死で会社を支えてくれましたし、忙しい中で暇を見つけては見舞いに来てくれました。
こうなった原因は私自身にあり、彼らに何一つ非はありませんが、事故発生時に私に同行していたというだけで責任を感じ、彼らも私の意識が戻るまで生きた心地がしなかったようです。
…退院後もしばらくは療養した方がいいということで、現在は彼女を連れて実家に帰り、ゆっくりしています。
「それにしても、不思議な話だね」
彼女がしみじみと言います。…本当に、不思議な体験でした。
私が虚構の世界から抜け出し、いるべき現実へと帰ることが出来たのは奇跡かもしれません。
虚構を彷徨いながら実際の私はベッドで昏睡していたわけですが、医師によると意識を取り戻す見込みはほとんど絶望的だったということでした。
ぜんぶうそ、と呟いたシロタ君の姿は、今も脳裏に焼き付いています。
彼は私の脳が作り出した虚構の一部だと誰もが言うでしょうが、それにしても腑に落ちないのです。
なぜ気がつかなかったのかはわかりませんが、今思い返して解ることがひとつあります。
虚構の中で直接に触れ合った人物はすべて私の知人であり、見知らぬ人間はいなかったということです。
塾講師の面々、そして私が担当した生徒たちは、私が子供の頃に教えられた講師たちであり、私と同じく塾に通っていた友人たちでした。
しかし彼だけが…最後に現れたシロタ君ただ一人だけが、私の実際の記憶に無い正体不明の人物なのです。
だからこそ私はシロタ君という存在に奇跡のようなものを感じます。
彼のメッセージによって、私はあの世界が全部嘘だと気づかされたのですから。
それにしても…私の作り出した虚構の世界は、なぜ彼を導いたのでしょう。
私と繋がりのある人物だとしたら、いったい何者なのか…それを知らずにはいられません。
「そろそろ歩こうか」
私は彼女と二人で外に出ました。すでに普通に歩けるようにはなりましたが、毎日歩いて体力をつけなければいけません。
私は予め考えていた場所へ…もちろん、あの塾へ行こうと提案しました。
塾長が現役なら、シロタ君のことが何か解るかもしれないからです。
「もう潰れちゃってたり移転してたらどうすんの?」
「まぁそれでも構わないよ。あそこまでの道のりを歩くだけでもいいんだ」
私は子供の頃を思い出し、虚構の記憶と重ね合わせながら歩きました。
そしてつくづく、今こうして再び彼女と一緒にいられる幸せを噛み締めました。
塾は駅前にある雑居ビルの一階と二階に入っていましたが、到着して見てみると彼女が危惧していたとおりでした。
現在は一階が法律事務所、二階は空きテナントになっています。
実際には、私は十年以上この場所に来ていませんでした。
街全体が昔見た風景から大きく様変わりしていて、虚構の世界もやはり子供の頃に見たままの風景だったことを改めて実感します。
私はふと思いついてビルの外壁に当時残した落書きを探してみましたが、塗り替えられたのか、残念ながら見当たりません。
「何してんの?」
「いや、当時好きだった子の名前をここに彫ったんだけどね…」
言いながら、膝ががくりと崩れました。
まだ歩くには遠すぎたのか、どっと疲労を感じます。
それにしても、この寒気はなんだろうか…風邪でも引いたのかもしれません。
sound:14
コンコン
乾いた音が頭上から聞こえます。窓を叩いたような音。
sound:14
コンコン
…私は音に構わず、ゆっくりと建物から背を向けて離れました。
「二階の空き部屋に、誰かいない?」
彼女に尋ねると、ちらっと私の背後を見上げて「いいや、なんで?」と訝しげな顔をします。
私は勘違いであることを願いながら、恐る恐る振り返りました。
…何もいません。ビルは二階の一列だけ灯かりが消えており、窓の向こうにはただ闇があるだけです。
ひとまず安心しましたが悪寒が治まりません。歩いて帰れるでしょうか…
一歩足を踏み出すと、地面がぐらりと揺れます。また膝が折れ、彼女が慌てて私の腕をとります。
「大丈夫だから…」
そう言って見上げた先にあったのは、彼女の顔ではありません。
music:3
「怖い話、教えてあげるよ」
…私は生きるべき現実へと戻ってきたはずではなかったのでしょうか。
…君は何者なんだ。いったい私をどうしたいのだ。
彼はゆっくりと、私の耳元へ顔を近づけてきます。
shake
暗転していく世界のなかで、私はいったいどこからが嘘なのか考えていました。




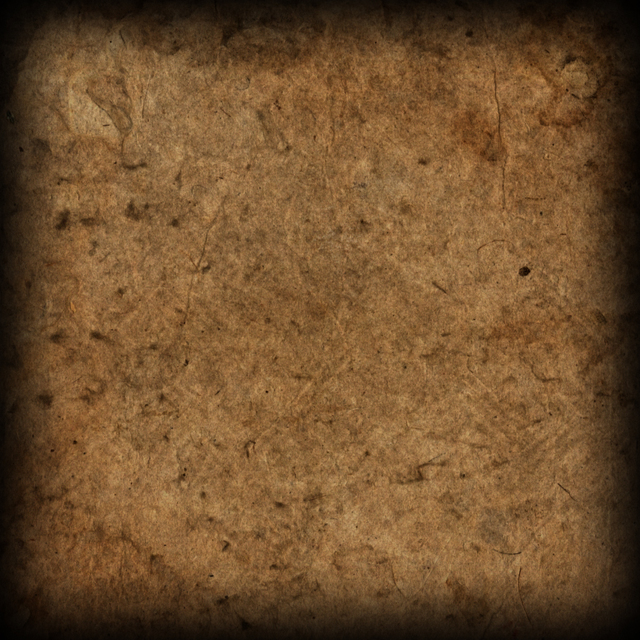

作者たらちねの
これもまたひとつのパターンですが。