ある若い男の話だ。
昨年の秋のことだ。
カズキとミユキのカップルは都内のビル群の中、デートをした。
カズキは会社から十分満足できる額の給料を受け取り、余裕のある生活を送っていた。ミユキは大学卒業後もアパレル・ショップのアルバイトを続けていた。
「良い鞄か、香水を買ってあげようと思っていたんだ。アルバイトの給料ではあまり良い物は買えないだろうから――」
カズキはそのように振り返り、語る。
昼過ぎ、煉瓦造りの百貨店のビルの前を通った。
秋としては暑く、湿った空気が不快感を誘う一日だった。チェックのベストを合わせた長袖のTシャツの内側が、じめじめと蒸れた。
信号、渡っちゃおう。
いや、無理だよ。もう赤になる――。
カズキは“次でいい”というように首を振った。信号は赤に変わった。
wallpaper:11
数秒後、不意に人通りが途切れた。街中にエアポケットが出現したかのようだった。
「寒くない?」
カズキはミユキに尋ねたという。
ミユキは不思議そうな顔を浮かべた。
こうううう。
物体が、猛スピードで風を切る音がした。上空を見た。頭の上から人が降って来た。
(え?)
ごうううううううう。
重力に従い、”人”の落下速度が、より早まっていく。左半身を下に、肩から地面に落ちるような恰好だったという。
桃が潰れ、岩が砕かれたような音の響きがあった。
粘性の血がはじけた。
ブラック・スーツに身を包んだロングヘアの女性だった。
痩せ形の体型だった。
腕と足は四方八方、あらぬ方向に曲がっていた。目付きは利発そうだった。ミユキよりも一、二歳ほど若く見えたという。
清掃員の男性が、水道の蛇口に取り付けたホースを手に、すぐに現場にやって来た。
ああ、またか――。
清掃員の男性は、面倒臭げに言った。
何故、こうも続けてうちのビルの屋上から飛び降りるかな。ここは樹海じゃないっていうのに――。
清掃員の男性が握るホースの先から、水が放たれた。
「ねえ、行かないで……」
「え?」
「行かないで……」
「どういうことーー」
ミユキはカズキの服の裾をぎゅっと握り、ロングヘアの女性の遺体を指差した。ロングヘアの女性の遺体の指先に、生前に施したであろうピンク色のネイル・アートが見えた。
あの女の人――。
あの女の人――。カズキの方を見て「次はお前だ」って――。
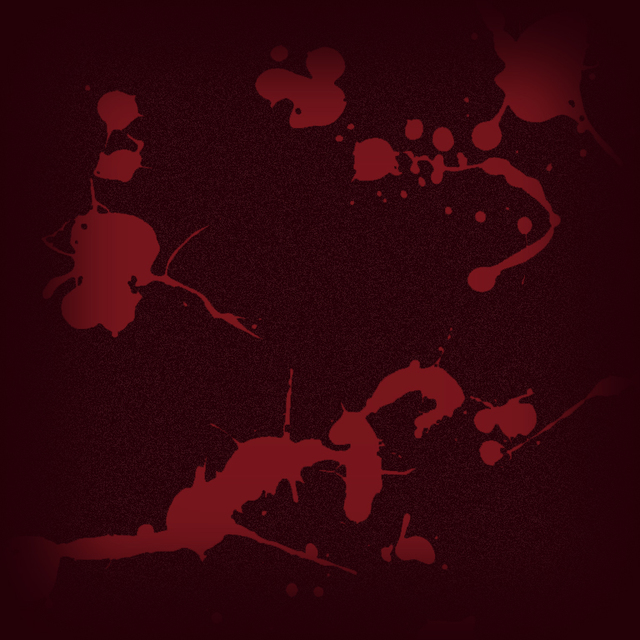




作者退会会員