music:5
wallpaper:214
トキタチホはY駅のホームから落ちて列車に轢かれて死んだ。
遺書は残っていない。刑事捜査を経て、過って落ちたのではないかと結論付けられた。
教室いっぱいに、喪失感が瀰漫していた。
但し一時の悲しみを乗り越えたところで決して元へは戻るまい。
シライシユキナは涙を隠さない。
「私が一緒だったら、もしかしたら…」
同じ駅を利用するユキナとチホはたいてい二人で登下校したが、その日は違った。
人目を憚らずさめざめと泣くユキナに、俺は目を奪われる。
ユキナの圧倒的に洗練された美貌を前にすれば、チホの器量など比較に値しない。
他クラスからはいつもユキナに視線が集まった。
浅はかな観客の目に映るのはいつだって主演女優ただ一人。しかし舞台上の人間もそれを揶揄はできない。
当の二年一組の俺たちですら、ユキナを中心としたスポットライトに決して足を踏み込めないのだから。
そんな卑しい級友たちの淡い夢想を誘うのは、現実離れしたユキナではなく、どちらかと云えば亡きチホの方だっただろう。
かく云う俺もそうだった。
チホは同性異性を問わず愛されていた。性根から塞ぎがちな生徒の懐にも訳なく飛び込む女だった。
ひとたび彼女に笑顔を向けられると、鏡を合わせたように誰もが破顔した。
まるで魔法のようだ、なんて無粋なことは云わない。チホの笑顔は魔法だ。
ユキナとチホは親しかった。
同じ教室でふたつの対極の美が惹かれ合ったことを俺たちは感謝しなければいけない。
没個性を集めた二年一組の教室は、そもそもがまるで鬱蒼とした迷いの森だった。
そこにおいて場違いにもほどがあるユキナの存在は、宛ら唯一の目印となる一輪の可憐な花。
そしてチホこそが、この森へ柔和に降り注ぐ木漏れ日だったのだ。
チホを失ったことで泣き暮れるのは当然ながらユキナだけではない。
教室を満たす啜り泣きの中で、男たちの低い嗚咽も少なからず混ざっていた。
俺は教室を見渡し、全ての悲嘆がユキナの美しさへ収斂されるのを虚しさとともに感じた。
日の射さない森でか弱くも枯れゆく花は、凛と花弁を晒していた頃を、或いは凌ぐほどに美しかった。
俺は自分が只それを際立たせる背景の一部に過ぎないことを自覚しながら、破滅の美を象るユキナをうっとりと眺めていた。
但し教室をカンバスにしたこの壮大な芸術は、歯痒くもただ一点の異物によって完成を阻まれる。
俺とユキナを結ぶ線上に着席する一人の男子生徒。キリュウヒサシがそこにいるせいで。
●
キリュウが生前のチホに執心していたことを知っている生徒はそういないだろう。
無論、チホに心惹かれるのは無理からぬことで、それは何もキリュウに限ったことではなく、俺自身も同じだ。
押並べて意気地の無い同胞たちの中にあって、チホへの告白を試みたごく一部の猛者たち。
いずれも願い叶わず俺たちはひっそりと安堵したが、彼らはその勇気を敬われこそすれ、嘲弄されることなど無かった。
キリュウもその内の一人に数えられるのかもしれない。
但し俺は、このキリュウに関してだけは、そこはかとない寒々しさを感じていたのだ。
それを俺が知ることになったのは、他でもなくチホ自身からだった。
文化祭の準備で居残っていた俺は、作業がてら彼女との他愛ない会話を楽しんでいた。
周知の通り、日常を逸れた学校行事は男女を結ぶ絶好の機会でもある。
俺はここぞとばかりにチホに接近したが、少々あからさま過ぎたかもしれない。
ともかく、チホが会話の中で何気なく漏らした一言が俺の耳にざらついた。
「でも、キリュウ君と同じ班じゃなくて良かった」
チホらしくない言葉だった。俺はそれを聞き流すことが出来ず追求した。
「苦手とかじゃないんだけど、ちょっと気まずくて」
まさか告白されたの?とカマをかけたが、チホは否定も肯定もしなかった。
「もうこのことは忘れて」と恥らい俯く姿は、余りにも明瞭な答えだった。
キリュウはチホに告白していた…。
俺は勇敢なはずのキリュウを讃える気分には到底なれなかった。
なぜならキリュウはその数日前に、ユキナに告白していたからだ。
数人の男子からの報告で、俺はそれを知った。
「キリュウがユキナちゃんを呼び出して告白したらしいぞ」
ひねもす文庫本の世界に没頭し、外の世界など一瞥もくれない男だと思っていた。
ところが実のところ人知れず恋心を燻らせており、突然それを剥き出しにしたのだ。
仮にも相手はユキナである。俺たちとは別世界の住人である、あのユキナに。
確認するまでも無いが、キリュウの想いがユキナに通じるはずがない。
そもそも一人の女に振られた直後にまた別の女に挑むなど、通常の場合であっても受け入れ難い。
それをキリュウは、あろうことかユキナとチホを相手にやったのだ。
…二年一組とは即ちユキナとチホ。
ユキナとチホの一組。
一組の象徴。
象徴は一対。
一対で完全。
二人を犯すことは、完全な禁忌。
キリュウヒサシとは…そうした摂理を正しく理解しない、二年一組の異物。
●
チホが死んでから数日経ち、二年一組に落ち込んだ翳りは未だ払拭されない。
訃報に接したあの日、ユキナが刹那的に放った痛烈なタナトスを再び感じることは叶わなかったが、やはり美しいことに変わりは無い。
「誰かに付き纏われてる気がする」
ユキナが数人の級友を相手に漏らした言葉が、偶然耳に入った。
聞いている女子たちは然程心配している風でもない。そもそも本人が平気な顔をしている。
生前のチホから聞いた話を思い出す。ユキナにとって軽度のストーカー被害は日常茶飯事だと云っていた。
気丈なところもユキナの魅力だが、世の中には善からぬ考えの人間が少なからず存在することを知るべきだ。何かが起ってからでは遅い。
明くる朝、俺は教室でただひとつの空席に百合の花を手向けた。花瓶には既に新しい菊が挿されていた。
チホへの手向け花は、俺とユキナが世話することになっている。
親友だったユキナと、文化祭を通してチホとの仲を深めていた俺。
とはいえ俺が気安くユキナに声を掛けられるわけもなく、互いの連携は無いままに、それぞれが持ち寄った花が一緒に飾られた。
俺が仕上げに机を布巾がけしていると、ふいに「ねえ」と声が掛かった。
ユキナがケータイを操作しながら、俺の傍へ寄って来る。
俺は緊張し、生唾を飲む間抜けな音が漏れた。
「これ見て」
出し抜けに手渡されたiphoneはtwitterを開いていた。
一枚の画像。至近距離で撮られた女の安らかな寝顔。
“まだ生きてる”と書かれている。
「それ私。帰りの電車の中で撮られたんだと思う」
日付は昨日。俺は寒気に襲われながら、「履歴見て」と促すユキナに従った。
いくつかのつまらないツイートを見送り、あるところで目が留まる。
“まだ生きてる”先程と同じ文面。
ユキナは画面に食い入る俺に顔を寄せ「誰だと思う?」と云う。
同様に画像が付いている。やや低いアングルから撮られた女子学生の横顔。ユキナではない。
「チホだ」俺は確信を持って云った。
「そう。そうなんだけど、それ撮った人…誰だと思う?」
出鱈目にアルファベットを並べたようなユーザー名。フォロワーはゼロ。
「さあ…誰なんだろう。捨てアカだろうけど」
問題はこのツイートがチホが死ぬより前のものだということ。
“まだ生きてる”…つまりこの時点でチホの死を示唆している。
「昨日の夜中にこの人にフォローされてたんだ。フォローされることなんて滅多に無いんだけど。
私、他人のつぶやきをただ見てるだけだし、もちろん本名じゃないから…」
俺は掛けるべき言葉を探したが何も云えずに画面を見ていた。
「私…狙われてる?このチホの画像って…」
「キリュウだ」
俺はユキナの言葉を遮って、思いつくままに捲くし立てた。
「キリュウとお前、たしか同じ路線だよな?こんな盗撮できんのはあいつぐらいだよ。
昨日の帰りの電車でキリュウと一緒じゃなかった?よく思い出してみて」
ユキナは黙って思案していた。俺は続ける。
「…キリュウに告白されたんだろ?知ってるかもしれないけど…あいつその後すぐに、チホにも告白してたんだ。勿論、それで犯人だと断定するのは早いかもしれないけど」
ユキナは絶句し、ただ目をぱちくりとさせるだけだった。
深く澄んだ瞳に、はっきりと戦慄が浮かんだ。
…決して狼狽えることのない女が、恐怖を感じている。
ユキナが持ち得ないはずの官能美を、俺はその瞳の中に見た。
「…今日は俺が一緒に着いて行ってやろうか?」
ふいに自分の口から出た言葉が信じられなかった。が、云ってしまったからにはもう遅い。ユキナの反応を待つ余裕は無かった。
「だって一人だろ?前はチホと一緒に登下校してたみたいだけど、今は…
だからさ、俺が一緒に電車に乗って、怪しい奴がいないか見張ってやるよ。
…大丈夫。別にカップルみたいにぴったりくっつくんじゃなくて、少し距離を空けてるから」
焦るあまり余計なことを口走ったかもしれない。卑屈な印象を与えただろうか。
しかしユキナは「それなら…」とだけ云った。それが承諾を意味していることが暫く理解できなかった。
wallpaper:51
●
放課後。
夢にすら見なかった状況に俺は舞い上がっていた。
恋人としてではない。友人としてでも、恐らくない。それでもユキナに望まれて、俺は彼女と帰路を共にしている。
道中に会話はなく、互いの距離は常に十メートル以上離れている。但しそれは前人未踏の領域に違いなかった。
すれ違う通行人がはたとユキナを振り返るのが俺には面白かった。見間違いではない、と云ってやりたい気分だった。
場所を電車に移してもちらちらとユキナを盗み見る乗客が一人や二人ではない。
やはりユキナは常にピンスポットが降りているような女なのだ。
そして今、この舞台にもう一筋のスポットライトがその相手役を照射していることは、俺だけが感じていればいい。
S駅で下車し、K神宮行きの乗り場へ移動する。
前方を歩くユキナは逐一振り返って、不安げな目で俺の姿を確認する。
その度に俺は浮かれる自分を戒めねばならなかった。ボディーガードとして付き添っていることをつい忘れてしまう。
再び車内へ。
俺は窓から望む景色を注視していた。ビル群を過ぎ、住宅街を抜けたところで突如として開ける。
そこには青々とした田園風景が広がっている。夕日が深く射し込んだ車内には光の粒子がきらきらと輝く。
この路線を走る電車が僅かな時間だけ迎えるノスタルジーを、俺は数える程しか無い経験の中で知っていた。
斜向かいにはユキナ。これ以上望めない被写体。しかしこの長閑なロケーションになぜかユキナは馴染まなかった。
ユキナの強すぎる個性は、ともすると全ての均衡を崩してしまう。何よりも表情の硬さが周囲との調和を許さない。
チホさえ隣にいれば…。そう思わずにはいられない。
チホが傍にいるだけで、ユキナの孤高は融和に変わる。ユキナの険しい顔は、微笑みに変わる。
…チホが死ぬまでは、二人は何度となくこの電車で並んでいたはずだ。
こんなつもりで同行したわけではない。わかっているが、それでも目頭が熱くなる。
…こんなのは美しくない。もはや彼女は完全ではない。
理屈ではない事実を目の当たりにして、チホへの恋しさばかりが募る。
やがて車両は減速し、Y駅のホームに入った。
ユキナが下車するのを見て、近くの扉からホームへ降り立った。
俺は立ち止まっているユキナに歩み寄る。
声を掛けようとした時、ふいにユキナがこちらの方を指さして何かを呟いた。
背後を振り返る。真っ直ぐにこちらへと闊歩して来る学生服の男。
キリュウだった。
不覚にも俺は動揺を隠せず、二歩三歩と後ずさった。まさか本当にキリュウに出くわすなど思いもしない。
しかしユキナの見ている前だ。これ以上取り乱してはいけない。
「キリュウ…お前が降りるのこの駅じゃないだろ」
なんとか言葉を発したがキリュウはそれに答えず、俺との距離を詰める。
ユキナ、俺、キリュウが一直線上に並ぶ。それに平行して、電車が唸りを上げて動き出す。
「おい何とか云えよ」
キリュウは、後ろ見ろ、とでも云うように軽く顎をしゃくって見せた。
俺は再びユキナへ視線を戻す。ユキナが何かを云ったが、至近距離からの轟音が声を掻き消す。
突風が吹き抜け、ユキナの長い黒髪を巻き上げる。厳しい眼差しで何かを叫んでいる。
「人殺し、だってさ」
耳元で、キリュウの低い声。
俺はとっさに振り返ってキリュウに掴みかかった。が、あっさりといなされる。
逆に腕を取られ、身体は反転し、背に回った腕が強く締め上げられる。肩に激痛が走る。
この陰気な男のどこにそんな力が隠されていたのか、全く身体が動かない。
最後尾の車両がホームを抜けると、声が鮮明になる。
「あんたがチホを突き飛ばしたんでしょ?…人殺し!」
ユキナの悲愴な顔。今にも泣き出しそうだった。
「見ろよ…可哀想に。あんな酷い顔は見たくなかった」…キリュウが云う。
俺は頭に血が上り始めるのを感じた。
「おい放せ!お前だろ、twitterで気持ち悪いことやってんの」
「…ほら、ちゃんと見ろよ」
ユキナはやはりこちらを指さして、ヒステリックに叫ぶ。
「人殺し!」
「おいキリュウ。まさか本当にお前が…」
「馬鹿。ちゃんと見ろって云ってんだろ。指はどっちへ向いてる?」
何が云いたいのかわからない。ユキナの指の先は…
…いや、そんなはずはない。ユキナは俺に対して云ってるんじゃない。
俺じゃない。俺を疑う理由がない。
「人殺し!」
ホームに少しずつ人が集まり始める。駅員が不審な目でこちらを見ている。
「…俺じゃねえよ」
この状況は何だ。なぜこうなったのか理解が出来ない。
「俺じゃねえ!俺じゃねえ!」
俺は声を荒げていた。遠巻きに周囲の目が集まる。意を決したように駅員が歩き出す。
キリュウが俺の髪を鷲づかみにして云った。
「さっきからどこ見てんだ。こっちだ」
頭を捻られ、ユキナを捕らえていた目線は電車が去った線路へと逸れた。
「あんな酷い顔、見たことねえよな」
「…………」
俺はその瞬間、力を失ってその場にストンとへたり込んだ。
スッと、血の気が引く。
確かに目にしている映像が現実のものと思えなかった。
…線路の上に女が立っている。
全身を真っ赤に染めた女の立ち姿は、余りにも凄惨だった。
片腕が捥げ、膝下はあらぬ方向へ曲がり、あちこちの骨を剥き出しにして…。
あんな状態で立っていられるはずがない…生きていられるはずがない。
「見えたろ」
キリュウはそう云うと、俺の腕を取って起き上がらせた。
しかし足の震えが止まらず、キリュウに肩を抱かれる。
「しっかり見ろ」
女のぼろぼろの身体は今にも崩れ落ちそうだったが、それでも見開いた両の瞳には強い意志があった。
…確かに、こんな酷い顔は見たことがない。
…彼女はこんな怨めしい目で人を見ない。
「チホ…」
そこでキリュウは俺の身体から手を放し、一歩下がって云った。
「…で、指はどっちへ向いてる?」
線路上のチホは骨の突き出た片腕をしっかりと上げていた。
「人殺し!」
血に濡れた指が示す先で、ユキナが金切り声を上げていた。
●
そこから先は、ほとんど茫然自失だった。
俺の意識は停滞したままで、周囲の時間だけが加速しているように感じた。
駅員の詰問をはぐらかすキリュウと、少し離れて立ち尽くすユキナ。
後続車両の到着を告げるアナウンスが妙にクリアに響いていた。
気がつくと俺はキリュウに手を引かれて、無抵抗のまま電車の中に連れ込まれていた。
窓外に目を向けると、ホームに残ったユキナと視線がぶつかり、遠ざかる。
俺とキリュウは並んで座席に着いたが、互いに無言だった。
思いもよらない状況だった。但しキリュウへの敵意はとっくに霧散していた。
…無残なチホの姿が、目の裏に焼きついて離れない。
恐ろしいとは思わない。あれを霊と呼ぶものなのか俺には解らない。
何であれ、あれは何かしらの意味を持って現れた啓示に違いない。
チホから発された強烈な怨恨。その矛先にユキナ。
…ユキナに殺された、と見ていいのだろうか。
少なくとも、チホが死んだことにユキナが深く関わっていることは解る。
それにしても、なぜ…
「降りよう」
キリュウが立ち上がって、ドアへ向かう。俺は黙ってその後に続いた。
…
ホームのベンチに座って、キリュウはぽつりぽつりと話し始めた。
キリュウはチホに片思いしていたことを自ら認めた。チホの存在が学校へ行く唯一の理由だったと、恥ずかしげもなく云った。
但し、ユキナへ告白したことはきっぱり否定した。
ユキナをこっそりと校舎裏へ呼び出したことは事実だが、目的は別だったと云う。
「twitterでへんな書き込み見つけて、あいつじゃないかと思って」
それはチホの画像を載せた“まだ生きてる”というツイートだった。
ある時チホのアカウントに不審なフォロワーが付いたのをキリュウは見逃さなかった。問題のツイートの後、すぐにフォローは解かれたらしい。
「他にも疑わしいことをいろいろやってたから、絶対ユキナが犯人だって思った」
俺はふいにキリュウがユキナと同じ中学に通っていたことを思い出した。ついぞ失念していたが、重要なことに思えた。
キリュウは他の生徒が知り得ないユキナの本性を見透かしていたのかもしれない。
「ただ、この時点ではユキナがチホを本気で殺す目論見だったとは思えない。
あいつは昔から影で悪趣味な憂さ晴らしをしてたけど、たいてい自己完結してるんだ。
あの気味悪いツイートもそのひとつに過ぎない。…でも俺はそれを放っとけなかった」
チホを想う気持ちがキリュウの正義感を駆り立てた。ユキナを呼び出し、問い詰めた。
しかし、それが全ての誤りだったと云う。
「完璧なユキナにとって、決して他人に悟られてはいけない唯一の恥部。よしゃいいのに俺はあいつの前で、それを暴いちまったんだ」
ユキナという狂人を相手に、犯してはならない禁忌…苦虫を噛んだような顔でキリュウは吐き捨てる。
「いずれ追放されるだろうって、覚悟した。せいぜい根も葉もない悪い噂を流す程度かと思ったよ。
だけど、そもそも俺はどこにも居場所が無い除け者だしな。…だからってよぉ、普通あんなこと考え付くかよ」
彼はそこで声を詰まらせ、代わりにちらと俺を見た。
…チホの残像が目に浮かんだ。
…図らずもユキナは知っていた。孤立したキリュウが毎日学校へ来るたったひとつの理由。
「ユキナにとっても好都合だったんだよ。…ことの発端は、暗にチホの死を望むようなツイートだったんだし。
つまりユキナの目的は俺への報復で、チホはその手段として殺されたんだ。そして全てを俺に擦り付けようとした」
そこまで聞いて、俺は教室でのことを思い出していた。
ふいに呼び止められ、渡されたiphone。謎のアカウントとツイート。
白々しくも自分で撮った寝顔の画像と、意味深なコメントを新たに加えて。
あの時、ユキナの口からその名は一度も出なかったはずだ。
「キリュウが怪しい」…そう云ったのは、他ならぬこの俺だった。
ユキナの思惑通り、俺はキリュウを犯人だと…チホの死にまで絡む犯人だと疑った。
あらゆる状況がキリュウにとって不利だったことは確かだ。キリュウに対して一際不信感を抱いていた俺を巻き込んだことも偶然とは思えない。
「とにかく、ユキナはタガが外れてる。そのくせやり口が巧妙なんだ」
そこまで云ってからキリュウは、すまん、と立ち上がった。
「明日ユキナに会ったら、適当に話を作って惚けろ。俺とここで話したことは云うな。
間違ってもユキナに、お前がチホを殺した、だなんて云うなよ。…あと、俺はもう学校へ行かないから」
そう云って改札を抜けて行く。
俺は慌ててキリュウを呼び止めたが、「ユキナから出来るだけ離れろ」という言葉を残しただけで、去って行った。
wallpaper:208
●
俺は今までと変わりなく学校へ通っている。
二年一組の教室はひとつ空席が増えた。
…秘密の共有。それは俺とユキナの距離を否応無く近付けていた。
ユキナは、twitterの犯人もチホを突き落としたのもキリュウだという物語を、俺が信じていると思い込んでいる。
但し、俺はtwitterがユキナの自作自演であり、チホの死にユキナが関与していることを確信している。…が、それを誰に明かすでもない。
…トキタチホは過ってホームから落ちた。未だそれが覆ることはなかった。
「キリュウ、学校来なくなってよかったよね」とユキナは云う。
「そうだね」俺は居たたまれない気持ちでユキナに付き合う。
相変わらず、ユキナは息を呑むほど奇麗だった。
相変わらず、ユキナには他クラスからうっとりとした目が集まった。
但し、二年一組の人間が彼女の領域に踏み込めないのは、逆説的にその現実離れした美貌のせいだ…というそれまでの認識は誤りであると、俺は気がついている。
勘のいい人間は少し近づいただけでユキナの危うさを察知するのかもしれない。
彼らも同様にユキナに降りたピンスポットを見ているが、その円が表すのは危険域だった。
俺はつくづく鈍感だったのだろう。但しチホの鈍感を誰も責めることは出来ない。
純粋で、分け隔てなく級友の懐へ飛び込んだチホは、その人の善さが却って仇となった。
俺たちはチホをユキナと引き合わせた運命を恨むしかない。
「新しい花買ってきたよ」
ユキナが抱えた花束を見て、俺はぎょっとする。
「チホには赤が似合うと思わない?」
ユキナは余分な茎をザクリとハサミで落とした。
「もっとかな」…ザクザクと、何度もハサミを入れる。俺は眩暈を覚える。
ふいにチホの苦悶の表情が頭をよぎる。車輪に四肢を断たれ、血飛沫が上がる。
真っ赤な花は花瓶の中へすっぽり沈んで消えた。
ユキナは、やりすぎちゃった、と頭を掻き、ケラケラと笑って云う。
「チホも天国で笑ってるかな」
ぞくぞくと全身が総毛立つ。
「…………」
…これ程の快感が、他にあるだろうか。
俺はもう只の観賞者ではないことを知っている。
狂気を孕んだユキナ。このえもいえぬ美しさを真に理解する人間はそういまい。
仮にそれを理解したところで、この痛切なまでの快感を味わうことは俺以外の誰一人にも許されない。
人は誰しも愛されることを望む。
但し、往々にして人はありふれた愛情に気づかず、いつまでも満たされないと嘆く。
あらゆる障害を振り払った末に、一途に注がれる愛情…日常を逸脱した愛情にこそ、人は満たされる。
況やその主が思いがけずも、決して手が届くはずがないと思われた絶世の美少女だったなら…その悦びは狂おしさすら伴うだろう。
…キリュウの話は概ね正しい。しかし彼はひとつだけ勘違いしている。
ユキナがチホを殺したのは、何もキリュウ如きを追いやるためばかりではない。
女が女を殺す理由など、大昔から今日まで本質は変わらないのだ。
「ねえトシ君、今日も一緒に帰ってくれる?」
上目遣いで誘う彼女の透き通るような白い手が、俺の身体に触れる。
「流石に毎日は無理だよ。それから、学校で俺のことトシ君って呼ぶな」
ユキナは悪戯を暴かれた子供のように、ペロっと舌を出した。
「はーい。先生」




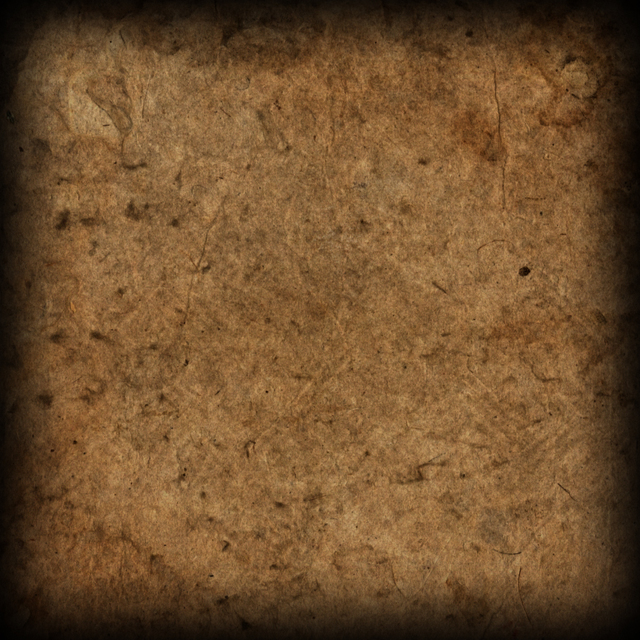

作者たらちねの
削りに削ってこの長さです。
最後まで読んで下さった方、ありがとうございます。