Zは高校卒業後、山梨県から上京し、都内の専門学校に入学しアクセサリー制作を学んだ。
「周りは女の子ばかりだったからその頃は馬鹿みたいに毎日飲んで、遊んでーー」
Zはそう語る。
専門学校を卒業した後は契約社員として紀伊国屋書店に就職した。
仕事は忙しく、時間当たりの給与は安く思ったほどには生活に余裕は生まれなかった。
「自分は東京で何をしているのだろう――。そう思うよ」
高校時代の友人や専門学校時代の友人と会う機会は無くなった。家系的に髪が薄く、Zはやや抜け毛を気に掛けるようになった。
*
入社から十一ヶ月が過ぎた春の日。
陽だまりの中、色付きの薄い桜の花びらが舞う。
「その頃は妙に疲れていたのかもしれない」
前日の出勤の際、Zの顔色の悪さを見兼ねた上司は休暇を取ることを勧めた。
上司の勧めを受けZは休みを取りレンタカー会社から車を借り、山梨に帰省した。
「故郷の学校や塾、公園を見て回ろうと考えてーー」
Zは大森靖子の『魔法が使えないなら死にたい』を車中に流しつつ、高速道路を走行した。
二時間あまりで山梨県に到着した。
Zが通った小学校は地域の人口減少に伴う教育機関の統廃合の影響を受け、閉鎖されていた。Zの通った中学校も同様だった。高校は春休みに入り、人の姿はまばらだった。
駄菓子屋があった場所には、ファミリーマートがオープンしていた。
スポーツ用品店があった場所には、パチンコ店がオープンしていた。
公園の敷地内から男子高校生の笑い声が聞こえた。公園の右隅の時計は鏡面に大きなひびが入り、時刻を読み取ることは出来なかった。
足下にサッカー・ボールを置き、鉄棒に腰掛けた男子高校生の内の一人がZに声を掛ける。
「それは高校時代のクラスメイトだった。クラスメイトは“18歳のまま”だった。全員、制服を着ていて......。彼の周りは高校時代から、時が進んでいないかのようだった」
お前、一浪するんだろ。赤本進めてる?
いや、全然。そもそも、志望校何処にするかもまた揺らいで来てさ。
沈黙が広がる。
お前、委員長とはどうなの?
不意にZに話が振られる。東京に行ったら委員長とはもう別れないとーー。
Zはクラスメイトの居る方角に向け、サッカー・ボールを大きく蹴り出した。
ふとクラスメイトの身体は“消え”た。
周辺に葉が舞う。
サッカー・ボールはクラスメイトの身体を擦り抜け、公園の反対側へ転がった。
転がるサッカー・ボールを女子高生が取り上げた。
「高校時代の彼女だった」
彼女は何処か青褪め、頬は痩せこけているように見えた。
Zは「彼女と話をしたい」と思った。頬の薄いそばかすや、彼女のトレードマークであった首元のハート・マークの痣を指で確認したいと思った。
彼女の口が動く。
”老けたね”
瞬間、彼女は通学鞄から取り出した拳銃を口の中に押し入れ自らの脳漿を撃ち抜いた。Zが駆け寄るとそこに彼女の肉体は既に無く、飛び散った脳や血液、髄液だけが残されていた。
Zは無性に喉の渇きを覚えた。
Zは一番近くの自販機の、男性アルバイトによる商品の補充作業が終わるのを待ちC.C.Lemonを購入した。
「地面に一滴、C.C.Lemonを垂らしてみようと思った」
C.C.Lemonと脳、血液、髄液が混じった“液体”は地面に黒々とした染みを作り出した。
五分ほど経ち、染みの跡には松の木の根が芽生えた。
翌朝。
松の木の根は大木に育っていた。その枝の一端には麻縄が結び付けられ、先端には黒猫の死体がぶら下がっていた。
「道行く人の誰もが、そのことをまるで気に掛けていないようだった。だから――。おれも一切、死体のことを気にしないことに決めた」
Zは明るく語る。
東京に戻りZはいま紀伊国屋書店の正社員登用試験に向け、対策を進めている。




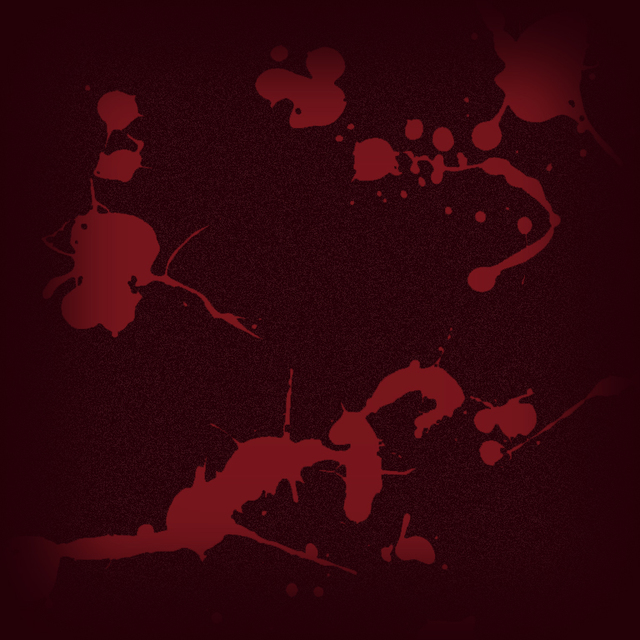

作者退会会員