小さい頃の記憶というものが、私には殆どない。ふわふわと立ち上る蜃気楼のように、曖昧模糊で断片的な記憶ならば、少しだけ思い出せるのだけれど。
長い長い廊下を歩く。ここはいつ来てもひんやりとうなじが涼しかった。私の手を引いてくれていたのは誰だったか。女性だったのか男性だったのか……それすらも忘れてしまった。
記憶を遡る時、私はいつもこの場面から思い出す。背の高い人物のひやりと冷たい手を握り、薄暗い廊下をひたむきに歩いたシーン。
廊下を歩く私はいつも緊張していた。緊張のあまり、シクシクと痛み出すお腹を左手で押さえ、喉の奥に小石が詰まったような息苦しさを感じながら。
どれほどそうしていただろう。私の手を引いてくれていた人がひたりと立ち止まる。私もつられて立ち止まる。
座敷と廊下を隔てている一枚の障子戸。ぴたりと隙間なく閉め切られているはずなのに、ツンと薬臭い臭いが漏れてきて、私はそれが堪らなく嫌だった。
「ーーー様。お連れ致しました」
私の手を引いてくれていた人が、障子戸に向かって声を掛けた。誰かの名前を畏まって呼んだようだけれど、何と言ったのかはよく聞き取れなかった。
しばしの沈黙。さらさらと衣擦れの音がして、か細い声がした。
「お入り」
温めたミルクのような優しい声音。その声にかちりと固まっていた緊張の糸が切れた。強張っていた頬が少しだけ緩み、肩からすうっと力が抜けた。
障子戸が横に開き、広々とした座敷が視界に映る。手を引かれ、こわごわと中に入る。
座敷の中は閑散としたもので、家具らしい物は何一つなかった。その代わりにテロテロと艶めく白い布を被せた祭壇と、その前に敷かれた一組の布団。布団に埋もれるようにして寝ていた人物がゆっくりと体を起こす。
私は黙ってその様子をじぃっと見つめていた。やがてその人物は上半身だけ起こして私を見た。行燈の光がゆらりと揺れ、炎が時節パチパチと音を立てる。
その人は垂らした前髪から透かして私を見つめていた。肩を丸め、異様なくらいの猫背。老婆のように頼りない、小柄な体つきだった。袖口から覗く、骨ばっているが白く華奢な手首を見る限り、女性であることが窺える。
妖艶な赤い唇が、うっすらと笑みの形に結ばれた。
「おいで。こちらに来て顔を見せて」
か細い声で、その人は言った。
「こちらにおいでーーー”宴”」
◎◎◎
久しぶりに再会した昔馴染みの男が、夜店の屋台で売られているような狐の面を被っていたら……あなたならどう反応するだろう。
「似合わない」
きっぱり言い捨てると、男はパカリと面をずらして自嘲気味に笑った。端正な顔立ちだが、下手くそな笑い方をするせいで台無しである。
「酷いなあ。お面に似合うも似合わないもないでしょうに」
「お前が付けると何でも胡散臭く見えるんだよ」
「破破。よく言われます」
男は濃紺色の着流しの袂から細長い煙草を取り出した。マッチで火を点け、もったいぶるように息を吸い、唇を尖らせて煙を吐いた。
煙草の煙が大の苦手である私は、顔をしかめて窓を開けた。窓の桟に溜まっていた細かな埃がふわりと舞い、紫煙が吸い込まれるように窓の外へと流れていく。
男の名は桐島楓。裏寂れた骨董品屋の店長をを勤めている。
狭くはないが、決して広くもない店内には、壺やら掛け軸やら絵画やらが窮屈そうに鎮座している。店の奥には書庫が立ち並んでおり、黄ばんだ表紙の古書が整然と仕舞われていた。入りきらない本は、床の上に積み重ねられており、こちらは薄く埃を被ってしまっている。
「あのう……」
椅子に腰を下ろした桐島が躊躇いがちに声を掛けてきた。言葉には出さず、目線で「何」と答えると、彼はこんなことを尋ねてきた。
「あなたのことは何てお呼びしたらいいでしょうか」
「御影でいい」
「御影さん……ですか」
「何か言いたそうな口振りだな」
「いやいや、そんなことは……良い名前だなあと思いましてね」
とってつけたように桐島は言う。私が眉を吊り上げたことに気が付いたのだろう。
腕を組み、壁に寄り掛かる。私の機嫌を損ねたと思ったらしく、桐島は苦笑を浮かべ、くゆらせていた煙草を灰皿に押し付けた。ジュッと焼ける音と、焦げたようなひりつく匂いに私は一層眉に皺を寄せる。
「で。用件は何なの」
学校帰りのこと。歩いていたら、ひらりと何かが頭上を掠めるようにして飛んできた。最初は鳥か何かだと思ったが違った。いや、鳥といえばそうなのだが。
鳥は鳥でも啼かない鳥。白い折り紙で折られた一羽の鶴だった。
手を差しのべると、飼い慣らされた小鳥のようにぱさりと落ちてきた。そっと広げると、美しい文体でひとこと添えられてあった。
ー店にてお待ちしています。かしこ 桐島ー
その手紙を頼りに、私は裏寂れた骨董品屋まで足を運ぶ羽目となった。
実は桐島が店主を務める骨董品屋には一度も行ったことがない。
タクシーでも呼ぼうか。そんな考えがちらりと脳裏を掠めた時、不思議な感覚がした。
指先に絡んだ見えない糸に手繰り寄せられるかのように、私は歩き出していた。糸は柔らかく私を引き寄せ、こちらですよと道案内をしてくれた。
そうして辿り着いたのがこの店である。
「そういえば」と。黄昏時の真っ赤な夕陽が差し込むような店内を見つめながら、私は口火を切った。
用件を尋ねる前に気になっていたことがあったのだ。
「この店、看板がないね」
タ店に付いた時、そういえば名前は何というのだろうかと思い、看板の類を探した。だが、それらしい物は見つからなかった。
一桐島はパカリと面を付け直した。私と直接顔を合わせることに苦痛を覚えたのかもしれない。
目元に隈取りの施された狐の面は、笑っているようにも怒っているようにも見えた。夕陽に照らされ、じわりと面が赤々しく照った。
「名前がないんですよ。昔から」
面越しにくぐもった声で桐島が言った。
「祖父は店に名前を付けようとしなかったんですよね」
「何故」
「さあ。何か考えがあってのことなのか……。聞いたことがないから知りません」
「ふうん」
一時、看板のない店が流行ったことがあった。有名人や知識人がお忍びで訪れるレストランなどがそうだ。敢えて看板を出さず、ひっそりと経営される店。
だが骨董品屋にしては珍しい。どの骨董品屋も、がちんと古めかしい名前を店頭に掲げているものなのに。
私はすぐこの話題に興味をなくし、ふと桐島を見た。彼は右手親指と中指、薬指をくっつけ、人差し指と小指をぴんと伸ばした。狐の形である。
よくよく見れば、親指と中指、薬指の間にはビー玉が挟まれていた。狐が咥えているようにも見えた。
「口の中に入っていたそうですよ」
「口の中」
「そう。見覚えありますか」
私はとろりと光るビー玉を見つめた。幾つかの気泡が入り混じる淡い水色の硝子玉。
その時、頭の中にバチリと電流が走った。
◎◎◎
その人は一年中床に伏せっていた。枕元にはいつも薬が入った袋と水挿しが置かれていたので、病を患っていたのかもしれなかった。
たまにだが、その人は縁側に座っていることがあった。体調がいい時だったのだろう。白い寝間着姿に肩掛けを羽織り、猫のようにきゅうと肩を丸めて、ぼんやりと庭を眺めていた。
幼い私が背の高い人物に手を引かれて縁側に来ると、その人は嬉しそうに顔を綻ばせた。か細い声で「おいでおいで」と手招きされ、隣に座らされた。
その人は寝間着の袂から赤茶けた小袋を取り出し、中身を私に見せた。ころんと小さなビー玉がたくさん顔を覗かせている。私がわあっと声を上げると、その人は嬉しそうに目を細めた。
それから二人で長いことビー玉を指先で弾いて楽しんだ。ころころと廊下を転がる玉を見て笑い、ぽとりと縁側から落ちた玉を見て笑い、始終笑い合った。
「綺麗だね」
一通り遊んだ後のこと。私は水色のビー玉を指先で摘みながら言った。私の隣に腰掛けていたその人は「そうだね」とか細い声で答えた。
ざあっと風が庭先を渡った。生暖かい、ぬめりとした湿気を含んだ風だったけれど、その人は寒そうに体を縮こませて震えた。骨ばった手をしきりに擦り合わせ、カチカチと歯を鳴らし始めた。
「お身体に障ります。部屋に戻りましょう」
傍らに控えていた人物が言った。私の手を引いてここまで連れてきた人だ。
私の隣に腰掛けていたその人は、喉に小骨が刺さったような痛ましい顔をした。そして私の頬に手をあてがい、「次はいつになるかしら」と何度も繰り返した。
あまりにも寂しそうだったので、私はビー玉を摘まんで差し出した。幾つかの気泡が入り混じる、淡い水色をしたビー玉。
その人は一瞬驚いたような顔つきになったが、すぐに表情を和らげた。そして恭しい手付きでビー玉を受け取った。
「ありがとうね」
眸を潤ませながら、その人は言った。
◎◎◎
「大丈夫ですか」
肩を揺すぶられ、はっと我に返る。狐の面を付けたままの桐島が私の横に立っていた。
「水でもお持ちしましょうか」
「いい……。平気、大丈夫だから」
「顔色が優れないようですよ」
「大丈夫。本当に大丈夫だから」
大きく息を吸い込んだ。上手く肺が膨らまないような気がして、数秒呼吸を止めてすぐ息を吐いた。
過去の記憶を一気に思い出した反動からくるものなのか。背中が汗でじんわりと濡れた。額に手をやると、やはり汗で湿っている。
「そのビー玉は、」
声が震えているのが自分でも分かった。
「口から出てきたの?」
桐島はすぐに答えようとはしなかった。天井を見上げたり、床を見つめたり、書庫が置かれてある店の奥に目をやったりと、せわしなく顔を動かした。
そしてふいに呟いた。
「亡くなられたんですよ。つい先日のことでした。死に化粧を施そうと家人が遺体に触れたところ、口の中にこれが入っていたらしくて」
桐島は手の平でビー玉を転がした。私は黙って桐島の手の平で回転するそれを見つめた。
そうか。あれからずっと持っていてくれたのか。
今和の際にでも口の中に含んだのだろうか。飴玉でもしゃぶるかのように。
ねっとりとした唾液にまみれさせ、舌の上でビー玉を転がす様子を思い浮かべた。奇怪なその光景は思い浮かべただけでも背筋がぞわりとする。
「僕も葬式に参列してきましてね。無理を言って頂いてきたんです。あなたに渡そうと思いまして」
私の手の平にビー玉を載せようとしたが、私は頑として受け取らなかった。桐島の手の平を押し返す私を見、彼は肩を竦めた。
「要りませんでしたか」
「要らない。私にはもう関係ない。私はもう、あの家とは何の繋がりもない」
強張った表情に固い声で突っぱねると、彼はそれ以上何も言わなかった。優しく私の手を払うと、ビー玉を手の平に包み込み、そのまま引っ込めた。
「用件はそれだけ?ならもう帰る」
やりこめない思いを抱え、踵を返すと。桐島は「こちらが本題ですよ」と言った。
「お渡ししたい物があって」
「遺品なら受け取らない」
「違います。祖父があなたからお預かりしていた物をお返ししたいのです」
「桐島、」
思わず桐島の胸倉を掴みそうになった。だが彼は、猛禽類の追撃のような私の手をするりと交わし、書庫のほうへと足を運んだ。
間もなくして、彼は骨壷ほどの小さな桐箱を持って戻ってきた。沸々と頭が熱くなり、ぎゅうっと力強く握り締めた拳が痛くなった。
今頃になって返してくるなんて。一体この男は何を考えているのだろう。
「あなたの物です。お返ししたくてお呼びしたんですよ」
物腰柔らかく桐島は言った。私は彼の視線から逃れるように、自分の着ている制服のネクタイを見つめていた。
だが、彼は私のつまらない黙りなど許さないとでも言うように、カラコロと下駄を笑わせながら近付いてきた。
私は外界の世界を遮断するために、ゆっくりと目を閉じた。そんなことをしても無駄だということは知っているけれど。
「祖父があなたから譲り受けた物。あなたの”子宮”をお返しします」
◎◎◎
「カミサマを宿すの」
からりと晴れたとある夏の日。縁側に腰掛けたその人は、私の下腹部を執拗に撫でながら言った。
じっとりと汗ばむ季節にも関わらず、その人はいつも白い寝間着姿に肩掛けをぐるりと羽織っていた。顔にも首筋にも汗の一筋もかいておらず、むしろ寒そうに体を小さく縮めていたのが印象的だった。
梅雨時はずっと伏せっていたようだが、今は少し体調が回復したらしい。小さな卵形の顔は、相変わらず血の気がなかったが、機嫌はいいらしかった。
私は縁側に座り、ソーダー味のアイスキャンディーをちびちびかじっていた。するとふいにその人が華奢な腕を伸ばし、私の下腹部を撫で始めたのだ。
「カミサマ、カミサマ、カミサマ、カミサマ、カミサマ、カミサマ、カミサマ、カミサマ、カミサマ、カミサマ……」
ゆらゆらと体を前後に揺すりながら、幸せそうにその人は繰り返し呟いた。私は驚き、食べかけのアイスキャンディーを取り落としてしまった。アイスキャンディーはその人の手の甲にポタリと落ちたが、全く気にならないようだった。
「ここに宿すの。カミサマを宿すの。宿すの、宿すの、宿すの、宿すの………」
体温を感じない、アイスキャンディーみたいに冷たい手で下腹部を撫で回され、子どもながらにぞうっとした。すーっと汗が引き潮のように引いていき、ぷつぷつと鳥肌が立った。
私は立ち上がり、「外で遊んでくる」と言い残してその場をあとにした。廊下の曲がり角で振り返ると、彼女はゆらゆら揺れたまま、何もない空間を撫でていた。
玄関で靴を履き替え、庭に出た。外に出たはいいものの、これといった目的があったわけではない。手持ち無沙汰に小石を拾い集めて並べてみたが、すぐに飽きてしまった。
ただ、あの人から逃げてみただけなのだ。恐れをなしたというわけではないけれど、あの時の彼女はどこか薄気味悪い気がしてならなかった。
どろりとした土臭い沼のような雰囲気をまとっていたように思う。底が全く見えず、ぬらぬらと黒光りする泥に覆われた深い沼。
足を突っ込んだら、一気に引き込まれて抜け出せなくなるに違いない。そんな気がしてならなかったのだ。
「お嬢ちゃん、久しぶりだね」
いつの間にそこにいたのか。濃厚色の着物に袖を通した矍鑠とした老人が私の傍に立っていた。彫りの深い顔立ちに幾つも刻まれた皺。細い目には鋭い光を漲らせている。
一見、厳しそうな顔立ちをしているが、根は優しい人だということを私は知っていた。
彼こそ、今は亡き桐島の祖父にあたる人物である。彼はよくこの屋敷に出入りしており、時には土産として自分の店から持ち出した骨董品を気紛れに屋敷内に置いていくような人だった。
あの人とも少なからず親交があったのだと思う。彼女は屋敷から出られないので、買い付けをする時は外部から商人を呼んでいるらしかった。桐島の祖父もその中の一人だったのだろう。
彼は時々、当時二十歳そこそこだった桐島を連れて屋敷に来ていた。私も何度か顔を合わせていたが、挨拶を交わす程度で会話らしい会話はしたことがなかった。
今日は連れてきていないらしく、庭にいるのは彼一人きりだった。
私は立ち上がり、ぱんぱんと土に汚れた両手を払った。どこかで蜩が物寂しく啼く声がして、何だかあ
の人が泣いているようだと思った。
「お嬢ちゃんは何かに怯えているんだね」
桐島の祖父が噛んで含めるように言った。心中を見透かされたような物言いに、どきりと心臓が鳴った。私が何とも言えない浮かない表情を浮かべると、彼は目尻に皺を寄せ微笑んだ。
「逃げ出したいかい」
彼はすっと屋敷を指差した。カナカナカナ、と蜩が啼いた。あの人に呼ばれたような気がして、そわそわしてしまう。
「逃げ出したいのなら、手伝ってあげよう」
彼は膝を折り曲げ、私と視線を合わせた。灰色がかかった黒目の中には、幼い私が口をきゅっと結んで立ち竦んでいるのが映っていた。
「カミサマになりたいかい」
私は首を横に振った。
それを聞いた彼は、にんまりと満足げに笑った。人間らしい笑い方だった。
「ならば、私に預けてほしい物があるんだよ」
◎◎◎
どれくらいの時間、目を閉じていたのだろう。
柱時計がごぉんごぉんと六つ鳴ったところで、私はようやく目を開けた。
開けたままの窓からは、ひゅうひょうと冷たい風が入り込んでくる。椅子に腰を下ろした桐島が湯飲みを片手に私を見た。狐の面は外され、椅子の背もたれにひょいと掛けられていた。
「良かった。眠ってしまわれたのかと思いました」
「ふん。立ったまま寝られる奴がいるか」
「祖父はよく立ったまま居眠りをしていましたけどね」
真実とも冗談とも取れる軽口を言いながら、桐島は湯飲みを啜った。湯飲みの中身はお茶ではなく珈琲なのだろう。豆を轢いた香ばしい匂いがふんわりと漂ってくる。
「御影さんも如何です」
彼はカウンターに置かれた湯飲みを顎で示したが、私はゆっくりと首を振った。
「帰る。弟が家で待ってるからな」
「お幾つなんですか」
私は少し黙った後、「中学二年」と伝えた。桐島はふむふむと何度も頷き、また湯飲みを口にした。
「可愛いでしょう。下の存在というのは」
「まあね」
「僕も逢ってみたいな」
「そんなことさせられるか。誰がお前みたいな危険な奴に」
「だって、ほら、ねぇ」
桐島は苦虫を噛み潰したような嫌な表情を浮かべると、先程の桐箱をことんとカウンターに置いた。
桐箱は澄ましたように静かに置かれているだけだったが、それこそが私には恐ろしく、下腹部の辺りがぎゅうぎゅうと締め付けられたような錯覚に襲われた。
そっと下腹部に手を当てる。あるべき物が欠けている、空っぽの下腹部を。
「あなたが受け取りを拒否するのなら、あなたに代わる誰かに渡さなくてはなりません」
宥めるような口振りで桐島は言った。駄々をこねる子どもに対るような甘やかな口調だった。少々苛立ちを覚えたが、私は毅然とした態度で臨んだ。
「それはもう私の物じゃない。私の手から離れた時点で私の所有物ではなくなった。それはお前の物だ。お前がじいさんから引き継いだんだろう?ならば好きにすればいい。棄てようが燃やそうが、お前が決めたらいいさ」
「僕は祖父を尊敬しています」
物憂げな目をした桐島は、壊れ物を扱うような手付きで桐箱を手に取った。私は彼がその箱を開ける気ではないだろうかと冷や汗ものだったが、桐島は開けることはしなかった。
でもね、と。桐島はぎこちなく笑って私を見た。薄い唇が引きつり、肉々しい歯茎がちらりと見えた。
「祖父は唯一失敗したのです。あなたからこれを取り上げることはなかったんですよ」
「私が望んだことだ」
「そうでしょうか」
「後悔はない」
「本当に?」
「言っただろう。私はもう、あの家とは何の関わりもない。それこそが私の望んだことだ。じいさんなは感謝してるよ。……だからーーーどうか頼むからーーー」
私は体を前屈させ、深々と頭を下げた。他人に対してここまで卑屈になったのは、これが初めてなのかもしれない。
「これ以上ーーー蒸し返すような真似だけは、止めてほしい」
血を振り絞るように、私は言った。
「欧介をーーーあの子だけはーーー巻き込まないで」
あの人はもういない。だけれど、血筋が途絶えてしまったわけじゃない。
私がいるから。本来ならば、私があの人の跡継ぎになるはずだったのだ。「カミサマ」をこの身に宿して。
しかし、私はそれを拒んだ。恐怖から逃れるために「カミサマ」を拒み、あの人を拒んだ。そして”子宮”を手離した。
”子宮”を桐島の祖父に預けたりしなければ。あの人は狂わずに済んだのかもしれない。
◎◎◎
しんしんと雪の降り積もる今朝方のことだった。私がぽつねんとストーブで手を温めていると、背の高い人物が部屋に駆け込んできた。
「魅梓(ミシネ)。どうしたの」
そうだ。私は彼女のことを魅梓と呼んでいた。
魅梓は綺麗な眉を吊り上げ、怒ったような顔をして私に顔を寄せた。いつもなら物静かで、あまり感情を面に出さない彼女にしては珍しい振る舞いだった。
「あなた、一体何をしたんです」
魅梓は私の両肩を掴むと、がくがくと揺さぶった。
「昨晩からあの方のご様子はおかしかった。ここのところ、体調は安定していたんです。それなのに何度も発作を起こされて。今も大変なのです」
廊下のほうから獣が断末魔を上げたような悲鳴が聞こえてきた。私達は一斉に顔をそちらに向けた。数秒後、再び悲鳴が上がり、屋敷全体を震わすようだった。
魅梓は私の腕を掴むと、引きずるように立たせた。そして般若の形相でぎろりと睨んだ。
「私と一緒に来て下さい。話はそれからです」
私達が部屋に駆けつけると、世話人の女中達が慌ただしい様子で布団の周囲に集まっていた。誰もが瓜のような青ざめた顔をしていたし、口々に何やら喋っていたようだった。
あの人がいた。彼女は仰向けに寝ながら甲高い声で悲鳴を上げ続けていた。喉が破れてしまうのではないかと不安になるくらい、からからとした悲鳴だった。咽せたのか激しく咳き込んだりもした。
魅梓が私を引っ張るようにして前に進み出た。みんなの視線が一挙に集まり、居心地悪くてむずむずする。
「お連れしました。どうかお気をしっかりなさって下さい」
魅梓が強張った口調で話しかけると、その人は苦しげに呻いた。女中が差し出す水差しを手で押しやり、肘をついてむくりと起き上がった。
その人は泣いていた。息を乱しながら、ぼろぼろと涙を零した。真っ赤に充血しきった目で私を見ると、頭をうなだれた。
「どうして……?」
かさかさに渇いた声だった。いつのか細い声より弱々しく、幽霊のようにどろんと消え入るような小さな声音だった。
「どうして、なくしたりしたの」
その言葉を言い終えた後、彼女はぱたりと倒れ込んだ。取り囲む女中達は短い悲鳴を上げ、医者を呼んでくると言って数人が部屋から出て行った。
魅梓は私を部屋から追い出すと、今日は一日中自室にいるようにと厳しく命じた。私はその言葉に従い、喧騒ざわめく部屋をあとにした。
この時になって、ようやく悪いことをしたのだと理解した。
騒ぎが一段落するまで、ひと月はかかった。いつもは静かな屋敷内に、多くの人間が押し寄せた。廊下ですれ違う度に、何やら怖くて足早に通り過ぎるようにしていた。
大人達は部屋に集まり、日夜話し合いをしているようだった。時には私までその場に呼ばれ、矢継ぎ早に質問されたが、何を言われても「分からない」「知らない」と言い張った。
話し合いに参加していた人物の中には、桐島の祖父もいた。彼は私と目が合うと、他の人間に気付かれないようにこっそりと笑った。陰鬱な顔触れの中で、唯一彼だけが楽しそうだった。
結果からして、私はこの屋敷にいられなくなった。養子に出されることが決まり、大人達は里親探しに躍起になっていた。
私は流れに身を任せるようにじっとしていた。きゅうっと体を猫のように丸めて。
里親が見つかったと聞いたのは、梅の蕾がぽちぽちと綻んできた春先のこと。桐島の祖父の伝手でどうにか見つかったらしかった。
「私の店のお得意さんでね。気だてのいい若者だ。早くに学生結婚をして、男の子を一人もうけたと言っていたよ。君より四つ年下だから、弟になるわけだね。まあ、仲良くするんだね」
桐島の祖父は里親となる人物についてそう教えてくれた。その人は玖埜霧という男性らしく、彼には既に妻と子どもがいるという。
私は人事のように聞き流しながら、あの人のことを思った。あの日以来、彼女はまともに話が出来ない状態になってしまった。魅梓が付きっきりで看病しているが、ずっと床に伏せったままだ。
あの人に会いたいと申し出たことがあったけれど、魅梓は受け付けてくれなかった。あの人がああなったのは私のせいだからと、悔しそうに呟きながら。
「あなたのせいです。あなたがあの方を狂わせたのです。もう二度とお会いすることは許しません」
最後まであの人に会えないまま、迎えに来た玖埜霧夫妻に連れられて、私は屋敷をあとにした。
振り返ることなく。
◎◎◎
硝子戸を開け、外に出る。既に陽は落ちて辺りは深い闇に包まれていた。ほつりほつりと頼りない街灯の光が仄かに光り続けている。
「またいずれお逢いしましょう」
別れの挨拶もなく、早足で店を出た私の背中に桐島の声が掛かった。一瞬足を止めたが、もう振り返らない。
後戻りは出来ないのだ。
「二度と逢わないよ。私とお前は、」
水と油だ。火と水じゃない。水と油。
溶け合わないし、解け合わないし、噛み合わないし、分かり合えない。私達は最初から出逢うべきではなかったのかもしれない。
私は大きく息を吐いた。今度こそ肺は大きく膨らみ、新鮮な空気が体中を巡るような感覚がした。
「弟さんに宜しく」
笑いを含んだ桐島の声を聞きながら、硝子戸をぴしゃりと閉める。
どこかで蜩が鳴いたような気がした。
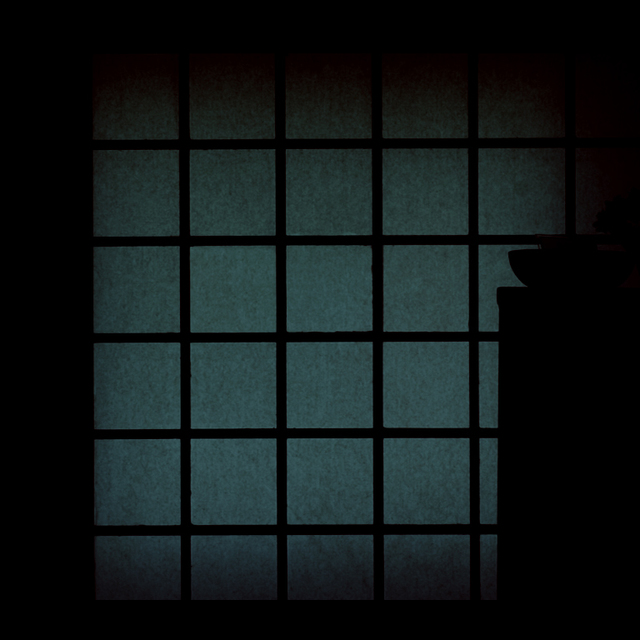

作者まめのすけ。
ホラーテラーに登録されている皆様。一日遅れになりましたが、明けましておめでとうございます。
行く先々の家で茶菓子にとケーキを出され、若干胃腸がアレなまめのすけ。です。食べ過ぎはいけませんね……(笑)。
まだまだ若輩者ではありますが。これからも皆様と共に活動を続けさせて頂きたいと思っております。
皆様にとって、かけがえのない一年となりますように。
今年も宜しくお願い致します。