父親が事業に失敗し、私達一家は引っ越しを余儀なくされた。
それまで住んでいた一戸建ては売りに出され、私達は狭い団地暮らしをすることになった。長年広い一戸建てに住んでいたせいもあってか、団地暮らしが息苦しくて仕方ない。夜中に音楽を聴くことも、シャワーを浴びることも出来なくなってしまった。造りが古い団地なため、壁が薄いからだ。集団生活とも言えなくもない。
日常生活をする上でも必要最低限の音を出さぬように、隣人に迷惑を掛けないようにと、管理人からきつく言われた。私も母親も、そして父親も。これからの生活を考えると気が重かった。暮らしぶりは質素になり、贅沢は赦されないようになり、父親の稼ぎだけではやっていけないからと母親もパートに出ることになった。
私は地元の高校に通っているが、それすら辞めなくてはならないような状況だった。だが、自分でも何とかアルバイトをしてお金を貯めるからと両親を納得させ、掛け持ちで3つアルバイトをしている。アルバイト三昧な生活なため、それまで必死に練習してきたバスケ部は辞めざるを得なかった。私は心底、憔悴し切っていた。
そんな私に追い打ちを掛けるように、友人の愛子がこんな話題を振ってきた。
「あんたさあ、今○○団地にいるんでしょ。あのけったいなボロい団地」
愛子は気のいい友人の1人なのだけれど、遠慮というものがない。オブラートに包んだ物言いも決してしないし、直球だ。それが彼女のいいところであり、短所と呼ぶべき欠点なのだろうが。私は嘆息交じりに愛子を見た。
「そうだけど。それが何」
「私、子どものとき、あそこの団地に住んでたことがあってさ。懐かしいなーって思ったから」
仏頂面の私とは違い、愛子はにこにこしている。何がそんなに面白いのだろうかと私は更に不機嫌になった。だが、愛子は話を止めようとはせず、捲し立てるような勢いで喋り出す。
「あそこの団地の裏にさ、小さな公園があるの知ってる?公園っつっても、立ち入り禁止の黄色いテープが貼ってあって、誰も入っちゃいけないんだけどね。遊具に至ってもジャングルジムと滑り台、それにブランコくらいしかない小さな公園でね。私が団地に住んでた時だったから、もう10年くらい前かなあ。その時は立ち入り禁止になってなかったし、団地に住んでる子ども達がよく遊びに来てたんだよ。私もよく遊んでたんだけどね」
「公園・・・・・・?」
公園があるなんて初めて知った。そもそも引っ越ししてきたのはつい先日のことだし、団地の周辺のことなどまるで分からないのだ。それに公園があるだなんて知ったところで、高校生の私としては別に嬉しくも何ともない情報だった。
そこの公園なんだけどさ、と。愛子は急にニヤリと笑った。
「幽霊が出るって噂があったんだよ」
愛子によると、そこの公園には幽霊が出るという噂が立ったことがあったらしい。というのも、いつもブランコに座っている男の子がいるらしいのだ。まあ、そこまで聞くと別に他愛のない話に聞こえるが。男の子がブランコで遊ぶこと自体は別に異常なことではないし、至って普通の光景である。だが、一点だけ妙なことがあった。
「だってその子___毎日いるんだよ」
毎日毎日、その男の子はブランコに座っていたらしい。平日だろうが祝日だろうが土日だろうが関係なく。当時、愛子の父親は毎晩のように仕事が遅かったらしいのだが。帰り道、公園の前に差し掛かると、その男の子がブランコに座って俯いていたのを目撃したらしい。時刻にして午後11時半。そんな遅い時間帯まで子どもが外で遊んだりするだろうか。
「当時は本当、その噂で団地中がもちきりだったの。子ども達も怖がって公園に近寄らなくなるし、中には怖がって引っ越ししたお宅もいたくらい。何かされるとか被害が出たわけじゃあなかったんだけどね。不気味というか気味悪い話でしょ。でも、今にして思えば虐待とかだったのかもねえ」
愛子自身、何度かその男の子を目撃したことがあるらしい。学校からの帰り道、あの公園の前を通る度にブランコに座る男の子の姿を見たらしいのだ。愛子もまた、あれは幽霊だと思っていたため、じろじろと凝視することは出来なかったらしいのだが。しかし、何度となく目撃していると、次第に慣れが生じた。怖い気持ちには変わりなかったが、怖い者見たさの気持ちもある。凝視するまでには至らなかったが、ちらりと目の端に留めるくらいまではするようになった。
遠目からだったので、どんな顔つきをしていたのかまでは分からない。ただ、特筆すべきなことは些か時代遅れな坊主頭であったこと、黄色いTシャツに青い半ズボンを履いていたことくらいは分かった。いつ何時に見掛けても、同じ服装をしていたという。
「ネグレクトとか、ね。親が洋服も着替えさせないとか、家に入れないとか。或いはただの家出少年だったのかもしれないけど。通報するなり専門機関に電話して対処して貰うべきだったんでしょうけど、誰もそんなことはしなかったよ。みんな気味が悪がって、その子に話し掛ける人もいなかったし。その子の目撃情報は、私が団地を引っ越す頃まで絶えなかったなあ。今となっちゃ本当に幽霊だったかどうかは分からないんだけどさ」
愛子からそんな話を聞いた私は、高校からの帰り道、例の公園に寄ってみることにした。愛子の話を信じたとか、怖いもの見たさとか、そういう気分からではない。何となく家に帰りづらいというか・・・・・・あの狭い一室がどうしても自分の帰るべき家だとは思いたくなくて、寄り道をして出来るだけ家に留まる時間を減らそうという目論見からだ。
愛子の言った通り、公園の入り口には立ち入り禁止と書かれた黄色いテープが貼られていた。仰々しいその有様に、もしかしたら、この公園では以前、何か事件でもあったのだろうかとそんな予感がした。私の知る限りでは、そんなニュースはやっていなかったと思うけれど。
テープをくぐり、敷地内に入る。流石に誰もいない___ぐるりと辺りを見回し、私は息を呑んだ。
ブランコに男の子が座っていた。坊主頭に黄色いTシャツ、青い半ズボン。愛子が言っていたあの男の子だ。俯いているため、顔立ちははっきりしない。でも、こうして見る限り、その子は生きている人間に見えた。体は透けてもいなかったし、薄汚れたスニーカーからは妙に生活感が出ていた。
「・・・・・・」
私の視線に気が付いたのだろう。その子がふと顔を上げた。こちらも特に違和感があるわけではない。これといって特徴のない目鼻立ち、薄い唇。見たところ10歳前後かと思われた。その子は私をじっと見つめると、にこりと笑った。笑った口元から八重歯が見える。
「どおぞ」
男の子が言った。一瞬、何を言われたのか分からなかった。だが、その男の子が立ち上がり、ブランコを指差したのを見て、ようやく合点が言った。この子は私にブランコを譲ろうとしているのだと。
「どおぞ」
男の子が繰り返して言う。私がずっと見つめているのをブランコに乗りたいからだと勘違いしたのだろうか。男の子は嬉々とした、何かを期待するような顔をして笑ってブランコを指差している。だが、私は別にブランコに乗りたいと思っていたわけではないので、返事に困ってしまった。
「どおぞ」
「え・・・。いや、私は別にブランコに乗りたいとかそういうんじゃなくて・・・・・・」
「どおぞ」
男の子は焦ったような表情になる。その顔つきからして、幽霊ではなさそうだ。間近で見るとそれがよく分かる。肌の感じや口調からは生きている人間の匂いがした。それには安心したが、しかし。何を言えばいいのか分からない私に対し、男の子の顔色は必至の形相に変わった。今にも泣きだしそうな、大声で咽び泣きそうな顔をして、体を小刻みに震えさせ、尚も続ける。
「どおぞ」
ここで泣かれても困る。私は正直、子どもの扱いには慣れていないし、どちらかといえば苦手だ。子どもが泣いた時、どういった対処を取るべきなのかなんて分からない。ヘタしたら、泣き声を聞きつけて誰か来ても面倒だし・・・・・・。私はやれやれと肩を竦め、苦笑交じりに頷いた。
「分かった分かった。乗ればいいんでしょ。ありがとね」
男の子は満面の笑顔になった。目を細め、にこにことあどけなく笑う。その笑顔を見ていると、小さな親切を施したような気分になって、自分も嬉しくなった。ブランコに腰掛けると、その子はぺこりとお辞儀をした。
「ありがとうございます。ぼくのかわりになってください」
言うが早いか。その子はぱっと背中を向けると、一目散に公園から出て行ってしまった。私はその子の言っている意味がまたしても分からず、首を傾げる。
「ぼくのかわりに、って・・・・・・何それ」
ブランコを降りようとして気が付いた。足が動かないのである。はっとして足元を見る。・・・・・・何もない。茶色いローファーが見えるだけだ。なのに足が動かない。立ち上がりたくても立ち上がれない。
「な、何これ。誰か、ちょっと・・・・・・。う、動けない。どうしよう、動けないよ。な、何で?何でこんな____」
顔を上げると、公園の入り口にあの男の子が立っていた。さきほどまでのあどけない笑顔とは違い、ニヤニヤとしながら私を見ている。今にも泣きだしそうな私に向かって、男の子は大きな声で言った。
「おねえちゃんはぼくのかわりです。これでぼくはこうえんからでていくことができます」
おねえちゃんも、かわりをみつけたらでられます。
「だ、誰か____」
私の代わりに。
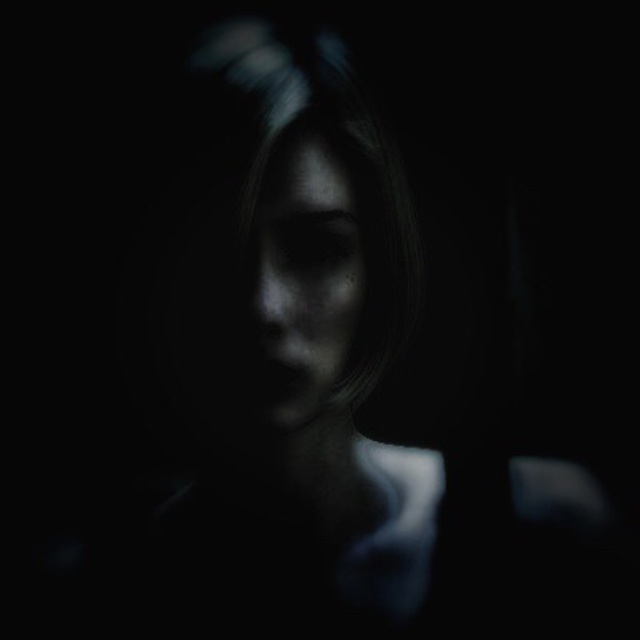

作者まめのすけ。