「ゴメンね、僕、携帯持ってないんだ。」
この言葉を発したとたんに、水を打ったように静かになる瞬間がいやだ。
今や、携帯を持っていないという言葉は、あなたとはコミュニケーションを取りたくないという発言に等しい。
「へ、へ~、珍しいね。今時。不便じゃないの?」
女の子は明らかに様子がおかしくなってきた。
僕は今、会社の連中に無理やり誘われた合コンに人数あわせで来ている。
こうなるから嫌だったんだ。僕は断ったのに、同僚に目の前で手を合わせられて
「お願い!一人どうしても足りないんだよ。ちょっとだけでもいいから。」
と懇願されたのだ。
こいつらの魂胆はわかっている。どうせ僕は通信手段を持たないのだから、女の子たちから
対象として除外される。とりあえず人数あわせで僕を入れておいて、自分達の当確を高めようってわけ。
僕は愛想笑いをしながら、席を立つ。トイレにも行きたくないのにトイレに立つ。
「あ、私も。」
僕のあとから、女の子たちも女子トイレに向かった。おそらくお化粧直しだろう。
僕は、トイレに誰もいないのを見計らって個室に閉じこもった。
「何よ、あの男。ちょっとかっこいいからって勘違いしてね?」
「電話番号交換しよって言ったら携帯持ってない、ですって。みえみえの嘘よねえ。」
「そうよ。いったい合コンに何しに来てんだか。」
「ああ見えて、童貞だったりして!」
「そうかも~。それでアタシたちに恐れをなして。キャハハハハ。」
女子トイレからの会話筒抜けだよ。
僕はやはり勘違いされてるんだな。僕は女の子達の会話を聞いてげんなりした。
僕だって正常な男子だ。女の子と付き合いたいし、エッチなこともしてみたい。
ちなみに童貞ではない。初体験は高校2年の時だ。
nextpage
全ては、携帯の機種変更から始まったのだ。
携帯電話の機種変更をしたのは、社会人になってからだった。
僕は物持ちが良いほうで、高校生のころから使っていた携帯を大学まで
ずっと使っていたのだ。
就職を機にそろそろ携帯を買い換えようと思い、携帯電話のショップに向かったのだ。
そこで、ある機種をいたく気に入ってしまい、購入を申し出ると、もうそのデザインは売り切れだと言われ、がっかりした。僕はどうしても、そのデザインが欲しくて、今後入荷の予定は無いのかと聞いた。
すると、ショップ店員がお客様が気にされないのなら、と返品になったその機種を出してきたのだ。
壊れているとかいうのではなく、あくまでもお客様都合で返品になったとのことだった。
その代わり、割引価格で、と言われ、見た目も使用感がなくまったく綺麗なので僕は二つ返事で購入することにしたのだ。
僕はその日、欲しい機種が手に入ったので喜び勇んで自宅に帰った。
家に着くと同時に、電話が鳴った。見たことも無い番号だ。もしかして、ショップからかな?
僕はそう思い、通話ボタンを押した。
「・・・ぃやっ! ・・めて!お・・願い。許して・・・・。」
女の懇願するような声が聞こえてきた。間違い電話?僕はそう思い、
「もしもし?」
と声に出した。
「や、やめて。いやいやいやぁ~!」
今度は女は叫び声になった。
「ど、どうしたんですか?」
間違い電話の相手は窮地に立たされているらしい。僕はパニックになった。
「やめぅぐぅ。く、くるし・・・んぬう。」
苦しそうに必死で息を吸おうとする様子がうかがわれた。
これは、ヤバい。たぶん事件だ。
「もしもし!何があったんです?大丈夫ですか?」
僕が叫ぶと、電話口は静かになった。
そして、ツーツーツーと音がして切れたのだ。
僕は再ダイヤルした。すると女性の声で
「この電話番号は、現在使われていません。もう一度、番号をお確かめのうえ・・・。」
と乾いたガイダンスが流れた。
う、嘘だろ?確かに今、この電話番号から電話が・・・。
それが全ての恐怖の始まりだった。
nextpage
separator
「おとうさん、おかあさん、ごめ、ごめんな さい。」
風が強い。ことりと何かを置く音がする。
そして、すぅっと息を吸い、吐く音が震えている。
そして次の瞬間、轟音とともに少年のわぁぁぁあと叫ぶ声が数秒続き、ごがんという鈍い音と共に何かが潰れた音がする。あとは静寂が流れ、周りの悲鳴が聞こえる。そこでつーつーつーと音声が途絶えた。
案の定、その電話番号は使われていないと告げられた。
聞いただけでも、少年が自殺をしたのだなという想像がつく。
nextpage
そういう電話がかかってくるので、僕は自分の登録した番号以外には電話を着拒否したのだ。
そんなある日、友人から着信があった。
「もしもし?」
僕が電話に出ると、ききーっっという車のブレーキの音がし、ドカン、ガチャンという音が連続してあった。
そして、自転車の車輪のような、カラカラと回る音。僕は口の中がからからになった。
友人が事故に遭った!そう思ったのだ。僕は慌てて、リダイヤルした。
そっか、リダイヤルしたところで、本人が怪我したら出れないじゃないか。僕がその思いにいたった瞬間に電話が繋がった。
「もしもし?」
友人の声だ。僕は心底ほっとした。
「お前、大丈夫だったか?今すごい音がしたけど。事故にでもあったのか?」
僕がそう言うと
「はぁ?何言ってんの?」
と返事が返ってきた。
「だって、さっきお前から電話があって、取ったらすごい音がしたから。車にでも自転車でぶつかったのかと。」
「かけてねーし。俺、ずっと家でゲームしてたから。お前、寝ぼけてんじゃね?」
そう友人に笑われた。
僕には思い当たる節があった。
まさか、友人の番号でまでかけてくるようになるとは。
これは明らかに、この電話がおかしい。
呪われている?
僕は絶望した。
せっかく機種変したばっかりなのに。
僕はその電話を手放す決心をしたのだ。
僕は、携帯電話を解約した。
たぶんあの携帯はいわくツキだ。
あの携帯を手にした日からおかしな電話がかかってくるようになった。
きっとあの携帯は何か理由があって手放されたに違いない。
僕は携帯を解約するかわりに、自宅に固定電話をつけた。
元々昔は固定電話しかなかったじゃないか。これで不便はないはず。
僕は友人に携帯を解約したことを告げ、かわりに自宅の電話番号を告げた。
これでもうあの、忌まわしい終末電話から解放される。
なんで全てが死に際なのかわからない。やはり呪われているのだろう。
そんなある日、僕の自宅の電話に着信があった。
いろいろ面倒な電話がかかってくるので、自宅に居ても留守電にしているのだ。
留守電のランプが点滅していたので、僕は会社から帰宅して、録音を聞くためボタンを押した。
(ただいま留守にしております。ご用件のある方は発信音の後にお話ください。ピー。)
「お母さん・・・。怖いよ。なんで、包丁持ってんの?」
「死のう。一緒に。もうこれ以上生きていけないのよ。」
「いやだ。死ぬのはいやだ。怖い、怖いよーうわーん。」
僕はその場に凍りついた。
なんで?
携帯はもう解約したのに!
「ぎゃーーーーーー!痛い、痛いよ!ぎゃーーーーーーー!」
痛ましい子供の声に僕は耳を塞いだ。
「ごめんね、ごめんね、ごめんね。」
何度も泣きながら謝る女の声。子供の声がしなくなった。
すると、低くしめった音がした。
「ぐふっ!ごぼぼ、ごぶぉほ!」
「こん、どは・・リセット・・・ごぼぼ・・しなくていい・・げぼっ!しなくちゃ。」
そう言い残すと電話が切れた。
ツーツーツー。
再生終了。
僕は膝から崩れ落ちた。
何で?何でだよ。僕ばっかり。
それからも、人の死に際と思われる録音が残されていることが多々あった。
終わらない終末電話に僕は途方に暮れた。
ほどなくして、僕はついに、固定電話までも手放すことになったのだ。
僕はまるで世捨て人のような生活を送っていた。
家に帰れば、もう通信手段はない。
あんな電話を聞くのはもうまっぴらだ。
世捨て人というのは大げさだが、僕は意外に誰にも干渉されない生活に居心地の良さを感じていた。なんだ。電話なんてなくても大丈夫じゃないか。
僕はもっぱら連絡はパソコンのメールに入れてもらうことにした。
だから、パソコンを開く時間が少しだけ長くなった。
パソコンを時々開いてはメールをチェックして、あとはずっと夜長本を読んで過ごした。だが、その安心も打ち壊されることになった。
僕は、ある日会社にかかってきた一本の電話に出た。
「お電話ありがとうございます。〇〇商事でございます。」
「・・・ろして。はぁはぁはぁ。もう・・・こ・・ろしてくれ。」
それは小さくほとんど息のような声だった。
「こんなに・・・くる・・・しいのなら・・。もういきたくない。」
「何を言ってるの?お父さん!気を確かに持って!家に帰るんでしょ?」
女のすすり泣くような非難する声。
「おれは、もう・・・だめ・・・だと。しっているから・・。もうしなせて・・くれ。はぁはぁはぁ。」
息も絶え絶えの声。
僕はあまりのショックに立ち尽くす。周りの同僚が奇異な目で見ているにも関わらず、動揺が隠せない。
「おとうさーーーん!ダメ!目を開けて!おとうさーーーーーん!わぁああぁ。」
ツーツーツー。
「どうしたんだ?お前?」
同僚に横から突かれてようやく我にかえった。
ひきつる頬を無理やり緩めながら
「ああ、間違い電話。はは。」
と吐き出すように笑った。
同僚は僕の様子を怪訝な目で見ていた。
その頃の僕はほとほと困っていた。
ついに会社の電話にまで。
しばらく電話恐怖症になり、なかなか出れなかった。
だが、会社組織というもの、電話にまったく出ないというわけにはいかない。
唯一電話から解放される、昼休み、僕は一歩でも会社を離れたくて、外食することにした。自分の部署を出て、長い廊下を歩いていると、向こうから長身のロン毛、見たことも無い男が歩いてきた。よその課の男かな。年のころは25くらい。僕と同じくらいか。その男は遠くからでもわかるように、僕の方を見ていた。見ていたというより、睨んでいる。知り合いでもないし、睨まれる覚えも無い。そして彼はすれ違いざまに、チッと舌打ちしたのだ。僕が驚いてその男の顔を見た。胸の名札には「龍石」と書いてある。りゅうごく?って読むのかな。
僕はいわれのない、舌打ちに戸惑っていた。
なんだよ、僕が何をしたって言うんだ。
僕はあの電話があった日から会社の電話すら、出るのが怖くなった。
いつまでも鳴り止まない電話を知らぬふりをしていると、皆が怪訝な表情で見てくるから仕方なく出るのだが、終末電話は時々かかってくるようになった。
いったい僕が何をしたと言うのだ。もうこれは電話の問題ではない。
昼休みに、社食でそんなことを考えていたら、僕の前に一人の男がドカっと座った。空いているのに、わざわざ僕の前。知り合いかと顔を上げてみると、そうではなかった。名札には「龍石」の名前。いつも僕を睨むやつだ。僕がポカンとしていると、龍石は、ふうっと溜息をつき、
「ようやく気付いたのか。クソ鈍い野郎め。」
と悪態をついた。僕は、わけがわからずに、
「え?何が?君は誰?」
と龍石に言った。
「だから、電話の所為じゃない。お前に憑いてんの。」
そう言うと、僕の頭の上を指先で指した。
僕は電話という言葉に過剰に反応し、ガタっと立ち上がった。
その瞬間に、足が机に当たってしまい、見事に龍石のスーツを濡らしてしまった。
「あぁっ!ごめん!」
僕が慌ててハンカチを出すと、龍石は手でいらないと伝えて自分のハンカチでこぼれてかかった水を拭いた。
「今日、仕事終わったら俺に付き合え。終業後、エントランスで待ってる。」
そう言い残すと、すたすたと行ってしまった。
結局僕は何も聞けないまま、呆然と立ち尽くした。
あいつは何故電話のことを知っている。ツイテルって言った。
僕は仕事があまり手につかず、デートの前のようにそわそわした。
あまりにも謎が多い龍石。彼はいったい誰なんだ。
龍石は、エントランスの椅子に足を組んで、こちらをまっすぐに見ていた。よく見れば、長身で細身。スーツがよく似合っている。サラリーマンというよりは、どこかのホストのようだ。しかもイケメン。こんな目立つやつに今まで気付かなかったなんて。しかも、ここまでかっこいいと女子社員の間でかなり噂になるだろうけど、龍石という名前の一言も聞いたことはなかった。いくら男とはいえ、そこまでまっすぐ見つめられると、照れてしまう。
「行くぞ。」
僕が近づくと、そう龍石が言って立ち上がった。
「は?行くってどこへ?だいたい君が誰なのか僕は聞いてない。」
僕がそう言い、難色を示すと、龍石はかなりイライラした様子で言った。
「俺は、龍石。これでいいだろ。四の五の言ってないで来い!」
そう言うと、僕の手を強引に引っ張った。
「は、離せ!何をするんだ!」
僕が抵抗すると、龍石は異常なくらい端正な顔を僕の顔に近づけて言った。
「ここは、人目がありすぎる。」
何それ・・・。僕は何故か、ヘンに赤面してしまった。
どうかしてる、僕。
みんなの注目を浴びているのに気付き、僕らは足早にエントランスを後にした。
「いい加減、手を離してくれないかな。」
龍石は、僕の手をしっかり握って話さなかった。
男二人が手を繋いで歩いている様子はかなり注目を引く。みんなが龍石のルックスと、男二人が手を繋いでいる様子にチラチラと視線を投げかけてくる。これでは、ゲイだと思われるではないか。
「逃げないから。ちゃんと付き合うよ。」
僕がそういうと、ようやく手を離してくれた。
黙って龍石は前を歩く。
「僕をどこへ連れて行こうっての?」
龍石は答えない。これって駅に行ってないか?電車に乗るのか。
僕と龍石は、改札を抜けた。やはり電車に乗るらしい。
「そろそろちゃんと説明してくれないか。」
いい加減僕はしびれを切らした。龍石は前を向いたまま言った。
「お前、憑かれてるからへんな電話がかかってくるんだ。俺が、そいつをやっつけてやるから。」
龍石はどうやら、僕の悩みを全て知った上で助けてくれるらしい。
電車は混んでいたが、長く乗っていると、どうやら座れるスペースができた。
僕と龍石はそこに腰掛けた。
「何で僕におかしな電話がかかってくることを知っているの?君は何者なの?」
僕が聞くと、龍石はふと遠い目をした。
「お前は覚えていないだろうな。」
と一言つぶやいた。もしかして、僕は遠い昔、龍石に会ったことがあるのだろうか。随分と長い間、電車に乗っていると、なんだか懐かしい風景が飛び込んできた。
ここって。僕の実家がある町じゃないか。
龍石は、僕のふるさとの町の駅で降り、また歩いてどこかへ向かっている。
懐かしい風景。ここは僕が幼い頃、よく遊んだ神社だ。
ずっと黙って歩いていた龍石が、その神社の鳥居をくぐったところで止まった。
そして、くるりと僕に向き直り、スーツの内ポケットから古そうな鏡を出してきた。なんだか汚い鏡。裏は金属の複雑な模様が施されており、青さびが所々浮いている。
「お前、自分の頭見てみろ。」
僕は鏡を突きつけられ、龍石の手のひらの中の手鏡を見た。
「うわぁ!」
僕は驚いて後ろによろけてしりもちをついてしまった。
なんと、僕の頭の上に、髪の長い女性が噛み付いていたのだ。
龍石の手が、すうっと僕の頭に伸びてきた。鏡は持ったままだ。
僕の頭の上の女の頭をぐっと掴んだ。龍石の手にすごい力が加わり、女は苦悶の表情を浮かべだした。そして、次の瞬間、龍石の手の中で木っ端微塵に砕け散り、僕の頭の上に飛び散ったのだ。
「いやぁあぁああ!」
僕は女のような甲高い叫び声を出した。女が砕けて、僕の体にその禍々しい肉体が降り注いだ感触がしたからだ。実際には、僕の体には何もついていない。だが、感じたのだ。肉片を。血を。生暖かい内臓の感触を。
「もう心配ない。あの女は、お前が機種変した携帯の持ち主になるはずだった。あの携帯を取りに行く途中で、交通事故に遭って死んだんだ。あの女もあの携帯をいたく気に入ってて思念が残った。本当ならもっと生きるはずだった自分の人生が終わってしまったことが理解できなかったんだ。だから、お前に噛り付いて、この世にとどまろうとした。」
「君は、何者なの?」
僕はやっと口を動かすことができた。
「昔、お前に助けられた。だからこれでもう貸し借りなしだ。」
そう言うと、龍石は、神社の外ではなく、中のほうに歩いて行った。
「待って。ごめん、僕君を思い出せないけど。でも、ありがとう。」
僕がそう言うと、龍石が振り向いて、初めて笑った。
龍石の姿がだんだんと薄くなって行く。周りの景色に溶け込むように。
僕は自分の目を疑った。やがて、ほとんど輪郭しかわからないほど溶け込んで消えてしまったのだ。
こんな不思議な体験が信じられるだろうか。僕はまるで夢を見ているようだ。僕は無意識のうちに、龍石が消えたあたりまでふらふらと歩いて行った。そして、足元に小さな石碑のようなものがあることに気付いた。その石碑には、丸い石を抱いた龍が彫られてあり、あの鏡が石碑の下に落ちていた。
僕は、堰を切ったように思い出した。
お前、あの時の。
「見ろよ、へんな蛇!」
近所で一番の悪ガキが、長いものを振り回していた。
僕はそいつが嫌いだった。顔に知性のかけらもないと書いてある。
その生き物は振り回されてぐったりとしていた。
本当にバカだな。かわいそうなことをする。
僕はみかねて注意しようとしたが、素直に聞くガキではない。
「神社で生き物をいじめたら、龍神様のバチがあたるって、ばあちゃんが言ってた。」
僕はぼそっと、独り言のように言った。
その悪ガキは、バチという言葉が気になったのか、僕に突っかかってきた。
「なんだよ、どんなバチが当たるってんだ。言ってみろ。」
僕はにわかについた嘘に食い下がってくるとは思いもしなかったので焦った。
「確か、おちんちんが龍のように腫れるって聞いた。」
僕は適当に嘘に嘘を重ねた。
「嘘つけ、コノヤロウ。」
そう言いながらも、少しだけ勢いが弱まったような気がした。
心なしか内股になっている。
「あーあ、もう飽きた飽きた。行こうぜ、みんな。俺んちでゲームでもするか?」
そう言いながら、持っていた長い生き物を放り出して、神社から出て行った。
僕は心の中だけで笑った。意気地なし。
僕は放り出された、長い生き物を見た。
なんだこれ。蛇のようだけど、なんだか顔が違う。蛇にヒゲってあったっけ?
これは、まるで・・・。僕は、足元の石碑を見た。
この龍みたいだ。まさかね。蛇の突然変異だろう。
僕がじっと見てると、うねうねと動いた。
よかった。生きてる。
「もう悪ガキに見つかっちゃだめだよ。」
僕はそう、声を掛けて神社を後にした。
そのあくる日、あの悪ガキは学校を休んだ。
後で聞いた話によると、本当におちんちんが腫れたらしい。
僕が適当についた嘘なのに。自分でもちょっとぞっとしてしまった。
ある日、神社で遊んでいると、知らない男の子が鳥居の近くに立っていた。
ここらへんでは見ない顔だ。ハーフのように美しい顔の男の子。
「よお、あいつのちんちん、腫れただろ。」
まったく見ず知らずの男の子にそう話しかけられ、最初何のことかわからなかったけど、悪ガキのことだとわかった。
「君は、誰?あれは君の仕業なの?」
僕は、その子にたずねた。
「さぁな。龍神様のバチが当たったんだろ?」
そう言うと意味ありげに僕に笑った。
「借りはいつか、必ず返すからな。」
そう言うと神社の敷地の奥のほうに去っていった。
カリヲカエス?僕は言葉の意味がわからなくて、その子の後を追った。
神社の裏手のほうに行ったと思われ男の子はもう姿はなかった。
どこへ行ったんだろう?こちらには出口は無いはずだ。
よく見ると足元に、あの石碑があった。
龍が石を抱いている石碑。
これがおばあちゃんが言ってた、龍神様なのだろうか。
それにしては、あまりに小さすぎるな。
まさか、あの子は・・・。
僕は、25歳になった今、その不思議な体験を思い出していた。
どうして忘れていたんだろう。
「龍石、ありがとう。」
木々を渡る風が、こたえのように、僕の体を撫でた。
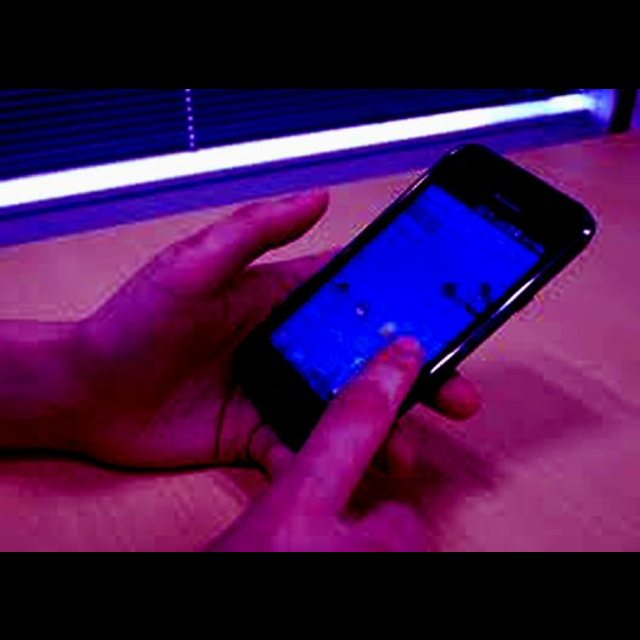




作者よもつひらさか