wallpaper:150
空は雲で厚く覆われているけれど、雷が鳴るような様子は無い。あの一瞬の雷は、一体どこから来たんだろうか。
ぼんやりと考えていると、私がほかのことを考える余裕ができたと察してか、白いのが離れた。その顔は、良かった、と思っているようにも見える、ほのかな笑みを浮かべていた。
「大丈夫ですか」
「荒瀬さん」
「……さっきので、居なくなりました。もう、ここには来ないでしょうし、私たちには、かかわらないでしょう。白いのが、いると分かったようですから」
背中をさすられて、ほっとする。粉々になった腕時計を、白いのが大事そうに、一粒ずつつまみあげているのが見えた。
白いのはそれを両手に取ると、こちらへ来た。パーツも割れて、粉々で、だけど。不思議と、焦げたり溶けたりはしていなかった。雷の直撃を、受けたかのように思えたのに。
「はい、えみ」
手を差し出す白いのに、うーん、と考えて、私はポケットからハンカチを出した。ここに置いてね、と言うと、それに従って白いのは掌の中の部品を、丁寧に置く。私はそれを包んで、白いのに伝えた。
「どうして私の腕時計が、必要だったの?」
「やくそくさせるため」
「約束?」
「やくそく、きまり。きまりごと。やぶっては、ならない、こと。だいじにって、いったのに」
つまり。白いのは、私の腕時計を外の者に与えて、『大事にして』と伝えた。与える、ということは、その対価が必要になる。白いのにとって、対価は約束。しかしその約束は、腕時計が壊れたことで破られた。破られた約束に対する罰を、まさか、白いのは外の何かに与えたということだろうか。
私は思わず、白いのの手を掴んでいた。
「なんでそんな危ないことしたの?」
「あぶなくない」
「恵美さん、落ち着いて」
荒瀬さんに言われて、ハッとする。白いのが、うつむいていた。しょんぼり、という表現が似合う様子に、私は慌ててしまった。
「……ごめんね。私の事、心配してくれたんだよね?」
のぞき込むように言うと、こくり、と小さな頷きが返る。
「わたし、は、えみの、むしだから。だから、した。あぶなく、ない」
「そっか。……ごめんね、すごくびっくりしちゃったの。白いのが、危険なことをしたんじゃないかって」
「へいき。わたしは、むしだから」
「ありがとう。じゃあ……うーん、お礼にってこの時計あげるのは、ちょっと違うか」
粉々になった時計を見て私が言うと、白いのが急に笑顔になった。くれるの? 、と期待しているようなので、頷いてハンカチごと渡す。
「家に帰ったら、もっといいやつにしようね」
「いいやつ?」
「これ、壊れちゃったから」
「こわれてないよ」
にこにこと返す白いのに、首をかしげる。壊れていない、という理由を聞こうとしたとき、だった。
にわかに廊下の方が騒がしくなる。
「無事ですか!」
戸を開けたのは、恵栄さんではなかった。だいぶお年を召していらっしゃるらしい、お坊さんだ。質素だけど美しい目の細かな生地で作られた衣装をまとっていて、その所作の一つ一つにも気品のようなものが感じられる。
そして、そのお坊さんは、部屋に居る私たちと、粉々になった腕時計を大事そうに持つ白いのを交互に見て、へたり込んだ。
「……ようございました。ご無事で、本当に、ようございました」
目に涙を浮かべて言われるから、まるで訳が分からなかった。ただ、荒瀬さんは状況を把握していたらしい。
「こちらに、来たのですね?」
そう荒瀬さんが尋ねると、そのお坊さんが姿勢をただして、さっと頭を下げた。
「申し遅れました。わたくし、住職の、甘英と申します。おっしゃる通り、あれは、本堂から離れ、あなた方のいるこちらに向かった様子でした」
思わずぽかんとした顔をさらしてしまった私に、甘英さんは話が飛躍しすぎていることに気が付いたらしい。部屋にはいるとふすまを閉めて、そして外の白いのを感慨深そうに見つめてから、私たち二人のほうへ向き直った。
「まず、田中様。あなたのご友人方は、先ほどの雷を持って、救われました。もう大丈夫です」
「……ええ?」
ほっとしていいやら、いけないやら。相手がどんなものかも分からないし、皆に何が起きていたかも理解していないから、救われたと言っても全く見当がつかない。
混乱する私に、甘英さんが順を追って話し始めてくれた。
「あなたのご友人方を追っていたのは、言葉として選ぶなら、神と呼ばれる存在です」
神。そう聞いてまず私は、かつて南光神社に祀られていただろう存在を、考えた。
しかしもう、南光神社は建物だけの存在で、中には何もいないはずだ。残されていたのは、空の社だけだった。いや、もしかして。
「もしかして、白いのが言う『とちゅう』が、みんなを狙っていて、それはもともと、土地に居たものということですか?」
私が思わず言うと、甘英さんが頷いてくれた。
「そうです。ご友人方は南光神社が建つ土地に封じられていた、神のなりそこない、それに追われていました。もっと言うなら、なりそこないの、声の様なものに追われていたんです。本体はいまだあの神社に居るでしょうが……先ほどの雷で、もう外へ出てくることは、無いでしょう」
「神様の、なりそこない……」
姿勢をただし、甘英さんが続ける。
「宗教とは、説かれた教えを信ずる人がいて初めて、成立します。それを形作るのに、人は時として、神と言う存在を求めます。そうですね、それが一番合理的で、分かりやすいからでしょうかね。力のある神体を見た人は、そこに救いを感じ取ります。それは概念であり、理念であり、信念であり、感情であり、観念です。儀礼、儀式によって武装された、力を崇めるための集団に名をつけるための教えを、人は宗教と呼びます。
ではその神は、どこから来るのでしょうか?」
神様は、どこから来るのだろう。この一日で、神様について考えさせられることが、増えた。
私が黙っていると、代わりに荒瀬さんが口を開いた。
「神は元より、人であった場合もあります。佛陀やキリスト教のイエス・キリストなども、これに当てはまりましょうか。孔子や諸葛孔明のように、今少し詳しく歴史が記されるようになった時代の者や、戦争で亡くなられた英霊を神とすることもあります。
その一方で、超自然的な脅威を、神として崇めることもあります。例えば、先ほどの雷、そして空、大地、海そのもの。自然がもつ、人には計れぬものを、古来から神と崇める風習は多くあります。
またあるいは、感覚的なものです。外の法、この世界とは異なる何かを、元とするものを感情的、情緒的、あるいは空間として捉え、人が力として崇めること。
それがいつの頃からあるのか、或いは最初は本当に神と言うものが何か固定された力の塊であったのか、そういったことは議論としては面白くありますが……。今は置いておきましょう。
ともかく、神と言う存在には、自然と人が集まります。人間が、神を支え、生み出します。人間の信仰が途絶えた神は、やがて消えます。少なくとも、強大な力や、邪な思いが込められていない限り、おおよその祀られぬ神は忘却され、消えさります。しかし単純な力を持っただけの何かは、残るのではないでしょうか?」
甘英さんが、頷いた。
「荒木教授の教え子ですね。……そうですね、私もそのような側面を感じることがあります。信仰に伴う、仕来りと儀礼、我々の想像力が、何か大いなる力を、神や御仏という形に押しとどめているのではないか。そして反対に、逆のことが、何か大いなる力を信仰やしきたりや儀礼、人々の考える力が、神というものを作り出すのではないか、と」
「ではこのたびの、あれは」
「……あなたには見えましたか」
頷いた荒瀬さんに、やっぱり、と思った。白いのが、私の目をふさいでいたんだ。その何かを、私が見てしまわないように。
「彼女は、この白いのが守っていますから、何が起きたのか。何が居たのか分からなかったと思います。私には……異形の人であるように、思えました」
「ええ。……その腕時計は」
「白いのが、約束を破らせるために渡したものです。それなりに長いこと、彼女が身に着けていたものです。身に着けているものを渡される、すなわち、供物として納められた。しかしあれは、腕時計を壊しました。神として、いえ、望まれた神としてしてはならぬことを、したのです」
私はふと、疑問を抱く。
ほしいの? 、と白いのは尋ねていた。なら、その腕時計を渡したものは、普通壊さないんじゃないだろうか。そう思って白いのを見ると、否定するように首を横に振った。
「えみ、は、あげられない。えみの、からだ、も、わたせない。かみ、は、ちからになる。つめも、そう。だから、えみ、のもちもの、で、こわれそうなの、えらんだ」
ごめんね、白いのが、言う。
そうなのか。納得して頷く私とは対照的に、甘英さんがため息をついた。荒瀬さんはもう、こういったやり取りに慣れている。私が白いのと会話するのも、私が白いのに何かあげるのも、もはやいつものことだった。
「……凄まじいことです」
甘英さんが、ひどく難しい顔をして、私を見た。
「対処としては、我々がしようとしていたものと、白いの、と申されましたか。そちらが執り行ったことは、似ております。しかし我々には、そのように直接的な方法は取れませんでした。なぜなら、あのように直接的に触れて、私たちのほうに被害が及ぶ可能性が、否定しきれないからです。時間は、より一層、かかったことでしょう」
「あの、友人たちが聞いていたことって、何ですか?」
「彼らを追ってきた者の、声です。表現は……しようがありませぬ。幼子の様な、老人が子供の声を出すような、何とも言えませぬ。我々とは、とても、とても、遠い存在なのです」
言葉が見つからなくなって、それはきっと怖いんだろうなと、私は想像することしかできなかった。恐ろしいものを、感じることはある。でもそのほとんどを、白いのが私から遠ざけてくれる。だから、私は、その恐怖を知らないままだ。いや、麻痺してしまったのかもしれない。
「田中様。……あなたはその者が、なんだと、考えておられますか?」
黙っていた私に、ふと甘英さんが尋ねた。
「白いのは、白いのだと思っています」
「……私が思うところですが、こちらは」
一度目を伏せて、そして甘英さんは言葉を区切った。白いのがいると、話しにくいのだろうか。
ちょっと外に行ってて、と言うと、いいよとばかりに頷いて、白いのは外に出た。私があげた壊れた腕時計、その部品をどうやら、並べているらしい。
これにまた、甘英さんが面食らったような、驚きすぎたような様子で、しばらくして気を取り直すように話し始めた。
「あれは……古い、ふるい、太古の力の一つに思われます」
「……はい?」
思わず聞き返した私とは対照的に、荒瀬さんが身を乗り出した。
「そう思う根拠はなんでしょうか」
「蟲、そう呼ばれていたのですね? そして、大きな、常ならざる力を振るったと」
「ええ。正確には、ある家に祀られることで封じられ、対価をもってその家に繁栄をもたらしてきました。そういう存在です」
そうだ。荒瀬さんは、白いのが何なのか、八塚の姫は何なのかを、考えてきた。白いのが外で、私の時計の始末にかかり切りな今は、そういう話をするにちょうどよかったらしい。
甘英さんは静かに続ける。
「宗教、というもの。その中でも神道、というものは、日本においては新しい概念です。神様、という概念は古くからあったでしょうが、それが宗教と言う統一的な形状になったのは、千年ばかりのことにございます。もっと古い興りもある、という声も聴かれますが、人々に道として、そして教えてとして受け入れられたのは、ごく最近のことなのですから、その形を持った存在は調べれば必ず何かの手掛かりをつかむことができます。
今回の件のあれも、その一端にあるものです。非常に邪な方法によるものではありましたが、人が神ではなく、宗教を作ろうとしたからこそ生れ落ちたものとすれば、対処は我々にとって難しくありませんでした。そういうものを産み落とす可能性が生じた折から、対処の法を守るべく、我々の様な存在はひそやかに活動してきたのです。
そうです。
生み出すものがあれば、封じる者も居る。では生み出すものにとって、厄介極まりない情報を持つ者たちを、放置するものが居るでしょうか?
おりませんとも。
おそらくこのたびのアレは、神社などに運び込まれ、そこの神社を守るものを食う存在です。だからこそ、中途半端に崇められ、神まがいになりつつあった。しかし、元はただの道具です。宗教を作ろうとしたものが失敗し、それを拝借した何者かが、手に余って人が寄り付かぬだろうあの神社へ捨て置いた。しかし、神として生み出された側面を忘れられずに、自らに祈ったとは分からなくとも、手を合わせて何かしら願ってくれたご友人方に、執着したのです」
状況がようやくわかって、ああここの話をしたかったのだ、と私は納得した。荒瀬さんはもうわかっていたみたいだけど、皆が神社にお参りしたことで、私が見なかった何かは、力を得てしまった。外に出る口実を、つながりを得てしまった。
それがどんな姿であれ、力だけは強いから、きっと友人たちにも見えたんだ。そして彼らが何とかして御仏にすがろうと、この寺に来た。そこで、私が見なかった何かは、気が付いた。
本堂には、仏が居る。
本堂には、自分に祈ってくれた、彼らがいる。
だからその何かは、懸命に友人たちに接触しようとして、力を使い恐れられた。その瞬間、信仰は、失われた。残されたのは、神ですらなくなった力の亡霊。
「このたびのアレは宗教を作ろうとして、何者かが生み出した。しかし、宗教に必要なのは、人がそれを教えと受け入れ敬うことです。人が集わねば、教えは必ず廃れ、書物として残ろうとも誰の目にも触れぬただの文字の集積物となります。アレは宗教としては成り立てなかった神の一つです。だから、白いの、とおっしゃられたか。あちらが称したように、ちがうもの、と言うわけです」
そして、と、甘英さんが言葉を区切った。
「白いのは、これと根幹から違います。宗教という形を必要としない、神そのもの。それが、あれの正体なのではないか。あなたを守るために取った行動から、私はそう思いました。蟲と称されておられますが、蟲は原始的な生命体です。つまるところ、より深い、命の源流に近いものから起こった、とても強い存在だと私は考えます」
「……はぁ」
大層な話に、私は全くついていけず、反対に荒瀬さんは興奮したようにその話をメモに書き留めている。白いの、といえば、腕時計の部品をちまちま並べていたのだが、不意に私を呼んだ。
「えみ」
「なぁに? ……あれ」
「こわれて、ない」
にっこりと笑った白いのが、手の中に大事そうに入れた腕時計を差し出してくる。それは、先ほど粉々になったはずの私の腕時計で、壊れる前と少しも変わらない、私の腕で動いていたのと同じ姿で、そこにいた。
「直してくれたの?」
「うん。でも、もらって、いい?」
「もちろん。だって、直したのは白いのだもの」
この寺に来てから、白いのはとても、いろいろな感情を示している。不思議なことだな、と思っていると、白いのが言う。
「えみ、おわったから、かえろ」
「あ、でも、友達にも会わないと……」
「かえろう」
駄々をこねるように抱き着いてくる白いのに、困ってしまう。せっかく、由美子の誤解を解決できるのに。もう安全になったのなら、会いに行きたい。
「皆と、ううん、由美子と話したい。それからじゃ、だめ?」
「いないよ」
「……え?」
白いのは静かに、繰り返す。
「あそこには、もう、いないよ」
本堂を指さす白いのに、何も考えられなくなる。空っぽって、どういうこと? 由美子は、あそこに居ないってこと? 最初から、居なかったっていうこと?
甘英さんが、立ち上がる。
「……まさか」
そして部屋を出て、どこかへ向かう。荒瀬さんが立ち上がって、私の背中を軽くたたいてくれた。
「見に行きましょう。……何が起きていたのか、を」
=====
本堂の前は、騒がしくなっていた。戸を開けた先に、人が4人いた。友人たち、でもその中に、由美子が居ない。
呆然とした様子で、甘英さんが膝をついている。他のお坊さんたちも、何が起きたのか分からず、混乱しているようだった。
「……由美子は、何処に」
「最初からいなかった、のか」
「え?」
「……彼も、居ませんね」
見回して、ハッとした。
恵栄さんが、居ない。聞いた限り、彼はこの件を、主体的に担当している様子だった。なのに今ここに居ないというのは、不思議だ。
「彼は、白いのが、とちゅう、と言う表現を使ったときに部屋を出ました。むやみに声に応えるな、そう言いおいて」
「そうでしたけど」
「……来た時に、思ったのです。ほら、見てください」
私たちが居た宿坊の、すぐそば。小さな祠に、小さなお地蔵様。その脇には、小さな木の立て札がある。見覚えのある文字に、唇が震えた。
「……恵栄、和尚」
「すでに祀られた、古い高僧だったのでしょう。主になって動いてくださったのは、今の彼らには手に余ると判断したからでしょう。白いのの言葉に、自分が為すべきことを、為しに行ったのでしょう」
「為すべきこと?」
荒瀬さんが、静かに答える。
「言われたでしょう? 人に祀られた人は、神となる。神は、祈りの形を、表している」
白いのが私の、手を握った。とたん、脳裏に焼き付くように映像が流れる。それは、私の記憶したものではない。
神社から寺まで来た皆は、歯を食いしばるように祈っていた。助けてください、助けてください、お願いします。
その祈りは、この小さな祠にも向けられた。この寺に居るすべてに、皆は願った。助けてください。
どうか、助けて、ください。
助けて。
助けて。
助けて。
私は、もう、手遅れだから。
映像が、切り替わる。神社だ、南光神社という鳥居。そこに、黄色い立ち入り禁止のテープが張り巡らされ、青い制服の警官が動き回っていて、開けた神社に人々が手を合わせている。開かれた扉の中に、足が見えた。二本の、白い足。その、足の裏。
それだけなのに、直感した。由美子だ。あれは、由美子だ。
目を開いた私に、白いのが言う。
「たましいを、もらったなら、がんばらないと、ね」
由美子は。
ああ、そうか、由美子は。
私のメッセージを見ることなく、死んだのだ。
死んでしまって、けれどそこにこびりついた祈りの声が、助けを求める声が、皆と共にここに届いた。この小さな、祠の中へ。それは、他の皆の声よりも、もっと強かった。
魂と言う、人がもっとも崇め、力として認識しやすい形となっていた。
「そっか……」
白いのも、同じだ。
20歳で死んでいった、八塚の姫たち。彼女らの魂を貰って、白いのはただひたすら、八塚の家の中に封じられた。本当なら、そういうものでは、なかったのかもしれないのに。
「……帰ろうか」
私が言うと、荒瀬さんが頷いた。甘英さんに声をかけると、しみじみと頷いて、早く帰りなさいと言ってくれた。
「長くいない方が良いです。……美味しいものを食べたあと、何を食べても味がしないのと今のここは、似ています」
そう言って、何もかも分かったかのように、あの宿坊のほうへ深く深く、頭を下げた。私と、白いのと、ここを結び付けてくださった。そう呟いて、両手を合わせていた。
私と荒瀬さん。そして白いのが寺の外に出てすぐ、お父さんがいた。帰ったんじゃないのか、と驚いて駆け寄ると、気になって戻ってきたと言われた。
「なんだか、すぐに帰らなくても、いいような気がしてな」
「……うん、終わったよ」
「そうか」
お父さんはそれきり、何も聞かなかった。早く終わってよかった、と、車に乗せてくれた。
白いのは、私の隣に乗った。それを見て、ああもう張り切らなくて良くなったんだ、と、ほっとした。私の腕時計はいつのまにか、白いのの右腕に収まっている。
「わたしは、ずっと、えみの、むし」
「うん」
そんなことを言う白いのに、なんだか安心する。
本人、本虫? が言うのだから、間違いじゃないだろう。
白いのは、神様ではない。祈りの形に左右され、己を失い、盲目となり果てて人の願いをかなえようとする、装置などではない。
これからも、この先も、分からないままでいい。あれ、これも私の願いなのだろうか。白いのは、それを叶えようとしてしまっているのだろうか。
「白いのは、白いのが思う通りで居てよ」
「……おもう?」
「私の蟲、じゃなくても、イイってこと」
「……やだ」
ひしーっと、全身でしがみついてくるので、そこはどうやら譲れないらしい。
「うーん、ヤなら、ヤでいいよ」
「じゃあ、これからも、えみの、むし」
「うん」
次の日。
由美子の母から、連絡が我が家に入った。由美子の死亡と、葬儀を伝える電話だった。電話口の由美子の母親は、泣いていた。母さんはそう言って、私の喪服を出しながら、ふと独り言のように言う。
「由美子ちゃんねぇ、小さい時にお父さんが亡くなってるのよ」
「……えっ?」
「あんたには、言わなかったかもしれんねぇ。今は、もう、奥さん再婚されてるし……」
私は思わず、白いのを見た。白いのはふんわりと笑うと、
「ひとも、かみの、うちになる。そせん、なら、なおさら」
そんなことを、楽し気に語ってくれた。
どうも今回の一件は、白いのをずいぶん成長させてくれたらしい。主に、言語面で。荒木教授は目ざとくそれに気が付いて、山積みの折り菓子をもって我が家にやってくる。私のLINEのメッセージに、もう二度と由美子の既読マークはつかないだろう。あの事件にかかわった同級生らとは、きっと疎遠になるだろう。そして彼らは私のことを、口に出すのかもしれないし、出さないのかもしれない。
「不思議と、悲しそうじゃないのね」
母さんに言われて、うん、と頷き返す。
「うん、なんだか、悲しくは、ないんだよね。今は、ね」
怪異は、そういうものだ。
不思議と、奇妙さと、未解決と、疑問ばかりを残して、そのほかの感情に目を向けるのを、遅くする。だってわからないことばかりだ、どうして由美子じゃないといけなかったのか、白いのを彼らは何だと思ったのか、助かったことを彼らはどう思うのか、そもそも神や仏に影響を及ぼすためのものってなんなのか。
分からない。でもそれは、学んだことで解決ができる類ではないし、私が答えを出すような問題でもない。
きっと時間が経つと、不意に悲しくなる。
白いのと出会ったばかりの時も、そうだった。疑問と疑念と恐怖が氷解して、ようやく、悲しみや怒りにたどり着ける。人間の防衛本能が、緩むことを許してくれる。
「えみ」
見慣れた複眼に、私の顔がそれぞれ映っている。少しだけ笑った、この世で一番見慣れた顔が、こちらを見つめ返している。
私の死に顔はこれより、もう少し、神々しいとイイな。
まだ見る気配もない子孫を考えて、そんなことをふと考えた。
おわり


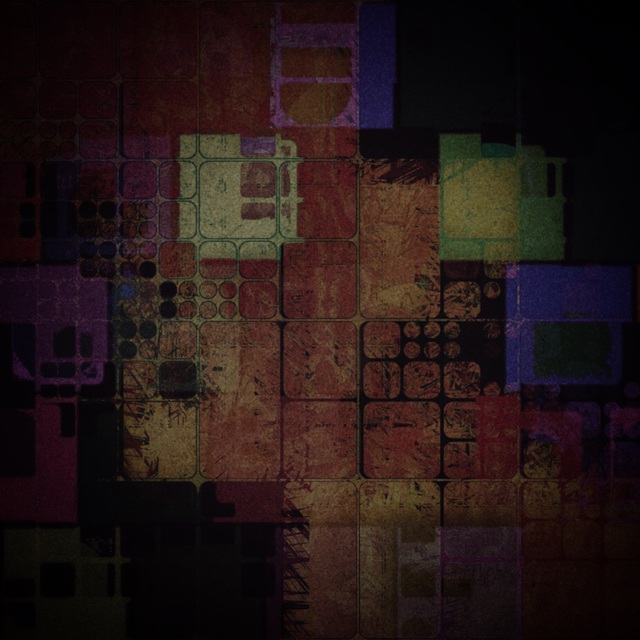
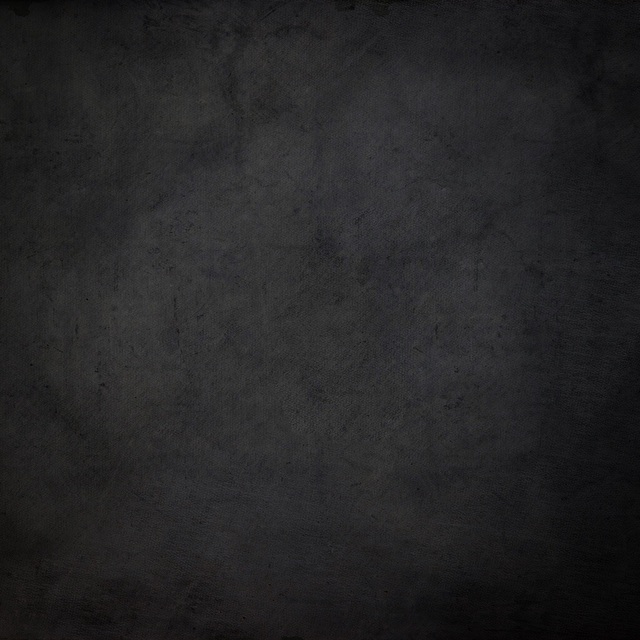
作者六角
読了ありがとうございます。
神と仏の生き死にを司るのは、人間なのではないか、という話。人間が書いている時点で、お察しではございますがね。
自分が書きたいところだけ書いたら話になってないという典型例で非常に申し訳ない……です。うーん。精進。
コメントもたくさん毎度、ありがとうございます。また、機会がございましたら、お行き会い致しましょう。