高校生最後の年。写真部の副部長となった私に、部活の内容以外の難題が降りかかっていた。
田中恵美という平凡な名前も、最近はいっそ平凡過ぎて非凡に思えてきた、今日この頃だ。
「あー、この人か、なるほどぉ……」
私の持ってきた写真をしげしげと眺めながら、そう言ったのは友人の長瀬香織。可愛らしいモンブランカラーのショートカットに、目鼻立ちをはっきりさせるすっぴん風化粧もばっちりな、まさに現代の女子高校生。けれど彼女は写真への情熱は本物で、傍らにはお年玉を小学生の時から去年まで、貯めに貯めて買ったという、一眼レフが鎮座している。写真を専門とする美術大学への進学希望を裏付ける、展覧会への入賞成績も持つ腕利きである。
写真部が放課後に活動をしているのは、学校に二か所ある理科室の一つだ。何故理科室かというと、ネット環境があって、パソコンが置けて、薄暗い部屋と薬品棚が確保できるからだ。
我が校の写真部は数年前のちょっとストイックな先輩たちによって、様々な写真を撮影し現像するノウハウが蓄積されている。いわゆる、液体の薬品に漬けて行う現像から、スマホの写真のプリントアウトまで対応。放課後はもっぱら、外に出て写真撮影をしたり、学校内で写真撮影をしていたりと、個々人の活動が主になる。
今は私と香織の二人と、倉庫と言う名の現像部屋で、薬品による現像に壮絶に集中している同級生の男子が一人、という三人きりだ。外には『写真加工中!ノックしてください!』という何時もの写真部プレートがかかっているので、滅多な事が無ければ中に入る人はいない。
……いや、正確には、三人と一つ、だろうか。
昆虫の様な、真っ黒な複眼。白の着流し、白の髪に、白い肌。夏休みの一件以来、何やらだいぶしっかりとしてきた白いのだけど、私だけには相変わらずだ。学校に居る間はいい子にするものだと刷り込まれているので、私の横で両腕を机の上に乗せ、その上にさらに顔を乗っけて、写真を不思議そうに眺めている。
「ちょっと特別感あるし、ドキッとしちゃう感じね」
「そうなの?」
「うんうん。それにさー、なんていうか、特別感のある要素てんこ盛りじゃない? 今の年齢なら惹かれちゃう子多そう」
なんだか大人びたことを言う香織に、そういうものだろうか、と私は首を傾げた。
「それで、この人がどうしたの?」
「うん」
写真に写るのは、痛んだ赤い髪を後ろに束ね、書物に埋まるようにしてさらに床に散らばる書類を集める男性。さらりと着こなした着流し姿の、荒瀬邦彦さんである。
私と秘密を共有し、妹さんの死の理由を追い求める、民俗学の研究者であり、ホストをしてお金を稼いでいる確かに『特別感のある要素てんこ盛り』な男性だ。そんな彼の写真を香織に見せたのは、私が副部長としての役割以上に悩んでいることを、相談するためだった。
「荒瀬さんって言うんだけどね、私のお母さんの親戚で、今私が住んでいる家を世話してくれたの」
「じゃあ家族ぐるみのお付き合いって感じ?」
「うん。電車で見かけたら、お互いに声かけるぐらいには仲いいよ。家もほぼ隣のようなものだし、お父さんもお母さんも働きに出ちゃって帰りが遅かったら、ご飯食べにおいでって言ってくれるし」
「そりゃ仲いいね。で?」
香織に相談したかったことを、私は話すことにした。
「この前の日曜日なんだけど……」
こういうことだった。
その日、民俗学の権威である(らしい)荒木教授と荒瀬さんに誘われて、私は近隣の古本市場に出かけることになった。こういうところで、面白い史料が手に入ることもあるらしくって、荒木教授は嬉しそうだった。行ってみて驚いたのだけど、荒木教授へ声をかけるお店の人のまあ多いこと多いこと。なんでも一度に買う量が、すごいらしい。荷物持ちに駆り出された学生さんたちが、怯えた目をしていた。いくら買う気なんだ。
初めて来たけれど、いろいろな本がある。資料や史料を探しているらしい人や、本がほしくて来ている人、絵本を探す親子連れまでいる。置かれたものは本当にいろいろな種類があって、私も見覚えがある最近の古本や漫画から、極太の大辞典に、糸で綴じられた正しく和書というやつから、インテリアに出来そうな洋書まである。雑貨物を取り扱っているエリアに出たので、そこで時間をつぶしたり、自然派なカフェの出店店舗でお茶したり、写真を撮ったりして集合場所に行った。
荒木教授も収穫があったらしくて、院生さん達が呻きながら本を車に運んでいる。ホクホク顔の教授とは対照的な光景に、ちょっと引いた。
と、いうことは、完全な前置きだ。
これがきっかけ、ではある。
翌日、登校した私に降りかかったことが、相談したい問題だ。
「どう関係するの?」
不思議そうな顔をする香織に、言う。
「古本市ね、定期的に開かれていて、月に一回は必ずあるんだって」
「うん」
「でね、この知り合いの教授と、荒瀬さんは、ほぼ毎回参加するんだって」
それがある意味、一番関係している。
月曜日。いつも通りに登校した私は、いつも通りに先生に貫通されながら体育座りをやめない白いのと並んで、いつものように授業を受けた。お昼は母さんのお弁当を食べて、トイレに寄った。お昼の時間は女子が一番たむろしててトイレが混むから、私はいつも人があまり来ない3階のトイレを使っている。今日も人気はなく、用を済ませて外に出たところで、
「田中さん」
呼び止められた。振り返ると、見覚えのある女子が立っている。
「えっと……テニス部の、城田さん、だっけ?」
部長会議に代理で出席したとき、女子テニス部の部長として来ていたので、名前だけは憶えていた。制服についている名札もその通りだったから、続けて尋ねた。
「何か、用事?」
「聞きたいことがあるんだけど」
「うん」
「あの人と、どういう関係?」
すごい、漫画みたい。と思った私だが、それどころじゃなかった。白いのが、ぎゅーんと首を伸ばして、彼女の顔を覗き込んでいる。完全に人間としての関節可動域を超えた伸び方で、ちょっと怖い。
「あの人、って、誰のこと?」
「昨日、古本市、来てたよね」
「ええ、ああ、うん。誘われて……」
その瞬間、城田さんの目がつり上がった。いや、もう、彼女なかなかの美人だから、怖いなんてものじゃなかった。もっと首を伸ばし始めた白いのとの恐怖の共演に、もうパニックになりそうだった。
だからなのかふと私は、彼女があの人と聞く人に、思い至った。
「あの人って、もしかして、荒瀬さん? 真っ赤な髪の、男の人?」
きゅーっ、と、城田さんの目が細くなる。
「そうよ……知り合いなの?」
「う、うん。お母さんの親戚」
「……そう」
どうやら、怒りは収まったらしい。彼女は私を急に、ふん、と可哀想なものを見る目で笑い、満足したかのように去っていった。御蔭で白いのが元の首の長さに戻ってくれたので、私としては彼女がなんと思おうが、知ったこっちゃない。
「ねぇ」
「なあに?」
「首、伸ばすの、禁止。怖すぎ」
「うん」
いやそういうことを相談するわけはないので、白いのの様子は香織に話していないのだけど、話してみてよくわかる。
城田さん、怖すぎる。
「えー、何それ。怖すぎない?」
香織は身をすくめるようにして、嫌そうな顔をした。
「でね、荒瀬さんに城田さんって知ってる? 、って、彼女の特徴と一緒に伝えたんだけど、知らないって」
「マジか。えっ、すごい怖い憶測言っていい?」
「待って。あのね、つまり、城田さんもその古本市に来てて、ずーっと、荒瀬さんのこと追いかけてたんじゃないかなーって……声もかけずに」
「イヤー、同じこと考えたけど、同じこと考えたけどさぁ!」
怖すぎる。という私たち二人の意見の一致に、ふと第三者の声が入ってきた。
「マジ、それ?」
暗室での作業を終えた、萩野裕也だった。私と、香織と、もう一人。今、この理科室に残っていた部員である。三年間同じ部活だし、同じクラスなので、最悪話を聞かれてもいいと思ったのだ。
「何処から聞いてた?」
「お昼の廊下で声かけられたところから。えー、マジか、じゃああの話の人って……」
「あの話?」
萩野は少し言いにくそうに、言葉を選んで話し始めた。
「城田さんって、女子テニスの部長だろ? 結構さ、男子の間じゃ可愛いって言われてて、人気もあって告白する奴いるんだよ」
「待って、ちょっと想像ついたかも」
香織が言うと、萩野がその想像を肯定するように、頷いた。
「彼氏がいるって、みんなずっと断られてたんだよ。でも、どこでどう付き合ってるとか、誰も知らなくってさ。女子テニス部の連中の間だと、嘘なんじゃないかってもっぱらの噂だったぐらいなんだ」
「……つまり」
「今の話聞いて、合点がいったわ。彼氏って、もしかして、その人……」
「萩野っちちょっとお口チャックして、怖すぎるから」
香織が口の前で、人差し指を交差させてバッテンを作る。しかし、私の話は、まだ終わっていない。
「続きもあるんだよね」
「うそでしょ……」
「今の、月曜日の話なんだけどね」
今日は、金曜日。部活はその間に毎日あったことに、香織は真顔になる。
「まって、今の話、続くの?」
「続くの」
「萩野、一緒に聞いて、お願い怖すぎる」
香織に頼られては男が廃るというやつなのか、萩野も座った。そして荒瀬さんの写真をのぞき込んで、イイ構図だ、とつぶやく。そこか。
「でまあ、怖かったんだけど……何もやましいことはないんだよね、私」
「そうよね、聞いている限りだと、面倒見のいいお兄さんって感じ」
「うん。でね、さっき言ったじゃん、電車で会ったら一緒に帰るくらいには仲良しだって。この前さ、雨で電車遅れてたじゃん、駅前の喫茶店入ってたらちょうど荒瀬さんも来てさ、一緒にお茶しながら時間まで古本市のこととかいろいろ話してたの」
ふと視線に気が付いて顔を上げたら、そこに城田さんが居た。
私と荒瀬さんが見える席に座って、じーっと、こちらを見つめていた。私が視線に気が付いたことなんて、気にしていない。というより、気が付いていない。
「どうしました?」
荒瀬さんに尋ねられたので、視線をそらして小さな声で、
「こっちずっと見てる人がいるんです」
と思わず言ってしまった。荒瀬さんは不思議そうな顔をして、私が見ていた方向を、振り返る。城田さんは、まだそこに居る。満面の笑みで、こちらを見ている。
どこか辟易としたような顔をして、荒瀬さんが頷いた。
「あれですか」
「あれです」
時計を見る。電車は、遅れからして、まだ来ない。
「タクシー拾います、帰りましょう」
「えっ」
「ああいう手合いは、関わらないに限りますから」
肩をすくめた荒瀬さんに言われるがまま、一緒に店を出た。制服姿の私と荒瀬さんの組み合わせに、一瞬もの言いたげにした運転手さんだったが、私がとっさにお兄ちゃんありがと助かったなんて口走った御蔭で、疑いの眼差しを消した。むろん、家に帰ってから、荒瀬さんにはお兄ちゃんと呼んだことを謝ったけれど、別にいいですよと実にあっさり許された。
「と、いう、一連のことがありまして」
「……えっ、ちょ、ええ」
「その件についても、今日のお昼に学校で堂々問い詰められまして」
「もしかして昼のあのざわつき感って、恵美が理由?」
状況が状況だったので、流石にクラスメイトも噂しにくかったのだろう。城田さんが突如お昼を食べていた私のところに来て、デートの邪魔しないでよ! 、と叫んで去っていったのだ。一緒に食べていた友人に、どういうこと、と聞かれたけれど、分からないとしか言いようがなかった。
萩野も香織も、その時はちょうどクラスに居なかったから、知らないと思う。
「つまりさ、城田さんの中では、その見つめているって行為自体がもはや、デートってこと……?」
「たぶん」
「……ど、どうしようもないというか、どうにもできないというか……」
戸惑った声を上げる香織に、その通りだと頷いた。
「怖くない?」
「怖いに決まってるでしょ!! 落ち着いてるあんたが不思議よ、先生とかも巻き込むべきじゃない、それ?」
うがーっと吠えた彼女には申し訳ないが、ようやく怖くなったので相談したかったのだ。荒瀬さん自身の危機感は微妙に薄くて、『行動力はほぼ無い様子ですし、心配していません』とクールな返しを頂いた。流石現役ホスト、しばらく駅に行くことは避けるというので、その点はちょっと安心した。
「それで田中さんどうするの? 変に嫌がらせ受けるかもよ」
「それならそれで好都合。向こうの言いがかりって証明できるし、荒瀬さんこの外見だけどちゃんとした文系の研究者だから、身元もはっきりしているし」
「前向きだなぁ」
感心した様子の萩野は、うんうん、と頷いてから、少し不思議そうに言う。
「……あれ」
「どしたの」
「ちょっと待ってて」
すると彼は鞄を持ってきて、中から一枚の紙を取り出した。いつどこでどこの部活の大会があるのか、そういうことが纏められた、新聞部が月一で発行している部活月報というやつだ。すーっと指で欄をなぞり、あった、と呟く。
「なあ、これ見て」
「……あれ」
「ちょっと、女子テニス、その日曜日って大会出てるじゃない。それに城田さん、シングルスで出場?」
大会の時間は、古本市があった時間帯と丸かぶりだ。流石に三年最後の大会、しかもシングルスで出場選手なのに、辞退するだろうか。思わず、私たち三人の間に、沈黙が訪れた。
と、ドアがノックされる音。ハッとして、ドアを開ける。
「先輩、ただいまですー」
1年生の子が二人、並んで立っていた。おかえりー、と声をかけて、中に入れる。そういえば、と思い至って、二人に尋ねた。
「ねぇねぇ、運動部の写真、よく撮ってるよね」
「そうですよ。日曜日の女子テニスの大会も、取りに行ったんですよ」
「三年の城田さんって人、出てた?」
ああ、と二人が顔を見合わせて頷く。首にかけていたデジタルカメラを操作して、見せてくれた。
「この人ですよね、部長さん! 凄かったんですよ、大接戦で」
日にち、時間、ともに古本市が開催されていた時刻だ。綺麗に撮影された過去の記録の中で、彼女は真剣な眼差しでボールを追いかけている。私たち三人が顔を見合わせると、後輩たちは不思議そうに首を傾げた。
「どうしたんですか、先輩」
「あー、ううん。今ね、人の動きについて話してたから」
「そうなんですか」
純粋に信じ切ったらしい後輩たちに申し訳なくなりながら、私は城田さんに声をかけられた時のことを思い出していた。
例えば、だ。例えば、城田さんが霊的な何かだったとしよう。とすると、白いのがただ見つめていただけ、というのが引っかかる。基本的に白いのは、霊的な存在を前にした時に、私がそうだと分かって危険が無ければ見せてくれる。危険度が高ければ、私にまとわりつく。それはあの、夏休みの一件から何も変わってはいない。だからこの線は違う、と思うのだが、白いのはなぜ顔を覗いていたのだろう。
後輩たちが立ち去ったところで、香織が言った。
「ね、早めに帰りなよ。これで土日になるしさ」
「……そうだね、そうする」
そのありがたい助言に従って、私は帰宅を決めた。
separator
駅に城田さんの姿も、荒瀬さんの姿もない。そのまま無事家に帰りつけたので、白いのに尋ねる。
「月曜日に、私に声かけてきた女の子覚えてる?」
「うん。かわいそう」
「可哀想?」
珍しい表現だな、と、思った。白いのが口にしたことのない種類だから、少し面白い、と感じてしまったのを慌てて振り払う。
「なんで可哀想なの?」
「たいへんだから」
「大変?」
ますます謎が深まってきた。白いのが何かしら、城田さんから感じ取っていたことは確かなようだけど、このままではちょっと難しすぎる。ここはひとつ、荒瀬さんにも相談すべきだろう。
善は急げだ、私は早速隣の家へと、裏庭の通り道を使って向かった。今日はいい天気のせいか、庭で荒木教授が古い本を広げていた。
「こんにちはー」
「おや、いらっしゃい。荒瀬君なら今来るよ」
私が自発的に来るときは、大抵荒瀬さんに用事があるときなので、教授にはお見通しだったらしい。ちょっともしない間に、荒瀬さんが本を抱えて現れた。
「珍しいですね、どうしました?」
「こんにちは。この前の、ほら、喫茶店でこちらを見ていた女の子のことなんですけれど……」
そこで私は、香織に聞かせた内容と同じことを、荒瀬さんにも報告した。話しているうちに、荒瀬さんの顔が険しくなっていく。最終的に、大きなため息をつかれてしまった。
「なるほど、そんなことに」
「え?」
「貴方の言う、城田さんですか? こちらをニコニコと見つめていた、女の子。彼女の真向かいに、もう一人座っていたのに、気が付かなかったんですね」
私がびっくりして目を見開くと、
「しーぃ」
と白いのが、荒瀬さんの話を遮りだした。どうやら、その、荒瀬さんが見ていた『もう一人』のことを、私に聞かせたくないらしい。
「聞いちゃダメなの?」
「うん」
ぶんぶんと首を縦に振る白いのに、荒瀬さんが困ったような顔をする。でも私としては、荒瀬さんの話を聞きたい。
「聞くと、私に何か起きるの?」
「かわいそう」
「私が?」
「ううん、あのこ、かわいそう、だから、だめ」
あの子、というのは、城田さんのこと。私が荒瀬さんの話を聞くと、城田さんが可哀想になる。いまいち話がつかめない私とは対照的に、荒瀬さんは、ああなるほどという顔をしていた。
私は当事者ではないのだろうか。いや、荒瀬さんこそ当事者か、私は巻き込まれたようなものだ。
「城田さん、私に何かしてくるかな」
「それ、しだい」
白いのが、すっ、と荒瀬さんを指さす。それって言っちゃダメでしょ、と指を下させると、荒瀬さんが困ったように笑った。
「やはり、そうなりますか」
「分かったんですか?」
「2、3日で済むと思います。月曜日は、元気に学校に行ってください」
荒瀬さんが言うなら、そうなるのだろう。今のところ、この人がこうした不思議な事象において、間違ったり見当はずれなことをしたためしがない。ちょっと出てきます、と言いおいて、荒瀬さんが出かけてしまったので、私は荒木教授の作業を手伝うことにした。本当なら荒瀬さんがやるはずの作業を、私が中断させてしまったからだ。
「あー、あったあった」
「なんですか?」
「ほら、見てごらん」
教授が開いて見せたのは、古い書物だった。黄色い表紙で、素材はほぼ全て和紙。糸でくくるように和綴じになっていて、表紙には植物、という文字が見て取れる。
「植物図鑑?」
「うん、江戸時代のものでね。ほら、これこれ」
示されたのは、一つの植物。
「ハコベ、って言うんだ。聞いたことあるかい、七草のひとつなんだが」
「あ、お祖母ちゃんと摘みに行ったことがあります」
「うん。これがねぇ、ふと頭をよぎって……なんでかなぁ」
不思議そうな顔をする荒木教授に、私もなんでですかねぇ、と答えた。でも、その古めかしい和紙の中の、丁寧に描かれたハコベは、妙に私の頭に残った。
結局のところ、その後城田さんが私に絡んでくることは無く、話はうやむやになってしまった。白いのにいまだに、どういうことだったか荒瀬さんに聞いていいかと尋ねるのだけど、まだダメ、と止められてしまうので話は聞かないことにしている。
聞いてしまえば、何かきっと、よくないものが繋がってしまう。
そんな想像が、ふと頭をよぎったから。
nextpage
毎月一度は、荒瀬邦彦は執事する荒木に付き添って、古本市へ顔を出す。古書店の店主から、古書店へと流通する前の段階を担うセドリの出入りも大きい、なかなか大きな古本市だ。
大量に買い付け、そこからあの本屋は良かったと噂を広めやすい荒木には、どこの店主もいそいそと売り込みに来る。それに付き添いながら、荒瀬邦彦は背後のそれをずっと、警戒していた。
覚えている限り、最も古い記憶は、1年前の3月の事。まだ雪も残る時期で、このいつもの広場ではなく、町の体育館を借りて行われた折のことだ。
すれ違ったのは、一瞬だった。目が合ったのも、ほんの一瞬。真っ赤に染めた髪と、着流し姿の荒瀬邦彦は、会場でも割と目立つ。彼自身、水商売で稼げるくらいには、整った顔立ちをしている。そうだったからか、それとももっと根本的な理由なのか。典型的な文系、そう呼ぶのがふさわしい外見の女と、確かに荒瀬邦彦はすれ違った。
そしてそれ以来、会場に来るたびに、彼女は後ろからついてくる。
下手な尾行だ、荒瀬邦彦はそう思う。時代劇じゃあるまいし、荒瀬邦彦は呆れている。
彼女は、一度たりとも、話しかけてこなかった。彼女は、一度たりとも、接触してこなかった。ただ、いつも、荒瀬邦彦が荒木に付き添ってやってくると、ひたすら後ろからついてくる。
それを荒瀬邦彦は、健気などと呼ばない。ストーカーだ、と、思っている。
しかしそんな彼女に変化が起きた。理由は、明白だった。何もしてこないものだから、甘く見ていた。
幾多の災難により、ある一族の忌々しい儀式の全ての理由を、その身に宿した少女。田中恵美を、折角だからと荒木が誘ったことが原因だった。白いの、と彼女が呼ぶ、八塚の蟲と呼ばれたそれは、夏の事件以来よりはっきりとした自我を宿し、言葉遣いも幾分か巧みになっている。その複眼で荒瀬邦彦を眺めて、そして静かに、ふつりと笑った。
妹を殺したのか。
そう聞こうと思ったことは、何度もある。しかし、そうは、聞けなかった。何を言うのかが、恐ろしかったから。
田中恵美とは、長い時間行動を共にしたわけではない。しかし一緒にここへ来たし、帰るときは待ち合わせもして、バザーで買ったというクッキーまで貰った。ある意味、運命共同体のような間柄であるし、彼女は年の離れた兄のように、または秘密の共有者として、猫のように荒瀬邦彦と会話をする。
背後の女が、居なくなった気配があった。人ごみの中、顔を覆いながら駆けていく姿があって、荒瀬邦彦は目を細めた。奇妙だったのは、そんな光景に目を向ける人も多かったのに、田中恵美は何も気が付かなかったのだ。白いのは、まだ、笑っている。
背後の女に再び出会ったのは、駅前の喫茶店だった。電車を待つという田中恵美に遭遇し、なんならと喫茶店に入った。白いのが最近覚えたことを報告してくる彼女だが、不意にその顔がこわばった。何かと思えば、こちらを見ている人がいる、という。振り返れば、会う視線。おかしい、と思った。いっそ背後の女なら、おかしくはなかった。
こちらを満面の笑みで見る女子生徒は、荒瀬邦彦の知らない少女だった。
面倒な気配に、その場を立ち去ることを選んで、荒瀬邦彦は気が付いた。その、満面の笑みでこちらを見ていた少女は、一人でそこに居る訳ではなかった。彼女の、前。正確には、荒瀬邦彦と背中合わせにある席に、その女は座っていた。
文系女子、そう呼ぶのがふさわしい、おかっぱに黒縁メガネの真面目そうな、あの女。
会場に来るたびに、荒瀬邦彦をずっと追ってきた、あの女。
彼女はこちらを、見ていなかった。いつもと同じように、荒瀬邦彦の後ろについてきたんだ。では、あの、満面の笑みの少女は。
その時荒瀬邦彦は、気が付いた。田中恵美は、気が付いていない。いや、偶然かもしれない。しかし荒瀬邦彦は、そうではないと、確信した。白いのが、見つめていたのだ。背後の女を、その黒い複眼で、何一つ動かぬ無表情で、彼女を見つめていた。
そして今日。荒瀬邦彦は、田中恵美から相談を受けた。城田さん、という少女の特徴を改めて聞いて、それが満面の笑みで見ていた少女だと理解して、荒瀬邦彦は決着をつける必要があると理解した。背後の女、彼女のことを田中恵美が知れば城田という少女は可哀想、という白いのの、その言葉を確かめるために。
土曜日。荒瀬邦彦はパソコンで、田中恵美が通う高校の名前を片っ端から調べ、最近の新聞記事だけをまとめて読み漁り、とある写真を見つけ出した。そして田中恵美にあることの確認をとり、なるほどとうなずいた。
日曜日。古本市は開かれないが、古本を持ち寄る市民から古本を受け入れるために、会場の設営者たちがいる。その時刻に、荒瀬邦彦は古本市の会場となる場所へ向かった。
果たして、彼女は、現れた。おかっぱ頭の、黒縁メガネの、文学が良く似合いそうな女だった。
こちらを見て、信じられないと口を覆い、そして駆け寄ってきた。
嬉しそうに、満面の笑みで。
「あの、わたし、城田っていいます」
彼女はそう、己を名乗った。
「覚えてますよね? 喫茶店で、目が合いましたもの!」
「覚えていますよ」
荒瀬邦彦は、微笑んだ。
「城田さんの真向かいに座っていらっしゃった。私の、背後にいらっしゃった。あなたと、私は、今初めて、こうして目を見て話しています」
女の顔が、ゆがんだ。
「わたしは、城田です。わたしは、城田です」
「いいえ、違います。あなたは、城田さんでは、ありません。あの日、私の目を見て、笑みを浮かべていた少女ではありません。あなたはいつも、会場で、ここで、私のあとをずっとついてきた、どうしようもないただのストーカーです」
女に対して、実に乱暴な口をきいていると、荒瀬邦彦は自覚していた。しかしそれほど言葉が乱暴になったのは、白いのが田中恵美に彼女のことを知らせようとしないからだった。決まっている、大切にするべき生徒を脅して田中恵美へと声をかけ、自分が動くことを見越せるほどの頭があるくせに、最も単純な方法をとることが出来ない目の前の女が、許せなかった。
城田と言う少女は、部活の部長をしているという。
そして目の前の女は、新聞の情報と田中恵美の情報から考えるに、その部費の割り振りにおいて一枚噛んでいる、生徒会顧問の一人のはずである。
「……部費を盾に、よくもまぁ、生徒を脅せましたね」
荒瀬邦彦がそういうと、女は数歩、勢いよく後ずさった。
「そんなことをする必要はなかった。なんなりと、貴方は私に声をかければよかった」
「っ、あなたにっ、わたしなんかがっ、好かれるわけがないっ!!」
女の絶叫に、荒瀬邦彦は動じなかった。女の悲鳴とヒステリックな衝動には、慣れていた。
「こんな地味で、不細工で、可愛くもなくて、ああそうよストーカーみたいな真似しかできない子なんて、好かれるわけがない! 声なんて、かけられない! ふざけないで!!」
「なんだ、分かっているじゃないですか」
荒瀬邦彦は、静かに笑った。
「後ろをついて回るしか能がない、鳥の雛のような女なんて、遊びがいも食いでもない。あなたのことなど、全く好みではございませんよ」
女はそれを聞いて、笑った。ああなるほどなぁ、と荒瀬邦彦は思う。
たまにいるのだ、どんなに言葉を尽くしても、どんなに言い方を工夫しても、包丁を腹に突き立てられたままでも、『貴方のためなの』と笑える、一番面倒な人種。
「そうよね、そうよね! 好きになんて、ならないわよね! だからね、気にしないでね、あなたをね、見ているだけで、ついていくだけで!」
「そこまでは妥協しますので、一つだけ。……田中恵美と、城田さんへかけていらっしゃる呪い、止めていただいてよろしいでしょうか?」
女が、ぴたりと、動きを止めた。人気のないそこで、彼女は生気のない顔で、真っ黒な目を大きくおおきく、見開いた。
「どぉおぉる、してぇええ……?」
「……いえ、正確には、城田さんを脅してかけさせている呪い、やめさせてあげてくださいませんかね?」
「いぃいいぃ、うぃいいやああああっっ!!!!」
悲鳴だった。しかし不思議と、誰も来ない。いや、むしろ、音がしない。
異界にいる。
そう理解したとき荒瀬邦彦は、気が付いた。女の背後に、立っている。黒い複眼、赤い舌、真っ白な身体に白の着流し。無表情の”八塚の蟲”が、女をじっと見つめていた。捧げられた少女を全てから守る”八塚の蟲”。その力は、今、田中恵美と言う一人きりの為に捧げられている。八塚のくびきから解き放たれ、それは今や、田中恵美のためだけに蠢くものになった。だがそれは、在り方だけだ。
為すことは、変わりがない。
「だって、だってだって!!」
「自分で呪いをかける根性もないくせ、まぁなんと卑怯者なことか……。今の状況ですとね、田中恵美から呪いを返しても、傷つくのは城田さんなのですよ。そうでしょう?」
荒瀬邦彦は、”八塚の蟲”に問いかけた。女が、振り返る。
「そうなの、だから、かわいそう」
”八塚の蟲”は、そう答えた。女の目が、見開かれる。絶叫を上げる女に、荒瀬邦彦は歩み寄った。そして彼女の腰を勢いよく抱き寄せると、その耳に囁きかける。
「呪いをかけされるため、あなたはどなたを、脅しましたか?」
絶叫が、歓喜の悲鳴に変わった。つくづく呆れた女だ、荒瀬邦彦は、そう思った。もう一度丁寧に、今度は吐息を吹き込むように囁くと、彼女は答える。
「し、しし、しろた、このえ、さんですっうぅう」
「脅したのは?」
「わた、わた、わたし、わたしです。清水春江ですっ!」
そうですか。荒瀬邦彦は、彼女から手を離した。座り込む彼女のすぐ後ろに、”八塚の蟲”が立っている。
「しみず、はるえ」
蜜が滴るような声でつぶやき、”八塚の蟲”は静かに笑った。荒瀬邦彦が立ち去る背後で、その声が嬉しそうに言う。
「よかった」
そして荒瀬邦彦は、荒木と暮らす我が家へ帰る。”白いの”も、田中恵美のもとへ帰ったのだろう。ふと振り返ったが、不思議とそこに、あの女の姿はない。
しばし考えて、ああ、と思いつく。
「白いの、どうでも良くなって、戻すのを忘れましたね」
田中恵美の安全が守られたのなら、あれにとってはそれで良いのだ。城田という少女も、脅す相手が居なくなったので、おそらく呪うことはやめるだろう。いや、呪うことをもしやめられなかったとしても、その時は『可哀想』と言って、白いのが何かしらするに違いない。そこまでの世話をする義理は、残念ながら荒瀬邦彦には存在しないのだから。
「あ、おかえりなさーい」
荒木の作業を手伝っていたのか、玄関に現れた田中恵美の背後には、いつものように白いのがまとわりついている。それはふわりと笑みを浮かべると、覚えたての言葉を言う幼子の様な朗らかさで、
「おかーえり」
そう言ったのであった。
おわり
wallpaper:205


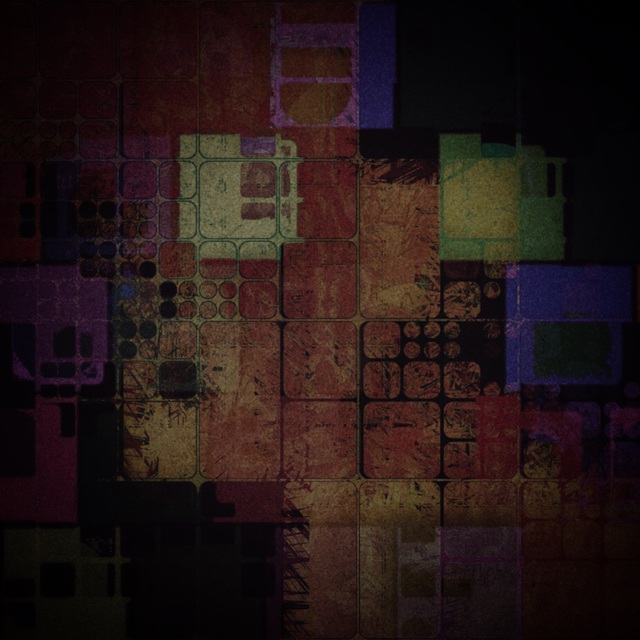
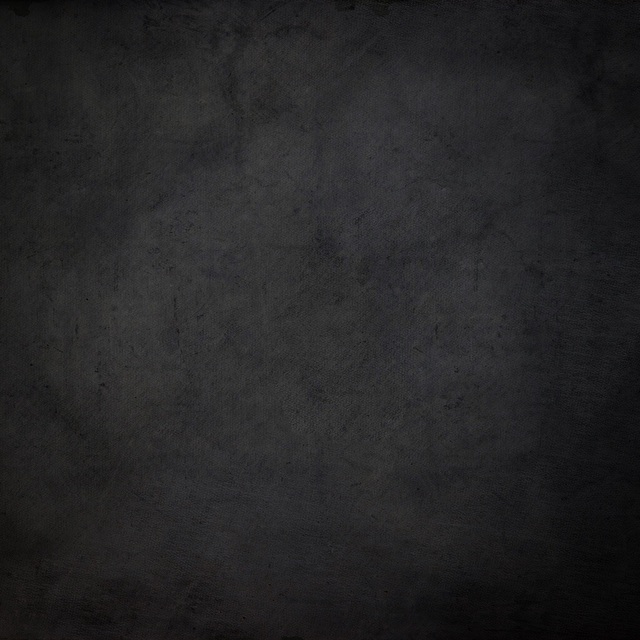
作者六角
コメントいつもありがとうございます。
続いたというか、何というか。ええと。すいません。
人間って最終的に、どういう形であれ己で死ぬと思いまして。心とか、精神とか、そういうことに限らず、肉体というものは自壊いたしますし、心が己を殺すときもあります。
不思議なものですが、そういうことにもなりうるという気持ちで書いた話でございます。