とある日曜の昼下がり
「やぁ、よく来たね」
同僚はドアを開け、僕を部屋に招じ入れた。
「お邪魔するよ」
僕はそう短く答えて、上がらせてもらった。
10畳ぐらいの程よい広さのリビングに通された僕は、促されるままにソファに座った。
奥のキッチンからは、同僚の奥さんが忙しそうに動いており、なにやら良い匂いがこちらまで漂ってくる。
「おーい、お茶でも淹れてくれないか」
「はーい、ちょっと待ってね」
同僚がキッチンにいる奥さんに声をかけると、明るい返事が返ってきた。
もう、この夫婦は大丈夫なようだ。
separator
数ヶ月前、この夫婦に悲劇が起こった。
二人の最愛の息子である拓ちゃんが、交通事故によってこの世を去ったのだ。
拓ちゃんは明るく、溌剌とした男の子で、いるだけで周りを和ませる雰囲気を持つ男の子だった
拓ちゃんの葬儀には僕も参加したが、それは見ているだけでも辛いものだった。
奥さんは発狂したかのように泣き叫び……、同僚はそんな奥さんを後ろから抱きしめ、その表情は溢れるようにこみ上げてくる感情を必死に耐えているようだった。
同じ年頃の娘を持つ僕は、同じことが娘に起こったらと考えただけでいたたまれない気持ちになったのを覚えている。
ただ、いまのこの二人の様子を見ていると、どうやらその悲劇を乗り越えたようであり、どことなく救われた感じがした。
separator
目の前には、奥さんが淹れてくれたお茶からゆっくりと湯気が立ち上がっている。
「なぁ、せっかくだし拓ちゃんにお線香でも上げさせてくれないか」
僕がそういうと、同僚は急に真顔になったかと思うと、台所にいる奥さんを盗み見て、奥さんに聞こえないような声でしゃべり始めた。
「悪いが、それは遠慮してくれ、もう仏壇もないしな」
「どういうこと?」
「ようやく妻は、立ち直りかけているんだ、ここまで来るのは大変だったんだ」
「だからって、仏壇を無くすこともないよ」
「いや、要らないんだよ。なぜなら今日、俺たち夫婦の元に拓は帰ってくるんだ」
「え、言ってることがおかしいよ、大丈夫?」
僕がそう言った時だった。
『ガチャリ』
玄関のほうで何者かがドアを開けた音がして
「ただいまー!」
という元気な男の子の声が聞こえた、
その声は覚え違いでなければ、紛れもなく生前の拓ちゃんのそれだった。
「拓が帰ってきた!!」
奥さんは声を上げると、料理をする手を止めて玄関のほうへ駆け出した。
僕も後を追うように廊下に出た。
そこにはキョトンしている拓ちゃん、それに泣きながら抱きつく奥さんの姿があった。
「お帰り!お帰り!拓!」
「痛いよ、お母さん!どうしたの?泣いているの?」
そんな光景を呆然と見ている僕の背中を、同僚が軽くたたいた。
僕たちは、そのまま無言で元通りリビングのソファに戻った。
「ねぇ、あれはどういうこと?拓ちゃんは・・・死んでいなかったの?」
「すまないが、妻に聞こえない程度の声でしゃべってくれないか」
興奮する俺に対して、同僚は妙に落ち着いた口調で答えた。
「機械音痴のお前は知らないだろうが、『代替ボット』って知っているか?」
「いや」
「まぁ、要するに人間に代わって、労役をするロボットのことだよ」
「ああ、それなら知ってる、コンビニの店員やら、交通整理やらするロボットでしょ?だけど、あんなに自発的に喋ったり、動いたりするのは見たことないよ」
「確かにそういうのは見たことないだろうが、技術的には可能なんだ。ただそれをしちゃうと人間の価値が薄れるだろう?」
「そうなの?」
「そうだろう、考えたり、自発的に行動したり、創造したりする事が出来るというのは、人間の価値そのものだ」
「AIが普及して随分たつように思うが?」
「あれは別に何か新しいものを創造しているわけではない、聞かれた事に対して膨大なバックデータの中から最適解を拾い上げてくるだけだ。質問形式を問わない、間口の広いコグニティブな受け取りが可能だから勘違いしやすいが、厳密には人工知能とは言えない」
「じゃぁあれは何なの」
僕は玄関の方指を指した。
「脳内モデルだよ」
「それは?」
「脳ってのは、要はとてつもなく複雑な入出力デバイスだろ」
「ああ」
「デバイスとして見るなら、個人個人の性能というのはそれほど変わる訳ではない」
「そうか?僕には随分、利口な人とそうでない人の違いは大きく思えるけど・・・・・・」
「それは使い方の問題なんだ。同スペックのマシンでも入れるアプリによって、できる事と出来ない事には差が出るだろ」
「そのアプリの内容はどこで決まるの?」
「育ってきた家庭環境やら、知識なんかだな。つまりだ、そういった個人差が出るところをモデリングして、アーキテクチャとして組み上げたものを脳内モデルと言うらしい」
「なんだ受け売りか」
「当たり前だろう、専門家じゃないんだから」
「だが、その脳内モデルって奴は死んだ人間からも作れるものなの・・・・・・あ、ごめん」
僕は無神経にも『死んだ人間』などという言葉を使ったことを後悔した。
「ああ、まぁ気にするな。基本的には出来ない、しかし、拓は死ぬ直前に学校でEQテストを受けていたんだ」
「EQテスト?心の知能指数って奴だっけか?」
「まぁ、そんな感じだ。それで十分って訳ではないが、足りないところは俺や、妻や、拓の友達などからのヒアリングや、俺たち夫婦の遺伝的な要素から補足して出来たのがあれだ」
僕は遠くから、嬉しき泣きしながら拓ちゃんの形をしたモノと喋る奥さんを眺めた。
「だけど・・・・・・これでいいのかな」
「どういう意味だ」
「いや、なんと言うか・・・・・・。これって現実から目を背けてるだけじゃないの」
「たとえ現実なんか見なくたって、本人が前向きに生きられるならそれでいいじゃないか」
「そうかも知れないが、本当にこれって正しいの」
「正しいってなんだ、現実から目を背けることは正しくないって誰が決めた」
「いや・・・・・その・・・・・・」
「お前はここ数ヶ月の俺たちの、いや、妻の様子を見てたとしてもさっきの台詞を言えるのか」
俺は黙っていることしなく、沈黙が流れた。
「すまない、少し興奮してしまった。本当はお前の意見もわからない訳でもない」
「いや、こっちも悪かった。君の気も知らないで・・・・・」
「今後のことは考える。すまないが今日だけでも良いから付き合って欲しい。今日は・・・・・・拓の誕生日なんだ」
「分かった、でも、ひとつだけ教えて欲しいことがある」
「なんだ?」
「何で今日僕を呼んだんだ?」
「何故って、お前を見てたら『代替ボット』のサービスを受けてもいいかなと・・・・・・あ、いや忘れてくれ。とにかく今日は、楽しんでいってくれ」
separator
「ただいま」
男は自宅に帰ってきた。
「お帰りなさい」
妻はそれを迎え入れた。
「あの娘はもう寝ているのか?」
「ええ、部屋で寝ているわ」
「そうか、すまないが水を一杯くれないか」
そういうと男は、少々疲れていたようで、リビングのソファに倒れこむように体を預けた。
「はい」
水の入ったグラスを男に渡すと、妻も向かいのソファに腰をかけた。
「僕は今日知ったんだが、君は『代替ボット』って知ってるかい」
「ええ、知っているわ」
「あいつ、拓ちゃんの『代替ボット』を買ったらしい」
「そう」
「君は、『代替ボット』についてどう思う?」
「どうって?」
「正直、僕はなんとなく現実から逃げているように感じたよ」
「実際、逃げてるんじゃない?でもそれが悪いことには思えないわ、あなたは違うようだけど」
「あいつと同じ意見なんだな」
男は顔を天井に向けて目を瞑ると、深い息をついた。
「なぁ、少し聞きたいんだが」
「なに?」
「今からちょうど1年前の2ヶ月分の記憶が、僕には無いんだがどうしてなんだろう?」
「あらやだ、あなた認知症じゃないの」
「それに今、僕は月一で心療内科に通っているのは何でだろう」
「それはあなたが不眠症だから・・・・・・」
「確かにそうだが、僕はいつ初診を受けに行ったんだろう?」
「あなた本当に認知症なんじゃないの?」
「記憶が無い2ヶ月より前には、行った記憶が無いのは確かだから、その期間に初診を受けたことになる。君は認知症じゃないかと言ったがが、2ヶ月前後の記憶はしっかり持っているのに、2カ月分記憶だけが無い、認知症にこんな症状はあるのかい?」
「専門医じゃないんだから知らないわ!」
「それに今の定期通院でも、君が必ず付き添いで来るのは何故?」
「それはあなたが心配だから!」
「そして、不眠症ならもっと近いクリニックでも診療してくれるのに。そこより遠い、『代替ボット』による治療も行っている心療内科に、通っているの何故?」
「あなたの不眠症は、あなたが思っているよりずっと重くてそこでしか見てくれなかったのよ。あなた・・・・・・何が言いたいの?」
男はそれを言うか躊躇しているらしかったが、やがて意を決したように口を開いた。
「僕は自分が気づいていないだけで、『代替ボット』なのではないかと不安になって。ねぇ、僕が通院しているのは、実は僕は死んでいて、それによる君の心の治療や『代替ボット』である僕のメンテナンスのためなんじゃないの?」
それは重い重い、数秒間の沈黙だった。
それを破ったのは部屋で寝ていた筈の娘だった。
「パパ、ママ、喧嘩しているの?」
娘がリビングに現れた。
「あら、ごめんね。なんでもないの、明日は学校なんだから、早く寝なさい」
妻は娘に近寄ると優しい声でそういうと、娘の部屋まで二人で消えて言った。
その様子を見ながら、男は独り言のように呟く。
「どうかしていたな、こんなに抑えきれない程の愛しいという気持ちが、ロボットから生まれる筈がない。それに、本物の『代替ボット』だというなら、妻をあんなに興奮させるような行動は取れないようになっている筈だ。僕は『代替ボット』なんかではない。」
separator
約一年前・・・・・・。
「代替ボット治療?」
「そうです、あなたのような犯罪被害などによって家族を失った人たちのための診療プログラムです」
「具代的などのような治療をするのでしょう?」
「貴方の場合、亡くなられた奥さん、娘さんの『代替ボット』を使用することになります」
「『代替ボット』については、こちらでも一通り調べましたが、それで僕の心が癒されるとはとてもじゃないけど信じられません」
「もちろん、『代替ボット』と共同生活するだけでは、治療としては不十分です」
「ではどうするのですか?」
「貴方に退行催眠をかけて、ここ2ヶ月の記憶を消させてもらいます。つまり、貴方の奥さんと娘さんが強盗に襲われたこと、そしてこれから行う施術も含めて無かった事にするのです」
「なるほど」
「但し、これだけ大掛かりな催眠を行うと、途中で催眠が解けてしまう可能性があります。そのため貴方には月一で、定期受診してもらう必要があります。また自然とそのように仕向けるように奥様のボットを調整します。大雑把に言うとこうなりますがどうでしょう?」
「それで、この紺精神的な苦痛から逃れられるなら」
「それは保障します。ただ、診療内科医としてはこの治療は苦肉の策です。現実に目を向けず、ただただ問題を先延ばしにする策でしかありません、それでも本当によろしいのですか」
「ええ・・・・・・、僕はかまいません」

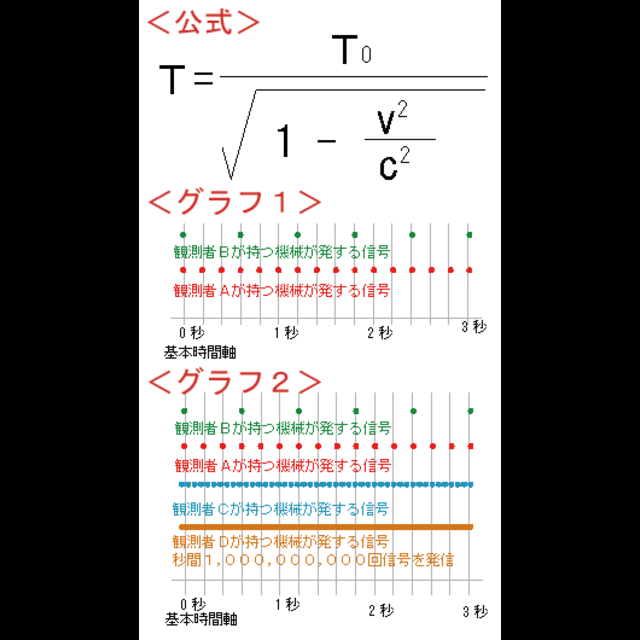
作者園長
なんか、あんまり、まとまってないです。