死にたいと思った。
私は、いろんな方法を考えた。
例えば大量の睡眠薬を飲む。
これには、睡眠障害を訴えて医師から睡眠薬を処方してもらい手に入れなければならない。
それまでに、死ぬ決心が鈍ってしまいそうで嫌だった。毎日この朝を迎えると思うと気が狂いそう。
もう一つは、練炭で自殺する方法。
でも、この方法だと、この部屋で自殺すればその後処理のこと、この部屋の大家さんにすれば、ここは事故物件としてもう価値がほぼなくなるなどの迷惑がかかるのだ。そんな死に方はダメだと常々思っていたからこれも却下。
海や川で入水自殺も考えたが、これは死体が最も醜くなると聞いたことがあるので、引き上げる方の気持ちを考えればこれもダメだ。
死ぬことを考えていると、いつの間にか、頬を涙が伝っていた。
何でこんなことになったんだろう。
私のどこがいけなかったのだろう。
あの人のことを色々疑ったことが悪かったのだろうか。
でも、結局あの人は、元の彼女のところに帰ってしまったではないか。
愛が重すぎるとあの人は言ったが、愛は重い物だろう。
自分から愛している愛していると連呼しておいてそれは無いだろう。
私だけその気になってバカみたい。
一人朝起きて、現実を認識するのが辛かった。
もうあの人は私の元には戻らない。
あの人に関わるものは全て捨てた。なのに、あの人は私の心の中から出て行かない。
よし。
私は涙を拭い、リュックを肩に部屋を出た。
大家さんへの手紙をそっと一階のポストに入れた。
一緒に私の荷物を処分するに足りるかどうかはわからないが、預金通帳と印鑑を同封した。
せっかく良くしてもらったのにごめんなさい。大家さんには、息子さんしかおらず、私は我が娘のように可愛がってもらった。両親は早くに亡くなってしまったので、私は大家さんを母親のように慕っていた。
目的地はあの山。
途中のホームセンターで、ロープを買った。
確か、あの山には中腹あたりに山小屋があったはずだ。
一度、彼と登山に行った時に、確か小さな椅子などもあったはず。梁にこのロープをかけて、あの小さな椅子を蹴れば、問題なく死ねるだろう。
今は、山登りのシーズンも終わり、山は枯野になっているからたぶん誰も来ないだろう。
皮肉にも私は未練がましく、彼との思い出の地を死の場所に選んだ。
一人いろんな思いを巡らせながら山道を登ると、あっという間に山小屋に着いた。
途中誰とも出会わなかった。それもそのはずである。まだ、暗い夜中のうちに部屋を出たのだ。
鍵の壊れたドアを開けると、朝の陽ざしに山小屋の中の埃がキラキラと輝いた。
リュックからロープを出すと、私は椅子に上り、梁に向けてロープを投げた。
なかなかうまく届かない。ロープは、はらりと床に落ちて埃を舞い上げた。
「はあ~。」
深いため息をついて、私は椅子から降りてロープを拾う。
「えっ?」
ロープを拾うために、腰をかがめると、床の隅に何かが落ちているのを見つけた。
近づいてみると、それがスマホだということがわかった。
その途端、着信があり、マナーにされているのかブーンブーンという振動音を立てて震えた。
誰かの忘れ物だろうか。放っておこうと思ったが、これを誰かが落としたのであれば、きっとここまで探しに来るだろう。それは困る。予定変更。私は絶望的な気分のまま、その電話に出た。
「もしもし?」
「・・て・・・は・・い」
ところどころ音声が途切れて声が聞えない。
「もしもし?ちょっと聞き取りにくいんですけど。」
「・・て・・・は・・い」
やはりうまく声が聞き取れない。
私は、仕方なく通話を終わらせた。
それからしばらく待ったが、着信は無かった。
私は、仕方なくそのスマホを手に、山を下りた。
きっと持ち主がこのスマホを探している。誰かの電話から、このスマホに着信を入れたが、おそらく山の中なので電波がうまく届かなかったのだろう。きっと自分の歩いた道をたどって、いずれこの山小屋にたどり着く。自殺の邪魔が入るのは困る。でも私は結局、怖気づいてしまったのかもしれない。
私は麓の交番にそのスマホを拾得物として届けた。
私が自分のフルネームを書き終わると、警官は私の顔を驚いたように見た。
私が怪訝な顔をしていると、その警官は、
「水無瀬 唯香さん?あなた、捜索願が出されていますよ?」
と言い、誰かに電話をかけた。
ああ、たぶん、大家さんだろう。私はとたんに恥ずかしくなった。
自殺を仄めかしておきながら、おめおめと舞い戻ってきたのだ。大家さんに合わせる顔などない。
私は、警官が電話をかけている途中で逃げようとしたが、あえなく捕まってしまった。
大家さんがすぐに青い顔でかけつけてきた。
「バカなことを考えるんじゃないわよ!」
大家さんは泣いていた。私も釣られて泣いた。
「ごめんなさい。ごめんなさい。」
「もう死ぬなんて、考えないで。若いんだから、これから何でもできるじゃない。」
私はバカだった。私が死んでも誰も悲しまないと思っていた。
私は落とし物のスマホを警察に届け、大家さんに付き添われて自宅へと戻った。
その夜、不思議な夢を見た。
夢の中であの山小屋で拾ったスマホが着信を告げているのだ。
私は、怖くなり、黙ってテーブルの上で鳴っている着信のバイブレーションを聞いている。
すると背後に人の気配がして、私を背中から抱きしめた。
私は、驚いて身を固くした。
「電話、出ないの?」
耳元で男の声で囁かれた。私を背中から抱きしめているのは男だ。
でも、あの山小屋に落ちていた電話の声は女だった。
「い、嫌っ!」
背中の男を振り払い自分の叫び声で目が覚めた。
冬にも関わらず、全身にびっしょりと汗をかいていた。
嫌な夢だ。額の汗を手で拭うと、着信を告げるバイブレーションの音がして、私は飛び上がった。
慌てて自分のスマホを手にするが、どうやら私のスマホの着信ではないようだ。
じゃあ、何の音?この音は、それ以外の何物でもない。
恐る恐る音のするテーブルのほうを見ると、その物体は着信を告げていた。
「な、何で?警察に届けたはずなのに!」
紛れもなく、それは昨日山小屋で拾い、警察に届けたあのスマホだった。
あの悪夢の続きのような気がして、私は思わず後ろを振り返ったが男は居なかった。
当たり前だ。ここは私一人暮らしなのだから誰もいるはずはない。
電話、出ないの?
私は、あの夢のように見知らぬ男に後ろから抱きしめられて耳元で囁かれそうな気がして、その電話に出てしまったのだ。
「も、もしもし?」
「・・て・・・は・・い」
やはり同じだ。女の声で、途切れ途切れの言葉は聞き取れない。
ここはそんなに電波状態は悪くないはずだ。このスマホは何かある。また警察に届ければ厄介なことになるだろう。自殺志願者がまた同じスマホを拾得物として届ければ怪しいことはこの上ない。
私は仕方なく、そのスマホを手にすると出かけた。電車に乗って、なるべく自宅から遠くのスーパーのゴミ箱にそのスマホを捨てた。きっと店の誰かが見つけて警察に届けるだろう。
しかし、何故、警察に届けたはずのスマホが私の元に戻ってきたのか。いくら考えても答えは見つからなかった。
《続く》
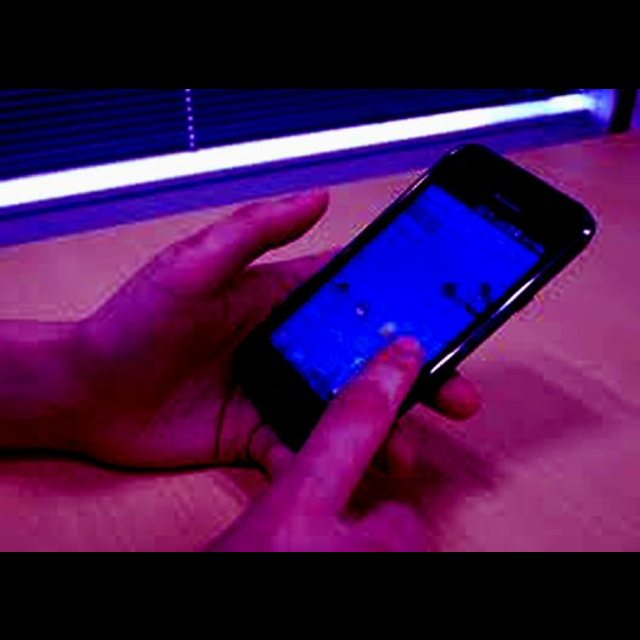




作者よもつひらさか