music:4
昭和の終わり頃にMさん(五十代、女性)が体験した。
ある夏の夜、Mさんは当時付き合っていた彼氏と二人でドライブに出掛けることにした。行き先は心霊スポットとしても知られている支笏湖である。
物心ついた頃からオカルトが三度の飯よりも大好きだったMさん。けれどもその日はオカルトよりも、純粋に彼氏とのデートを楽しむつもりで家を出たという。
東の空には月が輝いていた。
二人が暮らす札幌を離れて少ししたとき、不意に車道の脇に黒い塊を見つける。
「何だろう、あれ」
Mさんの問いに彼氏が「あ……ネコだ。ネコの轢死体だ」と教えてくれる。
暗くてMさんにはよく見えなかったが、どうやらそれは車にひかれて野ざらしのまま放置されている野良猫のようであった。
「かわいそうに。早く誰かが清掃事務所に連絡するなり、土に埋めてあげるなりしてあげるといいんだけれど」
「そうだな」
そんな会話を交わしたという。
それから三十分ほどで千歳市に入ることができた。その道を真っすぐ進んでいけばやがて支笏湖にたどり着く。道に迷う心配はない。二人が車内で世間話に花を咲かせていると、目の前の信号が赤に変わる。
ブルルルル……
停車した車内に一瞬だけ沈黙が訪れる。
「キャー!」
そのときに、Mさんがあるものに気付いて大絶叫する。
ネコだった。ネコの轢死体だった。
見るも無残な姿に変わり果てた野良猫の亡きがらが道路脇に放置されたままになっていた。
Mさんが「またネコの死体だわ。一匹ならまだしもこうして立て続けに見てしまうと……もちろんかわいそうだとは思うけれど、何だか気味が悪いわねえ」とつぶやくと、信号が青に変わる。
「俺も年に一度見るから見ないかだと思う。どうする? 気持ちが乗らないようなら引き返してもいいぞ」
「そうねえ、もう帰りましょう」
支笏湖へはまた今度明るい時間にドライブに行こう、と話がまとまり引き返そうとするのだが、転回できるような場所が見つからない。
とりあえず先に進むしかなかった。
待避所のような所が見えてくるまで、うねうねと蛇行する道を走り続けるしかなかった。
すると程なくしてからトンネルが見えてきた。その壁には明かり取りが付いていたので、正確にはトンネルではなく「覆道」である。
助手席から外の景色を眺めていたMさんの視界を、コンクリートの柱が何本も何本も猛スピードで横切ってゆく。その向こうでは、生い茂る草木が夜風にそよそよ揺れ動いていた。Mさんはそんな景色をただぼんやりと眺めていた。
するとその闇の奥深くから突然何かがぬうっと現れる。
シルクハットのような帽子をかぶった男性だった。月明かりを背に受けた男性の顔や服は逆光のため不明瞭だったが、こちらに向かって歩いてくる姿ははっきりと見て取れる。
夜遅くに、人家の途絶えた草原で、男は一人で一体何をしているのだろう?
Mさんはけげんに思った。
そして男が一歩、また一歩と、こちらに向かって歩いてくる様子を見ていたときにふと気付く。
大き過ぎる、と。
成人男性の倍近くに見える。三メートル近くあるのではないだろうか。
そしておかしなことに、高速で走る車に徒歩で近づく男性の姿がかき消されることがなかった。ひたひたと確実に近づいてくる。
巨男が車の真横にやって来るまでそう時間はかからなかった。
「開けて、窓、開けて! 早く!」
とっさにMさんが叫ぶ。自分でも助手席側の窓を開けて、彼氏にも運転手側の窓を開けてもらう。
その直後に巨男がすうっと車を通り抜けてどこかに消えた。
「良かった。間に合った!」
ほっと胸をなで下ろすMさん。
「何だよ。一体何が起きたんだ?」
彼氏には何も見えていなかったようで、覆道を抜けてから尋ねられた。
「三メートルくらいの巨大な男が近づいてきたの。もちろん人間なんかじゃないんだけど、だからといって霊にも見えなかった。妖怪、というよりも地底人だとか異星人に近いものだったんじゃないかしら? 私たちの乗った車にそれが急接近してきたから、どうにかしなきゃと思ったときに窓のことを思い出して、それで開けてもらったの」
十勝出身のMさんは、地元で車を運転しているときに怪異に見舞われることがしばしあった。そのときに車の両側の窓を開ければ、その「何者か」が車内にとどまることなくどこかに消えてしまうことを知っていたので、このときも同じ方法に頼ってみたのだという。
巨男が「霊」なのか何なのかよく分からなかったので、吉と出るか凶と出るか不安もあった。結果としては「吉」が出たので良かったが、あのとき二人が窓を開けずにいたら一体、どうなっていたことか。
ちなみにあのとき巨男が車を通過したタイミングで、彼氏も嫌なものを感じていた。
Mさんのようにはっきりと目で見たわけではないけれども、その瞬間だけ妙に体がぞくりとしたという。

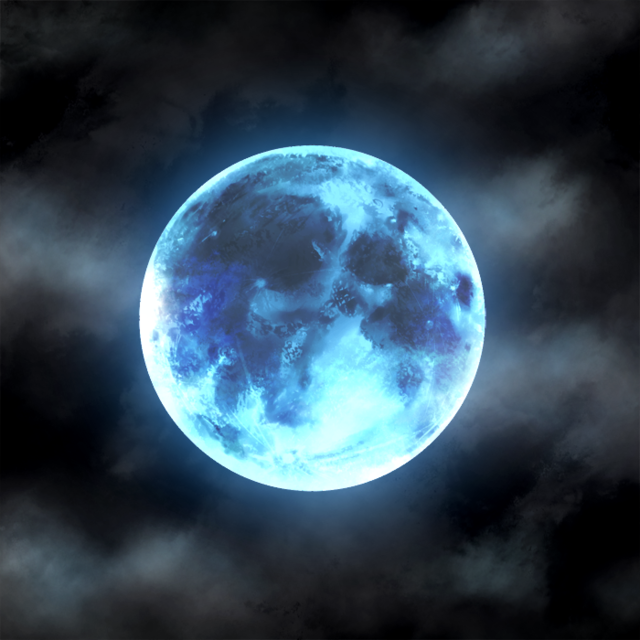
作者秋元円