水が嫌いだった。
幼い頃の、嫌な記憶のせいだと、長らく思っていた。だから僕は、若かりし日々に交際をした、それなりの人数の女性達とも、海やプールなどには決して出かけなかった。
気がつけば三十代も半ばで、気がつけば結婚していた。
妻は、水が好きだった。
その夏は、例年になく暑かった。ジリジリとした直射日光が肌を指し、周りの空気すら重く、体にのしかかってくる。酷暑という言葉などでは到底追いつかない、重苦しい痛みを毎日味わっていた。
「プールに行こうか」
と僕から妻を誘った。
なんせもう良い大人なのだから、僕は、自らの恐怖症との付き合い方くらいわかっているつもりだった。
車で三十分程走って、隣町の町営プールに出かけた。勿論、近場にも市営のプールは存在する。しかし僕は、あえて隣町を選んだ。単純に規模が大きいという、些細な理由だった。
昼食を軽く取り、僕らはその初めて行くプールに向かった。平日ということもあり、人は疎らに、それぞれの楽しみ方で涼を得ていた。
その日は、ほどほどの雲が空を漂い、寧ろ太陽が顔を出す時間の方が少ない、しかしながら、時たまその切れ目から刺す日光が容赦なく肌を焼くという、なんとも中途半端な天気だった。
学生時代以来のプール再デビューには、これぐらいが丁度良いのだ、などと言いながら、僕は流れるプールをビーチボールの浮力を頼りに漂っていた。
妻は競泳用のプールを行ったり来たりしながら、水を楽しんでいた。
水面を漂うのにいい加減飽きた僕は、ビーチボールを抱え、競泳用のプールサイドに日陰を見つけ、そこにするりと座り込んだ。
妻は器用に泳法を変えながら、相変わらず行ったり来たりしている。
ポタリポタリと、僕の前髪から落ちる水滴が、焼けたコンクリートに吸い込まれていく様を暫し楽しみ、そろそろ妻に声を掛けようかと視線をプールに向けた。
妻の背後を、妻が追いかけていた。
前を泳ぐ妻は優雅に泳いでいる。
後ろの妻は、まるで関節が壊れたオモチャの様に、無茶苦茶な動きで、しかし一定の距離を保ちながら、後を付けている。
前の妻の泳ぎが上手いのか、後ろの妻の泳ぎが下手なのか、距離は何故か縮まらず、両者黙々と泳ぎ続けていた。
そのあまりの光景に、僕の全身は粟立ち、思わずビーチボールをひしと抱きしめた。
──これは、何なのだ。
喉の渇きが急に僕を襲う。口の中がカラカラに乾燥し、声帯がまるで喉に張り付き固まった様な錯覚に襲われた。
ポカンと開けた唇に髪から伝う水滴が這い、思わぬ潤いを与える。
妻がこちらに視線を送りながら、背泳ぎで通り過ぎていく。
丁度、一人分程の距離を開け、ガチャガチャと泳ぐ妻が、真っ赤に充血した目で僕を睨みながら、妻を追いかけていく。
しかしこの異様な光景に、目を向いているのは僕以外いなかった。
大学生のバイトらしき監視員も、子供を遊ばせる同年代と思しき母親達も、大声ではしゃぎ回っている近所の男子中学生達も、誰も彼も、普段の日常を過ごしていた。
「どうしたものか……どうしたらいい……これはどうすれば……と言うか何なんだ」
僕は小刻みに唇を震えさせながら、ブツブツと呟く。
もうそれがプールの水なのか、己の汗なのかすらわからない、顔に纏わり付く不愉快な水滴を拭いながら、目の前の光景を、どうにか理解しようと必死に試みていた。
「顔色悪いよ。上がる?」
気がつけば妻が、水を滴らせながら、佇んでいた。
「え……ああ……」
聞き慣れた声に体の緊張が解ける。
瞼を閉じ、両手で目頭をぐりぐりと揉みほぐし、意識的に大きく深呼吸をする。目を開くと、視点の定まらない、薄ぼんやりとした世界に、手元から離れたビーチボールがテンテンと転がり、妻の足元に収まった。
目線が泳ぐ。
ゆらゆらと揺らめきながら、妻の顔を捉える。
心配気な表情でビーチボールを拾い上げる妻。そうだ、彼女は、大丈夫だ。
「いや……大丈夫だよ」
僕は無理に笑顔を作ると、熱いコンクリートの床に手を付き、ゆっくりと立ち上がった。
世界に色が戻ってくる。喧騒が耳に刺さりだす。子供の奇声。笑い声。きぬ擦れの音。水の跳ねる音。遠くで鳴く蝉。
水面から顔半分を出した、壊れた方の妻が、僕を睨んでいた。その一箇所だけ、周囲の色が失せている。
真っ赤に充血した目だけが、セピア色の世界に強く色を主張していた。
彼女は一度大きく上に跳ねると、水中に音もなく消えていった。不自然に歯を剥き出しにした、不気味な笑顔を僕に残して。
フラフラと妻の後を追い、僕はもう一度流れるプールに戻った。ソロソロと水に足を差し込む僕を見ながら、妻はビーチボールを抱え水面を漂いながら、ニコニコと笑っている。
なに、せいぜい腰の高さ程度の水深なのだ。恐れる事はない。
脱力すれば勝手に体が浮くと、そう妻は言うが、そもそも自分自身の浮力なぞ全く信用していない。
流れに身を任せて先を漂う、妻を追いかける様に、僕は不慣れで不格好な泳ぎ方で、水を掻き分ける。
トン、トンとプールの底を蹴りつつ、極力水が顔に触れない様に、しかし必死さを醸し出さず、余裕綽々だという風な表情を作りながら、僕は妻を追いかけた。
楕円形に造られたプールの、緩やかなカーブに差し掛かったところだった。
僕と妻の間、それは三メートル程離れていただろうか……底を蹴って推進力を得ようとしたその刹那、壊れた妻が、あの笑顔で、歯を剥き出した不愉快な笑顔で、僕の目の前に水中から生えてきた。
何故か首がぐるぐると回転している。
両手両足が無茶苦茶に暴れ回っている。
──フヒイヒヒアハハアハハ
聞こえない筈の、女の声が脳内に響く。
僕は……水の流れに逆らいながら、懸命に底を後ろ向きに蹴り続け、背中から水中に倒れこんだ。なんとしてでも、女と距離をとりたかったのだ。
その時初めて、僕はたとえ水深が浅くても、人は簡単に溺れる事を知った。
体が本能的に空気を求め、必死に立ち上がろうと足掻く。カーブするプールの縁を、手ががむしゃらに探る。
脱出したい一心で、平静を求めるよりも先に体をグッと伸ばし、プールサイドを目指した。水がゴボゴボと口に流れ込む。水中と水面を行き来する僕の視界が、あの女を微かに捉えた。
女が無茶苦茶な動きで、僕の腹をすり抜けるのと、僕がプールの縁を掴むのと、ほぼ同時だった……思い返すと、そうだった気がするだけなのだが。
勢いよくプールから抜け出すと、息を整える間も無く、強烈な吐き気に襲われ、口元を必死に抑えながら、プールから少し離れた人気の無いコンクリートの上に、盛大に吐いた。
監視員らしき人間が駆け寄ってくるのが、気配でわかる。荒い呼吸で体を震わせながら、僕は、灰色のコンクリートに散らばる、黄色い己の吐瀉物を見つめていた。
──そこに浮かぶ、真っ黒な毛玉が、不快で仕方なかった。
僕は熱中症という事で、医務室に運ばれた。
誰一人、妻でさえ、あのもう一人の壊れた妻を認識していなかった。
あの時、僕の腹を通り抜けた女は、僕の中に何を残していったのだろう。いつか分かる日が来るだろうか……
僕は……相変わらず水が嫌いだ。
〈終〉


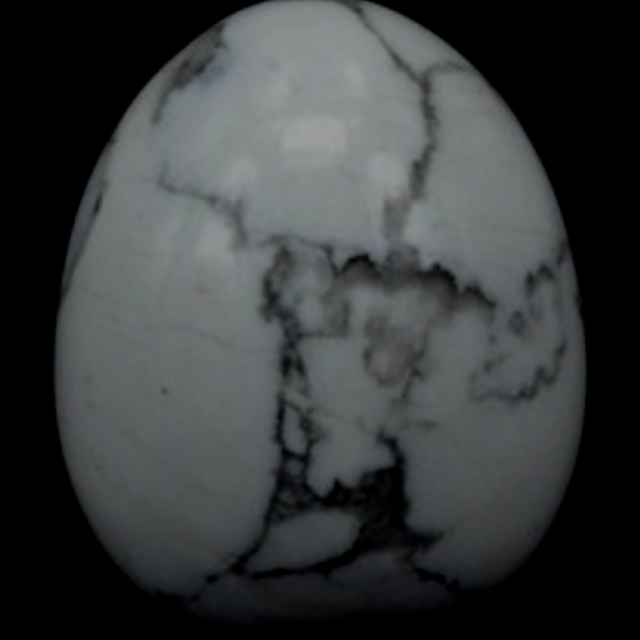


作者退会会員
はい、こんにちは。
あのですねぇ、僕は水が嫌いなんですねぇ。
息が出来ないのってものすごい怖いじゃないですかぁ。
プールもねぇ……お腹痛くなるし。
とにかく水はねぇ怖いですねぇ。