旧友と再会したのは、偶然といえば偶然だった。
幼馴染というやつだろうか、幼少期からただ、なんとなくウマがあったのだろう、二人で遊ぶことが多かった。
二十歳を超えると、お互いの道を歩むべく、疎遠とはいかないまでも、昔程同じ時間を過ごさなくなった。
決して順風満帆な人生ではなかった、と織先平《おりさきたいら》はときどき思いに耽る。
何度も失敗し、何度も挫折し、夢に敗れ、心を病み、紆余曲折を経て、織先は、なんとか生きていた。
織先は小説を書いている。とは云っても、あくまでも趣味である。幼い頃から長く続く数少ない、読書という趣味が功を奏したのか、文字を書く事は苦痛ではなかった。
只々、キーボードに向かい、頭の中を駆け巡る映像を文字に起こしている、其れだけの作業だった。しかし、何故か心は安らいだ。その瞬間だけ、胸を締め付ける心の病の呪縛から逃れられた。
生粋の飽き性を自認している織先は、自分でもいつまで続くかわからないこの行為を、己の己によるセラピーと位置づけ、仕事の合間に黙々と行なっていた。
その日も織先平《おりさきたいら》は散歩がてら、ふらふらと地元の本屋を散策していた。マスクを付け、お気に入りの音楽をイヤホンで聴きながら、陳列された表紙の文字達に視線を這わし続けていた。
不意に肩を叩かれた。
心拍数が跳ね上がり、瞬間的に息が上がる。
怯えた目で振り返ると、そこには──男がニヤニヤと笑っていた。
「……はい、えっと……」
──何ですか?という消え入りそうな織先の声をかき消すように、男は
「何やってんだよ?タイラよ」
と、眼鏡の奥の切れ長の目を細めて、男は云う。
高級そうなスリーピースの黒いスーツに身を固め、神経質そうなメタルフレームの眼鏡が、よく似合っていた。
「なにって……本屋なんだから本を見てるに決まってるじゃないかよ……」
マスクとイヤホンを外しながら織先は応える。
旧友、海城大至《うみしろたいし》とはこうやって再会した。
nextpage
海城に連れられ、昼間からやっている居酒屋に、織先は連れ込まれた。真昼間にもかかわらず店は賑わいをみせている。しかし、夜中の居酒屋の其れとは違う、ある種の独特な雰囲気に包まれていた。
ある者はカウンターで一人、人目を避けるように酒をちびちびと嗜み、ある者はまるで喫茶店でコーヒーを飲む様にジョッキを傾ける。畏怖と愉悦と、少しの優越感
が店内を漂っていた。
海城が頼んだツマミが数種類、小汚いテーブルに並び、真昼間の居酒屋という異質な空間で、十数年振りの再開を祝ったのだった。
「よくわかったよね……僕の事」
「全身タイツを着とったって分かるわい。お前の事くらい」
そう宣い、海城はジョッキを勢いよく空けていく。
織先の目線が、海城の手に集中する。不快な違和感を感じた。
──海城の、指にあるはずの爪が、全てなかった。
「なあ、タイラよ。お前にとって幸せって何だ?」
織先の目線に気づいたのか、海城はそう呟いた。
「対価ってあるだろう?世の中はな、対価が必要なんだよ。でも多くの人間はそんな事すら意識しない。地位だ名誉だ、金だなんだ、人間の欲望は果てしない」
──そう思わないか?と海城は織先に問いかける。
もごもごと織先が、言葉を選んでいると、海城は己の両手を突き出してきた。
爪のない指先。爪があったであろう場所に肉がこんもりと盛られている。
「コレが俺の払った対価だ。これのおかげで、俺はこうやって真昼間から酒を呑んでも、誰にも疎まれない生活を得ている」
織先は、テーブルに置いた海城の名刺に目を落とした。なんともご大層な役職が、名前の上に刻まれていた。
「なあ、タイラよ。お前にとって幸せって何だ?幸せを望むか?お前の感じる幸せが欲しいか?」
──ほしいなら教えてやるよ、と海城は、爪のない己の指先を見つめながら、そう呟いた──
nextpage
織先平《おりさきたいら》はその夜、なかなか眠りにつけなかった。
日中の、海城大至《うみさきたいし》の言葉が渦を巻いていた。
幸せとはなんだ?幸せとは……即答できる人間などいるのだろうか。
お金はある方がいいとは、織先も思う。ただ、食べていけたら十分だ、という意識もどこかにある。
小説で食べたい、という気持ちも無い訳ではないが、そこまで自分に才能があるとも思えない。
そもそも、書きたい事など織先には何も無いのだ。ただ、頭の中で再生される物を、文字として出力しているに過ぎない。
なので、他人が求める物など、売れる様な物など、元々書けないのだ。
書けるのは、織先の脳内に投影される、何とも気持ちの悪い、不快な世界だけである。
とは言え、人並みには幸せでありたいし、人並みに雨風を凌ぎ、人並みに注目もされたい。
だから織先は悩むのだ。
幸せとは……幸せとは……
「普通でありたい」
枕に顔を押し付け呟くと、少し気持ちが楽になった。
居酒屋での祝杯から一週間ばかり、うじうじと悩んだ結果、織先平《おりさきたいら》は海城大至《うみしろたいし》に連絡を取った。
忙しいであろう海城に気を使いメールにしたのだが、海城は直ぐに電話を掛けてきた。
「……なあ、本当に対価を払うのか?」
電話の向こうから聞こえる旧友の声には、どこか後悔の念が感じられる。
「お前だって、あんなに熱弁してたじゃないか。僕だってさ……」
──幸せが欲しいよ、と織先は自分のつま先を見つめながら、云った。幸せ……幸せ……消え入るようなその叫びは、織先の全身に響き、得体の知れない身震いすら覚えた。
「俺はよタイラ。お前の幸せを、誰よりも願ってるんだよ。なんなら、俺がお前の対価を払ってやってもいいくらいだ。今の俺には、それくらいの力はあるんだよ」
海城の言葉は、ずしりと織先を捉える。思わず携帯電話を投げ捨てたくなった。
──お前の言葉は重たいんだよ……昔からずっと。
内面から溢れ出る憤怒を抑える。苦しい、苦しい。
「それでは……意味が……ないよ。僕が対価を払わないと……後悔する」
切れ切れに言葉を発する織先の言葉を、海城は沈黙で返した。
「……一週間後に時間をくれ。連絡する」
海城は絞り出す様にそう云って、通話を切った。
恐ろしいまでの自己厭悪が織先を襲った。心拍数が跳ね上がる。息が荒くなる。視野が狭い、世界から色が消える……
苦しい。苦しい。苦しい……だが、何故か織先の顔は、その時微笑んでいた。
nextpage
一週間はあっという間に過ぎ去った。
織先平《おりさきたいら》は代わり映えのしない、鬱屈した毎日を過ごしていた。本を読み、文章を書き、粛々と本業の仕事をこなした。
海城大至《うみしろたいし》は、指定した日に車で迎えに来た。
時計は午後十時を回ったところだった。
久しぶりに再開したあの日と同じ、高級そうなスリーピースの黒いスーツに身を包んでいた。
「今からお前を、エヌ公園に連れて行く。知ってるよな?あの公園を」
昔、幼い頃に二人で駆け回っていた、山の麓にある公園の名前を海城は告げる。織先は、走る車の流れる風景を見ながら、ああ──とだけ云った。
くるくると住宅街を抜け、山道に入る。あの頃と違い、今では立派に整備された道路を、車のヘッドライトが切り裂いて行く。
坂を登り、小さな街灯が一つだけ主張する、こじんまりとした駐車場に車は吸い込まれていった。海城がエンジンを切ると、車内に静寂が訪れる。
まるで覚悟を決める様に、海城が大きく息を吐く。
「行くか」
織先の返事を待たずに、海城はさっさと外に出て行ってしまった。車内に取り残されると、急に恐ろしさが織先を襲った。慌てて海城を追う様に転げ出る。
夜風が心地よい。ああ──今は、秋だったのか。季節を感じる余裕すらなかったのかと、改めて織先は己を恥じた。いつもいつも恥じてばかりだ。
闇に溶け込む海城は、坂を登り始めた。革靴のくせにやたらと足が早い。そういえば、昔も先を行くのは海城で、その半歩程後ろを歩くのが好きだったなと、織先は久しぶりに笑った。
舗装された細い道が左にカーブしていき、だだっ広い公園に出る。昔は遊具が存在した記憶があったが、今は撤去されたようで、代わりに、まるでとってつけた様な小川が、真ん中をサラサラと流れていた。
公園を左手に見ながら進んで行くと、遊歩道に突き当たる。その遊歩道の脇に、山中へと続く、丸太で組まれた階段が隠される様に存在していた。この山を越えると、どうやら隣の県に行けるらしい。最もそれを誰から聞いたのかなど、織先には記憶すらないのだが。
海城は携帯電話のライトで灯りを取りながら、黙々と山中へ入っていく。
サワサワと擦れる葉の音に混じって、二人の荒い呼吸音が、漆黒の山に吸い込まれて行く。
唐突に、鳥居が現れた。まるで闇から生えてきた様に織先には感じられた。長年、手入れをされてないのだろう、朱色であった筈の表面は朽ち、木の地肌が顔を出していた。
朽ちかけた鳥居は、なんとも寒々しい気分にさせられる。
海城は意に介さず、淡々と進んで行く。織先には、後を追う以外の選択肢は与えられなかった。
小さな神社に突き当たった。その神社をぐるりと迂回する様に、道は左手に続いている。誰が供えたのか、蠟燭が数本、ちらちらと揺らめいていた。右手を見ると、何故かどこかしら欠損した地蔵が、道を挟む様に並べられていた。
「……大明神?」
色褪せた布に染め抜かれた、神社の名称を思わず織先は呟く。
「お詣りしていくか?」
いやいいよ──と、織先が答えると、海城は何も云わずに左手の道を進みだした。
暫く無言で歩いて行くと、左手に何かの作業所らしきプレハブ小屋が目に入った。道に面した磨りガラス越しに、薄っすらと明かりが見える。
海城は磨りガラスの窓に背を向けるように、道を挟んだ対面に向かって屈んだ。
──そこには、小さな小屋があった。
せいぜい五十センチ四方の、まるで小人の住む小屋の様な稚拙な、云うなればそれは、匣だった。
ご丁寧に小さく造られた扉には、不似合いな南京錠が付けられている。海城はガチャガチャと鍵を差し込み、南京錠を外している。
織先の背中に悪寒が走った。
咄嗟に振り返ると、プレハブ小屋の磨りガラス越しに──人の影があった。
その影はこちらを凝視しているようで、身動き一つしない。人形のようにただ突っ立ているだけの影が、恐ろしくてたまらなかった。
「気にするな、話は通してある」
振り向かずにそう云い放つ海城が、まるで化け物のように思えた。
──ここは、知らない世界だ。ここは、異界だ。
織先の視界から色が消える──苦しい……
口を覆うマスクに強く手を当て、鼻呼吸を意識する。
「アレは守り人だ。異人がこれを手に入れない様に、見守っているんだよ」
赤黒く錆びついたペンチが、海城の右手に握られていた。
織先が後ろを振り向くと、磨りガラスは元のまま、白く濁っているばかりだった。
nextpage
相変わらず周囲は墨を流した様に暗い。暗いというか黒い。空気が──やたらと黒い。
存在理由のわからない山道を、黙々と進んで行く。
前を行く海城大至《うみしろたいし》が、ピタリと足を止めた。
眼前には、廃墟としか思えない、朽ちた御堂が佇んでいた。
「ここからは、お前が先導しろ。必要なのは、強い気持ちだけだ」
黒い空気が二人にまとわりつく。海城に渡されたペンチが、ズシリと重い。
「あの御堂の裏手に回るんだ」
右側からな──と、遠くから海城の声が聞こえる。ただ唯一、肩に添えられた手から感じる温もりが、地獄に垂らされた蜘蛛の糸の様に、織先平《おりさきたいら》に希望を与えていた。
一歩一歩踏みしめるたびに、足裏から、悲鳴の様な不愉快な音か闇にこだまする。
朽ちた御堂を左目に見ながら、ぐるりと裏手に回る。
この御堂は……死んでいる。死して尚、埋葬されず、只々、存在だけが求められていた。
裏に回ると、鬱蒼とした雑木林が広がっていた。
手入れなぞされる筈もなく、好き勝手に枝を伸ばし、複雑怪奇に入り組んだ枝葉に、織先の全身が粟立ち、虫唾が走った。
奥から白い物がゆらゆらと近づいてきた。
ぎこちない動きで、あの悲鳴の様な不愉快な音を立てながら現れたのは──異様な姿の神主だった。
エラが強く張る角張った顔にかかる眼鏡は、恐ろしい迄にヒビが入り、奥の瞳が認識出来ない程だった。
煤を全身に浴びたかの様な、その黒く汚れきった服の上に百足が何匹もゾロゾロと這っていた。
両手を添えられ持たれた、朱い漆塗りの立派な盃が、この場には余りにも不釣り合いだった。
「爪を──奉納なさいませ」
男の様な女の様な、若者の様な老人の様な、人の様な獣の様な──声で神主は織先の前にぐっと盃を伸ばし、云った。
幸せを……幸せを……幸せを幸せを幸せを──
ガタガタと震える全身を必死に抑え、呆けた様にぶつぶつと呟きながら、織先は、赤黒く錆びたペンチを握りしめた。
敢えて伸ばし気味にしてきた、左手の爪を見つめる。一体どれだけ奉納したらいいのか……海城と同じ様に、全ての爪を……引き千切るのだろうか……
「あなた様は、多くを望んで、おられない様に、見受けられます。小指二本で、十分でしょう」
逡巡する織先を見兼ねたのか、神主が、雑音交じりの声でそう告げた。
唐突に強烈な吐き気に襲われ、身を折って織先は、その場に吐いた。嗚咽と体液の弾ける音が、周囲に響いた。海城の気配は先程から何故か、感じられない。肩に手が添えられていたにも関わらず、存在が無かった。
一頻り吐き出すと、織先は少し落ち着いた。
よろよろと立ち上がり、左手の小指の爪にペンチを噛ませる。力を加えると、指先に引きつる様な痛みが走った。予想以上の痛みに、織先は叫んだ。
そして──獣の様に叫びながら──一気に、引き千切った。
ぶちぶちと肉が切れる音が、体に響く。未だ嘗て体験した事のない、凄まじい痛みが襲う。ドクドクと左手の小指が脈打つ。激しく震える右手に握られたペンチの先には、織先の爪だった塊が、挟まっていた。
右手が硬直して、ペンチが離れない……このままでは、あの朱色に彩られた盃に、奉納出来ない──
痛む左手でこじ開けようとするが、どうにもままならなかった。
あ……あ……あ……あ……
織先の右手を、そっと優しく包む手があった。
爪のない手──海城の、大きく優しい手だった。
唐突に昔を思い出した。
幼き頃、そう──この公園で怪我をして、織先が今と同じように震えていた時、介抱してくれたのも海城だった。
ペンチが右手から離れ、カランと盃に爪が落ちた──
「先ずは、一本」
──奉納なさいませ、と神主が繰り返す。
海城が手早く織先の左手の小指に、強くハンカチを巻きつけ止血する。そして、無言でペンチを左手に握らせた。
見えなくても織先には分かっている。
旧友は──泣いていた。声を殺し、涙を流している。
──僕だってわかるよ。お前が僕を見つけたように。
織先は、躊躇なく、右手の小指の爪を引きちぎった。
何故か、先程よりも辛くなかった……
nextpage
カラリと二枚の爪が、朱色の盃に転がった。
──承りました、と神主は不気味に笑うと、ぎこちなく雑木林の中に消えていった。
脱力した織先平《おりさきたいら》は崩れ落ちる。多くの血飛沫と、欲望にまみれた悲鳴を、幾重にも吸い続けた地面に膝をつくと、あの不愉快な音がぬちゃりと傷口に響いた。
海城大至《うみしろたいし》に抱かれる様に、織先は朦朧としながら、あの長い山道を歩き続けた。まるで永遠に彷徨うような錯覚に襲われる。例の神社では、子供が走り回っている。其々に思い思いの仮面をつけて、音も無く子供が走り回っている。来る時に揺らめいていた蝋燭が、倍以上に増えていた。
車に放り込まれると、虚ろだった織先の意識は、遂に遠くなっていった──
長い長い夢を見ていたようだった。
その後の全ての処理は、海城大至《うみしろたいし》がこなしてくれた。
接客業だった本職も、自主退社となった。
爪の無い指で接客されたくない──向こう側の言い分は、そんな具合だったと思う。今ではもう、どうでもいい。
幸せとは……何なのか。未だ織先平《おりさきたいら》に答えは見つからない。
恐らく、死の間際に答えが出るのだろう、と、織先は爪の無い小指を見つめながら考える。
相変わらず、黒のスリーピースに身を固める海城は暇なのか、織先のデスクにやたらと現れ、無駄話に興じる。織先は疎ましく、しかし敬意をもって遇らう。
「もう……いい加減に」
──仕事をしてください社長、と織先が云うと、海城はニヤニヤしながら去っていく。
初めは萎縮していた周囲の人間も、今では失笑を隠さなくなった。
──君が来てから社長が明るくなった。
そう直属の上司から云われるが、織先はただ頭を描くばかりだった。
変わったのは環境だけだ。織先の内面は何もかわらない。仕事をし、本を読み、文章を書く。時々、爪の無い小指が痛むくらいだ。相変わらず心は軋む。
只、笑顔が、少しだけ増えた……らしい。
〈終〉



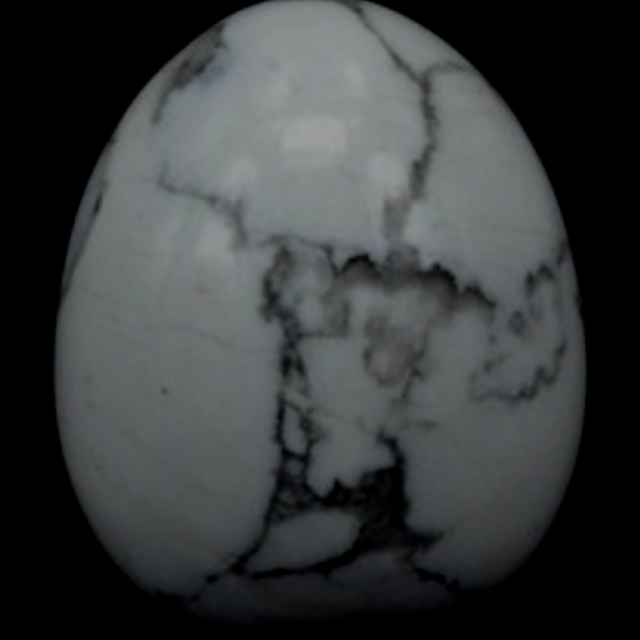

作者退会会員
少しづつ文章を書くことに慣れ、コンスタントに書けるようになってきたあたりの作品です。
といっても今年の話ですが──
文体がいまいち定まってないのは、ご愛嬌。
どうぞお暇な時にでも、読んで頂ければ幸いです。