wallpaper:5408
アルカディアベイ北部には森が鬱蒼と広がっており、その森を切り開くようにコンクリートの道路が永遠と敷かれ、その途中にはネイビーブルーのペンキで塗られたダイナーがポツンと店を開いていた。
店の前にはボロ板が立てかけられており、黄色の文字でオープンと陽気なフォントが描かれている。エンジン音が近づいてくると、一台の車がダイナーの前で停車した。
ドアが開き、男が一人降り立った。さっぱりと髪は整えられ、清潔さを主張する白のシャツに、まだくたびれていることのないブルージーンスがよく映えている。
彼はポケットからキーを取り出すと、車の鍵穴に差し込んで捻った。鍵をかけた彼はそれをポケットにしまいながらドアノブを引き、しっかいと施錠されているのか確認すると、ダイナーの入り口へと歩みを進めた。
消えかかり明滅するパラペット看板に、ネイビーブルーのペンキが塗装された板壁をくりぬくように貼り付けられたガラス窓からは、人気のない店内が見て取れた。
彼が歩くごとにブーツのソールに砂利がはじかれ、小石があちらこちらへと飛んでいった。
砂埃をかぶった入り口前の段差を彼が通り過ぎると、二つの靴跡がくっきりと残って、シャラランという軽快な鈴の音色が響くことで彼が入店したことを知らせた。
彼は入り口から、一番奥の席へと向かった。
そのダイナーは赤の合成皮革が貼り付けられたカウンターシートが十席とテーブルシートが五つ、ウエイトレスは一人だけ、中年の老婆がエプロンを首にかけ応対していた。印象的だったのは、その老婆の乾いたブロンドヘアーは腰まで伸び切っていたのである。
彼はやや不快感を抱いた。彼にとってそれはウエイトレスとして相応しくない格好だった。この老婆は清潔さというものの重要性をまったく理解していない。
彼は呆れつつも一番奥のテーブルシートへ腰を下ろした。席についた彼がまずしたことは、シートを人差し指で撫でることだった。
ほこりが残っていないかチャックしなければならなかったのだ。だがさいわいなことに、彼の指にほこりがこびりついてくることはなかった。もしもほこりがついていたりでもしたら、今すぐこの店を退出しなければならなかった。
彼は人知れずほっとした。一刻も早く空腹を満腹にしたい彼はそれだけは避けたかったのだ。彼のテーブルに老婆がコーヒージャグを片手にやってきた。
「ずっと、ずっと、待ってましたよ」唐突に、ウエイトレスの老婆はしわがれた声を振り絞るようにそう言った。そして、老婆は涙が伝えながらも、彼の傍らにカップが置き、熱々のコーヒーを注いだ。
「私はここが初めてだ。人違いでは」彼は整然と受け答えした。
「ええ、そうでしょう。初めてのはずです」「では、ここにはそんなに人が来ないのか」
彼は老婆が久しぶりの来客を喜んだのだと考えた。
「ええ。まったく」「そうか」
老婆は目元に溜まった涙を指で拭くと、彼に熱々のコーヒーを勧めた。
彼は勧められるがままコーヒーカップを口元へと持っていった。「注文が決まったら呼んでくださいね」老婆はメニューをテーブルに置くと、再びカウンターへと帰っていった。
彼はコーヒーを二口目に差し掛かったところで、その香りを堪能しながら窓の外へ視線を向けた。
前方には深い森の木々が立ち並んでおり、景色は楽しめたものではない。楽しめるものといえばダイナーの前に停車した自慢の車だけだった。
だが、ふたたび彼の癪に障るものが目に入った。その隣、彼の車の隣に停車する車だった。ボンネット一面が砂埃を被り、雨風に晒されたことで腐食している部分も見受けられた。
廃車だろうか。しかし、いったいなぜこんな所に置いておくのだろうか。まったく、景観を汚しているではないか。
彼はむしゃくしゃする気持ちを落ち着けるように三口目のコーヒーを味わった。そして、空いた腹を満たすためにテーブルに置かれたメニュー表へと視線を落とした。
メニューはそれほど多くなく、文字を見るだけで食欲が刺激された彼は、カウンターの老婆に声を掛け呼ぶと、ベーコンエッグとトースト、そしてメープルワッフルを注文した。
老婆は注文をうけたまわると、にんまりと笑みを残してカウンターへ戻っていった。彼はその笑みが妙に不気味に思えた。彼の清潔さに違反する髪を伸ばしきった老婆がそうしたから不気味に感じられたのか。
いづれにせよ、彼がこの店に入店してから満足できていることはコーヒーの香りぐらいだった。
それ以外はすべて “Shit” だったのだ。
カウンターからパチっと油が弾けた音が響いた。フライパンにベーコンと卵が落とされたのか。彼は早くも待ち遠しくなった。
せめて食事ぐらいは満足いくものであって欲しい。香り高いコーヒーを提供できるならば、食事にもそこそこ期待できるだろう。
ジュワジュワとフライパンの上で油がリズミカルに弾み、ベーコンの濃厚な匂いが漂ってきた。そして、さらに匂いは混ざった。
甘ったるいメープルの匂いがベーコンと混ざり合ったのだ。彼の口はもう待ちきれずといったように、よだれがどんどんと溢れ出した。
やがて、チンっとトースターが焼き上がりを告げると、老婆がベーコンエッグ、トースト、メープルワッフルを両手に乗せて彼のテーブルへと届けにやってきた。
老婆は順番にそれらをテーブルへと置いていった。彼にとってそれは待ちに待った瞬間だった。老婆は食事をすべて置き終わると、彼に対してこう言った。「ごゆっくり」
彼は手始めにベーコンエッグを口に運ぶためにフォークですくい上げた。口の中へそれを運ぼうとした。しかし、彼の動きはそこで止まった。
眼前の光景に気を取られたのであった。シャラランと鈴の音色が響いて、なぜか老婆は店の外へ出ていったのである。
老婆は空気を楽しむようにめいっぱい吸い込んだ。
老婆はひとしきりそれを味わった後、車の側まで近づいていった。さきの景観を汚す廃車である。
老婆はキーで扉を開けると、車の中へその身を滑り込ませた。そして、汚いエンジンが吹かされた。
老婆の乗った廃車どうぜんのその車は、砂利から舗装された道路へ。
そして、道路の先へ。走り去っていった。
客を置いて、どこかへ向かうのだろうか。彼はベーコンエッグを口元でお預けにしたまま、その光景を見届けていた。
シボレーのエンジン音が駆け抜けていく。アルカディアベイ北部の33番道路。
そこは森を切り開いた道路で、通過する車を森の木々が見下ろすように監視する曰く付きの道路であった。
「なあ、お前も聞いたことあるだろ」「何を?」
「ここの噂だよ」「やめてよ」
運転席でアクセルを踏む若者が、助手席にすわるガールフレンドを脅かすようにそう切り出した。
「どこにあるかは誰も知らない。それはこの森のどこかにあるらしい」「だからやめてって」
「大丈夫だって」
嫌がるガーフレンドをなだめながらも、若者は話の続きを語り出した。
「この森のどこかには不思議なダイナーがあるらしい」「うん」
「そのダイナーにはルールがあるらしい。まず、客が来たら食事を提供しなくちゃいけない」「それは当たり前じゃない」
「いや、違う。客が客に提供するのさ」「何を言ってるの?」
「くそっ、俺は説明が下手だって分かってるだろ。最後まで聞いてくれよ」「わかった」
「そのな。そのダイナーには店員がいないんだよ」「へえ」
「客が店員になるのさ」「ああ、つまり─。前に入店した客が、次の客に食事を提供しなくちゃいけないってこと」
「そうそうそう。そういうこと」
ガールフレンドは優しく微笑んだ。
「それで」
さっきまで嫌がっていたガールフレンドだったが、彼にその続きを話すように促した。
「怖いのはな。食事を提供しなきゃ出れないんだよ、そのダイナーからは」「そうなの」
「ああ。これは噂なんだけどな。18歳から60歳まで、そのダイナーに閉じ込められていた少女もいるらしい」「ええ、怖いね」
「だろ」
そのとき、甲高いブレーキ音が響いた。車が急停車したのだ。
助手席に座っていたガールフレンドの髪が振られ、停車したあとで彼女はそれを直しながら抗議した。
「なにっ」「いや、あれ」
運転手の彼が指差した方向を。彼女は振り返りながらその方向の先を見やった。森の中に、そこに、ぽっかりと空間ができていて、ダイナーがあった。
車一台が通れる砂利道のすこしさきに、ダイナーがあったのである。「まさかだよなっ」
彼は興奮気味に助手席の窓まで身を乗り出した。彼女は目の前を彼に占領されたことで、仰け反りながらそのダイナーを見ていた。
そこからでもなんとか店内の様子を確認することができた。店の中には赤の合成皮革を貼り付けたカウンターシートとテーブルシートがありごく一般的な作りだった。
しかし、何もかもが汚かった。
それは遠目からでもわかるほどだ。砂埃がべったりとくっついた窓ガラスを通して、使い終わった食器がテーブルに山積みになっているのが見えた。店内はぐちゃぐちゃだ。
店の外には一台の廃車が放置されていた。それは噂にある通りならば、最後の客が乗っていたものなのだろうか。だいぶ、年月が経っているようだが。
そうしてしばらくのあいだ、二人はそのダイナーへ注目していた。そんなときだった。「あっ」
ガールフレンドが驚きの声を発して、隣で見ていた彼も黙っていたがその存在を確かに視界に捉えていた。
その店内には老人がいたのである。ぼさぼさの長髪の間からこちらを見つめる老いた男性。
老人はぼろぼろの布切れを纏っていた。
おそらく、それはシャツだったのであろう。黄ばでいて、破れていて。それは着ていると表現できず、纏っていると表現するしかなかった。
老人の口元から生えるひげは胸元まで伸び切っていた。下半身は─。下半身は何も履いていなかった。「いやだ」
彼女もそれに気づいたようで、両手で顔を覆った。彼は安心させるために、彼女を抱き寄せた。だが、視線はそいつを捉えたままだ。
そして、老人は─。
老人は手招きした、ゆっくりと、ゆっくりと。
それは喋り方を忘れた人間のようにぎこちなく、ゆっくり、ゆっくり。
やがて─。
老人は猿みたいにはしゃぎだした。
そして、がさがさにしゃがれた声でこう叫けびだした。
「おいでぇぇぇ」
彼女は耳を塞いだ。
「おいでぇぇぇ」
そして、その後も。
「おいでぇぇぇ、おいでぇぇぇ、おいでぇぇぇ」
ずっと、あいつは呼び続けてた。
それは森の中で不気味に響いていたんだ。

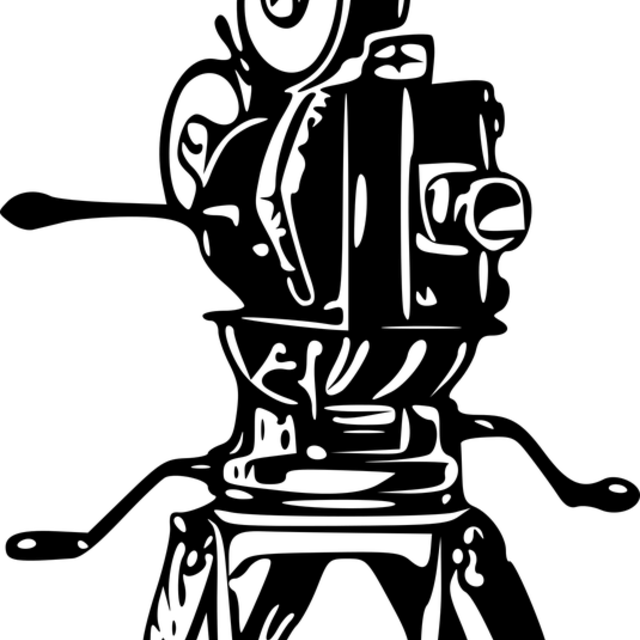
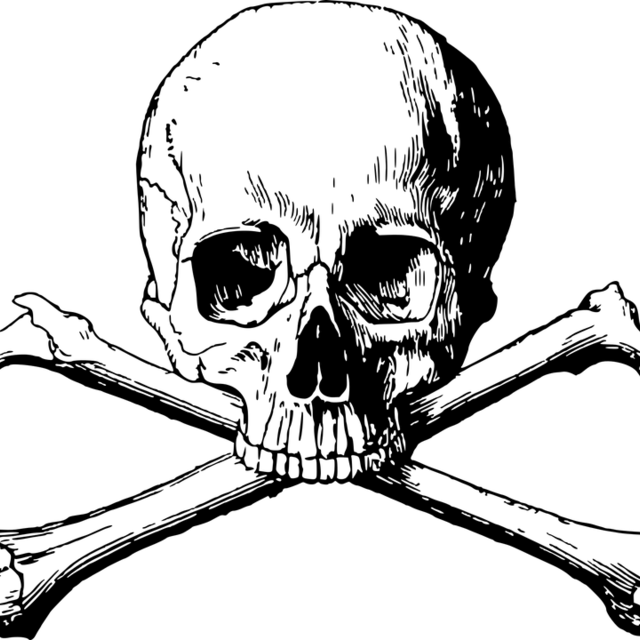
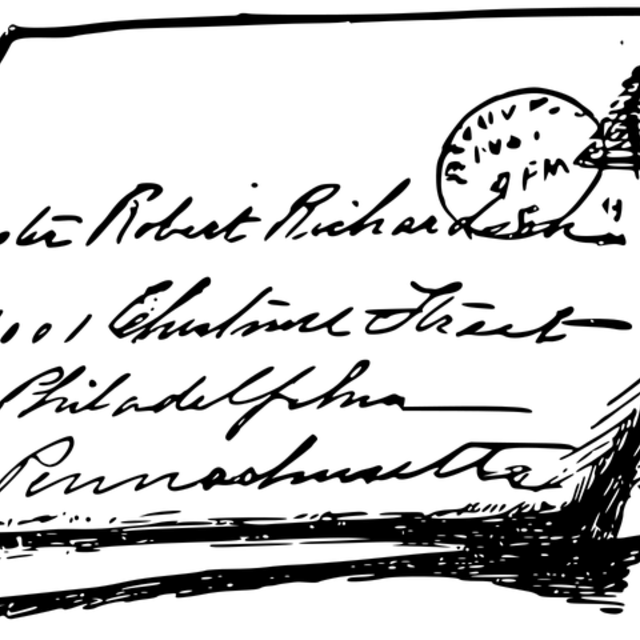
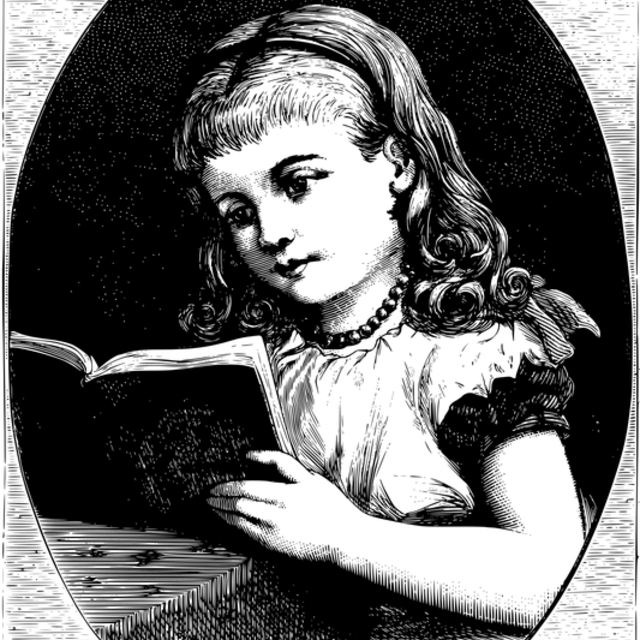
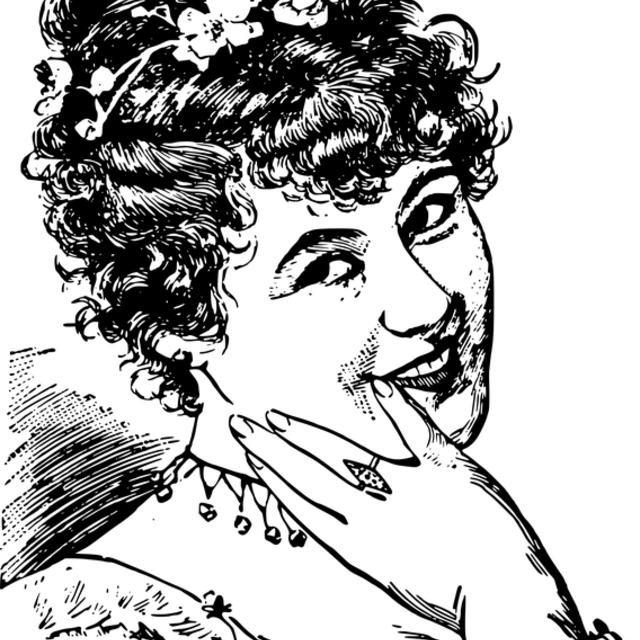
作者Yu