この世ならざるもの。いわゆる幽霊や妖怪の類。到底理解しがたいその存在をいったいどれだけの人が信じているのだろうか。おそらく、非現実的なことだと、非科学的なことだとバカにして信じない人がほとんどだ。
今だって目の前にいるかもしれないのに、そうとは気づかずに背後をとられ、寝首をかかれ、足元をすくわれ…。そうやって知らず知らずのうちに闇に呑まれていった人が果たしてどれだけいるのだろうか。幸い、私はまだ闇に呑まれた人を見たことはない。
ところで、さも幽霊や妖怪が本当にいるかのような私の口ぶりだけれども、なんとなんと驚くなかれ、幽霊も妖怪もしっかりとこの世に存在しているのだ。
あっ、誤解しないでほしいのだけれど、別に私は頭がおかしくてこんなことを言ってるわけじゃない。そう断言できてしまう理由があるのだ。
理由というのは大学の友人たちと心霊スポットに訪れた際、私がそれにとり憑かれてしまったことがきっかけだった。
自殺の名所として有名だった廃屋には、人々の負の想像で生まれた怪異がいて、私は運悪くそれにとり憑かれてしまった。当然見えない私には成す術もなく、ただただ恐怖におびえ、震えていることしかできなかった。
だけどそんなとき、私を見えない脅威から救ってくれた人がいた。その人こそが私に怪異の存在を知らしめてくれた張本人であり、アルバイト先の常連さんでもある椥辻生雲(なぎつじいくも)さんという人だった。
椥辻さんはいわゆる見える人で、その風貌は全身黒尽くめの服装に長い前髪で片目を隠しているから、見るからに怪しげだけど、いつもにんまり笑顔を崩さない穏やかで優しい人だ。
彼が所持している怪しげな日本刀はそれらを祓える不思議な力をもっているらしく、私に憑いた怪異もその刀で見事に祓ってくれた。
まあ、要するに霊能力者のような人だと思うのだけど、どうやらそうではないらしい。本人いわく骨董蒐集が趣味の普通の男、だそうだ。見ることができて祓うこともできるのはもうそれだけで普通じゃないと思うのだけれど。
ともかく、こうして私は椥辻さんと出会ったことで不可思議な世界へと足を踏み入れてしまったわけだ。
そして今回、私はさらに不可思議な現象に遭遇し、椥辻さんの凄まじい力を目の当たりにしてしまった。それは彼がちゃんと本物で、怪異もしっかりとこの世に存在しているんだと、あらためて実感させてくれる出来事であった。
〇
おとといから7月になって、それまでの肌寒さが嘘のように暑くなり、いよいよ夏の到来を感じさせる今日この頃。けれども相変わらず骨董品店米納津(よのづ)屋はカンコドリが鳴いていた。
今年の初め頃からアルバイトとしてお世話になっているこのお店は、築年数がだいぶありそうな店舗兼住居の木造2階建ての一軒家で、その古い佇まいはなんだか実家に帰ってきたような居心地のよさがある。
骨董屋さんと聞くと物でごちゃごちゃしてるイメージだけれど、ここはだいぶ違ってキレイにこじんまりとまとまっている。骨董屋さんというよりは小さな美術館みたい。
そんなお店で私がすることのたいはんは清掃なのだけど、すっきりとした内装のおかげで掃除は楽だし、うっかり体がぶつかって高価な物を落としてしまうハプニングもないから安心だ。
ちなみに今現在、私はその業務を終えて店番の最中。店主の米納津さんはお座敷の奥に引っ込んで事務作業をもくもくとこなしている。
ここは常連さん以外ほとんどお客さんがないので、必然的に暇な時間が多くなる。楽なのはいいけれど、こうしてなにもしてないあいだもお給料が発生してると思うとなんだか申し訳がない。
ほどなくして暇をもてあまし、指紋のぐるぐるを目でなぞって遊んでいると可愛い小鳥のさえずりが店内に響いた。「まさかカンコドリが」と顔を上げると、かざられている鳩時計の時報であった。
時刻は3時。
すると奥から米納津さんがやってきて、お店と住居をへだてる暖簾をめくってひょこりと顔をのぞかせた。
「すまん春ちゃん、時計見とらんかった。おやつ休憩にするが、そろそろ饅頭が切れそうだからその前にお遣い頼むよ」
このお店では3時のおやつ休憩も大事な業務のひとつに組み込まれている。玉露のおいしいお茶をすすりながら買い置きしてあるおまんじゅうを頬張るのがいつもなのだけど、おまんじゅうが切れそうになるとこうしておつかいを頼まれる。
ちなみに春ちゃんとは私、金浦春(このうらはる)のこと。
「米納津さん。おまんじゅう買いだめしないで、私がいないときはお散歩ついでにご自分で買いに行かれたらどうです?出不精は健康によくないですよ」
「何を言うか。この間銀行まで歩いたぞ。しかも二回も往復したんじゃ。二回も」
「こないだって先週のことじゃないですか。毎日歩きましょうよ。それに2回往復したのも米納津さんがお約束でお財布忘れたせいじゃないですか」
「お約束」というのは、米納津さんが出かけるたびに毎回お財布を忘れてしまうのだ。普段はしっかりしているのに、変なところが抜けている。
米納津さんは「はいはい」と軽く手を振ると再びお座敷に引っ込んでしまった。米納津さんのことを思って言ってるのに、いつもこう。ほんとに頑固。とはいえ、たまのおつかいで食べられるみたらし団子が楽しみのひとつでもあるので致し方ないか。私はおつかい用のがま口財布を手に取ると颯爽とお店から出ていった。
外はセミがちらほらと鳴きはじめ、吹く風は生暖かく、少し汗ばむような陽気だった。そんな中、これから向かうのは老舗和菓子屋の今生津(いもづ)屋さん。米納津屋からは徒歩でおよそ10分くらいの距離だけれど、あのお店の絶品みたらし団子が食べられると思うと足取りも軽い。
駅前の大通りを通り過ぎ、入り口に鳥居みたいな形をした大きなゲートがそびえる商店街を通り抜け、目の前の横断歩道を渡ってすぐの呉服屋さんから3軒先の角を左へ曲がって真っ直ぐ進む。すると古めかしくも立派な佇まいの今生津屋さんが見えてきた。
その古風な外観に似合わない現代的な音を立てながら扉が開くと、涼しい風と共に上品な甘い香りが鼻の中いっぱいに広がり、ショーケースに並べられた和菓子たちが放つ魅惑の輝きに目がくらんだ。外に比べたらここは天国だ。
買い物を済ませてすぐに帰ろうと思ったのだけど、その居心地のよさも手伝って店員のおばちゃんとの世間話に花も咲き、気づけばもう3時半を過ぎようとしていた。いやはやいつもこうして長話してしまう。私はおばちゃんにお別れの挨拶をすると、お茶菓子の入った豪華な紙袋を片手に今生津屋さんをあとにした。
帰り道は気持ちばかりの早歩き。米納津さんをお待たせしてしまうのは申し訳ない。けれどお店に到着して時刻を確認するといつも通り10分くらいで帰ってきてしまった。早歩きとはなんだったのか。気持ちばかりだから仕方ないか。それよりもお待ちかねのおやつタイムだ。
うきうきでお店の引き戸に手をかけようとしたその時だった。がらっと勢いよく戸が開き、灰色のスーツと趣味の悪い柄のネクタイが目の前に飛び込んできた。
おそるおそる顔を上げると、黒縁メガネになんだか偉そうなおヒゲを生やした中年の男性が立っていて、吊り上がったするどい目つきで私をギロリとにらみつけていた。
「…何か?」
男は低い声でずいぶんと不機嫌そうに言った。
「あ、ごめんなさい…」
男は「ふん」と鼻を鳴らすと呆気に取られて立ちすくむ私の肩にわざとらしくぶつかり、何も言わずにそのまま行ってしまった。通せんぼしちゃった私も悪いけど、なにもそこまでしなくても…。
なんだか気分が悪いままお店に入ると、米納津さんが物珍しそうにガラスの魚をながめていた。小ぶりのアジよりちょっと大きいくらいだろうか。よくおじいちゃんが釣ってきたなあ。たぶん、さっきの人から買い取ったんだと思われる。
「それ、今出てった方のです?」
「ああ、そうじゃ。いやあ…春ちゃん、こりゃ凄いぞ」
興奮気味に言うけれど、宝石とガラス玉の区別もつかない私からしたら何がすごいのか全く理解できなかった。それに近くでよく見ると表面には傷があり、そのせいか輝きも濁って汚い。
そしてさらなる違和感に気づいたのは、くるっと回して反対側を確認したときだった。こちらのほうだけやけにウロコの表現がリアルなのだ。グリルステーキみたいな可愛いデザインに対し、こちらは1枚1枚貼りつけたような丁寧で繊細な作り。とはいってもそのウロコも2枚欠けているので、やはり状態がよくない粗悪品に見えてしまう。
「米納津さん、これって傷もあるし、デザインも左右非対称だし、ウロコも2枚ないし…、もしかして粗悪品じゃないですか?」
「馬鹿を言うな。それが『味』と言うやつじゃ。ジーンズだってそうじゃろう」
ジーンズはジーンズだから色落ちや傷が味になるのであって、こういうのはまた別の話じゃないだろうか。まあ、とりあえずは「味」ということにして納得しよう。骨董とは奥が深いのだ。素人はだまっていよう。
結局その日、米納津さんは魚がよほど気に入ったのか、私が帰るまでずっとそれを愛でていた。しかしなんだかその愛で方が異様というか異常というか。米納津さんのいつもと違う様子が少し不気味に思えた。
なんだかそれが何かにとり憑かれたように見えて、私は「もしかして…」と思ってしまう。数が少ないとはいえ、お店での経験をふまえると私は疑ってしまうわけだ。
「まあ、まさかね…。気のせい気のせい」
帰途、揺られるバスの中で私は自分にそう言い聞かせた。
〇
私の下宿先は富士浪(ふじなみ)市足袋広(たびひろ)の国道沿い近くに建つ、パステルグリーンが特徴的な3階建ての可愛らしいアパートだ。
まわりは田舎というほど落ち着いているわけでも都会というほど騒がしいわけでもなく、ほどよく栄えてほどよく落ち着いたほどよい町である。
最寄りの富士浪駅まではバスでだいたい15分ほどで、米納津屋もその駅の近くにある。大学は富士浪駅から電車で2駅行ったところにある北茅野(きたかやの)大学前駅を降りればすぐそこだ。
交通の便もよくてコンビニも近い。こんな何不自由なく、ほどよいところに住めた私は運がいい。紹介してくれた伯父さんには感謝しかない。
ちなみに今日は大学もアルバイトもお休みなので、午後から優雅に富士浪駅周辺でお買い物を楽しんでいる最中だ。
ひととおり買い物を終えた頃にはすっかり日も傾いて、向こうの空はほんのりオレンジ色に染まっていた。帰る前に何かお腹に入れていこうかとうろうろしていると、カランコロンとゲタの音が聞こえた。「もしかして」と思い、建物の角から顔を出すと、お店の常連さんを発見した。
常連さんというよりは米納津さんのお友達と言った方が正しいかもしれない。米納津さんとは古い付き合いらしく、月に1、2回くらいだけどお店にひょっこり顔を出しては、いつも2人で将棋をさしている。
今日もいつものように小説家の先生みたいな和装にオシャレな中折れハットをかぶった素敵ファッションで、しかしなんだか顔色は優れない様子だった。
具合でも悪いのだろうか。声をかけようか迷っていると向こうが私に気づき、「あっ!」と声を上げると、カラッカラッとゲタを鳴らしてこちらに走ってきた。具合が悪いわけじゃないみたい。そうして挨拶もそこそこに私に訊ねてきたのだ。
「六郎(ろくろう)ちゃん、何かあったのかい?」
六郎ちゃんとは米納津さんのこと。訊かれた私はなんのことか分からず首を傾げると、「あの不細工な鼠が描かれた粗悪品だよ」と常連さんは続けた。
聞けば米納津さんが歪で芸術性のかけらもない粗悪品を蒐集し、それにありえない金額をつけて売り出しているというのだ。いったい私が休んでいたわずか2日のあいだに何があったんだ。
とにかく私は現状を確認するために常連さんと一緒にお店に向かったのだけど、確かにひどいありさまだった。小規模ではあるけれど、お店の一角がフリーマーケットみたいな雑多なスペースに様変わりしていたのだ。
急須に花瓶、靴下に目覚まし時計、マグカップに電気スタンド、ペンケースにランチョンマットなどなど。その統一性のない歪な品々全てに不細工な鼠のイラストが描かれており、ここだけ見るとネズミグッズを専門に扱う雑貨屋さんのようだった。そして常連さんの仰る通り結構なお値段である。
「なんじゃ、また来たんか」
暖簾の向こうから顔を出した米納津さんが呆れたように言った。
「何度だって来るぞ。お前さんが目を覚ますまではな」
常連さんがそう返すとどこかで「カーン」とゴングが鳴った気がした。そしてそれを合図に2人は私にお構いなしで口喧嘩を始めてしまったのだ。
「お前の目は節穴か。こんな物に一銭の価値もないだろ」
「節穴はお前の方じゃ。目ん玉に穴ぼこでも空いとるんじゃないか」
「頭でもおかしくなったか!医者にでも診てもらえ!」
「お前こそ医者に行け!」
怒りのボルテージはどんどん上がっていき、声のボリュームもだんだん大きくなり、互いのおでこがくっつきそうなくらい距離はみるみる縮まっていく。このまま放っておくと殴り合いの喧嘩になりそうだ。私は意を決して2人のあいだに割って入ることにした。
「おふたりとも落ち着いて!」
私の言葉に2人は「んー」と唸るとしばらくにらみ合い、
「…春ちゃんに免じて今日は許してやるわい」
と米納津さんはそのままお座敷に引っ込んでいき、その背中に向かって常連さんは、
「次は容赦せんからな」
と、吐き捨てるように言った。ひとまず喧嘩はおさまってくれたみたいだ。安堵していると常連さんが深いため息をつき、踵を返すとそのままお店から出ていこうとするので、私もお見送りのためにあわててあとについて行った。
「春ちゃんと言ったかな」
表に出ると常連さんが私に向き直ってそう訊ねた。
「はい、そうです。金浦春です」
「うむ…。すまんが春ちゃん、私が言っても聞かないだろうから、医者に診てもらうようあいつに勧めてはもらえないだろうか」
常連さんはずいぶん深刻そうだった。確かに何かの病気ならそれは一大事である。
「米納津さん、もともと何か患ってらっしゃるんですか?」
「あいつは昔から病気知らずだよ。出先で財布を忘れた事に気づく位のおっちょこちょいではあるが、しかしあんな素人でも分かるようなガラクタに高値をつけるなんて、脳に異常があるとしか考えられん」
ああ、先月の銀行振込みのときもそうだったけど、その他用事で出かける際、もろもろが入ったお財布を堂々と忘れて出かけるあれは昔からだったのか。
しかしながら常連さんの仰る通り、あれらに1円の価値もないのは素人の私にもわかるくらい明白だ。あのランチョンマットなんて私が作った方がいくらかまし。
常連さんはまた大きなため息をつくと、「またしばらくしたら様子を見に来る。頼むよ」と言い残し、カランコロンとゲタを鳴らして帰っていった。心なしかゲタの音も悲しく響いている気がした。
それからお店に戻ると米納津さんが「帰ったか?」と、ばつが悪そうに顔をのぞかせた。一見どこも悪そうには見えないけれど、やっぱり外見だけじゃわからないな。とにかく私はこの2日間でいったい何があったのか訊ねることにした。
するとどうだろう。2日前にガラスの魚を持ってきたあの男がこの粗悪品たちを何度も何度も売りにきたというのだ。見た目からして怪しいヤツとは思っていたけれど、こんなお年寄りをつかまえて粗悪品をムリヤリ押しつけるなんて信じられない。
きっと米納津さんは粗悪品とは理解しつつも、あの男から脅されて仕方なくこれらの粗悪品を買い取ってしまったんだ。そうでなければこんな物、米納津さんが引き取るはずがないもの。
「そうですよね、米納津さん!」
「馬鹿を言うな」
米納津さんはそう言って私に一喝いれると、手袋を両手にかっちりとはめて粗悪品を丁寧に手に取り、声高らかに、そして長々と語りだしてしまった。
「見ろ、この光沢」
「見ろ、この曲線」
「見ろ、この色彩」
小一時間、粗悪品1つ1つの素晴らしさについて熱弁されたけれど、そのよさに関して何一つ理解できず、米納津さんがおかしくなってしまったことはちゃんと理解できた。
確かに常連さんが仰る通り、米納津さんは何かの病気なのかもしれない。脳に異常があるなら病院に連れてく必要がある。なにかあってからでは遅い。
「米納津さん、お医者さんに診てもらいましょう」
「医者?馬鹿を言うな。ワシは見ての通りピンピンしとる。病気なんてどこにもない」
病気ってそういうものなんです、米納津さん。
それから病院に行かせたい私と、病院には行きたくない米納津さんとの押し問答がしばらく続き、気づけば日は完全に沈んで辺りはすっかり暗くなっていた。
こういうとき老人ってほんと頑固。そういえば私のおじいちゃんも病院嫌いで、血を吐いて倒れるまでお医者さんに行こうとはしなかったな。私から見たら「病院嫌い」というよりは「病院怖い」って感じだったけど。
結局その日、米納津さんをお医者さんへ連れて行くことはできなかった。明日もアルバイトは休みだけど、もう一度米納津さんを説得しに行こう。私は帰りのバスの中でそう決心した。
しかし心のどこかで「本当に病気なんだろうか」と疑問に思っていた。こういった症状を一括りに「病気」として片づけてしまうには、ここ最近の経験上やっぱりできないわけだ。病気以外に原因があるとするならば、可能性は1つしかない。それは…。
———怪異現象。
もしそうだとしたら…、米納津さんがおかしくなってしまった原因が幽霊や妖怪の仕業だとしたら、米納津さんをお医者さんに診てもらったところで意味はない。もしそうなら、またあの人の助けが必要になるわけなのだけど…。
〇
午後の講義を終え、私はすぐに米納津屋へ向かった。昨日の内に脳神経内科の病院がどこにあるかはチェック済み。泣き落としのための目薬も薬局で購入済み。最悪ムリヤリでも引っ張り出すための縄も準備しようかと思ったけれど、縄に苦い思い出のある私にそれは無理だった。
とにかく怪異の可能性は一旦置いておくとして、病気だった場合のことを考えると症状がこれ以上ひどくなる前になんとかしなければいけない。
しかし、状況はさらに悪化していた。
お店に入って飛び込んできた光景に私は自分の目を疑った。なぜなら米納津さんが恍惚とした表情でバケツを愛でていたからだ。いや、ただのバケツならまだいい。まだいい、なんてことはないけど、それがボコボコでサビにまみれ、底に穴が空いて本来の役割なんて到底果たせそうもないガラクタであった場合、話は別である。
「米納津さん…、なんですかそれ?」
私が声をかけると米納津さんは「うおう!」と驚きの声をあげた。どうやらバケツに見惚れて私に気づいてなかったらしい。
「ああ、これは例の鼠色の背広の男がな…。美しいじゃろ?」
美しくないです。それはもう粗悪品ですらないただの粗大ゴミです米納津さん。
「しかし春ちゃん、今日は午後も授業の日だから休みじゃろ。いったい何の用…」
米納津さんは言い終わる前に、私がお店を訪ねた理由を察して眉をひそめた。そして勢いよく立ち上がると、「ワシは医者には行かんぞ!」とお座敷に引っ込んでしまった。ああ、もうほんと頑固。
しかしまあ、いよいよ以てこれはおかしい。物の善し悪し以前にゴミかどうかの判別もできないくらい、米納津さんはおかしくなっている。ここまでくるとやっぱり病気よりも怪異現象を疑ったほうがしっくりくる。
だけど、そうだとしたら私にはどうすることもできない。例えば米納津さんに塩をまくとか、お酒を吹きかけるとか、店中そこかしこに線香を焚くとか古典的なことは思いつくけれど、果たしてそんなことをして効果があるだろうか。それともこんな私でも、念仏を唱えれば多少の効果が…いや、ないか。
あらためてバケツに目を落とす。なんとまあ、どこからどう見てもただのガラクタだ。赤茶のサビは元々そこにあったみたいに偉そうにこべりつき、投棄された場所の名残りなのか、底の辺りなんかは青々とコケむしている。
こんな物のどこに美を感じるのだろう。もしかして私のほうがおかしいのだろうか。そうか。これはきっと美しいバケツなんだ。
「わあ、なんて美しいバケツ」
と一瞬思ったけど、「いや、そんなわけない」とすぐ正気に戻った。しっかりしろ私。
はあ、なんで私がこんないっぱいいっぱいになんなきゃいけないの。もう意味わかんないよ。…泣きそうです。
「変わりはないかな」
「ぃひゃあっ!」
突然耳元でささやかれ、みっともない悲鳴を上げてしまった。あわてて振り返ると、なんとそこにいたのは椥辻さんだった。
「な、椥辻さん…!いつからそこに…」
「今さっき。何度も声を掛けたんだが…」
相変わらずの真っ黒な服装に怪しげな刀袋を背負い、顔の右半分がすっぽり隠れてしまうくらいのさらさらで長い髪。その装いのおかげで不気味に思えるにんまり顔だけれども、今日は女神が微笑んだように輝いて見えた。
「そ、それはすいませんでした。ちょっと色々ありまして考えごとを…」
「そうかい」
なんて素敵なタイミングで登場してくれたのだろう。今まさにあなたの力をお借りしたいと思っていた所存でございます。
「それより…」と、前屈みだった椥辻さんは姿勢を戻すとバケツを指しながら、
「暫く来ない間に、廃品回収の仕事でも始めたのかい」
「あの、実はそのことで椥辻さんにご相談がありまして…」
するとお座敷の奥からどたどたと足音が近づいてきた。悲鳴を聞いた米納津さんがあわてて様子を伺いにきたらしい。「どうした!」と心配そうに飛び出してきたけれど、その表情は椥辻さんを見るなり一瞬で嬉々としたものに変わっていた。
「生雲!これ!これを見てくれ!」
米納津さんはバケツを手にすると、椥辻さんに自慢するようにそれを掲げた。それが子供のように無邪気で、とてもとても無邪気で…、だからすごく気味が悪かった。
「成程…。また厄介なモノに憑かれたね」
「え…」
今、椥辻さんは「憑かれた」と言った。ならやっぱり米納津さんは病気じゃなくて、何か悪いものにとり憑かれてるんだ。
「椥辻さん!米納津さん急におかしくなっちゃって…。お願いします!助けて下さい!」
救いを求める私に椥辻さんは、「勿論」と屈託のないにんまり笑顔で答えてくれた。するとおもむろにポケットからタバコとオイルライターを取り出し、なんの躊躇もなく火を点けてしまった。ここ禁煙なのに。
「生雲!ここは禁煙じゃ!」
そうです禁煙なんです。けれど椥辻さんは米納津さんの言葉に耳を貸さず、カチンと気持ちのいい音を鳴らしてライターを閉じると、それをポケットにしまった。
「少し下がってて」
そう言うと椥辻さんは深く、深く煙を吸い込んだ。そしてタバコをくわえたまま胸の前で、パンっと音を鳴らして両手を合わせた。その瞬間、椥辻さんの体中からドライアイスみたいに、もくもくと真っ白な煙が噴き出したのだ。
「な、椥辻さん!?」
私は慌てて椥辻さんから距離をとるように後退った。
「取り敢えず、話を聞く前に米納津さんを何とかしないとね」
椥辻さんがまとっていた煙はタコの足みたいに米納津さんのほうへ伸びていき、あれよあれよという間に全ての煙が米納津さんを包み込んでしまった。
果たしてこれは現実なのか。想像をはるかに超える光景に私は再び自分の目を疑った。この人は普通じゃないと思っていたけど、これはもう本当に普通じゃない。
「なんじゃこれは!」
米納津さんはバケツを庇いながら、60過ぎとは思えないキレのある動きで煙を振り払おうとしていたけど、煙相手にそれはまったく意味をなさなかった。それよりも、このまま暴れ続けると大事な骨董品までガラクタになってしまう。
「米納津さん、悪いけど大人しくしてくれるかな。自らの手で瓦落多を増やしたくはないだろう」
米納津さんは「んー」と小さく唸って椥辻さんの言葉に素直に従った。煙の中でぜーはーぜーはー肩で大きく息をする米納津さんは、影絵みたいに黒いシルエットではっきりと確認できた。
「椥辻さん、この煙はいったい…」
私が訊ねると椥辻さんは、「あの鼠を捕まえる為にね」と煙の中を指さした。私が知りたかったのはどうやってあの煙を操っているのかということだったのだけど、確かに指し示す先、米納津さんのちょうど頭の上に狼狽するネズミの影が見てとれた。
「ネ、ネズミ?」
すると椥辻さんはその手を目一杯開き、そして今度は力強く握りしめた。同時に煙が渦を巻いてネズミの元へ集まっていくと、あっという間に小さな球体になってネズミを包み込んでしまったのだ。
「ガシャーン」とバケツの落ちる音が店内に響きわたって、見ると米納津さんが耳、鼻、口からもくもくと煙を吐き出しながら床に倒れていた。あわてて駆け寄ると、どうやら気を失っているだけのようだった。
「その内目を覚ますから、心配しなくて大丈夫だよ」
椥辻さんはネズミを捕らえた煙玉を粗悪なネズミグッズが置かれた一角にそっと並べながら言った。それから私達の前にやってきてその場に片膝をつくと、真っ白な煙をくゆらせながら米納津さんの顔をぐいっとのぞきこんだ。
私たちの周りを漂う煙からはタバコの嫌な臭いはせず、ほんのりとペパーミントのいい香りがした。たぶん、普通のタバコじゃないんだろうな。
「米納津さんがおかしくなった原因って、あのネズミのせいなんですか?」
「あれは只の目印。原因はこっちだね」
椥辻さんは左手で米納津さんのまぶたを開くと、右手のひとさし指の先でそっと瞳に触れた。息を呑んで見守っていると、今度はその指先を蛍光灯に向かってかざしてみた。すると指先がぼわーんと光が屈折したみたいに歪んで見えたのだ。
「見えないけど、何かあるのはわかります。なんですか?」
私はなぜか驚くほど冷静だった。たぶん、さっきの妙技に比べたら指の先が歪むくらい大したことない、なんて思ったのかもしれない。椥辻さんは自分の指先をしばらくながめ、それからゆっくりと口を開いた。
「…魚の鱗だね」
ウロコ?なぜウロコ?一瞬わからなかったけれど、あのときのことを思い出して「あっ!」と大きな声を上げた。それから急いでお座敷に上がって2階へ駆けあがり、米納津さんがお気に入りの骨董品を保管してる秘密の部屋へ入った。
———あった。ウロコの欠けたガラスの魚。それを抱えて戻ると椥辻さんが、「成程ね」と何か納得したようにうなずいた。
「そのまま持っていて」と、椥辻さんがウロコの欠けた部分に指先でそっと触れてみた。すると指先からインクが滲むように濁ったウロコが姿を現し、それがぴったりと欠けた箇所に納まってしまったのだ。異様な光景のはずなのに、私は「わあ」と感嘆の声をもらしていた。
そのとき、ふと椥辻さんと初めて会ったときのことを思い出した。あのとき椥辻さんは「人々の想像から怪異は創造される」と言い、その中には言葉遊びで誕生してしまう怪異もあるのだと教えてくれた。だからこれはきっとそういうことなんだと思ったのだ。
「これって『目からウロコが落ちる』ってことですか?」
私の言葉に椥辻さんはどこか感心した様子だった。
「そういう事だね。『目から鱗が落ちる』の言葉通り、怪異的に人の目から生じた鱗だ。とは言ってもこれは米納津さんに元々付いていた鱗ではなく、何処ぞの人間から剥がれ落ちた、要は他人の鱗。因みにそれ、その鱗を保存する為の魚の置物だよ」
椥辻さんが魚の頭を指で軽くはじくと、こんっと鈍い音がした。
「ウロコを…保存?」
「この鱗の様に、人の体から怪異的に生じたモノを集める変わった蒐集家が居るんだよ。目の上の瘤とか、耳の胼胝とか…、珍しいモノだと喉から出た手とか、一皮剥けた人の抜け殻とか、まあ色々とね」
想像して寒気がした。要するに蛇の抜け殻、象牙や虎の毛皮なんかと同じことだろうか。そういう要領で人の体から剥がれ落ちた物を集めるなんて、言っちゃ悪いけど悪趣味だ。
「…そんな変わった人がこの世にいるんですね。やっぱり見えてる人は私たちと———」
椥辻さんは「いや…」と私の言葉をさえぎると、にんまり顔を崩さず続けた。
「集めているのは妖だがね」
〇
結局、米納津さんがあんな状態なので私の判断でお店は閉めることにした。閉めるとはいっても私にできることは「商い中」の掛札をうらっかえすくらいであっという間だった。とりあえず米納津さんになにが起きたのかは客間でゆっくりと話すことになった。
米納津さんは椥辻さんにおまかせして、私はお茶を淹れに台所へ入った。ヤカンに水をはって、それを火にかけて、お茶っ葉の入った缶と買いだめしてあったおまんじゅうを棚からおろして、そうやって忙しなくしていると昂っていた気持ちがだんだんと落ち着いてきた。
ずいぶんとすごいものを目撃してしまった。疑ってたわけじゃないけど、やっぱりあの人は本物なんだ。神秘的な光景だったな、あのウロコ。それにあのネズミ。シルエットとはいえ初めてこの目で怪異を見てしまった。それからタバコを使ったあの妙技。すごかったなあ。
さっきの出来事を振り返っていると「ぴゅー」っとヤカンが湯気を噴いて鳴き出した。さっきの煙と比べるとささやかな薄い煙だ。あれはいったいどういう仕組みなんだろう。訊いてみたいけど、訊いたら迷惑だろうか。
「手伝おうか」
ヤカンが悲鳴を上げ続けたままだったので椥辻さんが心配して様子を見にきてしまった。
「ああ、ごめんなさい。ぼーっとしちゃって…。今お茶とおまんじゅう持っていきますから」
椥辻さんは、「そうかい」と返事をしつつも視線はおまんじゅうのほうに向いていて、「じゃあ饅頭は僕が持ってくよ」とおまんじゅうの入ったうつわを持っていってしまった。好きなのかな、おまんじゅう。
お茶をもって客間に入ると、中央に置かれたちゃぶ台の上にガラスの魚が鎮座していた。いわくの品と知ったあとだと、その鈍い輝きが不気味で後退りしてしまう。
「ああ、悪い。今退けるから」
私は椥辻さんが魚を畳みの上に下ろしてくれるのを待って、湯呑みをちゃぶ台に並べた。
「有難う、頂くよ」
椥辻さんはお茶をすすると小さくため息をついた。私も対面に腰をおろし、ならうようにお茶をすすった。なんだろう。椥辻さんの前だとよくわからない緊張感が体中をかけめぐって仕方がない。
それから私はここ数日このお店で起こったことについて、知っている限りのことを話した。しっかり細部まで目撃したわけではないので、ほんとに知ってる限りのことしか説明できなかったけれど。
「———だからたぶん、その男の人が知っててそのガラスの魚を米納津さんに売りつけたと思うんです。もしかしたら、椥辻さんと同じで見える人なのかもしれないです」
私の話が終わると椥辻さんは再びお茶をすすり小さくため息をついて、それからほんの少し沈黙が続いた。たった数秒だけど、その少しの静寂のせいでせっかく和らいでいた緊張感が再び戻ってきてしまった。
こうして向かい合って座っていると、悪いことをして母親から怒られてる子供みたいな気持ちになる。私、悪いことしてないのに。
そして数秒後、静寂を破るように椥辻さんは口を開いた。
「…やはり、米納津さんがああなったのはその鼠の仕業だね」
「え?ネズミって…、米納津さんがおかしくなったのってウロコが原因じゃなかったんです?」
「そう、原因は鱗。元凶は鼠の方だ」
「ネズミって米納津さんの頭に乗っていたあのネズミです?でも、このガラスの魚を持ってきたのは背広の男性ですよ。だからきっと———」
「だから其奴だよ」
椥辻さんは私の言葉を遮るように言った。
「そいつって…」
「君が見たって言う、黒縁眼鏡に偉そうな髭を生やした背広の男」
「…えっ?」
椥辻さんはとんでもないことをあっさりと言ってのけた。そして呆気に取られている私を気にする様子もなく、美味しそうにおまんじゅうをひとくち頬張った。
「…あの人が、妖怪?でも、…どこからどう見ても人間でしたよ」
「聞いた事ないかい?人を化かす狐や狸の怪異譚。それと同じ類で、…、其奴は人に化けた鼠だよ」
「人に、化けた…」
ゆっくりと自分の肩に視線を落とす。あのときぶつかられた感触が生々しく蘇ってきて、同時に悪寒が肩から全身へとかけめぐっていった。なら、もしかして…。
「あ、あの…、私、その…そのネズミに、肩ぶつかられて…」
「そう、それは失敬な奴だね」
「いや…、あの、そうじゃなくて…、もしかして、私にもなにか悪いものが…」
「ああ、そういう…。安心して、君には何も憑いてない。もしそうなら僕が既に対処してる」
ああ、言われてみれば、そうか。とはいえ私の肩はこわばったまま、左手はぶるぶると震えが止まらなかった。
———とりあえず、一旦お茶を飲んで落ち着こう。
〇
キツネやタヌキ、イヌにネコ。古来から動物の怪異は様々いるけれど、中でもネズミは意地汚くずる賢いそうだ。そしてあのとき私が見たあの怪しい男の人が、信じられないけど人に化けたネズミだったのだ。
あのネズミがどういう手段でこんな珍品を手に入れたかはわからないけれど、コンタクトの要領で貼りつけられたこのウロコのせいで米納津さんはあんなにおかしくなってしまったわけだ。
「目からウロコが落ちる」
何かをきっかけに視野が広がり、今まで見えなかったものが見えるようになることの例えとして用いられるこの言葉。それはわかりやすく言うならレベルアップみたいなものだ。
そしてその言葉通り、レベルアップの瞬間に怪異的に人の目から剥がれ落ちたウロコは、言うなれば古くて使えなくなった劣化品。その濁りに濁って見通しの悪いウロコが元に戻るということは、一生懸命あげたレベルを元に戻してしまうということになるわけだ。
ましてや米納津さんに貼りつけられたのは他人のウロコ。いったいどんな視覚レベルの人から落ちたウロコなのかは知らないけれど、結果的に米納津さんは物の善し悪し以前に、ゴミかどうかの判別もできないくらいおかしくなってしまったのだから恐ろしい。まさに怪異だ。
ちなみに頭に乗っていたネズミは「こいつはカモだぞ」って他の妖怪たちに知らせるための目印なんだそうだ。つまりはカモの共有。妖怪はそうやって人を陥れるらしい。でも米納津さんの出不精な性格が幸いして人目に、ていうか妖目につかなかったおかげで大きな被害は免れた。
以前から健康のために外へ出るよう勧めていたけれど、今回はその出不精が吉と出たわけだ。
「人に化ける妖怪なんて本当にいるんですね。アニメやおとぎ話だけの存在だと思ってました」
「そうは言っても其処彼処に居る訳じゃない。それこそ大昔は沢山居たそうだが、今では棲み処を追われて殆どが絶滅危惧種だよ」
どこかの長編アニメ作品でもそんな描かれかたをしていたけど、現実でもそうなのか。そうなると素直に妖怪が悪いとは思えなくなってしまう。
それからしばらくして米納津さんが目を覚まし、正常な状態で見るお店の惨状にひざを落とし意気消沈していた。それにしたってひどい落ち込みようなので理由を訊ねると、どうやらあの粗悪品たちを手に入れる為に何十品もお店の商品をあのネズミにゆずり、あまつさえあのバケツを手に入れるために貴重なコレクションをも手放してしまったというのだ。
江戸時代に作られたなんたら焼きの大皿。それはコレクションの中でも1、2を争うお気に入りだと聞いている。働き始めた頃にその素晴らしさについて長々と話していたけれど、それをサビまみれのバケツと物々交換したとなればこの落ち込みようもうなずける。
ていうかこのバケツがあの大皿と同等かそれ以上の物に見えていたってことか。ほんとに恐ろしいな。
米納津さんはなんとか取り返してもらえないかと懇願したけど、椥辻さんは黙って首を横に振った。
「奴等が求めるのは米納津さん、今貴方がこうして失意の底に落ちた時の表情や心の有り様。奴等にはそれがこの上なく滑稽で愉快なんだ。君達にとって価値のある物も、奴等にはこの瓦落多と同等かそれ以下の価値でしかない物なんだよ」
椥辻さんはサビにまみれたバケツを指してそう言った。おそらくもうお皿や他の骨董品は粉々に破壊されているか、良くても山の中か海の底か…。ちなみにガラスの魚に関しては椥辻さんが責任を持って預かってくれることになった。
ひとまず今回の件は椥辻さんのおかげで一件落着となった。それから失意のどん底にいる米納津さんとの用事を済ませた椥辻さんは最後のおまんじゅうを頬張ると、もごもごと米納津さんに励ましの言葉をかけながら客間から出ていった。
米納津さんはもう見送る元気もないらしく、声をかけてもおでこをちゃぶ台にくっつけたまま動こうとしなかった。私はお見送りのために客間を出ると急いで椥辻さんのあとを追いかけた。
遅れて表へ出ると椥辻さんは何か品定めするようにお店をながめていた。すると鞄の中からまっしろなお札を取り出し、それをお店の入り口の横辺りにぺたりと貼りつけた。
また何かするつもりなんだと、内心わくわくしていた。そして今度は立派な太筆を取り出すとそれでお札に何か書き始めたのだ。とはいっても筆先が黒く染まっているだけで墨に浸したわけでもないから、当然お札には何も書かれていない。
「今度は何をされたんです?」
「妖御断りって書いておいた、侵入を防げる訳じゃないが、こうしておけば程度の知れた臆病な妖は警戒して寄って来ないだろうからね」
「私には見えないです」
「そういう墨だからね」
すると椥辻さんはいつの間に回収していたのか、ネズミが捕らえられた煙玉を取り出すとそれを地面に落してしまったのだ。ぽわんとバウンドした煙玉はおそらく今の衝撃でヒビが入ったらしく、その箇所から煙が漏れ出していた。そして案の定、そこからネズミが脱走してしまった。
「あっ!逃がしちゃっていいんですか?」
さっきまで煙の中で黒いシルエットで視認できていたネズミの姿は、もう私にはすっかり見えなくなっていた。けれどその代わり、ネズミがたどったであろう道の上に飛行機雲みたいに煙の筋が伸びていた。
「あれで棲み処へ案内してもらうから大丈夫。大事な友人が世話になったから、ちゃんと挨拶しておかないとね」
なるほど、そういうことか。初めからそれも計算の内だったのか。やっぱりすごいなこの人は。
「それじゃ、失敬するよ。またね」
「あ、はいっ!今日はありがとうございました!お気をつけて!」
椥辻さんは小さく手を振ってこたえると、そのまま煙をたどってお店をあとにした。
…挨拶か。煮るのか焼くのかわからないけど、椥辻さんがにんまり顔でネズミを痛めつけてるところを想像して身震いした。
ああ、こわいこわい。
〇
翌日お店に出勤すると米納津さんが昨日にも増して沈んでいた。どうやら椥辻さんから連絡があったらしく、例のなんたら焼きの大皿とその他の骨董品たちが見るも無残な姿で発見されたそうだ。
昨日もそうだったけど、こうなってしまうとどんな言葉をかけようとも意味をなさない。2つ3つ励ましの言葉をかけたけれどやっぱり効果はなくて、私は重い空気に耐えられずにホウキをもってお店から出ていった。しばらくあんな状態が続くのかな。
せかせか店先を掃いていると、ふと昨日のお札が目に入った。それからネズミがたどった煙の筋を思い出して道を眺める。それから、こんどは自分の周囲を見回してみた。見えないけれどもしかしたら今、私の目の前を何かが通り過ぎたかもしれない。…なんて想像してみる。
私にはここに書かれた「妖御断り」の文字も、米納津さんに憑いていたネズミも見えなかったけど、それはちゃんと存在しているんだ。
不謹慎とは思うけど、またあの怪奇な現象に遭遇できないかと期待してしまう。そしたらまた椥辻さんがタバコの煙で妖怪を捕まえたり、あの刀で悪霊を祓ったり、そんな場面を想像すると心が躍ってしまう。やっぱりお札や数珠を使ったり、あの筆で結界を書いたりするんだろうか。
そんな映画やアニメの世界で起こりそうなことを妄想しているとガラリとお店の戸が開いた。
「春ちゃん、ちょいと散歩してくるから店番頼む」
「お散歩って、また珍しい」
「ああ、気晴らしに歩きたい。いつまでも落ち込んどるわけにはいかんからな。残り少ない人生、前向きに生きんとな。ついでにお茶請けも買うてくるよ。それじゃあ店番頼むな」
そう言って米納津さんはゆったりとしたペースで歩き始めた。まだちょっと声に元気はなかったけど、少しは元気になってくれたみたいでよかった。
店番のためにお店に戻ると、まだ微かにタバコの香りが残っていることに気がついた。昨日の出来事が嘘みたいに思えるけど、全てはちゃんとここで起きたことなんだ。椥辻さんの不可思議な力も、人に化けたネズミも煙に捕らわれたネズミの影も、私はしっかりと見たんだ。
あらためて妖怪はいるんだと実感して身震いしてしまう。まだ怖い妖怪にしか遭遇してないけど、心の優しい妖怪もいるのだろうか。いるなら会ってみたいし、お話ししたり、できれば一緒に遊んだりもしてみたいものだ。見える人だったらそれができてしまうのか。そう思うと、なんだか見えないことがちょっぴり悔しい気もする。
「…あっ」
ふいにそれが視界に入って思わず声をあげてしまった。それは日常生活ではよくあることだけど、このお店での経験をふまえると見えない何かの仕業である可能性も大いに考えられる。けれど、普段の米納津さんの行動と、常連さんから聞いた話を思い出して、「これは多分違うかな」と、そう思った。
私はそれを手に取ると颯爽とお店を飛び出して、まだ見える距離にいる米納津さんに向かって大きな声で叫んだ。
「米納津さーん!お財布忘れてまーす!」


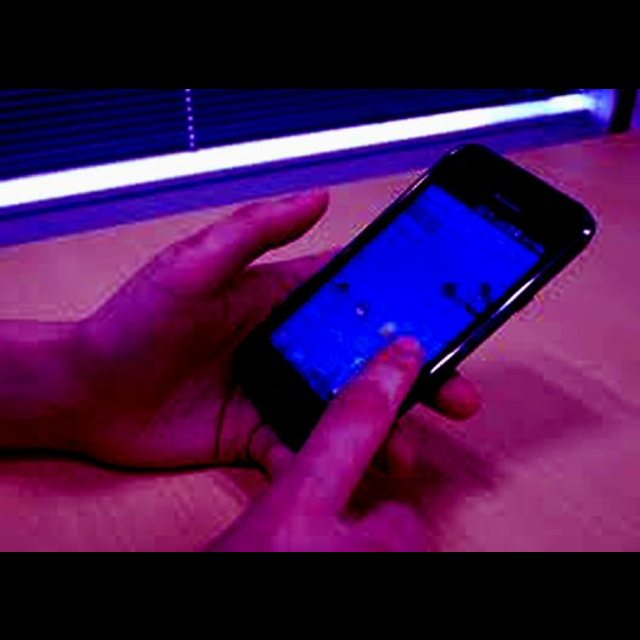



作者一日一日一ヨ羊羽子
新年明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
新年最初の投稿でこの挨拶をしようと決心して気づけばもう8月も終わりですね。
お久しぶりです。
一日一日一ヨ羊羽子こと串山show子(くしやましょうこ)です。
今年一発目は椥辻生雲のお話です。シーズン2です。
長いお話なってしまって申し訳ありません。
今後彼はこんな感じのとんでもパワーを使う事があると思います。
鬼太郎で言うリモコン下駄とか髪の毛針みたいな感じです。
もしよろしければまたしばらくお付き合いください。
今回からは完全不定期です。なるべく早く次回のお話を投稿したいです。
今後は椥辻生雲のお話には◆を、
もう一方の槻木莉柚のお話には◇をタイトルの両端につけます。
今回のお話を呼んで「ああ、こういうの苦手だな」って方はこれを目印にしてください。
⇩◆椥辻生雲のお話第一話◆⇩
https://kowabana.jp/stories/33091
⇩◇槻木莉柚のお話第一話◇⇩
https://kowabana.jp/stories/33468