「怖いっていうか…凄く不気味な体験をしたことなら、あるんです。尤も、あれが生きている人間だったのか、そうでなかったかは分からないんですけど」
片桐さんが「不気味」な体験をしたのは、つい先月のことだったという。
その日、上司から残業を命じられた片桐さんは、長いことパソコンと睨めっこをしていた。眠い目を擦りながら腕時計を見る。時刻は既に夜の10時を回っていた。
慌てて残りの作業をこなし、会社を出た。いつもなら徒歩で帰るのだが、今日は心身共に疲れ切っていた。一刻も早く帰って、熱いシャワーを浴び、ビールでも飲んで寝たい…。
片桐さんはタクシーを掴まえると、自宅のマンションへと帰っていった。疲れた足を引きずり、エレベーターのボタンを押した。彼女の自宅は9階である。
エレベーターはすぐに下りてきた。時間は10時半を回っていたし、こんな時間帯にエレベーターを活用する人もいないのだろう…そう思った。
が。
開いた扉の奥には先客が乗っていた。
「中年のおばさんがいたんです。薄いクリーム色のニットに、下はジーンズ姿の…。私に背中を向ける形で立ってたから、表情は分かりませんでしたけど
」
片桐さんはおばさんが降りるのを待った。しかし、おばさんは微動だにしない。
隅っこの方に立って、少し俯き加減で…とにかく、エレベーターから降りようとはしなかった。
声を掛けようか…。そう思ったが、何となく躊躇した。正直、このおばさんと狭いエレベーター内で2人きりになりたくなかったが、早く家に帰りたい気持ちが勝ち、彼女は覚悟を決めて乗り込んだ。
そして「9」のボタンを押す。9以外のボタンは点灯していなかった。
エレベーターはガコン、と起動した。足元からグググッと持ち上げられる感覚がする。
1…2…3…
時折、おばさんの様子が気になり、横目でチラチラと見てしまう。
やはり身動ぎ1つしない。こちらに背中を向け、静かに立っている。
4…5…6…
何をされた訳でもない。別に怪しい感じもしなかったし、普通の中年のおばさんだ。
だが…不気味だった。密室空間にいるからだろうか…何とはなしに息苦しく、掌がじっとりと汗ばみ、口の中がカラカラに渇く。
早く…早く9階に着いて。早く…早く!
7…8…9。
チーンと音がして、扉が開いた。片桐さんは勢い良くエレベーターを飛び出す。
そっと振り向いたが、おばさんは降りてこなかった。ほっと息をつく。
自分の部屋に着き、やれやれと鞄を下ろし、髪を解いた。あのおばさん…このマンションの住人なんだろうか。
ゾクリと寒気がした。腕を見ると鳥肌が立っている。止めよう。もう余計なことは考えないことにしよう。片桐さんは入浴の準備に勤しんだ。
熱いシャワーを浴び、サッパリしたところで。お風呂上がりといえば、ビール。冷蔵庫を開け、缶ビールに手を伸ばすーーー
「…あれぇ?」
買い置きしてあったと思ったが、1本もない。どこを見てもない。品切れだった。
人間、ないと思うと余計欲しくなる生き物である。幸い、マンションのすぐ近くにはコンビニがあった。夜更けなので、ジャージ姿のまま買いに出掛けた。
今度は1階に下りるため、エレベーターを待つ。先程のおばさんのことも気になったが、あれから悠に1時間は経っている。遭遇することはないだろう。まさか、あれからずっとエレベーターに乗り続けているわけでもあるまいし。
待つこと数分。エレベーターが9階に到着し、扉が開く。
片桐さんは言葉を失った。
「いたんですよ、あのおばさんが…。さっきと同じように隅っこに立ってたんです。後ろ向きの姿勢のまま…」
今度は乗れなかった。茫然と立ちすくんだまま、何も言えなかった。言えるはずもなかった。
エレベーターの扉は閉まった。全身が粟立ち、心臓が激しく動悸を奏でる。
もう、コンビニに行く気もとうに失せ、とぼとぼと帰宅した。
「結局、あのおばさんが誰だったのかは分かりません。その後、遭遇したことはないんです。あれは何だったんでしょうねぇ。ずーっと乗ったままだったんですかねぇ…。不気味でしたよ、ホント」
あの日以来、片桐さんはエレベーターに乗れなくなってしまったという。
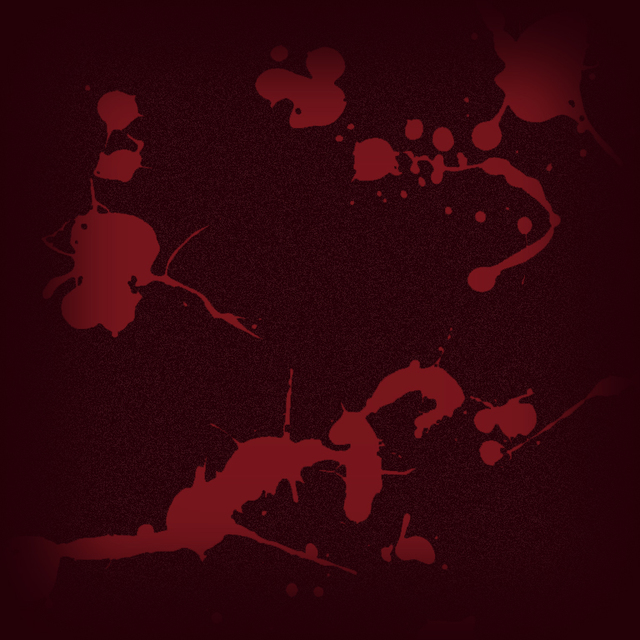

作者まめのすけ。