wallpaper:4
同じ高校に通っていた、ヨシカの話だ。
ヨシカはバングラデシュ人の母親と日本人の父親の間に埋まれたハーフだ。
父方の曾祖父はドイツ人だという。
浅黒い肌とぱっちりした目付き、すらっとした血色の良い足は他の女子と比べても“ものが違う”という感じだった。
外国の血が流れていながら外国語が全く話せないところも、むしろヨシカのチャームポイントとなっていた。
ヨシカとは同じクラスの文化祭実行委員を務めていた。
ヨシカとは気が合った。
夏前から文化祭の出し物について話し合うという名目でミスタードーナツに行き、気付いたら全く関係無い話を何時間にも渡ってしているということもあった。
「私、もっと肌を綺麗にしたい」とヨシカは言っていた。
「別にいまだって、十分に綺麗だよ」
「そういうことじゃなくて。アメリカの女優みたいに肌を白くしたいの」
「それは......。向こうは白人で、ヨシカはそうじゃない。ヨシカのお母さんはイスラム系だし」
「でも、ひいお祖父ちゃんは白人だよ?」
ヨシカはそう言った。
その年の夏休み明けから、ヨシカは一時限目の授業に遅刻して来ることが増えた。
「化粧をしているだろう。それは校則違反だ」と、生活指導の教師に注意を受けているのを見ることも増えた。
ヨシカの見た目が派手になっているということは全く無かった。夏前と変わらない。
それなのに何故か、ヨシカは化粧をしているのだ。
またヨシカは体育の授業を休むようになった。
他のクラスメイトが校庭の外周を走る中、隅で膝を抱えて座るヨシカの姿を見るようになった。
ある日、ヨシカと一緒にミスタードーナツに行った。
暦の上ではすっかり秋だったが気温が高く暑い日だった。
ミスタードーナツの店内の空調は壊れており、そのことを詫びる内容の紙が貼り出されていた。
「お腹は減ってないから、オレンジジュースだけでいい」
ヨシカは呟いた。
ヨシカはひどく汗を掻いており神経質に制服のシャツの胸元をぱたばたとはためかせた。
覗く肌は白かった。怖いと思った。ヨシカらしくない仕草だった。
翌日。
ヨシカは目の下に真っ黒な隈を作っていた。
それから一ヶ月もしないうちに、ヨシカはげっそりと痩せていった。
ヨシカは入院した。
病院に見舞いに行くと、ヨシカの母親とばったり会った。
美しい母親だった。
頭を下げると、ヨシカの母親は「あの子を大切にしてあげて下さい」とだけ流暢な日本語で言った。
病室に入るとヨシカと目が合った。バニラ味のアイスクリームの空き箱が室内に散らばっていた。
ヨシカの顔はところどころ腫れ上がり白斑だらけだった。
まるで蛇のようだった。
浅黒い肌は失われてしまっていた。
以前に比べ、目がぎゅっと釣り上がっているように見えた。
手近なコップに水を注ぎ手渡した。ヨシカの手は死人のように冷たかった。
「ありがと」とヨシカは言い、水を飲んだ。
僅かに赤黒い舌が覗いた。
「ごめんね。こんな顔になっちゃった。きっと化粧品に良くない成分が入っていたんだと思う......」
ヨシカは咳き込んだ。
咳は二、三分止まらなかった。ヨシカは嘔吐き、しゃっくりも繰り返した。
ごとん。
咳が収まる頃、ヨシカの口から何かの塊が、唾を糸引き床に落ちた。
それは沖縄の海のように透明なエメラルドの塊だった。
そんなものが人体から出てくるはずは無い。だが、その時のおれはエメラルドの存在を微塵も疑わなかった。
明かりの下でヨシカの唾液がぬらりと光った。
「飾っておく?」
と訊くと、ヨシカは首を横に振った。
「大事に持ち帰って。何処か静かなところに置いて。そして、出来ればそのエメラルドを私だと思って」
家に帰ったおれは物置の綺麗なところにエメラルドを置いた。
文化祭はヨシカが居なくとも、特に問題なく進み、終わった。
ヨシカは転院した。
風の噂でいまのヨシカの容体を聞く。体調は落ち着いており、特に変わった点は無いそうだ。




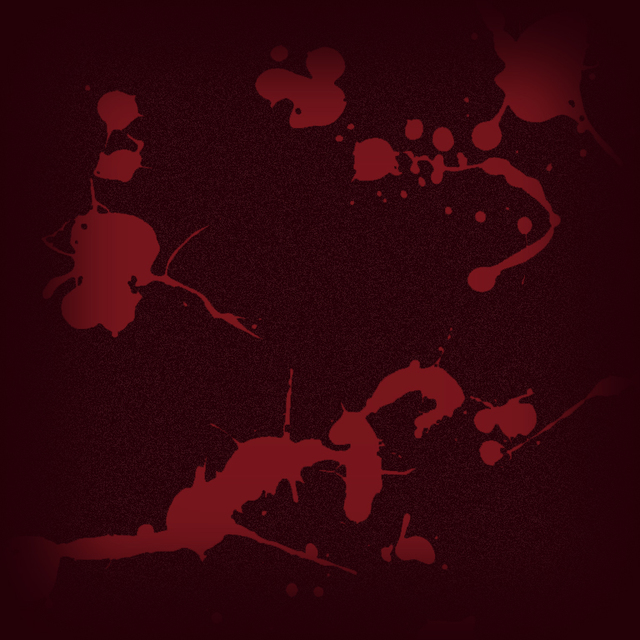

作者退会会員